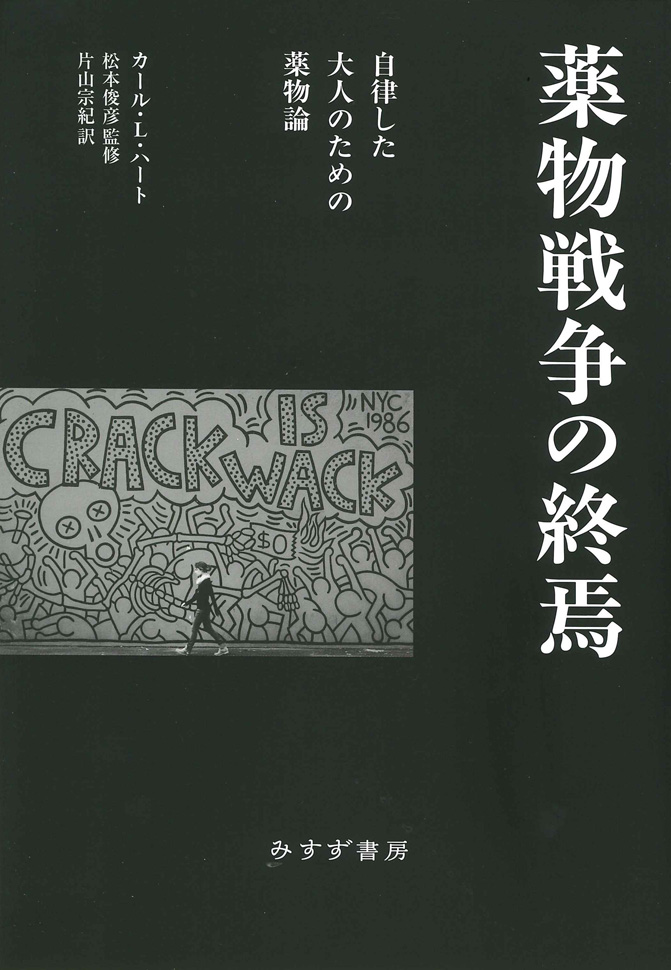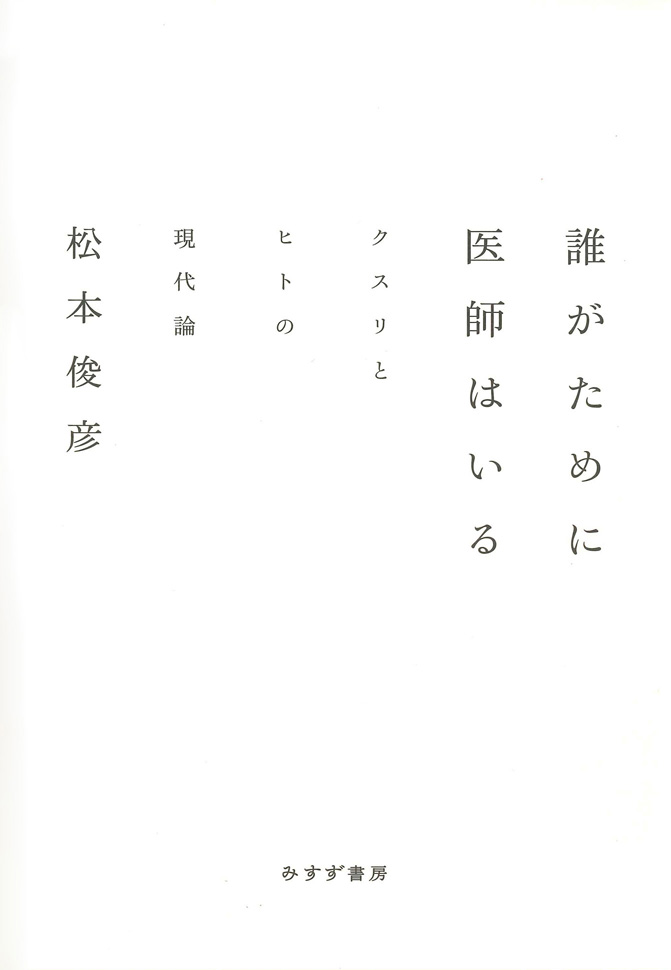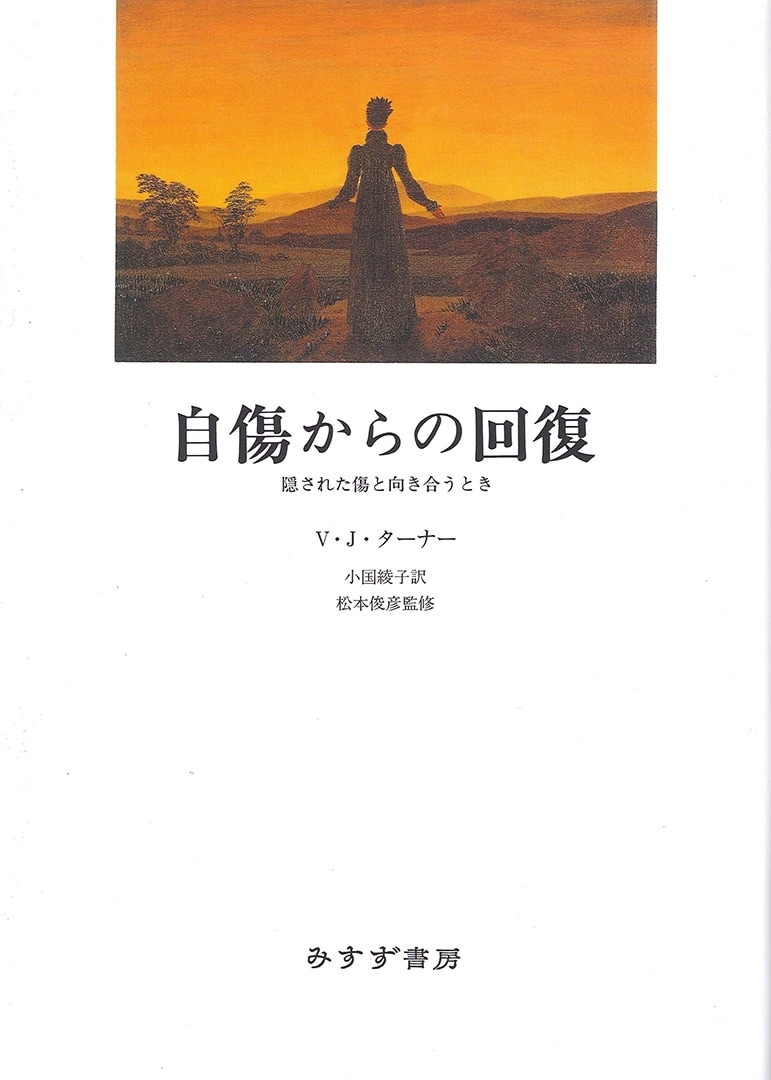いまからおよそ10年前のことだ。私の知っている人物が、覚醒剤の問題で依存症専門外来にやってきた。
すぐには気づかなかった。どこかで見かけたことがある……とは感じたものの、「いや、でもわりとどこにでもいそうなタイプだし……」と思い直したりして、最初は判断を保留していた。
その人物は、50代半ばの中年男性で、ダメージジーンズに白いTシャツ、その上からレザージャケットを羽織って、1990年代のロックミュージシャンのような、少し時代遅れの若作りをしていた。しかし、茶色に染めた髪の根元が白くなっているあたり、最近、自分の身繕いどころではなくなるような、何かよんどころない事情があったことをうかがわせた。
強さと弱さが同居する佇まいの人だった。やたらと声が大きく、いかつい顔の造作をしているのに、大きな目だけは子どものような無邪気さを宿している。それから、股を広げて尊大そうに椅子に腰掛けているのに、脅えたようにあたりをキョロキョロ見回し、ずっと貧乏揺すりをしている。
診察をはじめて10分ほど経過した頃、曖昧な印象は確信へと変わった。初回診察のルーティンに従って住所や職業などを聞いているうちに、目の前の映像と、記憶のなかの靄に包まれた人影とが重なったのだ。私は思わず声をあげそうになった。
改めて彼の顔をまじまじと眺める。まちがいない、行きつけの激辛ラーメン店の「大将」だ。
当時、私はある店の激辛ラーメンにハマっていた。
店を訪れるのはいつも深夜だった。外来診療で疲れきった日の夜、最終電車で自宅最寄り駅を降りると、なぜか私の足はその店へと向かってしまうのだ。徒歩で駅から3分ほど、商店街のネオンが途絶えて急に辺りが暗くなるエリアまで行くと、その店は闇のなかから忽然と姿を現す。
粗末なバラック小屋の店舗だった。深夜、街灯に照らされたその外観は、簡素を超えて貧相、いや、どこかお化け屋敷めいた風情さえあったが、実は地元では「知る人ぞ知る」という店だった。
店内はお世辞にも衛生的とはいえなかった。床はもちろん、テーブルにもいくら拭っても拭いきれない油の粘着感が残っているし、長年使い込まれているプラスティック製の水飲みグラスは、樹脂の劣化で白く曇っていて、「これで水飲んでも変な病気に罹らないか?」と、口をつける際に湧き起こる躊躇はいかんともしがたかった。
何より特筆すべきなのは、「大将」がおそろしく短気で、客の方が彼の機嫌をうかがわなければならない、ということだった。たとえば、酩酊のあまり注文さえままならない客は、「酔いを覚ましてから出直してこい」と容赦なく追っ払われたし、クレームをつける客には平気で逆ギレした。特に店内が混雑してくると短気に拍車がかかって、突然、「もう勘弁してちょうだいよぉーっ!」と熊の咆哮のような声をあげては、店内の客を震え上がらせた。私自身、怒声に脅えながらラーメンを啜るなんてことは、決して一度や二度ではなかった。
それにもかかわらず、深夜でも客足が途切れないのは驚きだった。それだけ彼が作る激辛ラーメンのファンが多いということなのだろう。実際、さすがに順番待ちの行列こそなかったものの、店内はいつもそれなりに混雑していた。
私は少なくとも月に2回はその店を訪れていた。入店するや否や、私はカウンター席に陣取り、メニューも見ずに「ラーメン、激辛で」と注文する。すると、「あいよぉー」と、「大将」の威勢のよい声が反応する。その後、ラーメンが運ばれてくるまでの時間、スマートフォンをいじりながら、私は内面の暗い螺旋階段を降りていく――なんていうと格好よいが、何のことはない、単に外来診療のひとり反省会をやるのが、いつものパターンだった。
一日の終わり、すでに私の脳は疲労困憊状態にあるが、それでも、その日の診療でまずかった点は不思議と明瞭に思い出せる。特に夕方以降はミスが頻発する「魔の時間帯」だ。朝から昼休憩もとらずにぶっ通しで診療をした結果、その時間帯には血糖値が低下し、血中ニコチン濃度の下降曲線も底を打って、もはや私は抜け殻のようになってしまっているのだ。
だったら昼休憩をとればよいではないか――そう説教されそうだが、話はそう簡単ではない。私の診療は大概予約時間が押して渋滞している。さすがに1時間待ち、2時間待ちの患者を尻目に休憩はとれない。それに、昼食をとると必ず午後、睡魔に襲われ、そうなるとがくんと診療のペースが落ちてしまって、時間内に診療をやり遂げることができなくなる。
結局、16時以降の私は、12ラウンド目のボクサーのように、「立っているだけで精一杯」というありさまになるわけだ。そんなときにかぎって、つい患者に対して説教めいた発言をしたり、トラウマ記憶を刺激する地雷を踏みつける発言をしたり、あるいは、綱引きのような不毛な論争に巻き込まれたりして、後味の悪い診察となってしまう。そんな私にムカついた患者は、きっとSNSとかに私の悪評を投稿しているにちがいない。
悩ましいのは、具合の悪い患者ほど夕方に訪れる確率が高いことだ。そうした患者の多くはさまざまなトラウマを抱えていて、夜は恐怖の時間だった。なにしろ、彼らが経験した人生の惨事は、大抵、夜に発生している。だから夜、寝つこうとして意識が濁りかけると、過去のトラウマ記憶がむっくりと鎌首をもたげてきて、途端に脳は過覚醒状態になってしまうのだ。そうなると、いくら睡眠薬を追加しても眠れない。そのくせ、夜明け近く、窓の外で空が白みはじめると、急に緊張がほどけて意識が弛緩し、いきなり暴力的な睡魔に襲われるわけだ。そして目覚めると午後……。夕方の時間帯に来院する背景にはそうした事情がある。
いつも驚かされたのは、私の反省と自責が佳境を迎える絶妙なタイミングで、注文したラーメンが運ばれてくることだった。赤いスープは地獄のように沸き立ち煮えたぎり、表面には鷹の爪や花椒の粒が点在している。眺めているだけで眼の結膜が刺激され、いまにも涙が出てきそうだ。
美味しいのかと問われると、いささか自信はない。当時、私が求めていたのは、辛さと痺れが入り交じった、一種の痛みに近い感覚だった。うまい/まずいの問題ではない。
私はそんなラーメンをむせ込みながら口腔内に掻き込む。それは故意にみずからに痛みを加える行為ではあるが、その痛みが不思議と鬱屈した気分を霧散させ、さらには私の脳を再起動し、覚醒させるのだ。そこには、リストカットをくりかえす患者がよくいう、「切ると気分がスッキリする」という効果に一脈通じる機能、いや、ほとんど同じ機能があるのかもしれない。おかげで、SNSに自分の悪評が投稿されていないかエゴサーチする、などといった馬鹿をしないですむ。
およそ健康的でないのは承知していた。深夜に激辛ラーメンを食べるのと、飲酒や喫煙、あるいはリストカットと比べて、いずれがより深刻な健康被害をもたらすかと問われれば、どう考えてもそれは激辛ラーメンだろう。なにしろ、翌日には腹痛を伴う下痢に見舞われ、排便時には肛門周辺を火箸でつつかれる感覚に苛まれる拷問が待っている。
激辛ラーメンから一夜明けた朝、便座の上で身を震わせながら、私は何度、「もう金輪際やめよう」とかたく誓ったことか。しかし、1週間もすると苦痛の記憶は喉元をすぎ、気づくと私の足はその店に向かっている……。
そうなのだ。まちがいなく、当時の私は激辛依存症だった。
診察室で、「大将」は私のことに気づいていないようだった。私など数ある客の一人にすぎなかったろうし、厨房はいつも湯気で煙っているから、カウンター席に居並ぶ客の顔などどれも同じ、何なら「カオナシ」並みのモブキャラにしか見えないのかもしれない。そもそも、私もまた店のカウンターではいつもうつむいていた。料理がくる前はスマートフォンの画面に視線を落としているし、料理が来たら来たで、今度は丼の上に覆い被さって食べることに没頭している。
彼は、1カ月ほど前に覚醒剤取締法で逮捕され、20日間、警察の留置所での勾留を経て、ほんの2、3日前に保釈されたばかりだった。まだ日程は決まっていないが、これから1、2カ月中には裁判が開かれる予定だという。
覚醒剤をはじめたのは、昨日今日の話ではなかった。10代の終わり頃から使いはじめ、そのせいで少年院にも入ったし、成人後もすでに2回、覚醒剤で逮捕され、一度は刑務所にも服役している。しかし、いずれも20代の話で、30歳以降、ラーメン屋の修業を本格的に始めてからは一度も逮捕されていなかった。そして40歳になる頃には、自分の店を持つとともに現在の妻と結婚し、少なくとも表面上、ごくふつうの暮らしを手に入れていた。
ただ、その間まったく覚醒剤を使っていなかったかといえば、そうではない。さすがに若い頃のように、仕事を放り出して何日間も籠もりきりで覚醒剤に没頭する、といった見境のない使い方こそしなくなった。けれども、仕事前に必要最小限の量だけ使う、それも注射ではなく「炙り」(加熱吸煙摂取)で使うといった工夫を凝らしつつ、結局は覚醒剤を続けていたのだった。
刑務所を出所した時点では、彼はかたく断薬を決意していたはずだった。しかし、ラーメン屋の修業をはじめて気づいたのは、覚醒剤を使わないとマルチタスク――客の注文を聞きながら麺のゆで具合に気を配ったり、麺のゆであがり待ちの隙に客の会計対応をしたり――をこなせない、ということだった。特に店が混雑する時間帯、一度に多数の注文をされると、頭が真っ白になってパニックに陥ってしまうのだ。
客と喧嘩するのは、大概そんなときだった。そこに彼の特異な点があった。一般に、覚醒剤を使うとテンションが上がってハイになったり、怒りっぽくなったりするものだが、彼の場合は反対だった。むしろ落ち着き払った態度となり、厨房と客席の双方に理性的な気配りができるのだ。
もっとも、覚醒剤を使ったからといって、仕事上のトラブルを完全に回避できたわけではない。というのも、勤務時間の後半――大抵は午前零時すぎ――になると覚醒剤の効果はとうに切れていて、酔客から乱暴な言葉を浴びせられると、感情は瞬時にして沸騰し、怒りの蒸気が心の鍋蓋を吹き飛ばしてしまうからだ。それでも、「仕事のために最小限だけ使う」「絶対に娯楽目的では使わない」という自分ルールを遵守することで、逮捕の危険を回避しながら仕事上のトラブルを最小化する、という困難な均衡を維持してきたのだった。
ところが不運なことに、あるとき筋の悪い客を相手に喧嘩してしまったのだという。
彼はうなだれてこういった。
「相手が若いチンピラだったんです。ありゃたぶん下っ端の暴力団員ですかね。で、怒鳴り合った挙げ句、「外に出ろ!」ということになって、こっちも引き下がれなくって、受けて立ったわけですよ。こう見えて、こっちも20代はそれなりにヤンチャな世界に生きてましたからね。でも、さすがにもう全然歯が立たなくて、ボコボコに殴られた挙げ句、気絶しちゃったんです」
警察と救急隊が到着したときには、喧嘩の相手は姿を消していたという。彼はそのまま救急車に乗せられて近くの公立総合病院救急外来に搬送され、頭部CTスキャンをはじめとするさまざまな検査を受けた。脳内には出血や挫傷といった異常所見はなく、「単なる脳震盪でしょう」という結論だった。しかし、意識障害の原因を精査するために実施した、尿の簡易薬物検査からは、担当医が予期しなかった所見が得られた。それが覚醒剤の陽性反応だったわけだ。
担当医は何の躊躇もなく警察通報した。そして翌朝、退院の許しを得た彼が病院の玄関を後にした直後、いきなり数人の警察官に取り囲まれたのだ。文字通りの「門前逮捕」だった。
医師にとって、守秘は自身の職業的な存在理由の根幹にかかわる重大事項だ。そのことは、古代ギリシャの医師ヒポクラテスが神々に捧げた、医師の倫理と任務に関する宣誓文、「ヒポクラテスの誓い」にも明記されている。
断言しておくが、わが国には、患者の違法薬物使用に関して、医師に警察通報を義務づけた法令は存在しない。それどころか医師の守秘義務は、医師法という業法などではなく、刑法という重い法律によって規定されている。刑法134条1項は、医師に対し、「正当な理由がないのに、その業務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」(秘密漏示罪)と定めている。
しかし、絶対に告発してはならないわけでもない。最高裁判例(1)によれば、現に犯罪に当たる行為が存在するなど、「正当な理由」がある場合には、秘密漏示罪は適用されないとされている。しばしば誤解されているが、この判例は決して医師の守秘義務放棄を推奨するものではない。あくまでも「犯罪にあたる場合」には、「通報してもいいし、しなくともいい」として、その裁量を医師に委ねたものなのだ。
それにもかかわらず、患者を警察通報する医師がいる。これまで私が担当した患者のなかにも、他の医師によって警察通報され、逮捕されてしまった者が何人かいた。どうやら医師のなかには、あの最高裁判例を「通報すべき」と誤読している者が少なくないようだ。
参考までに、最高裁判例の根拠となった事件の概要を紹介しておこう。
――ある女性が某公立病院の救命救急センターに搬送されてきた。女性は脇腹に刺し傷を負っており、しかも非常に興奮した状態だった。何でも同棲相手の男性と口論となった末、男性にナイフで刺されたとのことであった。出血量が多く、刺傷が臓器に達している可能性も否定できないと考えた担当医は、全身麻酔下での手術の必要があると判断した。そしてその旨説明し、患者の同意を得て手術を実施した。
当初から患者の興奮状態に違和感を覚えていた担当医は、患者に事前説明していない検査を追加した。全身麻酔下の手術なので当然尿道カテーテルが挿入されていたわけだが、そこから採取した尿検体を使って簡易薬物検査を実施したのだ。
案の定、覚醒剤の陽性反応が出た。担当医は、同行する患者の両親に対し、「公立病院に勤務する医師には、犯罪告発の義務がある」と説明して警察通報した。その結果、患者は覚醒剤取締法違反によって逮捕された。
患者は担当医を相手どって提訴した。理由は、治療上知り得た秘密を治療以外の目的で使用したこと、つまり、医師の守秘義務違反だった。これに対して担当医側は、自身の行動が刑事訴訟法239条「公務員の犯罪告発義務」に定められた正当なものである、と抗弁した。裁判はもつれ長引き、最高裁まで争うこととなった。
この争いに関する最高裁の判断についてはすでに述べたが、注目すべきなのは、その判決文に、担当医の抗弁根拠、「公務員の犯罪告発義務」に関する言及がまったくなかったことだ。
当然だろう。確かに公務員は刑事訴訟法によって犯罪告発義務を課されているが、同時に、国家公務員法や地方自治体法によって守秘義務も課せられている。したがって、そのいずれを優先するかは、当該公務員の本務が何かによるのだ(2)。
たとえば、捜査や取り締まりを本務とする公務員が、「改悛の情がある」として告発しなければ、これは職務怠慢だ。しかしその一方で、医療や相談、教育を本務とする公務員が、本務遂行という職務上正当な理由があれば、守秘義務優先は許容される。実際、公立高校の教員が、生徒(未成年)の飲酒や喫煙を告発せず、教育的指導に代えることは、これまでも広く許容されてきた。
そう考えてみると、私の患者を通報した医師たちは、実は医療を本務としておらず、「白衣でコスプレした捜査・取締員」だったのかもしれない。
くどいようだが、医師が警察通報を義務づけられた薬物はない。しかし、その薬物が覚醒剤ではなく「麻薬」に分類されるものである場合には、話がやや複雑になる。都道府県知事への届出をしなければならない可能性があるからだ。
わが国の麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻向法)58条の2は、「医師は、診察の結果、受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない」と定めている。そして、ひとたび麻薬中毒者として届け出られると、患者は麻向法による措置入院(精神保健福祉法による「自傷・他害のおそれ」にもとづく措置入院とは異なる)の要否を判断すべく精神鑑定を受けなければならない。
それだけではない。患者の名前は、都道府県で保管される「麻薬中毒者台帳」に収載され、長期間、都道府県薬務課、ならびに地方厚生局麻薬取締部の監視下に置かれるのだ。
ここでいう「麻薬」とは、一体いかなる薬物を指しているのか?
実は、この「麻薬」なる言葉は医学用語ではない。「麻向法第2条第1項で定義された薬物」という法律の条文でしか定義できない、行政上の用語なのだ。
歴史的にみると、「麻薬(narcotics)」なる概念は、1912年に調印された、世界初の薬物規制に関する国際条約「万国阿片条約」にまで遡ることができる。同条約では、当初、アヘンとコカイン、およびその誘導体に対して「麻薬」という用語を適用して規制対象としたが、その後、米国の強い要望――かの悪名高い初代連邦麻薬局長官ハリー・アンスリンガーの剛腕――により、対象は大麻および大麻製剤にまで拡大された。そして、その定義はそのまま第二次世界大戦後の「麻薬に関する単一条約」(1961年)に引き継がれ、今日における麻薬の定義となっている。
したがって、国際的には、「麻薬」は「アヘン系麻薬」「コカ系麻薬」「大麻系麻薬」の3種を指すが、わが国の場合、「麻薬」の概念はそれとは少々異なる。というのも、それら3種に加えて、LSDやMDMAといった、国際的には「向精神薬」に分類される化学合成物質まで含めているからだ。その結果、わが国の麻薬概念はガラパゴス的な様相を帯びた、独自のものとなっている。
では、そのような麻薬の「中毒者」とは、一体いかなる状態を意味するのだろうか?
この「中毒者」もまた医学的概念ではなく、その定義は、昭和41年の厚生省薬務局長通達という行政文書に遡らなければならない。その文書は麻薬中毒者についてこう記している。「麻薬に対する精神的身体的欲求を生じこれを自ら抑制することが困難な状態」
この一節を読むと、どうやら「依存症」とほぼ近似した意味らしいと見当がつくが、名称があまりにも今日的でない。確かに、かつてアルコール依存症を「アルコール中毒(アル中)」と、そして薬物依存症を「薬物中毒(ヤク中)」と呼んでいた時代はあった。しかし、こうした呼称は侮蔑の念を帯びた俗称であり、当事者への偏見や差別意識を強めるとしてとうの昔に廃棄されているのだ。
そもそも、「中毒」とは「毒が身体の中にある」状態を意味する。だとすると、その治療は「解毒」――毒を体外に出す――することで足りるはずだが、現実にはそうではない。何年断酒していてもアルコール依存症患者にはたえず再飲酒の危険がつきまとうものだし、長い刑務所収監により「解毒」を完了しているにもかかわらず、出所直後に覚醒剤に手を出す人は少なくない。
いうまでもないが、依存症とは、体内における依存性物質の残留を原因とする病気ではない。長年、そのような依存性物質をくりかえし使用することにより、個体の体質や習慣が変化することによって生じる病気なのだ。だから今日、医学領域で「中毒」というとき、それはあくまでも薬物摂取による酩酊状態、すなわち急性中毒に限定した病態を指す。
それ以上にまずいのは、「中毒」という病名に「者」をつけた表現だ。今日、医学の領域では、「統合失調症者」とか「薬物依存症者」といった具合に、病名に「者」をつけた標記はタブーとなっている。病気はあくまでもその人の属性の一部でしかないにもかかわらず、あたかも病名がその人の全体を表象するかのごとき表現は、人権擁護という観点から完全にアウトだ。
要するに、あらゆる点において「麻薬中毒者」なる言葉はあまりに時代錯誤的なのだ。
現在、この「麻薬中毒者届出制度」はほとんど「死に体」制度となっている。事実、1990年から2007年までに、麻向法による措置入院となった麻薬中毒者は、毎年0~2件程度であり、2008年以降は0人という状況が続いている。もちろん、薬物依存症患者のなかには強制入院を余儀なくされる者もいるが、その際にも、「自傷・他害のおそれ」を根拠とした、精神保健福祉法による措置入院の運用で十分こと足りてきた(3)。
届出件数自体も非常に少なく、2010年以降、毎年1~7件程度だ(4)。たとえば、大麻はこの「麻薬」概念に含まれているが、国内における大麻依存症患者数が数人程度かといえば、まさかそんなはずはない。いかに大麻がアルコールやタバコよりも依存性が低いとしても、国内全体で数人などということはあり得ない。
届出件数が少ない理由は明らかだ。医師の多くがこの制度を知らない、いや、正確にいうと、忘れているからだ。実は、麻薬中毒者届出制度は医師国家試験における公衆衛生学分野の問題としてよく出題されるが、大抵の医学生は、内科学や外科学に比べると公衆衛生学を軽視していて、試験直前の詰め込み式暗記で片づけ、試験後は瞬時にして忘却してしまっているのだ。
それにしても、なぜかくも時代錯誤的な制度ができたのだろうか?
かねて覚醒剤一辺倒のわが国にも、一過性ながらヘロインなどのオピオイド(アヘン類)の乱用が社会問題化した時期があった。第二次大戦敗戦後、軍需品だったヒロポンの市中放出による覚醒剤乱用禍への対策として、1951年に覚醒剤取締法が制定された。その後、規制強化によって覚醒剤が入手困難となった影響で、1960年代初頭、代替薬としてヘロインが市中に出回るようになった。なかでも横浜市はヘロイン常用者が各地より集まり、治安上の問題となったらしい。
そして1962年7月、後に「横浜・日ノ出町異変」と称される事態が勃発した。突如として、路上のあちこちで多数の人たちが昏睡状態で倒れ込む、という異様な光景が出現したのだ。これは、悪天候により海路経由のヘロイン供給が一時的に途絶え、その結果、離脱の苦痛に憔悴しきったヘロイン常用者たちが、苦痛を紛らわせるべく、市販睡眠薬を多量摂取して生じた現象だった。
この事態を受けて、政府は、麻薬に対する規制強化だけでなく、同時に、麻薬依存症――特にアヘン類(オピオイド)の依存症――に陥った者に対する医療的措置が必要と判断し、1963年に麻薬中毒者専門医療施設の設置を計画するとともに、麻薬独自の診断および入院措置制度、すなわち、麻薬中毒者届出制度を創設した。この制度は、供給低減(規制強化)に併せて需要低減(依存症治療・回復支援)の双方をカバーするものだった。
しかし皮肉なことに、麻薬中毒者専門医療施設が整備された頃には、わが国の麻薬乱用問題はすでに事実上収束していた。結局のところ、供給低減だけで十分効果があったわけだ。この成功体験は、不幸にもその後のわが国の薬物対策――供給低減に偏重した施策――を正当化するものとなってしまった。
少なくとも1960年代時点では、麻薬中毒者届出制度は先進的な取り組みであった。ヘロインをはじめとするオピオイドは身体依存がきわめて強力で、離脱時には、大量の下痢と発汗、嘔気・嘔吐、全身の体毛が逆立つ現象を伴う悪寒、激しい焦燥、さらには、骨の奥が軋むような全身の痛みが2週間あまり続くのだ。これは、到底、自力で乗り切れるものではなく、当時の医学水準では、措置入院によって強制的に隔離する以外、薬物から離れる手立てはなかった。
けれども、現代の医学水準ではそのような強制入院は現実的ではない。今日、オピオイド離脱の治療はメサドンやブプレノルフィンといった、「より安全なオピオイド薬剤」で代替する治療法が一般的となっている。それどころか、代替オピオイドを投与せずに物理的隔離だけで解毒するのは、患者に意図的に苦痛を加える、懲罰的かつ人権侵害的な医療とみなされる風潮さえある。
何より問題なのは、この届出制度は、長期間監視下に置かれるという過剰な人権侵害を許容している、という点だ。というのも、ひとたび麻薬中毒者として台帳に名前が収載されると、その名前抹消は容易ではないからだ。一般に名前抹消には、5年以上の断薬継続に加え、正規雇用されて就労し、安定した社会生活が送れている、といった条件が求められている。
しかし実際には、台帳に収載された多くの人が「死亡」をもって名前抹消となっているのだ。たとえ5年以上の断薬を維持していても、景気の停滞や職業スキルの不足などにより非正規雇用に甘んじるしかない者、あるいは、心身の障害により生活保護受給下での療養生活を送らざるを得ない者は、名前抹消は見込めず、生涯、観察・指導下に置かれかねない。その結果、あくまでも公衆衛生のための制度でありながら、監督期間は数十年という、保護観察等の刑事司法制度をしのぐ長期におよんでしまうのだ。
いや、それどころか、台帳に名前が収載されながらも、実際には何らのフォローアップもされずに長期間放置されている場合さえある。おそらく長い時間経過のなかで都道府県薬務課担当者が何人も交代し、そのどさくさで存在を忘れ去られた「麻薬中毒者」もいるのだろう。
だが、存在を忘れられていても、台帳に名前があるだけで、その人の人生は確実に制限を受ける。というのも、特定の職業――医師、薬剤師、看護師、調理師、理容師、美容師など――の免許申請には、「麻薬中毒者ではない」ことの診断書が必要だからだ。したがって、台帳に名前が収載されているかぎり、これらの資格の新規取得や喪失資格の回復はほぼ不可能といってよい。
いまでも覚えていることがある。30年以上もの昔、医師国家試験に合格した私は、保健所への医籍登録に必要な、「麻薬中毒者ではない」との診断書を、近所の開業医に書いてもらった。
その医師による「診断」は実にいい加減なものであった。医師が「きみ、麻薬とか覚醒剤とか使ったことはないよね?」と質問し、私はそれに「ないです」と答える――ただそれだけだった。診断書作成料は確か数千円だったと記憶している。私は内心、「この局面で、「麻薬を使いました」などと正直に話す奴はいるのか?」と思い、制度のいい加減さ、ばかばかしさに呆れたものだった。
しかし、ひとたび「麻薬中毒者」として台帳に収載されてしまうと、そうはいかない。「麻薬中毒者ではない」ことの証明は非現実的なほどむずかしくなってしまうのだ。
麻薬つながりで、いま思い出したことがある。自分の父のことだ。
小さな不動産会社を経営していた私の父は、ロータリアン――ロータリークラブ会員のことだ――だった。公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターは、1980年代後半以降、毎年6月末からの1カ月間、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を展開してきた。この普及運動を国内各地で支えてきたのが、ロータリークラブやライオンズクラブといった社会奉仕団体だ。
いまから25年ほど前、父は、ロータリークラブが主催する、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動関連のイベントに、俄然、意欲を燃やしはじめた。それまでいっさい関心がなかっただけに、非常に唐突に感じられたが、当時、私が依存症専門病院に勤務していたことが何か影響していたのだろうか? たとえば、父なりに息子の仕事を応援するつもりだった、なんて具合に。
実家を訪れた際、その活動の一幕を収めた写真を見せられたことがある。写真のなかで、父を含むロータリアン十数名が、蛍光色の派手なウィンドブレーカーを着て、カメラに向かって陽気にピースサインをしていた。そして彼らが囲む中央には、麻薬・覚せい剤乱用防止センターのマスコット、「ダメ。ゼッタイ。」君の着ぐるみ――地球儀を顔に見立てて目と口をつけ、そしてその顔から直接手脚が伸びている、ハンプティ・ダンプティさながらのシュールな生命体だ――がうつろな顔で棒立ちしている……。
その写真を示しながら、父は得意げに薬物の恐ろしさについてにわか仕込みの知識を開陳し、自分たちの活動の意義を誇った。いずれの知識も麻薬・覚せい剤乱用防止センターが作ったパンフレットの受け売りで、誇張と脅しにみちた噴飯物の内容だった。聞いていて痛々しくてならなかった。何より悲しかったのは、父には覚醒剤と麻薬の区別さえついていなかったことだ。
なかば呆れながら、私は考えた――父のこの自信、無邪気すぎるはしゃぎようは何なのだ? まるで新興宗教の信者のようではないか?
しかし、父にかぎった話ではないのだ。なぜか人々は、薬物依存症の治療経験がないばかりか、一度だって薬物依存症の当事者に会ったことさえないのに、こと薬物に関しては自信満々、訳知り顔に語る傾向がある。
著名人が薬物事件で逮捕されるたびに、私はよくメディアから取材を申し込まれるが、無理して受けても嫌な気分になることが多い。つい最近もある若手俳優の大麻事件に関して、専門家としてテレビニュースの取材に応じ、「大麻使用による健康被害より、逮捕や、メディアでのバッシングのような社会的制裁の方がはるかに有害」とコメントをした。これは、30年近い自身の薬物依存症臨床から得た偽らざる実感だった。
ところが後日、そのニュース記事がネットニュースに転載されると、一般人から、「この医者、薬物の恐ろしさを何もわかってない。勉強不足だ」といった類いのコメントが多数ついたのだった。
実に不思議だ。なぜ人々は、薬物に関してそこまで自信満々になれるのだろうか?
再び激辛ラーメン店の「大将」の話だ。
最後の刑務所出所からすでに20年を経過しており、彼の犯罪歴はリセットされていた。だから今回、彼が執行猶予判決を得るのは確実だった。
しかし、次に逮捕されたら必ず刑務所送りになる。だから彼は、再度の逮捕だけは何としても避けたかった。じっとしているのが苦手な彼にとって、刑務所経験は地獄以外の何ものでもなかった。もうあんな体験は絶対にしたくない――そのような経緯で彼は私の外来にやってきたのだ。
診察に同席していた彼の妻にも話を振ってみた。聞けば、もともと彼とは小学校、中学校の同級生の間柄で、「腐れ縁みたいな感じで一緒にいる」という。
「困った人なんですけど、憎めないんです。小学校の頃からいたずらっ子で、先生からはいつも叱られてましたが、一方ですごくひょうきんで、私たちには人気でした。中学生の頃でしょうか、お笑い芸人になるなんていいだして、でも、内心、いけるかもって期待してたほどです。なのに、悪い仲間とつきあうようになって、その後、人づてにクスリで逮捕されたって噂も耳にして……」
特に促したわけではなかったが、妻は自分から夫婦の歴史を語りはじめた。
「二人が40歳のとき、たまたま同窓会で再会して、彼、「今度、ラーメン屋をやるんだ」って話してたんです。そのときすごく熱心に交際を迫られて。ちょうど私も離婚したばかりで、仕事もなかったから、店を手伝ってあげることにしたんです。色恋というより、なんかほっとけなくて」
年齢も年齢だったことに加えて、店が忙しかったし、そもそも、夫自体がすでに子どものようなところがあったから、子どもを作る暇もなければそんな気持ちにもならなかった、という。
「そりゃ、何度もクスリをやめてっていいましたよ。でも、無理でした。それに断薬すると感情の浮き沈みが激しくなって、ささいなことでめちゃくちゃ荒れる。私にも手を上げて、警察を呼ぼうと思ったこともあります。でも、前科前歴があるから、呼べば尿を調べられてしまうだろうし……」
「正直、クスリを使っているときの方が穏やかなんです。ですから、だんだんとクスリのことをうるさくいわなくなってしまいました……それが悪かったんですかねえ」
診察の最後、次回までの宿題として彼にひとつお願いをした。それは、実家のご両親に連絡をとって、小・中学校時代の通知表を入手してほしい、というものであった。
彼は困ったように顔をしかめた。
「両親はまだ健在ですけど、さすがに40年以上昔の通知表なんてもうないと思いますよ」
しかし、奇跡的に通知表は保管されていた。
次の診察時、黄ばみ、角が丸く削れて、あたかも古文書のように年季の入った通知表を持参してきた。予想通り、通知票の担任教師所見は、彼が注意欠如・多動症(Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD)だったことを証明してあまりあるものだった。それどころか、家庭からの返信欄には、「(彼が)病院に行きたがらず、治療薬も飲みたがらなくて困っている」という母親のぼやきまで記されてあった。
え? これ、どういうことです?――私は彼に尋ねた。もしかして子どもの頃、精神科に通っていたとか?
「ええ、まあ」
なぜ前回、話してくれなかったのですか?
「覚醒剤とは関係ないかなと思って……。それに、あまりよい思い出でもなかったですし」
詳細は不明だが、児童精神科では何らかの治療薬を処方されていて、その効果は非常に顕著だった。なにしろ、服用すれば授業中ずっと席に座っていられたからだ。しかし、それにもかかわらず、彼はその治療薬の服用を嫌がった。
「医者からもらった薬を服用しないと教室にいることが許されない問題児、というイメージが嫌だったんです。ただでさえいつも先生から叱られてばかりで、ダメな奴と自分でも思っていたのに、ますます自分のことが嫌いになりそうで……」
中学を卒業すると不良交遊をはじめ、やがて10代の終わりに覚醒剤を知った。覚醒剤を使うと、考えがまとまって物事に集中できたし、当時やっていた内装の仕事でもミスが激減した。何よりも、病院でもらった薬を飲めば「病人」だが、悪い仲間のなかで覚醒剤を使えば、「ワルのなかのワル」と目される点が重要だった。幼い頃から何かにつけて叱られてばかりで、大人には不信感しかなかった彼にとっては、親や教師ではなく、仲間から認められることが重要だったのだ。
私は彼にADHDの治療薬――覚醒剤類似の薬剤だ――を投与した。効果は劇的だった。店で客に怒鳴り散らさなくなったばかりか、それまで断薬時に彼を悩ませてきた不注意や物忘れの多さ、さらには身悶えするような焦燥が消えたのだ。
その後8年ほど、私は主治医として彼の治療を担当したが、その間、一度たりとも覚醒剤に手を出すことはなかった。おそらく彼は、自身のADHD症状への自己治療として覚醒剤を使ってきたのだろう。そしていま、それと同じ効果を持つ薬剤を合法的に使用できるようになったのだ。
これならば依存症専門外来でなくともフォローできる、と判断した私は、彼を自宅近くの精神科クリニックに紹介し、彼との治療関係は終結した。
まだ私の外来に通っている頃、彼がよくこう愚痴っていたのを覚えている。
「先生、俺が逮捕されたり、刑務所に入ったりしたのって、一体何の意味があったんでしょうね? 最近よく思うんですよ。俺は悪いことをしたんじゃなくて、ただ単に自分の障害を何とか克服しようと涙ぐましく足掻いていただけじゃなかったのかって」
確かにそうだ。薬物を使うことは、刑務所に入らねばならないほどの悪なのか?
それについては、私自身、これまで何度となく自問してきた――誰かを傷つけたわけでも、あるいは、他人の財産を窃取したわけでもない、単に自分の健康を損ねただけではないか?
なるほど、一部には、「違法薬物使用は反社会勢力への資金提供になるから悪なのだ」と強弁する人もいないことはない。しかし、そもそも法規制などするから、反社会勢力にビジネスチャンスを与えることになったのではないのか?
もちろん、薬物を使っていれば何かと周囲に迷惑をかける可能性がある、といわれれば、まあ確率的にはそうかもしれない。だが、そのような未然予防が目的の罰ならば、スピード違反のような道交法違反と同程度でよい気もする。
頭の体操として、ひとつ考えてみてほしいことがある。
私の専門外来は、原則、物質の依存症を対象としているが、まれに「盗撮癖」という行動の依存症の治療を求めて受診してくる人もいる。スマートフォンのカメラを用いて女性のスカートの中、あるいは、スカートの裾から露出する脚を無断撮影して逮捕された人たちだ。不思議と社会的立場のある人が多い。上場企業の役員や大学教授、あるいは国家公務員や医師……などなど。
多くは、逮捕された後、弁護士の勧めで来院する。要するに、減刑目的の戦略だ。逮捕のきっかけとなった事件の被害者は一人だが、それは氷山の一角であることが多い。通常、自宅パソコン内には、おびただしい数の盗撮写真を収めたフォルダが保管されている。そこには、見知らぬ女性の身体の一部がクローズアップされた映像があまた居並び、ルーブル美術館さながらの壮大なギャラリーが作り上げられているのだ。
私は再発防止目的のカウンセリングを提供し、彼らの減刑に協力するわけだが、どうしても複雑な心境になるのを抑えきれない。というのも、被害者との示談が成立すると、少なくとも初犯ならば患者は起訴されず、したがって、前科にも残らなければ、職を失うこともないからだ。一方、薬物犯罪はというと、被害者なるものが存在せず、したがって、示談したくともする相手がいないのだ。だから、ほぼ確実に起訴されるし、前科として残る。
あなたはどう考えるだろうか? 薬物使用と盗撮、いずれがより「悪」だろうか?
彼の主治医となって以来、私はあの激辛ラーメン店に行くのを控えた。内科や整形外科といった身体科ならばともかく、精神科の場合、多重関係――すなわち、現実の生活で関係がある者と治療関係を結ぶこと――は好ましくないとされている。ましてや彼が抱える問題は違法薬物の依存症だ。そんな重大な秘密を知っている医者が来店すれば、とてもじゃないが、彼は心穏やかではいられまい。ついでにいえば、私がかつて常連客であったことも、彼には伝えていない。
それでも一度だけ、仕事帰りに近くまで立ち寄って、遠目から店の様子をのぞいたことがある。街灯の少ない夜闇の底で店はオレンジ色の光を放ち、以前よりも繁盛しているのか、店外には入店待ちの客が列をなして待っていた。さらに近づいてみると、湯気に曇ったガラス窓の向こうで、カウンター内を機敏かつ縦横無尽に動きまわる彼の姿がうっすらと見えた。
私はその姿に満足して踵を返し、そこから5分ほど歩いた場所にある別のラーメン屋に入った。もちろん、注文するのは激辛ラーメンだ。
辛さにむせながら、私は取り憑かれたようにして麺を掻き込む。すると、口腔粘膜いっぱいに鋭い痛みが広がった。だが、その感覚はさほど長引かずにすぐに消える。何かが足りない。
弁明するつもりはない。私は激辛依存症だ。明らかに耐性が上昇し、辛さへの渇望がエスカレートしている。中途半端な刺激はかえって渇望の呼び水となるばかりだ。あるいは、彼の店のラーメンスープには、唐辛子や花椒のほかに何かやばい成分――たとえば麻薬に相当するようなアルカロイド――が含まれていたのだろうか?
あり得ない話ではない。なにしろ、七味唐辛子にだって、加熱処理をされているとはいえ、大麻の種が入っているのだ。だとすれば、私は「麻薬中毒者」の嫌疑を免れないが、さいわい私が彼の店に行くことはもうない。ひとたび彼の治療にかかわった以上、私には守るべき距離がある。
不意に思い立って、私は箸を置き、スマートフォンを手にとった。なぜかその夜、エゴサーチなる自虐行為をやってみたい衝動に駆られたのだ。しかしその直後、私は全身の力が抜けるほどの衝撃に見舞われることとなる。検索結果のなかに、「よくテレビで薬物事件のコメントをしている精神科医が、いますごい勢いで激辛ラーメンを食べている」というSNS投稿を発見したからだ。
さっき消えたはずの辛さの感覚が、突然、口腔内で鮮明に蘇り、思わず咳き込んだ。
ちっ。私は舌打ちをする。まだ半分以上麺は残っていたが、諦めるしかない。私は席を立つとそそくさと会計を済ませ、逃げるようにして店を出た。
参考文献
- 最高裁平成17年7月19日決定、最高裁判所刑事判例集、59巻6号、600頁。
- 河上和雄、古田佑紀、原田國男、中山善房、渡辺咲子、河村博編『大コンメンタール刑事訴訟法 第2版 第4巻(第189条~第246条)』769-770頁、青林書院、2012年。
- 松本俊彦「麻薬中毒者届出制度の意義と課題」精神神経学雑誌、122(8): 602-609、2020年。
- 同上。
編集部注:本連載では、登場人物の匿名性を保つため、プロフィールの細部に変更を加えています。