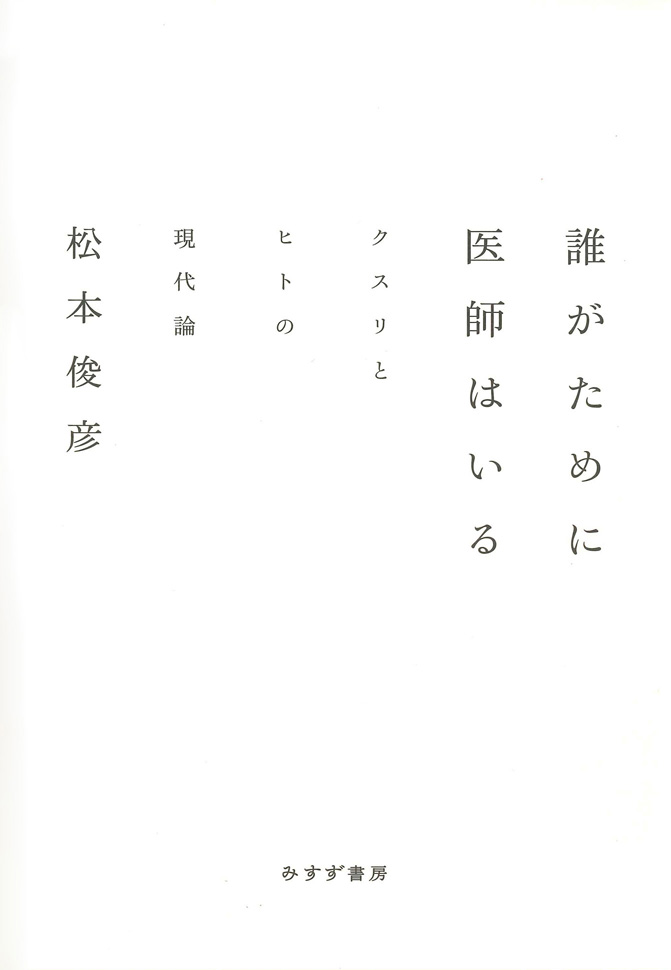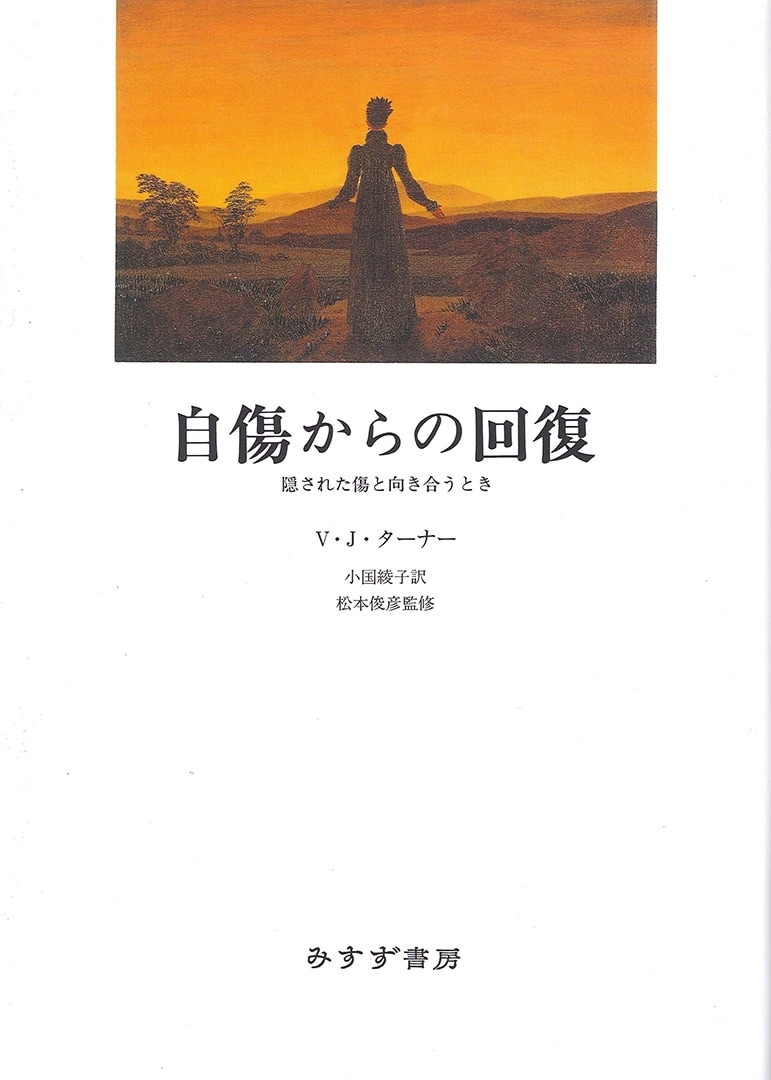鬱蒼とした樹々のあいだから、街灯が深夜の公園を頼りなく照らし出している。この公園は、最寄りの駅からの帰宅途上にあり、私はよく公園を突っ切って、帰路を大幅にショートカットしている。その夜もそうだった。
私は立ち止まり、人目がないのをよいことに煙草に火をつけた。そして、深々と煙を吸い込みながら、ほの暗い街灯の下を走り過ぎていく人たちを眺めた。さまざまな背格好の人が、思い思いのペースで走っている。滑らかな動きと大きなストライドで駆け抜ける、明らかにアスリートとおぼしき人、そして、ドタドタと大きな音を立て、喘ぐような荒い息づかいで走る太った中年男性、さらには、早々に走るのを諦めて歩きながらスマホを操作し、おそらくはワイヤレスイヤホンから流す音楽の選択に迷っている若者……。
時刻はもうすぐ午前1時だ。よくもまあこんな時間に走るものだな、と呆れ気味に思う。深夜まで居残り仕事をし、こうして路上で喫煙している私も大概だが、こんな時間に走る人たちもそれなりにイカれている。少なくとも健康的とはいえない気がする。
ぼんやりそんなことを考えていると、ちょうど目の前を、サウナスーツを着込んだ若い女性が通り過ぎた。深く被ったフードからのぞく顔は青白く、何か思い詰めたように強ばった表情をしている。落ち窪んだ目とこけた頬の様子から察するに、この女性は摂食障害に罹患していて、さらなる減量を目指して走っているのだろう。
やはり、ここにいる人たちは健康的ではない。そもそも、こんな時間帯に走ること自体、一種の自傷行為じゃないのか――そんなふうに皮肉ってみたい気持ちになるが、同時に自分のなかに、少し憧れに似た気持ちが湧き起こっているのも自覚している。いつの日か、自分もまたこんなふうに走る生活をしてみたらどうだろうか? たとえば煙草をやめ、酒も控え、仕事前に軽く走ってから出勤する――そんな生活だ。
私は再び走ることができるのだろうか?
現在の私を知る人はにわかに信じられないかもしれないが、かつて私はランニング中毒者(アディクト)だった。それは40年前の話、まだ自分が何者になるのか皆目見当がつかなかった、思春期の頃の話だ。
私が通った中学校は小田原の海岸と隣接した場所にあり、防波堤がグラウンドと砂浜を分かつ境界線となっていて、教室からは、陽光を照り返す鏡のような相模湾が見えた。そのような立地のせいか、週1回開催される海岸マラソンが学校の恒例行事となっていた。毎週火曜日の6時限目、全学年の生徒は号砲に合わせていっせいにスタートし、砂浜を走る。男子は2キロ、女子は1キロだ。毎回、順位とタイムがチェックされ、男女別に全校生徒中の上位10パーセントにあたる30位までが校内に貼り出される。
多くの生徒にとって、海岸マラソンは理不尽な拷問であり、実際、仮病を使ってこの恒例行事をサボる者もいた。しかし、私の場合は違った。これこそが中学校生活最大の楽しみだったのだ。
なぜか? それは、長距離走だけが自分にできる唯一のスポーツだったからだ。運動音痴の私にとって、それまで体育の授業といえば悪夢のような時間であり、特に野球やサッカー、バレーボール、テニス……といった球技については、それらの競技の消滅を願って呪詛したいほど憎んでいた。球技に比べれば、走るのはまだましだった。しかし、決して足が速かったわけではなく、走ることならば少なくとも悪目立ちしないですむ、といった程度の話だ。
ところが、中学生になって初めて海岸マラソンを体験したとき、私は重大な発見をした。それは、「長距離走ならば人並みより少し上くらいかもしれない」というものだ。運動に関して「人並みより少し上」というのは、私にとって人生初の快挙だった。さらに4、5回ほど海岸マラソンを経験するうちに、「長距離走は、唯一人に誇れるスポーツ種目になるかもしれない」との思いを深めた。というのも、1年生ながら全校上位30位以内に入るようになったからだ。
マッチョなことをいうようで恥ずかしいのだが、思春期の男子にとって、人に誇れるスポーツ種目があるか否かは、まさに沽券に関わる問題だ。なるほど、陸上競技は野球やサッカー、バスケットボールに比べればいかにも地味だが、それでも、何も得意なスポーツがないよりはましだ。それに個人種目だから、失敗しても、チームメイトからの顰蹙を買う屈辱は避けられる。私は勇んで陸上競技部の門を叩き、以来、3年間、必死に長距離走にしがみつくことになった。
振り返ってみると、私の中学生活は走ること一色に覆われていた気がする。毎朝、制服を鞄のなかに詰めてジャージ姿で家を出発し、学校までの2キロの登校経路を走った。そして、始業1時間前に学校に着くと、今度は、海を横目に見ながら防波堤上の道を2キロ走るのだ。そして放課後は、陸上競技部の練習メニューを通常通りこなし、それが終わると再び走って下校する。帰宅して夕食をとると、それからまた1、2キロ走る……。ざっと計算すると、1日の走行距離は軽く8キロは超えていた。中学生のトレーニング・メニューとしては十分すぎる量だ。おかげでいつも疲れていて、授業中はよく居眠りをした。夜も21時以降は起きていられず、そのせいで話題のテレビドラマや歌番組にも疎かった。
休日も走った。というか、走らないと不安だった。1日休むと筋肉や心肺機能が低下する気がしたのだ。筋肉痛がない状態が不安だった。筋肉痛こそが筋肉の成長の証と勘違いしていたこともあるが、それだけではない。筋肉痛がないと脚が妙に軽すぎて、自分の身体ではないような居心地の悪さを感じたのだった。
生来の凝り性を発揮して、私は情報収集にも余念がなかった。少しでも暇があると、近所の書店で長距離走トレーニングの指南書や陸上競技雑誌を片っ端から立ち読みした。また、テレビでマラソン大会や駅伝、陸上競技大会の中継があると知れば、テレビにかじりついて観戦した。たとえ時差のある海外開催のマラソンであっても、衛星中継放映があれば、仮眠をとって深夜に起き出し、眠い目をこすりながらテレビの前に陣取った。
私には憧れのランナーが2人いた。1人は英国の中距離選手セバスチャン・コーであり、もう1人は米国のマラソン選手アルベルト・サラザールだった。
セバスチャン・コーは、1980年のモスクワ・オリンピックと1984年のロサンゼルス・オリンピックの2大会連続で、1500メートルの金メダルを獲得している。そのほかにも、中距離トラック競技で9つの屋外と3つの屋内の世界記録を樹立し、中距離種目における世界記録更新はなんと12回にもおよんでいる。特にオリンピックや世界陸上選手権のたびに演じた、同じ英国人ライバル、スティーブ・オベットとの熾烈なデッドヒートは、当時、陸上競技マニアならずとも注目し、話題になっていた。
コーのランニングフォームは独特だった。上体を鳩胸のように反り返らせ、腕を、それこそ拳が自らの顔面を殴りつけそうなほど大きく振り、腿をやたらと高く上げて走る。確かに正面から見ると、そのフォームはまるで、「子ども相手に蒸気機関車の真似をする、ひょうきんな大人」といった風情だが、横から見ると、そうした滑稽感は霧散する。左右の脚がサバンナを疾駆するチーターのように前後に伸びやかに開き、大きく、そして美しい形のストライドを作り出しているのだ。そのせいか、中距離選手としては小柄な方なのに、走っているときの彼は大きく見えた。
とりわけ印象的なのは、最後の100メートル、ラストスパートの瞬間だった。彼は歯を食いしばって顎を上げ、ますます腕を大きく振り、いっそう腿を高く上げ、フォームは完全に短距離走者のそれへと変容するのだ。そしてみるみるうちに、他の選手を引き離す。そのときのコーの歪んだ顔を、私は精悍で美しいと思った。ゴール後も元気だった。スタンドの観客に対して手を挙げながら、国旗を身にまとってウィニングランをするのが、コーお決まりの儀式だった。
一方、サラザールは、1980年から1982年までニューヨークシティマラソンで3年連続優勝を飾っている。そのうちの初回にあたる1980年のレースは、彼にとっての初マラソンであったが、文字通り「彗星のごとく」登場し、この1戦で一気に期待の大型新人と目されるようになった。なにしろ、初マラソンでいきなりサブテン(2時間10分切り)を実現し、しかも、それは当時の米国内第2位の記録だったのだ。さらに翌年の同大会では、2時間8分13秒という暫定世界記録で優勝し、あわや12年ぶりの世界記録更新かと、世界中のマラソンファンを興奮させたのだった(後の再測定で、コース距離が42.195キロメートルに約148メートル足りないことが判明し、残念ながらその記録は抹消された)。
もっとも、サラザール人気には、いかにもカリビアン的異国情緒が漂う甘いマスクも貢献していただろう。しかし、現実の彼はカリビアン的享楽性とは無縁で、むしろ真逆の、自分に厳しい禁欲主義者だった。彼は「走ること」「勝つこと」に執着し、その練習量はライバルたちより突出して多く、たえず極限まで自分を追い詰めようとしていた。おそらく彼の魅力はそうした矛盾にこそあり、だからこそ、スポーツライターのジョン・ブラントなどは、皮肉めいた表現で彼を次のように形容したのだろう。曰く、「主婦たちを狂わす、神学校出たての若い司祭のようだ」と(1)。
サラザールは、さまざまな点でコーとは対照的なランナーであった。身長180センチと、マラソンランナーとしては大柄であるにもかかわらず、そのランニングフォームは小さくまとまり、どこか身を屈めて摺り足で移動する、古代中国の宦官を彷彿させた。つまり、歩幅ではなく、回転数でスピードを稼ぐピッチ走法――地面をキックした足を高く蹴り上げることもなければ、腿を高く上げることもない、ひたすら摺り足という地味なフォームだ。
何よりもコーと異なっていたのは、ゴール後の様子だった。フィニッシュラインに達するや、彼はいつも出迎えの係員たちの腕のなかに崩れるようにして倒れ込み、そのまま抱えられて医務室直行だった。おそらく勝利への執着心が、肉体的限界を超えてもなお彼を走らせていたのだろう。これではウィニングランどころではない。
サラザールが勝利したレースでとりわけ忘れられないのは、1982年のボストンマラソンだ。私はそのレースの一部始終をテレビで観戦していた。ライブ中継だったのか、それとも録画だったのかは定かではないが、確かにその映像を鮮明に記憶している。
その大会で、サラザールはディック・ビアズリー――もともとは一市民ランナーにすぎなかったが、めきめきと頭角を現し、レースのたびに自己最高記録を大幅に塗り替えてきた奇跡の男――とすさまじいデッドヒートを演じた。その日は、4月のボストンにしてはめずらしく気温が高く、容赦なく太陽が照りつけていた。そんな悪条件のなか、2人は、ボストンマラソン名物「心臓破りの丘」を過ぎた35キロ以降からゴールまで、およそ7キロにわたる一騎打ちをくりひろげたのだ。
この一騎打ちは、後に「太陽の決闘(Duel in the Sun)」と名づけられた。コース上に沿道の観客があふれだし、先導する白バイ隊が観客を制止しながらかろうじて切り拓いた隘路を、2人は交互に順位を入れ替えながら進んだ。まちがいなく、どちらにも勝つチャンスがあった。しかし、ラスト100メートル地点で、サラザールは「摺り足」のピッチを一気に上げ、わずか2秒という僅差で優勝を手にしたのだ。タイムも見事だった。悪条件下でのレースであったのに、1位、2位ともに米国記録を塗り替えたからだ(2時間8分51秒と2時間8分53秒)。
ともあれ、中学時代、私はそのコーとサラザールに夢中だった。そして、好きが昂じて、2人のランニングフォームまで真似る、という無謀な努力までした。もちろん、その試みは失敗に終わった。かえって通常よりも走行タイムが落ちたのだ。まああたりまえだ。体幹を含めた全身の筋力の鍛え方が違うのだから、トップアスリートと同じフォームで走れるわけがない。
仕方がなく、好きな人の所持品を真似ることに切り替えた。ロードレース用のシューズだ。私は、サラザールが履いているナイキのシューズを購入した。当時、中学生の陸上競技選手でアシックス以外のシューズを履いている者などいなかったこともあり、そのシューズを履いて練習していると誇らしい気分になったものだ。
私が長距離走に熱中したのは、「思春期男子の沽券の問題」だけではなかった。実は、単純に走ることが気持ちよかったのだ。ただし、この気持ちよさはなかなかむずかしいところがあり、走れば必ず体験できたわけではない。むしろ「運がよければ体験できる」といった種類のものだった。しかし、ギャンブル依存症でも明らかなように、必ず報酬が得られる場合よりも、たまに「アタリが出る」といった間欠強化の方が、人をハマらせる力は強いのだ。
初めてその感覚を体験したのは、中学1年時の正月に参加した市民マラソン大会だった。その大会は元旦恒例の催しで、小田原城址周囲を3周し、総距離はおよそ5キロになる。新年最初の日に、小田原城の天守閣を仰ぎ見ながら走るのは何とも晴れやかな気分だったが、そうした景観以上にこの5キロという距離と、そしてその距離に合わせた走りのペース配分が、少なくとも当時の私にはマッチしていたようだ。
具体的には、最初の2周は慎重にペースを抑えて走るよう心がける。ここが肝心だった。ここでうっかり周囲のペースに引きずられると、早い段階で筋肉に乳酸が蓄積し、最後の1周で脚が動かなくなる。しかし、最初の2周で自分のペースを守ることができれば、最後の1周に入った頃には不意に腿の重だるさやふくらはぎの痛みが気にならなくなる。そして、気分が高揚して自信が漲り、どれだけでも走れる感覚を体験できるのだ。その状態に達すると、私はペースを上げて追い上げをはかり、何人もの先行者を追い越すことができた。
これがいわゆるランナーズハイなのか――少なくとも私はそう信じてきた。かねてよりランナーズハイの状態においては脳内の内因性オピオイド、β‐エンドルフィンが大量に分泌されているといわれてきた。しかし最近では、ランナーズハイをもたらす物質はβ‐エンドルフィンではなく、脳内の大麻成分類似物質、内因性カンナビノイドの一種ではないか、という説も提唱されているらしい。まあどちらでもよい。要するに、私は中学生にしてオピオイドやカンナビノイドといった依存性物質の薬理作用に魅了され、虜になっていたわけだ。
ただ、そうはいっても、やはりレースの順位や走行タイムといった競技成績は気になる。当時、私は、練習量については他の誰よりも多いと自負していたが、それほどの努力にもかかわらず、競技成績はパッとしなかった。確かに校内では速い部類ではあったが、市大会レベルになるとまったく通用しなかった。これはどう考えても、よほど才能に恵まれていないことの証左だろう。
結局のところ、距離の長短の違いこそあれ、最後は肉体全体の運動性能が問われる。特に、私がトラック競技の主戦場としていた1500メートルでは、ラスト1周、いやラスト200メートルは完全に短距離走の勝負になる。瞬発的なスピードに欠ける私は、たとえそれまで集団の先頭を走っていても、ラスト1周の鐘が鳴った途端に一気に置いて行かれ、気づくと最後尾という悲劇を何度も体験していた。そこにはランナーズハイなど微塵もなく、あるのは窒息寸前の息苦しさと、痺れて思い通りに動かない自分の脚への苛立ち、そして絶望的な恥辱感だ。とてもじゃないが、コーのような爆発的なスパートなど無理だった。
私なりに無我夢中で走り続け、気づけば中学3年の秋を迎えていた。この時期、学校の方針によって、高校受験を控える3年生は有無をいわさず、部活動を引退させられた。これまでは走ることに執着し、悪天候で走れない日が続くとイライラしていた私だったが、この部活動引退命令のおかげで不思議と気持ちが楽になった。さらに不思議だったのは、あっという間に「走らない生活」に安住し、腿に筋肉痛がない状態にも慣れたことだった。
やがて受験が終わり、高校に入学した。入学して最初の1週間、私は陸上競技部に入るかどうか迷ったが、中学時代に何度も経験した、最後の1周で大勢の選手に一気に抜き去られる悪夢を思い返すたびに、もう一度それを体験する気持ちにはなれなかった。私は入部しないことに決め、自分にこう言い聞かせた。「走ることが唯一得意なスポーツだと信じていたが、それは勘違いだった。自分には所詮スポーツは無縁なものなのだ」と。
それでも、未練は残った。「また走ろうかな」と考える日は周期的にやってきて、ときおり書店で陸上競技雑誌のページをめくっては、コーとサラザールの動向を追いかけたものだ。
高校2年の夏、ロサンゼルス・オリンピックが開催された。私は、テレビにかじりついて、2人のヒーローの動向を見守った。コーは、800メートルでこそライバル、スティーブ・オベットに敗れて銀メダルに甘んじたものの、1500メートルでは見事なラストスパートを炸裂させ、モスクワ大会に続いて金メダルを獲った。一方、サラザールは精彩を欠いていた。金メダルを期待されていたマラソンにおいて、彼は早々に先頭集団から脱落し、最終的に15位――やはり期待外れに終わった瀬古利彦のすぐ後ろ――でゴールした。最後、陸上競技場に戻ってきた彼は、負傷兵のように痛々しかった。
ヒーローたちの戦果は見事に明暗が分かれ、それ以来、サラザールはマラソン界で名前を聞かなくなった。
今回、本稿を執筆するにあたって、ふと気になってロサンゼルス・オリンピック以降、姿を消したサラザールについて調べてみた。すると、ロサンゼルスでの惨敗の背景が理解できる気がした。
どうやら、1982年のボストンマラソンにおける「太陽の決闘」こそが彼の競技生活の頂点であり、それを境に、彼のコンディションは音を立てて崩れ出したらしいのだ。ボストンでのレース中、ほとんど水分補給をしなかったサラザールは、ゴール後にひどい脱水状態に陥り、そのまま救急医療センターに搬送されて、生理食塩水の点滴を6リットルも投与されたという。ということは、あのラストスパートは文字通りの命懸けであったわけだ。
その一件を機に、彼のなかで走ることに対する感情が激変したらしい。以前は走ることが好きでたまらなかったのに、あのレース以後、彼は走ることが苦痛になり、少しでも走ると呼吸が苦しくなる、という怪現象に襲われるようになったのだ。当然ながら、競技成績も低迷した。するとサラザールはますます焦って、トレーニングに執着し、いっそう走り込もうとした。つまり、「長く走れば走るほどよい」という考えに取り憑かれたのだ。その結果、彼の免疫系は不調を来たし、年に何回も呼吸困難になるほどの気管支炎に罹患するようになった。
あのレースから10年あまり、彼は走ることを憎み続けていたという。それにもかかわらず、無理に自らを追い立てて走り込み、その結果、体調を崩した。完全に悪循環だ。当時のことを後に彼はこう述懐している。「片足を失うような大ケガをしたらいいのにと思ったものだ。ひどい話に聞こえるだろうが、片足を失ったらもう自分を苦しめる必要はない」。まもなく彼は、医師からうつ病と診断され、抗うつ薬を服用するようになった。
ちなみに、「太陽の決闘」の相手、ビアズリーも決して無傷ではなかった。あのボストンマラソンから10年のうちに、彼は不運なケガや交通事故にくりかえし遭遇し、首や背中、あるいは膝などの手術を合計4回受けた。そのたびに医師によって医療用麻薬が大量に処方され、1995年頃には医療用麻薬依存症の状態に陥っていたようだ。
そして1996年9月30日、ある報道が全米に衝撃を与えた。ビアズリーが処方箋偽造の嫌疑で逮捕されたのだ。不正な方法で医療用麻薬を入手したという。幸いにして懲役刑は免れたものの、代わりに、彼は精神科入院とリハビリ施設での長期にわたる生活、薬物依存症の自助グループへの参加を余儀なくされた。なお、現在の彼は薬物依存症から回復し、自ら財団を立ち上げ、薬物依存症に苦しむ人への支援活動に従事しているらしい。
いうまでもなく、「走る」という行為は、人類が二本足歩行を始めた当初より備わる基本的動作だ。二本足で走ることのメリットは大きい。広い視野を確保できるので、攻めるにせよ、逃げるにせよ好都合だし、手に武器を持つこともできる。また人類は、全身を覆う体毛を失ったことで高い体温冷却能力を得て、長距離の連続走行が可能になった。考えれば考えるほど、走ることは人類に与えられた特別な恩寵といわざるを得ないだろう。
それに、走ることは、もっとも金がかからない、そして場所や環境も選ばないスポーツだ。だからこそ、その種目であれば、貧しい国に住む若者、あるいは移民の若者にも活躍のチャンスがある――キューバ移民のサラザールはもとより、モハメド・ファラー(ロンドン・オリンピック5000メートル、10000メートルの金メダリスト。ソマリアから人身売買被害者として英国へ)やシファン・ハッサン(東京オリンピック5000メートル、10000メートル、およびパリ・オリンピック女子マラソン金メダリスト。エチオピアから難民としてオランダへ)などはその好例だろう。
しかし他方で、「走る」ことで人生を狂わせる人もいる。
思い出すのは、かつて治療を担当していた、摂食障害の元長距離選手のことだ。
彼女は幼い頃から走るのが好きだった。登下校はあたりまえのように走り、友人と自転車に乗って遠出をする予定があれば、彼女はわざと徒歩で集合場所に赴いた。そうすれば、みんなが自転車で移動する際、友人を追いかける、という正当な理由で走ることができるからだ。それくらい走ることが好きだった。当然、中学では早くも長距離走で頭角を現し、高校時代は、自己流の練習だけでインターハイで活躍した。彼女はほとんど野生のランナーだった。
その後、スカウトされて実業団の陸上競技部に入ることとなったが、チームの監督は非常に厳格で、いままでのような「野生」を許容しなかった。特にうるさく指導したのが食事と体重の管理だった。監督はケーキをうれしそうに頬張る彼女を見咎めて、怒声を上げた。「ケーキなんか食べちゃダメだ。長距離走者は軽くなければならない。そうしないと心臓の負担が大きい」。いつしか彼女が戦うべき敵は、他チームの選手ではなく、空腹感になった。
まもなく彼女は、食後に喉の奥に指を突っ込み、嘔吐することを覚えた。そうすればいくら食べても体重は増えないから、監督に叱責されずにすむ。しかし、低栄養やそれによる内分泌異常は無月経のみならず、骨密度の低下をもたらし、疲労骨折などのケガを多発させた。次第に彼女は練習を休む日が増え、大会出場はキャンセル続きとなった。20代半ばには、何の成績も残さないまま、実業団チームから去ることを余儀なくされた。
夢を失った彼女は精神的に追い詰められ、ますます過食・嘔吐に没頭した。日を追って増大する食費を自力でまかなえなくなると、スーパーやコンビニで食料品の万引きをするようになった。栄養状態は悪化し、身体は衰弱した。精神科病院にも何度か入院したが、点滴や経鼻栄養管の自己抜去、あるいは、頑固な拒食や盗食行為のせいで病院側が先に音を上げた。万引きで何度か警察沙汰になったが、彼女の、頭蓋骨の形がはっきりわかるほど痩せた顔、割り箸のような四肢に驚いた検察官は、勾留中に死亡しかねないと危険を感じ、起訴猶予として釈放した。
初めて診察室で会ったとき、まだ30代なのに50代かと見紛うほど、彼女の顔は皺だらけで、老け込んで見えた。すでに多数回の精神科入院を経ていて、彼女にはもはや精神科治療に対する期待などなかった。だから、入院や栄養補給といった積極的治療のいっさいを拒絶し、「もうこれ以上傷つきたくないんです」「自分で死ぬのは怖いけど、早く死にたい……誰か殺してくれたらいいのに」といった言葉を口癖のようにくりかえした。
手の施しようがなかった。体重28キロ、加えて重度の貧血と低カリウム血症を呈するなど深刻な状態であったが、ここまでひどいと、うかつに点滴で栄養補給や電解質補正をしようものなら、かえって体内の電解質と浸透圧の均衡を崩し、致死的な事態を招きかねない。
4年ほど診察室で彼女と会い続けた。すっかり精神科医嫌いになっていた彼女が、それでも4年通い続けたのは、私が過食・嘔吐や万引きを「やめろ」といわなかったからだろう。もっとも、「いまさら何もいえない」というのが正直なところだった。なにしろ、下手に過食・嘔吐をやめれば、それだってかろうじて保っている体内のさまざまな均衡を崩しかねない。私にできたのは、受診のたびに「今週も生きててよかった」と声をかけることくらいだった。
その後、彼女はちょっとした転倒で大腿骨頚部を骨折し、その手術後に併発したありふれた感染症によりあっけなく死亡した。
ところで、サラザールにはなおも波乱に富んだ後日譚がある。
現役選手を引退し、うつ病から回復したサラザールは、今度はコーチ業に専念することとなった。ナイキ・オレゴンプロジェクトのコーチだ。サラザールが指導した選手のなかにはオリンピック出場選手が枚挙に暇がないほど存在し(わが国の大迫傑もそのひとりだ)、それは、彼が指導者として優れた人物であったことを証明している。なかでも、2012年ロンドン・オリンピックでは、教え子のモハメド・ファラーとゲーレン・ラップが10000メートルで金メダルと銀メダルを獲り、ファラーに至っては5000メートルでも金メダルを獲っている。
しかし、それが指導者としてのサラザールの頂点だった。2019年、サラザールは指導していた選手にドーピングを指示したとして4年間の活動禁止処分を受け、ナイキ・オレゴンプロジェクトは閉鎖に追い込まれた。さらに女性選手から身体的、精神的、性的虐待の告発も受けた。どうやら彼は、選手に苛酷な減量を強要したばかりか、「生理を止めろ」「痩せてもっと乳房を小さくしろ」といった、選手の女性性を否定するような指導をしていたらしいのだ。これにより、2020年、サラザールはスポーツ指導者としての資格を永久に剥奪された。
あの謹厳な禁欲主義者は、一体どこで道に迷い、あるいは、ボタンを掛け違えたのだろうか?
ちなみに、サラザールとは対照的に、コーは引退後も光ある場所を歩み続けた。活躍の場を政治に移して国会議員となり、2000年には男爵として終身貴族に叙された。併行して、国際オリンピック委員会や国際陸上競技連盟での要職も歴任し、国際陸上競技連盟会長在任中には、陸上競技におけるドーピング撲滅に尽力したことが知られている。
深夜の公園でランナーたちを眺めながら、私はスマホを取り出し、暇つぶしにSNSのアプリを起動する。タイムラインには、同業の友人たちがランニングに関する記事を投稿していて、どこかのマラソン大会で完走し、清々しい笑顔でガッツポーズやピースサインする写真が流れてくる。いずれも何らかの事情から一念発起し、ある日を境に不摂生な生活から足を洗い、ランニングに精を出すようになった人たちだ。
煙草をくゆらせながら私は考えた。最後に全力疾走し、ランナーズハイを体験したのはいつだったろうか、と。
おそらくそれは高校2年時の元旦だ。大晦日の夜、私は、いつもつるんでいた同級生3人と友人宅に集まり、酒盛りをしていた。年明け以降、大学受験へと続く、長く重苦しい季節に突入し、そのまま卒業、そしてそれぞれの道へと散ったことを考えると、本当の意味で彼らと胸襟を開いて話したのは、それが最後だったかもしれない。
ともあれ、夜通し騒いだその酒宴も、さすがに未明をすぎる頃には疲れと眠気によって勢いを失い、会話も途切れがちになった。そんなとき誰かが声を上げて提案したのだった。
「外が明るくなり始めてる。いまから海に行って初日の出を見ようぜ」
「もう間に合わないよ」
「いや、たぶんギリギリ大丈夫」
「走れば間に合うかも」
結局、私たち4人は外に出て、まだ群青色の底でまどろんでいる郊外に立った。商店街のある大通りに出て南に1.5キロ進めば、海岸に突き当たる。軽く走るにはよい距離だ。
最初はふざけ半分で気楽に走っていた。しかし、途中で誰からともなく競うような空気が生じ、横並びの列がいつしか縦に長く伸び、気づくと自分が最後尾になっていた。
「マジか!?」
その瞬間、陸上競技部時代の負けん気に火がついた。私は地面を蹴る足に力をこめ、腿を高く上げストライドを広げて、一気に先頭に立った。まだ誰かが背後にぴったりついてくる気配がある。そこで今度はピッチも上げた。まもなく背後の足音が遠退き、やがて聞こえなくなった。私はペースを弛めなかった。後で「何ひとりで勝手に本気になってんの?」と茶化されるなと思ったが、かまわなかった。徹夜明け、それも酒盛りの後だったが、気分は高揚し、全身に力が漲っていた。私は思った。「まるで何かヤバいドラッグでもキメているみたいだ」と。
それが最後のランナーズハイだった。そのとき自分の心拍音以外、周囲からいっさいの音が消え去り、風景も見えなくなっていた。私は、誰もいない無音の世界、青いトンネルのような空間を走り続けていた。
注
- John Brant, Duel in the Sun: Alberto Salazar, Dick Beardsley, and America's Greatest Marathon, Rodale Books, 2006.
編集部注:本連載では、登場人物の匿名性を保つため、プロフィールの細部に変更を加えています。