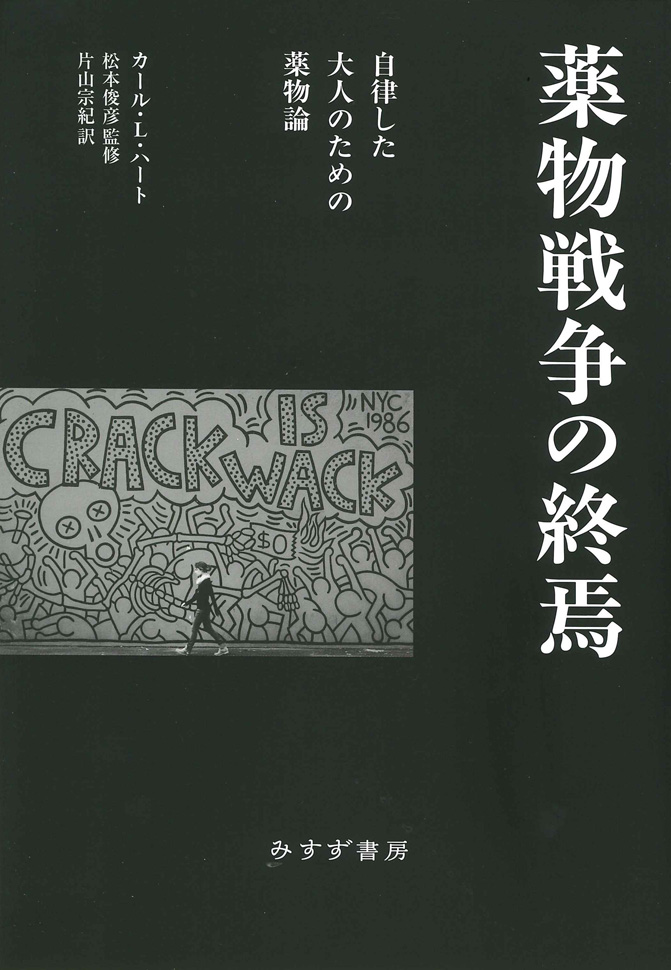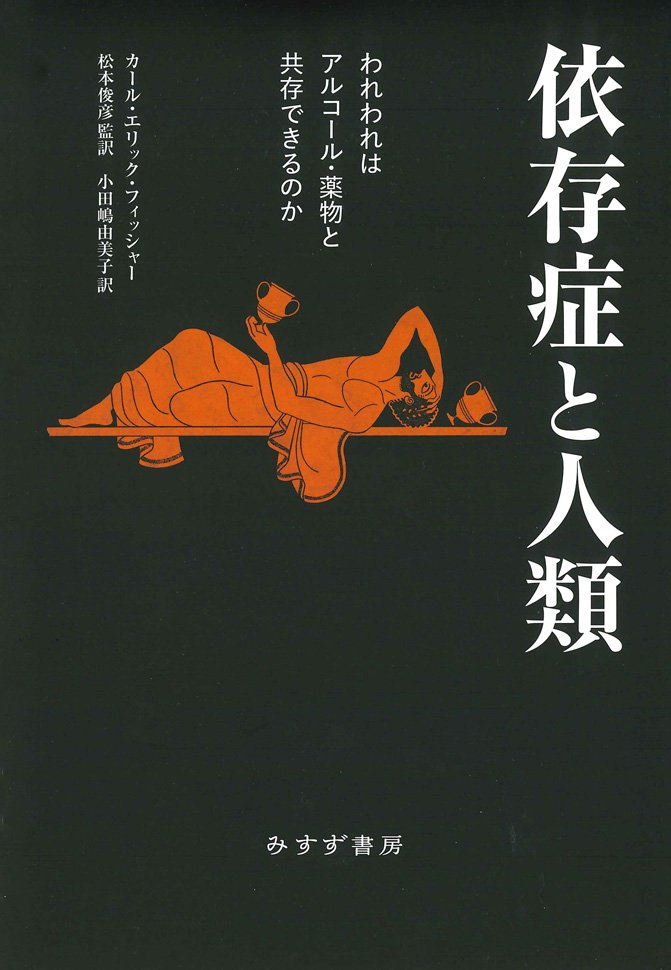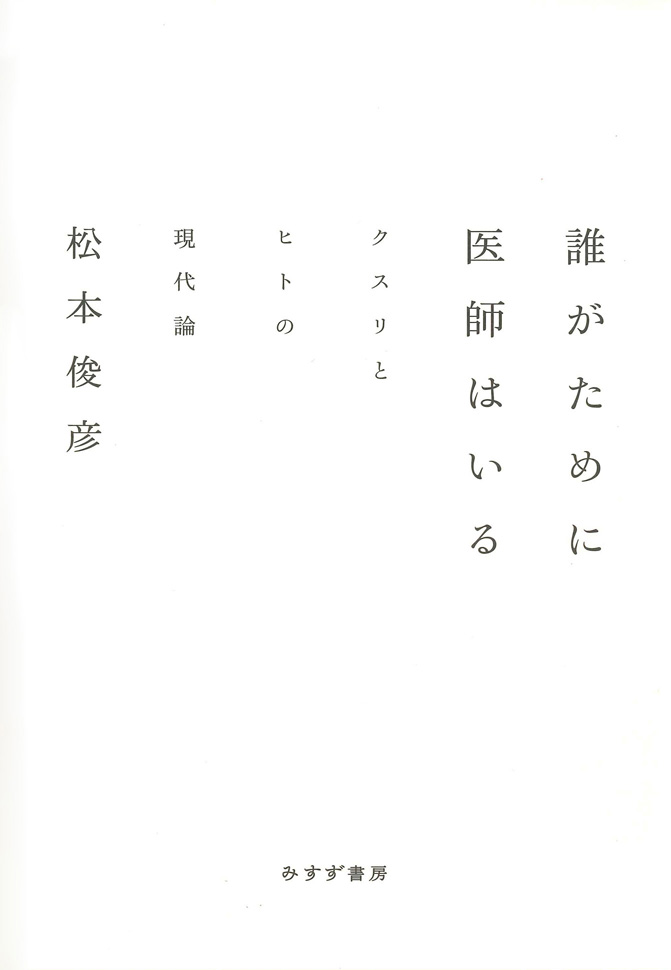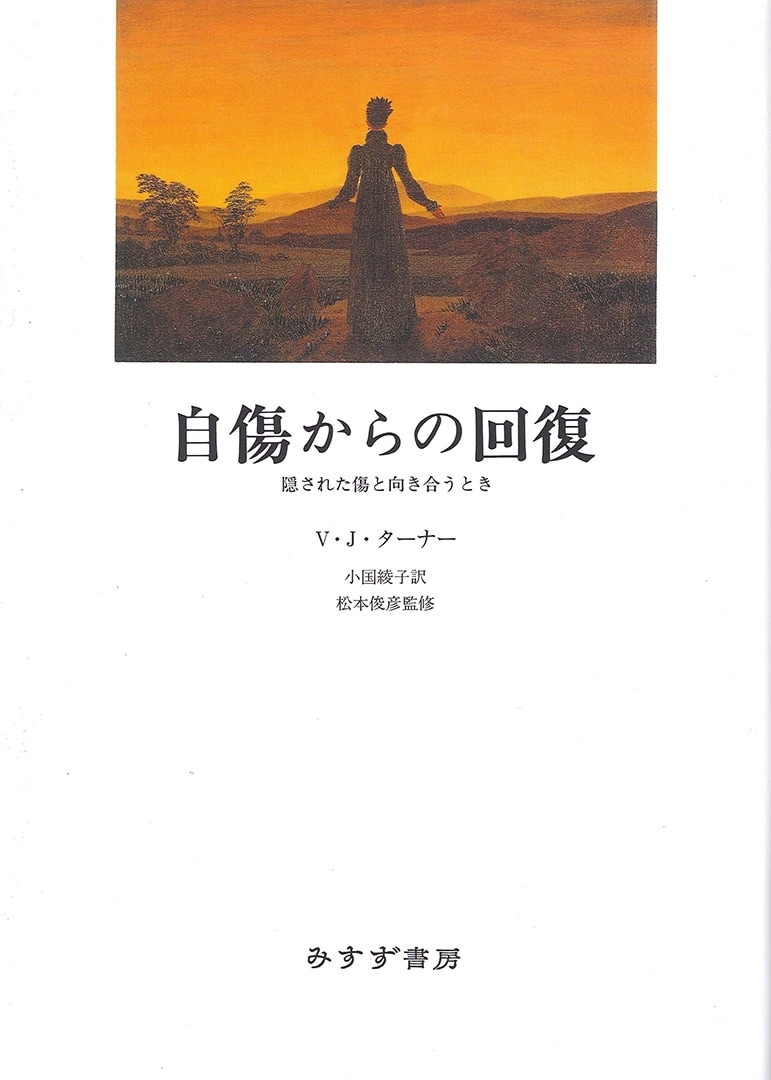真夏の昼下がり、私は木製の塀で仕切られた喫煙所にいた。その場所は、日比谷公園敷地内、桜田門側の端に設置されていて、周囲を樹木が覆っている。そのせいか私は、官公庁ビルが林立する無機質な風景のなかで、そこだけ緑溢れるオアシスのように感じてしまうのだ。
私は、塀の内側で紫煙をくゆらす面々を見わたした。大半が腕まくりしたワイシャツ姿の男性だ。おそらく午前中、ニコチン渇望に耐えながら執務をこなし、昼休憩でようやく身もだえする焦燥から解放された、霞が関の官僚たちなのだろう。
しかし、そのワイシャツの一群に混じって、周囲とはやや異質な二人――Tシャツ姿とポロシャツ姿の中年男――がそれぞれ離れて立っている。服装だけで判断すれば、一見、「公園散策を楽しむ休日のパパ」風だが、その佇まいは、早朝、パチンコ店に並んでいる人に相通じるものがある。二人とも周囲を見回してはしきりと時計を気にし、緊張が伝わってくる。
おそらく二人は、これから保護観察所に初出頭する人たち――つまりは刑務所出所まもない人たち――なのだろう。そのような人たちにとって、この喫煙所は実に使い勝手がよい。なにしろ、保護観察所が入っている法務省合同庁舎ビルは、横断歩道を挟んですぐ目の前だからだ。
もう10年近く昔の話になる。
その喫煙所で、私もまたあの二人に相通じる異質さを漂わせていたかもしれない。というのも、私もまた保護観察所に用事があったからだ。薬物再乱用防止プログラムの助言・指導という仕事である。そして、これから数時間続く長い禁断に備えるべく、喫煙所に立ち寄ったわけだ。
煙草をくゆらしながらスマートフォンでメールをチェックしていると、「至急」と銘打ったメールが届いているのに気がついた。職場からだ。慌ててメールを開くと、「××警察署の刑事から電話があり、担当患者のことで折り返し電話がほしいとのことです」と書いてある。
指に煙草を挟んだまま、すぐに電話を入れてみた。
「○○××という名前の患者はご存じですか?」
電話の向こうから、刑事は開口一番そう質問してきた。
何でもその日の早朝、ある男性が、突然、血相を変えて警察署に駆け込んできたというのだ。彼は、「追い込みをかけられている」「殺される」と意味不明なことを叫び散らして、自身を保護するよう切羽詰まった様子で懇願してきたらしい。そして、所持品のなかに当院の診察券と予約票があり、担当医として私の名前が書かれていたことから、今回の連絡となったようだ。
「ついては、その患者の診断名と治療内容を教えていただけませんか?」
それが刑事からの要請であった。
まちがいなく名前は私の担当患者と同一だった。30代後半という年齢も完全に一致している。
――もしかして自爆逮捕?
自爆逮捕とは、覚醒剤依存症患者に時折見られる現象だ。覚醒剤に誘発された妄想の影響で「命を狙われている」という恐怖に圧倒された者が、妄想上の「敵」からの保護を求めて自ら警察に飛び込み、結果的に逮捕されてしまう、という皮肉な事態を指している。
嫌な予感がした。
たとえ捜査上の要請といえども、軽々に「覚醒剤依存症」という診断名を伝えるわけにはいかない。もちろん、患者は執行猶予中の身柄だったから、警察が尿を調べるのは時間の問題だが、だからといって、わざわざ私からそのタイミングを早める情報を提供したくはない。
周囲の喫煙者たちを警戒しながら、私は声をひそめてこう答えた。
――申し訳ないですが、守秘義務を優先したいと思います。捜査関係情報照会を希望されるならば、必ず被疑者本人の署名・捺印のある同意書を添えたうえで、当院医事課を通して文書で申請してください。そうすれば、こちらも文書で回答しますので。
電話を切った後、私は信じられない気持ちで呆然としていた。
青天の霹靂だった。彼は、真摯に自身の薬物問題と向き合っていた。すでに通院開始から2年を経過していたが、最初の1年間は、週1回通院して依存症集団療法(通称「SMARPP」)に参加した。それ以外の日はダルクに通所してさまざまなプログラムに取り組み、夜は薬物依存症の自助グループNA(ナルコティクス・アノニマス)のミーティングに日参した。要するに、できるかぎりの努力をしていたのだ。もちろん、治療経過中、覚醒剤を再使用することはなかった。
もっとも、懸念がなかったわけではない。半年前に就労し、通院間隔は週1回から月1回へと延び、ダルク通所も困難となった。それでも当初、NAだけは欠かさなかったが、仕事に慣れて業務量が増えてくると、次第に退勤時刻が遅くなり、NAの参加もままならなくなったのだ。
保護観察所の一室には、小さなテーブルがついた折りたたみ椅子が数脚、円形に並べられていた。すでに若い女性の保護観察官が緊張した面持ちでその椅子の一つに座っていたので、私はその対面の席に腰かけることにした。
「プログラムの司会、今日が初めてなので、すごく緊張しています」
女性保護観察官は眉をハの字にして、少々大げさに半泣きの顔の物真似をして見せた。
――気楽にいきましょう。研修の際にもいいましたが、大事なことはワークブックの内容を理解させることではなく、このプログラムを「楽しい時間」にすることです。もしもグループの議論が変な方向へと脱線したら、私が適宜介入して軌道修正します。大丈夫、きっとうまくいきますよ。
私はそう声をかけた。
まもなく簡易薬物検査で「陰性」という結果を出し、「身の潔白」を証明することができた保護観察対象者が、一人、また一人と部屋に入ってきた。そのうちの二人の顔を見て、私は思わず頬が緩むのを禁じ得なかった。というのも、その二人は、日比谷公園の喫煙所で見かけたポロシャツ男とTシャツ男だったからだ。当の二人も、「おまえもそうだったの」と、声にこそ出さないものの、驚いたように顔を見合わせ、互いに会釈しあった。
その頃、保護観察所は、試行錯誤しながら集団再乱用防止プログラムを実施していた。これまでマンツーマンで対象者を監督・指導してきた保護観察官にとって、集団プログラムは大きな挑戦だった。というのも、かねてより法務省関係者のあいだでは、「悪風感染」という、医学部では決して教わることのない、謎の感染症を警戒する伝統があったからだ。この言葉は、刑務所や保護観察所で処遇されている者同士が親しくなることで、「悪のネットワーク」を拡大し、相互に犯罪性を助長することを意味する、一種の業界内方言だ。その観点からいえば、集団プログラムはまさに濃厚接触多発地帯といってよかった。
それにもかかわらず、プログラム監修者の私は、研修会のたびに「和気あいあいとした雰囲気が大事」「「クスリをやりたい、やめたくない」と安心していえる場に」と、悪風感染防止対策上好ましくない主張をしてきたのだ。したがって、もしも保護観察所がそのような実践を本気でやるならば、それはほとんど天変地異レベルの劇的なパラダイムシフトとなろう。
「それでは、プログラムをはじめましょう」
女性保護観察官は緊張した声でそう切り出した。しかし、全部で5名ほどいる保護観察対象の男性はみな一様に暗い表情で、なかにはあからさまにふてくされた態度の男もいる。
その重苦しさにめげることなく、彼女は続けた。
「今日はゲストをお招きしています。このプログラムの監修をした精神科の医師です」
私が椅子から立ち上がって自己紹介すると、参加者の一人が不意に声をあげた。
「俺、この先生のこと知ってます。刑務所のビデオで見ました」
呼応して、Tシャツ男もいった。
「やっぱ、そうなんだ。俺もなんか見覚えあると思ってました。ビデオ、面白い話だったんだけど、「依存症の人はミネラルウォーターのペットボトルを見ただけで、腸が踊ったり虫が湧いたりする」とか、まるで俺たちみたいな言葉を使ってましたよね? そのせいで、みんな「この医者、シャブ使ったことがあるんじゃないの」という噂で持ちきりでした」
ポロシャツ男が口を挟んだ。
「そうそう、ビデオ映像のなかですごく汗だくになって顔がテカってたし、めちゃくちゃ早口で、なんかシャブでバキバキになっている感じだった」
あの法務省の動画教材か……。すぐに思い当たって、私は慌てて弁明した。曰く、あの動画教材は、新設された官民協働刑務所で収録したのだが、まだその刑務所の工事が終わってなくて、真夏だったのにエアコンが使えなかったこと、伝えたいことがたくさんあるのに動画の尺がかぎられていて、早口を余儀なくされたこと……などなど。
どうやら私は刑務所界隈ではちょっとした有名人らしい。
「先生、さっき日比谷公園の喫煙所にいませんでしたか?」
ポロシャツ男がにやにやしながらいった。
――ええ、そうです。重度のニコチン依存症なんです。
私は頭を掻いてわざとらしく照れて見せた。
「依存症の依存症専門医なんですね」
誰かの一言で、参加者全員がどっと笑った。おかげで一気に場がなごみ、若い保護観察官も緊張がほどけたのか、表情が明るくなった。
その日、保護観察所で集団再乱用防止プログラムが始まってちょうど丸1年が経ったところだった。振り返ってみると、保護観察官たちの変化はまさに刮目に値するものだった。初めのうちこそ堅苦しく、教師然とした雰囲気が抜けきらなかったが、回を重ねるにつれて徐々に態度が軟化し、セッション中に参加者から笑いが起こる回数も増えた。なかには、参加者の失笑を怖れずに自身のだらしない飲酒癖まで開陳し、なんとかして参加者との垣根を壊そうとする保護観察官までいて、いささかやりすぎの感はあるにせよ、姿勢そのものは悪くなかった。
そうした変化には、今回のように私のような専門家にプログラムへの助言を求めるだけでなく、ダルクのスタッフをプログラムに招いたりしたことも少なからず影響したと思う。というのも、これまでクスリをやめられない人とばかり会ってきた保護観察官の多くにとって、ダルクのスタッフは初めて出会う「クスリをやめ続けている」生身の人間だったからだ。そして、そのような偉業を達成しているにもかかわらず、「仲間のおかげでなんとか断薬を続けられている」「今でも、「こんなときにクスリがあったらなぁ」と考える瞬間がある」と率直に語るのだった。その謙虚な姿が、保護観察官たちに「薬物依存症者=悪人」というステレオタイプを破棄させ、新たに「回復」の具体的なイメージと希望を植えつけたにちがいなかった。
保護観察所がプログラムに力を入れるようになった背景には、刑事政策上の転換――2016年6月の「刑の一部執行猶予制度」(以下、一部執行猶予)施行――があった。これは、施設内処遇を短縮し、その分、社会内処遇を長くする制度であり、主に薬物事犯者を念頭に置いている。
もう少し具体的に説明しよう。
覚醒剤取締法違反による初回逮捕は、通常、全部執行猶予判決となって、刑務所に収監されることはない。しかし、執行猶予期間中に再度覚醒剤で逮捕されてしまうと、今度は、二回の違反行為に対する懲役が課され、おおむね3年程度の服役を余儀なくされてしまう。
ところが、判決に際して一部執行猶予が適用されると、たとえば、通常刑期より1年短い、2年間の服役で出所できる代わりに、2年間の保護観察がつけられることとなる。その場合、出所後2年間は、定期的に保護観察所に出頭し、簡易薬物検査を受けるとともに、薬物再乱用防止プログラムへの参加が義務づけられるのだ。
私自身は、この制度に肯定的な立場をとっていた。少なくとも従前よりは「まし」と考えていた。というのも、一般に覚醒剤の再使用は刑務所出所直後や精神科病院退院直後に生じやすい。したがって、再犯防止という点で、物理的な隔離の効果にはおのずと限界があるからだ。
思えば、わが国の薬物問題に関する刑事政策は、迷走に次ぐ迷走だった。1951年の覚醒剤取締法制定以降、覚醒剤がらみの事件が巷で話題となるたびに、「量刑の加重」という厳罰化を加速させてきた。だが、そうした対策がもたらしたのは、刑務所の過剰収容と再犯者率の深刻な上昇だけだった。そもそも、覚醒剤取締法事犯者における再犯者率の高さ自体、刑事司法システムが再犯防止に奏功していないことの証拠といえた。
いや、単に効果がないだけではすまされないかもしれなかった。刑事司法システムこそが「マッチポンプ式」に事態を悪化させている張本人、という可能性さえあったのだ。事実、法務省のデータベースを用いた研究は、刑務所により長く、そしてより頻回に入るほど、覚醒剤取締法事犯者の再犯リスクが高くなる、という皮肉な現実を明らかにしている(1)。
しかし、一筋の希望もあった。その研究は、刑務所とは反対に、保護観察所がかかわる期間が長くなるほど再犯リスクが低減する可能性を示していたからだ。つまり、再犯防止という観点でいえば、薬物事犯者は施設内処遇よりも社会内処遇の方が効果的ということなのだ。実際、欧米諸国では、すでに1990年代より違法薬物の自己使用や少量所持は、施設内ではなく社会内で処遇するのが主流となっている。
一部執行猶予の導入は、遅ればせながらわが国が欧米の水準に追いつくチャンスだった。刑務所出所直後から保護観察所に定期的に出頭させ、簡易薬物検査を行うとともに、薬物再乱用防止プログラムを提供する。そうすれば、刑務所出所直後の再使用を抑止できるかもしれない。
問題は、保護観察期間にいかなるプログラムを提供するかだ。
そこで白羽の矢が立ったのが、私たちが開発した「SMARPP」――認知行動療法の手法を活用した依存症集団療法――だった(2)。もちろん、厳密にいえば、保護観察所ではSMARPPの実現は不可能だ。なにしろ、SMARPPの根幹は、失敗の正直な申告を歓迎、称賛する点にある。それを法務省関連機関で実現するのは、さすがに無理筋というものだろう。まあ、口でいうだけならまだしも許容される余地もあろうが、簡易薬物検査で「陽性」が出てしまえば、さすがに一発アウト、再び刑務所に舞い戻らなくてはならない。
そうしたことを承知しつつも、「いまは社会内処遇の実現に向けて少しでも前に進むことが重要」と考えた。だからこそ私は、法務省の要請に応えて、保護観察官にSMARPP実施のためのトレーニングを提供し、さらには、各地の保護観察所に赴いては、集団再乱用防止プログラムの実地指導に努めてきたのだった。
しかし、楽観的になるのはまだ早かった。一部執行猶予によって社会内処遇が強化されたからといって、それだけで覚醒剤依存症からの回復が実現するわけではない。というのも、刑務所出所直後に次いで再使用が多いのは、保護観察終了直後だからだ。
要するに、刑務所収監によって物理的に薬物を遠ざけても、あるいは、保護観察によって心理的なプレッシャーを加えても、その効果は一時的なのだ。依存症は、長期にわたるセルフケアを必要とする慢性疾患であり、その点で糖尿病などの生活習慣病と同じ性質を持っている。だからこそ、保護観察という社会内処遇終了後に、地域の支援資源につなげることが重要になってくる。
いかにしたら、この保護観察という法的強制力を持つ支援から、地域における任意の支援へのつなぎをシームレス化できるのか?
その実現には、保護観察終了間際に慌てて地域につなげたのでは遅い。保護観察期間中の断薬に成功した者ほど、「もう大丈夫」と安心しきって、依存症専門医療機関やダルクにつながる必要性を感じなくなるからだ。そうなると、地域の支援資源につながろうという意欲が最も高いのは、誰が何といおうと刑務所出所直後=保護観察開始時点だ。
そこで、2017年初頭より私たちの研究チームは、あるプロジェクトを立ち上げた。名づけて「Voice Bridges Project」(「声の架け橋」プロジェクト、通称「VBP」)という(3)。この試みは、コホート研究の体をとりながら、その研究のプラットフォームを活用し、保護観察から地域の支援資源へとつなぐシステムの構築を目指している。
具体的には、薬物関連犯罪による保護観察対象者に対し、保護観察開始からおよそ3年間、精神保健福祉センターから定期的に電話で接触するのだ。その際にコホート研究に必要な情報収集をするわけだが、ニーズがあれば情報提供や個別相談、あるいは、薬物依存症回復プログラムも提供できる。加えて、法務省との協議を通じ、たとえ対象者が薬物使用を告白しても、「あくまでも守秘義務を優先し、保護観察所には報告しない」とのコンセンサスも得られている。
このように、地域の側から積極的に保護観察対象者に接触することで、保護観察期間中にある程度「なじみの関係」になっておけば、保護観察終了後に地域の支援資源につながる薬物依存症者が増える、いや、仮にすぐにはつながらなくとも、薬物再使用時には、深刻な乱用に陥ったり、逮捕されたりする前に、地域の支援資源にアクセスする者が増えるはず――そう考えたのだ。
なお、精神保健福祉センターとは、都道府県・政令指定都市に少なくとも1箇所は設置されている、メンタルヘルスに特化した保健行政機関のことだ。そして、すでに国内69箇所のセンターの7割でSMARPPに準拠した薬物依存症回復プログラムが実施されていて、薬物依存症支援の実績は十分にある。しかも、医療機関ではなく、あくまでも住民に対する行政サービスなので、プログラム参加にお金がかからず、当然ながら保険証もいらない。これは、刑務所を出所してまもない人――その多くはお金も保険証も持っていない――にとってはありがたいことだ。
VBPの着想にあたっては、ある自殺に関する研究がヒントになっている(4)。以下のような研究だ。まず、自殺未遂によって救命救急センターに入院した患者を、退院時、ランダムに2つのグループに分ける。1つのグループは退院後いっさい連絡をとらず(通常はこうだ)、一方、もう1つのグループには、3、4カ月に1回の頻度で、健康を気遣う言葉と相談窓口情報からなる短い定型文の手紙を送ることとする。そして、両群における退院後の転帰を比較するというものだ。
興味深い結果だった。救命救急センター退院後1年以内の企図率、ならびに自殺既遂による死亡率を両群間で比較したところ、手紙を送られたグループの方が明らかに自殺再企図率と自殺死亡率が低かったのである。要するに、たとえ数カ月に1回の「おせっかいな手紙」であっても、何もしない場合よりははるかに救える命が多くなるのだ。
その研究結果を知って私はこう考えた――薬物依存症の地域支援においても、同様の「おせっかい」の仕組みを作りたい、そして、それによって地域に「多重構造のざる」を作りたい、と。
自身の臨床経験を振り返るたびに思い知らされることがある。それは、依存症の治療・回復支援とは、「ざるで水をすくう」がごとき仕事であるということだ。実際、私はこれまで数千人の薬物依存症患者と出会ってきたが、残念ながら、そのうち自分が回復に貢献できたと実感できる患者はごくわずかしかいない。
私にかぎった話ではないはずだ。他の依存症専門医やダルクのスタッフ、あるいは、刑務所や保護観察所でプログラムを実施する教育専門官や保護観察官――つまりは、治療や回復支援にかかわる誰もが、そのような感覚を抱いている。
なるほど、今日、SMARPPはすでに多くの専門病院で実施されており、ダルクに至っては国内で100近い施設が存在する。また、先述したように、今や精神保健福祉センターや保護観察所においても、SMARPPに準拠したプログラムが実施されているのだ。しかし、いずれもしょせんは「ざる」だ。誰がどう足掻いても、この仕事は「ざるで水をすくう」がごとき作業であるという現実は変わらない。
ならば、その「ざる」を何枚も緊密に重ね、「多重構造のざる」を作ったらどうか。そうすれば、ざるから漏れ出る水は少なくなり、ざるの目の上に残る水が多くなるのではないか――それが発想の原点だった。私は、保護観察から地域への架け橋として、「電話によるおせっかい」という新たな「ざる」――それも「ざる」同士の接着剤になるような「ざる」――を、国内中に拡充したいと考えたのだ。
本稿執筆時点でVBPは開始から早9年を経過している。2017年に、わずか4箇所の精神保健福祉センターで立ち上げたこのプロジェクトも、現在、33箇所の精神保健福祉センター(全精神保健福祉センターの半数弱)で実施されるところまで広がった。現時点までで、追跡対象者の断薬継続率は1年経過時点で約91%、2年経過時点で約88%、3年経過時点で約83%と、予想を超える好成績を叩き出している(5)。
だが、「多重構造のざる」にも限界はある。どれだけ保護観察所でプログラムを提供しても、あるいは、日本中に「おせっかいな電話」が充溢し、多くの人が地域の支援資源につながっても、刑事司法制度を起点とする以上、どうにも消せない烙印が残る。
そう、犯罪歴だ。その烙印には、人の運命を狂わせるのに十分すぎるほどの破壊力がある。
逮捕や服役は、家族や友人、知人とのつながりをしばしば深刻に切断する。親からの勘当や配偶者との離婚は言うに及ばず、かつての職場の同僚、あるいは、薬物とは縁のない友人や恋人とのつながりの喪失、電話の着信拒否やSNSのブロックといった暴力的な拒絶……。結果的に、彼らの声に耳を傾け、受け容れてくれる存在は、現在もまだ薬物を使っている人間か、さもなければ薬物の密売人しかいなくなるわけだ。
仕事を探すのも容易ではない。服役中の空白期間を履歴書でどう説明するのかが問題となる。もちろん、刑務所出所者を積極的に受け容れる協力雇用主と呼ばれる企業経営者はいるし、協力雇用主からの求人広告を集めた雑誌も存在する。しかし、その雑誌に掲載される求人広告のなかには、「ただし、覚醒剤取締法事犯者を除く」と追記しているものも少なくないのだ。
奇妙な話ではないか。殺人や傷害、強盗、放火よりも、「被害者なき犯罪」である薬物犯罪の方が忌避される現状というのは、どうにも解せないところがある。あくまでも推測だが、薬物乱用防止啓発の影響もあるのだろう。そのような啓発教育においては、覚醒剤使用者はあたかもゾンビやモンスターのように恐ろしく描かれるのがつねであり、それゆえ、凶悪なイメージが社会に深く浸透してしまっている気がしてならない。
それでも、犯罪歴だけならばまだしも工夫のしようがある。なぜなら、本人さえ黙っていれば誰にも知られることはないからだ。ところが、実名報道となるとそうはいかない。
冒頭に紹介した自爆逮捕男性こそが、その実名報道の被害者だった。彼は、有名大学を卒業後、大手銀行に勤務してきたエリート銀行員だった。この「エリート銀行員と覚醒剤」という組み合わせは、取締側からすれば「薬物汚染拡大の深刻さ」をアピールし、予算獲得や人員増強にあたっての武器になっただろう。メディアにとっても、「エリート転落の物語」として人々に「シャーデンフロイデ」的な喜びを与える話題として、視聴率や雑誌発行部数を稼ぐ格好のネタとなったはずだ。だからこそ、警察は実名を発表するし、メディアも警察発表にそのまま追随するわけだが、彼の場合、顔写真まで公表されてしまった。そのせいで、彼の顔と名前は半永久的にインターネット空間を浮遊し、衆目に曝され続けることとなったのだ。
診察室で彼から実名報道の影響を知らされるたびに、私は、社会的制裁という、刑法の定めによらない集団リンチの恐ろしさに言葉を失うばかりだった。
とにかく仕事が見つからなかった。通院治療開始から1年を経過した頃より、彼は社会復帰を考えて求職活動をはじめ、その応募回数は気が遠くなるほどであったが、すべて空振りに終わった。毎回、書類審査はパスするのだが、そこから先に進めない。運よく内定が出たにもかかわらず、数日後には取り消される、という悲劇にも遭遇した。おそらく立派すぎる経歴のせいで、かえって採用する側の疑心暗鬼が刺激され、インターネットで名前を検索されてしまったのだろう。
彼は頭を抱えた。かつて新卒当時、彼は有名企業から引く手あまたの存在であり、そうした企業からの内定を蹴って、大手銀行を選択したのだった。それなのに、この変わりようはどうだ。
しかたなくハローワークを訪れ、犯罪歴のある人を対象とした窓口でも相談してみた。しかしそこで紹介される仕事といえば、土木・建築業などの肉体労働ばかりだった。自分がこれまで積み上げてきたスキルが一切役立たない領域、それどころか、もっとも苦手で、もっとも経験の乏しい領域でしか社会と接点が持てないのか――そのことに彼は深く落胆した。
彼には犯罪歴の他にも秘密があった。男性同性愛者にして、HIV感染症罹患者だったのだ。要するに彼は、性的マイノリティにしてHIV感染症罹患者、さらに違法薬物使用者と三拍子揃った、二重三重の意味で孤立しやすい状況に置かれていたことになる。
2000年代後半以降、わが国のゲイ・コミュニティでは、覚醒剤がセックスドラッグとして広まり、彼もまたそのコミュニティのなかで覚醒剤を用いたセックスを体験したのだった。
誤解しないでほしいのだが、私はここで性的マイノリティ=違法薬物使用者と断じているのではない。違法薬物の経験率が高いのは何も性的マイノリティにかぎった話ではなく、人種的・民族的なマイノリティにおいても同様の傾向が見られる。つまり、マジョリティ文化から差別され、迫害され、あるいは偏見や好奇の目に曝される社会的状況こそが、マイノリティとされる人たちに規範に対する忠誠心を損なわせ、違法薬物へのアクセスを高める最大の要因と考えるべきなのだ。
彼が通院を開始してまだ日が浅い頃、私は診察室で彼に質問したことがある。
――なぜゲイのコミュニティでは、セックスと覚醒剤が密接に結びついているのだろうか?
「私の場合は、という限定的な言い方になりますけど……」
そう前置きをしてから彼はいった。
「クスリを使うのは……狂いたいからです。いや、「狂う」っていうのは正しくないかな。何というか……そう、行為に集中するためです。クスリがないと行為に集中できないんです」
――集中?
「ここ数年、実家に帰省するたびに母親がくりかえす言葉、つまり、「早く孫の顔が見たい」という言葉、そういうときの老いた母親の淋しそうな顔が、いつも脳裏から離れませんでした」
父親が早逝したために、彼は母親に女手一つで育てられたのだった。母親の期待に応えて彼は勉強に没頭し、有名大学を経て大手銀行に就職と、絵に描いたようなエリート街道を邁進してきた。そうした努力もすべて母親の思いを忖度すればこそであったのだ。
「そのせいで、意中の人とのセックスのときにも、「早く孫の顔が見たい」という言葉が脳裏を駆け巡って集中できないんです。クスリはそういうぐるぐるする考えを消し、脇目も振らず目の前のことに没頭させてくれるんです」
雷に打たれた気分だった。マイノリティ集団における薬物問題の解決に必要なのは、薬物再乱用防止プログラムではないのだ。おそらく変わるべきなのは、問題を抱える個人ではなく、その問題と無縁な人々、つまり社会の側なのだろう。
ただ、使用する理由が何であれ、覚醒剤は人を無防備にし、危険なセックスを避ける力を弱めてしまう。彼もそうだった。平日における勤勉と抑圧の反動のように、週末のたびにハッテン場でセックスの相手を渉猟するうちに、いつしかHIVに感染していた。
もちろん、医学のめざましい進歩により、今日、HIV感染症の治療成績は劇的に改善し、死なない病気となった。早期に治療を行えば、その平均余命はもはや非感染者と変わらないほどだ。
しかし、だからといって、感染の事実を誰に対してもオープンにできるわけではない。ただでさえ、性的指向を親に告白できていないのに、今度はHIV感染症という新たな秘密が加わったことになる。そのことが彼の罪悪感を増強し、彼をますます覚醒剤セックスへと没入させていった。
ある日、とうとう彼は逮捕されてしまった。そして、執行猶予判決を言い渡された翌日、彼は初めて私の外来を訪れたのだった。
なお、VBP追跡データの解析では、薬物再使用のハイリスクグループには「男性」「未婚」「身体障害者手帳所有」という三つの特徴があることが同定されている(6)。これらの特徴を満たす覚醒剤使用者とは、いうまでもなくHIV感染症を抱える男性同性愛者となろう。
つまり、彼にそのままあてはまる特徴なのだ。
時間経過に伴い、彼が抱える秘密はさらに増えた。
なかなか仕事が決まらないことに痺れを切らした彼は、とうとう犯罪歴ばかりか、立派な学歴と職歴をあえて低く偽り、さらには名前まで偽って求人に応募したのだ。一時的には悪くないアイデアだった。現に、彼はすぐにとある零細企業の事務職に採用されたわけだから。しかし長期的に見てみると、秘密と孤独を増す事態をみずから招いた感は否めない。
彼は優秀な新入社員としてすぐに頭角を現した。円満な性格と紳士的なふるまいから同僚にも好かれ、退勤時にはたびたび飲みに誘われた。また、魅力的な外見の持ち主であった彼に関心を抱く若い女性社員もいて、あれこれと世話を焼いては、彼のプライベートを知りたがった。
しかし、彼はいかなる誘いもすべて断り、誰とも親しくならないよう慎重にふるまった。それだけではない。心というものに何重もの鎧を被せて本音を隠し、私生活に煙幕を張った。
「秘密が多くなればなるほど、孤独はますます深くなりますね」
あるとき彼は、診察室でそうつぶやいて、寂しそうに笑った。
――どこでもいい、何一つ嘘をつかず、正直に秘密を話せる場所があるとよいけど?
そう私は懸念を示した。
「この診察室がまさにそういう場所です」
――でも、前は毎週だったけど、仕事を始めてからは月1回だよね。頻度が少なくないかな? 最近、NAには参加してるの?
彼は押し黙った。連日の残業に追われて、NAどころではなかったようだった。
診察室で彼と最後に会ったのは、確か警察から連絡があった日の1カ月前のことだ。彼が自身のSNS投稿が炎上した話を、憤懣やるかたないといった調子で語っていたのを覚えている。
当時、「某大学運動部の学生が大麻所持で逮捕」という事件がメディアを賑わせていた。その際、容疑の段階であるにもかかわらず、当該大学生の実名はもとより、顔写真まで報じられたのだ。その事実を知った彼は、同じ実名報道の被害者として憤然とした。実名を発表した警察にも、そして、唯々諾々とそれに追従するメディアにも怒りを抑えきれなかった。それで、矢も楯もたまらず、SNS上で自分の思いを匿名投稿したのだ。
「納得ができない。かつて若い警察官が大麻で逮捕されるという事件があったが、その際、警察は、「将来ある若者」という理由から実名公表を控えたのだった。当時、そうした警察の対応を非難するメディアはなかった。ならば大学生の事件はどうか? 「将来ある若者」という点ではこの大学生もまったく同じはずだ」
すると、投稿にはおびただしい数の誹謗中傷コメントがついて、炎上状態を呈した。曰く、「これ書いてる奴、絶対にヤク中本人 氏ね」「ヤク中がヤク中を庇う 笑」「法を犯した奴は全員実名と顔を曝すべきだ」……云々。
これが社会の多数派を占める見解なのか? 予期せぬ展開に、彼はいきなり冷水をぶっかけられた気分になり、そして、目の前が暗くなった。
翌日出社してみると、同僚たちが急にそっけなくなったように感じられたという。最初、気のせいかと思い直したが、いつもは親切な女性社員にまで冷淡な態度をとられたことで、理性のたがが外れた。彼の不安は波紋を描いて同心円状に広がり、炎上中のSNS投稿の主が自分であることが社内に知れわたっているのではないか、いや、それだけではなく、自分の偽名もとっくに露見しているにちがいない……と不安が一挙に膨張し、彼を圧倒した。
診察室で一連の顛末を語る彼は、すっかり憔悴し、疲弊しきっていた。
「いまの会社、もうやめなきゃいけないかも……です」
彼はうつむいて身を震わせた。
「頑張ってクスリをやめ続けたって、何の意味もないですね……」
その後、彼がどういう経緯で覚醒剤を再使用し、そして自爆逮捕に至ったのかはわからない。
しかし、一つはっきりいえるのは、薬物で人がおかしくなるのは単にその薬理作用だけのせいではない、ということだ。むしろ薬理作用以上に重要なのは、その人が置かれた状況――つまり、セット(思考、気分、期待など、薬物使用時におけるその人の精神状態)とセッティング(薬物使用時にその人が置かれた環境や社会的状況)――なのだ。事実、覚醒剤取締法制定以降、覚醒剤誘発精神障害の病像が単なる「躁状態」から、「被害妄想」「追跡妄想」へと変化したとの報告があり、その背景要因として、違法化による使用者自身の罪悪感が精神症状を修飾した可能性が指摘されている(7)。
おそらく彼は、猜疑心と不安が渦巻く精神状態のなかで、それこそ自暴自棄になって覚醒剤を使ったにちがいない。だが、摂取した瞬間に強い後悔と罪悪感に襲われたはずだ。なにしろ、やっと築いた2年近いクリーンタイムを一瞬にしてふいにしたわけだから。
おまけに、長期の断薬によって彼の中枢神経系は耐性や馴化がリセットされ、皮肉にも覚醒剤に対する敏感さを取り戻していたにちがいない。久しぶりの覚醒剤は鋭く脳を揺さぶり、大量のドーパミンを噴出させたことだろう。そして、彼はたちまち被害妄想の渦に巻き込まれ、恐怖に圧倒されて、警察に助けを求める事態に追い詰められたのではないか……。
その日、保護観察所のプログラムは、明るい雰囲気のまま無事終了した。女性保護観察官は心底安堵した様子だった。
しかし、いくら変わったとはいえ、しょせんは保護観察所だ。たとえプログラムの場は和気あいあいでも、プログラムの外で参加者同士が交流して「悪風感染」が生じないように、あいかわらず周到な対策を講じていたのだった。つまり、プログラム終了後、いっせいに対象者を帰宅させるのではなく、担当保護観察官が対象者の順次個人面談をしてわざとらしく時間を稼ぎ、一人ひとり時間差をつけて退庁させる、という涙ぐましい努力をしていたのだ。
もちろん、そんな子ども騙しが通用するほど、保護観察対象者はぬるい人たちではない。
保護観察官たちとの反省会を終えると、私は保護観察所を出た。そしてそのまま横断歩道を渡り、日比谷公園の喫煙所へと急いだ。地下鉄に乗る前に一服したかったのだ。
すると、すでにそこにはTシャツ男とポロシャツ男がいた。時間差で退庁させたところで、喫煙者が向かう先など最初から決まっている。
私が入ってきたのに気づくと、二人は「お疲れ様です。先ほどはありがとうございました」と声を揃えて挨拶してくれた。私もそれに応えた。
――あなた方こそお疲れさまでした。もしかしてお二人でプログラムの反省会ですか?
すると、ポロシャツ男がいった。
「まさか。でも、プログラム、予想していたよりも楽しかったです。先生の病院でもこんな感じのプログラムをやってるんですか?」
――ええ。ただ、病院の場合だと、もっとゆるくて気楽な雰囲気ですよ。
「病院だったら、クスリを使っちゃっても警察に通報されたりしないんですよね?」
――もちろんです。うちの病院で依存症患者さんに伝えているメッセージが3つあります。第一に死なないこと、第二に逮捕されないこと。そして最後に、どんなに失敗をくりかえしても治療を諦めないことです。
「いいメッセージっすね。なあ? そう思うだろう?」
うなずきながら聞いていたTシャツ男がポロシャツ男に同意を求めると、ポロシャツ男はいった。
「もう刑務所は懲り懲りだから、もしも俺らがまたクスリに手を出しちゃったときには、すぐに先生のいる病院に行きますよ……次こそは逮捕される前に」
――そう、自爆逮捕される前に……。
私は、思わず口をついて出かかった自分の言葉に驚いて、慌てて言葉を飲んだ。代わりに、深く吸い込んだ煙草の煙をことさらにゆっくりと吐き出しながら、空を見上げた。不意に脳裏にある言葉が横切る――曰く、人はなぜ秘密を抱え、そして孤独になるのか。
陽が傾きはじめていた。西の空は喀血のような色を帯び、その色は、宙に不思議な図形を描いている紫煙をも染めた。そのさまは、静脈を探り当てた針を介して注射器内へと逆流してくる、あの赤黒い血液のように見えた。
参考文献
- Hazama, K. & Katsuta, S. Factors Associated with Drug-Related Recidivism Among Paroled Amphetamine-Type Stimulant Users in Japan. Asian Journal of Criminology, 15(5): 1-14, 2020.
- 松本俊彦、今村扶美、近藤あゆみ監修『SMARPP-24 物質使用障害治療プログラム 改訂版』金剛出版、2022年。
- 熊倉陽介、高野歩、松本俊彦「Voice Bridges Project――薬物依存症地域支援のための「おせっかい」な電話による「声」の架け橋プロジェクト」精神科治療学、32: 1445-1451、2017年。
- Motto, J.A. & Bostrom, A.G. A randomized controlled trial of postcrisis suicide prevention. Psychiatric Services, 52: 828-833, 2001.
- 松本俊彦、宇佐美貴士、熊倉陽介ほか「保護観察の対象となった薬物依存症者のコホート調査システムの開発とその転帰に関する研究」『令和4年度厚生労働省依存症調査研究事業 保護観察の対象となった薬物依存症者のコホート調査システムの開発とその転帰に関する研究(研究責任者 松本俊彦)研究報告書』、1-47頁、2025年。
- 同上。
- 坂口正道、中谷陽二、藤森英之ほか「覚醒剤精神病における妄想主題について」精神医学、31: 1021-1029、1989年。
編集部注:本連載では、登場人物の匿名性を保つため、プロフィールの細部に変更を加えています。