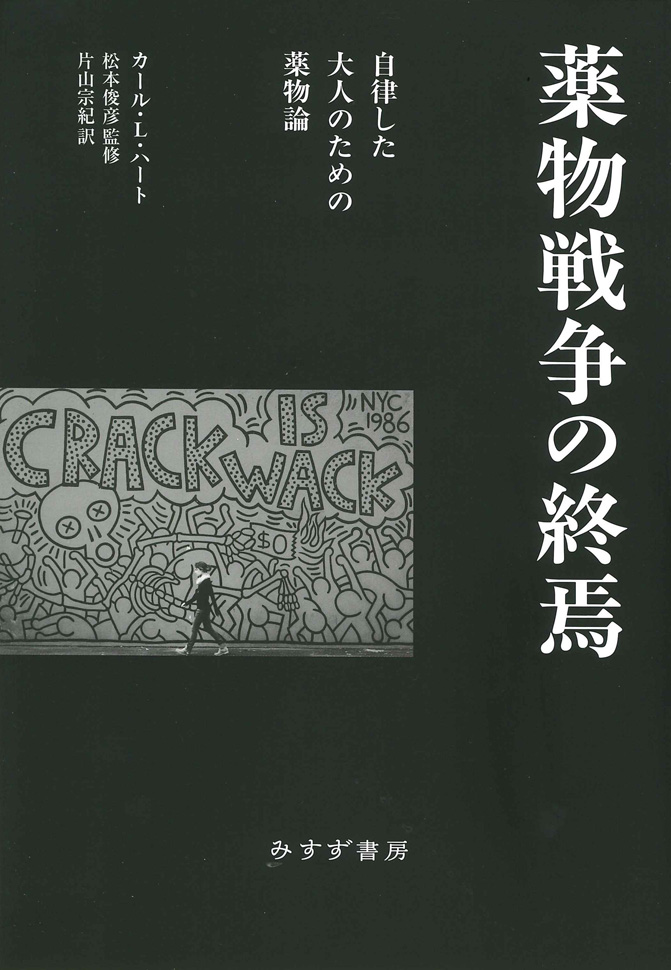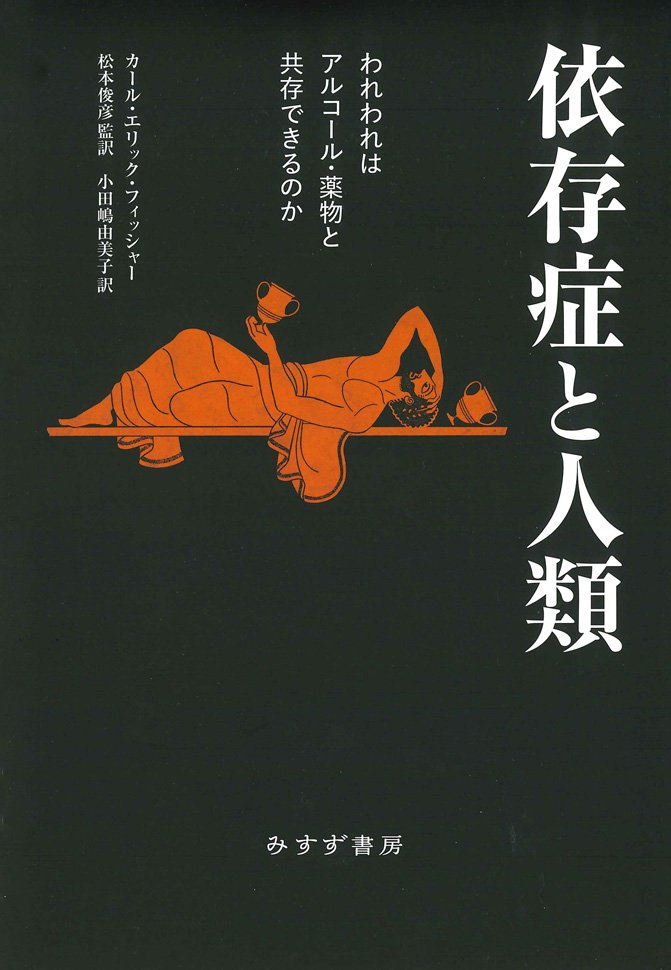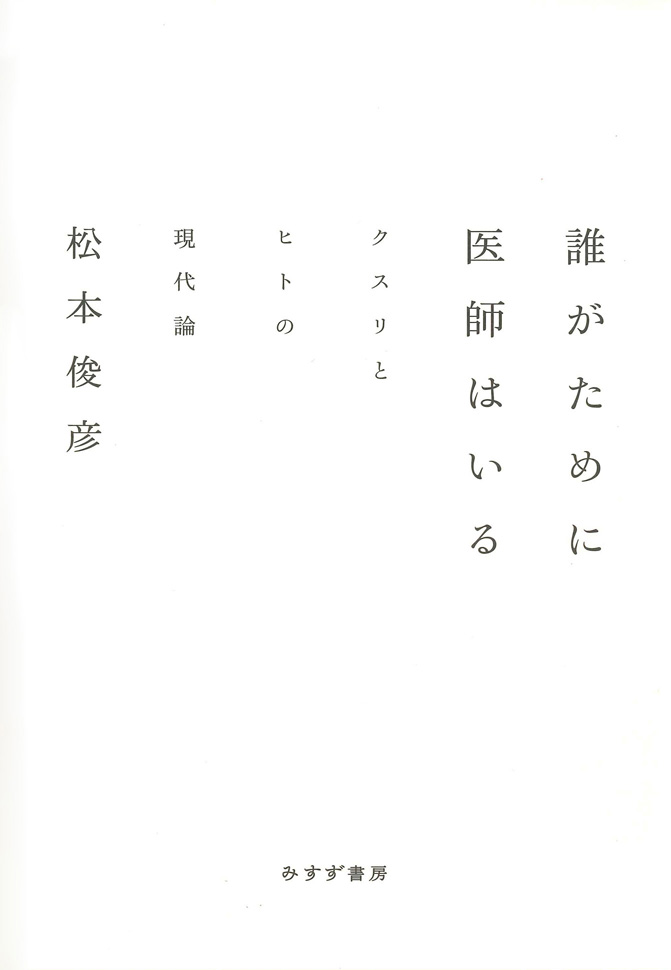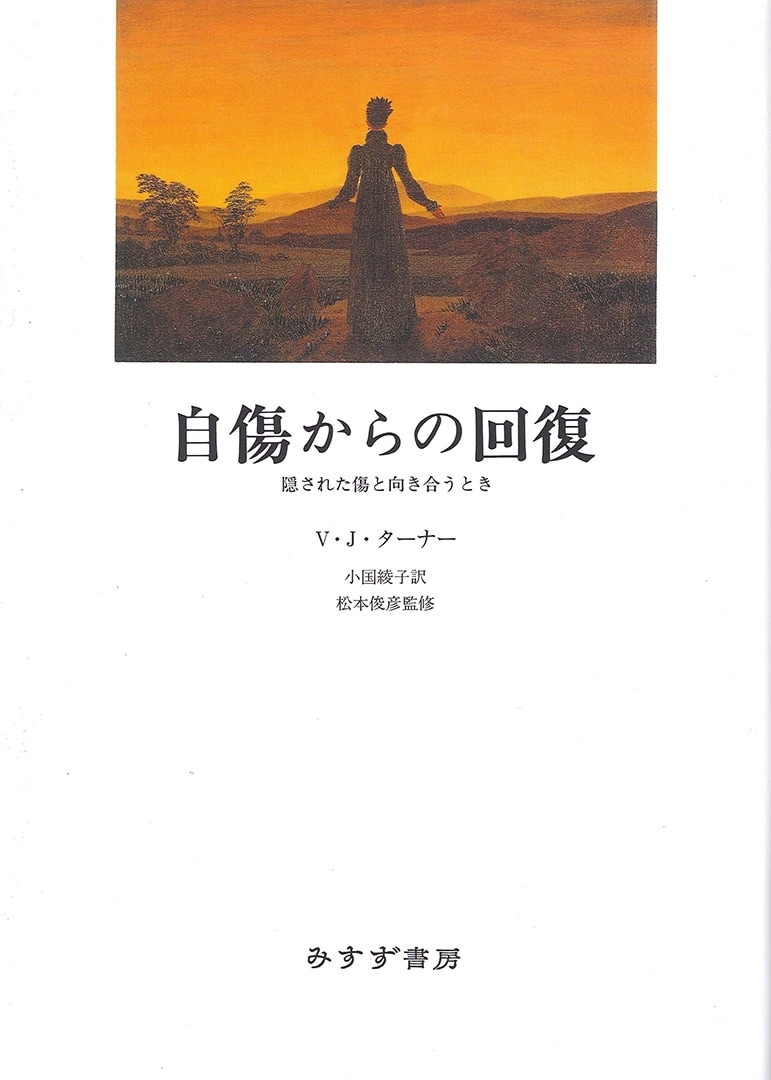「大変な時期はありましたけど、子育てって過ぎてしまうとなんだかあっという間ですね」
その女性患者はしみじみと語った。
年齢は40代後半、タートルネックのニットにジーンズというシンプルな身なりをしていて、現在の自分に満足している人特有の落ち着いた雰囲気がある。
彼女は、3カ月に1回ほどの頻度で通院している。何かを相談するというよりも近況報告をしにきている感じだ。現在は、近所の書店でパートタイム就労をしながら、会社員の夫、二人の子どもと郊外で暮らしている。かつて子育てに苦慮した時期もあったが、それもいまは遠い過去、第一子の長男はすでに大学を卒業して社会人1年目、そして第二子の長女も今年大学に入学し、いまや子どもたちは少しずつ彼女の手を離れつつある。
「実は報告がありまして」
彼女はそういうと、トートバッグのなかから名刺大のカードを取り出して私に見せた。大学の学生証だ。子育てが一段落し、自分の時間ができたので、通信制大学に入学したのだという。
とてもいいですね、ぜひ思い切り勉強してください、と私はいった。
確かにそうだ。10代から20代前半にかけての彼女には、勉強などする余裕はなかった。その時期、彼女は疾風怒濤の渦中にあり、ようやく精神的に落ち着いた20代後半以降は、子育てに忙殺される毎日を送ってきた。
彼女との治療関係はすでに30年近くに及んでいる。長い治療経過中にはさまざまな事件や紆余曲折があったが、第一子がもう社会人と聞くと何とも感慨深い。
彼女の診断名は解離性同一性障害(dissociative identity disorder; DID)――俗にいう多重人格――だ。正確にいうと、現在はすでにその診断基準を満たさなくなっているが、極期の病状はまさにそう診断せざるを得ない状態だった。
実は、精神科医のあいだでDIDの評判は必ずしもよいものではない。いや、悪いといってよいだろう。同業者の集まる症例検討会でうっかりその診断名を口にしようものなら、瞬時にして一同は鼻白み、その場に気まずい空気が流れてしまう。表情から察するに、「おまえも「あっち側」――おそらくはオカルト系といった意味合い――か!?」と失望している同業者も、おそらくいる。
しかし、DIDなる病態は確かに実在し、時折、私たち精神科医の前に現れるのだ。
初めて彼女を診察したのは、私がまだ横浜の大学病院で精神科修行中の頃だ。当時、彼女は高校1年生であり、両親ともに大酒家で酒乱という逆境的環境で生育し、3年前に両親は離婚して、彼女は母親に引き取られた。
受診した理由を尋ねると、彼女は、
「担任の先生に腕のリストカットの傷痕を発見されてしまったから……」
と答えた。
表情が乏しく、感情の起伏を感じさせない平板な声の持ち主だった。リストカットする理由について、「強い感情が爆発しそうで、ヤバい、抑えなきゃと思って」と答えた。皮膚を切るなんて痛くないのかと質問すると、「最初は全然感じないです。でも、何度か切っていると、少しずつ痛みみたいなものを感じるようになって、はっと我に返る感じです」と答えた。
彼女はこうもいった。
「すべてがガラス越しの風景みたいにちょっと遠退いて見えますし、まわりの人の声が遠く聞こえるというか、耳栓した状態で聞いてるみたいな感じです」
「最近記憶力が悪くなった気がします。忘れっぽくなったというより、過去の出来事がバラバラで、時間の前後関係がわからないんです。たとえると……そうですね、年代順に整理してアルバムに貼ってある写真を全部剥ぎ取って、バラバラにテーブルの上に放り出したみたいな……」
言語的な表現力が高いぶん、かえって彼女の苦痛が非常に抽象的なものと感じられてしまって、いまひとつピンと来ない。想像するに、どうやら彼女と現実とのあいだに薄い皮膜が生じていて、すべてのダイレクトな知覚から疎外されている、ということだろうか? 加えて、瞬間ごとの記憶が分断、あるいは断片化されて、連続して流れる時間の感覚というものが失われているようだ。
彼女が語っている内的体験は、ドイツの精神病理学者ヴォルフガング・ブランケンブルクが、著書『自明性の喪失』で提示した、寡症状性統合失調症の症例アンネ・ラウにそっくりの離人症だと感じた(1)。それから、彼女が自覚する記憶と時間感覚の変調は、わが国の精神病理学者木村敏が統合失調症患者に特徴的な時間感覚として指摘した、「アンテ・フェストゥム(祝祭前の緊迫した時間感覚)」とも酷似していた(2)。
こんなことも語っていた。
「部屋で机に向かっていると、自分の背後に誰かがいて、じっと自分を見ている感じがします」
これは実体的意識性と呼ばれる症候であり、当時、注察妄想(誰かに見られている、監視されている)の萌芽的な症状として、初期統合失調症の一症候と見なされていた。
私は彼女のことをレジュメにまとめて、大学精神科医局の症例検討会で発表し、上級医に意見を求めた。案の定、諸先輩たちの意見は、「統合失調症の前駆状態」で一致した。
私が精神科医になった1990年代前半、精神科臨床における中心的疾患は統合失調症であった。そして精神科医の力量は、一見ささいな精神的変調のなかに統合失調症の萌芽的兆候を見いだし、早期に診断する能力をもって評価される風潮があった。だから、表出されている症状が不安や抑うつ気分、強迫観念といった非精神病性のものであったとしても、精神科医たちは、統合失調症が潜伏しているのではないかと、文字通り「鵜の目鷹の目」で観察したのだった。
事実、すでに触れたブランケンブルクや木村敏をはじめとする、20世紀後半の精神病理学者の多くが、幻聴や妄想といった精神病症状が顕現するはるか手前で見られる、微細な兆候を捉えることに血道を上げていた。そしてその成果として、「単純型」「偽神経症性」「寡症状性」「初期」といった修飾語を前につけた、あまたの統合失調症の臨床亜型が提唱されてきたのだ。
もちろん、そうした姿勢が完全なまちがいとは思わないが、「がんの早期診断」とはわけがちがう。無節操にやりすぎれば「統合失調症の前駆状態」の乱発を引き起こす。実際、私が駆け出しの頃、大学病院の精神科入院患者の多くが、顕在発症以前の「潜在的統合失調症」と見なされていた。しかし、そのような早期診断にはその成否を評価する手立てがなかった。というのも治療経過中、統合失調症が顕在発症しなかった場合、それが治療の成功を意味するのか、それとも、そもそもの最初から誤診であったのかは、誰にも証明できないからだ。
生意気にも私は、「幻聴も妄想もないのに、一体、何を根拠に先生は統合失調症と診断したのか?」と先輩たちによく食い下がったものだ。すると、先輩たちはこう答えた。「統合失調症の本質は、幻聴や妄想といった陽性症状ではない。むしろ陰性症状――それも滅裂や解体ではなく、もっと基底的で純粋な欠陥なんだよ」
私はその答えに納得できず、たいてい、次の質問を重ねたものだった。「それでは、その基底的で純粋な欠陥って、具体的には何なんですか?」。すると、先輩たちは、「言葉で表現するのは難しいな。まあ、君も経験を積めばわかるよ」と私の肩を叩いてその場を立ち去るのが常だった。
私にはそうした早期診断の意義がわからなかった。というのも、統合失調症と診断したところで治療上の打開策は何一つ得られなかったからだ。事実、私は彼女に抗精神病薬を投与したが、リストカットは少しも収まらなかったばかりか、過剰な鎮静効果によって呂律が回らなくなり、患者の話し言葉が聞き取りづらくなっただけだった。
くだんの女子高生患者には、診断とは別に気になる点があった。それは性的虐待に関する嫌疑だ。診察の際、彼女はこんな話をした――小学校高学年以降、実父は泥酔すると決まって彼女のベッドに入り込んできて、酔って熱くなった実父の足が自分の足に触れて気持ち悪くて怖かった、と。他にも早口で何か話したが、うまく聞き取れなかった。
え? いまいったこと、もう一度話してもらえないかな? そう私は聞き返したが、彼女は、「いえ、いいです、いいです、どうでもいいことなんで」とはぐらかし、うやむやにした。そして次回以降の診察では、彼女の雰囲気から例の一件をほじくり返すことを制する気配――私の勘違いかもしれないが――が感じられて、再度の質問を躊躇してしまった。
結局、私にはそれが性的虐待なのかどうかを確かめる術はなく、さらにいえば、両親の離婚がそうした出来事に関係しているのか否かもわからなかった。診察に母親が同行していれば母親に確認するという手もあっただろうが、初回診察のときに同行して以来、母親はまったく来院しなくなっていた。
症例検討会ではこの情報も提示してみた。先輩たちからは、「米国ならいざ知らず、日本では養育者による性的虐待はめったにない」「米国ではそうした患者の訴えを真に受けた精神科医が、「患者の偽記憶を強化した」として裁判で敗訴している」「現実の出来事ではなく、患者のファンタジーだろう」といった意見が出て、この問題を深掘りしないよう私はたしなめられた。
諸先輩からの助言に従って、それ以降、私は、診察場面で例の疑惑を取り上げなくなった。それがよかったのか悪かったのかはわからない。リストカットは一時期ほど頻繁ではなくなっていたものの、依然として続いていた。私は少しも効かない抗精神病薬を漫然と処方していたが、まもなく彼女がそれをほとんど服用していないことに気づき、処方をやめた。次第に彼女は受診をキャンセルすることが多くなり、治療を開始して数カ月を経過した頃、通院は途絶えてしまった。
精神科医をはじめて3年が経過した頃には、私は早くも精神医学に倦みはじめていた。しかしちょうどそんなとき、新たな精神医学上のムーブメントの噂が耳に入り、少しだけ心がざわついた。
そのムーブメントの情報を教えてくれたのは、同じ大学精神科医局の少しだけ先輩の精神科医だった。初期研修医の時代から、彼とは一緒に勉強会を開いたり、その後に飲みにいって真面目な議論をしたりと、いわば盟友関係にあった。もともと近畿地方出身の彼は、阪神淡路大震災が発生すると、矢も盾もたまらず、発災直後より神戸大学精神科――当時、全国から有志の精神科医が附属病院の精神科病棟に集まっていた――に駆けつけ、しばらく同地に滞在して震災支援ボランティアに従事したのだ。そして一仕事終えて横浜に戻ってきたとき、彼は以前とは別人になっていた。彼は、三つの耳新しい言葉を九官鳥のようにくりかえし連呼する人間に変貌していたのだ。その三つの言葉とは、「トラウマ」と「解離」、それから「安克昌」だった。
私はその事実にちょっとした衝撃を受けたのを覚えている。というのも、彼はもとより熱狂的な中井久夫信者であったのに、中井久夫率いる神戸大学から戻るや否や、その彼の口から熱を帯びて語られる名前がなぜか別の人物の名前だったからだ。
いま神戸で起こっている新しいムーブメントについて、彼は医局の仲間に熱っぽく語ってまわり、さまざまなイベントを企画し、実行した。神戸大学精神科発の解離性障害メーリングリストが紹介され、話題の治療法、EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing: 眼球運動による脱感作と再処理法。心的外傷後ストレス障害に対する効果が確立されている治療法)のワークショップ横浜開催にも尽力していた。
さらには、米国の多重人格障害治療専門医ラルフ・ブリュースター・アリソン――『「私」が、私でない人たち――〈多重人格〉専門医の診察室から』の著者のひとり――が招聘され、講演会が開催された(3)。その講演会でアリソンは、帯同してきたDID患者の人格を交代させ、そして元の主人格に戻す、という作業を披露したのだった。そのマジックショーめいた、いささかいかがわしいパフォーマンスを、私はいまでも鮮明に記憶している。
実は、当初、私はこのトラウマ・解離ブームには冷ややかな態度をとっていた。当時の私は、「トラウマ」という言葉に対して、嫌悪感とはいわないまでも、少なくとも警戒心を抱いていた。その頃すでにアディクション臨床に従事していた私は、再飲酒や薬物再使用のたびに「トラウマが……」と弁明する依存症患者に辟易としていた。当時の私には、そうした弁明が「アルコールや薬物をやめる気のない患者お決まりのセリフ」としか思えなかったのだ。
それでいながら、無視することもできなかった。理由は安克昌だった。一連のトラウマ・解離ブームの中心に彼がいたからだ。すでに彼は、後にテレビドラマ化される著書『心の傷を癒すということ』を刊行し、サントリー学芸賞を受賞していたが、当時はそのこと以上に、中井久夫を変節させた一番弟子として知られていたように思う(4)。
統合失調症の精神病理で名を馳せた中井だが、どこかの新聞記事に、「多重人格は一種の医原病」といった趣旨の寄稿をするなど、少なくともかつては、DIDを含む解離現象に批判的な立場にあると認識されていた。ところが、震災を境に一転してトラウマや解離について饒舌に語りだし、ジュディス・ハーマン著『心的外傷と回復』の翻訳までしている(5)。私はその劇的な変節に驚き、仕掛け人である安に対する関心が否応なしに高まっていたのだ。
そして、ついに安を招いての講演会が横浜で開催されることになった。
しかし、妙なこともあるものだ。相当に前向きな気持ちで参加した安の講演であったにもかかわらず、なぜか登壇する安の視覚的な記憶がすっぽり抜け落ちている。私は居眠りをしていたのだろうか?
逆に、講演会ではなく、その後、みなとみらいのホテル内バーで開催された、クローズドな打ち上げの情景については、やけに克明に記憶している。雰囲気のよい店だった。暗い店内でテーブル上のキャンドルだけを頼りにグラスを傾けていると、そこが、洞窟のなかで焚き火を前に車座になって語り明かすのに似た、静かで神聖で、それでいて親密な空間に感じられたからだ。
安は、終始、大きな氷の入ったウィスキーのグラスをゆっくりと回していて、ごくたまに口元にグラスを運んだ。ひっきりなしに人がやってきては、安に矢継ぎ早に質問を浴びせかけていた。おそらく誰もが安のDIDに関する講演に衝撃を受け、自分なりの納得をしようと必死だったのだろうが、そうした人たちの熱によっても安の静謐さは微塵も乱されなかった。
私は、強引に安の真向かいの席に陣取ることに成功したまではよかったが、自分からは何一つ質問することができなかった。交わした会話は次のやりとりだけだった。私が、「自分は駆け出しの精神科医です。現在は依存症専門病院に勤務しています」と簡単な自己紹介をすると、安は「依存症患者さんのなかにはわりとDIDの方がいますね」と応えてくれた。驚いた私が、「そうなんですか!?」と返したところ、安は「ええ。これからきっとたくさんのDID患者と会うことになりますよ」とうなずく……これだけだ。後は、安のもとには次々に精神科医や心理士がやってきて途切れず、私は口を挟むタイミングを失った。代わりに私は、安と他の人とのやりとりに耳をそばだて、暗闇に漂う言葉を拾い集めることに必死になった。
その言葉をつなぎ合わせると、おおよそ次のようなことを話していた。
――DIDはしばしば看過されている。非典型的な統合失調症や双極性障害、あるいは、治療に難渋する境界性パーソナリティ障害や依存症の患者のなかに紛れ込んでいる。会うたびに印象が異なる患者がいたらDIDを疑ってみる必要がある。
――交代人格が出現した場合には、まずはきちんと自己紹介して、その凶暴な人格の怒りの背後にある悲しみを見いだすように努める。ひとわたり交代人格の主張に耳を傾けたら、登場と発言をねぎらった上で、最後は主人格に戻ってもらう。交代人格のまま帰すと、病院からの帰路でいろいろとトラブルを起こす危険がある。
――交代人格が出現していない場合でも、決して交代人格を批判してはならない。主人格の背後で交代人格は医師とのやりとりを聴いている可能性が高い。いかに粗暴で、一見邪悪な考えを持っている交代人格であっても、すべて意味があって存在している。凶暴な人格は患者が暴力から自分の身を守るのに役立ってきただろうし、性的に奔放で誘惑的な人格も、暴力的に組み敷かれるのを回避し、状況を自分のコントロール下に治めるのに役立った可能性がある。
――自殺願望にとらわれた交代人格は主人格を守るためにつらい出来事や感情の記憶、さらには、被害を受けた際に体験した自殺念慮の記憶を一手に引き受けてきたのかもしれない。そういう記憶を交代人格が引き受けることで、主人格の自殺を回避するのに役立った可能性もありえる。その意味では、人格間の健忘隔壁を尊重し、人格の統合を拙速に行おうとすべきではない。
――主人格に殺意を抱く人格もいるが、それは表面上の「よい子」を演じて過剰適応し、つらい感情やつらい記憶を安易に交代人格に押しつける主人格に憤りを感じているからで、その殺意には多少とも同情すべき事情があること……などなど。
妖術のような話だった。語られる内容はそれぞれ理路整然としていたが、交代人格というものを単なる「症状」としてではなく、あたかもそれぞれ独自の意志と感情を持つ個体、独立した生命体のように扱うという前提が、どうにも受け容れがたかった。それは、科学でも何でもなく、新興宗教かおとぎ話、少なくとも精神分析よりもさらに悪質な迷信であって、医学はもちろん、従来の精神病理学にさえ接ぎ木することのできない理屈と感じたのだ。
それなのに、目の前の安が醸す静謐な雰囲気はきわめて魅力的だった。彼はその3年後の2000年に39歳で夭折するのだが、逆にいえば、弱冠30代半ばにしてそのようなただならぬ佇まいをまとっていたことになる。それだけに私は余計に葛藤したわけだが、それでもなお受け容れがたかった。というか、「これを受け容れたら、ようやく自分なりに頭のなかで整理がついてきた精神医学が瓦解し、わけがわからなくなってしまう」という危機感を抱いたのだ。
もちろん、そうした考えを安に伝える勇気もチャンスもなく、その夜は、私は口をつぐんで静かにウィスキーを啜りつづけたのを覚えている。
そのわずか3日後、奇蹟が起きた。私は信仰とは無縁の人間だが、このときだけは奇蹟なる現象を信じたくなったし、いまでもそれは奇蹟だと信じている。
その日、私が勤務する依存症専門病院にひとりの新患が受診したのだ。ベンゾジアゼピン(睡眠薬・抗不安薬に含有される依存性物質成分)依存症の患者だった。40代のすらりとした怜悧な美貌の女性であり、育ちのよさを感じさせる上品な言葉遣い、しかしどこか機械のような、人を寄せつけない硬質な空気をまとっていた。
その患者は、それまで自分が診てきたベンゾジアゼピン依存症患者とはさまざまな点で異なっていた。連日、処方許容上限量の20倍という大量のベンゾジアゼピンを服用しており、事実、診察時点でもすでに大量の薬剤を服用した状態であったにもかかわらず、酩酊した印象がまったく感じられなかったのだ。高度な耐性が形成されているのだろうか、まあ、そういうこともあるかもしれない――私はそう考えた。
しかし、だとすれば、大量の服薬ができない状況では、相当深刻な離脱症状が出現するはずだ。ところが、彼女の場合はそうではなかった。彼女には周期的にまったく服薬をしなくなる時期が訪れるのだ。不意に薬物に振り回されている自分に嫌気がさして、1、2カ月ほどぴたりといっさいの薬物をやめてしまうのだという。決して漸減ではない。ふつうあれだけの量を連日服用していたら、急な中断によって離脱けいれん、最低でも激しい焦燥感や手指の振戦が出現しておかしくないところだが、これまでそうした挿話がまったくなかったというのだ。実に不思議だ。
気になるのは、10代の頃、頻回に自傷行為をくりかえしていた時期があったということだ。当時、自分でも気がつかないうちに腕を切っていて、はっと我に返ると腕から血が流れていたのだという。そして最近では、ベンゾジアゼピン服用の有無にかかわりなく、突然、錯乱状態に陥って器物を損壊したり、自殺行動におよんで救急搬送されたりしていたが、いずれの場合も、行為後には健忘を残していた。
診察の途中まで、私はあくまでも通常のベンゾジアゼピン依存症患者に対するのと同じように、薬物使用歴を中心に問診を行っていた。彼女は診察に協力的で、こちらの質問に的確に答えてくれていたが、現在の問題に関して聞き終え、今度は、問診の主題が生育歴などの子ども時代の話におよんだあたりで、彼女の様子が急変した。
突然、彼女は深く首をうなだれて身を屈め、小刻みに身体を震わせはじめたのだ。まもなく唸り声を出し、次第にその声は大きく、そして声質も野太くなって、不意に途切れた。不気味な静寂がひとしきりあった後にむっくりと顔を上げると、そこにはさっきまでとはまったく別人の顔があった。顔から怜悧さは消え失せ、まるでセクシー女優のような艶めかしく、しかも少々野卑な表情で、私に向かってこういったのだ。
「あんた、誰?」
30年あまり精神科医をやってきて、このときほどの恐怖はいまだ体験したことがない。なるほど、駆け出しの頃には、患者に刃物を向けられたり、殴られたりしたこともあったが、それよりもこのときの方がはるかに怖かった。その瞬間、私は、戦慄が稲妻のように背骨を貫き、強盗に銃口を向けられた銀行員のように身体がかたまり、口を開けたまま声を失っていた。
彼女は目を細め、頭から足先まで私をなめ回すように眺めると、舌なめずりしてみせた。
「あんた、あたしと一発やりてえんだろ? なぁ、そうなんだろう? ふん、どうせ男なんかみんなそんなもんだ」
まるで映画に出てくる場末の商売女のような口調だった。その発言は、世の男性全員を敵視し、性的に誘惑しながら同時にその誘惑相手を蔑む言葉だった。
まさか、交代人格? 心臓の拍動音が乱打される和太鼓のように激しく、やけに大きく聞こえた。
しかし、その瞬間、不意に3日前の安の話が脳裏に閃いたのだ。私は、必死に冷静な態度を装って自己紹介を試みた。話しながら、自分の声が震えているのがわかった。
もちろん、最初のうち交代人格は猜疑的な態度で、私にあれこれと文句をぶつけてきたが、私は自分なりに怒り猛る人格の背後にある悲しみを見いだそうと努めた。すると、次第に怒りのトーンは鎮静化し、交代人格は、自身の搾取と被害の歴史を語り、男たちへの怒りと、それでもなお過剰適応を続ける主人格への不満を漏らした。
私はその話をひとわたり傾聴し、苦労をねぎらった。問題解決に向かって今後はこの診察室で「交通整理」をしたいと伝え、同意を得た。そして、相手が納得したのを確認すると、最後は主人格に戻ってもらった。もちろん、主人格は自分に何が起こったのかを把握しておらず、自分をとりまく空気が変化しているのを感じたのか、相変わらず上品な態度で、「私、いま何か変なことをしませんでしたか?」と戸惑っている様子だった。
これがDIDなのか? いずれにしても、私はそのとき、安から教えられた方法で何とか危機を乗り越えることができたのだ。
彼女の交代人格と会ったのはこれが最初で最後であったが、主人格と会っているときにも、背後で交代人格が聞いていることは確信できた。そして不思議なことに、まもなく彼女のベンゾジアゼピン乱用は憑きものが落ちたようにあっさりと消失してしまったのだ。
それから1年後、今度は、自分がよく見知った担当患者を介して、自分が見落としていたDIDと遭遇することとなった。
その患者こそ、かつて統合失調症の前駆状態と診断されたリストカット女子高生だった。通院を中断してすでに2年の月日が流れ、そのときすでに高校3年生になっていたが、最近、5階にある自宅マンションのベランダから飛び降りたというのだ。幸い外傷は神経損傷を伴わない脊椎圧迫骨折のみで、大学病院での治療によって自力で歩行できる状態にまで回復した。
退院してすぐ彼女は私の外来にやってきた。彼女によれば、離婚後に母親がひそかに父親と逢瀬を重ねていたことを知った途端、強烈な感情に圧倒されたのだという。なぜ母親が父親と会うことにかくも激しく感情を揺さぶられたのかは語らなかったが、やはり父親とのあいだに何か深刻な出来事があったのだろう。
彼女はいった。
「あのときは、突然、身体がいうことをきかなくなりました。自分が巨大なカプセルみたいな殻に包まれる感じで、視界が周りから暗く小さくなって、外の世界がまるでサランラップの筒越しに覗いている感じに見えました。母さんの声が遠くなって、身体が鎧でも着てるみたいにすごく重くなって動かせなくなったんです。誰かに身体を支配された感じで、勝手に身体がベランダの方に運ばれてしまって、全然抵抗できませんでした。それでベランダから落ちてしまったんです」
その瞬間、彼女もまたDIDではないか、と直感した。
彼女が経験した現象は、自分の意志で身体を動かすという行為の能動性が失われ、他者の意志で自身の身体を操られるという体験だった。これは統合失調症診断で重視されてきたシュナイダーの一級症状の一つ、作為体験(させられ体験)というものだが、これこそが患者がDIDに罹患していることの重要な傍証なのだ。
安が語っていたように、DIDは統合失調症と誤診されやすい。というのもDIDでは、交代人格の声は患者自身にとっては幻聴として体験されるからだ。もしもそれが主人格に何らかの行動を指示する内容であれば命令性幻聴として体験されるし、複数の交代人格間で議論として聞こえてくれば対話性幻聴として体験されるだろう。そして交代人格によって身体を支配され、主人格の能動性が奪われている場合には、彼女の場合と同様、主人格にとっては作為体験となる。事実、シュナイダーの一級症状は、統合失調症患者よりもDID患者においてはるかに多く認められるという報告もあり(6)、その意味では、シュナイダーの一級症状はDIDに特徴的な症候といった方がよいくらいなのだ。
そう考えてみると、ブランケンブルクがその古典的名著のなかで提示した症例アンネ・ラウなどは、統合失調症ではなく、離人症からDIDに及ぶ解離のスペクトラムで捉えるべきなのかもしれない。というのも彼女は、幼少時に父親から不適切な養育を受けており、成人後は、執拗に離人感や現実感喪失を訴えていたからだ。偉大な先人を貶めるようで心苦しいのだが、ブランケンブルクが深刻な被害体験を見落としていた可能性、あるいは、意図的に無視した可能性を、私はかなり本気で疑っている。
通院を再開した女子高生患者は、その後しばらく日記を持参して受診した。
「自分では書いた覚えがないのに、誰かが勝手に日記に変なことを書き込んでいるんです」
確かに、彼女の日記には筆跡と文体の異なる複数の記述が混在していた。どうやら日記を介して交代人格同士が意思疎通を試みているようだ。診察場面で交代人格が現れる日はかなり近いかもしれない――そう私は感じた。
案の定、以降から続く2回の診察は、それぞれ別の交代人格が前に出た状態で来院した。そのことは、いつもの彼女とは異なる話し方と服装ですぐに気づいた。ふだん彼女は、カットソーにジーンズというシンプルで中性的な服装だったのに、次回には、ボロボロのダメージジーンズにライダースジャケットを着て現れて、「俺」という一人称でぶっきらぼうに話した。さらに次の診察では、一転して、レースのフリルのついた、お姫様風ワンピースを着て、「あたし」という一人称の甘えた口調の話しぶりだった。DID患者では主人格と反対の性を持つ交代人格が存在することが多いが、彼女もまたその例に漏れず、異なる人格が順番に私に会いにきたのだろう。
私はその都度、丁寧に自己紹介し、それぞれの人格が抱えている思いを尋ね、彼らの怒りや不満を受けとめ、それぞれがはたしてきた役割をねぎらった。そのうえで、主人格が生き延びるのに協力してほしい旨を伝え、最終的には理解が得られた。
しかし、診察室でのやりとりだけでは不十分だった。どうしても母親との同居を解消する必要があったのだ。というのも、母親と顔を合わせるたびに二人は激しく衝突しており、そのたびに本人は解離状態に陥って家庭内で暴れて家具を破壊し、他方で、母親は母親で大量飲酒して泥酔し、酩酊状態で暴言を吐いていたからだ。
そこで、自治体の福祉課と相談し、未成年でありながら世帯を分離して単身生活をさせ、生活保護受給下で学業を続ける、という環境を整える必要があった。幸い関係者の理解が得られてこの異例の支援が実現し、まもなく彼女は無事に高校を卒業することができた。
その後、彼女は、地元の食品会社に事務員として就職し、生活保護を廃止した。
飛び降り事故から3年が経ち、彼女には恋人ができた。やがて同棲、結婚、妊娠と進むなかで新たな危機が発生した。
ちょうど第一子出産直前だった。それまで順調に妊娠が経過し、臨月を迎えていたが、破水した直後に、彼女は突如として自宅を出奔してしまったのだ。夫をはじめ周囲は騒然とし、警察も捜索に動いた。結局、その日の深夜になって、彼女は子どものように声をあげて泣きながら裸足で山下公園を徘徊しているところを保護されたのだった。
久しぶりの解離症状だった。おそらくではあるが、10代にして実母に失望し、「自分は母親のようにはならない」「自分の力で幸せな家庭を作る」と誓っただろう彼女といえども、いざ自分が妊娠して母親になることが現実味を帯びると、戸惑いと不安が高まったにちがいない。長いこと意識の奥で休眠状態にあった幼児人格が、突然、鎌首をもたげるように覚醒したのだった。その幼児人格は、「赤ちゃんが生まれたら私の存在が忘れられる。私はかわいがってもらえなくなってしまう」と訴えて、出産に激しく抵抗しているらしかった。
山下公園で保護された翌日、彼女は大学病院の産婦人科に入院となり、当時、同じ病院の精神科に勤務していた私はすぐに産婦人科病棟に向かった。すると、病室の彼女はまさに幼児人格が登場している真っ最中で、ベッドサイドの若い夫に無理難題を訴えているところだった。当時まだ大学生だった若い夫が、おろおろしながらも赤ん坊をあやすように必死に幼児人格をなだめている光景は、いまでも強く印象に残っている。
その後、第一子の養育には少々苦労し、地域の保健師をはじめさまざまな支援を受けた時期もあったが、30代以降になると、生活全体に余裕が感じられるようになった。二人の子どもが通う学校では、押しに弱い性格が災いして、しばしば保護者会役員の仕事を押しつけられたが、意外なリーダーシップを発揮し、会長をしていた時期もある。
解離症状はもう20年間出現していないし、何らの精神科治療薬も服用していない。しかし、疲れがたまったり、夫や子どもに対する不満が募ると少しだけ離人感が強まったり、漠然と「消えたい」「いなくなりたい」という自殺念慮というか、虚無感が湧いてくることがあるようだ。そのような場合には、夫と共通の趣味である野外フェスで一緒に盛り上がると消失するという。
実母とは一定の距離をとり続けている。どうしても年1、2回、実家に足を運ばねばならない用事があるが、その際も必ず日帰りの旅程とし、宿泊を避ける努力をしている。あまりに長い時間、母親と接していると、「何となく具合が悪くなるような感じがする」からだそうだ。
そういうわけで、私はこの30年間、子ども時代の被害体験について彼女からその詳細を聞かされることのないまま経過している。短い診察時間のなかで私がやっていることといえば、日常生活に関するちょっとした愚痴に耳を傾け、相槌を打ったり唸ったりしているだけだ――これはもはや相談ですらなく、雑談というべきだろう。しかし、実は雑談こそが重要なのだ。
安が予言した通り、その後、私はアディクション臨床のなかで相当数のDID患者と遭遇してきた。必ずしも高頻度とはいえないものの、確かにアディクションに悩む人のなかには一定の割合でDIDを抱える人が存在する。そして、DIDが併存する依存症患者は、従来のやり方ではなかなか断酒・断薬には至れないことが多い。
そうした患者では、アルコールや薬物による意識変容は、強烈な痛みを伴う感情や記憶から意識を遠ざける、という点で解離と等価の機能をはたしている。当然、アルコールや薬物があったからこそ延命できた、と見なすべき患者も少なくないのだろう。要するに、やっかいな問題にはすべて意味があるのだ。であるならば、性急に断酒・断薬を目指すのではなく、まずは治療の継続を優先し、アルコール・薬物使用による弊害を最小化する方策――まさにハームリダクションだ――を模索するという治療上の選択も、まったく不自然な話とはいえない。
こうして振り返ってみると、今日における私のアディクション臨床の起点には安がいる、といっても過言ではない気がしてくる。そう、すべては、あの、薄暗いバーで耳をそばだてて聞いた安の言葉を、そのわずか3日後に実体験を通じて完全に受容した瞬間から萌芽した。
私にとってそれは、あたかもヘレン・ケラーが手のひらに水を受けながら初めて言葉と世界を認識した瞬間にも比せられるくらい、衝撃的で革命的な体験だった。
参考文献
- ヴォルフガング・ブランケンブルク『自明性の喪失――分裂病の現象学』木村敏・岡本進・島弘嗣訳、みすず書房、1978年。
- 木村敏『自己・あいだ・時間――現象学的精神病理学』弘文堂、1981年。
- ラルフ・ブリュースター・アリソン、テッド・シュワルツ『「私」が、私でない人たち――〈多重人格〉専門医の診察室から』藤田真利子訳、作品社、1997年。
- 安克昌『心の傷を癒すということ――神戸…365日』作品社、1996年。
- ジュディス・ハーマン『心的外傷と回復』中井久夫訳、みすず書房、1996年。
- Ross, C.A.: Dissociative identity disorder: diagnosis, clinical features, treatment of multiple personality. 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc, NY, 1996.
編集部注:本連載では、登場人物の匿名性を保つため、プロフィールの細部に変更を加えています。