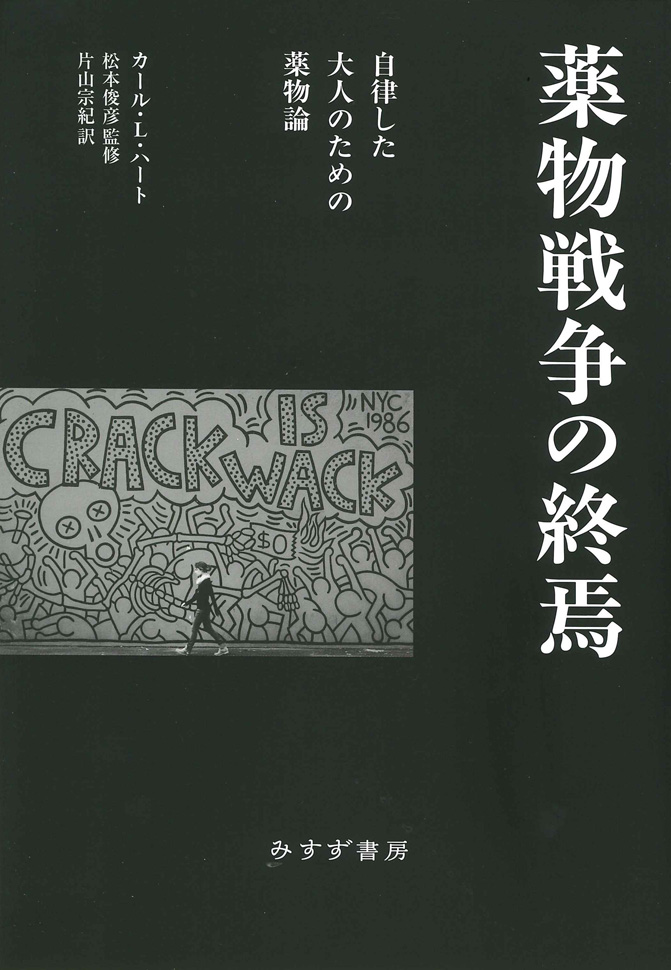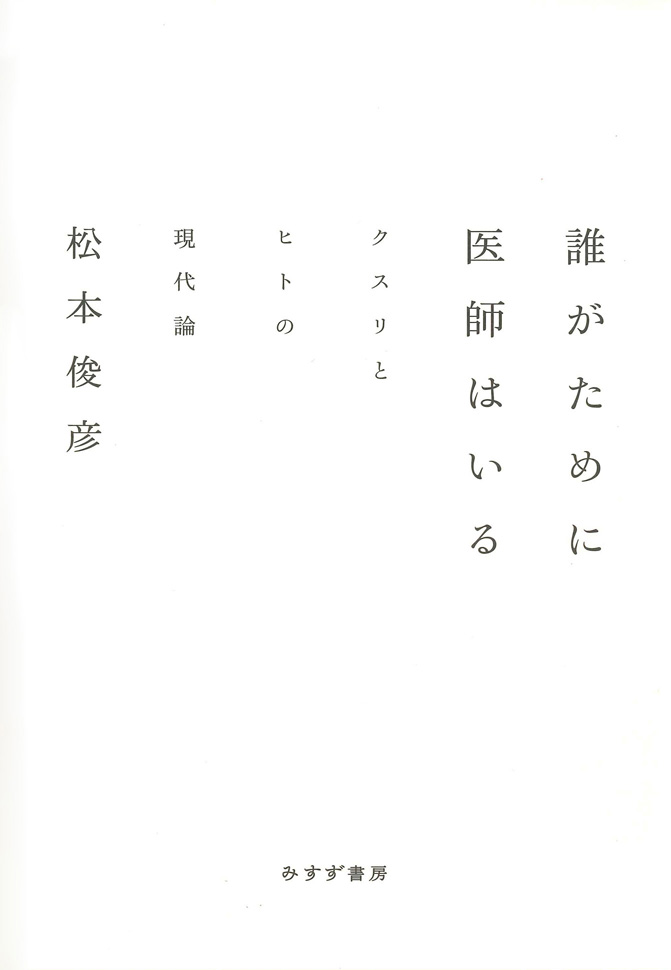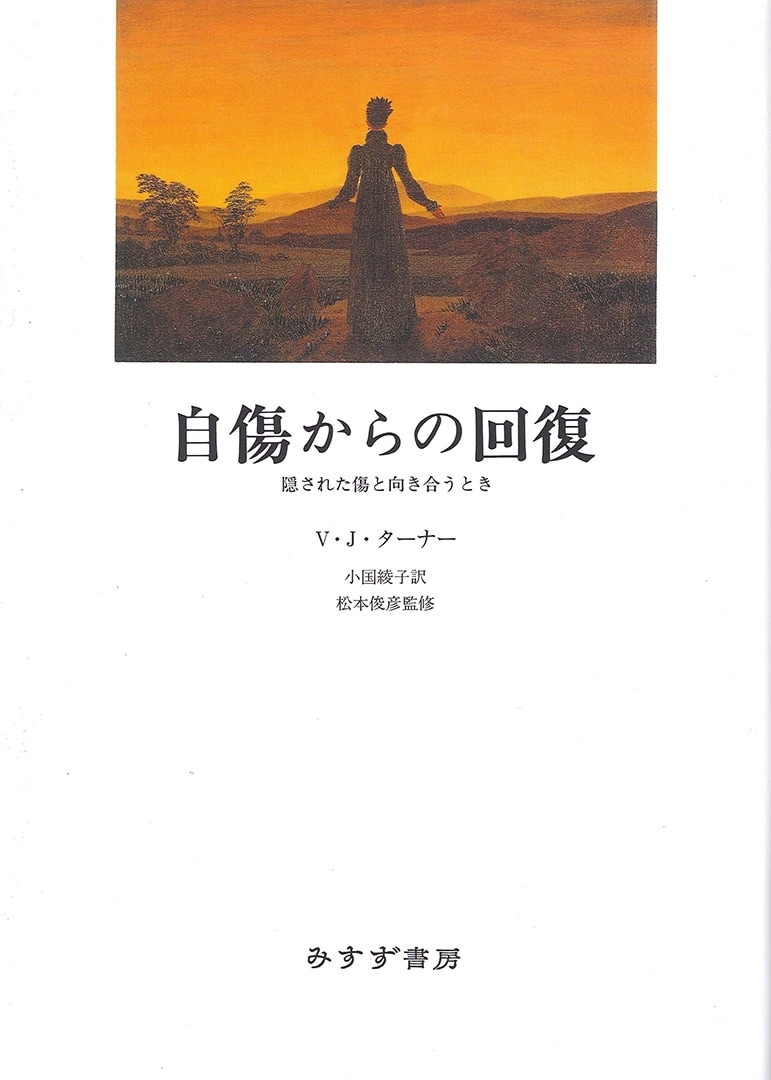外来診療日の朝はいつも緊張する。9時に精神科外来に到着すると、すでに待合室にはたくさんの患者が診察を待っていて、ひどい混雑ぶりだ。その光景に遭遇するたびに、「今日、自分は生きて帰れるだろうか」と悲壮な気持ちになってしまう。
待合室を通り抜けてひとたび診察室に入れば、17時まで私はその狭い部屋から出ることができない。私は、患者を診察室に呼び込むや、近況を聞き、何かコメントや提案をし、処方箋や予約票を渡すと、また次の患者を呼び込む、ということを何十回もくりかえさなければならない。まるで延々と続けられる、相撲部屋のぶつかり稽古みたいだ。
それにしても、薬物依存症臨床に携わりはじめてから30年近く、その間、患者の姿は大きく変化した。かつての「反社」っぽい風体の人はすっかり影をひそめ、待合室は、スターバックスでアップルのノートパソコンを開いていそうな、こざっぱりとした身なりの人ばかりになった。
そうしたなかで、最近ちらほら目立ち始めたのは若い女性、それも「地雷系メイク」――というのだろうか? みな一様に血色の悪そうな、そして、夜通し泣き腫らしたみたいな顔をしている――の女性だ。その多くは、フリルのついた洋服の半袖から自傷痕のある前腕が覗いている。
彼女たちは市販薬依存症の患者だ。その多くが、朦朧とした表情をしていたり、不自然にハイテンションだったり、待合室の椅子にぐったりと身を沈めていたりする。おそらく朝自宅を出る前に市販薬を過剰服薬(overdose; OD)してきたのだろう。そうしないと、とてもじゃないが受診できない。というのも、彼女たちの多くがさまざまな心の傷と精神疾患を抱えていて、その影響で混雑した公共の交通機関は怖くて乗ることができないからだ。無理して乗れば、パニック発作に襲われるか、あるいは、恐怖のあまり解離状態に陥って意識が飛んでしまうかする。そうした事態を回避するには、通院日の朝はODせざるを得ない――ODしてでも受診した方がよいのか、それとも、ODするくらいならずっと自宅にこもっていた方がよいのか、これは実に悩ましい問題だ。
私は、その日最初の患者として、そうした若い女性患者のひとりを診察室に呼び込んだ。もちろん、依然として市販薬ODは続いていたが、受診自体は称賛に値する。なぜなら、その患者は遅くとも朝6時には起床し、診療開始の1時間前から待っていたことになるからだ。
一通りの話が終わり、処方箋と次回の予約票を受けとった彼女は、診察室から去りかけたところで、そうだ、と急に何か思い出したかのように向き直った。
「今朝、病院の駐車場で先生が出勤してくるところを見ましたよ。車通勤なんですね」
意表を突かれて、私は困惑した顔をしていたにちがいない。まるで業務用スーパーマーケットで、トイレットペーパーを大量購入する現場を目撃されたみたいな気分だ。
「先生の車、めちゃくちゃうるさいですね。暴走族みたいじゃないですか」
確かに、最近、私は車通勤をしている――それも、暴走族のように騒がしい車で。
2年ほど前、私は知り合いの先輩精神科医から車を安く譲ってもらった。それは7年落ちのイタリア車で、もともとはフィアット純正のキュートな小型大衆車に、アバルトというチューニング・メーカーが改造を施したものだ。つまり、軽自動車並みの小さなボディに、不相応に大きなエンジンとタービンを押し込み、太いタイヤを履かせ、それを張り出したブリスターフェンダーで覆う、といった感じの改造だ。その結果、かわいらしさと強面感が混在する、奇形的な佇まいの車になった。たとえるならば、ランドセルを背負った小学1年生が、アナボリック・ステロイドによるドーピングで、童顔を残したまま、身体だけ筋骨隆々のマッチョになったような感じだ。
以前乗っていた古いマセラティは、とても日常の足に使える代物ではなかった。もちろん、マルチェロ・ガンディーニの手になるグラマラスなボディが気に入っていて、だからこそ、12年もの長きにわたって維持し続けたが、正直、乗りこなせていたとはいえない。なにしろ、V8 2800ccのツインターボ、280馬力のエンジンは獰猛な加速を見せるものの、驚くほどブレーキが貧弱で、スピードを出すのは怖かった。しかも、30年落ちのイタリア車らしい「ドッカン・ターボ」で、3000回転あたりから唐突にターボが効き始め、予期せぬ暴力のように、突然、トルクが爆発するのだ。一度などは、雨の日の高速道路合流時、雑なアクセルワークで加速したところ、後輪が暴れ出して車はお尻を左右に振って踊り出し、制御不能になった。もしも後続車が来ていたらまちがいなく大事故となっていただろう。私は猛獣使いにはなれなかったわけだ。
問題はそれだけではなかった。燃費は市街地走行でリッター3kmと、環境に対する優しさなど微塵もなく、夏は、渋滞にはまるたびにオーバーヒートの恐怖と対峙した。そんなとき冷却ファンは狂ったように回り続け、不安になった私がエアコンを切ると、今度は車内が40度超えの灼熱地獄となった。まるで戦車の操縦だった。もちろん、出先で車が立ち往生し、途方に暮れながら路上でレッカー車の到着を待つなんてことは、一度や二度ではない。
ところが、アバルトは違った。なるほど、直列4気筒1400ccにターボ過給で180馬力というスペックは、小さなボディには十分過ぎるほどパワフルだが、なんとか自分の手に負える範囲内だった。燃費もリッター10~11kmとそこそこ、真夏の渋滞でもエアコンが使える。いまのところ、出先での立ち往生もなければ、故障もない。あの、工業製品信頼性後進国イタリアも、最近はさすがに工業技術が向上したらしい。
特筆すべきは、こうした信頼性向上が運転する楽しさを損なっていないことだった。レコード・モンツァ製マフラーのせいで排気音がやけに勇ましく、確かに近所迷惑この上ないだろうが、運転する者の気分は高揚する。エンジンはトルクフルでどの回転数からでも力強く加速し、回転数の高まりとともになだらかに力強さを増していく。だから、通勤中、無用にマニュアルシフトをいじっては、エンジンの回転数を合わせて丁寧にクラッチをつなぐ、という作業が楽しくてしかたない。そんなとき私は、車がみずからの身体の延長となり、自分が車の動きのすべてを操作し、制御し、支配している、という万能感――まあ、まやかしなのだろうが――に浸っている。
要するに、車通勤をするようになって、退勤後は、一人きりの空間でのこうした体験が最高の気分転換になる、ということを発見したのだ。かつて電車で通勤していた頃には、帰路に飲み屋で一杯やるというのが気晴らしだったが、酔いに煙った脳は、帰宅後、メールの返信すらままならない有様だった。だが、車通勤ならばその心配はない。
とりわけ外来診療日の夜は、こうした気晴らしが重要だった。というのも、その日の夜、私は、猛打を浴びながら12ラウンド立ち続けたボクサーのような気分になっている。思えば、臨床は予期せぬ出来事、予想外の連続で思うに任せぬことばかり、精神科医を30年あまりやっていても、臨床はいまだ自信喪失の連続だからだ。しかし、それでも、車の運転を通じての自己制御感や自己効力感の確認体験は、そんな私にささやかな誇りを取り戻させてくれる。
話を薬物依存症臨床に戻そう。
自身の臨床をふりかえるたびに驚くのは、乱用薬物のめまぐるしい変遷だ。私が依存症臨床にかかわりはじめた1990年代後半、薬物といえばもっぱら覚醒剤で、時代はまさに「第三次覚醒剤乱用期」の真っ只中だった。2000年代は、精神科クリニックの増加に伴って、睡眠薬・抗不安薬などの精神科治療薬の乱用・依存が問題となり、さらに2010年代前半には、危険ドラッグ乱用禍が拡大した。そして2010年代後半以降、メディアは、大麻取締法違反による検挙者の増加をやたらと喧伝してきたが、それは臨床現場の実感とは大きく乖離した報道だった。
むしろ2010年代後半から現在まで、臨床現場で私たちを苦慮させてきた薬物は、大麻でも覚醒剤でもなく、市販薬だった。市販薬は、全年代では覚醒剤、睡眠薬・抗不安薬に次ぐ第3位の乱用薬物だが、10代の患者にかぎれば、薬物依存症患者の7割近くが市販薬を乱用薬物としている。また、危険ドラッグが社会を席巻していた2010年代前半と比べても、10代の薬物依存症患者の数は倍近くまで増加しているのだ。まちがいなく市販薬は新たな乱用者を開拓し、薬物依存症患者を増やすのに一役買っている。
それにしても、なぜ市販薬依存症患者が増えたのだろうか?
市販薬依存症患者には、トラウマを抱え、発達障害が併存する若い女性患者が多い。しかし、だからといって、人にトラウマを与える有形・無形の暴力が増えたとか、環境ホルモンないしは謎のウイルス感染症の影響で国民の発達障害罹患率が上昇した……という説明は乱暴すぎるだろう。むしろこう考えるべきだ。曰く、「生きづらさ」を抱える若い女性たちが、ここ最近、急速に市販薬にアクセスしやすい状況になった、と。
なぜアクセスしやすくなったのか?
「やはりSNSの影響ですか?」
メディア取材では、記者たちは申し合わせたようにそう質問してきたが、そのたびにいつも嘆息を禁じ得なかった。なぜ人々は、自分が理解できない現象を、新たに登場してきた、自分が使いこなせないデバイスやツールのせいにするのだろうか?
市販薬乱用禍が広がった最大の要因ははっきりしている。それはドラッグストアの急増だ。いまやドラッグストアチェーン業界は8兆円を超える市場規模に成長し、ここ数年、毎年国内では1000~1500店舗ずつドラッグストアが新規開店している。
実は、この乱用禍には国も加担している。年々増大する医療費を少しでも削減するには、国民にできるだけ医療機関を受診させないようにする必要がある。それには、医師抜きで医薬品にアクセスできる環境を整備しなければならない。そのような意図から、政府は処方薬の市販薬化を推進し、「ガスター」や「ロキソニン」、「メジコン」といった、かつては医師の処方箋がなければ入手できなかった医薬品が、いまやドラッグストアで簡単に入手できるようになった。それだけではない。インターネット販売の規制緩和によって、オンラインでも市販薬を入手できるようになったし、確定申告時に市販薬購入の領収書をかき集めれば、医療費控除も受けられるようになった。
しかし、業界成長にもっとも貢献した施策は、何といっても2009年の「登録販売者」なる資格制度の施行だろう。これまでは、薬剤師が薬局での販売と調剤双方の責任を担ってきたが、そこが店舗拡大の障壁となっていた。薬剤師の数にはかぎりがあるし、そもそも人件費が高い。そこで、学歴不問、試験合格だけで取得できる「格安資格」――登録販売者――を作り出した。これによって、薬剤師なしで市販薬製品の大半を販売できる状況が整ったのだ。
この制度施行以降、ドラッグストアは急激な勢いで店舗数を増やし、営業時間を延長していった。そして今日、各地の繁華街には、狭いエリアに複数のドラッグストアチェーンの店舗が軒を争っている。コンビニエンスストアであれば、客を食い合って共倒れになるところが、なぜかドラッグストアはどの店舗も繁盛している。改めて日本人は薬好きなのだ、と実感する光景だ。
しかし、訝しく思うのだ。日本人はいつからかくも風邪をひきやすくなり、咳や痰で苦しむ人が増えたのだろうか? 大気汚染が最近急速に深刻化したとでもいうのだろうか? それというのも、市販薬製品別売り上げランキングでは、いつも「エスエスブロン錠」(以下、ブロン)や「パブロンゴールドA」(通称、金パブ)といった、薬物依存症臨床でおなじみの商品がランキング上位に入っているからだ。ちなみに、平成22年国民生活基礎調査によれば、日本国民が日頃もっとも困っている症状は、断トツで「腰痛」が多く、次いで「頭痛」だ。「咳・痰」といった感冒関連の症状は、これら2つの痛みに比べればはるかに少ない。
もう1つ不思議に感じていることがある。わが国には、市販の感冒薬や鎮咳薬には実に多数の製品があり、実際、テレビCMでもさまざまな製品の宣伝を見かける。それなのに、なぜAmazonのベストセラー商品を見ると、感冒薬部門では金パブがいつも圧倒的首位の座に君臨し続け、咳止め薬部門ではブロンとメジコンが上位1位、2位を独占し、他製品を大きく引き離しているのか? ちなみに、この3薬剤、いずれも薬物依存症臨床に従事する者ならば誰もが知っている、乱用者が好む3大市販薬だ。
つまり、こういう可能性はないだろうか? 製薬企業を支えているのは、真にその薬を必要としている人たちではなく、別の目的で不適切に使用している人たちである、と。
市販薬依存症を抱える若い女性患者は、薬物依存症治療のあり方を根本から覆しつつある。理由は2つある。1つは、彼女たちには、従来、「依存症治療の原則」とされてきた方法論が通用しないからであり、もう1つは、彼女たちにとって薬物の問題は、治療や支援につながるための入場券にすぎず、本当の問題は別のところにあるからだ。
かつて薬物依存症の治療目標は、問答無用で「断薬」だった。たとえば覚醒剤依存症の治療がそうだ。なるほど、結果的に「まだ完全には覚醒剤をやめ切れてはいないが、それでも前よりマシになった」という状況はめずらしくないが、公式な治療目標として、「覚醒剤を使用する頻度や量を減らしましょう」と高らかに宣言されることはない。
ところが、市販薬依存症の治療はそうはいかない。患者の多くは、トラウマに関連する症状――フラッシュバックや過覚醒、不安や恐怖、突発的に涌き起こる自殺衝動――への対処として、いわば自己治療的に市販薬を使用している。したがって、断薬は自身の苦痛を悪化させるばかりか、ときには死を引き寄せることさえあるのだ。実際、市販薬依存症患者のなかには、ODによる肝障害や呼吸停止で不本意にも事故死した者がいる一方で、断薬後にフラッシュバックが悪化し、それがもたらす圧倒的な恐怖と自殺衝動に突き動かされて自ら死を選択した者もいる――それも、縊首などOD以外の方法で。つまり、断薬すればそれで患者がハッピーになるわけではない。むしろ、「続けても地獄、やめても地獄」というべきだ。
こうした患者たちと日々会い続けるなかで、私は治療目標の変更を余儀なくされた。もはや「やめる/やめない」よりも、いかにして生き延びてもらうかが優先課題となったのだ。
私は、患者に性急な変化――つまり、薬物をただちにやめること――を求めなくなった。薬物使用が止まらないのは相応の事情があり、それにもかかわらず、治療者が断薬を求め続ければ、それは患者にとって残酷な宣告となってしまう。曰く、「いまのまま、ありのままのあなたはダメだ」という宣告だ。これでは、虐待やいじめ、さまざまな暴力を生き延び、すでに十分なほど自己愛を毀損されている患者に対して、今度は、治療者がお墨付きを与えることになってしまう。「やはり私はダメ人間なのだ」と悟った患者は、治療から離れ、ますます市販薬に溺れるしかなくなるだろう。
新しい治療方針はこうだ。まず必要なのは、患者の現在、「いまのまま、ありのまま」を肯定することだ。正確にいうと、「今日まで生き延びてきた」、あるいは、「変化できなくとも変化を諦めていない」という現在を肯定する。そして、患者とともに薬物使用をモニタリングし、トリガーとアンカーを探し出すのだ。つまり、どんな状況だと市販薬乱用が激化し、あるいは緩和するのかを分析して、薬物使用量・使用頻度低減のための具体的方策を話し合っていく。
しかし、こうした治療方針が他の医療者に理解されるとはかぎらない。実際、私は、内科医や救急医から、「薬物依存症患者に薬物使用を許容するなど医者のすることではない」と非難されたことがある。のみならず、身内の精神科医からさえ理解が得られない場合があった。ある意欲満々の若手精神科医は、「こんなの治療じゃない。もしトラウマ関連の精神疾患があって薬物使用がとまらないのであれば、トラウマに関する根本的な治療をすべきではないか」と私に抗議した。
もちろん、理屈のうえではその通りだ。しかし問題は、患者の側にその準備が整っているとはかぎらない、ということだ。痛みを伴う記憶に脅え、薬物の作用を使って長年心に蓋をしてきた人に、蓋を開くよう強いるのは深刻な侵襲であり、自傷や自殺を誘発しかねない暴挙といっていい。仮にそうした危険を回避できても、社会的機能が低下し、それまでやれていた仕事や学業などのパフォーマンスには相当深刻な影響が出る。
私は決してトラウマに対する心理療法を否定しているのではない。タイミングや患者自身の内的および外的な準備性を見計らう必要がある、といいたいのだ。それを無視して機械的にトラウマに対する心理療法を提供すれば、患者の多くは、以前にも増して高まる苦痛に耐えかねて、中途で治療から離脱してしまうだろう。
冷静に考えると、ブロンと金パブはともにけっこう恐ろしい成分を含んでいる。それは、メチルエフェドリン(dl-メチルエフェドリン塩酸塩)と、ジヒドロコデイン(ジヒドロコデインリン酸塩)だ。これらは、前者は覚醒剤取締法によって覚醒剤原料として、後者はれっきとしたオピオイド(アヘン由来の物質)であり、麻薬及び向精神薬取締法によって麻薬として、それぞれ規制対象となっている。それにもかかわらず、特例的にいずれも低濃度であれば規制対象外とされているのだ。
奇妙な話だ。中学・高校における薬物乱用防止教室では、覚醒剤や麻薬に関して、「1回やったら人生終わり」といった趣旨の啓発が行われてきた。しかし現実には、それらを含む医薬品はドラッグストアで普通に販売されていて、ある意味で国も「薄めて使えば大丈夫」と太鼓判を押す格好になっているのだ。いうまでもないことだが、たとえ低濃度でも大量に摂取すれば依存症には罹患しうる。いまどき「ビールだけ飲んでいれば、どれだけ飲んでも決してアルコール依存症にはならない」なんて理屈は、冗談でも通用しない。
かねて北米では、オキシコドンやフェンタニルなどのオピオイド鎮痛薬が乱用され、多くの依存症患者や過剰摂取死亡者が作り出され、「オピオイド・クライシス」と名づけられて深刻な社会問題になっている。これまで日本は、そうした事態を「対岸の火事」として静観し、「わが国は欧米のような悲惨な状況を回避している。やはりわが国の厳罰主義的薬物政策は正しい」と自画自賛してきた。しかし、本当にそうだろうか? 近年における、ジヒドロコデイン含有市販薬の乱用禍こそが、日本版オピオイド・クライシスとはいえないだろうか?
オピオイドはがん性疼痛の緩和には欠かせない強力な鎮痛薬だが、その鎮痛作用は身体だけでなく、心の痛みに効いてしまう。それは、人の意識を心理的な痛みからも遠ざけ、孤独や孤立に耐えやすくする。事実、健常者にオピオイド受容体拮抗薬を投与した実験では、「他者との社会的断絶感」が強まることが明らかにされている(1)。だとすると、市販薬依存症患者は「内因性オピオイド欠乏症」の状態にあり、それがもたらす孤独感や孤立感という症状を自己治療すべくブロンや金パブを大量摂取している、という仮説は十分に許容されるだろう。
同じ理屈は、メジコンに含有されるデキストロメトルファン(デキストロメトルファン臭化水素酸塩)にもあてはまる。このNMDA受容体拮抗薬は幻覚薬ケタミンと類似した薬理作用を持ち、大量摂取時には人工的に解離症状、なかでも離人症――五感すべての知覚が遠退き、現実感が希薄化し、ときに幽体離脱して上方から自身を俯瞰するような異常感覚体験――と類似した体験を引き起こす。ちなみに、この解離という心的防衛機制には、意識を心理的苦痛から遠ざける効果があり、だからこそ、心的外傷後ストレス障害にはしばしば解離症状が伴うのだ。そう考えると、メジコンを乱用する者もまた、その市販薬がもたらす人工的な「化学的解離」によって、一時的に心理的無痛状態を得ている、という可能性は否定できない。
では、どうすればこの問題を解決できるのか? もしも私たち精神科医が、彼らが乱用する市販薬の代わりに、より安全で依存性の低い精神科治療薬を投与できれば、完治とは行かなくとも問題を扱いやすくすることができるはずだ。
しかし、次の2つの理由からそれは実現困難だろう。1つは安全性という点だ。精神科治療薬の方が絶対に安全とはいいきれないのだ。たとえばベンゾジアゼピン系の抗不安薬は、酩酊によって衝動性を高める危険があるし、何より依存性が高い。抗精神病薬については、依存性ははるかにましだが、身体が強力に鎮静されるわりに意識は明瞭という中途半端な状況を作り出す。これが、「誰かに羽交い締めにされ逃げ出せない」という被害状況を想起させ、恐怖感を助長する場合がある。また、大量投与時には、悪性症候群などの重篤な副作用も考慮すべきだ。
もう1つの理由は、依存症患者にとって市販薬最大のメリットが、「みずから調達し、みずからその服用を裁量できる」という点にあることと関係している。処方薬の場合、医師に苦痛を訴え、説得し、処方させる、という一連の手続きが必要となる。当然、患者の思い通りになるとはかぎらず、患者は医師に支配され、隷属していると感じるだろう。ところが、市販薬はそうではない。調達はもとより、服用するタイミング、そして頻度や量を決めるのは、すべて自分自身だ。
トラウマを抱える患者の多くはこの自己裁量権に執着し、それを手放すことを怖れている。逆にいえば、それほど彼らは、「自分は何もコントロールできない」という無力感に打ちひしがれ、また、「誰も助けてくれない」という不信感に苛まれているのだ。その意味で、医師を介さずに自身を制御できる市販薬は、彼らが失った自信を取り戻すのに貢献する面がある。
依存症からの回復に自助グループやダルクなどの社会資源が有効である、というのは、一般論としては正しい。しかし、若い女性が多い市販薬依存症患者にはその有用性は限定的だ。
というのも、そうした社会資源利用者の多くは、依存症患者の大多数を占める男性であり、それゆえ、若い女性――それもさまざまな暴力を生き延びてきた女性――にとっては必ずしも安全な場とはいえない。また、ナルコティックス・アノニマス(Narcotics Anonymous; NA)などの自助グループは、原則として断薬を前提とし、その維持を目標とする。だから、市販薬を乱用しながらの参加が許容される雰囲気ではない。そもそも、市販薬依存症患者の多くは人の多い場所が苦手であり、そのような場に参加するには、それこそODでもしなければ不可能だろう。
結局のところ、市販薬依存症の治療は医療機関で抱え込まざるを得ないのが現状だ。しかし、課題は多い。なかでも最大の課題は、市販薬依存症患者が医療者の陰性感情を刺激し、忌避されやすい傾向があることだ。
理由はいくつもある。たとえば、自殺の危機で緊急入院をしながらも、いざ入院すると自分勝手な都合で退院する、といったことを頻回にくりかえす。こうした事態に翻弄されるうちに、医療者のなかで患者に対する徒労感や怒りが高まってしまうのだ。まして前回退院から3カ月以内の再入院は、診療報酬上の収益も低く、そのことがますます患者を忌避させる。
また、「性暴力被害者である」「男性が怖い」と訴える一方で、夜の接客業や風俗業といった、性的被害リスクの高い仕事を選択しては、予想通り心の傷を増やす患者も少なくない。こうした事態に対し、「自業自得ではないか」と眉をひそめる医療者が一定数いるのだ。
残念なことに、過去の被害体験が将来の被害リスクを高める、という事実は、必ずしも医療者のあいだで十分に共有されていないようだ。トラウマを抱える者は、自分を大事にすることができず、一種の自傷行為として自らを危険な状況に置こうとする傾向がある。そして、男性に声をかけられるとフリーズ状態に陥り、まるで操り人形のように男性のいいなりになってしまうのだ。あるいは、「銀行強盗に恋愛感情を抱いてしまう人質の女性銀行員」というストックホルム症候群ではないが、極度の恐怖に瀕して加害者との関係性を性愛化する、という無意識の生存戦略をとってしまう場合もある。さらには、意図的に過去の被害場面と類似した状況――たとえば風俗業がそうだ――にみずからを置き、今度は、その場の主導権を自身がコントロールすることで、無力感を否認しようとする者もいるのだ。
それから、受診するたびに送迎する男性と車種が変わる患者がいて、こうした光景を目の当たりにした医療者のなかには、「受診するたびに同行する男が違う。ふしだらだ」と非難する者もいる。しかし、公共交通機関が苦手な患者にとって、通院送迎してくれる男性の複数名確保は、まさに死活問題なのだ。ただ、こうした「アッシー男」を渡り歩くうちに「人混み免疫」を失い、長じては、自力では公共の交通機関を利用できなくなってしまう者も少なくない。
ところで、かねて依存症業界では、回復には「自分の足を使う」ことの大切さが強調されてきた。確かに、家族に車で送迎してもらって通院や自助グループ参加をするようでは、依存症からの回復はなかなかおぼつかない。だから、自助グループでは、「足を使って回復する」という言葉がよく語られてきた。「お百度参り」めいた話ではあるが、私もその正しさを実感している。
しかし、それとは異なる理由から、私はこれまで女性の依存症患者に、可能なかぎり公共交通機関を利用するよう推奨してきた。曰く、「男に頼って受診するな。車に乗るなら、助手席ではなく、運転席に乗れ」だ。もちろん、その結果、通院のために朝からODをせざるを得ない患者もいるが、個人的には、「アッシー男」の支援を受けてしらふで通院するよりも、少々ODしながらでも自力で通院する習慣をつけた方が、長期的には好ましい結果となるように思う。それに、好きでもない男性への依存度を無用に高めるのは、不本意な隷属へと発展する危険もある。また、将来、生活保護受給が必要となった場合、「病状のせいで公共交通機関を利用できないからタクシー利用を認めろ」と主張しても、そうそう役所の理解を得られるものではない。
移動手段にちなんでいうと、興味深い市販薬依存症患者と会ったことがある。かれこれ15年ほど昔の話になるが、初診時、彼女は20代後半だった。すでに人生の闘いの山場を乗り越えて、名古屋でタクシー運転手として稼働しながら、静かな単身生活を送っていた。受診したきっかけは、私の著書を読んで、「1年間だけ、3カ月に一度でよいから、この人に話を聞いてもらいたい」と思ったのだという。もちろん、私は了承した。
驚いたことに、毎回、彼女は名古屋から東京までみずから車を運転してやってきた。いつもテンガロンハットに両袖にフリンジがついたスウェードジャケット、そしてミニスカートにウェスタンブーツという印象的な出で立ちで、まさにカウボーイならぬ「カウガール」だった。
彼女の自分語りは実に興味深かった。彼女が出生したのは拘置所内だった。それというのも、母親が覚醒剤取締法違反で逮捕されたとき、彼女はまだ母親の胎内にいて、しかも、折悪しく臨月だったからだ。その後、乳児院や児童養護施設を転々とし、そのあいまに刑務所を出所した母親と短期間過ごした時期に、母親の恋人から性的虐待を受けたのだった。そんなわけで彼女は、10代半ば以降、断続的に接客業や風俗業で生計を立てながら、文字通り「生き延びる」ためにリストカットや市販薬ODをくりかえした。その疾風怒濤の歴史は、両前腕の皮膚の、幾条も深く掘り込まれた塹壕のような古い自傷痕に垣間見ることができた。
そんな彼女に転機が訪れた。きっかけは、自動車運転免許をとり、風俗時代に貯めたお金で中古のスポーツカーを手に入れたことだった。それまでは公共交通機関が苦手で、徒歩圏内の狭いエリアで生活していた彼女が、それを契機に一気に行動範囲を広げたのだ。彼女は精神科医や心理士の本を貪るように読み、「この著者に会いたい」と思ったら、みずから車を運転して日本中どこへでも、それこそ縦横無尽に移動した。そして、ちょうど依存症患者が回復のためにせっせと自助グループのミーティングまわりをするように、そうした著者の診察を受けたり、講演会に参加したりした。そのような活動を続けているうちに、少しずつリストカットやODを手放せるようになった、というのだ。
それから数年後、長野県の講演会で彼女に再会した。講演中、聴衆のなかに彼女の姿を見つけたのだ。特徴的なカウガール・ファッションだったから、壇上からでもすぐに識別できた。講演後に駆け寄ってみると、例によって、名古屋から車で駆けつけたのだという。驚いた。彼女が語った、「講演全国行脚」の話は本当だったのだ。
いまでも鮮明に覚えている。はじめて診察室で会ったとき、名古屋から車を運転してやってきたと聞いて言葉を失った私に、彼女はにべもなくこう語ったのだった。
「車の運転が好きなんです。私にとって車は、鎧というか、ガンダムに出てくるモビルスーツみたいなものです。これさえあれば怖くない。私はどこへでも行けます」
翌週の外来診療日、やはり一番乗りで来院し、その日最初の患者となった、あの市販薬依存症の女性は、診察の際にこういった。
「先生、今朝もやかましい暴走族でしたね」
申し訳ない、と私は謝った。
「実は、最近、新しい目標ができたんですよ」
患者はそういった。
「いつか私も自分の車を買いたいなって。そのために治療を頑張って、ODをやめようって思ったんです」
それはいい、ぜひその夢を叶えた方がいい――私はそう返した。
その夜、私は、まっすぐ帰宅せず、気まぐれな寄り道をした。立ち寄ったのは新宿歌舞伎町トー横界隈だ。私はコインパーキングに車を停め、そのエリアに点在するドラッグストアを訪れてみることにしたのだった。
すると、数人の地雷系ファッションに身を包んだ若い女性が、それぞれ単独にドラッグストアを何軒か巡っては、それぞれの店でブロンや金パブ、あるいはメジコンを購入する、まさにその瞬間に立ち会うことができたのだ。これらの市販薬のなかには、厚生労働省からの通達により1人1箱と販売個数制限がなされている製品もあるが、界隈にこれだけの数ドラッグストアがあれば、かなりの量を集めることができる。極彩色のネオン瞬く夜の歌舞伎町で、人の群れを搔き分けながらドラッグストアをはしごする少女たちは、まさしく獲物を狙う狩猟人――ドラッグストア・カウガールだった。
ちょっとしたいたずら心から、私もまたドラッグストアでブロンの購入を試みた。すると、登録販売者とおぼしき女性がやってきて、神妙な顔で質問し始めた――曰く、「他の店でも同じ薬を購入していませんか? 不適切な使用はしていませんか?」と。さらに続けて彼女は、ブロンの依存性や健康被害について、滔々と私にプレゼンしはじめたのだった。おそらくたくさん勉強したのだろう。まるで学位審査に臨む博士候補者みたいに力んだ演説だ。
――誰に向かっていってんのか、この人わかってるのかな。内心、そう感じながら、私はプレゼンに耳を傾けた。
最後に彼女はこういった。
「過剰に摂取すると、命を落とすこともあります。ご注意ください」
――いやいや、ODする子たちは、「ワンチャン、死ねたらラッキー」と思ってるって。そんな言葉じゃOD予防なんてできないよ。
そう意見しようと考えたが、さすがに大人気ないと思い直し、やっぱり買うのやめます、といって商品を返した。店を出ると、私は脇目もふらず車を停めているコインパーキングに向かった。早くアバルトを運転したかった。
注
- Inagaki T et al, Opioids and social bonding: naltrexone reduces feelings of social connection. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11(5): 728-735, 2016.
編集部注:本連載では、登場人物の匿名性を保つため、プロフィールの細部に変更を加えています。