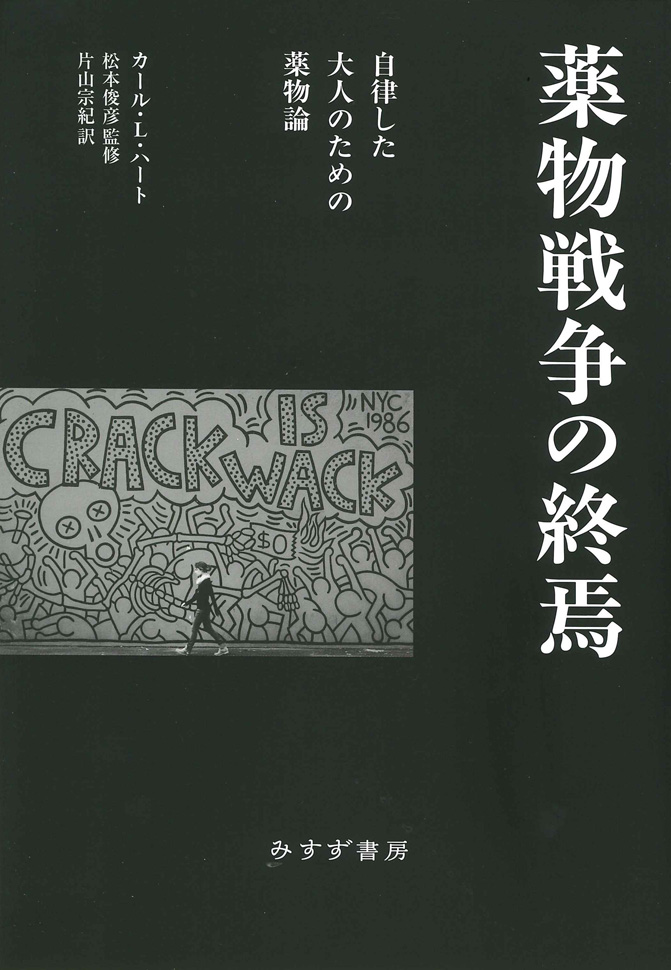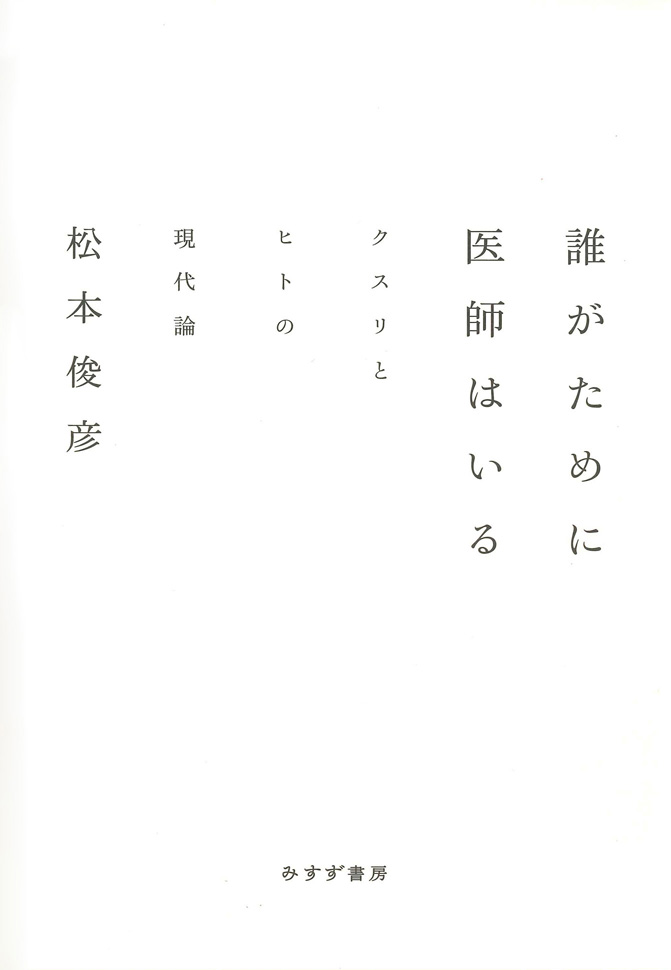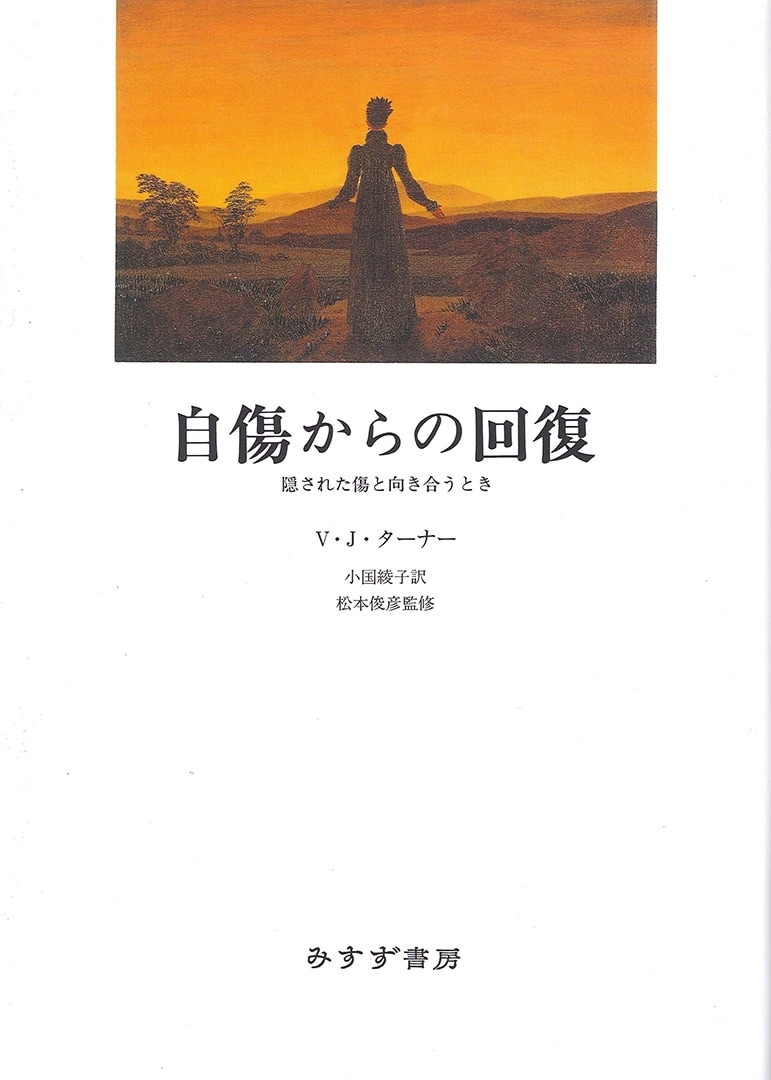21時すぎ、地下鉄の出口から地上に出ると、路肩に駐車するワンボックスタイプのハイヤーが目にとまった。その車は、街灯に照らし出され、深海魚のように黒光りしている。すぐに私の姿に気づいたらしく、運転手は慌てて車を降りてきて、うやうやしい仕草で私を座席に誘導した。
ワンボックスは、交通量の多い幹線道路をしばらく進むと、不意に細い路地へと左折した。途端に辺りは暗くなり、風景は閑静な高級住宅街に変わる。まもなく私はワンボックスを降り、今度は、待機していたシルバーのメルセデスへと乗り換えた。助手席でシートベルトの装着に手間取っていると、「いつも夜分遅くにすいません」と、運転席からサングラス姿の女性が会釈した。
メルセデスは一直線に目的地には行かずに、高級住宅街を何周かまわった。運転席の女性はしきりとフロントガラスの向こうに広がる闇に目を凝らし、道の左右へと交互に視線を投げて、不審な人影に注意を払っている。そうやって辺り一帯をひとしきり旋回すると、意を決したように邸宅の高い外壁の前に車を止め、リモコンでガレージのシャッターを上げた……。
かれこれ20年近く昔に何回となく体験したシーンだ。当時、私はある著名人を定期的に往診していた。その記憶のなかでは、あらゆる情景は水墨画のようにモノトーンなのに、唯一、ガレージでメルセデスの隣にあったフェラーリだけは、まぶしいほど鮮やかな赤を放っている。
この隠密裏の往診をはじめたのは、ある年配の精神科医からの依頼がきっかけだった。彼は私よりも二回り以上も年長で、すでに要職を退いていたとはいえ、依然として学界の重鎮的存在であった。もちろん、当時まだ「青二才」にすぎなかった私など、直接の面識などあろうはずもなく、「雲の上の人」とぼんやり仰ぎ見るだけだった。
ところが、ある日突然、その老精神科医から私の研究室に電話がかかってきたのだ。用件はこうだった――自分はいまある著名人の妻から夫の違法薬物使用について相談を受けている。その妻が、彼の書斎にあやしげな白い粉を発見し、嫌な予感がして本人を問い詰めたところ、「確かに過去には覚醒剤を使っていたが、いまはもうやめている」と告白したそうだ。妻は驚きのあまりパニックに陥ったが、何とか冷静さを取り戻し、共通の知人を介してその老精神科医に、「彼が依存症の状態なのか、治療が必要なのかを診断してほしい」と依頼してきたのだという。
「私はもっぱら統合失調症中心の臨床をやってきたから、薬物依存症のことはまったくわからない。そこで、あなたにお願いがある。その著名人と一度会ってほしい」
電話の向こうで老精神科医はそういった。
なぜ私なのかと返すと、「昨年の精神神経学会で薬物依存症に関してなかなか面白い発表をしていて、印象に残っていた」とその理由を語った。
到底、納得できる理由ではなかった。ただ、面白いという印象だけで、どこの馬の骨かわからない男に著名人の診療を任せるなんて、いくら何でも馬鹿げている。しかし、当時の私には、重鎮からの「直電依頼」を断る度胸などあろうはずはなく、気圧されたまま、「では、ひとまず一回だけ……」と回答してしまったのだ。
老精神科医から、「くれぐれも極秘で……」と念を押されたこともあり、自分が勤務する施設で診察するのではなく、私が直接その人物の自宅へと往診することにした。なにしろ、違法薬物にかかわる話だ。所属施設で診察をすれば、たとえ他患者の目を避けることができたとしても、どうしたって一部の職員には知られてしまう。だから、診察という形式をとらず――つまり、カルテを作らず、お金も一切受けとらず、あくまでも私的な相談というスタイルをとることにした。さらに著名人の妻からの要望で、まずは最寄り駅で待機するハイヤーに乗り、途中で妻が運転する自家用車に乗り換える、というややこしい手続きを受け容れることとなった。
私にとって初めての経験だった。いまならば電子カルテにパスワードロックをかけ、管理職クラスの事務方と看護師に対応の依頼をし、さらには、人目を避けるために特別な診察室とそこへの動線を準備するところだが、当時はそのような知恵も経験もなかったのだ。
最初の顔合わせが終わった直後から、これは困ったことになった、と頭を抱えた。てっきり一回きりのつもりだったのに、定期的に往診を継続する羽目になってしまったからだ。
その夜、面接は著名人の書斎で行われた。彼は、白いものが混じる長い髪をかき上げながら、自身の過去の薬物使用歴について率直に話してくれた。
「確かにさまざまな薬物を使ったことがあります。ええ、もちろん、覚醒剤もです。まずいことはわかっていましたが、ある時期、自分にはどうしても必要でした。ただ、それで仕事に支障を来たしたことはないし、家族に暴言を吐いたり、暴力をふるったりしたこともありません」
一言でいえば、彼は好漢だった。偉ぶらず、紳士的で、年少者の私に対しても丁重に接してくれた。著名人のなかには精神医学や精神科医療に批判的な人もいないわけではないが、彼はそうではなく、むしろ精神科医という職業に一定の敬意を払っているように感じた。もしかすると個人的に精神医学に関心を抱いていたのかもしれない。というのも、精神科臨床の実際について積極的にさまざまな質問をしてきたからだ。そのせいで、診察というよりも、私自身がインタビューを受ける側に立たされているような、居心地の悪さを覚えた。
世間話のようなやりとりが一区切りついた頃、彼がいよいよ本題とばかりに切り出した。
「今回のことでは妻にはずいぶんと心配をかけてしまいました。おそらく『裏切られた』という気持ちを抱いていることでしょう。この点について、本当に申し訳ないと思っていて、どうにかして妻を安心させたいと考えています」
安心……ですか? 私は彼を見返した。
「そうです。私から1つお願いがあります。月に1回くらいの頻度で、こんなふうにお話しする機会を作っていただき、さらにそのついでに、私の尿を検査して薬物反応を調べてほしいのです」
そういってから、彼は顎に手を当てて少し考え込み、ややあってからさらに続けた。
「うーん……そうですね、訪問日はあらかじめ決めずに、先生の都合のよいタイミングで直前に連絡をしてください。そうすれば、尿検査も『抜き打ち』っぽくなりますよね」
私は虚を突かれたような表情をしていたにちがいない。
「難しいでしょうか? 1年間だけでよいのですが……」
そのような前向きな計画を、よりによって本人から提案されるとさすがに断りにくい。結局、私はその提案を受け容れた。
場をリビングルームに移すと、彼の妻はソファから立ち上がって、笑顔で私たちを迎えた。彼女はすらりとした美しい中年女性だった。艶やかなワンレングスの黒髪と、スキニーパンツに包まれた長く細い脚は、上品さと華やかさの双方を体現していた。
彼は私とのあいだで合意された「治療計画」について報告した。
「それはとてもよい計画だわ」
妻は安堵した表情を見せたが、すぐに私の方に不安げな顔を向けた。
「でも、これから何回も来ていただくの、ご迷惑ではないでしょうか?」
問題ない、と私は答えた。というか、とても拒めるような状況ではなかった。
以降、月に1回、仕事帰りの夜遅い時間に彼の邸宅に立ち寄った。不思議な往診だった。そもそも、それは診察と呼べるような代物ではなかった。毎回、彼はいかめしいデロンギのコーヒーマシンを使ってエスプレッソを淹れてくれ、私たちは、デミタスカップとソーサーを片手に、最近の社会情勢についてとりとめのない話をするのだ。薬物の話はまったくといってよいほど話題にのぼらなかった。彼の方からその話を切り出すことはなかったし、私もあえては尋ねなかった。
やがて話が一段落すると、彼はトイレに行き、尿の入った紙コップを持って書斎に戻ってくる。そして、紙コップを受けとった私は、スポイトで尿を採取し、簡易検査キットに一滴垂らすわけだ。一緒に結果を確認したら、それで診察終了だった。
簡易薬物検査キットは私が箱ごと彼の自宅に持ち込んだ。箱のなかには25回分の検査キットが入っていた。以前、研究用に大量購入したものの、品質保証期限が迫ってしまい、廃棄処分目前のものが多数余っていたので、それを活用することにしたのだ。
薬物検査は1年間ずっと陰性だった。毎回、結果が出るたびに、必ず彼は、「ほら、今回も大丈夫だよ」と妻に示していた。
いざはじめてみると、時の流れは速かった。約束通り1年を経過したところで、この不思議な往診は終了となった。
その当時、私は、薬物依存症治療プログラムの開発に注力していた。いや、「開発」というのはいささかおこがましいかもしれない。というのも、実際にやっていたことといえば、勤務先の施設で、使われなくなった古い建物の一角を使って、薬物依存症患者数名とともにテーブルを囲み、グループ療法を実施していただけだったからだ。
実に和やかな雰囲気だった。参加者の前には手製のワークブックが開かれ、それぞれコーヒーや菓子を交互に口に運びながら、ワークブックを朗読し、自分の意見を発言するのだ。窓の外では、解体作業を行う重機の音が鳴り響き、ともすれば進行役の私の声はかき消されがちであったが、それでもめげずにプログラムを進めた。
患者の一人はうなだれていった。
「ずっとクスリをやめてたんですけど、ふと『いまでもあの売人は活動しているのかな?』と思って、例の密売サイトを覗いてみたんですよ。まあ、ちょっとパトロールしてみよう……みたいな気持ちで。でも、実際にサイトを見たらスイッチが入ってしまって、もう抵抗できなかったんです。たまたま給料日直後で、手もとにお金があったのがまずかった。それで、売人にコンタクトをとってみたら、すぐにモノが届いて……」
購入した分は全部身体に入れてしまいましたか? そう私は訊いた。
「いえ、半分くらい入れちゃって、でも、これはまずいと思って、残り半分はトイレに流しました」
すると、別の患者がいった。
「すごいじゃん。俺には真似できないよ」
その言葉にうなずきながら私はいった。確かにすごいですね。ふつうだったらそのまま部屋にこもって使い続けるところなのに、残りを捨て、今日、こうやってこのプログラムに来たわけですから。
さらに別の患者も声をかけた。
「そうそう、まずは来ることが大事だよ。考えてみると、俺も最初の頃は毎週クスリを使いながらこのグループに参加していたよ。大丈夫、使いながらでも諦めずに参加していれば、自然とクスリを使わない日が増えていくから。いま大事なのは、とにかく逮捕されないことだよ」
これは、後にSMARPP(Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program)と呼ばれることになる、依存症治療プログラム立ち上げ黎明期の一幕だ。このSMARPPは、その後、国内各地の精神科医療機関や精神保健福祉センターに広まり、2016年からは診療報酬算定項目に追加されて、わが国における、最初にして、現時点では唯一の公式な薬物依存症治療法として認められることとなった。
SMARPPとは何か、と質問されれば、教科書的には、「認知行動療法的な考えを援用し、グループ療法として提供される、薬物再乱用防止スキルトレーニング」ということになろう。
しかし、これはあくまでも表面的な回答だ。告白すれば、私は決して認知行動療法の専門家ではないし、その信奉者でもない。叱責や批判を覚悟でいうと、そもそも敬意すらさほど抱いていない。というのも、自身の経験から、SMARPPを通じて回復した患者の大半が、その後の生活においてプログラムで習得した対処スキルを使っていない、というのを実感しているからだ。
SMARPPの開発にあたって私が重視したのは、入院ではなく通院による治療であり、それから、「安心して失敗を語れる場」を作って治療からの離脱を防ぐことだった。実際、依存症治療で最も重要なのは、短期的な断薬ではなく、薬物を使いながらでも治療から離脱しないことなのだ。したがって、治療の場は、「クスリをやりたい」「やってしまった」「やめられない」――そういっても、誰も悲しげな顔をせず、誰も不機嫌にならない、そして、自身に不利益が絶対に起きない、安心・安全な場所でなければならない。
もしもこの私に、多少ともわが国の精神医学への貢献があるとすれば、それは、「安心して悪い知らせを話せる治療環境」「安心して『シャブ』を使いながら通院できる依存症治療」を定式化し、診療報酬という医療保険の枠組みに乗せたことだろう。
とはいえ、自身の所属施設で薬物依存症専門外来を立ち上げ、SMARPPの試行へと漕ぎ着けるのは、容易なことではなかった。2年近い期間をかけて所属施設の幹部を説得し、現場の医師や看護師の理解を求める作業が必要だったからだ。最終的に何とか幹部の理解を得たものの、私に与えられた場所は、取り壊し目前の、幽霊屋敷のような建物の一角だった。
ちなみに私は、専門外来受診やSMARPP参加にあたって、患者に「強固な断薬の決意」や「鋼のように強い治療意欲」を求めなかった。「覚醒剤をやめるかどうかはまだ決めかねているが、逮捕はされたくない」といった程度でも、患者自身が参加を希望すれば、快く受け容れた。
そこには、私なりの思いがあった。
わが国の薬物依存症分野は、比較的最近まで――少なくとも2000年代前半まで――前時代的な医療を提供していた。一般の精神科病院であれば、まちがいなく糾弾の対象となるような人権侵害的な治療、あるいは、刑務所さながらの収容主義が、なぜか薬物依存症専門病院にだけは許されてきたのだ。
その証拠となるのが、医学書院の定期刊行専門誌『精神医学』2001年5月号特別企画「薬物依存者に対する精神保健・精神科医療体制」だ。この特別企画で掲載されたいくつかの論文が堂々と掲載され、しかも刊行後もまったく批判に曝されていない、という事実だ。
その特別企画では、印象的なキャッチコピーを用いて、わが国の薬物依存症入院治療を3つのモデル――「病棟に鍵をかける」「脳に鍵をかける」「心に鍵をかける」――に類型化している。
1つ目の「病棟に鍵をかける」というのは、文字通り閉鎖病棟という物理的障壁を用いて薬物渇望に対峙する治療法だった。その治療モデルの提唱者は、特集記事のなかで次のような趣旨の説明をしている。曰く、覚醒剤依存症患者は、最終使用から2~3週間という時期に「渇望期」を体験する。この時期、患者は医療スタッフに当たり散らしたり、入院生活の不平不満を訴えて強硬に退院を要求したり、あるいは、唐突にやんごとなき重大な急用を思い出し、早急な退院の必要性を切々と、ときには涙ながら訴えてきたりする。いずれも渇望が引き起こす行動であり、その段階で退院させると、患者はまちがいなく覚醒剤を使用する。だから、たとえ患者が幻覚や妄想を呈しておらず、十分な判断力があるように見えても、最低1カ月は閉鎖病棟内にとどめ置かなければいけない……。
2つ目の「脳に鍵をかける」は、閉鎖病棟への強制入院に加えて、大量の抗精神病薬を用いて脳を化学的に拘束する治療法だった。特集記事ではこう説明されている。曰く、覚醒剤断薬後から1~3年は、周期的に精神的不安定な状態をくりかえし、自傷行為や過食、あるいは粗暴行為におよぶ傾向がある。それらはいずれも、薬物によってダメージを受けた脳が引き起こす「遷延性退薬徴候」であり、これを抑えるためには、きわめて長期間の強制入院と、大量の抗精神病薬――記事で紹介されていた投与量は、非常識なほど大量だった――による脳の鎮静が必要なのだ……。
最後の「心に鍵をかける」は、精神科医にして作家のなだいなだ(本名:堀内秀)が久里浜医療センターで立ち上げた、アルコール依存症治療プログラム「久里浜方式」を、そのまま薬物依存症治療に適用したものだ。つまり、開放病棟への自発的入院を原則とし、病棟運営は患者自治会に委ねるなど、患者の主体性を重視している。患者の人権擁護の観点からは最も好ましいやり方だが、家族からは、「家族の人権をないがしろにしている」と不評を買いやすい面もある。というのも、家族がどんなに求めても、本人が拒めば入院させないし、首尾よく入院となっても、本人が翻意すれば、治療中途で退院となるからだ。
ただ、弁護させてもらえば、まったくの無策で患者の好き放題を許容しているのではない。まず、あくまでも患者の主体性を尊重することで、退院後の通院継続率を高める意図がある(強制入院をさせられた病院になど、誰だって通院したくはないだろう)。
それから、この治療モデルでは、依存症民間回復施設「ダルク」の職員や、薬物依存症の自助グループ「ナルコティクス・アノニマス(Narcotics Anonymous: NA)」のメンバーといった、依存症からの回復者を病棟に招き、患者と交流するようお願いしている。これは、退院後に患者がダルクや自助グループにつながることを期待してのことだ。要するに、「心に鍵をかける」というのは、「先行く仲間」との心理的なつながりによって、渇望と闘う治療モデルだった。
今日の精神科医療における人権擁護の感覚でいえば、前二者の治療モデル――「病棟に鍵をかける」と「脳に鍵をかける」――は問答無用でアウトだ。しかし、四半世紀前はそうではなく、主流は前二者であって、「心に鍵をかける」は完全に亜流であった。
私は、この亜流とされる治療モデルの専門病院で薬物依存症臨床を学んだ。そのせいで、駆け出しの頃、依存症関係の学会では、物理的/化学的拘束モデルを採用する病院に勤務する医療者から多くの嫌味や批判に曝されたものだった。たとえば、「あの治療法をやっている病院は、本気で治す気がないか、軽症例しか診ないってことだ」「やめる気がある奴だけ入院させて、翻意したらすぐに退院させるとか、正気の沙汰ではない。自分の意志で薬物をやめられないからこその入院なのに、患者に入退院の決定を委ねるなんて、医師としての役割を放棄している」……などなど。学会などでこき下ろされるたびに、悔しい思いをしたものだ。
しかし、前述した人権侵害的な入院治療も、「渇望との闘い」という大義名分がある分、通院治療よりはまだましだった。通院治療に至っては、もはやそのような大義名分すらなく、完全に捜査機関の下請け仕事のような様相を呈していた。
当時、薬物依存症の標準的通院治療として提唱されていたのが、「条件契約療法」なる方法だった。具体的には、外来受診のたびに尿検査をし、「覚醒剤反応が陽性だった場合には、その結果を持って警察に自首する」という契約下で行われる治療法だった。
おかしな理屈だった。すでに当時の時点で、「薬物依存症は脳の病気。だから治療が必要」という趣旨の啓発が行われていた。そして、いうまでもなく、その病気の中核症状は、「わかっちゃいるけどクスリを使ってしまう」であった。本来、病気の症状が悪化したならば、医療がすべきことはただ一つ、より強力な治療を提供することだ。実際、前述の通り、入院治療においては、渇望を「自分の意志では制御困難」と捉えて強制入院の根拠としたはずだ。ところが、条件契約療法はそうではなかった。逆に、患者を治療から放り出し、警察へと突き出すのだ。
完全なる二枚舌だった。当然ながら、覚醒剤を再使用した患者に残された選択肢は次の2つしかない。つまり、通院治療を諦めるか、あるいは、通院先を変えるか、だ。実際、当時、条件契約療法を採用する病院に通っている患者が、突然、紹介状もなしに私が勤務する病院に受診してくることがあった。患者は、「再使用してしまった。次に受診したら自首しなければならなくなる。しかし、自分としてはまだ治療を続けたい」と語った。
おかしかったのは薬物依存症専門医だけではなかった可能性もある。というのも、当時、精神科関係の学会で薬物依存症治療が話題にのぼると、きまって会場は異様な熱気を帯び、「尿」の話で持ちきりとなったからだ。事情を知らない部外者ならば、その場を泌尿器科の学会と勘違いしたにちがいない。要するに、尿検査で覚醒剤反応陽性となった場合、医師は警察通報すべきか否か、という議論が紛糾していたのだ。あまりにも愚かな議論だった。わが国において医師の守秘義務を定めているのは、医師法という業法なんかではなく、刑法という重い法律であり、それはヒポクラテスの誓い以来、一貫して医師のレーゾン・デートルであったはずだ。一体、何をいまさら議論しているのか……。私は憤怒を超えて、ただ、呆れるしかなかった。
かくて薬物依存症臨床にはあまりにも多くの理不尽がまかり通っていた。私は十指に余る疑問を抱きながらも、しかし、そうした流れに大声でノーを突きつけることができなかった。なぜなら、諸先輩たちは野武士のように威風堂々として強面揃いだったからだ。実際、武闘派の精神科医も少なくなかった。「あの先生は、昔、総合格闘技をやっていた」とか、「ヤクザ者の患者もあの先生の前では借りてきた猫のように大人しい」といった、精神科医としての力量とは別次元の武勇伝をよく耳にしたものだった。
SMARPP開発に着手してから20年近くが経過し、いまや私の所属施設は国内有数の薬物依存症専門医療機関となった。
薬物依存症臨床に長く従事するなかでわかったことがある。先人たちは極端な視野狭窄に陥っていて、薬物依存症患者が呈するさまざまな症状をあまりにも薬物と関連づけすぎた、ということだ。たとえば、物理的拘束を要するとされた渇望の半分は、強制収容という異常事態に対する拘禁反応であり、残り半分は覚醒剤使用中止によるADHD(注意欠如・多動症)症状の悪化――おそらくその患者は、無意識のうちに覚醒剤をADHD治療薬として用いてきたのだろう――だった。それから、化学的拘束を要するとされた遷延性退薬兆候とは、薬物使用以前から存在する精神障害の症状悪化、なかでも、過去のトラウマに起因するPTSD(心的外傷後ストレス症)の症状再燃であることが多かった。いずれにしても、閉鎖病棟や薬物療法で解決する問題ではないばかりか、場合によってはそれらがかえって事態を悪化させることだってあるのだ。
これまで縁あってさまざまな著名人を診察してきた。いずれも、違法薬物の使用や所持による逮捕がきっかけだった。もちろん、そんな実績は名誉でも何でもない。単に他に引き受けてくれる物好きな医師がいないがために、泣く泣く私に依頼してきた、というのが実情だったろう。
なかには、重篤な依存症に罹患していて、明らかに刑罰よりも治療が必要という人もいたが、その一方で、長年、節度をもって薬物を使用し、心身は健康そのもの、単に周囲を納得させるための「禊」として、形式的に治療を受ける人もいた。病気なのに監獄行きというのもどうかと思うが、他方で、病気でもないのに病院で治療を受ける、というのも妙な話だ。
ただ、いずれの著名人たちも、逮捕直後の激しいバッシング報道に打ちのめされ、一時は真剣に自殺を考えるほど追い詰められていた。皮肉な話だ。「被害者なき行為」である薬物使用を法と刑罰によって規制したのは、「人類の健康及び福祉に思いをいたし」(「麻薬に関する単一条約」前文、1961年)のはずだったのに、いまや規制法が人の健康と福祉を蹂躙している。
それだけではない。社会はその著名人を生け贄にして、一連の逮捕劇をエンターテインメントとして消費するのだ。そして、その裏で捜査機関は巧妙に自らのプレゼンスを誇示し、メディアはメディアで、えげつなく視聴率や雑誌売り上げ部数を稼いでいる。
実際、著名人が逮捕されるたびに、世の中はお祭り騒ぎとなる。以前、一度だけ私は、ある著名人の情状証人として法廷に立ったことがある。その際、傍聴席のすさまじい混雑もさることながら、何より驚いたのは、著名人の発言を逐一報道すべく、公判中、何人もの記者がめまぐるしく法廷を出入りしていたことだ。裁判終了後は、詰めかけた報道陣に通常の出入り口が塞がれ、やむなく裁判所職員の案内で、秘密の地下通路を使って脱出しなければならなかった。
警察やマトリ(麻薬取締官)のような捜査機関関係者ですら油断できなかった。彼らは自分たちが逮捕した著名人に対して私のもとに受診するように勧めた後、私が内々に決定した診察日を著名人の家族から聞き出し、その情報をマスコミにリークしている疑いがあった。事実、診察終了後、人目を避けて著名人を病院の非常用通用口から出るように誘導すると、なぜか出口に記者たちが待機していて、いっせいにフラッシュが焚かれたことがあったのだ。ちなみに、そうした場合、週刊誌の記事に使われるのは、決まって不本意な表情――眉をひそめて上目遣いにした瞬間、あるいは、半目閉じの瞬間を捉えた顔――の写真だった。
このようにして収集された情報が、キャンプファイアーにくべられる焚き木のように、ワイドショー番組に供され、騒ぎを炎上させる。そして、司会者やコメンテーターは善人面をして逮捕された著名人を非難し、罵倒して、その炎をいっそう煽る。実に不快きわまりない光景だ。
薬物依存症臨床に30年近く従事してきて、確信していることがある。「ダメ。ゼッタイ。」啓発では、「薬物を1回でもやったら人生破滅」というメッセージが連呼されるが、この破滅は薬理作用によってもたらされるのではない。社会の「村八分」によるものだ。つまり、恐ろしいのは薬物ではなく、社会の方なのだ。健康被害ならば医療にもできることはあるが、社会的排除に対しては、どうあがいても医療は無力だ。
隠密往診の終了から1年後、突如として彼は逮捕された。当然ながら、新聞や週刊誌でもそこそこ大きく扱われ、ワイドショー番組でもとりあげられた。
なかでもクローズアップされたのは、家宅捜索により簡易薬物検査キットが押収されたことだった。週刊誌には、「1箱25個入りの検査キットであるはずが、13個しか残っていなかった。すでに12個の検査キットが何らかの用途で使用されたと見られている」と書かれていた。
ワイドショー番組では、元マトリ捜査官の解説者が神妙そうな顔つきでこう語っていた。
「おそらく自分で薬物反応を確認しながら、周到に逮捕されるリスクを避けてきたのでしょう。これは相当に熟練した常用者の行動で、きわめて悪質です」
何も知らないくせに……。テレビを眺めながら、私は何ともやるせない気持ちになった。12個なくなっているのは、月1回の往診を1年間やったからだ。
数日後、著名人の妻から一通のメールが届いた。
「連日、自宅に報道陣が詰めかけてきて、インターフォンを無視していると、ガレージのシャッターをすごい勢いで叩いてきます。昼夜を問わずです。もう怖くて、とても生活できる状況ではありません。ですから、おとといからずっと都内のホテルを転々と逃げ回っています」
そう近況を報告した後、末尾にこう書かれてあった。
「今後の夫の治療について相談させていただけないでしょうか?」
翌日夜半、私は指定されたホテルに出向き、あらかじめ伝えられていた番号の客室をノックした。部屋は雑然としていた。大きなスーツケースは開かれたままで、床には衣類やタオル類が散乱している。彼女はスウェットスーツという出で立ちで、髪は乱れ、化粧っ気のない顔には疲れがにじみ、別人のように老け込んで見えた。本当に「着の身着のまま」逃げ出したのだろう。
彼女は、いざ私を呼びつけたものの、何から話せばよいのかわからず、混乱している様子だった。やがて意を決し、「先生……」といいかけたが、そこで力尽きて言葉を飲んだ。しばしの重苦しい沈黙の後、彼女はひとり言のようにこう呟いた。
「薬物って、家族がこんな目に遭わなければいけないほど、悪いことなんでしょうか?」
逮捕以降、あの著名人の動向はまったくわからない。少なくともメディアでその姿を見ることはなくなった。風の噂によれば、一度、依存症啓発イベントに登壇してもらおうと、広告代理店が内々にコンタクトをとったそうだが、いくら待っても返事はなかったという。
いまでも鮮明な記憶として残っていることがある。往診最終日のことだ。いつもならば彼の妻が私のためにタクシーを呼ぶところを、その日に限って彼がそれを制し、自分が運転して送り届けると申し出たのだった。彼なりに謝意を示そうとしたのかもしれない。
そんなわけで私は、ガレージで鮫のように低く身構える、あの赤い車に乗ることになったのだ。車のなかで私たち二人は終始無言であり、ともに眼前に広がる濃密な漆黒をただ凝視していた。そのとき闇を切り裂いていた、12気筒の甲高い咆哮は、いまだに耳の奥で残響している。
編集部注:本連載では、登場人物の匿名性を保つため、プロフィールの細部に変更を加えています。