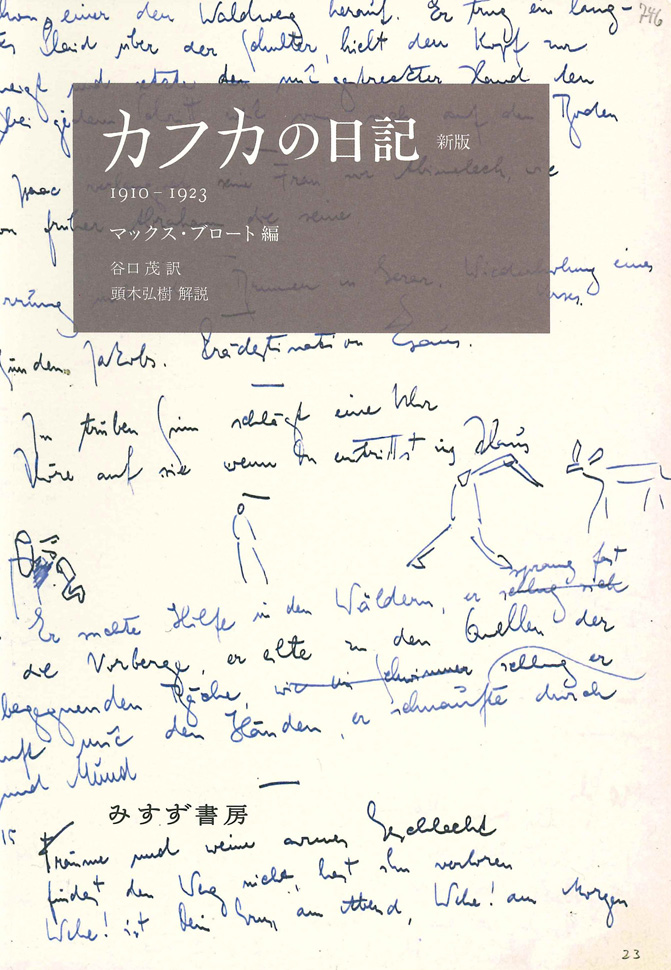この連載では、フランツ・カフカの小説『変身』を新訳しながら、超スローリーディングしていく(ものすごくゆっくり読む)。
さらに、読みながら私が思い出したこと考えたことも、脱線を気にせずに、どんどん書いていく。というのも、読書の半分は、本に書いてあることではなく、本を読みながら自分の内にわきあがってきたことにあると思うからだ。
私の脱線につられて、みなさんもそれぞれに、いろんなことを思い出したり考えたりしていただけたら幸いだ。自分の城の中にある、自分でもまだ知らない広間。
それを開く鍵のような働きが、多くの本にはある。(オスカー・ポラックへの手紙 1903年11月9日)
●前回まで
居間でヴァイオリンを弾き始めた妹。両親も、間借人たち3人も、みんな居間にいる。
その居間に、グレーゴルは這い出てしまう。妹の演奏に惹きつけられたからだ。
間借人たちはすぐに妹の演奏にうんざりしてしまう。しかし、こんな素晴らしい演奏になぜ感動しないのか、グレーゴルには理解できない。こんなに感動している自分は、それでも虫なのか。
グレーゴルは妹のところまで突き進んでいって、スカートのすそを引っぱり、自分の部屋に呼ぶつもりだ。演奏しがいのある相手は、ここでは自分だけなのだから。
そして、もう妹を部屋から出さないつもりだ。もちろん、妹が自主的にそうしてくれるのでなければならない。妹を音楽学校に行かせるつもりだったという話をすれば、妹は感激してくれるだろう。わっと泣き出すかもしれない。そうしたら、首にキスをしてやろう。
そんなふうに思いをふくらませながら、グレーゴルは居間の床を進んでいくのだった。
●首にキスの件
前回の最後に、私はこう書いた。
妹が「家にいたときには首を隠していて、働きに出るようになると、首にリボンも巻かず、襟のついた服も着ないというのは、どういうことなのか、私にはよくわからない。意味のわかる人がいたら、ぜひ教えてほしい」
このことについて、『どんな日もエレガンス』(大和書房)などの著作のある、ベルサイユ在住のドメストル美紀さんから、このようなご連絡をいただいた。「リボンですが、フランスでは、昔の服は、レースの襟など取り外し式で、ネックレスなどより高価だったと聞いています。なので、困窮していることを意味しているのかな、と思いました」
これには、なるほどと思った。レースの襟などがネックレスよりも高価だったとは、まったく知らなかった。フランスのことではあるが、プラハでも同様だったかもしれない。
そして、妹が「リボンも巻かず、襟のついた服も着なくなっていたので、むき出しになっている首」というのが“困窮”を意味するとしたら、グレーゴルがそこにキスをするというのも納得がいく。
じつは、このシーンに関しては、性的な解釈があることは知っていた。首をむき出しにしているのは、男性客をひきつけるためとか、妹がもう少女ではなく大人の女になったことを表しているとか、グレーゴルがそこにキスをすることに関しても……。
しかし、性的な解釈をすれば、何か裏側の真実を見抜いたような気になるのは、前にも書いたように(第18回)、フロイト以降のよくない偏りだと思うので、あえて紹介しなかった。それのみを紹介すると、どうしてもその印象を拭えなくなるので。
こうした別の解釈もありそうなことがわかったので、安心して紹介しておく。
自分だけではわからないことを途中で教えてもらえるのが、連載のありがたいところだと、あらためて思った。
●グレーゴル、見つかる!
「ザムザさん!」と3人の間借人の真ん中の男が父親に向かって叫び、それ以上は何も言わず、ひとさし指で、のろのろと前進してくるグレーゴルを指さした。ヴァイオリンの音がやんだ。真ん中の間借人は左右の仲間と顔を見合わせてにやりと笑い、それからまたグレーゴルのほうを見た。父親はグレーゴルを追い払うよりも、まず間借人たちを落ち着かせるほうが先決だと思ったらしい。ところが、間借人たちはまったく取り乱してなどいなかったし、むしろヴァイオリンの演奏よりもグレーゴルのほうが彼らを面白がらせているようだった。父親は3人のところにとんでいき、両腕を広げて、彼らを自分たちの部屋に押し戻そうとし、同時に自分の身体で視界をさえぎって、グレーゴルの姿を見られないようにした。すると3人は本当に少し怒り出した。父親の態度のせいなのか、それとも、グレーゴルのような同居人がいることを知らずにいたのだと、今ようやく心づいたからなのか、それはわからなかった。3人は父親に説明を求め、自分たちも腕をふりあげ、落ち着かない様子で髭を引っぱり、ひどくゆっくり部屋に退いていった。
部屋に這い出してきたグレーゴルを、間借人が最初に見つけてしまう。妹は楽譜を見つめているし、両親は妹や間借人を気にしているし、見つけるとしたら、退屈している間借人たちということになってしまう。
「妹のところまで突き進んでいって、スカートのすそを引っぱろうと」と決心したグレーゴルなのに(前回)、「のろのろ」と前進していたのは、林檎が身体にめりこんだままで、もはやのろのろとしか動けなくなっているからだ。「傷のせいで、思うように身体を動かせなくなっていた。おそらくこの先もずっと。今は部屋を横切るだけでも、年老いた傷痍軍人のようにずいぶん時間がかかった」と前に書いてあった(第20回)。しかも、このところずっと何も食べていない。
ヴァイオリンの音がやむ。高尚な時間は終わりだ。間借人たちはにやりと笑う。本来なら、自分たちの住んでいる住居に大きな虫が現れたのだから、ぎょっとしたり、嫌悪感をもよおしたり、怒ったりするところだ。しかし、取り乱すことさえなく、落ち着いて、にやりと笑い合っている。これは父親たちとの権力闘争の最中であったからだろう。相手の落ち度を見つけた喜びのほうが、巨大な虫を見つけた衝撃より勝ったわけだ。
たとえば、会社で出世争いをしているときに、相手が巨額の損失を出せば、つい喜んでしまう。会社が危うくなれば元も子もないのに。権力闘争には、目先の勝利だけに気持ちを集中させるところがある。他のことには動じなくなるほどに。まるで大物のような落ち着きと微笑み。
父親のほうも、まず間借人たちを気にする。その様子はますます間借人たちを喜ばせただろう。彼らにとってはこれで、この権力闘争は簡単に勝てる勝負となったのだから。あとは相手のあわてぶりを楽しんで、もてあそぶだけだ。もはや闘争ではなく、面白い見世物だ。
もしここで父親がまずグレーゴルのほうに駆け寄り、そちらばかり気にしていたとしたら、間借人たちは気分を害し、笑いは怒りに転じていただろう。
間借人たちが少し怒り出すのは、部屋に押し戻されそうになってからだ。もう見世物は終わりとばかり、虫を隠され、居間から追い出されそうになる。
しかし、父親は歳をとっているし、なんといってもひとりだ。3対1なら、押し返せないはずはない。それでも、ひどくゆっくりとはいえ、部屋に退いていくのは、間借人たちのほうにも、退きたい気持ちがあるからだろう。
他人の秘密が漏れ出たとき、これはしめたと面白がって、さらに引っぱり出そうとする人は多い。しかし、下手に引っぱり出さないほうがいいほどの秘密かもしれないと気づいたときには、今度はしまったとなって、なんのかんのと文句を言いながらも、退いていくものだ。恐ろしい秘密は、隠していた者だけでなく、知った者にまで影響を及ぼしかねないから。
「3人は父親に説明を求め、自分たちも腕をふりあげ」というのは、ただおとなしく部屋にひっこんだのでは、かっこうがつかないからであり、実際には「落ち着かない様子で髭を引っぱり」という不安を感じさせる動作のほうが本音だろう。だから、速くなりすぎないよう、ひどくゆっくり、でもたったひとりの父親に押されて退いていく。
●いつもどおりの仕事をこなす妹
演奏を突然中断させられた妹は、茫然として、一方の手にヴァイオリン、もう一方の手に弓を持ったまま、両手をだらりと下げて、まだ演奏を続けているかのようにしばらく楽譜をながめていたが、こうした騒ぎのあいだに気をとり直し、急に動き出した。椅子に座ったまま呼吸困難におちいってぜいぜい喉を鳴らしている母親のひざの上に楽器を置き、間借人たちの部屋にとびこんだ。3人の間借人たちは、父親に押しまくられて、さっきよりも足を速めて部屋に近づいていた。枕や毛布が宙を舞い、妹は慣れた手つきで、みるみるベッドを整えていった。3人が部屋に入ってくるより前に、妹はベッドを整え終えて、するりと脱け出した。
突然のことに、妹は放心状態になる。演奏はやめて、両手はだらりと下げているが、まだ目は楽譜をながめている。思いがけないことが起きると、人はその前にやっていたことをなんとなく続けてしまうものだ。心にも慣性の法則のようなものがある。
母親はショックで呼吸困難におちいっている。母親には喘息の持病があると以前に書いてあった(第15回)。そんな母親のひざの上に妹がヴァイオリンを置くのはなぜなのか。しっかりしてということなのか。今は介抱していられないという意味なのか。
放心状態だった妹が、はっと気をとり直し、動き始めるのは、間借人たちが部屋に押し戻されそうになったからだろう。妹は素速く部屋に入り込み、たちまちベッドメイキングをして、またするりと脱け出す。慣れていなければこうはいかない。いつも妹がベッドメイキングをしていたということだ。兄の世話も妹がしていたが、間借人の部屋を整えるのも妹がもっぱら担当していたのだろう。
さっきまで放心状態だったのに素速く動けたのは、いつもの慣れた動作だったからだ。いつもやっていることは、心がここにあらずの状態でも、こなせるものだ。これも心の慣性の法則のひとつだろう。
いつもどおりのことをちゃんとこなしているから、大丈夫なのだろうと、周囲は思ってしまいがちだが、それはまったくちがうこともある。心はこわれかけているということもある。
●完璧な、部屋への入り方
父親はまたしても意固地になってしまったようで、間借人たちに対する最低限の敬意まで失っていた。ただもう押して押しまくっていたが、ついに部屋のドアのところまで来たとき、真ん中の男がドシンと足を踏み鳴らしたので、やっと立ち止まった。「私はここに宣言します」と真ん中の男は言い、片手を挙げて、母親と娘を目で探した。「この住居と家族を覆っている唾棄すべき状況からして」──ここで男は、ためらいもせず、床にペッと唾を吐いた──「ただちに部屋を解約します。もちろん、これまでの分の部屋代もいっさい払いません。一方で、こちらからなんらかの損害賠償を請求するかどうかは──脅しではありませんよ──れっきとした根拠があるのですから、これからじっくり考えさせてもらいます」彼は口をつぐみ、何かを待ちうけるかのようにまっすぐ前を見つめた。はたして2人の仲間がすぐに口をそろえた。「われわれもただちに解約します」それから真ん中の男は、ドアのノブをつかみ、バタンと音を立ててドアを閉めた。
気にしすぎるほどに間借人たちの機嫌を気にしていたはずなのに、今も間借人たちを落ち着かせることが目的であったはずなのに、間借人たちを力ずくで押しているうちに父親は意固地になってしまう。ただもう押して押しまくってしまう。手段は簡単に目的化してしまいがちだ。力まかせなことはとくに。力が通用すれば、さらに力を込めてしまう。
それを間借人たちも感じる。このまま部屋に押しこまれたのでは、せっかくの権力闘争の勝利も、曖昧になってしまう。主導権はこちらにあるという、断固たるところを示さなければならない。真ん中の男がドシンと足を踏み鳴らす。父親はそれで止まらなければならないのだ。
実際、父親は止まる。
そして、真ん中の男が宣言する。ここで男は床に唾を吐く。ちなみに、私が「ためらいもせず」と訳した箇所(kurz entschlossen)は、既訳では「とっさに決心して」という感じに訳してあったり、訳出していなかったりする場合が多いが、「ためらわずに」という意味を載せている辞書もあり、私はそれがふさわしいように思った。床に唾を吐くというのは、もちろんひどい行為だが、そこにためらいがないほうが、よけいに衝撃がある。真ん中の男は、ためらいのなさを見せつけたのではないだろうか。
真ん中の男は、部屋を解約し、部屋代を払わないし、さらに損害賠償を請求するかどうかこれから考えると宣言して、それから部屋に入って、ドアを閉める。これなら部屋に戻っても、かっこうがつく。力ずくで部屋に押し戻されたのではない。自分から部屋に入ってドアを閉めたのだ。不安で部屋に逃げ込んだのでもない。部屋に入ってドアを閉めることで、もう交渉もしないし、こちらがすべて一方的に決めることができるのだと示したのだ。今起きたことから自分たちが追い払われたのではなく、逆に、部屋の外にいる者たちとの関係を自分たちが断ったのだ。さらに、自分たちが部屋の中でどんな決断をするのか、部屋の外にいる者たちに気にさせ、不安におとしいれることもできる。権力闘争としては完璧な、部屋への入り方と言えるだろう。実際には、かなり不安にかられ、いったん部屋に逃げ込みたかったとしても。
間借人の他の2人は、真ん中の男にすぐに同調する。真ん中の男もそれを確信している。この3人の関係が気になるかもしれないし、これならひとりでも同じではないかと思うかもしれないが、前にも書いたように(第22回)、彼らは3人で1組なのだ。
●父親の手さぐり
父親はよろめきながら手さぐりで安楽椅子までたどりつき、どさりと腰を下ろした。手足をだらりと伸ばし、いつものように晩の居眠りを始めそうにも見えたが、頭がぐらぐらと激しく揺れていて、まったく眠っていないのはあきらかだった。グレーゴルはこうした騒ぎのあいだずっと、間借人たちに見つかった場所でそのままじっとしていた。失望していた。自分が思い描いていたようにはならなかった。いや、動けないのは、ずっと何も食べていなくて身体が衰弱しているせいもあったかもしれない。彼は恐れていた。確信のようなものがあったのだ。次の瞬間にはすべてが崩壊して自分に降りかかってくるだろうと。彼はそれを待っていた。手を震わせている母親のひざからヴァイオリンがすべり落ち、床にぶつかって大きな音を立てたときも、彼は少しも驚かなかった。
間借人たちのねらいどおり、父親はショックを受ける。押して押しまくっているあいだは、それで一生懸命だっただろうが、今、立ち尽くしてみると、何が起きてしまったのか、あらためて受けとめなければならない。ずっと隠してきたもの、隠しとおしていきたかったもの、隠しとおせるかどうか不安だったものが、ついに隠しきれなかったのだ。やっぱりという思いもあるだろう、なぜという思いもあるだろう、こうなるはずではなかったという思いもあるだろう。
受けとめきれず、父親はよろめく。さっきまでは力強く3人を押していたのに、今は自分の身体だけを支えることも難しい。自分の安楽椅子、使い慣れた、いつも安らぎを与えてくれるものに、倒れ込むようにして抱きかかえてもらう。
このとき、父親は「手さぐり」で動いている。よろめいているのだから当然でもあるが、「何かにつかまりながら」ではなくて「手さぐり」というのは、目が見えない状態を連想させる。希望が絶たれたときなどに「目の前が真っ暗になる」という言い方をしたりするが、そういうふうなことが父親にも起きているのかもしれない。
ここでまたハロルド・ピンターの作品が思い出される。今度は『ティー・パーティ』という短編小説だ。前回紹介した『かすかな痛み』でも、じつは視力の喪失というモチーフが使われているのだが、こちらではそれがさらに中心になっている。視力の衰えが、今までの自分、自分の立場、居場所を失うことと連動して起きる。短編小説の最後のところを少し引用してみよう。──あらすじを紹介してもあまり意味がないタイプの短編だが(全体が詩的で、明確なストーリーはないので)、いちおう簡単に書いておくと、語り手には妻とふたごの息子がいる。家族の仲はいい。語り手は視力の衰えを感じているが、主治医は目に問題はないと言う。語り手の妻はこの主治医のところで看護師をしているようだ。妻の兄を誘って共同経営者にした。会社の秘書のウェンディは仕事ができて信頼できる。語り手はウェンディに性的な欲望を感じている。しかし、義兄(共同経営者)がウェンディと関係しているのではないかと疑っている。義兄と卓球の勝負をするとき、いつも語り手が勝って、義兄がうろたえていたのだが、最近は目が見えなくなってきたせいで、うろたえるのは語り手のほうだった。
ドアがばたんと閉った。私はどこにいたのか。会社か、それとも家か。共同経営者が出て行った時に、誰かが入って来たのか。共同経営者は出て行ったのか。私の耳に聞えたのは沈黙だったのか、このざわめきやきしみや叫びやこする音やこもった音やおさえた音は。茶が注がれていた。肉づきのいい太股が(ウェンディのか? 妻のか? 両方か? 別々にか? 一緒にか?)こわばってふるえた。私はその液体を飲んだ。有難かった。私の主治医が愛想よく話しかけて来た。君、すぐにその目隠しを外してやるよ。ケーキどうだい。私は遠慮した。小鳥たちが水を浴びてるわ、と彼の白衣の妻が言った。一同は急いで見に行った。息子たちは何かを飛ばせた。誰かをだろうか? まさか、そんなことはない。息子たちがこれほど元気でいるのを聞いたことはなかった。彼等はよくしゃべり、くすくす笑い、学校のことを叔父と熱心に話し合った。私の両親は黙っていた。その部屋は非常に小さく──私が記憶しているよりも小さく感じられた。どこに何があるかは、隅々まで分っていた。しかし、部屋のにおいは変ってしまっていた。おそらく人が入りすぎていたせいだろう。妻は結婚して間もなくの頃によくやったように、不意にどうにもならないほど笑い出してあえぎながら妙な声を出した。なぜ彼女は笑っていたのか。誰かが面白い話をしたのか。誰が? 息子たちか? そうではあるまい。息子たちは学校のことを医者夫妻と話し合っていた。君、すぐにそっちへ行くよ、と医者は私に呼びかけた。一方、共同経営者は手頃な壇の上で二人の女を半ば裸にしていた。どちらの身体の方が豊満か。私は忘れてしまっていた。私はピンポン球をとり上げた。それは堅かった。彼は女たちをどこまで裸にしただろう、と私は考えた。上半身か下半身か。それとも彼は、今や眼鏡をあげて、妻の豊満な尻と秘書の豊満な乳房とを眺めているのではないだろうか。どうしたら確かめられるだろう。動きで、ふれてみることで。しかし、それは問題外だった。それに、こういう光景が一体わが子たちの目前で展開するということがありえようか。息子たちは、今なおやっているように、私の主治医を相手にしゃべったりくすくす笑ったりし続けるだろうか。いくら何でも。だが、しっかり目隠しをし、それを堅く縛ったままでいるのはいい気持だった。
(『ハロルド・ピンター全集3』喜志哲雄訳 新潮社)
絶妙ではないだろうか。個人的な思い出話になるが、私がハロルド・ピンターに興味を持ったときには、本はすべて絶版で、しかも入手困難だった(今は復刊されている。またなくなりそうだが)。国会図書館に通ってコピーしたが、枚数に制限があったから、戯曲を優先して、短編小説は後回しにした。しかし、見開きの関係で、この『ティー・パーティ』という短編小説の最後の1ページ(上に引用した箇所)だけが含まれていた。それを読んで、なんて面白そうな! と驚いた。あわてて、全体のコピーにまた行ったものだ。
『変身』の父親は視力を失ったわけではないが、手さぐりという表現には、よろめいてしまうということと同時に、もう何が起きているのか、自分の目でしっかり見ることができない、手さぐりをするしかないという、そういう喪失感も込められているのかもしれない。
椅子に腰を下ろした父親は、目をつぶったようだ。だらりと伸びた手足は、さっきまで3人の間借人を押しまくっていた手足だ。その姿はいつもの居眠りをする様子と変わらないが、眠ってはいない。頭が激しく動いている。この動き方だが、「頭がぐらぐらと激しく揺れていて」と訳した箇所は、直訳すると「不安定な感じの頭を強くうなずかせた」となる。なので既訳でも、「支えのなくなったような頭が強くうなずいている」とか「さかんに上下させている」とか「がくんがくんさせている」のように訳されていることが多い。しかし、ここでなぜうなずくのか、よくわからない。また、がくんがくんさせていたら、むしろ居眠りしているように見えないだろうか。「まったく眠っていないのはあきらかだった」と不一致な感じがする。それで、原文では Nicken という語が使われているが、これは nicken という動詞が名詞化されたもので、nicken には「うなずく」の他に「揺れる」という意味もあるので、そちらにしておいた。しかし、正直、ここはどういう動作なのかよくわからない。衝撃を受けて悩み、頭をしっかり支えていられなくて、大きく動かしているのだろうが、それで「まったく眠っていないのはあきらかだった」とは、どんな動かし方なのか。どうも釈然としない。また頼って申し訳ないが、ここの意味がわかる方がおられたら、ぜひ教えていただきたい。
●気づいた人たち
間借人たちにグレーゴルの存在を気づかれ、父親はショックを受けている。母親も妹もだろう。
もちろん、大きな虫が家にいることに気づかれたのだから、しまったと思うのは当然だ。
しかし、あらためて考えてみると、グレーゴルの存在に気づいたのは、間借人たちが初めてではない。
グレーゴルの会社の支配人、そして2人の女中(すぐに辞めた女中と、辛抱していたが、ザムザ家の困窮によって暇を出された女中)にも、気づかれている。
もっとも、家族も、彼らと同時に気づいたのであって、どうしようもなかった。みんなでいっしょに驚いたのであって、まだ隠していたわけではない。
そして、彼らはまったくの他人ではなく、グレーゴルの関係者でもある。支配人はグレーゴルの上司であり、女中たちはグレーゴルと同じ屋根の下に住んでいた者たちである。グレーゴルの存在を世間に知られることは、彼らにとってもプラスにはならない。
家族がグレーゴルを隠し始めてから気づかれた、まったくの他人は、掃除婦と間借人たちだ。
掃除婦がグレーゴルの存在に気づいていることに、家族もきっと気づいているだろう。いや、そもそも掃除婦が気づくかどうか、家族の者たちはそれほど気にしている様子がない。掃除婦も世間の人間のひとりであり、他のいろいろな家に出入りしているのだから、あちこちで「あそこの家には大きな虫がいて……」とうわさ話をされたら、困ったことになるはずだ。しかし、ザムザ家の人たちは、そんな心配をまったくしていない。これはなぜか? 掃除婦もまた、グレーゴルのように、社会から隔絶された、見えない存在だからだろう。誰もやりたくないきつい家事だけを引き受けて回るような立場であり、うわさ話の相手にさえ、なりえないのだろう。見えない存在が何を見たって、気にする必要はないわけだ。
しかし、間借人たちに気づかれたことには、家族の者たちはこんなにも深くショックを受ける。初めての間借人だし、お金も必要だし、すごく気を遣ってはいたが、特別な人たちではない。この人たちが出て行けば、また別の間借人を見つければいいだけのことだ。
しかし、ただの一般人であるだけに、彼らは世間そのものだったのだろう。世間にグレーゴルのことを隠してやっていこうとしたのに、それができなかった。世間にバレてしまった。そのことで、この先の自信を失ってしまったのだろう。同じようなことがきっとまた起きる。ずっと隠しとおしてやっていくなんてことは、しょせんできないのではないか。
私は自分が難病であることを、長いあいだ隠して生きてきた。隠しとおしてやっていけるのではないかと思ったこともあったが、やっぱり入院になったりして、ごまかしきれずバレてしまうことがあった。それは、ひとつの仕事を失うというだけでなく、もっと大きなショックだった。
もちろん、同じ難病仲間に知られることは、なんの問題もなかった。家族が掃除婦を気にしないのは、おそらく無自覚な差別意識のためだろうが、掃除婦のほうは、この一家にそうした仲間意識を感じ始めていたのではないだろうか。
●グレーゴルは恐れつつ待つ
グレーゴルは、妹に向かって突進していたわけだが(実際にはのろのろとだが)、間借人たちに見つかった地点から動けずにいる。
動けない理由は、失望と飢餓による衰弱だ。飢餓による衰弱はもともとだが、気力でここまで進んでいたのだろう。失望してしまっては、動けなくなるのも無理はない。
妹との感動的なやりとりを思い描いていたのに、実際に起きたのは、間借人と父親のくだらない権力闘争だ。演奏は止まり、自分が決定的なことをしでかしてしまったことに気づく。
次の瞬間にはすべてが崩壊し、それが自分に降りかかってくるだろうと、グレーゴルは覚悟する。破滅の予感というのは、不思議に、かなりはっきりした確信として心の内に現れるものだ。実際にはもうずっと前から兆しはあったからだろう。こうなることは前からわかっていたのだ。それがいつなのか、はっきりしなかっただけで。すべてにヒビが入っていた。そのヒビが広がっていくのもわかっていた。しかし、見ないようにしていた。見ないでいられるあいだは。しかし、いつか最後のひと押しが……。それが今だった。
「彼は恐れていた」のに「彼はそれを待っていた」というのは、矛盾と感じるかもしれない。しかし、そんなことはない。破滅の予感は、当然、恐ろしい。逃げられるものなら、防げるものなら、そうするだろう。しかし、そうはいかない。それはわかっている。できるのは、待つことだけだ。もちろん、楽しみに待っているわけではない。受け入れて、心の準備ができている、というのともちがう。どうせなら早く起きてくれ、というのとも少しちがうだろう。恐れながら、待っているのだ。そうすることしかできないから。じつにいやなものだ。グレーゴルがじっと動かずにいるのは、恐れつつ待っているからでもあるだろう。
妹が母親のひざの上に置いたヴァイオリンは、母親が手を震わせているために、ひざからすべり落ちてしまう。楽器だから、床に落ちたときの音は、普通のものが落ちたとき以上に大きく響き渡っただろう。それでもグレーゴルが動じないのは、もっと大きな崩壊がやってくることがわかっているからだ。沈む船の上で、コップを落として水をこぼしたからといって、誰があわてるだろう。
次回、あの妹のセリフがついに吐かれることになる……。