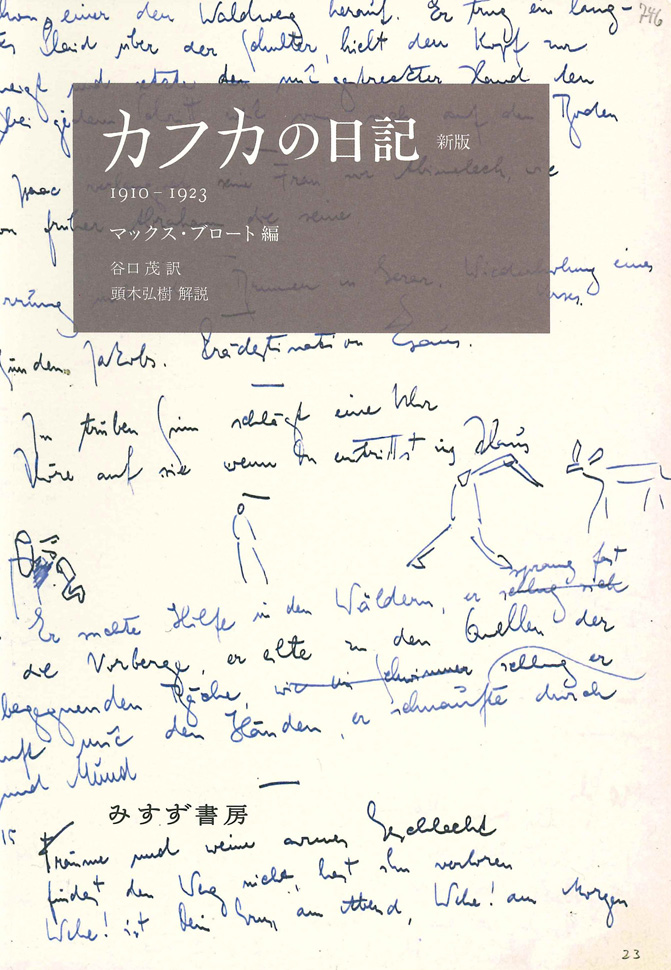●前回まで
この連載では、フランツ・カフカの小説『変身』を新訳しながら、超スローリーディングしていく(ものすごくゆっくり読む)。
前回までの内容を、まず簡単に紹介しておこう。
ある朝、虫に変身したグレーゴルは、そのことを知られないよう、自分の部屋に閉じこもっていたが、ついにドアを開けて姿を見せたとき、家族は驚愕し、今度は家族によって部屋の中に閉じこめられる。
世話をしてくれるのは妹のグレーテだけで、父親も母親も部屋の中には入ってこない。妹は、グレーゴルが壁や天井を這い回っていることに気づく。そして、もっと自由に這い回れるように、部屋の家具を外に運び出してあげようと思いつく。
ひとりでは家具を動かせないので、グレーテは母親に協力を頼む。母親は、部屋はそのままにしておいたほうがいいのではないかと忠告する。それを聞いてグレーゴルも、本当にそうだと思う。がらんとした部屋になってしまったら、人間の心を失ってしまう。
しかしグレーテは、母親に口出しされて、かえって自分の思いつきに固執する。もともとはグレーゴルのために思いついたことだったが、「グレーテは今、誘惑にかられていた。グレーゴルの境遇を、よりいっそう人が恐怖を感じるものにしたいという誘惑だ。そうすれば、これまでより、もっとずっと、兄のために尽くしてあげることができるのだ」(前回訳した箇所からの引用)
今回は、その続きから。
●「あなたのため」の恐ろしさ
そういうわけで、せっかくの母親の忠告も、妹を思いとどまらせることはなかった。母親もこの部屋では気持ちが落ち着かず、自分の言葉に自信が持てないようで、じきに黙りこみ、妹が戸棚を運び出すのをせいいっぱい手伝っていた。こうなったら、もう戸棚がなくなるのはしかたないとしても、机はなんとか残したい。そこでグレーゴルは、母親と妹がはあはあ言いながら戸棚を押して部屋の外に出ていくと、すぐにソファーの下から頭を出した。できるだけ事を荒立てることなく、片づけをやめてもらうにはどうしたらいいだろうかと、部屋の中をながめた。だが、あいにくそこに母親が戻ってきた。グレーテはまだとなりの部屋で戸棚の位置を整えようと、ひとりでゆすっていた。そんなことで動きはしないのに。母親はグレーゴルの姿を見慣れていないから、急に見たら具合が悪くなってしまうかもしれない、とグレーゴルは心配になって、あわててソファの反対側の端まであとずさりした。けれど、ソファにかけてあるシーツが少し揺れてしまった。それはどうしようもなかった。それだけで母親の注意を引くには充分だった。彼女は立ち止まり、そのままじっとしていたが、すぐにグレーテのところに戻っていった。
妹は母親の忠告を聞かず、むしろ自分の思いつきに固執する。母親のほうも自分の言葉に自信が持てない。虫になったグレーゴルの部屋に初めて入って、気持ちが落ち着かないのだ。けっきょく、二人で家具を運び出しはじめる。
グレーゴルはあせる。「こうなったら、もう戸棚がなくなるのはしかたないとしても、机はなんとか残したい」という一文は体験話法だ。なんとかしなければという気持ちの高まりが表れている。
自分のためという理由で、自分にとってはやめてほしいことが、目の前でどんどん進められ、しかしそれに口を出すこともできない。とても苦しい状況だ。
口を出せないのは、しゃべっても通じないからだし、そもそも姿を現すことができない。妹でさえ、虫になったグレーゴルの姿を見ると、びっくりして逃げてしまうし、母親となると、具合が悪くなるかもしれない。
それでも、二人がいないすきに、ソファーから頭を出さずにいられない。まだ家具のほとんどは残っている。それらをながめながら、いったいどうしたらやめてもらえるか考える。まだ、事を荒立てる気はない。なんとか穏便に中止にもっていけないかと思っている。
そこに母親が戻ってくる。グレーゴルはあわてて隠れる。母親は最近はグレーゴルの部屋に入りたがり、「グレーゴルに会わせて! かわいそうな、わたしの息子に! わたしがそばに行ってやらなきゃならないのが、わからないの?」と叫んだりしていた(第16回)。しかし、ソファにかけてあるシーツが少し揺れているのを見て、そこにグレーゴルがいることに気づいただろうに、母親はそばに寄っていって声をかけたりはしない。一瞬、硬直し、すぐにグレーテのところに逃げ帰ってしまう。
このことをグレーゴルがどう感じたかという描写はない。しかし、「何もなくなってがらんとした壁や床や天井を、ただグレーゴルだけが這い回っているような部屋には、グレーテ以外、この先、誰も足を踏み入れる勇気はないだろう」(前回訳した箇所からの引用)ということを、いっそう確信しただろう。母親はとても入ってきてくれそうにない。
●心と身体を使って、なんとか耐えようとする
グレーゴルは何度も自分に言い聞かせた。たいしたことじゃない、ただたんに家具の配置を少し変えているだけだと。しかし、自分をごまかし続けるのは無理だった。彼女たちの行ったり来たり、小さなかけ声、家具が床をこする音、それらがだんだん、四方八方からわき起こる大騒ぎのように感じられてきた。頭と脚をぎゅっと縮め、身体を床にぴったりと押しつけていたが、それでも、このままでは長くはもたないぞ、と思わずにはいられなかった。自分の部屋を空っぽにされてしまう、自分にとっては大切なものをすべて取りあげられてしまう、すでに糸ノコギリなどの工具が入っていた戸棚は運び出されてしまった。いまや机に手がかかっていて、床にしっかりすえつけてあるのを動かそうとしているのだ(1)。小学生の頃からこの机で勉強し、中学生のときも、商業学校生のときも使ってきた。──母親と妹が善意でしてくれていることだとしても、彼にはもう限界だった。いや、もう二人のことなどほとんど念頭になかった。母親と妹は疲れて声も出さなくなり、黙々と作業していて、聞こえてくるのは重い足音だけだった。
グレーゴルは自分に言い聞かせる。たいしたことではないと。家具の配置を変えるだけだと。人間、自分にはどうしようもない不幸に直面すると、なんとか「こんなのはたいしたことではない」と自分に思いこませようとするものだ。事実を変えられない以上、自分の認識を変えるしか手がない。それでうまくいくときもあるし、ごまかしきれないときもある。
がらんとした部屋になることは、自分がますます人間らしさを失い、しかもグレーテ以外の人との関係がますます失われるということだ。ただの部屋の模様替えとは、やはりちがう。母親と妹が家具を運び出す物音が、たいへんな圧迫となってグレーゴルに迫ってくるのも無理はないだろう。
こんなとき人は、身体をぎゅっと縮め、何かに身体をぴったりくっつけようとするものだ。ひざを抱えて丸くなったり、ぬいぐるみやふとんを抱きしめたり。なぜなのだろう? 発達障害者は圧迫刺激(人に抱きしめてもらったり)で落ち着くということを聞いたが、発達障害者に限らず、人は追いつめられると、自分で自分の身体に圧迫刺激を与えて落ち着こうとするのかもしれない。
グレーゴルは、認識を変えようとする、そして自分の身体に圧迫を与える。そうやって、心と身体の両面から、なんとかストレスを回避しようとしているのだ。なかなか涙ぐましい。
●断捨離の無惨
しかし、それでも、どうしても無理だ。「自分の部屋を空っぽにされてしまう、自分にとっては大切なものをすべて取りあげられてしまう」という思いがあふれる。
いったんあふれると、とめどがない。もうあきらめたはずの戸棚のことも、あらためて嘆かずにいられない。そこには、糸ノコギリなどの工具が入っている。前に出てきたように(第8回)、グレーゴルは糸ノコ細工が趣味なのだ。他人にはどうでもいいものでも、グレーゴルにとっては大切で愛着のあるものだ。
捨てられたわけではないが、部屋に閉じ込められているグレーゴルにとって、部屋の外に出されてしまうことは、もう自分には手が届かなくなるわけで、捨てられるにも等しい。
自分のものを勝手に家族に捨てられて、悔しい思いをしたことのある人は少なくないだろう。『ドラえもん』で、のび太のママは、のび太の部屋の漫画やその他のものを、しばしば勝手に処分する。のび太は大いに嘆くことに。多くの子どもたちが共感するシーンだ。しかし、子どもの頃はまだいい。未来があるからだ。大人になってから、結婚した相手に自分のものを捨てられるということもある。これは結婚生活が続けば、長期にわたるから、なかなか問題だ。しかし、さらに問題なのは、高齢になってから、自分のものを子どもに捨てられてしまうことだろう。親の家には、子どもの目から見ると、もう捨てたほうがいいものがたくさんある。捨てたほうが家の中がすっきりして、親のためにもいいはずだと思える。
しかし、高齢になるほど、過去の思い出は増えるし、その大切さも増している。たとえば仕事を引退した人にとって、仕事の道具や資料は、もはや無用のものだが、だからといって簡単には捨てられないだろう。それを見れば、いろんなことが思い出される。捨てたって思い出は残ると思うかもしれないが、思い出すには何かよすがが必要だ。
これは聞いた話だが、中国のある村では、その村の物語(神話や昔話や歴史などだろう)を代々語り継いでいく家が決まっていて、その家では親から子に物語を伝承していく。そのとき、香り壺がたくさんあって、ひとつのお話にひとつの香りが対応させてあるのだそうだ。つまり、ある物語を親が子どもに覚えさせるときには、その物語に対応した香り壺のふたを開けて、その香りの中で伝える。そうすると子どもは、その香りをかぐと、その物語を思い出せるというわけだ。前(第13回)にも紹介した「プルースト効果」(においで記憶が呼び起こされる現象)だ。
においほどではなくても、さまざまなモノが記憶を呼び起こすよすがとなる。思い出の品に囲まれていれば、思い出にひたることができるのだ。それを捨てられてしまうことは、過去の思い出を捨てられることになる。
たとえば、私は古い壊れた電動髭剃りを持っている。これは祖父が使っていたものだ。幼い頃の私はまだ自分にはない髭というものが面白くて、祖父が電動髭剃りでジョリジョリと髭をそるのを、目を丸くして見ていた。それで祖父も私の目の前でいつも髭をそってくれていた。祖父が亡くなったとき、だから私は電動髭剃りをもらった。以来、大切に持っているが、これは人から見たら、まったくのゴミだ。役に立つ立たないでいえば、まったく役に立たないし、いつか使うということもありえない。しかし、だからといって、捨てられては困る。
最近は、捨てることで幸せがやってくるなどと言う人もいるが、たとえそれが本当だとしても、今後の幸せとひきかえに、過去の大切な思い出を捨てるのはどうなのか。父の形見とか、母の形見とか言えば、さすがに捨てろと言う人はいないだろう。
高齢者の家にはそういう大切な思い出の品がたくさんあるはずだ。だから、それをいちがいに、「もう使わないでしょ」「捨てたほうがすっきりして暮らしやすいんだから」「幸せを呼び込むから」などと処分してしまうのは、どうにも無惨な気がしてしまう。
もちろん、近所のゴミまで拾ってきてゴミ屋敷になっている場合などもあるので、それこそ、いちがいには言えないが。
グレーゴルの場合は、高齢者ではないが、虫に変身してしまったわけで、人間のときの思い出の品を運び出されてしまうのは、たまらないものがあるだろう。使う使わない、便利不便の問題ではない。ついに机にまで手がかかる。この机も、小学生のときからの思い出の品だ。
グレーゴルは「できるだけ事を荒立てることなく」と考えていたし、母親が部屋に戻ったときもあわてて隠れている。母親と妹の気持ちをとても大切にしていた。しかし、ついに限界がくる。「もう二人のことなどほとんど念頭になかった」という心境にまで到達してしまう。
●グレーゴル、ついに飛び出す
彼は突然、飛び出したが──母親と妹はちょうど、となりの部屋で机にもたれて一休みしているところだった──まだ部屋に残っているものの中で、まず何を守るべきか、あせってわからなくなってしまって、あちらこちらと、走る方向を4回も変えた。そのとき、すっかりがらんとしてしまった壁に、毛皮を着た女性の絵だけが残っているのが目に入った。彼は急いで壁を這いのぼっていき、絵を身体で覆った。額縁のガラスがほてった腹にぴたりとくっつき、その冷たさが心地よかった。こうして上にかぶさっていれば、少なくともこの絵だけは、誰にも持っていかれずにすむだろう。母親と妹が戻ってくるのが見えるように、彼は居間のドアのほうに頭をねじ曲げた。
グレーゴルはついに飛び出す。これまではずっと遠慮して生活してきたのに、ついに能動的な行動に出る。映画やドラマでよくある、入院患者が点滴の管を引き抜いて、病室を飛び出していくような、見ているほうが、そんな無茶をして大丈夫なのかと心配になるシーンだ。
母親と妹はとなりの部屋で机にもたれて一休みしている。つまり、「なんとか残したい」とグレーゴルが願っていた机は、もう部屋から運び出されてしまっている。なので、グレーゴルは次に何を守ったらいいのか迷う。あれかこれかとうろうろしてしまう。
そのとき、毛皮を着た女性の絵がまだ壁にかかっているのが目に入る。これは『変身』のかなり最初のほうで出てきた絵だ。
「壁には、絵がかけてあった。彼がつい最近、グラビア雑誌から切り取って、きれいな金色の額縁に入れたのだ。描かれているのは、ひとりの女性で、毛皮の帽子をかぶり毛皮のえり巻きをし、背筋を伸ばして座り、ひじのところまで入る重そうな毛皮のマフを、見る者のほうに向けていた」(第5回で訳した箇所からの引用)
その後、この額縁はグレーゴルのお手製であることが、母親の口から語られる。
「糸ノコ細工でもしていれば、それであの子には気晴らしなんです。そう、つい先日も、二晩か三晩かけて、小さな額縁をこしらえました。見事なできばえですから、びっくりなさいますよ。部屋の中に掛けてありますから」(第8回で訳した箇所からの引用)
すでに糸ノコなどの工具が入っていた戸棚は運び出されてしまったが、その糸ノコなどの工具で作った額縁は、まだ壁に残っていたのだ。
グレーゴルはこの絵を守ることにする。額縁を身体で覆う。「こうして上にかぶさっていれば、少なくともこの絵だけは、誰にも持っていかれずにすむだろう」だけ体験話法になっている。自分の身体が嫌がられているからこそ、この守り方が成立するのだ。悲しい守り方と言えよう。ずっと見せないように気を使ってきた身体を見せることで、グレーゴルははっきりと抵抗の意志を示す。母親と妹が部屋に入ってくるのを待ちかまえる。
●性的象徴と犬の糞
なお、この毛皮を身につけた女性の絵に関しては、マゾッホの小説『毛皮を着たヴィーナス』の影響が、昔から指摘されている。まぎれもなく関連があるという批評家から、完全否定の批評家までさまざまだが。
そして、このあたりのシーンを、エディプス・コンプレックスの観点から、フロイト的に解釈する批評家も少なくない。
そういう説も紹介すべきだが、やめておくことにする。というのは、こういう説は、いったん聞いてしまうと、それはちがうと思っても、つい思い出してしまうからだ。
私はかつて、ある大好きな作品について、そういう説を聞いてしまって、たいへん後悔した。その作品には、入口に立ちはだかった女性のまたをくぐって、男が部屋の中に入るシーンがあった。私はそのシーンがとても好きだったのだが、ある人が「これは胎内回帰願望を表している」と分析した。それはまったくちがうと私はすぐに思ったが、にもかかわらず、このシーンを読むと、必ずその説を思い出してしまって、もう前のように純粋に楽しめないのだ。そのシーンを好きと思うことさえ難しくなってしまった。もうとりかえしがつかない。
『くしゃみ講釈』という落語で、講釈師が暗い道を歩いていて、何か踏む。なんだろうと履き物にさわってみると、それは犬の糞。指についてしまった犬の糞を、壁になすりつけようとして、まちがって、暗がりにいた男の鼻の頭になすりつけてしまう。なすりつけられた男は、そのあと、恋人にふられてしまう。犬の糞とその男は何の関係もないし、うっかりしたのは講釈師のほうでその男には何の落ち度もないのだが、それでもやっぱり、そういうことになってしまう。
そういうことが起きないよう、あえて紹介はひかえておく。興味のある人は、「カフカ 『毛皮を着たヴィーナス』」「カフカ 変身 エディプス・コンプレックス」などでインターネットを検索すれば、きっといろいろ出てくるだろう。ただし、私のように後悔しないよう、気をつけてほしい。
私個人は、性的な象徴を読み取って、これぞ隠された意味だと小躍りするのは、どうかと思っている。性的な表現が許されない時代ならともかく、そうでなければ、それだけのために作品を書くだろうか。カフカのある短編についても、草むらをストックでつっつくシーンがあることから、これはセックスを描いているのだとする説がある。しかし、セックスシーンなら、『失踪者(アメリカ)』にも『城』にもある。「顔をゆがめながら息づかいも荒々しく、自分の女中部屋につれ込み、鍵をかけた。そして、彼女はカールの首をしめるのかと思うくらい強くだきしめ、自分を裸にしてくれるようにと頼んだが、実際には彼女がカールの服をぬがせ、彼を自分のベッドに横たえさせ、まるでこの瞬間からもはや誰にも手をふれさせずに、彼を愛撫し、この世の終りまで彼のめんどうを見たいと望んでいるかのようであった」(『決定版カフカ全集4 アメリカ』千野栄一訳 新潮社)くらいの描写はしているのだ。セックスとわからないような短編を書いて、じつはセックスを象徴させるというようなことを、カフカがわざわざするとは思えない。隠された性的刺激で商品を売ろうとするデザイナーとかではないのだから。
人は隠された意味に弱い。隠してあったものを見つけたと思ってしまうからだ。しかもそれによって、いろんなことがうまく説明できるとなると、それがまったくの間違いとは思えなくなってしまう。しかし、昔、ブルーバックスの栞に書いてあった、この言葉は金言だと思う(誰の言葉かは忘れてしまったが)。「すべてがうまくあてはまる説明があったとしても、それが正しいとは限らない」
これは科学の言葉だが、もちろん文学にもあてはまるだろう。すべてがうまく説明できるだけで正しいのなら、陰謀論だってすべて正しいことになってしまう。
性的象徴ということで、私が思い出すのは、こんな小話だ。
医師「どんな夢を見たんですか?」
患者「バナナが出てきました」
医師「それはペニスですね」
患者「高い塔にのぼりました」
医師「それはペニスですね」
患者「ピストルを取り出しました」
医師「それはペニスですね」
患者「ズボンを下げて、ペニスを出しました」
医師「うーん、それは何だろう?」
●最大の援助者が最大の敵になる
母親と妹はゆっくり休もうとはせず、すぐに戻ってきた。グレーテは母親の身体に片腕をまわして支え、ほとんど抱きかかえるようにしていた。「さあ、次は何を運ぶ?」と言って、グレーテは部屋の中を見回した。そして、壁にいるグレーゴルと、一瞬、目が合った。母親がそばにいたからだろう、妹はなんとか平静を保った。母親が壁のほうを見ないように、母親の顔をのぞきこんで、「ねえ、ちょっと居間に戻ったほうがいいんじゃない?」と思わず言ったが、その声はふるえていた。グレーテがどういうつもりか、すぐにわかった。気づかれないところまで母親を連れ出してから、ぼくを壁から追い払おうというのだ。さあ、やれるもんならやってみろ! この絵にしがみついて、渡しはしない。渡すくらいなら、グレーテの顔に飛びかかってやる。
母親と妹は長くは休まない。というより、妹が休ませない。妹は心が燃え上がっているから、どんどん進めたいのだろう。母親は妹に抱きかかえられるようにして、歩かされている。母親は「歳だし、喘息の持病があって、家の中を歩き回るのさえ苦しそうで、一日おきに呼吸困難におちいって、開いた窓のそばのソファで休んでいなければもたない」と前に説明されている(第15回)。それが重い家具を運ばされて、ろくに休ませてももらえないのだから、支えてもらわないと歩けないのも当然だろう。そんな母を抱えて、「さあ、次は何を運ぶ?」と言い放つ妹。妹の熱狂ぶりが伝わってくる描写だ。
そのとき、部屋の中をぐるりと見渡した妹の視線と、妹たちのほうをじっと見ているグレーゴルの視線が交錯する。もし妹がひとりでいたとしたら、悲鳴をあげたり、飛んで逃げたかもしれない。しかし、母親がいるので、妹はぐっとこらえる。まずはとにかく、母親にグレーゴルの姿を見せないようにし、部屋から連れ出そうとする。
そのあとは、妹との1対1の対決になるだろうと、グレーゴルは予想する。この最後のところは体験話法になっている。ここで驚くべきは、グレーゴルが妹に対してすっかり対決姿勢になっていることだ。絵を渡すくらいなら、「グレーテの顔に飛びかかってやる」とまで考えている。直接的な攻撃も辞さないかまえなのだ。
これまでずっとグレーゴルは、ただひとり自分の世話をしてくれるグレーテに深く感謝してきた。そして、妹のやることはすべて好意的に解釈してきた。読むほうが「そうかな?」と疑問に感じるほどに。そこには、自分だけでは生きられない者が、他人に面倒をみてもらっているときの心理が如実にあらわれていた。自分の命を左右できる人が、いい人でなければ、困ってしまうのだ。だから、なるべくそう思いたいのだ。
しかし、母親が自分に会いたがったことで、妹が唯一の頼りではなくなり、グレーゴルは初めてグレーテに対して、少し客観的な見方をするようになる。
そして、部屋から家具を運び出すという行為を、母親に止められても強行する妹に対して、ついにグレーゴルは反旗をひるがえすのだ。
この展開はじつに自然であると同時に、じつに不思議でもある。ちょっと前までは、家族の中でひとりだけ献身的にグレーゴルに接していた妹と、それに深く感謝していた兄なのである。そういう美しい関係の二人だったのだ。もともと仲のいい兄妹で、それが虫に変身した後も続いていたのだ。
それが、たちまち、兄の境遇をより悲惨なものにしようとする妹と、そうはさせまいとして「顔に飛びかかってやる」とまで身がまえる兄になってしまったのだ。
それでも、読んでいて、「こんなことはありえない」とは思わず、ある種の感動にとらわれるのは、こういうことはあると、どこかで感じるからだろう。
たとえば親は子どもを育てる。子どもは大人の援助なしでは生きていけない。親は最大の援助者だ。しかし、その親が、子どもにとって最大の敵となることもある。親と闘っている子どもがどれほど多いことか。その闘いに人生の大半を費やしてしまう子どももいる。
親子関係以外でも、心強い味方であった人が、のちに困った敵となることはままある。
グレーゴルの反抗を、恩知らずと感じる人もあるかもしれないが、面倒を見てもらってばかりというのは、かなり心理的な負債感になる。借金がたまっていく一方の人が、金貸しに感じるような憎しみを、無自覚なままためこんでしまっていなかったとも限らない。
なお、このグレーゴルの態度を、ただたんにこの絵に対する激しい執着と解釈する向きもあるが、私はそうは思わない。少なくとも、それだけとは思えない。この絵でなくても、たとえばまだ机が部屋の中にあれば机でも、同じようにグレーゴルはしがみついて、「渡しはしない。渡すくらいなら、グレーテの顔に飛びかかってやる」と思ったのではないだろうか。
●気絶する母、昔を思い出す兄と思い出さない妹
ところが、グレーテにそう言われて、母親はかえって不安になり、グレーテから少し身体を離した。すると、花柄の壁紙の上に大きな褐色のしみができているのが目に入った。それがグレーゴルだと気づく前に、もう大きなしわがれた叫び声をあげていた。「ああ、神様、ああ、神様!」すべてを投げ出すように両腕を広げて、ソファの上に倒れこみ、動かなくなった。「グレーゴル兄さん!」と妹は叫び、こぶしをふりあげて、刺すようなまなざしで兄を見た。変身以来、妹が兄に口をきいたのはこれが初めてだった。気を失っている母親のために妹は、気つけ薬になりそうな香油を取りに、となりの部屋に駆けていった。グレーゴルも手伝いたかったが──絵はまたあとで守ればいいのだ──身体がガラスにしっかりはりついていたので、はがすのにひと苦労だった。それから彼もとなりの部屋に急いで行った。以前のように、妹の助けになれる気でいたのだ。しかし、妹がいろいろな小瓶をひっかき回しているあいだ、その後ろにむなしくとどまっているしかなかった。しかも、ふり向いた妹を、驚かせてしまった。小瓶がひとつ、床に落ちて割れた。破片でグレーゴルの顔が傷つき、小瓶の中の腐食性の薬液もグレーゴルに飛び散った。グレーテはくずぐずしていないで、持てるだけのたくさんの小瓶を抱えて、母親のところに駆けていった。彼女は足でドアをばたんと閉めた。こうしてグレーゴルは、自分のせいで死にかけているかもしれない母親から、隔絶された。ドアを開けるわけにはいかなかった。妹は母親のそばにいなければならないのだ。その妹を追い払いたくはなかった。今はただ待っているしかなかった。自責の念と心配とでいたたまれず、彼は這い回りはじめた。壁、家具、天井、いたるところを這い続け、やがて部屋全体がぐるぐる回りだした頃、絶望して、ついに大きなテーブルの真ん中に落ちた。
母親にしてみれば、自分を抱えてまで歩かせ、「さあ、次は何を運ぶ?」と強引に作業の継続を迫ったグレーテが、すぐに「ねえ、ちょっと居間に戻ったほうがいいんじゃない?」と言い出したのだから、それは不安になるだろう。不安にさせられると、人はその相手から身体を離すものだ。
グレーゴルの部屋の壁紙が花柄だったことが、ここで初めてわかる。このことに関して、三原弟平が「『変身』を劇化する人は誰も、グレゴールの部屋の壁はただの灰色の壁にするだろう」(『カフカ『変身』注釈』平凡社)と書いていて、たしかにと思って面白かった。実際、英訳では、花柄というのを省略して、ただ the wallpaper としているものが4つもある。
しかし、犯人と刑事の壮絶な格闘シーンに、あえて子どもたちが歌う「ちょうちょ」を重ねる黒澤明の手法(映画『野良犬』)が効果的なように、灰色の壁に褐色の虫がはりついているより、花柄の壁に褐色の虫がはりついているほうが、より無惨な感じがする。
壁の大きなしみがグレーゴルだと気づくより前に、母親は悲鳴をあげる。これも実感としてすごくわかる。悲鳴をあげてから、なぜ自分が悲鳴をあげたのか気づくことがあるものだ。最近の研究では、感情というのは身体を通して感じるものらしい。たとえば何か怖いものを見たとき、まず目を通して脳が知覚し、自律神経に伝わり、心臓の鼓動が早くなるとか血圧が上がるなどの身体の変化が起き、その身体の変化をまた脳が感知し、知覚した状況と統合して、「怖い」という感情が生まれるのだそうだ。だから、最終的な脳の判断より前に、身体が叫んでいても、おかしくはないのかもしれない。
一方、怖いものではないともうわかっているのに、叫びが止まらないこともある。夜道で冗談で友達が私を脅かしたとき、すぐに友達だと気がついたのに、まだ少しのあいだ叫んでいた。身体の反応は、認識に先立ち、後まで続くのかもしれない。心臓のどきどきもすぐにはおさまらないし。ちなみに、その友達は、叫ぶ私の顔がすごく怖かったそうで、「人をおどかすと、自分のほうが怖くなるから、もうやめた」と言っていた。
これまでグレーゴルがその下に隠れていたソファ。その上に今度は母親が倒れる。グレーゴルは母親がソファのシーツをとってくれることを期待していたが、実際にはそれどころではなかった。
妹が怒って、「グレーゴル兄さん!」と叫ぶ。しかし、「変身以来、妹が兄に口をきいたのはこれが初めてだった」のだ。よく面倒は見ていたが、それが人間的なあつかいではなかったことに、あらためて気づかされる。
となりの部屋に気つけ薬となる香油を取りに行った妹のあとを、グレーゴルは追いかける。「以前のように、妹の助けになれる気でいた」というのが悲しい。もうずっと面倒をみてもらう一方だったのに、ふとそんな昔の自分の姿に立ち返ってしまったのだ。しかし、現実には、なんの助けにもならないどころか、ふり向いた妹は、兄の姿を見てびっくりしてしまう。小瓶を落として割ってしまうほどに。
その小瓶の破片でグレーゴルが顔にケガをして、さらに腐食性の薬液がグレーゴルにもかかったのに、妹はそれにはいっさいかまわない。母親が緊急事態だからでもあるが、兄のほうは昔の自分を思い出しても、妹のほうは昔の兄を思い出さない。
さらに、急いでいる中でも、ドアを足で閉めるのを忘れない。兄が入ってこないようにするのだ。母親がまた見てしまわないようにという気遣いでもあるだろうが、兄に対してはっきり拒絶を示している。
虫になって自分の部屋にひきこもったグレーゴルは、次に部屋に閉じ込められ、そして今度は、部屋から閉め出される。鍵まではかけられていないだろうが、物理的には開けることが可能だとしても、心理的に開けることのできないドアだ。
久しぶりに自分の部屋から出たわけだが、もちろん、解放感を味わっている余裕はない。自分の部屋で、もしかすると母親が死にかけているかもしれないのだ。
いたたまれなくて、彼は這い回る。壁、家具、天井、いたるところを這い続ける。「グレーゴルが這い回ると、粘液の跡がそこかしこに残る」と前に説明があった(第17回)。だから、居間のいたるところに粘液の跡が残ったことだろう。
やがて目が回ってきて、絶望のうちに、グレーゴルは大きなテーブルの真ん中に落ちる。おそらく天井から落ちたのだろう。このテーブルは、虫になったグレーゴルが初めて居間につづくドアを開けたときに、朝食が並べられていた、あのテーブルだろう。居間のいたるところに粘液の跡をつけたうえに、みんなが食事をするテーブルの上に落ちたわけだ。
今回は母親と妹が相手で、父親は留守をしていたが、次回は父親が戻ってきて、父親との話になる。そして、例の有名な林檎のシーンへとつながる。
注
(1)じつはここの原文の意味がよくわからなかった。机について「床にしっかりすえつけてある」と訳したが、ここには eingraben(埋め込む)という言葉が使われている。だから、既訳でもたとえば「床にしっかとめりこんでいる机」(原田義人訳)などとなっている。これがよくわからない。なぜ机が床にめりこんでいるのか。
当時のプラハでは机を床にめりこませていたのか、そういうことに詳しい方に聞いてみたが、そんなことはないそうだ。
長年置いてあるので、重みでめりこんだのか。しかし、机自体は小学生のときから使ってきた古いものであっても、今の住居に子どもの頃から住んでいたわけではない。前に「5年も住んでいる部屋」とあったから(第13回)、まだ5年だ(ちなみに、5年前というのは父親の店が倒産したときで、グレーゴルが働き出したのも5年前だ。そして、あとで(物語の最後のほうで)「グレーゴルが見つけてくれたこれまでの家」という説明も出てくる。父親の店が倒産したとき、グレーゴルは働きだし、今の住居もグレーゴルが見つけたようだ)。
英訳にひとつだけ、which(関係代名詞で先行詞はthe writing desk)was almost stuck in the carpet と、床ではなくカーペットにしてある訳(Daudert訳)があった。これはなるほどと思った。グレーゴルの部屋の床には絨毯が敷いてある。そのことはこれまでに何度も出てきた(第8回、第9回)。絨毯なら、机がめりこむという表現もありうる。しかし、これが正しいのかはわからない。原文には絨毯とは書いてない。
「床にしっかりすえつけてある」というのは、じつはごまかした訳だ。ここを読んで「どういう意味だろう?」とひっかかった人は、鋭い。ここの意味がわかる人がいたら、ぜひ教えてほしい。