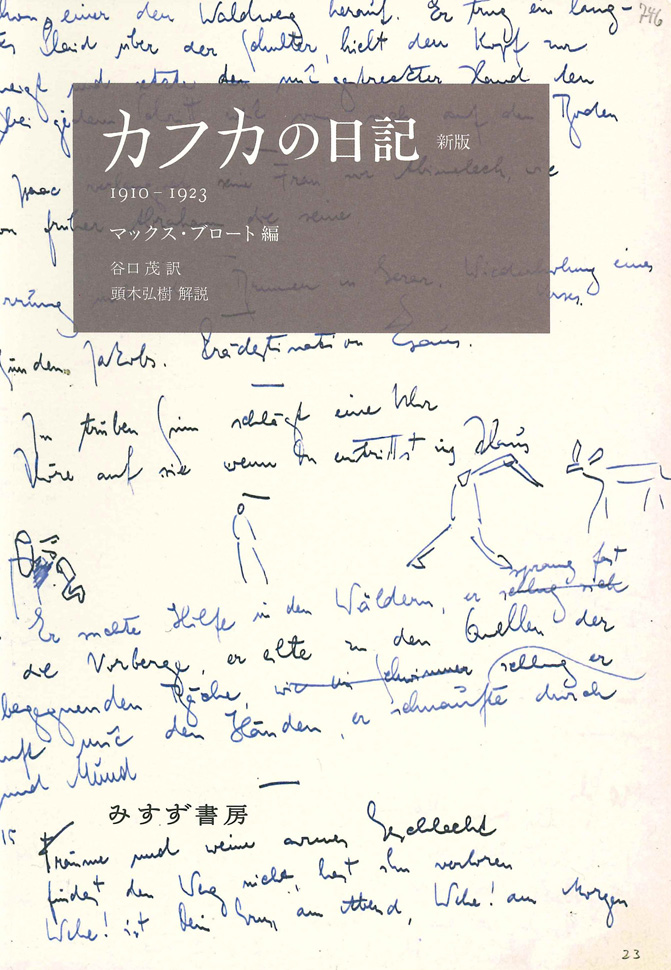この連載では、フランツ・カフカの小説『変身』を新訳しながら、超スローリーディングしていく(ものすごくゆっくり読む)。
さらに、読みながら私が思い出したこと考えたことも、脱線を気にせずに、どんどん書いていく。というのも、読書の半分は、本に書いてあることではなく、本を読みながら自分のうちにわきあがってきたことにあると思うからだ。
私の脱線につられて、みなさんもそれぞれに、いろんなことを思い出したり考えたりしていただけたら幸いだ。自分の城の中にある、自分でもまだ知らない広間。
それを開く鍵のような働きが、多くの本にはある。(オスカー・ポラックへの手紙 1903年11月9日)
●前回まで
間借人たちが居間で夕食をとるようになったことで、グレーゴルの部屋のドアは再び閉ざされるようになる。しかし、あれほどドアを開けてほしがっていたグレーゴルが、もうさほど残念とも思わなくなっている。
ある夜、たまたま掃除婦が閉めそこねたドアのすき間から、グレーゴルは居間で夕食をとる間借人たちの姿を見る。間借人たちは横柄にふるまい、母と妹は間借人たちの機嫌に一喜一憂し、家族の者は台所で食事をとるようになっていた。
間借人たちががつがつ食べる音が、グレーゴルのところまで響いてくる。グレーゴルは今ではもうほとんど何も食べなくなっていた。しかし、それは食べたくないからではなく、食べたいものが見つからないからだった。「間借人たちが食べて生きつづけ、ぼくが食べずに死んでいくとは!」とグレーゴルは嘆く。
そのとき、台所で妹がヴァイオリンを弾きはじめる。グレーゴルが虫になって以来のことだ。間借人たちはそれを耳にして、居間で弾くようにすすめる。妹は両親といっしょに居間にやってきて、今度は間借人たちと両親の前で弾きはじめる。
グレーゴルはその演奏にひきつけられて、居間に少し這い出してしまう。その姿はほこりにまみれ、糸くずや髪の毛や食べ物のかすが背中やわき腹にくっついていて、以前よりもずっと汚れていた。周囲に気をつかう人間であったグレーゴルが、もうあらゆることに無関心になっていて、身だしなみにも気をつかわなくなっていた。
●微細な権力闘争
もっとも、みんなのほうも誰ひとり、彼に気づかなかった。家族の者は、ヴァイオリンの演奏にすっかり気をとられていた。間借人たちは逆に、最初のうちこそズボンのポケットに手をつっこんで譜面台のすぐうしろに並び、あまりに近かったから楽譜をのぞきこめるほどで、きっと妹の邪魔になっていたにちがいないが、ほどなく小声で何か言い交わしながら顔を伏せて窓際まで遠ざかり、父親が気にしてじっと見ていたが、そこから動かなかった。間借人たちの態度は見えすいていて、あからさまだった。ヴァイオリンの美しい演奏、あるいは楽しい演奏を聴けると思っていたのに、期待外れでがっかりしてしまった、もうすっかりうんざりだが、ただ礼儀からうるさいのを我慢しているのだ、と言わんばかりだった。とくに3人が鼻や口から煙草の煙をふーっと勢いよく吹き出している様子は、ひどくじれったがっているように見えた。妹はこんなに素晴らしい演奏をしているのに。
グレーゴルは演奏にひきつけられて、つい人目を気にすることも忘れて這い出してしまったのだが、家族や間借人のほうもグレーゴルに気づかない。家族は妹の演奏に気をとられているからだし、間借人たちのほうは、演奏にうんざりしていることをアピールするのに気をとられているからだ。
間借人たちは、自分たちで妹を居間に呼び出して演奏させたくせに、どうしてこんなにすぐにうんざりしてしまったのか? 間借人たちは、台所で妹がヴァイオリンを弾き出したとき、「ヴァイオリンが鳴りはじめると、3人は聞き耳を立て、それから立ち上がって、廊下のドアのところまでそっと爪先立ちで行き、そこで身体を寄せ合って立ったままでいた」のだ。かなりの関心だ。それに気づいた父親が「ヴァイオリンの音がうるさいですか? それならすぐにやめさせますが」と言ったのに対しても、間借人たちは「とんでもない」と返事をし、「娘さんはこちらに来て、ここで弾きたいのでは? この部屋のほうがくつろいで弾きやすいでしょう」と自分たちから居間に誘ったのだ。それなのになぜ、演奏が始まってすぐにうんざりしてしまうのか?
「ヴァイオリンの美しい演奏、あるいは楽しい演奏を聴けると思っていたのに、期待外れでがっかりしてしまった」という態度をとっているが、演奏はそもそも聴いていたのだ。もちろん、台所から響いてくるときには、いい演奏に思えたのだが、実際に居間で目の前で直に聴いてみると、それほどでもなかった、ということもありうるだろう。しかし、ここまで態度が変わるほどのちがいがあるだろうか?
私はここのところがよくわからなかった。うんざりしてみせるために、わざわざ呼び出したのかとも思ったが、それでは少しひどすぎるだろう。間借人たちがそこまでする理由はない。
すると、前回の連載を読んで、京都大学の川島隆教授が、こんな感想を寄せてくださった。「(妹がヴァイオリンを)ずっと弾いていなかったのに今回弾いた理由は、ほかでもなく間借人に聴かせるためだと私は受け取っていたと思います。音楽をたしなむハイソな家なんですよ、というアピールのためなのかと。その意味では、微細な権力闘争がずっと続いているということなのだと思っています」
これを読んで、なるほど! と思った。台所で妹がヴァイオリンを弾き出したことについて、私は前回書いたように、「みんなが働きだして、下宿代も得られるようになって、少し気持ちに余裕ができたのか。それとも、台所で食事をしている父母をあわれに思い、少しでもなぐさめようとしたのか」くらいに思っていた。
しかし、家族と間借人たちの “微細な権力闘争” の中で、ヴァイオリンが弾きはじめられたわけで、これはその一環と考えるほうがぴったりくる。父親は間借人たちの食卓の周囲をぐるりと回り、台所で食事をとったあと、妹にヴァイオリンを弾くように言ったのかもしれない。間借人たちに聞こえるのを承知で、アピールのために。
間借人たちのほうも、その意図を感じとったのかもしれない。だから、「聞き耳を立て、それから立ち上がって、廊下のドアのところまでそっと爪先立ちで行き、そこで身体を寄せ合って立ったままでいた」のだ。これは音楽への関心ではなく、権力闘争への関心であったわけだ。
アピールが功を奏したので、父親はにんまりして、「ヴァイオリンの音がうるさいですか? それならすぐにやめさせますが」と言う。その含むところは、「あなたたちには音楽は理解できないでしょう。騒音でしかないでしょう。だったらやめさせますよ」ということだろう。
だから間借人たちも、「とんでもない」と否定し、「娘さんはこちらに来て、ここで弾きたいのでは? この部屋のほうがくつろいで弾きやすいでしょう」と、自分たちが音楽に理解があり、音楽を鑑賞したがる人間であることをアピールする。
そして、「譜面台のすぐうしろに並び、あまりに近かったから楽譜をのぞきこめるほどで、きっと妹の邪魔になっていたにちがいない」というほど、演奏に関心を示してみせる。しかし、本当に演奏を聴きたいわけではない。だから実際に、たちまち演奏にあきてしまっただろう。それに、演奏が「期待外れでがっかり」という態度を示したほうが、マウントをとれる。そこで、自分たちの気持ちに正直になり、さらにそれを家族に見せつけるようにする。「父親が気にしてじっと見ていたが、そこから動かなかった」のは、むしろ父親が見ているからこそだろう。自分たちは礼儀を重んじる人間だということを示しながら、同時にあからさまにうんざりした態度を示してみせたわけだ。
そこにあるのは、微細な権力闘争であり、音楽はどうでもいいのだ。純粋に音楽を聴いているのは、汚い姿のグレーゴルだけだ。音楽に感動してひきつけられ、思わず前ににじり出てしまっている。グレーゴルはもはや権力闘争には参加していない。音楽を音楽として聴いている。そんな彼にとっては、間借人たちの態度は理解できない。「妹はこんなに素晴らしい演奏をしているのに」と不思議に思ってしまう。
もちろん、グレーゴルの評価にも、妹へのひいき目があったかもしれないが。
●日常のマウントのとりあい
それにしても、まさになんと “微細な権力闘争” だろう。そして、カフカのなんと微細で絶妙な書き方だろう。前にも紹介したように(第9回)、カネッティはカフカを「権力の真の精通者」と呼んでいる(『もう一つの審判』小松太郎、竹内豊治訳 法政大学出版局)。『変身』のこうしたシーンを読むだけでも、それがとても納得される。
もちろん、このシーンを権力闘争と読むのは、ひとつの読み方にすぎず、他の読み方もできるかもしれない。また、どれかひとつの読み方が正解ということもありえない。さまざまな読み方が可能で、いろんな場合にあてはまるのが、文学というものだ。前でも書いたように(第1回)、万有引力の法則が林檎だけでなく、ミカンにもスイカにも、月にもあてはまるのと同じで。
ただ、人間がこのような “微細な権力闘争” を日々くりひろげているのはたしかなことだ。いったいなぜなのだろう? こんなマウントのとりあいに勝って、いったい何の意味があるだろう。でも、相手がマウントをとってくると、ついむっとしてこちらもやり返してしまう。そういうことは日常生活の中にも満ち満ちている。仕事ではもちろん、家庭内でさえ、夫が妻に、妻が夫にマウントをとったりする。恋人どうしでさえ、そういうことはある。配偶者や恋人をおさえつけて、何もいいことはないが、それでもやってしまうのは、人間の根本的なかなしさのひとつだろうか。
病院の六人部屋でもよくそういうことがあった。胃の手術をした会社の同僚のところに、「いやー、昨夜はステーキを3枚もペロリだよ」と言いに来る見舞客。どちらの病気のほうが大変かという病人どうしの不幸比べ。自分の病状のほうが深刻で、相手がぐうの音も出ないときの、病人の顔に一瞬浮かぶ勝利の喜悦。しかし、すぐに暗く深く沈みこんでいく。病気でマウントをとるほど悲しいことはない。
日常の会話の “微細な権力闘争” というと、私にはハロルド・ピンターの戯曲が思い浮かぶ。2005年にノーベル文学賞とフランツ・カフカ賞を受賞したイギリスの劇作家ハロルド・ピンターは、インタビューで「ベケットとカフカが一番ぼくの心に残りました。(中略)ぼくの世界はいまでもほかの作家たちによって支えられています——それがぼくの最良の部分の一つです」と語っているが(小田島雄志訳『新劇』1968年10月号)、ピンターこそ、「権力の真の精通者」としてのカフカの後継者と言えるのではないだろうか。以前、『かすかな痛み』という戯曲のあらすじを紹介したが(第13回)、その出だしはこんな会話だ。手入れの行き届いた庭のある家で、夫婦が朝食をとっている。夫は新聞を読んでいる。
フローラ 今朝、スイカズラをごらんになった?
エドワード なにカズラ?
フローラ スイカズラ。
エドワード スイカズラ? どこの?
フローラ 裏門のそばのよ、エドワード。
エドワード あれ、スイカズラか? おれはまた……ヒルガオかなんかかと思ってた。
フローラ だってご存じのはずよ、スイカズラだってこと。
エドワード おれはヒルガオだと思ってたんだよ。
(間)
フローラ すばらしいわよ、あの花。
エドワード そいつは見なくちゃ。
フローラ 今朝は庭いっぱいに花が咲いて。センニンソウでしょう。ヒルガオでしょう。
なにもかも。七時ごろ庭に出てみたの。プールのところまで。
エドワード なんだって──ヒルガオも咲いていたのか?
フローラ そうよ。
エドワード だっておまえ、さっきそんな花はないって言ったじゃないか。
フローラ さっきはスイカズラの話をしてたのよ。
エドワード なんの話だって?
フローラ (落ちついて)エドワード──ご存じでしょう、物置小屋の外側にある茂み……
エドワード ああ。
フローラ あれがヒルガオよ。
エドワード あれが?
フローラ そうよ。
エドワード そうか。
(間)
おれ、あれはツバキかと思ってた。
フローラ とんでもない。
エドワード ティーポット、取ってくれないか。
(「かすかな痛み」小田島雄志訳 『ハロルド・ピンター全集』第1巻 新潮社)
妻が熱心に手入れをしているらしい庭の花に対して、夫は関心を示さない。妻が「だってご存じのはずよ、スイカズラだってこと」と言っているから、植えるときに夫に相談したか、そうでなくても話をしているはずだ。しかし、夫はおぼえていない。知っているはずだったかどうかにはふれず、「おれはヒルガオだと思ってたんだよ」と、自分がどう思っていたかをくり返す。
そして夫は、自分が口にしたのに、妻が否定したヒルガオが、庭にあったということには、「だっておまえ、さっきそんな花はないって言ったじゃないか」と反応する。スイカズラの話には、「なんの話だって?」と、あくまでとりあわない。ヒルガオをさらにツバキと言う。そして、「ティーポット、取ってくれないか」。
カフカよりさらに微細だが、素晴らしく絶妙ではないだろうか。最後に夫は家を出て行かされることになる。カフカが好きな人は、きっとハロルド・ピンターも好きだから、ぜひ読んでみてほしい。
●音楽に感動するのは、人間だからか、動物だからか?
首を横に少し傾け、たしかめるように楽譜の1行1行を目で追っている妹の姿は、かなしげでもあった。グレーゴルはさらに少し前に這い出して、床にくっつくまで頭を下げた。そうすれば妹と目が合うかもしれないと思ったからだ。こんなにも音楽に心を動かされているのに、それでもぼくは人間ではないのか? まるで道が開けたかのようだった。それが何なのかわからないまま、ずっと求めつづけてきた、生きる糧への道が。彼は決心した。妹のところまで突き進んでいって、スカートのすそを引っぱろうと。そうすれば妹にもわかるだろう、ヴァイオリンを持って兄さんの部屋においで、と伝えようとしていることが。なにしろ、ぼくほど演奏しがいのある相手は、ここには他に誰もいないのだ。
妹が首を横に傾けているのは、ヴァイオリンを弾くときにはそうする人が多いから、たんにそれだけのことだろう。かなしげに見えるのは、その首を傾けた姿勢や、きちんと楽譜を確認する様子が健気で、そう感じられたということなのか。それとも、こんな権力闘争に巻き込まれて弾かされるのが、妹はかなしかったのか。あるいはグレーゴルが、そんな妹をかなしく感じたのか。
グレーゴルはさらに前に這い出して、妹と目を合わせようとする。そんなことをしたら嫌がられるとは考えていない。以前、グレーテがグレーゴルの部屋から家具を運び出そうとしたとき、壁の絵を守ろうとしてその上に覆いかぶさったグレーゴルは、「さあ、次は何を運ぶ?」と言って部屋の中を見回したグレーテと、一瞬、目が合ったことがある(第18回)。そのあとは悲惨なことになった。グレーゴルの背中に林檎がめりこんだのも、そのときのことだ。しかし今、グレーゴルはそのときのことを思い出しもしない。それほど音楽に魅了されているということなのか。
「こんなにも音楽に心を動かされているのに、それでもぼくは人間ではないのか?」という一文は、体験話法だ。グレーゴルの感情の高まりが感じられる。
私は後半を「それでもぼくは人間ではないのか?」と訳したが、直訳すると「ぼくは動物なのか?」となる。虫を動物と呼ぶのはどうかと思い、こうしたが、ようするに、人間なのか、そうではないのかということだ。
じつはこの文については、解釈が大きく2つに分かれる。邦訳でも英訳でも。きっと他の言語の訳でもそうだろう。というのも、原文がどちらにも解釈できるからだ。原文は次のとおり。
War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff?
この文は、
「こんなにも音楽に心を動かされているのに、ぼくは動物なのか?」
「こんなにも音楽に心を動かされているから、ぼくは動物なのか?」
という2つの訳し方ができる(接続詞の da がどちらの意味にもとれるのだ。なお、War を現在形に訳し、er を「ぼくは」と訳しているのは、この文が体験話法だからだ)。
ほとんど同じで、ちがっているのは「のに」と「から」だけだ。しかし、内容は正反対と言ってもいいほどちがってしまう。
前者は、音楽に感動するのは人間で、動物は感動しない、ということになる。後者は、人間よりも、むしろ動物のほうが、音楽に心を動かされる、ということになる。どちらに解釈するかは、そこをどう考えるかによるだろう。
「ここはある意味では『変身』解釈上の岐路ともなるような重大な個所のように思える」とまで三原弟平は書いている(『カフカ『変身』注釈』平󠄁凡社)。
邦訳では、初訳の高橋義孝(1952年)は「のに」派で、ここから27年間ずっと種村季弘(1979年)まで「のに」派がつづく。しかし、川村二郎(1980年)が初めて「とは」と訳す。ここから、丘沢静也(2007年)まで、また27年間、今度は「とは」派がつづく。しかし、浅井健二郎(2008年)がまた「のに」と訳し、ここから現在に至るまで、また「のに」派がつづいている(唯一の例外が2012年の酒寄進一の「とは」)。
つまり、訳者によって解釈が分かれているというより、時代によって分かれているわけだ。
どうしてそういうことになったかだが、おそらく『ロリータ』などの作品で有名な作家ウラジーミル・ナボコフの影響だと思われる(ただし、『アメリカのナボコフ』〔慶應義塾大学出版会〕などの著作もある秋草俊一郎は、邦訳にナボコフの影響は「まったくなかった」という意見だ)。ナボコフは1940年に渡米し、複数の大学でヨーロッパ文学の講義を行った。その講義録を1980年に出版している(『ヨーロッパ文学講義』として1982年には日本でも邦訳されている。現在は『ナボコフの文学講義』というタイトルで河出文庫から出ている)。
この本には『変身』の講義も入っているのだが、そのなかでナボコフは「から」説を強烈に主張している。
なにも音楽愛好家を敵にまわす気は毛頭ないのだが、一般的意味に解して考えると、音楽は消費者が享受するかぎりにおいて、文学や絵画よりも芸術の価値尺度上、より原始的で、より動物的な形式に属するものである。
(中略)
カフカが音楽一般について感じていたことは、わたしが今さっき述べたこと、すなわち人を茫然とさせ、麻痺させる、動物のような音楽の性質のことなのだ。このような彼の態度を銘記しておかなければ、今まで何人かの翻訳家が誤解してきたひとつの重要な文章を解釈することができないのである。その文章とは、文字通りはこういうものだ、「グレゴールはこんなに音楽に感動すべき動物だったのだろうか?」。つまり、人間の姿でいたときには、彼は音楽になんの関心もなかったが、この場面、彼が甲虫になったとき、初めてグレゴールは音楽に屈服するということだ──(後略)
(『ナボコフの文学講義』下巻 野島秀勝訳 河出文庫)
ここで「グレゴールはこんなに音楽に感動すべき動物だったのだろうか?」と訳されている原文(英語)は、〈Was he an animal that music had such an effect upon him?〉で、that は「とは」の意味で使われている。ナボコフが元にした、Willa & Edwin Muir訳(1948年)も that になっているので(本によっては since)、ナボコフが最初の「とは」派ではないが、その後の英訳に強い影響を与えたのは、やはりナボコフのこの強い断定だろう。「今まで何人かの翻訳家が誤解してきた」とナボコフが書いているように、たとえば Lloyd(1937年)は〈Could it be that he was only an animal, when music moved him so?〉と訳している。whenは「……ならば」「……とき」という意味とも、「……であっても」という感じにも解せるので、どちらの派なのか曖昧とも言えるが、おそらく「のに」派だろう。
that や since を「とは」派、when や if を「のに」派とするなら、英訳では、時代によってちがうというより、訳者ごとに判断が分かれている。数としては半々くらいだ。ただ、when や if をどっちつかずの訳とするなら、「とは」派が圧倒していることになる。批判版カフカ全集の編者のひとりでもあるマルコム・パスリーも「とは」派(that)だ。
ナボコフの影響以外に考えられるのが、人間中心主義からの脱却という1960〜70年代くらいから始まった流れだ。「人間が他の生物よりも優れていると考えるべきではない」ということが主張されるようになっていった。
三原弟平も、人間中心主義の観点からこう書いている(前掲書)。
彼はけだものじゃない、音楽に感動するから人間なんだ、というとらえ方だ。けれども、いってみればこれはけだものを差別する考え方、人間中心主義なのかもしれない。
ナボコフも、昆虫学者でもあり、昆虫が大好きだから、昆虫は音楽に感動しない、感動するのは人間だけだというような考え方は、とても容認できなかったのかもしれない。
カフカ自身も、動物より人間を上と考える人ではなかった。動物を主人公にした短編小説を多数書いている。小さくて弱いものへの共感が強く、そういう感性から、自分を「東洋人」と見なしていたほどだ。
では、「とは」派のほうが適切なのか?
しかし、現時点で最新の全訳である角川文庫の『変身』(2022年)の解説で、訳者の川島隆はこう書いている。
だが、拙訳ではあえて人間中心主義的な訳し方を採用した。カフカが接続詞 da を同時性の意味で用いるのは珍しいことではなく、特にこの場面では、身体は「動物」に変わったにもかかわらず意識の面ではまだ人間中心の価値観に縛られているグレゴールの滑稽さと哀れさを表現することに主眼があると思うからだ。
そして、川島隆は「こんなにも音楽に感動しているのに、それでも動物なのか?」と訳している。
なお、ここをどう訳すかについて、書籍で訳した当人が自分の考えを詳細に書いているのは、私の知る限りでは、ここで紹介した3名のみだ。年代順に、ナボコフ(1980年、『ナボコフの文学講義』下巻 野島秀勝訳 河出文庫)、三原弟平(1995年、『カフカ『変身』注釈』平󠄁凡社)、川島隆(2022年、『変身』角川文庫)。それぞれの説を読み比べてみるのも面白いだろう。
では、私はどう考えたかだが、カフカに動物に対する差別意識がなかったのはたしかだと思うが、この『変身』という小説では、虫になるということは、働くことができなくなり、家族に養ってもらうしかなくなり、さらに家族の負担となり不幸の原因となるという、そういう意味合いを持っている。だから、グレーゴルは人間に戻りたいと思っている。
グレーテが部屋の家具を運び出そうとしたときも(第17回)、そのほうが自由に這い回れると最初は喜ぶのだが、母親の「こんなふうに家具を運び出してしまったら、あの子が回復することを私たちがすっかりあきらめてしまったと、見せつけるようなことにはならない?」という言葉を聞いて、ハッとし、「部屋に何もなくなれば、どこだって自由に這い回れるだろう。でも、そんなことをしていたら、自分が人間だった過去もすぐにすっかり忘れてしまうのではないだろうか。(中略)家具は何ひとつ、動かしちゃだめだ。みんな、そのまま置いておかなければ。家具はきっとぼくに、いい影響を与えてくれる。だから、なくてはならない。あちこち這い回るのに家具が邪魔になるとしても、それはぼくにとって困ったことではなく、むしろすごくいいことなのだ」と考えている。虫として不便であっても、人間だったことのほうを、また人間に戻れるかもしれないことのほうを大切にするのだ。
そういうグレーゴルにとって、音楽に感動したときに思うのは、「自分は人間だ」ということだろうか、それとも「自分は動物だ」ということだろうか。次につづく文では、「まるで道が開けたかのようだった」と希望を見出しているのだ。
『変身』の文脈では、私はここは「自分は人間だ」のほうだと思う。グレーゴルの意識がこのときいかに変化していたにしても、自分が虫であることに生きる希望を見出すとは思えない。その後の展開とも矛盾する。
だから私は、「こんなにも音楽に心を動かされているのに、それでもぼくは人間ではないのか?」と訳した。
もちろん、これは私の考えにすぎず、正しいとは限らない。
ただ、誰の訳を読むかで、ここは意味が大きく変わってくるということは、おぼえておいていいかもしれない。
翻訳のそうしたちがいを、欠点と考える人もいる。原文通りが知りたいのに、訳者によってちがうのは、困ったことだと。しかし、私はクラシック音楽が演奏する人によって変わり、ある人の演奏では嫌いだった曲に、他の人の演奏では感動したりするように、あるいは、落語の同じ演目でも演者によってまるで面白さがちがうように、楽しむべき長所だと思う。原文はひとつなのに、びっくりするような新作翻訳に出合えるかもしれないのだ。翻訳の火によって、原作は何度も新たによみがえる不死鳥となる。
●待ちこがれていた未知の栄養
「まるで道が開けたかのようだった。それが何なのかわからないまま、ずっと求めつづけてきた、生きる糧への道が」というところは、少しわかりにくいかもしれない。この道は、直訳すると「待ちこがれていた未知の栄養への道」となる。だから、かなり意訳だし、私の解釈が入っている。
グレーゴルは「今ではもうほとんど何も食べなくなっていた」(第22回)。しかし、食欲がないわけではなく、「ぼくだって食べたくないわけじゃない」と思っている(第23回)。でも、間借人たちが夕食をがつがつ食べているのを見て、「でも、あんなものは食べたくない」とも思っている(同前)。
第23回でも引用したように、カフカの短編小説『断食芸人』に出てくる断食芸人のように、「私はうまいと思う食べ物を見つけることができなかった。もし好きな食べ物を見つけていたら、断食で世間を騒がせたりしないで、みんなと同じように、たらふく食べて暮らしたにちがいないんだ」(『絶望名人カフカの人生論』拙訳 新潮文庫)という状態なのだ。食べ物への拒否は、現実への拒否でもある。食べられないというのは、目の前の現実を受け入れられない/受け入れてもらえない、ということだ。好きな食べ物=生きていける現実が見つからないのだ。
これなら食べられる、これなら生きられるということがわかっているのなら、まだ探しようもあるが、それがどういうものなのか、自分でもわからないのだ。でも、わからないまま、それを強く求めている。あこがれている。
「待ちこがれていた未知の栄養」というのは、そういうことだと思う。
太宰治の短編小説『待つ』が思い出される。
ある小さな駅に、「私」は毎日行って、ベンチに腰をおろして、改札口を見ている。
いったい私は、毎日ここに坐って、誰を待っているのでしょう。どんな人を? いいえ、私の待っているものは、人間でないかも知れない。
(中略)
いったい、私は、誰を待っているのだろう。はっきりした形のものは何もない。ただ、もやもやしている。けれども、私は待っている。(中略)私は誰を待っているのだろう。旦那さま。ちがう。恋人。ちがいます。お友達。いやだ。お金。まさか。亡霊。おお、いやだ。
もっとなごやかな、ぱっと明るい、素晴らしいもの。なんだか、わからない。たとえば、春のようなもの。いや、ちがう。青葉。五月。麦畑を流れる清水。やっぱり、ちがう。ああ、けれども私は待っているのです。胸を躍らせて待っているのだ。
(青空文庫)
これを読んだときは、本当に衝撃だった。
ごく短いもので、文庫本で4ページ。今、青空文庫で確認してみたら2068文字だったから、原稿用紙5枚と少ししかない。
しかし、その衝撃は大きく、余韻は今に至るまでずっと響き続けている。
私もまた、何かを待っていると感じたからだ。病気をしてからずっと。それが何なのかはわからない。だけど今も、毎日、ずっと待っている。何を待っているのかわからないまま、待ちこがれている。
あなたはそんなことはないだろうか?
いくら待っていても、その何かがあらわれてくれることは、おそらくないだろう。しかし、グレーゴルは、そこに至る道が開けた気がしたのだ。
これはすごいことだ。たんに音楽ということではないだろう。もちろん、食べ物のことでもない。こういうふうになら生きていけるかもしれないという道を、見つけられた気がしたのだ。
グレーゴルは「妹のところまで突き進んでいって、スカートのすそを引っぱろう」と決心する。そんなことをしたら大変なことになるとは考えない。妹にも自分の気持ちが伝わると考えている。
なにしろ、これまで見つからなかった、自分の生きる糧への道が開けたのだ。そこを進むしかない。それが悲惨につながるとは、とても考えられない。
こんなふうに、光に向かって進んで行って、破滅してしまう人もいるのだろう。それこそ、火に飛び込む虫のようだ。
ただ、「なにしろ、ぼくほど演奏しがいのある相手は、ここには他に誰もいないのだ」というのだけは、たしかにそのとおりだろう。
●カエルの王子
もうぼくの部屋から妹を出したくない。少なくとも、ぼくの生きているあいだは。人をぎょっとさせる姿になったことも、初めて役に立つというものだ。部屋のすべてのドアのところで同時に待ちかまえ、侵入者にはシューシューと声を立ててやる。だが、妹に無理強いはしたくない。自分の意思でぼくのところにいてくれるというのでなければ。ソファに並んで座り、妹はぼくのほうに耳を寄せるんだ。そうしたらぼくは、打ち明けるんだ。おまえを音楽学校に行かせてあげると、ぼくはちゃんと心に決めていたんだ。こんな不幸さえ起きなかったら、この前のクリスマスに──そう、クリスマスはもう過ぎたんだよね?──みんなに言っていたはずなんだ。なんだかんだ反対されたって、かまうもんか。これを聞いたら、妹は感激してわっと泣き出すだろう。そうしたらぼくは、妹の肩のあたりまで伸び上がって、首にキスをしてやるのだ。店で働くようになってから、リボンも巻かず、襟のついた服も着なくなっていたので、むき出しになっている首に。
先の「なにしろ、ぼくほど演奏しがいのある相手は、ここには他に誰もいないのだ」から体験話法になり、ここはすべてそうだ。
そして、体験話法はここで終わりだ。『変身』には、これまで見てきたように体験話法がたくさん出てくるが、これ以降はいっさい出てこない。
グレーゴルの最後の気持ちの高まりだ。
前には妹が、他の誰もグレーゴルの部屋に入らないようにして、グレーゴルを独占しようとした。「グレーテは今、誘惑にかられていた。グレーゴルの境遇を、よりいっそう人が恐怖を感じるものにしたいという誘惑だ。そうすれば、これまでより、もっとずっと、兄のために尽くしてあげることができるのだ。というのも、何もなくなってがらんとした壁や床や天井を、ただグレーゴルだけが這い回っているような部屋には、グレーテ以外、この先、誰も足を踏み入れる勇気はないだろうからだ」(第17回)
そして今度はグレーゴルが、「もうぼくの部屋から妹を出したくない」と考えている。自分の姿が人をぎょっとさせるという悲しいことまでも利用して(これもグレーテが考えたことと同じだ)。
「部屋のすべてのドアのところで同時に待ちかまえ」というのはいかにも誤訳という感じがするし、実際、もっと現実的な内容に変更してある訳も多いが、原文にはこう書いてある。こんなことは現実には不可能だが、それだけグレーゴルの意気込みが凄まじいということだろう。
「だが、妹に無理強いはしたくない。自分の意思でぼくのところにいてくれるというのでなければ」というのは、一見、無理強いをしなくて立派なようだが、実際には、それ以上に過大な要求だ。自分の自由意志で、進んで自分のそばにいるというのでなければならない、というのだから。無理強いでは監禁になってしまう。グレーゴルは妹を監禁したいわけではなく、そばにいてほしいのだ。でもそれは、もっと贅沢な無理強い、自由意志の強制という、ひどくおそろしいことにもなりかねない。
グレーゴルは妄想する。妹とふたりでソファに並んで座って、妹が自分のほうに耳を寄せてくれるところを。音楽学校に行かせてあげるつもりだったことを打ち明けると、妄想の中の妹は感激してわっと泣き出してくれる。
わっと泣き出しているのだから、目はよく見えないだろう。顔を手でおおっているかもしれない。さらにうつむいているかもしれない。そのすきに、グレーゴルは伸び上がって、妹の首にキスをしようというのだ。
もし本当にそんなことをしたら、大変なことになるだろう。妹は悲鳴を上げるだろうし、気絶してしまうかもしれない。妹だって、虫になったグレーゴルの姿を無気味に感じているのだ。まして、今はさらにひどく汚れた状態だ。妹に自分の姿を見せないよう、ソファの下に隠れてさえいたグレーゴルが、どうしてこんな大胆なことを考えるのか? それは先に「こんなにも音楽に心を動かされているのに、それでもぼくは人間ではないのか?」とあったように、このときは自分を人間だと考えているからだろう。カエルがお姫さまとキスをしようとするのは、自分が本当は人間の王子だとわかっているからだ。
家にいたときには首を隠していて、働きに出るようになると、首にリボンも巻かず、襟のついた服も着ないというのは、どういうことなのか、私にはよくわからない。意味のわかる人がいたら、ぜひ教えてほしい。
妄想にひたりながら、妹に向かって居間の床を前進していくグレーゴル。
次回、ついに決定的な出来事が起きてしまう……。