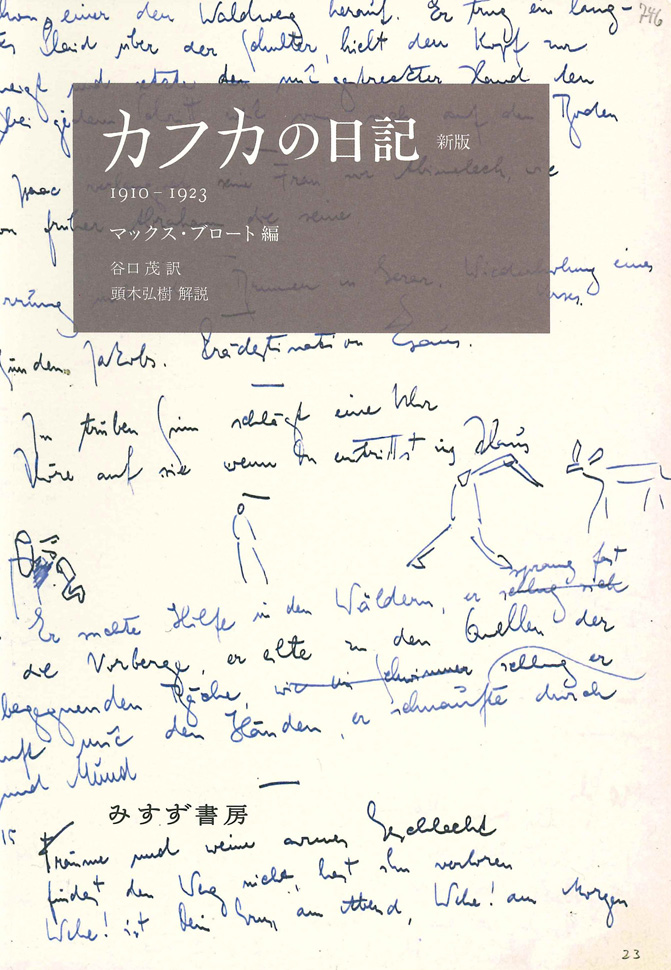この連載では、フランツ・カフカの小説『変身』を新訳しながら、超スローリーディングしていく(ものすごくゆっくり読む)。
さらに、読みながら私が思い出したこと考えたことも、脱線を気にせずに、どんどん書いていく。というのも、読書の半分は、本に書いてあることではなく、本を読みながら自分のうちにわきあがってきたことにあると思うからだ。
私の脱線につられて、みなさんもそれぞれに、いろんなことを思い出したり考えたりしていただけたら幸いだ。自分の城の中にある、自分でもまだ知らない広間。
それを開く鍵のような働きが、多くの本にはある。(オスカー・ポラックへの手紙 1903年11月9日)
●前回まで
働きだして忙しくなった妹は、グレーゴルの世話の手抜きをし始め、それはだんだんひどくなる。しかし、母親が手出しすることは許さない。グレーゴルの部屋はどんどん汚れていく。
掃除婦が偶然、グレーゴルの存在に気づく。しかし、おびえて辞めるようなことはなく、むしろ「クソ虫のじいさん」と呼びかけて、ちょっかいを出す。ただし、掃除をしてくれるわけではない。
経済的に苦しいザムザ家は、部屋を人に貸すことにする。ひとつの部屋を3人の男たちが借りる。この間借人たちは、家具などを持ち込むだけでなく、家全体の片づけを要求した。そのため、たくさんの不要品がグレーゴルの部屋に持ち込まれることに。
グレーゴルは、部屋の中を自由に這い回ることも難しくなり、ガラクタを動かしながら、なんとか這い回っていたのだが、だんだん動かすことが楽しくもなってきて、そんな自分が悲しくなる。
●ドアが開いても家族とのつながりは取り戻せない
間借人たちが居間で夕食をとることもあったので、居間のドアが閉ざされていることも増えた。だが、グレーゴルはさほど残念にも思わなかった。ドアが開いていても、もう居間の様子を気にすることもなく、家族に気づかれることもなく、部屋のいちばん暗い片隅でうずくまっていることが多かったのだ。ところがあるとき、掃除婦が居間のドアを少し開けたままにして帰った。夜になって、間借人たちが居間に入ってきて明かりが灯されたときにも、そのままだった。間借人たちはテーブルの上座にすわった。以前は父親と母親とグレーゴルがすわっていた場所だ。3人がナプキンをひろげ、ナイフとフォークを手にすると、すぐさま母親が肉料理の大皿を手にして現れ、すぐあとから妹がジャガイモを山盛りにした大皿を持ってつづいた。料理はもうもうと湯気を立てていた。食べる前にチェックしなければというように、間借人たちは料理の皿をのぞきこんだ。実際、真ん中の席にすわっている、他の2人に一目置かれているらしい男が、大皿の上で直接、肉にナイフを入れた。肉がちゃんとやわらかいかどうか、台所に突き返さなくてもいいかどうか、たしかめたのだ。男が満足したので、はらはらしながら見守っていた母親と妹は、ほっと息をついて微笑みはじめた。
グレーゴルの存在は当然、間借人たちには隠されているので、間借人たちが居間で夕食をとるときには、居間に通じるグレーゴルの部屋のドアは閉ざされたままになる。
このドアを夜だけでも開けてもらえるのは、少し前まではグレーゴルにとってとても大きなことだった。父親に投げつけられた林檎が背中にくい込んだままで苦しんでいるという、かわいそうな存在になったことで、家族から同情され、夜だけは開けてもらえるようになったのだ。思うように身体を動かせなくなったほどのひどい傷なのに、グレーゴルは「充分な埋め合わせを得られた」と満足していた。それほど彼はドアを開けてほしかったのだ。
ところが、そのドアを閉ざされることが増えても、グレーゴルはもうさほど残念に思わなくなっている。以前は「自分の姿が家族に見えないよう、暗闇の中にうずくまりながら、自分抜きの家族団欒の姿をながめ、その声を聞く」ことに熱心だったのに、今はちがう。今も暗がりにうずくまっているが、それは家族に自分の姿を見せないための配慮ではなく、もはや居間の様子を気にしていないのだ。
なぜこんなに変わってしまったのか。ひとつには、グレーゴルの世話のことで、妹と母親と父親が大騒ぎをくりひろげ、居間のドアが開いていたために、グレーゴルはその一部始終を見聞きしてしまったということがあるだろう。「こんな光景や騒音を見聞きさせないよう、ドアを閉めてあげようと、誰も思いついてくれなかった」ことにグレーゴルは腹を立てていた。ドアを開けてくれても、そこにいることを忘れているのでは、ドアを閉めてグレーゴルを家族の団欒から隔絶していたときと変わらない。
ドアを開けてもらえるようになったことで、家族とのつながりを少しは取り戻せたと思っていたことが、錯覚にすぎないと、そういう出来事で気づかされたのかもしれない。ドアの問題ではなく、もはやグレーゴルは人として気遣われていないのだ。
実際、家族に背を向け、部屋のいちばん暗い片隅でうずくまっているようになっても、その変化に家族は気づいていない。
●援助する側と援助される側
3人組の間借人たちが、ずいぶん大きな顔をしている。
以前は父親と母親とグレーゴルがすわっていた席にすわり、母親と妹がかいがいしく料理を運んでくる。できたての湯気がもうもうとあがる料理だ。量も多そうだ。しかも、それをすぐに食べるのではなく、取り分ける前に、大皿の上でナイフを入れるようなことをして、チェックする。気に入らなければ、台所に突き返そうというのだ。なんという傲慢な態度だろう。それなのに、母親と妹は、間借人たちが満足するかどうか顔色をうかがい、満足するとほっとして笑みをもらす。この笑みは、ほっとしたためでもあるだろうが、料理のことが一段落したので、今度は間借人たちに笑顔を振りまいているのでもあるだろう。まるで接客している店員とVIP客だ。
どうしてこんなに3人組は態度が横柄で、家族の者たちは卑屈なのか。
ひとつには、あとで出てくるが、「これまで人に部屋を貸したことがなかったので、間借人たちに遠慮しすぎて」ということもあるだろう。
しかし、それだけではこうはならない。部屋を貸す、借りるというのは、本来は対等な関係のはずだ。しかし、たとえば借りる部屋が見つからなくて困っている人が、貸しても貸さなくても平気という人から部屋を借りる場合、どうしても借りるほうが下手に出ることになってしまう。逆に、貸すほうがお金に困っていて、借りるほうはこの部屋でなくてもいいという場合、貸すほうが下手に出ることになる。ザムザ家の場合は、後者だ。3人組は、ザムザ家が部屋を貸すことに慣れておらず、お金に困って貸すことにしたのを感じとったのだろう。だから、かさにかかっている。客に逆らえない店員に対するように、自分たちの要求を強気で通そうとする。
ザムザ家において、3人の間借人は援助する側であり、家族は援助される側なのだ。医学書院の『精神看護』という雑誌の2024年9月号に齋藤美衣が「それは〈支援〉か〈施し〉か──「透明でない」わたしとして存在するために」という特別記事を書いている。その中に「わたしを含む『支援される』人は、これまでずっと、外部からの施しの視線、そして施されているという内なる視線を受けて言葉を失い、物を言わない透明な物として存在してきた」とある。この「外部からの施しの視線」と「施されているという内なる視線」というのはやっかいで、悪循環を起こす。つまり、「施している」という視線で相手を見たとき、相手も「施されている」という視線でこちらを見返しているのだ。あるいは逆に、「施されている」という視線で相手を見たとき、相手も「施している」という視線でこちらを見返しているのだ。自分の視線と相手の視線が一致するわけで、そうすると視線を交わすたびに、「外部からの施しの視線」も「施されているという内なる視線」もどんどん強化されていってしまう。それだけ、対等な関係からずれていく。
ザムザ家の家族が、間借人たちに対して卑屈なのは、もちろん、お金のことだけが原因ではない。もっと大きいのは、虫になった家族がいるということだ。それを隠しているということだ。その引け目があるから、どうしても卑屈になってしまう。不幸は人を困難に落とし込むだけでなく、卑屈にしてしまう。せめて卑屈にはならないようにと思っても、他人の態度が、自分の「内なる視線」が、それを許してくれない。幸福だったときの自然な鷹揚さ、人と自分が対等であると特に意識することもない、傷ついていない自尊心を取り戻すことは、とても困難だ。
●すわって食べることと、立って歩くこと
家族は台所で食事をしていた。ただ、父親は台所に行く前に、居間に入ってきて、制服の帽子を手に持って一度だけお辞儀をし、食卓の周囲をぐるりと回った。間借人たちはみんな立ち上がり、髭の中で何かもごもご言った。3人だけになると、間借人たちはほぼ黙りこくって食事をした。食事をする物音だけが聞こえてきた。グレーゴルが妙に思ったのは、3人が歯でものを噛む音がやけに耳につくことだ。まるで、ものを食べるには歯が必要で、いくら立派な顎があったって歯がなければどうしようもない、とグレーゴルに示そうとしているかのようだった。「ぼくだって食べたくないわけじゃない」とグレーゴルは心配になってつぶやいた。「でも、あんなものは食べたくない。間借人たちが食べて生きつづけ、ぼくが食べずに死んでいくとは!」
間借人たちが居間で食事をし、家族は台所で食事をしている。
ただ、父親だけは、台所に行く前に、居間に顔を出す。台所に直行するのでは、威厳が保てないということだろうか。あいかわらず、家でも制服を着たままだ。礼儀として挨拶をするというのなら、お辞儀だけでいいわけだが、さらに食卓をぐるりとひと回りしている。これは相手に圧迫を与えるにはいい手だ。
通常、すわっているほうより、立っているほうが地位が低い。食べているほうより、食べていないほうが地位が低い。だから、すわって食べている人の前に、立って食べずにいる人がいる場合、すわっているほうは自分が上だということを示せるし、立っているほうは自分が下だということを受け入れたかたちになる。よく映画でも、そういうシーンがある。権力者がすわって豪華な食べ物をゆっくり口に入れている前で、下っぱが立ったまま命令を受けたりしている。
ところが、これが逆転する場合がある。立っている者が歩き回る場合だ。それも食べている者の横や背後まで。すわっているほうが、立っているよりも敏捷に動きにくい。また、食べている状態というのは無防備だ。だから、立っている者に自由に接近されると、すわって食べている者としては落ち着かないし、脅威だ。デ・パルマ監督の『アンタッチャブル』という映画で、大物たちが集まって大きなテーブルを囲んで食事をしているときに、アル・カポネだけが立ち上がって、テーブルの周囲を歩く。すわって食事をしているみんなの背後を回るわけだ。それだけでみんなは落ち着かない気持ちになる。そして実際、カポネはある男を背後からバットで殴って殺してしまう。
「人が食事をしているときに、そばに突っ立つな」などと怒る人は多い。攻撃されると思うわけではなくても、なんとなく落ち着かないのだ。
食卓をぐるりと回るという圧迫を加えられた間借人たちは、みんな立ち上がる。父親に対しての礼儀でもあるし、すわったまま食べているよりも、そのほうがましだからだ。
そして、髭の中で何かもごもご言う。こういうとき、髭は便利だ。髭がなくても、もごもご言うことはできるが、髭があるとなおさらごまかしが利く。なにしろ、口の動きがよく見えないのだから。こういうとき、何か言わないわけにはいかないが、何かはっきり言いたくもないものだ。はっきりしゃべれと命令できるのはつねに上の者であり、もごもごと言うのはせめてもの抵抗だ。立ち上がる代わりに、言葉のほうははっきりさせていない。立ち上がったのはあくまで礼儀からであり、父親に対しても下手に出るつもりはないわけだ。
人の生活というのは、こういうどうでもいい細かな権力闘争に満ちている。どうでもいいのに、細かくこだわってしまう。
●食べたいけれど、この食べ物ではない
3人の間借人は食事中にしゃべらない。だから、食事の音だけが響いてくることになる。カフカが3人に雑談をさせなかったのは、食事の音だけをグレーゴルに聞かせたかったからだろう。今ではもうほとんど何も食べなくなっているグレーゴルに。
食事中にはさまざまな音がするものだ。ナイフやフォークが皿にあたる音などのほうがうるさそうなものだが、グレーゴルの耳にことさら大きく響いてくるように感じられるのは、「3人が歯でものを噛む音」だ。
これは、虫になったときから、グレーゴルには歯がないからだ。丈夫な顎はあるのだが、その音は「いくら立派な顎があったって歯がなければどうしようもない」とまで告げているように感じられてしまう。
総入れ歯になった人に聞いたことがあるが、歯がなくなると、食事はずいぶん味気なくなるそうだ。私はまだその経験はないが、少しはわかる気がする。というのも、病気の治療のため長期間、絶食したことがあるからだ。点滴で栄養はとっているので飢餓感はないのだが、だんだんと「何か噛みたい!」という気持ちがこみあげてくるようになった。自分はおかしいのではないかと心配になったのは、隣のベッドのおじさんが、自分が飼っている犬の写真を、ペット自慢で見せてくれたときだ。写真の中の犬は、骨の形をしたおもちゃだかガムだか、そんなものを噛んでいた。それを見たとき、思わず、「うらやましい!」と思ってしまったのだ。自分もそんなふうに噛みがいのあるものに、噛みつきたかったのだ。「食べたい」という欲求は、普段は漠然としたひとつのものだが、実際には栄養補給だけでなく、噛みたいとか、飲み込みたいとか、味わいたいとか、さまざまな欲求の集合体であるということを、このとき知った。
もはや歯がないグレーゴルにとっては、歯でものを噛んでいる音というのは、あこがれずにいられないものであっただろう。ことさら耳につくのも無理はない。
グレーゴルは「ぼくだって食べたくないわけじゃない」「でも、あんなものは食べたくない」とつぶやく。ここでカフカの短編小説『断食芸人』のこの一節が思い出される。第13回でも引用したが、あらためて引用しておこう。
「私はうまいと思う食べ物を見つけることができなかった。
もし好きな食べ物を見つけていたら、
断食で世間を騒がせたりしないで、
みんなと同じように、
たらふく食べて暮らしたにちがいないんだ」
(『絶望名人カフカの人生論』拙訳 新潮文庫)
断食を芸としていた男が、死ぬときに、こう言い残すのだ。『変身』が書かれたのは1912年で、『断食芸人』は1922年。ちょうど10年前の『変身』にすでに『断食芸人』の萌芽があったということだ。
それもそのはずで、第13回でも書いたように、これはカフカ自身の「食べること」に対する思いだ。みんなと同じようにたらふく食べたいのだけれど、できない。みんなと同じように普通に生きたいのだけれど、できない。決して、そうしたくないわけではないのだけれど。
生きていくことに不安を感じながら、むさぼり食べて、エネルギーを得て、力強く生きる、ということができるはずもない。食べ物への拒否は、現実への拒否でもある。食べられないというのは、目の前の現実を受け入れられない/受け入れてもらえない、ということだ。
旺盛な生命力にあこがれながらも、そうやって生きていくのは他人であって、自分ではなかった。3人の間借人のように、他人の家でもたらふく食べて生きつづけられる人間もいれば、グレーゴルやカフカのように、自分の家でも食べられずに死んでいく人間もいる。
好きな食べ物=生きていける現実が見つからないのだ。
●変身以来のヴァイオリン
ちょうどその晩──あのとき以来、グレーゴルは耳にしたおぼえがなかった──ヴァイオリンの音が台所から響いてきた。間借人たちはすでに夕食を終えていて、真ん中の男が新聞を引っぱり出してきて、あとの2人に1枚ずつ配り、みんなで椅子の背にもたれて読み、煙草を吸っていた。ヴァイオリンが鳴りはじめると、3人は聞き耳を立て、それから立ち上がって、廊下のドアのところまでそっと爪先立ちで行き、そこで身体を寄せ合って立ったままでいた。その様子を台所でも察したらしく、父親が声をかけた。「ヴァイオリンの音がうるさいですか? それならすぐにやめさせますが」「とんでもない」と真ん中の男が言った。「娘さんはこちらに来て、ここで弾きたいのでは? この部屋のほうがくつろいで弾きやすいでしょう」「それはどうも!」と父親は、まるで自分がヴァイオリンを弾いていたかのように言った。間借人たちが居間に戻って待っていると、ほどなく父親が譜面台を、母親が楽譜を、妹がヴァイオリンを持ってやってきた。妹は落ち着いて演奏の準備を整えた。両親はこれまで人に部屋を貸したことがなかったので、間借人たちに遠慮しすぎて、自分の家の椅子なのにすわろうとしなかった。父親はドアにもたれ、きちんとボタンをとめた制服の上着の、2つのボタンのあいだに右手を差し入れていた。母親のほうは間借人のひとりに椅子をすすめられてすわったが、彼がたまたま置いた場所から椅子を動かそうとしなかったので、部屋のすみっこにひとり離れていることになった。
この「あのとき以来」を、「虫に変身してからずっと」「下宿人たちが来てからずっと」「その晩のはじめからこのときまでずっと」と説明している訳もある。
私は「虫に変身してからずっと」だと思う。兄が虫に変身して以来、グレーテにはヴァイオリンを弾く時間的なゆとりも、精神的なゆとりもなかっただろう。音楽学校に通うという夢も完全に断たれた。
では、なぜこの晩、急に弾きはじめたのか。みんなが働きだして、下宿代も得られるようになって、少し気持ちに余裕ができたのか。それとも、台所で食事をしている父母をあわれに思い、少しでもなぐさめようとしたのか。
私は若い頃にギターを少し弾いていたが、初めての長い入院から戻ったとき、自分の部屋に置いてあるギターを見て、なんだか不思議な気がした。自分のもののような気がしなかった。気楽にギターを爪弾いていた自分が、パラレルワールドの自分のような気がした。本当に今の自分にも弾けるのかと思って、手にとったおぼえがある。もちろん、手はおぼえているわけで、弾けた。手が勝手に弾いているような感じだったが。それでも、弾けるということに、自分の演奏に、かなりなぐさめられた。グレーテも、もしかすると、そんなふうなことだったのかもしれない。
意外にも、3人の間借人がヴァイオリンの音色に反応する。3人のうちのひとりがリーダー格で、少しは区別されているものの、前回述べたように、3人はほとんど一体となって動く。そろって聞き耳を立て、そろって立ち上がり、そろって爪先立ちで移動し、同じ場所で身を寄せ合って立っている。
3人は居間で演奏してもいいと寛大な態度を示す。父親は喜び、おそらく母親と妹も喜んで、みんなで居間にやってくる。
父親は遠慮して椅子にすわらないが、それでも制服はぴしっと着ているし、自慢の金ボタンのあいだに手を入れている。母親は椅子をすすめられてすわるが、間借人がたまたま置いた位置から椅子を動かそうとしないところに、遠慮があらわれている。
いずれにしても、全員が居間に集まったのである。グレーゴルも自分の部屋からのぞいている。
●なぜ身なりを気にしなくなっていくのか
妹は弾きはじめた。父親と母親はそれぞれ自分のいるところから、妹の両手の動きをじっと見守っていた。グレーゴルは演奏にひきつけられて、前に少し身をのり出し、もう頭が居間の中に入っていた。以前は周囲に気遣いできる人間であることを誇りにしていたのに、最近は人のことをろくに気にしなくなっていて、それを変だとさえ思わなくなっていた。それなのに、今では以前よりももっと、身を隠したほうがいい状態になってしまっていた。なにしろ、自分の部屋はほこりだらけで、ちょっと動いただけでも舞い上がり、それを全身にかぶっていたのだ。糸くずや髪の毛や食べ物のかすも背中やわき腹にくっついていて、それらをひきずりながら這っていた。以前は1日に何度も仰向けになって絨毯に身体をこすりつけていたのだが、あらゆることに無関心になっていて、そういうこともしなくなっていた。そんなありさまだったのに、しみひとつない居間の床の上に、遠慮なしに這い出してしまったのだ。
「掃除婦が居間のドアを少し開けたままにして帰った。夜になって、間借人たちが居間に入ってきて明かりが灯されたときにも、そのままだった」という箇所からここまで、グレーゴルはずっと観察者だった。
『変身』は三人称で書かれているのだから、グレーゴルが見ていない状態でも、居間のことを描写してもいいわけだが、カフカは決してそうしない。あくまで視点はグレーゴルと共にある。グレーゴルが見ることができることだけを見る。
しかし、ドアが開いていたのは、のぞくためだけではない。ここからグレーゴルは行動しはじめる。
あれほど家族のことを気にかけていた、「以前は周囲に気遣いできる人間であることを誇りにしていた」グレーゴルが、今では「人のことをろくに気にしなくなっていて、それを変だとさえ思わなくなっていた」。そして、ほこりまみれで、糸くずや髪の毛や食べ物のかすも背中やわき腹にくっついているのに、「以前は1日に何度も仰向けになって絨毯に身体をこすりつけていたのだが」「そういうこともしなくなっていた」。これはなぜなのか?
私はベートーヴェンのことを思い出した。ベートーヴェンはあるときから、だんだん服装に無頓着になっていった。初めてベートーヴェンに会った人が「ロビンソン・クルーソーかと思った」と言ったそうだ。あだ名も「汚れた熊」になってしまい、あんまりひどい身なりなので、怪しまれて逮捕されたことまであった。
なぜそんなことになったのか? それは難聴になったからだ。
難聴と身なりに何の関係があるのか? こんな関係があったのだ。
不機嫌で、打ち解けない、人間嫌い。
私のことをそう思っている人は多い。
しかし、そうではないのだ!
私がそんなふうに見える、
本当の理由を誰も知らない。
私は幼い頃から、情熱的で活発な性質だった。
人づきあいも好きなのだ。
しかし、あえて人々から遠ざかり、
孤独な生活を送らなければならなくなった。
無理をして、人々と交わろうとすれば、
耳の聞こえない悲しみが倍増してしまう。
つらい思いをしたあげく、
またひとりの生活に押し戻されてしまうのだ。
(「ハイリゲンシュタットの遺書」1802年10月6日
『絶望名言 文庫版』飛鳥新社)
ベートーヴェンは難聴になったために、人を避けて孤独に暮らすしかないと感じていたのだ。会いたくても人に会えない、ひきこもりのような暮らしをしていた。いわば無人島にいるようなもので、ロビンソン・クルーソーのようになるのは、むしろ自然なことだろう。いろいろ身だしなみを整えて、それでも人に会えないとなると、ますます悲しくなってしまう。
病院の入院患者も、最初は毎日きちんと髭を剃っていたりするのだが、だんだん無頓着になっていく。社会とだんだん遠ざかっていくのだから、無理もない。しかし、看護師さんたちはこれをとても嫌がった。どうにしかしてきちんと髭を剃らせようとした。そのことが不思議だったが、髭を剃らないことを放置しておくと、今度はお風呂に入らなくなり、着替えをしなくなりと、だんだん「汚れた熊」になっていくのかもしれない。身体的にも精神的にもあまり健康的とは言えないだろう。
グレーゴルも、ずっとひきこもっている状態で、最近では掃除婦しかのぞきにこない。掃除もしないままの汚い部屋に、ずっとひとりで閉じこめられているのだ。これでいつまでも身だしなみを整えていられるほうが不思議だ。もはや、人目を気にすることもなくなり、自分が汚い姿であることにも無頓着になるほうが、むしろ正常な心の変化と言えるだろう。
そんなグレーゴルが、だけど、妹の弾くヴァイオリンの音楽には思わず引き寄せられる。「あらゆることに無関心になって」いたのに、そういう心がちゃんと残っている。
そうして思わず這い出した居間の床は、グレーゴルの部屋とはちがって、きれいに磨き上げられているのだった。しみひとつない床の上の汚れたグレーゴルは、大きな生きたしみに見えるかもしれない。
さて、這い出してしまったグレーゴルはいったいどうなるのか。
次回、林檎の事件以来の、決定的な出来事が起きてしまう。