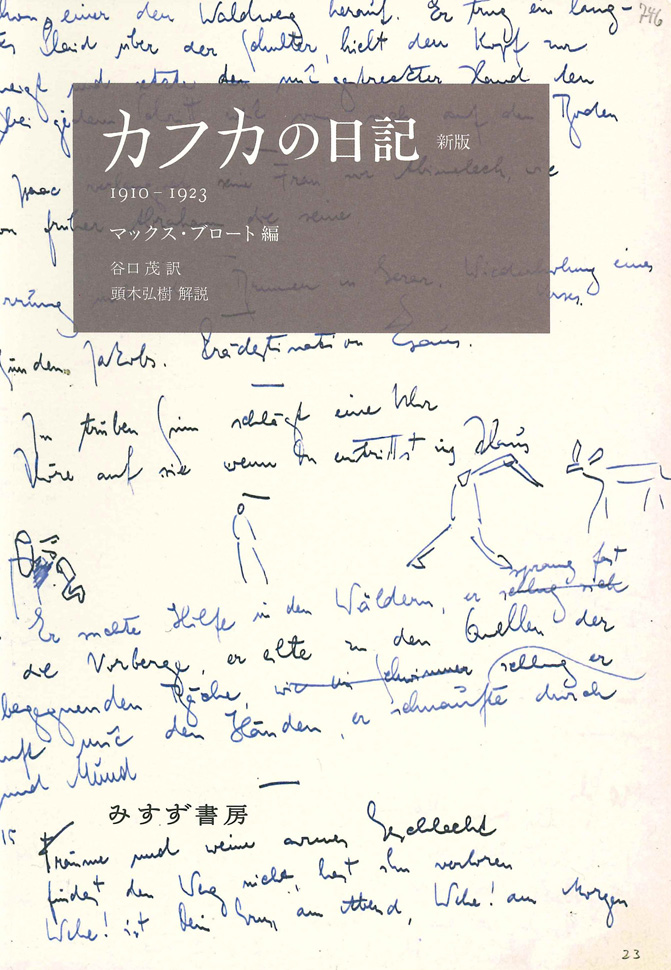この連載では、フランツ・カフカの小説『変身』を新訳しながら、超スローリーディングしていく(ものすごくゆっくり読む)。
さらに、読みながら私が思い出したこと考えたことも、脱線を気にせずに、どんどん書いていく。というのも、読書の半分は、本に書いてあることではなく、本を読みながら自分のうちにわきあがってきたことにあると思うからだ。
私の脱線につられて、みなさんもそれぞれに、いろんなことを思い出したり考えたりしていただけたら幸いだ。自分の城の中にある、自分でもまだ知らない広間。
それを開く鍵のような働きが、多くの本にはある。(オスカー・ポラックへの手紙 1903年11月9日)
●前回まで
働き手のグレーゴルが虫になってしまったことで、これまで働いていなかった父親、母親、妹がそれぞれに仕事を始める。しかし、それでも家計は苦しい。生活を切り詰めながら、しかも働きづめで、家族はどんどん疲れ果てていく。代々受け継いできた宝石類も売り払う。これまでいた女中にも暇を出す。
しかし、こういう貧窮した家に、それでも限られた時間だけ雇われてやってくる掃除婦がいる。朝と晩だけ来て、いちばん骨の折れる仕事を任されてしまう。
もっと狭い住まいに引っ越したほうがいいのだが、家族は不幸に打ちのめされていて、その元気が出ない。虫になったグレーゴルを運ぶのが難しいことを言い訳に、現状のままでいる。
貧乏になると、世間からどんな目にあわされるのか、家族は味わわされることになる。母親と妹は、父親を寝かせたあと、身を寄せ合って泣く。あるいは、涙さえ出なくなる。
しかし、そんな貧乏な家に、さらに雇われる掃除婦の境遇には、目を向けることはない。掃除婦はそんな境遇でも平気に見えるが、それくらい頑健でなければ、生きてこられなかっただろう。
グレーゴルは、眠らなくなっていく。自分が家族を助ける日がまた来るのではないかと夢想する。いろんな知り合いの顔が思い浮かぶが、もうみんながとても遠く感じられる。
家族に対する怒りがこみ上げてくることもある。忙しくなった妹は、もう以前のように熱心に世話をしてくれることはなくなり、どんどんあつかいが雑になっていく。食事も雑になり、部屋はほこりだらけになっていく。
見かねた母親が、グレーゴルの部屋の掃除をする。それに気がついた妹は、侮辱を感じ、身を震わせて泣きだす。手抜きをしていただけに、なおさら手出しはされたくなかったのだ。居眠りをしていた父親も飛び起きるほどの騒動になり、父親は母親にも妹にも、もうグレーゴルの部屋の掃除はするなと怒鳴る。開いたままのドアから、グレーゴルはその一部始終を見聞きし、ドアを閉めようと誰も思いついてくれないことに腹を立てる。
●掃除婦がグレーゴルに気づく
しかし、妹が仕事で疲れ切って、もう以前のようにグレーゴルの世話をするのは嫌になってきたとしても、母親がその代わりをする必要はなかったし、それでグレーゴルがほったらかしにされるわけでもなかった。今では掃除婦がいたからだ。この老未亡人は、これまでの長い人生、どんな最悪な状況も、頑健な身体のおかげで生き延びてきたようだったが、最初からグレーゴルのことを、本当に忌み嫌いはしなかった。あるとき、べつに好奇心にかられたわけではなく、たまたまグレーゴルの部屋のドアを開けたのだ。びっくりしたグレーゴルは、追い立てられたわけでもないのに、あちこちと部屋を這い回った。掃除婦はそれをあっけにとられてながめながら、両手を腹の前で組んで突っ立っていた。それ以来、いつも朝と晩に、ちょっとだけドアを開けて、グレーゴルのことをのぞくようになった。はじめのうちは、グレーゴルを自分のほうに呼び寄せようとした。「こっちへおいで、クソ虫のじいさん!」とか「ほうら、クソ虫のじいさんだ!」とか、彼女としては親しみをこめたつもりの言葉をかけてきた。でも、グレーゴルのほうはいっさい返事をせず、ドアが開けられたことさえ無視して、その場から動かなかった。掃除婦のこんな邪魔で無意味な気まぐれを許すんだったら、いっそ部屋の掃除を毎日するように言いつけてくれればいいのに!
たまたまグレーゴルの部屋を開けた掃除婦は、あわてて這い回る大きな虫を目の当たりにする。まったく思いがけないことであったはずだ。さすがに「あっけにとられて」いるし、両手を身体の前で組んでいるのは、いくらか防御的な姿勢なのかもしれない。
今までの女中は、ひとりはグレーゴルが虫になったとたん辞めたし、もうひとりの辞めなかったほうも、決してグレーゴルの部屋には近づこうとはせず、台所にひきこもっていた。
しかし、この掃除婦はちがう。いつも朝と晩、グレーゴルの部屋をのぞくようになる。掃除婦がザムザ家に来るのは朝と晩なので、来たときには必ずということだ。声をかけて自分のほうに呼び寄せようとさえする。まるで、犬か猫でも見つけたかのような態度だ。
「クソ虫のじいさん」というひどい呼び方をしているが、これは彼女の目にはフンコロガシのような虫に見えたからだろうし、「じいさん」というのは、弱っていてよろよろしているからだろう(グレーゴルは背中に林檎がくい込んだままで、苦しみつづけている)。本当に年寄りと思ったのか、おぼつかない動きだからそう呼んだだけなのか、それはわからない。
いずれにしても、グレーゴルには嬉しい呼び方ではない。クソ虫ではなく人間だし、じいさんではなく青年なのだから。掃除婦の呼びかけを完全に無視するのも当然だろう。
しかし、今、グレーゴルを気にかけてくれる者は、この掃除婦しかいない。以前は、他の誰もグレーゴルの部屋に近づかないよう、妹が気を配っていたが、もうそんなこともないようだ。許されているわけでもないだろうが、掃除婦がグレーゴルの部屋をのぞいていることは、黙認されているか、あるいはまったく気づかれていない。それだけ家族のグレーゴルへの関心が薄くなっているということだ。もちろん、不幸の根源としては、つねに強烈に意識されているだろうが、グレーゴルの日々の暮らしについては、どうでもよくなってしまっている。掃除婦がこんなにしょっちゅうグレーゴルの部屋をのぞいているのに、家族からまったく注意されないというのは、そういうことだ。それを感じるからこそ、グレーゴルもなおさら腹が立つのだろう。
「掃除婦のこんな邪魔で無意味な気まぐれを許すんだったら、いっそ部屋の掃除を毎日するように言いつけてくれればいいのに!」という一文は、体験話法だ。感情がそれだけ高まっている。
「いっそ部屋の掃除を毎日するように言いつけてくれればいいのに!」ということは、やはりグレーゴルの部屋はまったく掃除されなくなっているようだ。妹もあいかわらず掃除をせず、母親ももうこりて手を出さない。父親が怒鳴ったとおりになったわけだ。掃除婦も、のぞくだけで、掃除してくれるわけではない。厳しく忙しい生活の中で、頼まれてもいない仕事までやる余裕があるはずもない。
ではなぜ、掃除婦はグレーゴルにかまうのか? そもそもなぜ他のみんなのように、グレーゴルを嫌がらないのか? 最初はたまたまドアを開けてしまったとしても、もう二度と開けないようにするのが普通だろう。
カフカは、掃除婦がグレーゴルのことを「本当に忌み嫌いはしなかった」と書いている。この「本当に(eigentlich)」は翻訳では省略されたり、「まったく嫌がらなかった」とか「特別には嫌がらなかった」という感じで訳されることが多いが、けっこう大事な言葉ではないかと思う。「真から嫌ってはいなかった」(高本研一、1966年)、「実のところ嫌っているともいえなかった」(川村二郎、1980年)、「忌み嫌う気持ちは本来、持っていなかった」(多和田葉子、2015年)などの訳が、この言葉を生かしていると思う。
私の「本当に忌み嫌いはしなかった」は直訳で、こなれているとは言えないし、シンプルに「忌み嫌いはしなかった」とするのと何がちがうのか、たんに少し強調されているだけではないかと思う人もいるかもしれない。
しかし、世の中には、忌み嫌わないようにしようと思っていても、本心では忌み嫌ってしまう人もいるし、ひどい態度のようでも、本当には忌み嫌わない人もいる。そういう意味で「本当に」と付けてあるのではないかと思うのだ。
掃除婦は、決して態度がいいわけではない。グレーゴルの姿にびっくりしているし、勝手にのぞくし、「クソ虫のじいさん」とひどい呼び方をするし、汚れた部屋を見ても掃除してくれるわけではない。しかし、グレーゴルのことを理解して、それで忌み嫌わなくなったというようなことではなく、そもそも最初からなのだ。それはなぜか?
この掃除婦は鈍感なのだとか、もともと図太いのだとか、そういうとらえ方もできるだろう。しかし、カフカはここで「この老未亡人は、これまでの長い人生、どんな最悪な状況も、頑健な身体のおかげで生き延びてきたようだった」とわざわざ書いている。この掃除婦は、頑健な身体でなければ生き延びられなかったような、最悪の状況も何度もあるような、そんな人生を長く生きてきているのだ。社会的にも虐げられる側、差別される側にいるだろう。だからこそ、より差別的になって、自分よりさらに弱い者を見つけて残虐に攻撃しようとする人もいる。もしそういう人が、こっそり部屋に隠されている虫を見つけたとしたら、家族も消えてほしがっていると知ったとしたら、どんなことになっていたか……。しかし、幸いにも、この掃除婦はそうではなかった。差別される側として生きてきたからこそ、差別心がなかった。異形の存在にびっくりはしても、「本当に忌み嫌いはしなかった」。普通にコミュニケーションをとろうとした。
また、この掃除婦は、これまでの苛酷な長い人生で、いろいろな経験をしただろう。普通の人は目にしないような社会の暗部も目にしたかもしれない。女中を雇う余裕のない、さまざまな家庭に出入りして、「いちばん骨の折れる家事」ばかりさせられているのだから、さまざまな不幸や秘密も漏れ知ったことだろう。だから、開けたドアの先に何があっても、それほど動揺しなかったのかもしれない。虫は初めてでも、虫のようなことはこれまでも経験していたことだろう。
もちろん、家族とちがって、グレーゴルが人間であろうが虫であろうが、掃除婦には何の関係もない。第三者だから冷静でいられるということもある。
いずれにしても、掃除婦の登場は、これまでとはまったく異なる人物の登場であり、『変身』は「家族だけの閉ざされた物語」と思われがちだが、じつはそうでもないのである。
●掃除婦は動じない
ある早朝のこと──もう春が近いのか、激しい雨が窓ガラスを叩いていた──掃除婦がまたいつものように呼びかけてきたとき、グレーゴルはひどくむかっ腹が立って、よろよろとゆっくりではあったが、掃除婦のほうに向き直り、攻撃するかのような構えを見せた。ところが掃除婦は怖がるどころか、ドアの近くにあった椅子をつかんだ。高く持ち上げただけだったが、口をかっと開けて立ちはだかっている様子を見ると、その椅子をグレーゴルの背中に振り下ろすまでは、口を閉じないつもりらしかった。「おや、かかってこないのかい?」と、グレーゴルがまた向きを変えるのを見て言い、椅子をおとなしく部屋の隅に戻した。
「春」と、季節の話が初めて出てきた。『変身』のラストは春めいた感じがする。ラストを春にしようと、このあたりで思いついたのかもしれない。
掃除婦のほうはいつものように呼びかけただけなのに、グレーゴルはひどくむかっ腹を立てる。こういうことはあるものだ。いつもと同じことを言っただけなのに、急に相手が怒りだす。怒られたほうは、「今日は機嫌がよくないのかな。それで八つ当たりされたのかな」と思ってしまいがちだが、そうとは限らない。機嫌のよくない日だったかもしれないし、これまでの蓄積かもしれない。ぎりぎりまで水の入ったコップでも、けっこうコインが何枚も入る。まだまだ大丈夫なように思えてくる。でも、やっぱりいつかはあふれる。そして、機嫌のよくない日だったとしても、不快なことを言うほうがよくないし、八つ当たりではない。
グレーゴルは攻撃するかのような構えをしてみせる。これは自分の姿が人には気味悪がられているとわかっているからこそだ。弱っている今の自分に、本当に攻撃する力がないことはわかっている。怒っているのに、のろのろとしか動けない姿を相手に見せるのは屈辱だ。それでも、自分がとびかかりそうにすれば、相手は悲鳴をあげて逃げるかもしれないと自覚しているわけだ。コロナ禍のとき、「オレはコロナだぞ」と叫んで人を脅かす人がいたが、ウソの場合はともかく、本当の場合には、それで相手があわてふためいて逃げ出せば、ずいぶんみじめな気持ちになっただろう。四谷怪談のお岩さんの幽霊は、自分の顔を見せて、相手を怖がらせるが、あれはお岩さんにとってもずいぶんきついのではないか。
掃除婦は、まったく動じない。これはむしろグレーゴルにとっては、ましな反応だったかもしれない。
掃除婦は、椅子を高く持ち上げ、グレーゴルが本当に攻撃してくれば、その椅子を背中に振り下ろす気だ。昔、奥深い自然を案内してもらったとき、自然を愛し生き物を大切にしている案内人さんが、毒のある生き物が迫ってきたときには、ためらいなく殺すので、意外で驚いたことがある。自然の中で生きるとは、攻撃に対しては、ためらわず攻撃し返すということなのかとも思った。掃除婦は、やさしいわけでも、慈悲心があるわけでもない。攻撃に対しては攻撃し返す。しかし、過剰な攻撃はしない。椅子を持ち上げはするが、それを振り回したり、むこうから攻撃をしかけてきたりはしない。グレーゴルが攻撃をやめれば、自分もおとなしく椅子を元に戻す。グレーゴルの覇気のなさに、いくらかのものたりなさも感じながら。
●3人組の登場
グレーゴルは今ではもうほとんど何も食べなくなっていた。用意された食事のそばをたまたま通りかかったときだけ、遊び半分でひと口かじってみるが、何時間も口の中に入れたままで、たいていは吐き出してしまった。最初のうち、食べられないのは、部屋の状態を悲しんでいるせいだと思っていた。しかし、部屋の変化にはじきに慣れた。置き場所のなくなったものをこの部屋に入れておくようになって、それらの品々がずいぶん増えていた。この家のひと部屋を3人の男たちに貸したからだ。気難しい人たちで──ドアのすき間から見えたのだが、3人とも髭面だった──整理整頓にうるさかった。自分たちの部屋だけでなく、この家に住むことになったからには家全体を、とくに台所をきちんと片づけないと気がすまなかった。不必要なものや汚れたものには我慢がならないのだ。しかも彼らは、家具や生活用品のほとんどを自分たちで持ち込んだ。そのため、もともとあった、たくさんのものがいらなくなった。売れるようなものではないし、かといって捨てるのはもったいないものが。それらが全部、グレーゴルの部屋に運び込まれたのだ。台所から灰箱とゴミ箱がやってきたのもそのためだ。いつだって忙しい掃除婦は、とりあえず必要のないものがあると、さっさとグレーゴルの部屋に放りこんだ。不要品とそれをつかんでいる手しか見えないことが多かったのは、グレーゴルにとってせめてもの幸いだった。
前回(第21回)、「昼も夜も、グレーゴルはほとんど眠らなかった」とあった。さらに今回、「グレーゴルは今ではもうほとんど何も食べなくなっていた」とある。眠れないことと、食べないことは、カフカ自身の特徴でもあるが、言うまでもなく、睡眠と食事は生きる基本だ。これらがうまくいかなくなると、死に近づいてしまう。
好物などを考慮してくれることはなくなったが、それでも妹はまだいちおう食事を用意してくれているようだ。食べられないようなものを出すことはできても、まるで何も出さずに人を餓死させるというのは、なかなかできることではない。
生きるために大切な食事を、グレーゴルはもう「たまたま」「遊び半分」でしか行わなくなっている。しかも、吐き出してしまう。
前にも書いたように(第13回)、「食べものへの拒否は、現実への拒否でもある」。ここでグレーゴルは、部屋のひどいありさまのせいで、食べられなくなっているのだと思っていた。しかし、そうではなかった。では、原因は何だったのかは、まだここでは語られない。
話は、なぜ部屋がひどいことになっているのかという説明のほうに進んでいく。そして唐突に、また新しい登場人物たちが現れる。3人の間借人たちだ。
ひと部屋を3人の男たちで借りるというのは、かなり狭苦しい感じがするし、3人はいったいどういう関係なんだと、いろいろ疑問に思うかもしれない。しかし、そういう説明はいっさい与えられない。しかも、3人を描き分けることもない。ここだけでなく、このあとも。容貌まで、「3人とも髭面だった」と共通している。髭面と、髭なしと、チョビ髭だったりしないのだ。
普通の小説なら、3人をきちんと描き分けるだろう。描き分けないのなら、なにも3人にする必要はない。ひとりの間借人ということにしても、展開上、ぜんぜん何の問題もない。なのに、なぜわざわざ3人にして、同じ顔で、同じことを同時にするという、なんとも不自然なことにしたのか? 前衛的な手法なのか、ギャグなのか。
しかし、じつはこういう3人組は、昔話などの口承文学の世界ではおなじみの登場人物なのだ。朗読好きなカフカが書いた作品には、目で読む文学とは異なる、口承文学(口で語り耳で聞く文学)の特徴が多々見られる、カフカは口承文学の文体で書いている──というのが私の持論なのだが、この3人組もその特徴のひとつだ。いちばん有名でわかりやすい例は、白雪姫の「7人のこびと」だろう。7人のこびとは、描き分けられることはない。ディズニーの映画『白雪姫』では、7人のこびとにそれぞれ名前と個性が与えられているが、原作のグリム童話では名前も個性もない。そして、7人はいつもいっしょに行動する。7人そろって山に行く。4人行って3人残るようなことはしない(だから白雪姫はいつも、7人のこびとといっしょか、ひとりでいるかで、ひとりのときに義母に3度、殺されかける)。7人は同じようにしゃべり、同じように考え、同じように判断する。7人のあいだで意見が分かれたりしない。
だったら、ひとりでいいじゃないかと思うかもしれない。実際、ひとりのことも多い。しかし、「三人組、七人組、十二人組になって登場する」ことも多く、それはなぜかというと、「昔話は数字一、二、三、七、十二を好む」のだ(マックス・リュティ『ヨーロッパの昔話――その形と本質』小澤俊夫訳 岩波文庫)。
カフカの長編小説『城』では2人の助手が登場するが、これは主人公のKと合わせて3人組を形成したと言える。そして、この2人の助手はやはり描き分けられることはない。それどころか、Kはこう言う。「きみたちがちがっているのは名前だけで、そのほかはまるで似ている」「ぼくはきみたちを、ひとりの人間のようにあつかい、2人ともアルトゥールと呼ぶことにしよう」2人を見分けることをせず、同じ名前で呼ぶのだ。
カフカの長編小説『審判』の終章でも、2人の処刑人が現れるが、どちらも「フロックコートを着て、青白く、太っていて、頭のシルクハットは動かすことができないように見えた」。つまり、外見の区別がつかない。2人は主人公のKに腕をからませて、3人でひとつになる。「いま彼らは3人とも、そのように一体となっているので、そのうちのひとりが誰かに殴り倒されたり投げられたりして、たたきのめされれば、全員が同じ目にあってしまうだろう。それはほとんど無生物のみが形作ることのできる統一体だった」
『変身』でも、このあと(次回になるが)、この3人組がいかに描き分けられないかに注目して読んでみていただきたい。
●自分の部屋が物置になる
3人の間借人は、みんな髭面だ。髭については、前にも書いたように(第14回)、カフカは生涯、一度も髭を伸ばすことがなかった。髭そりの調子がよくない日は外出をやめたりしているほどだ。大学生のときの集合写真を見ると、当時の男性は大学生になるともうみんな髭を生やしているのに、カフカだけ生やしていない。カフカの父親も当然、髭を生やしていた。
3人の間借人が髭面であることは、ある種の男らしさを示しているのだろうし、「気難しい人たち」ということにもつながるのだろう。間借りをするだけで、家全体のことに口を出し、整理整頓をさせる。台所のことにまで口を出す。「不必要なものや汚れたものには我慢がならない」とのことだが、虫になった今のグレーゴルはまさにそれに該当しそうだ。
彼らのせいで、たくさんの家具や生活用品が不要品と見なされ、これまでの場所からどかされて、行き場を失う。そして、それらがすべてグレーゴルの部屋に運び込まれることになる。妹はかつて、グレーゴルが自由に這い回れるように、部屋の中のものをすべて外に出そうとした。それが今や、不要品がグレーゴルの部屋に持ち込まれ、グレーゴルが這う場所はなくなっていくのだ。
進学や就職などで親元を巣立った人は、久しぶりに帰省したときに、自分の部屋が物置になっていて、あららと思ったことがあるかもしれない。私も帰省したときに、自分の部屋に米袋がたくさん積んであって、びっくりしたことがある。ベッドに寝ることはできたのだが、普通は部屋の中にないものが置いてあるのはかなり異様で、寝にくかった。他人の部屋でも、誰かが自分のために整えている部屋というのは、それなりに快適なものだが、雑多なものが乱雑に置いてある部屋というのは、とても落ち着かない。もう家に戻るつもりがなくて、一泊か二泊するだけなら笑い話だが、また戻ってくるつもりの場合は、一時的にせよ、自分の部屋が物置になっているのは、嬉しくないし、人によってはかなり不愉快に感じるだろう。
まして、ずっと住んでいるのに、物置にされればなおさらだ。そんなことは普通ないと思うかもしれないが、そうでもない。お年寄りの部屋には、「ちょっと置かせてくださいね。他に置き場所がないんで」などと不要品が持ち込まれたりしがちだ。活発に動いていなくて、いつもこたつに入っていたりするから、広い部屋の隅にものを置くくらいいいだろうなどと思ってしまうのだ。まして、寝たきりになると、動かないのだからスペースは必要ないだろうということで、ベッド以外の場所が物置化することもある。しかし、いくら動かなくても、視界には入る。また、モノの存在感というものもある。面倒を見てもらっているから文句が言えなくて、「いいよ、いいよ」と快く受け入れても、実際には精神的な苦痛や圧迫はかなりあるはずだ。自分の部屋というのは、自分が置きたくて置いたものだけであることが、落ち着きを与える。ゴミ屋敷のような部屋に住んでいる人でも、他人のがらくたを勝手に部屋の中に持ち込まれたら怒るはずだ。
なお、「灰箱(Aschenkiste)」というのは聞き慣れない言葉だろうが、日本でも江戸時代には、煮炊きをしたかまどに残った灰を箱に入れてためておいて、灰を買いに来る「灰買い」に売っていたそうだ。大きな商店や銭湯では、灰箱どころか灰小屋まであって、大量に灰をためて売り、灰問屋もあれば、灰市も立ったそうだ。ザムザ家でも、料理やストーブなどから灰が出て、それを箱に集めていたのだろう。それをどう処理していたのかはわからないが(ご存じの方がいらしたら、教えていただきたい)。
掃除婦は、家族から指示されたのだろうが、不要品をどんどんグレーゴルの部屋に放りこむ。やはりグレーゴルに同情心があったり、やさしかったりするわけではない。不要品と手しか見えないことを、グレーゴルが幸いと感じているのは、掃除婦の顔なんか見たくもないということだろう。今のグレーゴルにかまってくれるのは、その見たくもない顔の掃除婦だけなのだが。
●楽しいことが悲しい
掃除婦はいつか折を見てそれらのものをまた取り出すか、全部まとめて捨てるかするつもりだったのだろうが、実際には投げ入れた場所にそのまま置きっぱなしになった。グレーゴルはそのあいだを縫うようにして這い回っていたが、がらくたを動かしてしまうこともあった。そうしないと這い回れないから、しかたなく動かしていたのだが、そのうち、だんだん動かすのが楽しくなってきた。とはいえ、そんなハイキングのあとでは、死ぬほど疲れて悲しくなり、何時間もじっと動かなかった。
捨てるにはおしいし、いつかまた使うかもしれないし、ずっと使わないようだったら、そのとき捨てよう、などと思って物置とか、あまり使っていない部屋とかに入れておいたものは、けっきょくそのままになってしまいがちだ。そういう経験のある人は多いだろう。
それがただの物置や本当に使っていない部屋ならいいのだが、グレーゴルの場合は、自分が生活している部屋であり、しかも自分はその部屋でしか生活できないのだから、たまったものではない。自由に這い回ることもできない。しかたなしに、動かせるものは動かす。ところが、そうしているうちに、動かすのが楽しくなってきてしまう。こういうところが、人間の生きていく力とも言えるし、悲しいところとも言える。ぜんぜんやりたくなかったことでも、やっているうちに、そこに喜びを見いだしてしまう。そうしないとやっていけないからだし、どんなことにも達成感とか、工夫の余地とかがあるからだ。たとえば、やりたくなかった仕事でも、やっているうちに楽しくなってきた人もいるだろう。それは幸せなことでもある。しかし、ふとわれに返って、自分が本当にやりたかったのはこんなことではなかったのにと悲しくなってしまうこともあるだろう。私自身の経験でも、病気のせいで、日常生活でさまざまな工夫をしなければならない。それがうまくいくと、達成感を覚えて、上機嫌になったりしてしまう。しかし、次の瞬間には、ずどんと悲しくなる。こんな工夫は、病気でなければ、しなくてもいいことであり、じつのところは、みじめにあがいているだけなのだから。
グレーゴルも、がらくたを動かすことが楽しくなってきたとはいえ、背中に林檎がめりこんで弱っている身体で、ものを動かしたりするのはかなりの負担だろう。死ぬほど疲れるのも無理はない。そして、自分の今の境遇、それなのに楽しくなってしまっている自分に、悲しくならずにはいられないだろう。何時間も動けなくなるのも当然だ。
そんなふうにグレーゴルの部屋を物置にしてしまうきっかけとなった3人の間借人たちによって、次回、グレーゴルはさらに部屋のドアを閉ざされることになる。