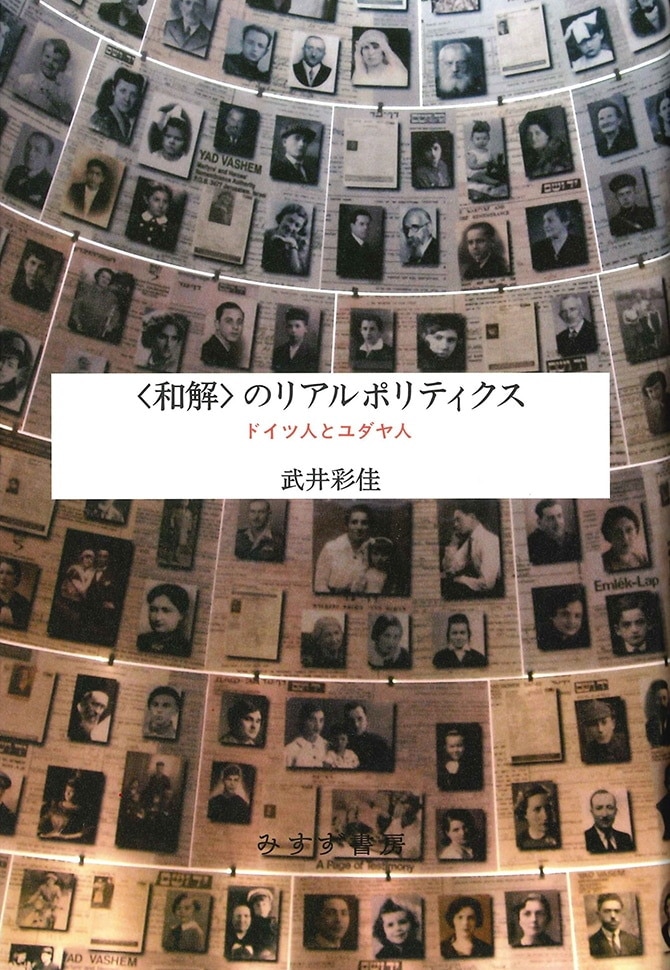中学校進学の壁
その2
諸事情により前回から1年近く経ってしまったが、その理由は読み進めればわかることとして、パリ近郊の国際リセ付属小学校に子どもを通わせる親の間では、付属中学への進学が一つの山と考えられていた。基本的に付属中に進むことができれば、高校(リセ)にも上がれるのだが、中学進学時に一定数が本人の成績、適正、その他の理由で振り落とされるシステムとなっていた。
どういうことかというと、国際リセはインターナショナルスクールでありながら公立なので、フランスの公立校のカリキュラムの上に、フランス語以外の言語(通常は生徒の母語)によるバイリンガル教育が乗っている。このバイリンガル教育の実施主体が、14のパートナー国が運営する日本セクション、アメリカ・セクション、ドイツ・セクションなどの各国セクションである。キャンパスは幼稚園から高校まで同じ場所にあるのだが、受入キャパシティの問題から、生徒全員が本キャンパスで学べるわけではなく、本キャンパスに通う生徒がいわば「正規生」である。本キャンパスで受け入れられない子どもは、普段は学区の公立校に通い、週に2、3回、バイリンガル教育を受けるためだけに外から通ってきていた。しかし、外の学校から午後だけ国際リセに通うというシステムは小学校までで、中学進学時に本キャンパスで受入可能な人数まで選抜がなされる。つまり付属中学に入ることが、高校(リセ)まで上がるための必要条件なのである。
選抜はイギリスとアメリカのセクションで特に厳しいとされていた。外から通ってくる子どもも含め、生徒数がかなり多いからだ。それは運営上の資金集めの面もあるだろう。学費の支払いが必要なのはバイリンガル教育の補習部分のみなのだが、所属セクションによって授業料が大きく異なる。日本セクションは極めて良心的な学費であったが、イギリス・セクションの家庭が払っていたのは日本人家庭の10倍くらいの額だと聞いた。それでも英米本国では私立学校の学費が非常に高いため、インターナショナルスクールでこの値段なら安いものだと多くのイギリス人やアメリカ人の親が考えるようだった。
実際、アングロサクソン系の国に比べてフランスは教育コストが比較的低いので、フランスの公立インターナショナルスクールからオックスブリッジやアイビーリーグに進むというのは魅力的かつ効率的な進路である。英米の名門私立大学に入る競争は極めて熾烈なため、トランプ一家のような大口の寄付者の子弟として「レガシー枠」で入れる場合はともかく、進学はかなり難しい。ハリウッドセレブが、大学の裏口入学を請け負う業者に大枚をはたいて、子どものSAT(学力基礎能力試験)のスコアを上乗せしたり、学習障害などないのに偽の診断書で試験時間の延長を得たり、スポーツとは無縁な生徒がボート部の選手としてアスリート枠で受け入れられたりといった不正が発覚して、大問題となったのが記憶に新しい。もはや、「ある程度」稼ぎが良いという程度の親が提供できる環境では、アメリカではエリートコースには乗れないのである。
このため、海外の名門高校を卒業したバイリンガルもしくはトリリンガルだという経歴はアピールになる。日本でも進学校に進めなかった生徒が、高校時に海外留学をして「海外帰国生」の枠で大学を受験する、一種の「敗者復活戦」のルートが親の経済力次第で存在し、これを斡旋する業者もいるが、そのハイスペック版といったところだろうか。同じようなことは、中国人学生が本国での苛酷な入試制度や就職事情の中で敗退し、早稲田をはじめとする日本の私立大やその大学院に外国人枠で入り、最終的に中国への凱旋帰国を狙うのに通じるものがある。どこの国でも子どもの成功を望む親は必死だが、そこで社会的な上昇気流に乗るのも資金が必要だ。
さて、毎朝半べそで学校に通っていた息子であるが、彼は幸いなことにそのまま付属中学に進めることになった。それは彼の能力いかんの問題というより、日本セクションでは先に小学校入学時の選抜で人数を絞り、中学進学時に振り落とされる子どもがあまり出ないように設計されているためであった。これは前もって苛酷な選抜を調整するという、ある意味日本的な温情といえたが、息子は欠員が出た時の編入生なので、いわば満員電車から数人降りたときに偶然乗り込めたような人であった。それでも私たち両親は、中学進学時で電車から降ろされるものと思っていたため、大いに安堵した。
さて、息子はフランス語ができない子どもが集められる集中フランス語のクラスで一日の大半を過ごしていたが、このクラスの仲間の3分の1ほどが、付属中学校への進学が認められなかった。そうした場合、子どもたちは学区内の公立中に進むことになり、それは国際リセに通わせるためにあえてこの学区に引っ越し、1年間子どもの尻を叩き続けた親にしてみれば、大きな屈辱に違いなかった。その事実を受け止める親もいれば、抵抗する者もおり、息子が親しくしていたイギリス人の子どもの親は、自身の子どもの付属中への進学を求める嘆願書にサインしてくれとお願いに来た。ここで振り落とされることが何を意味するか誰もが理解していたため、クラス全員の親が署名したと思うが、地区の教育委員会に即時却下された。また、泣き虫のオランダ人マティスは、スパルタ教育を嫌悪して自ら進学を希望しなかった。
小学校の終わりは、一つの分かれ道の様相を呈し、選別に残れなかった仲間との別れと、これから始まる中学への期待と畏れが入り交じる、親にも子どもにも、甘酸っぱい瞬間であった。
メリトクラシーを支えるのは能力ではない
実はこの文章を書いている今、息子はフランスで国際リセ付属中には通っていない。息子は進学が認められたのだが、想定していなかった理由で進学を諦めることとなった。彼の父親、つまり私の夫の深刻な病状が判明し、フランスでの教育を断念して日本に帰国したのである。
研究者としての自分にとって、子どもに他国の教育を受けさせる意味は、社会格差や移民受入の現状、人種差別といった日本の教育では極力見えないようにされている問題の近くに一度身を置いてみることにあった。実際、ハーレムの小学校には豊かな社会の中の貧困や、将来の格差のスタート地点があった。しかし同時に地域の連帯や一種の寛容さについて知る場所でもあって、上の子ども2人は今でも、教育的部分を除けば、ハーレムの学校が一番面白かったと言う。
逆にフランスでは、表向きは人種・ジェンダー・宗教による差別を許さない平等な社会国家におけるエリート形成とは何なのか、知ることができると思われた。自分も含めて、子どもが将来的に勝ち残れるように場外戦を繰り広げる親たちの姿を観察するに、最適な場所に違いない。それは子どもが実際にリングに上がる前に、ほぼ決着がついているという仕組みになっているのだが、リングに上がるまでの前哨戦でのふるい落としの実態や、それがどのような根拠で正当化されているのかを知ることは、これから日本にも来るだろう格差の固定化について考える鍵を与えるものと思われた。つまりハーレムもパリ近郊の学校も、方向は異なるものの、一種の参与観察なのであった。
夫の病気は、自分の子どもを社会実験の被験者にするなという戒めであっただろう。ところが、病気というやむにやまれぬ事情で帰国が決まったとき、私たち親が感じたのは、まさに「無念」以外になかったことを告白する。それは、本線を走る列車に乗り込めたのに、そこから自らの決断で降車して、出発する列車を見送るような感覚であったように思う。「せっかくがんばったのに」と悔しがるのは子どもではなく、親の方であるというのがポイントで、子どもら本人は親のそんな思いはどこ吹く風で、多くの場合、勉強から解放されて内心喜んでいただろう。息子も例外ではなく、泣きながらフランス語の動詞活用を暗記していた自分の姿は3日で記憶から抹消され、帰国した翌日からゲーム三昧の日本の小学生に復帰していた。
今振り返ると、当時親として感じた悔しさの中身はいったい何だったのかと思う。それは自分の中のメリトクラシーへの一種の信仰から生まれていたのではなかったか。努力すれば上に行け、また能力のある者はそれだけの社会的報酬(リワード)を得てしかるべきだという、能力主義的な制度への信頼。そこではフェアな競争が成立しているという理解。
メリトクラシーは実際には能力や実績を根拠とする制度ではなく、むしろそれ以外の要素に大きく規定されるにもかかわらず、能力に基づくと信じるところに、本質的な欺瞞がある。自分には能力があると「信じる」人々により、制度は維持されてゆくのであり、その意味で欺瞞はより深いようにも思われた。
資本のリレー
フランスのエリート教育への挑戦を諦めて2年後の現在、子どもたちが判断されていたのは「何の」能力だったのかと考える。10歳やそこらの子どもが将来的に「やっていける」「能力が足りない」と判断できるほどパフォーマンスの違いがあったとはとても思えず、やはりそれは本人の資質というよりは、家庭環境や親の職業など、子どもの後ろにあるものも含めて総合的な判断がなされていたように思う。ではそれが「不正」なのかというと、そうと言いきることも難しい。2人の生徒が能力的に同程度のパフォーマンスを示したと仮定すると、一方が教育に理解のある家庭の出身で、兄弟もその学校で学び良い成績で卒業している子どもで、もう一方の子どもは、不安定な家庭環境にあることが見て取れ、家庭内のジェンダー規範に制約を受けるとすると、今後のパフォーマンスに差が出る可能性を考慮することは、「不正」だろうか。
国を引っ張るエリートを育成するという理念を持つ国家としては、教員が選抜において学力以外の要素も含めて、「確率的に」より成功しそうな生徒を選ぶという行為は、正当なものに思われるだろう。教員が10歳児の能力を正しく測定することはできなくても、教育現場での経験知から、また社会学的な経験値としても、経済力と勉学に対する理解のある家庭で育つ子どもの方が、最終的な到達点が高いと予測することはありうるからである。もちろんフランスは経済的に不利な家庭や、そういった家庭が多い地域に教育的なてこ入れもしており、固定化した状況に落ち込んでいる生徒をすくいあげる制度も持っている。しかし一部の個人はすくいあげられるが、全員ではないため、結局一般的な統計がものを言うことになる。これはフェアなのか、フェアでないのか。
人種的マイノリティや移民といった社会的弱者の状況について考える際に、100メートル走の比喩が使われることがある。例えばアメリカ黒人のように、抑圧の歴史がある集団の場合、平等なスタートラインに立ったとしても、背中に背負っている過去からの重荷があって速く走れない。そうした場合、同じスタートラインにつくという名目的な平等(equality)では、これまでに蓄積されてきた経済・教育資本の差を縮めることはできないため、彼らのスタートラインを多少前にずらすことで、結果の公正さ(equity)を担保する必要があるとされてきた。それがアファーマティブ・アクション(積極的差別是正策)の基本的な考え方であるが、現在アメリカでは大学入試における人種を理由としたアファーマティブ・アクションは違憲である。
個人の競争である100メートル走に対し、メリトクラシーはむしろ世代を超えたリレーに例えられる(1)。どういうことかというと、資本は通常親から子へと継承され、その最も可視的な形は親の死亡時における遺産の相続である。しかし現在の社会においては、富の継承は親の死のずっと以前から始まっている。それは、欠乏からの自由や安全な生育環境といった最低限の事項は当然のこと、家族関係による人的コネクション、効率的に教育目標に到達するためのノウハウ、芸術に触れる機会が育む感性、留学・異文化体験などを通して継承される。日本でも最近「体験格差」という言葉を聞くが、その蓄積は個人の最終学歴やその後の経済的到達点にも影響する。
こうした形の富の継承は数値として現れにくいために、それとして認識されにくいものの、実態としては子どもの社会化を通した富の継承に他ならない。これがブルデューの言う「文化資本」であるが、無形の価値でもあるため、その人の好みや振る舞い、所作といった個人の特徴として認識されがちである。またこのような社会資本を持つ人は、これを自分の能力であると考えるために、あたかも生来的に備わっているかのごとく振る舞う。しかし実際にはこれらは極めて社会的に形成されている。
つまりメリトクラシーのリレーにおいては、選手は前走者である親から不平等なスタート地点を受け継いでゆくのだ。このため、誰かがバトンを落とすといったことが起きない限り、大逆転は望めない。
日本の進む方向
教育格差とともに学歴格差が固定化されつつある日本ではあるが(2)、それでもまだ欧米と比べると、社会経済的な背景が個人の人生の到達点をほぼ決定するような社会にはなっていない。それは日本が平等圧力の強い社会であり、格差の拡大を好まない国民の性向と関係しているだろう。日本では、メリトクラシーのリレーで数世代前から一番前を走ってきた世襲政治家のような人たちまでが、自分も「庶民」であることをことさらに強調しなければ、選挙において支持が得られない。どぶ板選挙というものが存在するのも、政治家が市井の人々の代弁者を自認するがゆえだろう。
国のリーダーが庶民である必要があるのかというと、私はマクロン大統領が自身を「フランス市民」だと誇る場面はよく見るが、「庶民」であると強調するところを見たことがないし(そもそも彼が執務を取っているのは「エリゼ宮殿」である)、もとより億万長者であるトランプ大統領に至っては、公職にあっても富の拡大を求め続けていることを隠してさえいない。
日本人はお金に関連する不正には強く怒り、これに対して政治も敏感に反応するため、ある意味では庶民の代表であるという政治家のスタンスは、ポピュリスト的な主張への迎合につながる。しかし逆に言えばこうした「庶民寄り」のポーズが、議席を維持したいという政治家の思惑もあって、残酷な格差社会の到来に対する一種の防波堤として機能している。自民党が「国民政党」であるというのはまさにこの点にあり、一方では自由主義的な競争原理を導入し、他方では平等主義的な社会政策も維持しようとする、方向の異なるベクトルが同じ政権党の中に存在することで、日本を適度な、つまり社会の怒りが爆発して暴動が起こらない程度の格差社会に押しとどめているように思う。
実際には、この国でも富裕層による富の固定化とその子孫への継承がステルスで進行中なのだが、彼らが妬みの対象となることはあるにせよ、これを解体せよという声は生まれにくい。富の拡大再生産を続ける上層に対して、あまり怒りが向けられないのも日本の特徴のように思われる。例えばフランスだと「黄色いベスト」運動のように、経済的不利益に対する怒りを感じる層による巨大なデモなどが発生し、しょっちゅう社会機能が麻痺するのだが、日本ではそれが見られない。それはやはり固定的な富裕層があまり可視的でないこと、またその富の規模も、アメリカのようには極端でないこともあるだろう。何せアメリカでは、上位1%の富裕層が、国の富の3割以上を手にしている。
日本で人々の怒りが向けられるのは、制度から最大の利益を得ている集団ではなく、むしろ外国人や移民といった、外から来て自身との競争関係にあるように見える人々である。日本の排外的な傾向はまず、いわゆる「不良外国人」に向けられるが、それは彼らの文化宗教的な特徴や、日本の道徳観念と相容れない行為により、実際に目立つためでもある。彼らの可視性はネット社会では過剰に増幅するが、現実にはクルド人をネットで叩いたところで、格差社会の進行には歯止めがかからない。
これに対し、有利な状況にある集団は有利な状況を維持したまま、知識という富も含めて、資本を継承してゆく。彼らは制度の中で合法的にもリレーの先頭を走り続ける。また彼らこそが社会の制度設計を行っている集団であるので、自らに不利な変更を好んで導入する可能性は低い。そうした中で、能力がある者は相応の社会的報酬を得るという語りが、実際の受益者を不可視化するイデオロギーとして再生産されるのである。
注
- Stephen J. McNamee, The Meritocracy Myth: Who Gets Ahead and Why, Lanham: Rowman & Littlefield, 2024, p.208.
- 教育格差と学歴格差の違いについては、「ふつう」の人生を想像する | 松岡亮二「『凡庸な教育格差社会』で」 | せかいしそう