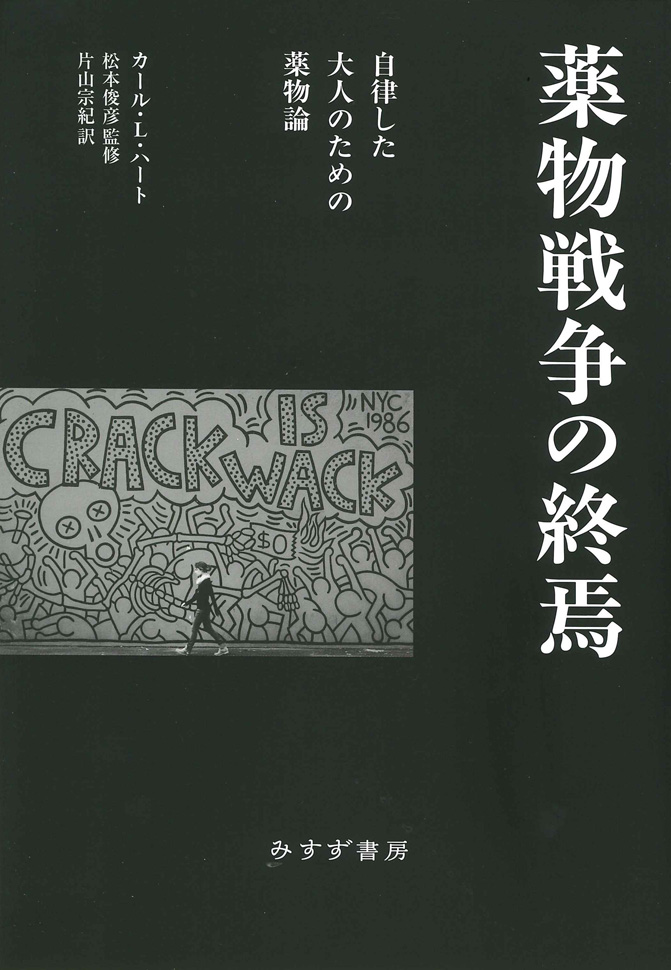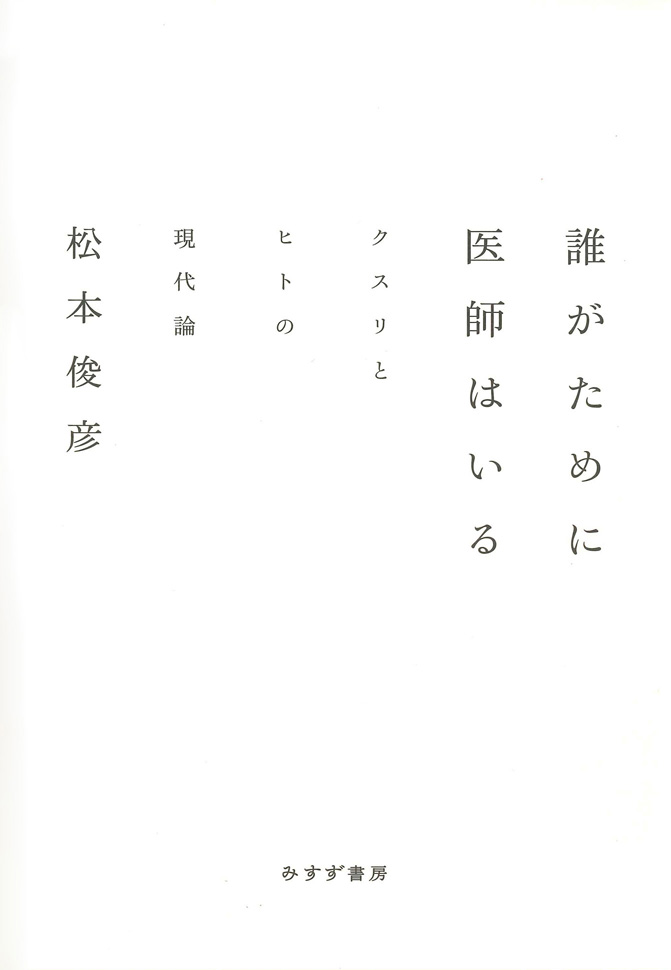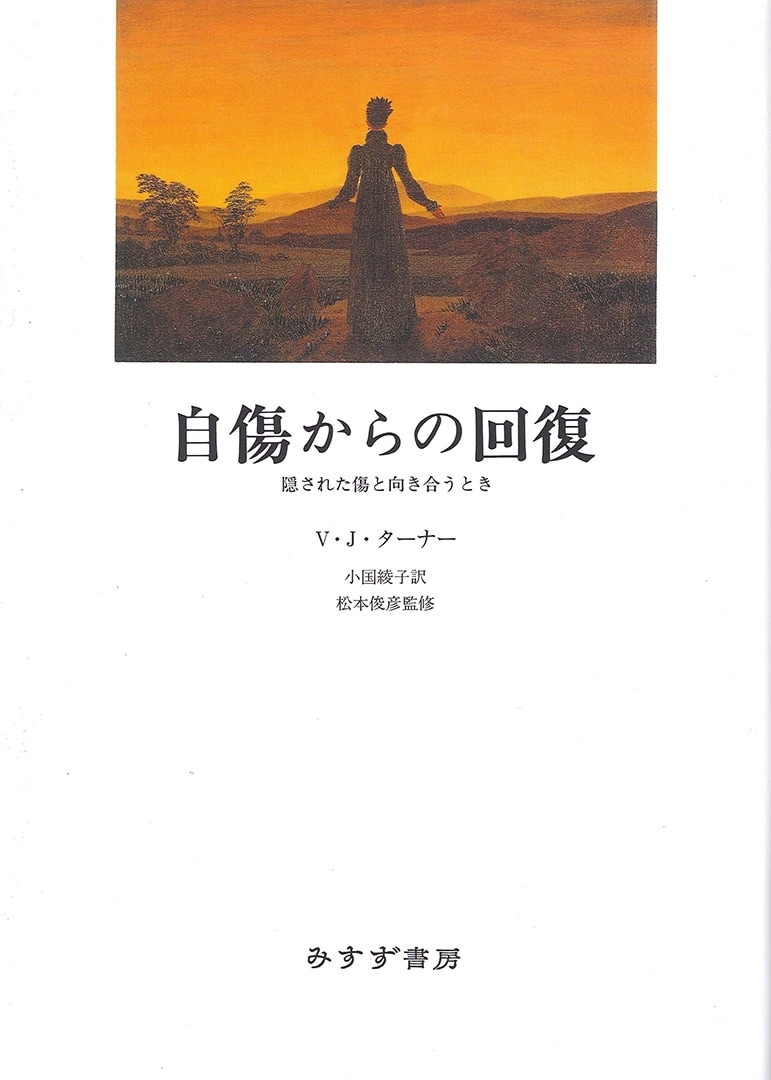2021年初夏の午後、私は、開始時間が迫った会議を目指して地下鉄駅構内を急いでいた。息を切らしながら階段を駆け上って地上に出たまではよかったが、今度は、おびただしく林立する官公庁ビル群のなかで道に迷ってしまった。途方に暮れた私は、会議の場所をGoogleマップで確認しようと思い直し、ジャケットの内ポケットからスマホを取り出した。
するとそのとき、すぐ近くで応援団風の勇ましい声が響いたのだ。
「松本先生、お疲れさまです。会議はこのビルです。頑張ってください。応援してます」
驚いて顔を上げると、目の前のビルの入口に、ドレッドヘアの大柄な若者が3名、私を遮るように立ちはだかっている。全員、大麻タバコをふかすボブ・マーリーの顔写真――アルバム『Catch A Fire』のジャケット写真だ――がプリントされた、お揃いのTシャツを着ていた。
一瞬、恐怖を覚えて身構えたが、「あ、そういうことか」と、私はすぐに事態を理解した。彼らは私が何者で、これから何をする予定なのかを知っているのだ。そう、そのとき私は、厚生労働省が主催する大麻取締法改正に関する有識者会議に出席するところだった。
彼らは大麻愛好家、あるいは、大麻規制の緩和を願う人たちなのだろう。なにしろ、レゲエと大麻は縁深い。いまでも覚えているのは、レゲエに熱中していた学生時代、毎年夏に野外ライブに参加するたびに、いつもどこからともなく重く甘ったるい匂いの煙が漂ってきたことだ。ガラムというインドネシア産タバコの匂いに似ていたが、少しココナッツの香りが混じっていた気がする。
当時の私は、それが一体どんなタバコなのかと興味津々で、どこかで売っていないかと、ライブ会場を探し回ったものだ。それくらい好きな匂いだった。後に依存症専門病院に勤務するようになって、それが大麻の匂いであると知ることになるわけだが、もしもずっと知らないままでいたら、私はどこかの段階で確実にそれに手を出していただろう。
話を会議に戻そう。
その会議は、政府の有識者会議としては異例なことに、秘密主義が貫かれていた。毎回、会議の開催場所は秘匿されており、委員にさえ期日直前まで知らされなかった。それだけではない。新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に会場には一般傍聴人を入れず、傍聴を許可されたのは事前登録をした記者だけで、記事にする際には発言者の個人名を出さないことが義務づけられた。もちろん、議事録も発言者の個人名は伏せられて作成された。
有識者会議発足から早半年を経過し、その日は、結論をとりまとめる最終会議だった。思うに、その大麻愛好家たちは、委員リストのなかで「一番話がわかりそうな人」として私に期待し、どこかで極秘の会議情報を入手して、応援に駆けつけたのだろう。もっとも、あいにく議論は大麻愛好家には厳しい流れとなっていて、いまさら流れを変えるのは困難だった。
私は、ドレッドヘアの男たちに軽く会釈をすると、意を決してビルのなかに入っていった。
今回の大麻取締法改正には医療上の大義があった。エピディオレックスなる医薬品が小児の難治性てんかんに効果があり、すでに欧米諸国では正式な治療薬として承認されていた。それなのに、大麻成分由来医薬品であるために日本では使えなかったのだ。その状況を変えるべく、厚生労働省には、学術団体などから同薬剤の国内承認を求める声が寄せられていた。
もちろん、治験だけならば従来の法律でも実施可能だが、日常診療でこの薬剤を処方することはできない。というのも、大麻取締法は「大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること」を厳しく規制していたからだ。その意味で、法改正は医療上不可欠だった。
問題は、法改正のどさくさに紛れて、政府が、これまで所持罪はあっても使用罪がなかった大麻に関して、新たに使用罪を創設しようとしている、という点にあった。
最近10年あまりで、大麻規制に関する国際的潮流は大きく変化した。現在、医療目的の大麻使用を認めている国は、オランダ、英国、スペイン、フランス、ベルギー、オーストリア、ポルトガル、フィンランドなどおよそ50カ国におよんでいる。すでにウルグアイやカナダにおいては大麻の嗜好的使用が合法化されていたが、2024年からドイツが新たに加わった。ドイツの動きは同じく合法化を検討しているスイスやイタリアをはじめとする欧州各国に大きな影響を与えるのは必至で、おそらく数年以内にEU諸国の大麻政策は一変するだろう。
一方、米国の場合、現時点では連邦政府として、大麻の嗜好的使用はおろか医療目的による使用も認めていない。そもそも、国際的な大麻規制を主導してきた張本人が米国であることを考えれば、これは当然だろう。しかし近年、そんな米国でも、州単位では大麻への規制緩和が進んでおり、全50州中38州で医療的使用が、そして24の州およびワシントンDCで嗜好的使用が合法化されている。
このような国際的潮流にあるにもかかわらず、わが国があえてこのタイミングで使用罪を創設し、大麻規制の強化・厳罰化を進めるのはなぜなのか?
厚生労働省は、使用罪を創設する理由として以下の3つを挙げていた。第一に、近年、大麻取締法による検挙者が急激に増加し、若者を中心に大麻汚染が広がっていること、第二に、海外で大麻寛容政策が進むなか、インターネット上では不正確な情報が氾濫しており、そのような状況で大麻成分由来医薬品を承認すれば、「日本も大麻寛容政策へと舵を切った」との誤解を招きかねないこと、そして最後に、わが国の規制薬物のなかで、大麻だけ「使用罪」がないのは不自然である、ということだった。
いうまでもなく、新たな犯罪の創設にあたっては、その裏づけとなる根拠が必要だ。
政府は、根拠として大麻取締法検挙者数の増加を挙げていたが、これは何の根拠にもならない。というのも、検挙者数というのは、検査体制や検査へのアクセスによって左右されるコロナ感染者数と同じく、それ自体に意味はないからだ。コロナ対策において真に重要なパラメーターは、感染者数ではなく死亡者数や重症患者数だ。同様にして、大麻に関しても健康被害や、交通事故や暴力といった社会的弊害への影響を議論すべきところだが、有識者会議ではこの点を曖昧に濁したまま議論が進められていた。
実際のところ、大麻使用による健康被害は増加しているのだろうか?
大麻取締法検挙者数の増加に伴って、大麻関連障害で精神科治療を受けている患者数もまた増加しているのかといえば、決してそんなことはない。私たちが隔年で実施している「全国の精神科医療機関における薬物関連精神疾患の実態調査」で見るかぎり、大麻関連精神障害患者はさほど増加はしていない。少なくとも検挙者数に見合った増加にはほど遠い。しかも、覚醒剤や処方薬(睡眠薬・抗不安薬)、市販薬の患者に比べると、大麻関連精神障害患者は、依存症該当率・無職者率が低く、むしろその病態が際立って軽症であるように感じられるのだ。
とりわけ重要な点は、地域と精神科医療現場とのあいだにおける、大麻使用者の割合に、大きな乖離が見られることだった。全国住民調査によると、わが国の一般住民における違法薬物の生涯経験率は、大麻が突出して高い。しかしその一方で、精神科治療中の薬物関連精神障害患者における大麻患者の割合はせいぜい全体の7%程度にとどまり、この数字は、患者の半数あまりを占める覚醒剤に遠く及ばない。つまり、使用経験者は多いのに、医療にアクセスする人が少ないのだ。このことは、大麻使用による健康被害の発生頻度の低さを間接的に示している。
ならば、社会的弊害の方はどうか?
わが国の交通事故や暴力犯罪の発生件数は、近年、一貫して減少傾向にある。確かに米国では、大麻の嗜好的使用を合法化した直後のコロラド州で、一時的に交通事故が増加したが、その後、コロラド州とワシントンDCを対象とした精緻な研究によって、大麻の嗜好的使用の合法化と交通事故の増加との関連は否定されている。そもそも、精神作用物質による運転の影響は、アルコールがもっとも深刻であり、大麻はそれに比べるべくもない水準だ。さらにいえば、科学警察研究所の研究(1)によれば、大麻よりも抗不安薬や抗うつ薬の方がはるかに自動車運転への影響が大きいのだ。
もちろん、こうした事実を列挙しても、なおも反駁する人たちがいる。その際に、決まって振りかざされるのが、例の「ゲートウェイ理論」、つまり、「大麻使用がより強力な依存性薬物への入門的薬物となる」という考え方だ。しかし、それとて疑わしい。というのも、わが国では、最近10年間で未成年の大麻取締法検挙者数が激増している一方で、覚醒剤取締法検挙者数は著しく減少している。もしも大麻がゲートウェイ・ドラッグならば、覚醒剤取締法検挙者数は増加すべきところだが、現実にはそうなってはいないのだ。
正直に告白すると、長らく依存症専門医をやっていながら、私は大麻という薬物に少しも学術的関心を抱けないでいた。理由は単純だった。臨床現場で大麻依存症患者と遭遇する機会がめったになかったからだ。なるほど、大麻使用経験を持つ患者は非常に多かったが、通常、治療上の標的となる主乱用薬物は、覚醒剤など別の薬物であるのが常だった。ときには大麻精神病との触れ込みで受診する患者もいたが、いざ治療をはじめてみると、単に大麻使用歴があるだけで、本質的には統合失調症と捉えるべきケースであった。
ところが、2010年代後半になって、大麻に対して急に興味が湧いてきたのだ。きっかけは、2010年代前半に発生した危険ドラッグ乱用禍だった。
意外に知られていないが、危険ドラッグ乱用禍の発生は、大麻に対する取り締まり強化に端を発している。2008~2009年頃、有名大学在籍中の大学生が大麻所持で逮捕される、という事件が相次ぎ、連日、ワイドショーでとりあげられた時期があった。その影響で、帰国子女や海外留学歴のある学生など、海外での大麻経験を持つ者のあいだで危機感が高まり、「大麻と似た作用があるが、逮捕されない類似品」へのニーズが高まった。そうしたニーズに合致する薬物が、大麻に含有されるTHC(tetrahydrocannabinol: 大麻が持つ精神作用の責任成分)の化学構造式を一部改変し、法規制の網の目をかいくぐった製品――そう、まさに「脱法ハーブ」(当初、合法ハーブと呼ばれ、後に「危険ドラッグ」に名称が統一された)――だったのだ。
脱法ハーブの流通が大麻使用者を減少させたのはまちがいない。実際、2000年以降一貫して増加傾向にあった大麻取締法検挙者数は、2009年にピークを示した後、一気に減少へと転じているからだ。大麻愛好家のなかで危険ドラッグへの乗り換えが進んだのだろう。
もっとも、国内に流通しはじめた当初の脱法ハーブは、何の効果も体感できない詐欺めいた代物だった。しかし皮肉なことに、国が規制強化をすればするほど、規制に対応して化学構造を改変した新製品は、ますます効果と有害性を強めていったのだ。
特に、2回におよぶ大規模かつ包括的な規制(2013年3月と2014年1月)以降、危険ドラッグの弊害はピークに達した。おそらく広範な規制強化が、未知の危険な成分を含有する薬物の流通を促したのだろう。その結果、国内各地で危険ドラッグ使用下での自動車暴走事故が頻発するようになり、診察室で遭遇する患者の病状も悲惨をきわめるようになった。実際、危険ドラッグは離脱時の渇望感が非常に強烈で、強い決意を持って断薬した患者も、往々にして翌日には渇望に耐えかねて再び危険ドラッグに手を出したものだった。さらに、使用時の症状は激越で、てんかん発作の症状を呈して救命救急センターに搬送される患者もめずらしくなかった。
最終的にこの乱用禍は、薬事法改正により、国の許可なく「あやしげなもの」を販売することが禁じられ、脱法ハーブ販売店舗が次々に撤退していったことで終焉した、とされている。それはまちがいではないが、完全に正しくもない。というのも、薬事法改正の少し前から、危険ドラッグ依存症患者は減り始めていたからだ。おそらく当事者のなかには、「この薬物マジでヤバい」と認識し、みずから危険ドラッグに見切りをつけた者も少なくなかったのだろう。
とはいえ、危険ドラッグを自力でやめるのは容易ではなく、苦肉の計として、危険ドラッグをやめる代わりに、かつて使用していた大麻に戻る者が続出したのだ。すると不思議なことに、患者は、もはや危険ドラッグの離脱や渇望にのたうち回ることがなくなり、外来受診時にも、先週まで憔悴しきっていた人物とは別人かと思うほど、穏やかで落ち着いた態度となった。
それでも、大麻という違法薬物を使う代償は小さくはなかったはずだ。事実、2010年以降顕著に減少していた大麻取締法検挙者数も、2014年以降、一気に増加に転じている。
診察室から垣間見た、こうした一連の出来事に、私はショックを受けた。なぜなら、大麻には、逮捕という点では社会的リスクがある一方で、医学的リスクは少ないことが明らかになってしまったからだ。これは、「自分は大麻について何も知らないのだ」と実感させられる出来事だった。
以来、私は大麻に関心を抱き、なぜ社会はこの薬物を規制することにしたのか、その経緯を知りたい、と考えるようになった。
人類と大麻とのつきあいの歴史はかなり古い。ユーラシア大陸に住む人類にかぎれば、タバコ、あるいはコーヒーや茶よりもはるかに昔に遡ることができる。
大麻は、紀元前5世紀頃、現在の中近東付近でスキタイ人やトラキア人によって使用されていたようだが、はたしていかなる用途であったのかを説明する記録はない。ただ、1~2世紀頃になると、大麻はもっぱら鎮痛・鎮静作用を持つ医薬品として用いられるようになった。
後漢時代に成立したとされる古代中国の『神農本草経』には、大麻に関する項目が存在し、毒性がなく、日常的に使用可能な養生薬として、便秘、痛風、リウマチ、生理不順に対する効能が記述されている。7世紀には大麻は薬草として日本にも導入され、近代日本においても大麻は医薬品として使用され、1886年以降65年間、大麻は「日本薬局方」に鎮痛薬や喘息治療薬として収載されてきた。
娯楽としての大麻使用が広がったのは、大航海時代以降のアメリカ大陸においてだ。大麻草が自生していないアメリカ大陸に最初に大麻を持ち込んだのは、1549年、アンゴラ出身の黒人奴隷とされている。そして、中南米の砂糖プランテーションにおいて過酷な労働に従事させられていた黒人奴隷たちは、サトウキビ畑の隅で大麻草も栽培し、仕事の合間に大麻を喫煙していたという。労働を監督する白人たちは、大麻を吸った方が奴隷たちの生産性が高まることに気づき、大麻喫煙を容認した。こうして中南米では大麻が普及し、特にメキシコでは大麻使用は大衆の娯楽として一般的な習慣になった。
大麻が社会の敵となったのは、20世紀前半の米国においてだった。米国が規制に踏み切ったのは、何か健康被害や社会的弊害が生じたからではない。単に13年続いた禁酒法が1933年に廃止となり、連邦禁酒局という組織の命運と、その組織に属するアルコール捜査官――アル・カポネを典型とする反社会的な酒の密造・密売組織を取り締まるために多数雇用されていた――の雇用が危機に瀕したからであった。
この状況を打開するために、ときの禁酒局副長官ハリー・J・アンスリンガーは「別の何か」を規制することを思いつき、そこで大麻に白羽の矢が立ったわけだ。こうして禁酒局は麻薬局へと看板を替え、アンスリンガーはめでたく麻薬局初代長官に就任したのだった。
彼は、有色人種に対する差別感情を巧みに利用した。1910年に起こったメキシコ革命により、メキシコの治安は悪化し、安全と豊かさを求めて多くのメキシコ人が米国内に移住した。当時、大恐慌後の不況下であり、白人のあいだでは、雇用競合者であるメキシコ人移民に対する敵意や差別感情が高まっていた。このため、移民の習慣である大麻喫煙への嫌悪感を煽るのは容易であった。アンスリンガーは、大麻を呼ぶ際に、その正式名称「カンナビス」ではなく、あえてメキシコ風の俗称「マリファナ」を用い、人々の潜在意識で大麻とメキシコ移民との結びつきを強固にした。
大麻嫌悪は黒人への差別意識とも関係していた。黒人ジャズミュージシャンに群がり、はしゃぐ白人女性たちの姿に危機感を覚えた白人男性にとって、ミュージシャンたちが吹かす大麻煙草は、やはり格好の憎悪対象となり得る。そこでアンスリンガーは、「大麻の蔓延が黒人男性と白人女性の混血児を増加させる」として、白人男性の不安を煽ったのだ。つまり、大麻の弊害を非現実的なまでに誇張して、「大麻は性欲を刺激し、人を発狂させる。女はみな淫乱になり、男は殺人鬼となる」といった噴飯物の啓発を展開した。
黒人と大麻とを結びつける考え方は、わが国の大麻規制にも適用された。わが国の大麻取締法は、第二次大戦後にGHQの指示によってやむをえず作られたものだ。古来わが国では、麻は神道の儀式に不可欠な植物であり、実際、国内には多数の麻農家が存在していたが、大麻使用による弊害は確認されていなかった。それにもかかわらず、突如、GHQより、「日本駐留中の黒人米兵の大麻使用を取り締まる必要がある」との指示があり、1948年に、麻農家に配慮した奇妙な部位規制――種子と成熟した茎を除く大麻草部位を「大麻」とする――にもとづく大麻取締法が制定されたのだった。
それにしても、驚きを禁じ得ないのは、アンスリンガーがなんと30年あまりもの長きにわたって連邦麻薬局初代長官の座に居座り続けたことだ。これは歴史的に見ても異例の事態だった。その結果、彼は国際的な強い影響力を手に入れ、好き放題といっても差し支えないほど無理筋の規制を行っていった。実際、大麻を「医療的な用途がまったくない有害薬物」に位置づけた、国連の「麻薬に関する単一条約」は、完全に彼の影響下で作られたものだ。
アンスリンガー退任後の1970年代以降も、彼の声は残響し続けた。米国の為政者たちが、反政府的な言論や政治活動を封殺し、支持率を向上させ、政権の安定的運営の武器として、薬物対策を利用したからだ。当時、米国内の政情は非常に不安定であった。公民権運動の激化とベトナム戦争の泥沼化、キング牧師の暗殺といった出来事が、若者たちに連邦政府への不信感を抱かせ、カウンター・カルチャーによる反戦運動の勃興を促したからだ。
1971年にニクソン大統領がはじめた「薬物戦争」は、そうした反戦運動を封殺するための、いわば力ずくの政策だった。運動の担い手である若者たちを大麻所持で次々に投獄し、また、カウンター・カルチャーにおいて神格化されていた、LSDやMDMAなどの幻覚薬を、意識変革体験を通じて反体制的な人間を作り出す危険な薬物と見なし、次々に規制していった。
危険ドラッグ乱用禍終焉後の2015年以降、大麻取締法検挙者が急増するのに伴い、大麻愛好家が薬物依存症外来にぽつぽつと受診するようになった。その多くは、大麻取締法で逮捕され、その保釈中に執行猶予を勝ち取るための法廷戦略として、「専門病院を受診して、再犯防止に努めている」というアリバイ作りを目的としていた。
患者の背景はさまざまであったが、総じて十分な教育歴があり、その日の終わりにリラックスして眠りにつくために大麻タバコを1本だけ吸う、といった節度ある使い方をしていた。当然、仕事への支障はまったくなかった。彼ら曰く、「晩酌をすると、翌朝、身体がだるくなる。大麻の方が、翌日身体が楽」とのことだった。実際、保釈中、就寝前の大麻一服をやめて、晩酌に切り替えて試す者もいた。しかし、確かに翌朝身体が怠いうえに、1カ月もそうした生活を続けるうちに、皮肉にも、初診時の血液検査で完璧だった肝機能のデータは、確実に悪化していた。
芋づる式に「見せしめ逮捕」の標的とされたのか、ラップ・ミュージシャンの受診が立て続いた時期もある。その多くは20年あまり毎日大麻を使用し続けた猛者たちだった。しかし、特段の後遺症もなく、むしろ礼儀正しく、愛すべき人柄の持ち主ばかりだった。
ただ、逮捕から勾留を経て、公判を控えた保釈期間中、久しぶりの完全クリーンな状態にある彼らを観察していると、注意欠如・多動症(ADHD)が疑われる者が実に多かった。実際、学童期には教室でじっとして授業を聞いていることができず、思春期以降は、ささいなことでキレやすく、遅刻や約束のすっぽかしが多い、といったエピソードに満ちていた。そして興味深いことに、これらの行動上の問題は大麻を使い出すと解決された、というのだ。
このようなラッパーたちに対して、ADHDの薬物療法を試みたこともあった。大抵の場合、ADHD症状の改善が見られたが、当の本人たちは口々に不満を訴えた。「なんか落ち着きすぎちゃう。これだとライブ・パフォーマンスができない」というのだ。そして、必ずこうもつけ加えた。「それにこの治療薬ってケミカルですよね? ヤバくないですか? 大麻の方がいいですよ。だって、大麻は薬物じゃなくて植物なんで」。私には返す言葉がなかった。
人によってはトラウマに関連する心身の不調にも効果があるようだった。ある性暴力被害のサバイバー女性は、悪夢と頑固な不眠、そして原因不明の身体的疼痛に長年苦しんでいた。これまでさまざまな治療を試みてきたが、効果はなかった。心理療法を受ければいつもセラピストと口論になり、精神科ではさまざまな治療薬をあれこれ試してみたものの、ただひどい副作用に苦しむだけだった。そして絶望の淵で、偶然、彼女は大麻と遭遇し、心身ともに救われるという体験をしたのだ。医師としての私が彼女に提供できたのは、海外移住の提案だけだった。
政府の薬物規制対策を眺めていて、いつも不思議に感じることがある。それは、政府は規制対象薬物を増やしたがっているのではないか、ということだ。
現に、厚生労働省の薬物規制に関する委員会では、規制候補薬物の有害性評価に際して、対照群のネズミに投与するのは、アルコールやカフェイン、あるいは既存の規制薬物ではなく、決まって生理食塩水か蒸留水だ。これでは、どんな薬物でも――何なら砂糖水でさえも――対照群よりは病的な行動を示すはずだ。事実、私は、同委員会において、新規の規制申請が却下されるのを見たことがない。おそらく厚生労働省の規制当局においては、規制薬物数や新たな規制法の成立は、当該部局の権限と予算獲得に影響するのだろう。
新規の犯罪創設によって犯罪者の増加をひそかに願っている省庁・部局だってあるように思う。たとえば捜査・法執行機関だ。最近10年あまり、わが国では覚醒剤取締法違反による逮捕者が激減し、かつて過剰収容が問題視された刑務所もいまや収容率が低下している。さらに、少子化と少年犯罪の減少により、少年鑑別所や少年院には閑古鳥が鳴く始末だ。この状況が続けば、当該省庁・部局は予算や人員の縮小が避けられないだろう。
このような事情を抱えた政府の意向は、科学的研究の方向性にも無視できない影響を及ぼす。事実、米国国立薬物乱用研究所に勤務経験のある神経科学者カール・ハートは、政府から資金援助を受けている研究者はもっぱら薬物の害に焦点を当てた研究しかしなくなる、と指摘している(2)。逆にいえば、薬物の有害性を否定するような研究成果は、研究費助成の打ち切りや研究者としてのポジションを失う危険さえ覚悟しなければならないのだ。
ここで直視すべきなのは、イデオロギーの前にはサイエンスなどひとたまりもない、という悲しい現実だ。アンスリンガーが大麻禁止政策を展開し始めた1930年代、連邦政府の大麻政策に疑問を抱いたニューヨーク市長ラガーディアは、独自に科学者たちを招集し、大麻の有害性に関する検証研究を依頼した。その検証研究の結論は、「有害とはいえない」というものであった。しかし、連邦政府はこの報告書を完全に黙殺した。同様に、ニクソン大統領もまた、科学者や専門医による大麻政策の見直しを求める勧告(1972年)を拒絶している。
ラットパーク実験で知られるカナダの心理学者ブルース・アレキサンダーは、まさしくそのような憂き目に遭った研究者の一人だ。彼は、仲間たちと一緒の環境に置かれたネズミはモルヒネ入りの水に見向きもしないのに、単身で檻に閉じ込められたネズミは、文字通り「狂ったように」大量のモルヒネ水を摂取する、ということを実験的に明らかにした。そしてその結果にもとづいて、依存症は「薬物」ではなく「環境」によって作られるのではないか、と主張したのだった。しかし、彼の主張は、当時の薬物政策――依存症の原因は薬物にあり、そのような危険な薬物を規制するには厳罰もやむなし――を真っ向から否定するものであった。結果的に研究助成は打ち切られ、彼のプロジェクトは頓挫した。
英国を代表する神経薬理学者にして精神科医、デヴィッド・ナットもまた同様の体験をしている。かねてより彼は、「大抵の違法薬物よりもアルコールの方が危険であり、社会的弊害が大きい」と主張し、政府の不興を買っていたが、ついに2009年、「MDMAの使用は乗馬よりも健康被害リスクが少ない」ことを統計学的に明らかにした。すると、これが当時の英国内務大臣の逆鱗に触れ、「政府の顧問と政治運動家とは兼任することはできない」「彼は科学よりも思想を優先した」という理由から、英国薬物規制諮問委員会会長を解任されたのだった――「科学より思想を優先」したのは、どう考えても政府の側であったわけだが。
それにしても、ナットはとてもタフな精神科医だ。彼の勢いは、会長解任以降もとどまるところを知らなかった。薬物規制が科学的根拠にもとづかずに、恣意的に決定されていることに異を唱え、解任翌年の2010年に、政府の干渉なしに薬物の健康被害を検討する団体、「薬物に関する独立科学評議会」を設立したのは、よく知られている。同評議会が多次元的評価に基づいて作成した、「薬物有害性リスト」は、薬物の合法・違法の区別には何らの医学的根拠もないことを明らかにした仕事として、これまで世界中の研究者によって頻繁に引用されてきた。
最近では、LSDやMDMAをはじめとする幻覚薬の医療的可能性を追求して、驚くべき成果を上げている(3)。そのなかでも近い将来、実用化される見込みがもっとも高いのは、マジックマッシュルームに含有される幻覚成分サイロシビンを用いた依存症や難治性うつ病の治療だ。ナットによれば、サイロシビンは、脳内のデフォルト・モード・ネットワークを休止させてマインドフルネスな状態を作り出すとともに、神経栄養因子を増加させる作用があるという。おそらくそれによって脳内ネットワークの再構成を促し、何かにとらわれた人間の意識を改変するのだ。
さもありなん、というべきだろう。アルコール依存症の自助グループAAの創始者ビル・ウィルソンのホワイトライト体験――断酒成功の端緒となった幻覚体験――は、ビルの主治医であったウィリアム・D・シルクワース博士が投与した幻覚薬によるものだったといわれている。
サイロシビンの治療効果に関する文献を読んでいると、近い将来、精神科薬物療法革命が起こる予感を覚えずにはいられない。それは、従来の「半永久的に服用し続ける薬物療法」から、「単回の服用で永続的な効果を出す薬物療法」への変化だ。これは、1970年代に「医療的用途がまったくない、害しかない薬物」と決めつけられ、規制対象となってしまった薬物が、あたかも敗者復活戦から勝ち登るような未来像といってよいだろう。
しかし同時に、私は罪悪感に苛まれるのだ。というのも、今日わが国でサイロシビン療法ができなくなってしまった状況に、私も加担しているからだ。実は、私が医者になって最初に書いた論文は、まさにマジックマッシュルーム精神病の症例報告だった。1999年のことだ。バリ島のマジックマッシュルーム体験ツアーに仲間とともに参加した男性が、マジックマッシュルーム入りのオムレツを食べたところ、他の仲間は数時間で幻覚の世界から戻ってきたのに、彼だけはそのまま慢性精神病の世界に嵌まり込み、バリ島から日本へと強制送還されてきたのだった。
いま思えば、彼はもともと統合失調症に罹患しており、強い不安を抱えた状態でマジックマッシュルームを摂取するという、最悪の状況での初使用だった。当時、マジックマッシュルームは法規制の埒外にあったために、大都市の繁華街では店頭販売されていることもめずらしくなかった。したがって、潜在的には多数の使用経験者がいたはずであり、トラブルを生じた者が少々存在したからといって、その弊害を一般化することには慎重であるべきだった。なにしろ、アルコールだっておかしくなる人間はいるわけだから。
しかし、野心的な若手精神科医であった私は、とにかく論文を書きたくて、ネタにしやすい稀少症例を、文字通り「鵜の目鷹の目」で探していた。そして、マジックマッシュルーム精神病はやっと巡り会えた、私にとって最高に美味しい獲物だった。私はわずか一症例だけに見られた現象を大げさに騒ぎ立て、さも「世の一大事」といわんばかりに警鐘を鳴らしたのだ。
そんな私の仕事が、2002年の「マジックマッシュルームの麻薬原料植物指定」に何らかの影響を与えたことはまちがいないだろう。
話を大麻に戻そう。
すでに述べたように、純粋な大麻依存症患者が薬物依存症外来を受診することは稀だ。したがって、依存症を専門とする精神科医といえども、大麻の健康被害について熟知しているとはかぎらない。他診療科の医師も同様だ。大麻の急性中毒で瀕死の状態になって救命救急センターに搬送される患者など、これまで見聞きしたことがない。
基礎研究者だって同様だ。彼らは大麻については動物に投与した場合の反応しか知らず、しかも、実験において動物に投与される大麻は、人間の体重に換算すると、あり得ないほど膨大な量であることも多い。
そう考えると、おそらく大麻に関してもっとも多くを熟知するのは、長年、大麻を使用している大麻愛好家自身だろう。とはいえ、違法薬物の経験を公に語るのは、容易な話ではない。
しかし、私たちはそうした制約を突破することを試みた。2020年、私は、医療用大麻の啓発を目的とする民間団体代表とともに、市中の大麻使用者に関するインターネット調査を行ったのだ(4)。わずか2週間という短いリクルート期間ながら4138名もの大麻使用経験者が調査に参加した。それまでの国内において最大規模の研究が71例の大麻関連精神障害患者を対象とするものであったことを踏まえると、国内では他の追随を許さない圧倒的な規模だ。
この調査からは多くのことが明らかになったが、なかでも重要なのは次の3つだ。第一に、使用者の大半は長期にわたって健康被害を呈することなく、いわば「節度をもって」大麻を使用していること、第二に、使用者の約95%が仕事に就いていること、そして最後に、大麻取締法逮捕経験者はわずか8.7%にすぎないことだ。
最後の逮捕経験者8.7%という数字は、裏を返せば、使用経験者の大半は逮捕されない、ということを意味する。そして使用罪創設は、まさにこの層――仕事をし、納税という社会人としての責務をはたしている人々――を前科者にし、社会から排除することになる。なにしろ、覚醒剤の場合、最終使用から1週間すれば尿中から検出できなくなるのに対し、大麻に含まれるTHCの場合、軽く1カ月は尿中から検出され続ける。したがって、大麻使用者が逮捕される可能性は、所持罪だけの頃とは比較にならないほど大きくなるはずなのだ。少子高齢化と子どもの自殺増加に悩むわが国にとって、このような未来像はあまりにも暗すぎないだろうか?
誤解しないでいただきたいのだが、私は決して大麻が完全に無害な薬物と思っているわけでもなければ、野放しにしてよいといいたいわけでもない。すでに私たちは、自身の調査から、THC濃度の高い大麻製品を使ったり、未成年のうちから使用したり、長期間使用したりすれば、依存症罹患リスクが高まることを確認している。しかし、これはアルコールやタバコだって同じだ。
私が問題視しているのは、大麻使用罪を創設し、国民のなかに犯罪歴を持つ人を増やすことの是非なのだ。というのも、犯罪歴は、その人間の活動領域を著しく狭め、居場所を奪うからだ。
思い出すのは、少年鑑別所出所後に私の外来につながった2人の少年のことだ。いずれも大麻取締法で逮捕されたわけだが、社会に戻る場所があるかないかで、その後の明暗がくっきりと分かれることを教えてくれた。
1人は、逮捕を契機に高校を退学となり、悪い噂ゆえに地元でまともな職にはありつけなかった。最終的には小さな建設会社に拾われたものの、そこの社長や従業員の何人かは覚醒剤常用者であり、そうした環境の影響で今度は覚醒剤に手を出し、成人後に再び逮捕された。
一方、もう1人は、校長の温情により在籍校に1学年遅れて復学し、高校卒業後は幸いにも大学にも進学できた。そして大学卒業後は、地方のそこそこ名前の知られた企業に就職した。
わが国は、犯罪歴を持つ人にとって生きやすい社会だろうか? あるいは、違法薬物の問題を抱えた人を、犯罪者として告発することなく、支援してもらえる場所は十分にあるのだろうか?
残念ながら、これについては年々厳しい状況となっている。特に2023年に起こった某大学アメフト部事件を契機に、教育機関のあいだでは、「隠蔽」の誹りを怖れ、守秘義務を優先して相談対応することよりも、まずは一刻も早く警察通報という気運が高まってしまっている。
それだけではない。くだんの某大学の学生は、容疑の段階でメディアに実名や顔写真まで晒されたのだ。おそらくそれらの個人情報はデジタル・タトゥーとなって、教育や就職の機会を奪い、賃貸物件の契約や事業への融資など、人生のさまざまな局面でその若者の行く手を阻み、永続的な社会的制裁を与え続けるにちがいない。
懸念は他にもある。CBD(cannabidiol: 大麻に含有される抗けいれん作用や抗炎症作用など医療的効果が期待されている成分)製品の危険ドラッグ化だ。実は、THC含有量が検出閾値未満という理由から、わが国で販売許可を得ているCBD製品でも、ごく簡単な化学的操作によってTHC類似物質を作り出せる。一時期、メディアを騒がせた「大麻グミ」などは、その典型だろう。そして、使用罪創設がまことしやかに噂されるようになると、こうしたCBD製品の危険ドラッグ化が始まったのだ。
もちろん、現在、政府はすでにそうした類似物質を見つけては次々に規制している。しかしそのたびに、用済みになった古い製品の在庫一掃安売りセールが行われ、同時に、新たな脱法的薬物――前の製品より有害であることが多い――が流通している、という現実がある。
既視感のある光景だ。すでに述べた、10年前の危険ドラッグ乱用禍と同じではないか。まるでシジフォスの神話、いや、捜査機関への予算拡大のための「マッチポンプ装置」というべきか?
いま日本は世界から完全に取り残されている。わが国に大麻取締法を作らせた張本人たる米国ですら、大麻政策は大きな転換点を迎えている。というのも、2022年10月、当時の大統領バイデンは、連邦法の下で大麻によって有罪判決を受けた人々に対して前科を取り消すという恩赦を与え、大麻をもっとも危険な薬物として分類する現行法を見直す、と発表したからだ。
バイデンは同日のビデオメッセージでこう語っていた。「誰も大麻を使用または所持しただけで刑務所に入れられるべきではない」。さらに続けてこう断言したのだ。「連邦政府の大麻に対するアプローチは失敗であり、あまりにも多くの人の人生を狂わせてきた。この過ちを正すときがきたのだ」
結局、有識者会議の最終回は苦々しい後味で終わった。自分たちが行った多数例調査は顧慮されず、なぜか症例報告の知見が重視された。そう、かつて駆け出しの私がその稀少性に小躍りしながら書いたのと同じ症例報告だ。
最終的に、使用罪創設に反対した委員は、私を含めごくわずかだった。有識者のなかには、大手新聞社編集委員や刑法学者といった、薬物問題の門外漢もいたが、長年の「ダメ。ゼッタイ。」啓発に洗脳された彼らは、症例報告というエビデンスレベルの低い根拠に躊躇することもなく、大麻の「恐るべき危険性」を無邪気に盲信したようだ。
会議を終えてビル1階の玄関から外に出ると、ドレッドヘアの応援団たちはまだ入口付近にいた。そして私の姿を認めると、彼らは「お疲れさまでした」と深々とお辞儀をしてくれた。長くボリュームのあるドレッドヘアが空中で真夏の夜の花火のように優雅に広がり、そして、スローモーションで落下していった。
そのさまに見とれていた私は、はたと我に返り、慌てて会釈を返した。何か話そうと口を動かしかけたが、適切な言葉が見当たらず、結局、黙ったままそそくさと地下鉄の入口へと急いだ。とてもじゃないが、彼らの顔――いや、正確には、彼らの胸にプリントされたボブ・マーリーの顔――を正視できる気分ではなかったのだ。
地下鉄の駅構内を歩きながら、私は彼らのことを心配した。使用罪が創設されたら、その風体ゆえに彼らはまっさきに警察官から職務質問され、尿検査を求められるにちがいないからだ。
大麻取締法改正に関する政府の委員会は、その後も名称を変えて継続されたが、もはや私に委員就任の声はかからなかった。私の後任として委員に就任したのは、使用罪創設に肯定的な依存症専門医だった。彼は、新たに組織された委員会において、大麻がさほど有害ではないことを認めつつも、その「悪習」をやめさせるには何らかのサンクションが必要、つまり、使用罪によって困らせて治療へと追い込む必要がある、という趣旨の主張をしたのだった。
何も困っていない人を困らせるために恣意的にルール変更を行い、それによってその人を病気認定して医療に追い詰める……。これは、高血圧や高脂血症の正常基準値を無用に下げ、より多くの国民を生活習慣病とするような、悪意ある操作に似ている。なるほど、そうすれば依存症治療・回復支援ビジネス界隈は盛況となるだろうが、それが本来あるべき医療の姿とは思えない。
そして2024年12月12日、ついに「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が施行された。この日を境に、大麻は法律上「麻薬」に位置づけられ、それに伴って使用罪が創設されるとともに、従来から存在する所持罪もその量刑が重くなったのだ。
参考文献
- 岡村和子、藤田悟郎、小菅律他「違法薬物・医薬品の使用と自動車運転――疫学的・実験的研究、及び対策の概観」交通心理学研究、30巻1号、1-25頁、2014年。
- Carl L. Hart, Drug Use for Grown-Ups: Chasing Liberty in the Land of Fear. Penguin Press, 2021.
- デヴィッド・ナット『幻覚剤と精神医学の最前線』鈴木ファストアーベント理恵訳、草思社、2024年。
- 正高佑志、杉山岳史、赤星栄志他「SNSを活用した市中大麻使用者における大麻関連健康被害に関する実態調査 第1報」日本アルコール・薬物医学会雑誌、56巻4号、128-141頁、2021年。
編集部注:本連載では、登場人物の匿名性を保つため、プロフィールの細部に変更を加えています。