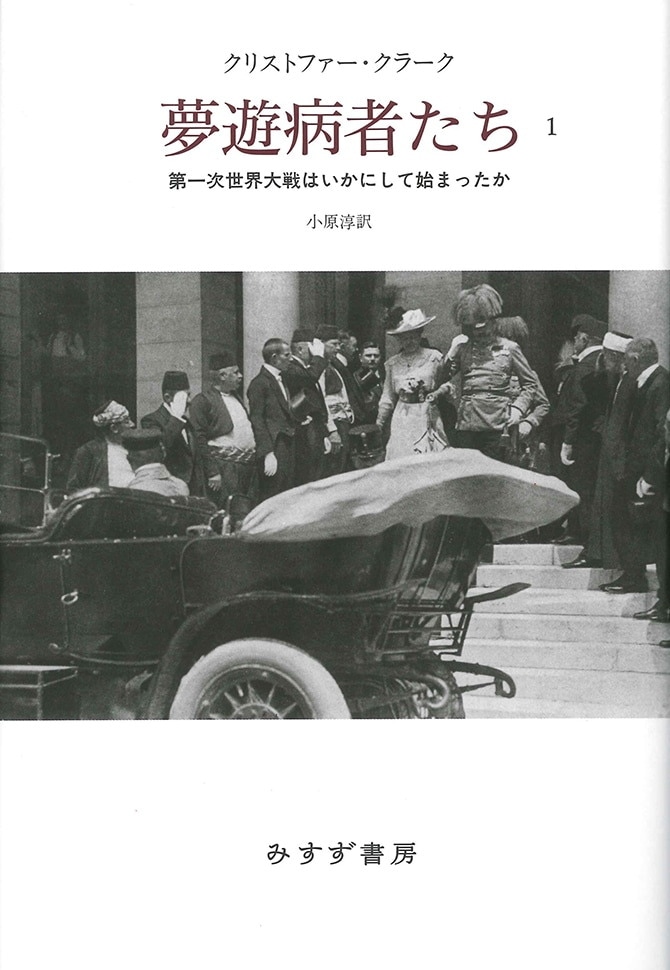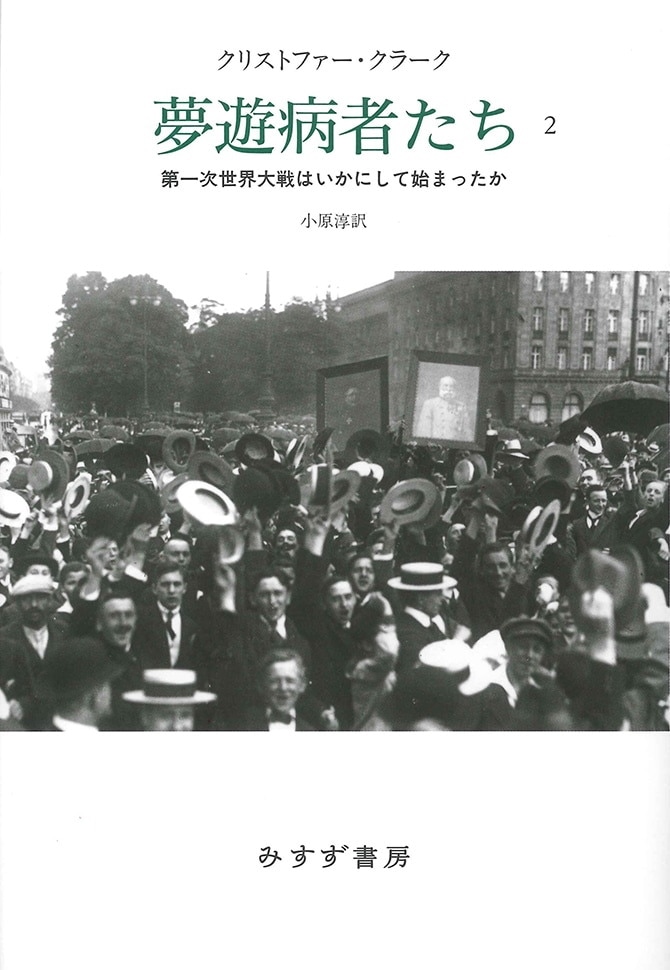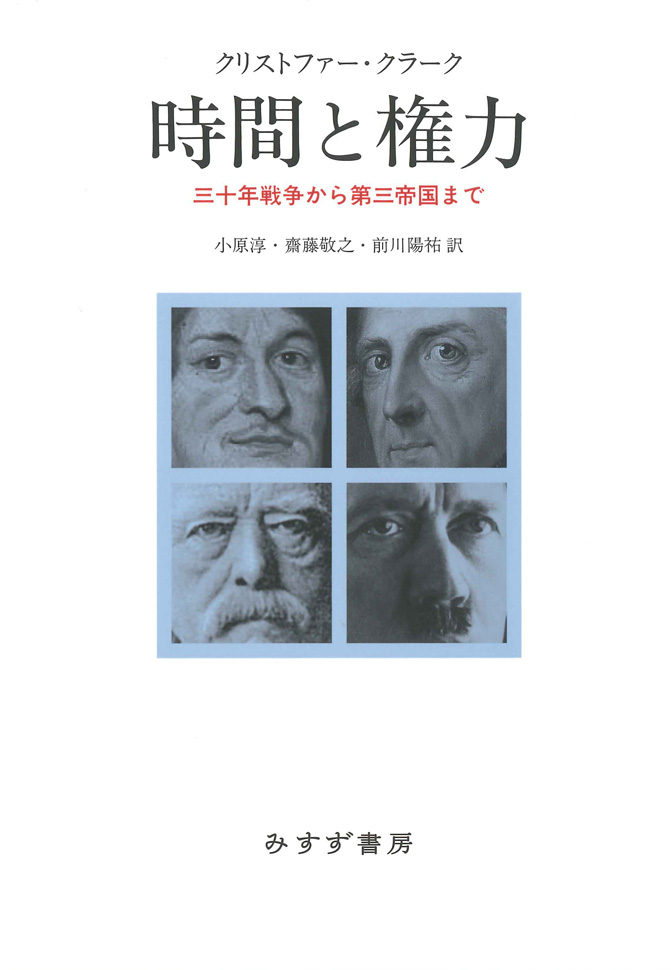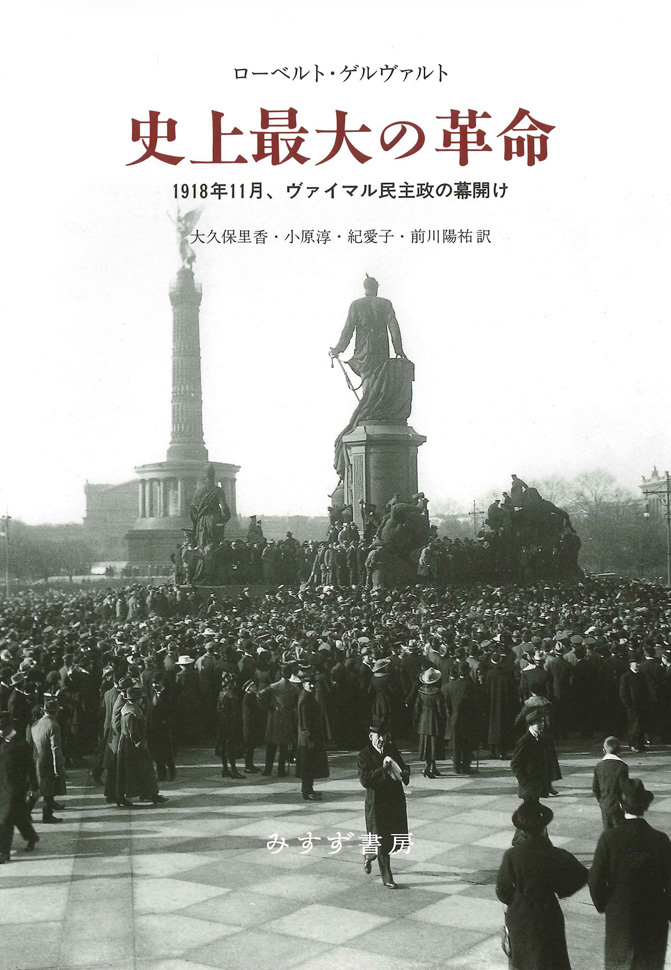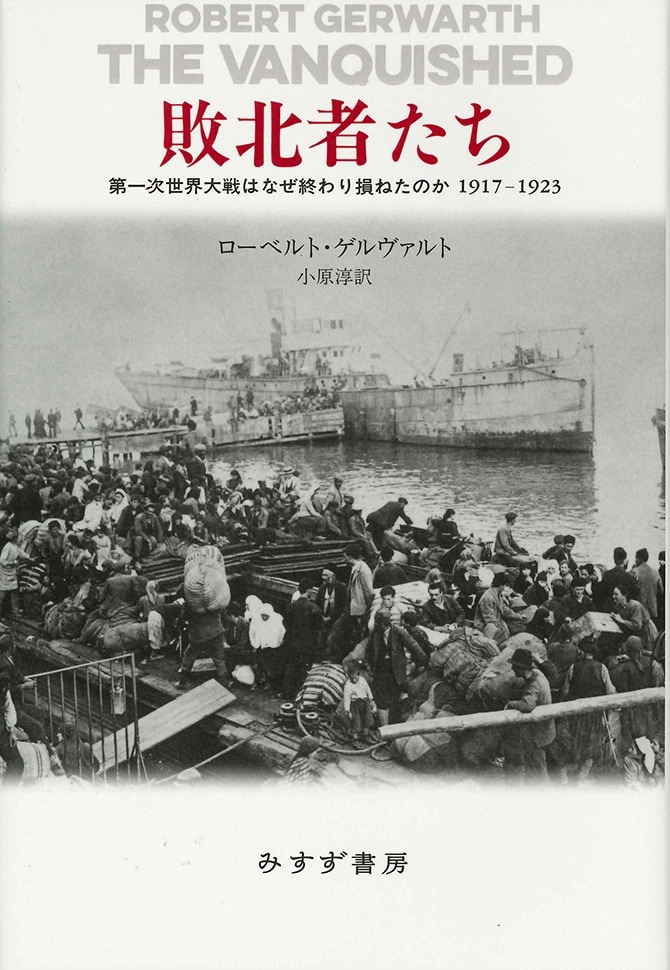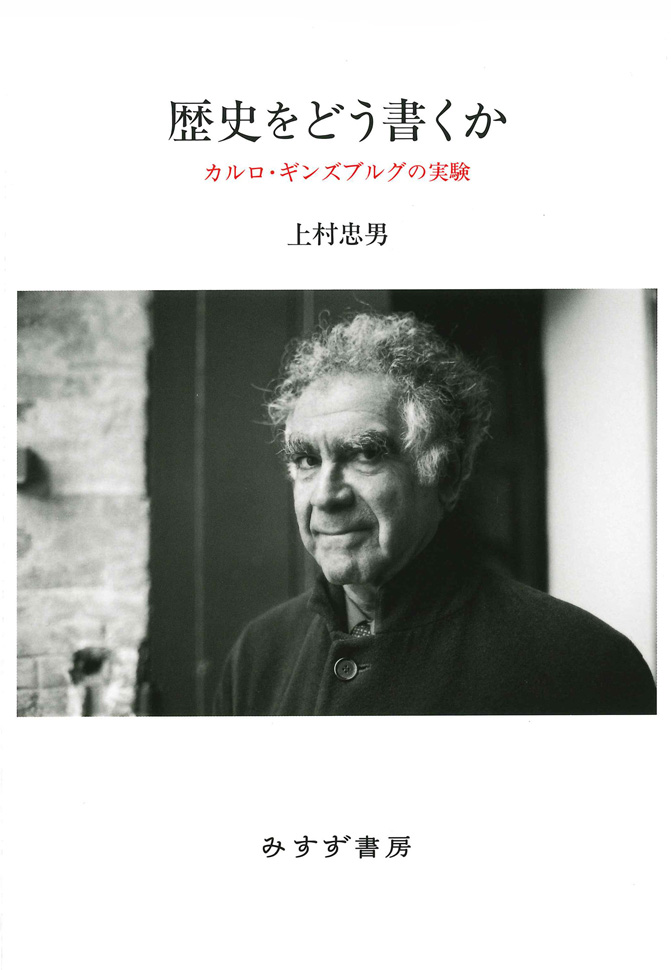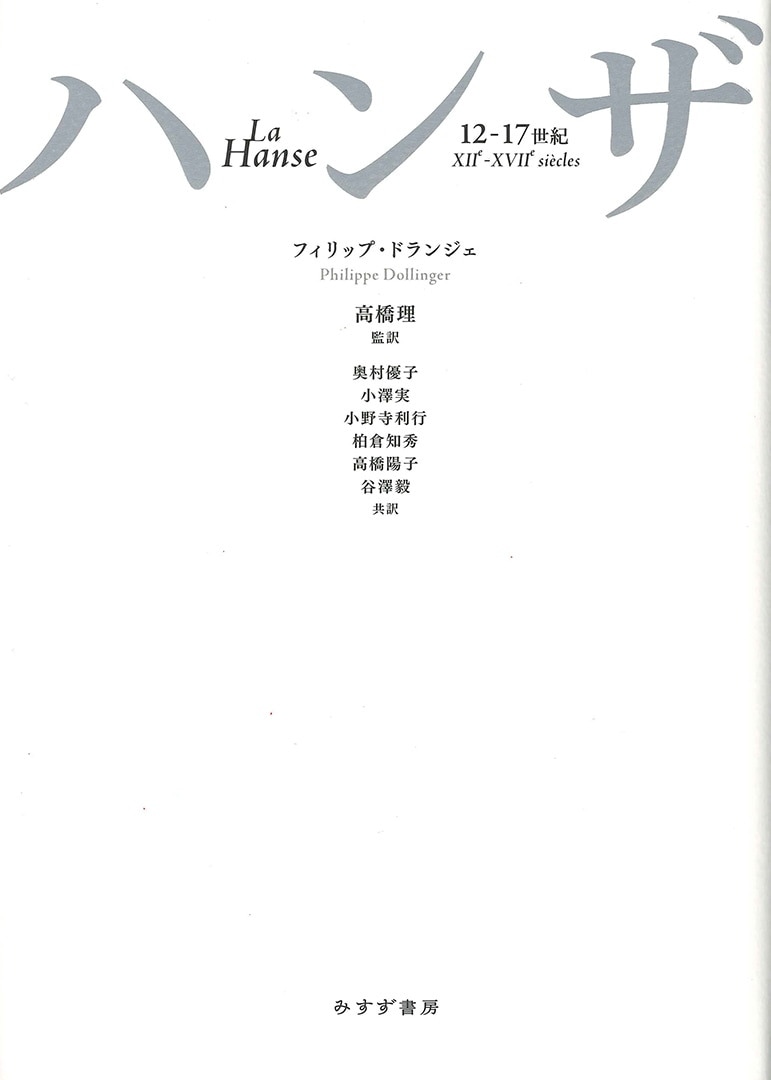近現代のドイツを中心としたヨーロッパの政治と歴史を研究する者として、ほぼ毎日、ドイツ語や英語、その他のヨーロッパ諸語の学術的な文献や論文に接している。しかし、というかだからこそ、翻訳には軽々に手を出せない、出してはいけない、と長らく思ってきた。
翻訳をやるとなれば、たとえばある部分のそれなりに意味の通じる訳文が仮にできたとしても、正確に理解したという十分な実感がなければ、その実感を得るために、少なくとも著者が参考にした文献や論文そのものにあたらなければならないと考えて、実際にそうすることだろう。十分に理解ができない理由が自分自身の勉強不足であれば、基本的な知識を補う作業を翻訳の途中にでも始めてしまうに違いない。そうした翻訳にともなう、訳文を実際に作る以外の準備作業は、勉強にはなるもののかなりの時間と手間を要することが予想される。翻訳にそこまでの労力をかけるべきなのか、多大な労力をかけてでも翻訳に値する本であることを見極めているのか。翻訳には強い覚悟が必要であると考えてきた。
[中略]
発端は2020年11月の著者とのメールのやり取りの中で、私が2017年から2018年にかけて研究滞在したベルリンで執筆しドイツの歴史学の学術雑誌に公表された論文(執筆にあたりランゲヴィーシェ氏から有益なコメントをいただいた)が、ドイツの著名な政治学者であるArthur Benz氏の著作(Föderale Demokratie:Regieren im Spannungsfeld von Interdependenz und Autonomie, Baden-Baden 2000)に引用されていたことを伝えたところ、ランゲヴィーシェ氏が、まもなく刊行される自分の本にもその論文を引用した、と知らせてくれたことであった。そして、新刊の概要を簡潔に示し、こういう内容の本が翻訳されたとしたら日本では関心をもたれるだろうか、と結ばれていたことであった。
ランゲヴィーシェ氏が新刊を出されることはすでに知っており、インターネットを通じて入手の手配も済ませていた。この歴史家が書いた文献や論文を数多く読み、かねてよりその研究を紹介したいと考えていた私には、出版予告の簡単な紹介を読んだ時点で、まもなく現物を読むことになるその書物が、氏の研究を紹介するのに最適な書物なのではないかという予感があった。ほどなくして届いた原著を一読し、その予感は間違いでないことがわかった。それどころか、小さからぬ感動をもって、これは自分が訳さなければならないと強く思ったのである。
ランゲヴィーシェ氏の著作をほとんど読んできた私にとって、原著が氏の研究のエッセンスを集約したものであるということは明らかであった。しかしながら、その冒頭には驚かされた。「初めにナポレオンがいた」「初めには何の革命もなかった」「初めにあったのは帝国であった」という、ドイツ史研究者ならば誰でも知っている有名な文(「解題」に書いたように、それぞれに独自性を有する近現代ドイツの通史の冒頭の一文である)を並べ、それらを書いた名高い歴史家たちに共通の「ドイツ史の支配的な語り方」に向けて、ランゲヴィーシェ氏自身のドイツ史の「対抗構想」を掲げていたのである。このような大胆なことができるのは、今のドイツの歴史学界にはランゲヴィーシェ氏を措いていないだろうと、感銘さえ覚えたのであった。
原著の学問的意義は当然のことながら、そのように極めて刺激的に始まる書物を前に、翻訳には軽々に手を出してはいけないなどという抑制はどこかに消え、何としてもこれを訳さなければならないという思いが生じていた。凝縮された内容の書物であるがゆえに、かなりの訳注を書かなければならないだろうと予想されたものの、それはごく当然で自然なことであると感じていた。
[中略]
このようにして生まれた本書を手に取った方は、なにより訳注の多さと詳しさに驚かれるかもしれない。それはまずもって本文の理解をできる限り助けるためにとの一心で書いたものであり、その結果、おのずと分量が増えてしまった。歴史的な事件や人名や制度のみならず、研究文献や論文からの一節が引用されているような箇所などには、その元の文献や論文にあたり、引用箇所の前後の文脈を含めて説明を加えるように努めたことも、訳注が多く詳しくなってしまった一因であろう。さらに、ここまで訳注を付すことは、訳者の分限を越えたかもしれない、ことによると必ずしも正確とは言えない記述が含まれているかもしれないと恐れてはいるものの、原著の面白さ──ということはドイツとヨーロッパの歴史の面白さである──を伝えたいという、私の強い思いから発してもいる。逆に言えば、それだけの価値のある書物である、と強調したいのである。本書の冒頭に置いた、「本書の理解のために──一つの概史として」という、おそらくあまり類例のない性格の文章についても、そのようなことを念頭に書かれたものであることをご理解いただければ幸いである。
とはいえ、ドイツとヨーロッパの歴史の面白さを享受したのは、まずは私自身であった。その面白さは、ヨーロッパ史を主に政治学の知見を動員しつつ考察する研究者にとっての学問的刺激といってもよく、本書を翻訳する過程でドイツとヨーロッパの歴史について新たに学ぶところが多かった。たとえば合意の政治についてである。つとに比較政治学は、合意の政治や合意型民主政治について論じてきた。その歴史的起源を探る際に神聖ローマ帝国に言及する研究者もいる。そして本書にもヨーロッパの合意の政治についての記述がある。ただし、合意の政治をめぐる政治学と歴史学の議論はほとんど交わらない。本書が参考にするような歴史学における合意の政治に関する知見は、政治学の世界においてはほとんど知られていないのではなかろうか。今後、比較政治学が合意の政治や合意型民主主義、さらにその起源を論じる際には、歴史学の研究蓄積を十分にふまえることが必要になるだろう。
[後略]
Copyright © IIDA Yoshihiro 2023
(筆者のご同意を得て転載しています。なお、
読みやすいよう行のあきなどを加えています)