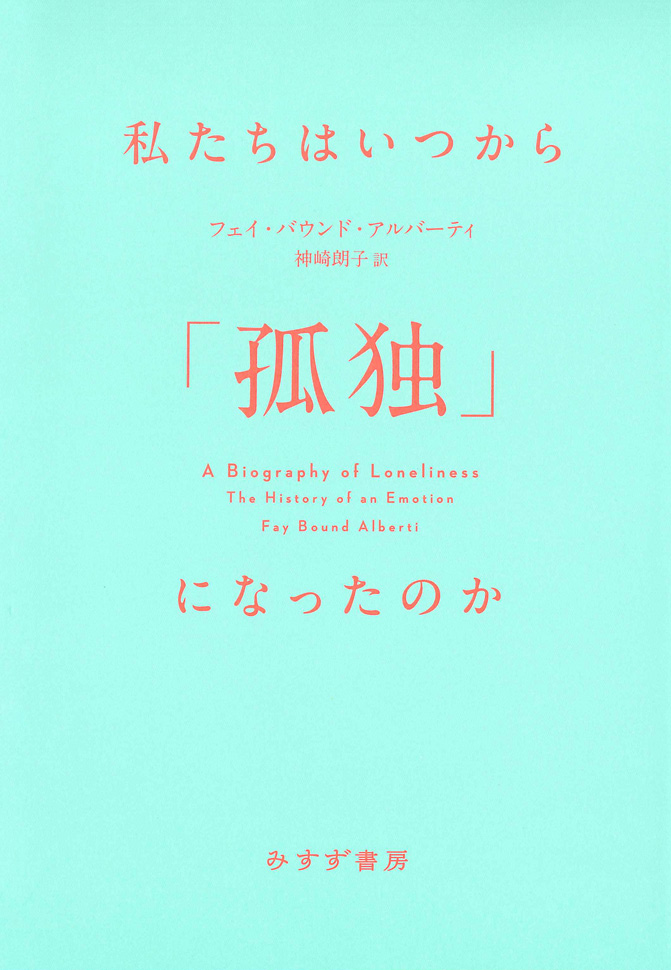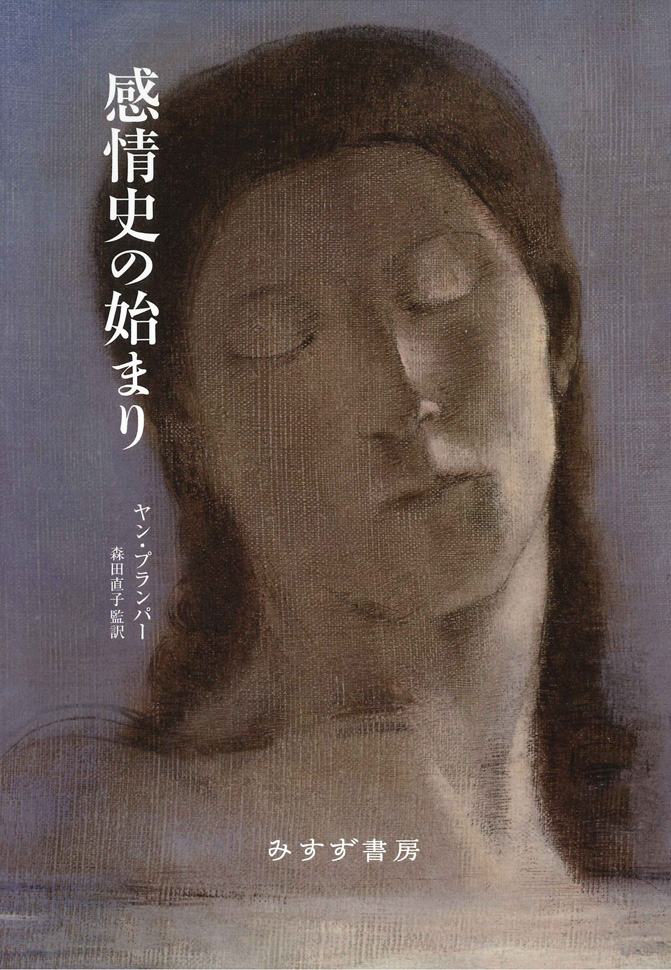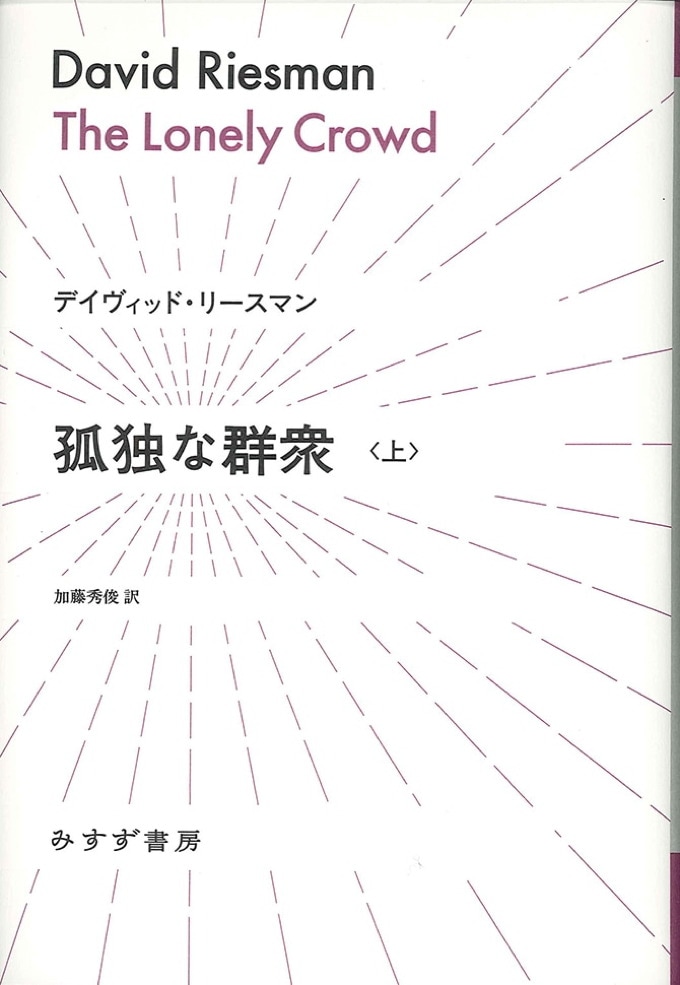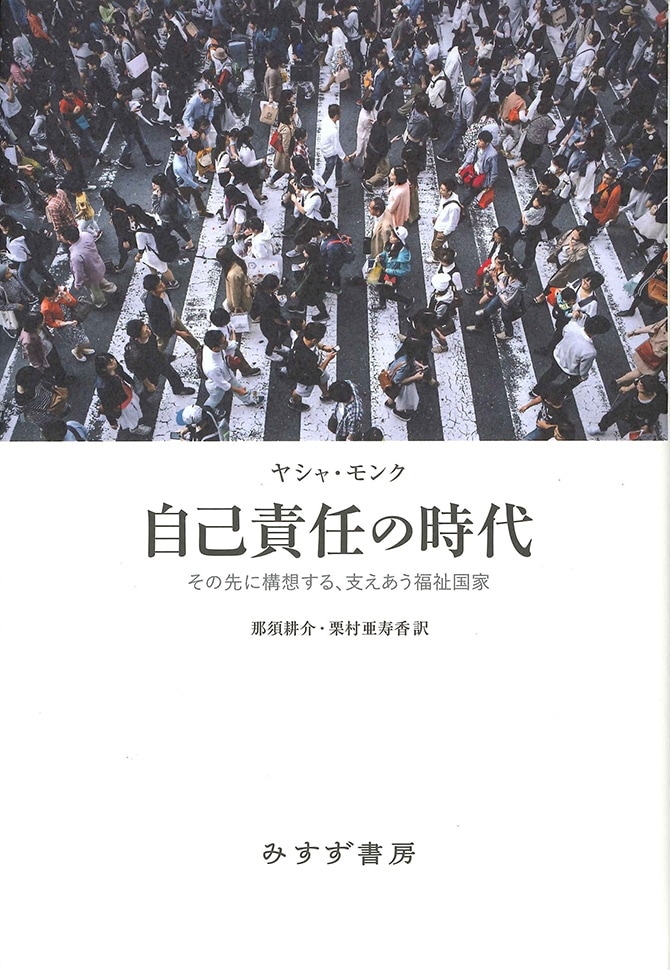No (Wo)man Is an Island
――人間は誰も(女も男も)孤島ではない
またどうして孤独について? この本を執筆していることを人に話すと、まずそう訊かれた。もちろん、全員ではない。そんなことを訊くのは孤独な日々を過ごしたことのない人や、暗闇のなか孤独感に苛まれたことのない人だ。ところが1年もしないうちに、孤独はさほどめずらしい話題ではなくなった――いつの間にか、孤独が至るところに存在するようになっていたのだ。新聞でも取り上げられ、ラジオ番組でも話題にのぼった。孤独は全国的に蔓延し、イギリス政府には孤独担当大臣 1 まで設置された。こうして21世紀の初めに、私たちは「孤独のエピデミック」の真っ只中にいることに気がついた。
同時に、孤独に対する不安が、孤独をいっそう避けがたいものにしていた。孤独についての会話は伝染病のごとく広まるらしく、すでに社会の一部と化してしまった。孤独は、多くの不満をぶら下げるのに便利なフックになった。また、孤独はさまざまな感情を詰め込む大きなカバンにもなった――それは幸福感の欠如や断絶感、憂うつや疎外感、孤立感などをあらわす省略表現なのだ。
だがいっぽう、そうではない場合もある。人はときに孤独を求め、渇望するからだ。また別の来歴をもつソリチュード〔独りでいること〕だけでなく、孤独を――肉体、精神、感覚、態度において、また象徴的な意味において感じる、あの痛切な断絶感を。
では、孤独とはいったいなんなのだろう? なぜこれほど遍在しているのだろうか? 感情的な身体について長いこと思索を重ねてきた文化史家としては、認識されてはいるが定義の定まっていない感情状態が、こうしたモラル・パニック 2 をたちまち引き起こす要因となりうることに興味を引かれる。そして孤独が、怒り、愛情、恐れ、悲しみといったほかの感情状態のように、文脈によってどのように異なる意味を帯びるのかについても興味がある。また、孤独が精神的であるだけでなく、肉体的なものでもあることや、個人の経験としての孤独が、より大きな社会的問題――たとえばジェンダーやエスニシティ、年齢、環境、宗教、科学、経済――によって左右され、それらを反映していることにも興味をもっている。
「経済まで?」と思う向きもあるかもしれないが、孤独は高くつくのだ。イギリス政府があれだけ孤独に注目しているのはほぼそのせいだと言ってよい。欧米では、人口の高齢化によって、孤独に関連する医療および社会的ケアのニーズが高まっている。いっぽうで、その他の国々の状況についてはほとんど注意が払われてこなかった。孤独が時間とともにどのように変化するか、また孤独に対する見方を変えたときにどのように異なる様相が見えてくるかについても、ほとんど注目されてこなかった。もし、孤独は普遍的なものであり、人間の条件の一部であると仮定してしまえば、剝奪 3 がどんなに横行しようとも、誰にもその責任はないということになってしまう。つまり、孤独は政治的なものでもあるのだ。
私の興味は、孤独の歴史にのみ向けられたものではなかった。私はずっと孤独だったのだ。子ども時代、10代のころ、そして作家となり、母となり、離婚を経験し――人生のそれぞれの段階をどう呼ぼうが、私はさまざまなかたちで孤独を味わってきたのであり、そこから本書の題名を思いついた。孤独には来歴がある。それは不変の「もの」ではなく、時間とともに姿を変える変幻自在の獣だ。歴史的には、孤独は「近代的」な感情として登場した。そして孤独は、意味の重層化した概念でもある。本書は、孤独という概念を歴史的にとらえ、孤独が心、身体、物、場所とさまざまに重なり合っていることについて著したものである。
場所というのは、周囲にいる人間と同じくらい、孤独の経験において重要な意味をもっている。私はウェールズの辺鄙な丘陵地で育った。1980年代のことで、まだインターネットはなかった。10代の終わりごろまで、我が家には電話すらなかったのだ。いちばん近くの隣家でさえ1マイルも離れていた。そんな我が家の家庭環境は貧しくて不幸でトラウマになるほどだった。イングランド出身の私たちとウェールズ語を話す村人たちとのあいだには溝があった。私たちはヒッピーで、どこからどう見ても〝よそ者〞だったのだ。私は孤立して独りぼっちだった。とはいえ、私は孤独に耐えていたわけではない。むしろ、愉しんでいた。生まれつき内向型の私は森のなかで物語をつくり、別の人生を思い描きながら日々を過ごした。私の世界には架空の人物たちが住んでいた。
それで満足だったかって?――子どものころは、満足だった。だが大きくなるとそうはいかなくなった。私たちが変わっていくなかで、ニーズも変化する。孤独の経験についても同じことだ。若いときに孤独を経験すると、年を取ってからも孤独が習慣化してしまう可能性があるため、高齢者の孤独に対する介入はもっと早い時期から始める必要があるのだ。また、孤独――とりわけ剝奪と関連性の高い慢性の孤独――は過酷なものになるおそれがある。社会的あるいは感情的に周りの人たちと断絶してしまった場合、人は病気になることがある。人との触れ合いや意義深い関わりを剝奪された場合には、死ぬことさえある。慢性の孤独は、相手を選ばない。依存症や虐待などによって精神的、肉体的な健康問題に苦しんできた人びとの身に、孤独が重くのしかかることもある。
それに対して、たとえば遠くの大学に通うために家を出るとか、転職や離婚などによって味わう一過性の孤独は、個人の成長にとってよい刺激となる場合があり、自分が人間関係において何を望むかを見極めることにもつながる――そして、何を望まないかも(群衆のなかで感じる孤独や、無関心な相手のせいで感じる孤独は、欠乏のなかでも最も悲惨なものだ)。孤独は、人生に暗い影を落とすどころか、人生の大切な選択や、人生という旅の道連れになる場合がある。孤独はときに前向きで人を育むものとなり、私たちが考え、成長し、学ぶ余地を与えてくれるのだ。これはたんにソリチュードや独りでいる状態がよいと言っているのではない。自己の境界線についての認識を深めることは、適切な状況においては、回復につながるということだ。孤独に足を踏み入れても、それがただの水たまりであるかのように、ひょいと抜け出す人もいる。いっぽう、ある人にとっては、それは果てしない海である。
孤独に対する治療法はあるのだろうか? というより、望まない孤独に対する治療法はあるのだろうか? やはり、問題となるのは選択の要素なのだ。手っ取り早く、万人に効く治療法などありはしない。近代の社会的苦悩としての孤独は、集団と対置された「個人の精神」という科学的かつ医学的な概念にもとづいた、包摂性の低く共同性の薄れた社会が形成される過程において、その亀裂のなかで顕在化した。孤独が増大するのは、個人と世界のあいだが断絶しているときだ。このような断絶は新自由主義の顕著な特徴であるが、人間の条件として必然的なものではない。
詩人のジョン・ダンは、1624年の詩〔瞑想録第17「誰がために鐘は鳴る」〕においてこう謳った。「誰が死んでも我が身を削られるも同じ/私もまた人類の一員なのだから」。人間であることによって、私たちは必然的に自分よりも大きな力の一部となる。独り身の高齢者が年を取るのを恐れることや、暴力の被害者が精神的なサポートを得られないことや、ホームレスの人びとが存在しヴァルネラブル 4 な状態にあることは、いずれも必然ではない。こうした構造的な孤独の強制は、環境やイデオロギーの産物なのだ。もちろん、裕福でも孤独な人や孤立した人はいて(むしろ、そういう人は多い)、お金は「帰属意識 5 」を保証するものではない。だがそれは、貧困によって追い込まれた社会的孤立とは異なる種類の孤独である。18世紀以来、自己と世界、個人と共同体、公と私のあいだで深まった分断やヒエラルキーの多くは、政治や個人主義の哲学を通じてもたらされたものだ。時を同じくして孤独という言葉が出現したのは、ただの偶然だろうか?
孤独が疫病だとすれば、その蔓延を食い止めるには、孤独がはびこる条件を一掃できるかどうかがカギとなる。だが私は何も、あらゆる孤独が悪いとか、欠乏感としての孤独は近代以前には存在しなかった、などと言っているのではない。「孤独は近代のものである」という主張に対する反論として考えられるのは、「1800年以前に孤独という言葉が存在しなかったからといって、人びとが孤独を感じていなかったとは限らない」というものだ。これに対し、私は簡潔にこう言いたい。孤独を表す言葉が発明されたのは、それまでなかった新しい感情状態がとらえられたことを反映しているのだ、と。
たしかにソリチュードという言葉は、近代以前にはネガティブな意味を帯びることもあり、人びとは独りで過ごすことをネガティブな意味で語った。だが、当時の哲学的、精神的な枠組みは異なっていた。近代以前のイギリスでは、人びとは一般的になんらかの神――ふつうは父権的な神――を信じていた。信仰は人びとに帰属意識の枠組みを与えたが、よかれ悪しかれ、それはもはや存在しない。中世の修道士は独りきりの隠遁生活を送っていたが、修道士は神がつねに存在する精神世界の住人であり、そのような物語の枠組みをもたない人のように、見捨てられた感覚や欠乏感を味わうことはなかっただろう。21世紀の私たちは、自分たちが創り上げた世界のなかで――集団的な帰属意識よりも、自己および自己の独自性に対する確信のほうがはるかに重要な意味をもつ世界で――宙ぶらりんになっているのだ。
本書は網羅的なものではなく、ひとつの来歴にすぎない。だが、近代における孤独の新たなとらえ方や探求の仕方を模索することで、孤独のもつ身体的、心理的な意味を考察していく。こうした心身の二元性、すなわち心と身体の分離については、歴史学の長期持続のアプローチによって広い視野でとらえる必要がある。私が研究してきたのは近代初期の文化であり、そこでは心身の分離は見られず、感情(あるいは情熱)は心身一体的なものとしてとらえられていた。だがこんにちでは、身体のケアも心のケアと同様に重要だと考えられてはいるものの、孤独はもっぱら精神的苦痛とみなされている。
私が本書を執筆しながら切実に感じたのは、孤独がいかに身体的なものであるか、欠乏感のせいでいかに空虚さを覚えるか、ということだった。私は孤独が及ぼす影響を自分の身体で観察したのだ。そうした身体化された経験から自分を切り離して考えることなどできるはずもなく、私は五感を楽しませた。ちょっと贅沢に、香りのよい石鹼やアロマキャンドルを買い、音楽や瞑想のBGMを繰り返し聴いた。犬をなで、赤ちゃんの首の匂いをかぎ、子どもたちを抱きしめた。バーベルをもち上げ、毎日1万歩以上歩き、野菜を刻み、料理をし、眠った。そうやって自分の身体をケアすることで、この身体がどこから来たのか、あらためてそのルーツに思いを馳せ、この私もまた過去から綿々と連なる共同体の一部なのだと感じた。私は身体をケアすることにも、感情面における経験がたんなる脳の働き以上のものであることを認識することにも、安らぎを覚えた。そして孤独は、ほかのあらゆる感情状態と同じように、精神的であるだけでなく身体的なものでもあることを思い知らされた。結局のところ、私たちは肉体をもつ存在であり、私たちの世界は、孤立だけでなく信念体系や物、動物、人間という他者との関係を通じて定義されるものなのだ。