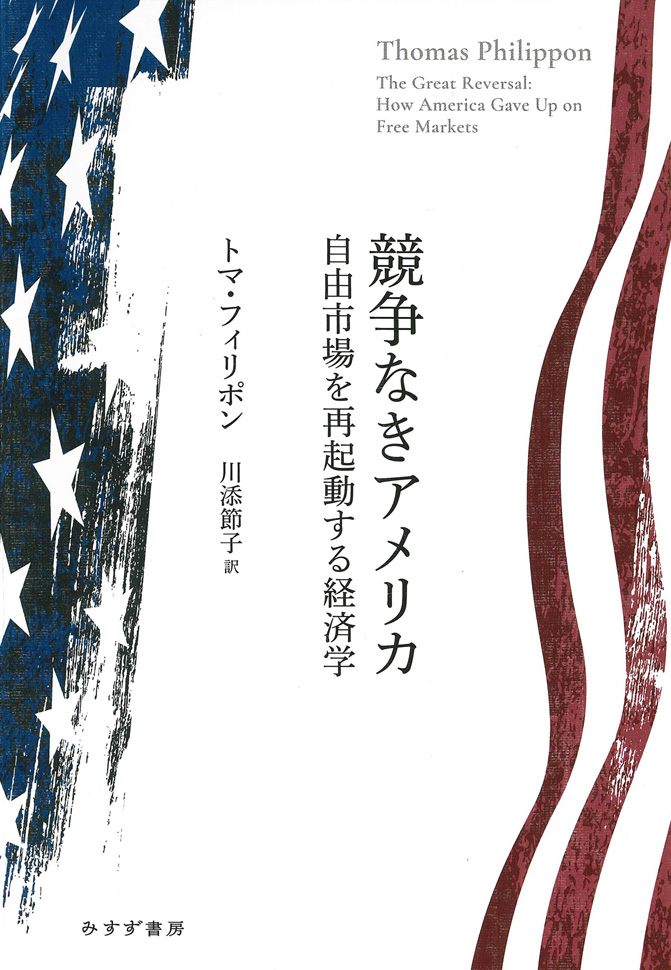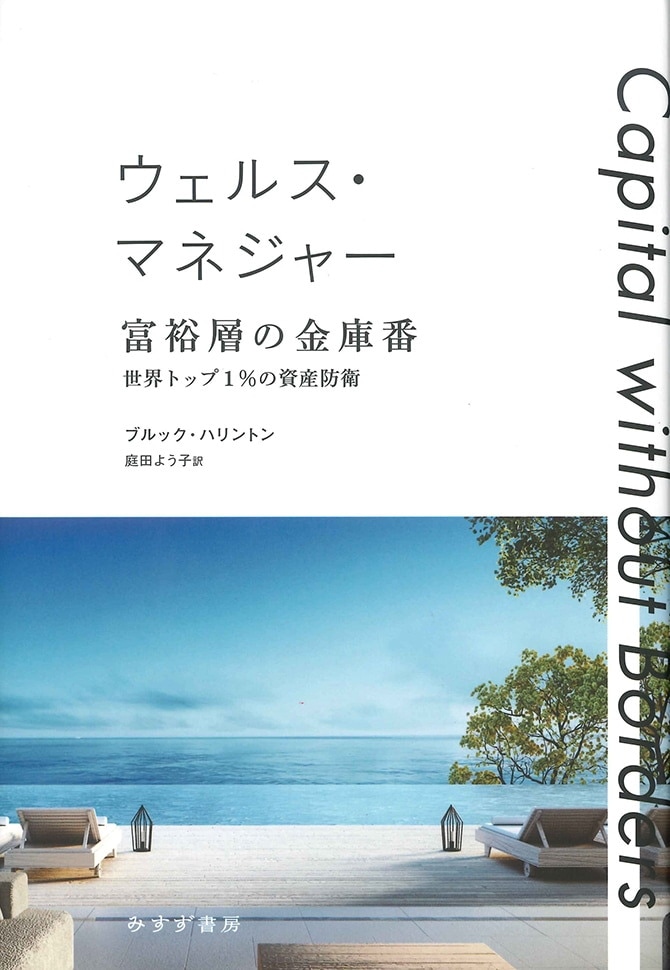世界には国がいくつあると思う? スマホで調べないで答えてみて。わからない? 答えは、約200カ国。ざっくりだけど。では、2150年ならどうかな。2150年の世界では国はいくつになっているだろうか。200より増えている? 減っている? 1000カ国になってたりして? それとも、わずか20カ国とか? 2カ国かも? あるいは、世界が統一国家になってたら?──この地図は、どんな未来を示しているだろう。将来の国の数によって、まったく違う未来が待っているとしたら?
2009年に同じ思考実験を行った人物がいた。41歳のベンチャー投資家ピーター・ティールだ。オンライン決済企業ペイパルの創業とフェイスブックへの初期投資で財を成したティールは、前年に起きた金融危機で大打撃を受けていた。考えることはただひとつ──税金を取りに来る民主国家から逃れる方法だ。
彼は書く。「私はもはや自由と民主主義が両立するとは思っていない。自由至上主義者(リバタリアン)が取り組むべき大仕事は、あらゆる形態の政治から逃れる方法を見つけることだ」。国の数が増えればそれだけ、カネを奪われる可能性のある場所は増える。しかし、どの国も『金の卵を産むガチョウ』が逃げると困るから、増税を避けようとするだろう。そして、ティールはこう述べた。「もっと自由な世界がいいなら、国の数を増やせばいい」。
ティールは「数千の政体からなる世界」というアイデアを未来の理想郷として提示した。ただ彼がそこで触れなかったのは、自分が説明しているその未来が、すでにいろんなかたちで実在している、という事実だ。
標準的な世界地図は、さまざまな色の不均等なモザイク模様になっている。欧州とアフリカでは色が混み合う一方で、アジアと北米では同じ色が広がる。これが見慣れた世界の姿であり、学齢期の子どもはこの地図で世界について学ぶ。ティールの言う、「それぞれの土地に国旗や国歌、民族衣装、特徴的な料理がある」世界だ。私たちは数年ごとに、この世界の姿をオリンピック開会式のパレードで目にして安心する。「みんなひとつの世界に暮らす仲間だね」と。
しかし、世界をこうした「国のジグソーパズル」としてのみ捉えていると判断を誤る。実際、学者らが指摘するように、いまの世界は穴やデコボコだらけ、ぼろぼろかつ不規則、小さく切り刻まれた不愉快な場所だ。国という容れ物の中に特別な法律が適用される異質な土地や、例外的な区域、特異な法域が存在する。その呼び名は、都市国家、ヘイブン、飛び地、自由港、ハイテク工業団地、免税特区、イノベーション・ハブなどさまざまである。いまや世界の国々の内部にはこうした特殊な区画、「ゾーン」が無数にあり、それが現在の国や政治のあり方を決めているというのに、私たちはそのことをようやく理解しはじめたばかりだ。
ゾーンとは何だろう。基本的には、通常のさまざまな規制の制限を受けない、国内の異質な「飛び地」だ。その区画内では一般的な課税権が留保される場合が多く、投資家(企業)が事実上、独自にルールを決められる。ゾーンは準治外法権区域であり、受け入れ国の土地でありながら異なるルールで動いている。ゾーンの種類は実にさまざまで、ある公式統計によれば、現在、世界には少なくとも82種類のゾーンがある。その代表的なものが、経済特区(スペシャル・エコノミック・ゾーン)、輸出加工区(エクスポート・プロセシング・ゾーン)、外国貿易地域(フォーリン・トレード・ゾーン)だ。社会経済学的な観点から見れば、ゾーンは国境をまたぐ製造ネットワークの拠点としての機能を持つ。多くの場合、有刺鉄線で囲まれているその場所は、人々が低賃金で働く製造現場だ。
そして視線を転じると、多国籍企業が利益の秘匿に利用する租税回避地としてのゾーンの姿が浮かび上がる──経済学者のガブリエル・ズックマンは、この利益を「失われた国家の富」と呼ぶ。企業の利益がこうした低税率または免税の法域に流れ込むことにより、米国だけで年間700億ドルの税収が失われる一方で、企業や個人が節税に利用する海外のタックスシェルターには、世界の富のうち推定8兆7000億ドルが眠っている。カリブ諸島の中には、住民の数より登録企業数のほうが多い島もある。バラク・オバマ元米大統領は1期目の出馬の際に、法人約1万2000社が拠点を置くケイマン諸島のビル「アグランドハウス」を問題視して糾弾した。「これは史上最大のビルか、もしくは史上最大の税金詐欺だ」。だが、その行為は実はまったく合法であり、世界の金融システムではごくありふれた現象だった。
いま世界には、5400カ所を超すゾーンがある。ティールが空想した「1000の国からなる未来の世界」よりはるかに多い数だ。実際、この10年だけで約1000カ所のゾーンが新たに誕生している。それはひとつの工場や倉庫ほどの大きさの場合もあれば、世界市場の物流ネットワークの中継地点や、関税を回避しつつ製品を保管・組立て・精製する基地であったりもする。また、韓国の松島新都市(松島国際ビジネス地区)、サウジアラビアのNEOM、日本の神奈川県藤沢市の一角など、まるで民間企業が運営する都市国家のように独自ルールで動く都市型の大型プロジェクトもある。
2021年には、米ネバダ州の議員らが同様のアイデアを提起した。州内に企業を誘致し、その企業に独自の法律を作らせたらどうかと考えたのだ。うまくすれば、100年前の企業城下町が「イノベーション・ゾーン」として復活する。また英国では、保守党政権がEU離脱後に脱工業化が進んだ北部の「底上げ」計画の目玉として、複数の免税特区や自由港の創設を打ち出した。なぜこんな奇抜なアイデアを? それは、1985年にドバイに開業したジュベル・アリ自由貿易地区に対抗するためだ。このドバイの特区では、企業が免税措置を50年にわたり享受できるうえに、寮に暮らしながら英国の生活賃金の数分の一の報酬で働く外国人労働者が使える。
資本主義のこうした仕組み──すなわち国民国家の領地に異なる法律で動く例外的な区域を作り、民主的配慮もなく運営する仕組みを説明するために、私は穿孔(穴を開けること)の比喩を使う。哲学者のグレゴワール・シャマユーは、民営化プロジェクトに別の比喩を用い、社会構造を内側から崩すカミキリムシになぞらえた。比喩は他にもある。すき間を生かして編んでいくレース編みを思い出してみよう。できあがったものは、編まない部分のおかげで模様が完成する。レース編みの世界では、これを透かし編みと呼ぶ。世界経済を理解するには、その「すき間」を見る必要があるのだ。
世界のゾーンのほとんどは、アジア、中南米、アフリカに集中している。そして、その半数近くを抱えるのが中国だ。欧州と北米のゾーンの数は、合わせても1割に満たない。しかし、後述するように、ゾーンを最も熱烈に支持するのは欧米企業で、こうした企業は私がミニ政体と呼ぶもの──つまり小規模な代替的政治体制を創造する実験場としてゾーンの存在を擁護している。ゾーンの支持者らは、国からの離脱と国土の細分化を進めて国内外に自由に活動できる領域を切り開くことで、他国への教育・実証効果が生まれ、やがて自由市場のユートピアが実現する可能性があると訴える。米保守系シンクタンクのヘリテージ財団に所属していた経済学者スチュアート・バトラーは、1982年に「国内に自由な領域ができれば、それを取り巻く不自由な国家の基盤を崩せるかもしれない」と書いた。「穿孔」を推進する者たちは、メロドラマに登場する右派のゲリラを気取り、国民国家をゾーンごとに切り崩して解体し、取り戻そうというのだ。ひとたび低税率で規制のない新規ゾーンに資本が集まれば、理論上は、それまで消極的だった国々もこの異常な形態を模倣せざるをえなくなるだろう。小さな土地からスタートしたゾーンは、こうして私たちが暮らす国家の新たな最終形態を目指して進んでいく。
本書は、既存の社会を壊しながら世界中に広がっている破壊系資本主義(crack-up capitalism)の物語である。それはすなわち、利益と安定した事業運営を目標とする民間企業による過去40年間の個別の活動と、政府の積極的な後押しにより実現したいまの世界を描写したものだ。また本書は、綿密に練られたイデオロギーの物語でもある。つまりこのタイトルには、いまの世界の仕組みを示すと同時に、その世界を変えようと努力する人々の姿を紹介する意図も含まれている。それは、かつてないほど人々が互いにつながり、同時にますます分断が進む世界を描くひとつの方法だ。急進的な資本主義者は、社会契約の突然変異の兆候に注目し、社会の解体作業を加速して儲けられないだろうか、と考える。彼らは、ライオネル・シュライヴァーが2016年に発表した近未来小説『マンディブル家の人々』で触れた、「最近できたばかりの終末論的経済学」の信奉者だ。
しかし、ゾーンが遠い世界の話かと言えば、実はそうでもない。類似の現象は一般家庭でも起きている。ほとんどの場合、それは国からの完全な離脱や新国家の樹立とまでは行かず、また権力の頂点を極めることでもなく、むしろ数多くの小さな拒否行為の積み重ねだ。ある急進的市場主義者は、これを穏やかな離脱と呼ぶ。私たちは、子どもを公立学校に行かせない、通貨を金や暗号資産(仮想通貨)に換える、税金の安い国に移住する、2つ目のパスポートを取得する、タックスヘイブンに国籍を移す、といった方法で実際に離脱を達成できる。民間企業が運営するミニ国家とも言えるゲーテッド・コミュニティーは、周囲を塀などで囲んで警備を強化した新形態の居住区だが、私たちはそうした場所に住むことで国から離脱できるし、実際に多くの人がそうしてきた。
21世紀が始まる頃には、米国の南部と西部で新たに着工した開発計画の約半数がゲーテッド・コミュニティーや総合開発型不動産になっていた。入口にゲートのあるこうした「飛び地」は、いまやラゴスからブエノスアイレスまで世界のいたるところにある。インドのゲーテッド・コミュニティーの建設は、まず鋼鉄製の板を経済特区周辺の公道に設置して道路を占拠することから始まる。その後、独創的な総合都市計画を土台とする複数の「植民地」が経済特区を取り囲む流れだ。
ピーター・ティールの下で働いていたあるベンチャー投資家は、この種の「穏やかな離脱」を指す絶妙な新語を生み出した。アンダースロー〔訳者注:アメフトで相手に届かないパスを投げること〕だ。彼にとって最高の政治モデルは、企業だった。顧客には選択権があり、商品が気に入らなければ他の店で買えばよい。誰も顧客に特別な要求はしないし、買う側が店に対して何らかの義務を感じる必要もない。半世紀前に経済学者のアルバート・ハーシュマンが提示した古典的な二項対立で説明すれば、私たちは「意見を述べる」より「退店する」という戦略を取りがちだ。
それぞれの「穏やかな離脱」の動きとは、企業がスイスやカリブ諸島に登記簿上の所在地を移して利益をため込む行為、免税制度の利用をめぐる税務当局とのにらみあい、巡回や拘束、抜き打ち検査のために警備員や警備会社、または傭兵を雇う、といったことだが、それはゾーンにとっての小さな勝利であると同時に、社会構造に生まれた小さな穴でもある。私たちにゾーンで暮らせと勧めてくるのは、共有すべき数々の責任を私たちが放棄することで最も利益を得る連中だ。100年前の資本家は「強盗男爵」と揶揄されながら図書館を作ったが、今日そうした金持ちは宇宙船を造っている。
本書で紹介するのは、直近の過去の出来事と、問題を抱えた世界の現状だ。この世界で大富豪は国家からの脱却を夢想し、公共の概念は忌み嫌われるものとなった。本書は、社会構造にいくつもの穴を開け、公共という考えを拒否し、国からの離脱や逃避を試みる人々の数十年にわたる活動の物語である。
*
本書のテーマである破壊系資本主義の存在感の大きさを理解するには、少し過去にさかのぼり、学者らが語ってきた過去数十年間の大きな出来事を思い出す必要がある。グローバル化の時代は、1989年11月9日に起きたベルリンの壁の崩壊で幕を開けた。ブルース・スターリングは小説『ネットの中の島々』で、この密につながった地球のビジョンを、「そのすべてにかぶさる網、グローバルな神経系、たこ足状のデータ網の中につなぎあわされた世界」と描いた。状況を視覚化する際に強調されるのは「つながり」だ。レーザーの青い光が世界の遠く離れた地点を結び、やりとりや移動を助ける。
この趨勢は相互連携の実現に向かい、壁の崩壊から数年のうちに世界貿易機関(WTO)、欧州連合(EU)、北米自由貿易協定(NAFTA)が誕生する。しかし、よく見れば歴史には別の流れがあり、世界ではこうした連携の裏で分断も同程度に進んでいた。東西ドイツは1990年に再統一したが、翌年にはソビエト連邦が崩壊する。またユーゴスラビアはEU創設の裏で瓦解していき、ソマリアでは内戦が勃発して10年以上も分裂状態が続いた。
冷戦が終わると、古いバリケードにかわって新しいバリケードが登場する。モノとカネは自由に行き来したが、人間はそうはいかない。こうして世界中に壁ができた。ある推計によれば、世界の1万6000キロメートルを超す国境が壁で補強されたそうだ。1990年、米国はサンディエゴの南に初の国境フェンスを設置。当時のビル・クリントン大統領は、北米の貿易を自由化する一方で「ゲートキーパー作戦」を承認し、メキシコとの国境管理をさらに強化した。
ベルリンの壁が崩壊した半年後、英BBCがドラマ『苦難の旅』を放送する。このドラマは、スーダンのある男性が、戦争と貧困で行き場をなくした人々を引き連れて北アフリカを横断し、欧州に向かう様子を描いたものだ。最後の場面で、一行はスペイン南部のリゾート地に到着する。ヘリコプターが頭上を飛ぶ中で、武装した兵士らが行く手を阻もうと隊列を組む。映像は、その隊列に向かって階段を登る人々の姿を映し出す。そして、マイアミ・ドルフィンズの帽子をかぶったアフリカの10代の少年が、兵士らに射殺される。コスモポリタニズムの約束が破綻する象徴的な場面だ。2014年以降だけで、2万4000人以上がアフリカから欧州に渡ろうとして海で亡くなっている。グローバル化には、求心力と遠心力が同時に働く。それは私たちを結びつける一方で、引き裂きもするのだ。
本書では、国家とポスト国家のさまざまなイメージを生み出した政治的揺籃期でありながら、過小評価されている1990年代という時代に注目する。かつてないほど広範な統合と、過去に例のない大規模な経済同盟を背景とするこの10年間の物語を通して、離脱主義者たちの莫大なエネルギーと、ミニ政体の実験に対する彼らの熱意を明らかにしたいと思う。
1989年に政治学者のフランシス・フクヤマが「歴史の終わり」について考察したとき、彼は世界が自由民主主義のモデルに収斂していくと想定したが、それは特定の統治モデルの支配が揺るがないことを前提としていた。つまり、単一の世界経済システムの中に、国境と自決権を有する複数の国民国家が収まり、それらが国際公法を通じてつながる、というモデルだ。しかし、資本主義が世界規模で進化する中で、その図式は変わった。帝国が滅び、共産主義が終焉したことで、新たな国民主権国家が次々と誕生したが、それと並行してもうひとつの政治形態も産声を上げていた。それが1990年代に始まり、現在ますます勢力を強めている「ゾーン」だ。この新たな領域は、いまや国民国家と肩を並べるまでになっている。
グローバル化の再考には、このゾーンの存在が役に立つ。ゾーンとは、従来の世界地図が崩れ去る中で、学者らの言う「オフショアの群島式経済区」として生まれ、移り気な顧客、節約したい企業、利益を求める投資家を引き付けようと絶え間ない競争が続く場所だ。経済学者のトマ・ピケティとエマニュエル・サエズが執筆してベストセラーとなった論文や、パナマ文書やパラダイス文書の衝撃的な暴露をきっかけに、私たちはタックスヘイブンという特殊なゾーンの詳細を学びはじめている。タックスヘイブンを「富をため込む人々」の道具とみなすのは正しいが、それだけでは不十分だ。私たちは、タックスヘイブンが急進的市場主義者の蓄財の手段であるばかりでなく、そこから世界の政治体制全体を再編するためのアイデアが生まれたことも押さえておく必要がある。
右派の資本主義者にとって、ゾーンはさまざまな役割を果たす。ゾーンの威圧的な性質とそれに伴う資本逃避(キャピタルフライト)の脅威は、西欧と北米にわずかに残る社会主義体制の存続を脅かすものとして機能する。またゾーンは、現代の政治的右派が共有するイメージの中心をなす第2の信念──すなわち「資本主義の実践に民主主義は不要」という信念も示している。
東西ドイツが再統一したとき、政治哲学者のレイモンド・プラントは次のように述べた。「東欧で共産主義が崩壊したことから、資本主義と民主主義の関係は明白だと思った人もいるだろう。しかし、それは間違いだ。知の最前線で自由市場について議論する学者の一部は、いまではむしろ市場と民主主義の関係を危惧している」。プラントは、「この議論によれば、西洋社会で発展してきた民主主義は、市場の成長と維持には有害である可能性がある」とも指摘した。ある意味、香港のような長らく植民地だった場所や、アパルトヘイト下の南アフリカ、アラビア半島の独裁主義的な「飛び地」は、政治的自由が経済的自由を実際に損なう可能性を証明している。
ところで、「資本主義の実践に民主主義は不要」という考えは、私たちの想像以上に広まっている。ドナルド・トランプの最初の選挙戦で上級経済顧問を務め、連邦準備理事会(FRB)の理事候補にもなったスティーブン・ムーアは、ヘリテージ財団で長年フェローを務める主流の右派知識人だが、彼は率直にこう述べている。「資本主義は民主主義よりずっと重要なものだ。私は民主主義をそれほど信じてもいない」。これは軽いジョークではなく、うっかり口を滑らせたのでもない。この考えは確固とした立場として過去50年間に静かに広がり、私たちの法律や制度、そして政治的野心の様相に多大な影響を与えてきた。
いま起きている世界地図の崩壊は、決して自生的に生じたものではない。この動きには強力な応援団がいた。本書では、ピーター・ティールの前後の時代に登場した一群、つまり国民国家からなる世界の崩壊を予見し、その動きに加勢した人々について書いている。冷戦が終わると、彼らは驚くべきことを口にした──資本主義は、本当は秘かに敗北していたのではないか。共産主義の超大国が去って社会民主主義の超大国があとを引き継いでも、国家の歳出は増加の一途をたどるばかりだ。資本主義が真に勝利するためには、おそらくそのやり方をもっと強力に推し進めるべきだった──。
もし歴史が終焉するとき、そこにあるのが自由民主主義という条件の下に200数カ国の国民国家が協力しあう世界ではなく、さまざまな政治体制を持ち、絶え間なく競争を続ける数万の法域からなる世界だとしたら? ある急進的市場主義者は、こう問いかけた。「もし国家権力の中央集権化という過去200年間で最大の政治トレンドが、21世紀にひっくり返るとしたら?」 もし私たちが社会を一から作り直す必要があるとしたら、どうしよう?
1970年代に始まったゾーンは、迷走しがちな大衆民主主義や、乱立し肥大化する扱いづらい国民国家のスマートな代替案としてもてはやされてきた。本書が主として取り上げる思想家たちのマントラは、グローバル化ではなく離脱・分離独立だ。本書では、資本主義のユートピアを求めて半世紀にわたり世界中を駆けめぐってきた、この急進的市場主義者の一団を追っている。
その旅は、香港からロンドンの再開発地区ドックランズや、都市国家のシンガポールへ、アパルトヘイト後期の南アフリカから現代の南部連合支持者が暮らす米国南部、また米国西部のかつての未開拓地区へ、「アフリカの角」とも呼ばれるソマリアの紛争地域からドバイとその世界最小の島々へ、そして最後にメタバースの仮想世界へと続く。これら破壊系資本主義を推進する人々は、新たな理想郷を思い描いていた。そこは資金を預けられる非常に柔軟な「動く要塞」であり、もっと公平な現在や未来を求めて要求を突きつけてくる民衆を排除できる場所だ。
2020年に刊行された小説『赤い薬』の中で、著者のハリ・クンズルは、幻覚を見ながら声明文を書く男の姿を描いた。その男が目指すのは「最終的に従来のオープンな政治を完全に排除し、政治を商業取引(ディール)の手法で代替する体制だ。その取引はブラックボックスで監督不能、実像は取引相手にしか見えない。そして三権分立や、取引当事者の決定事項に不服を申し立てる権利はもとより、いかなる権利も存在しなくなり、残るは権力の行使のみとなる」。この描写は、本書で紹介する世界をよく捉えている。
私たちがこれから目にするのは、民主主義なき世界で広がりつつある急進的な資本主義の実像である。