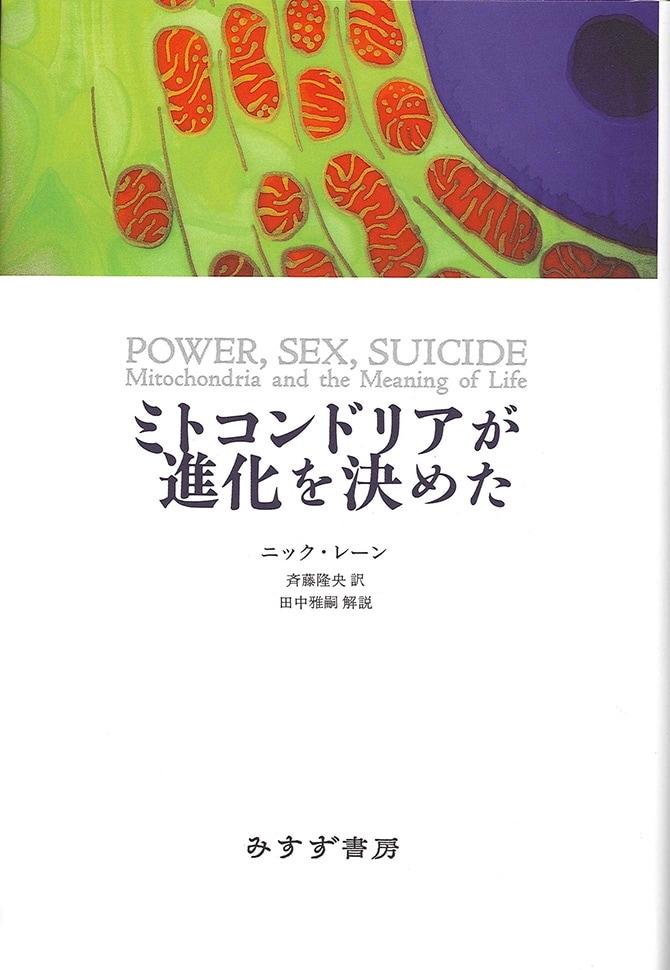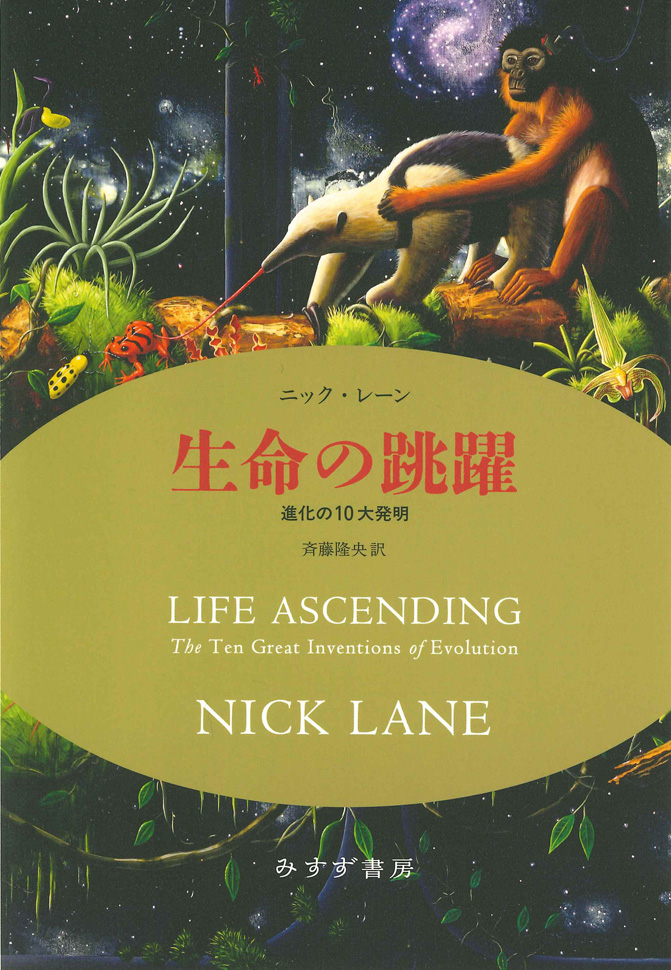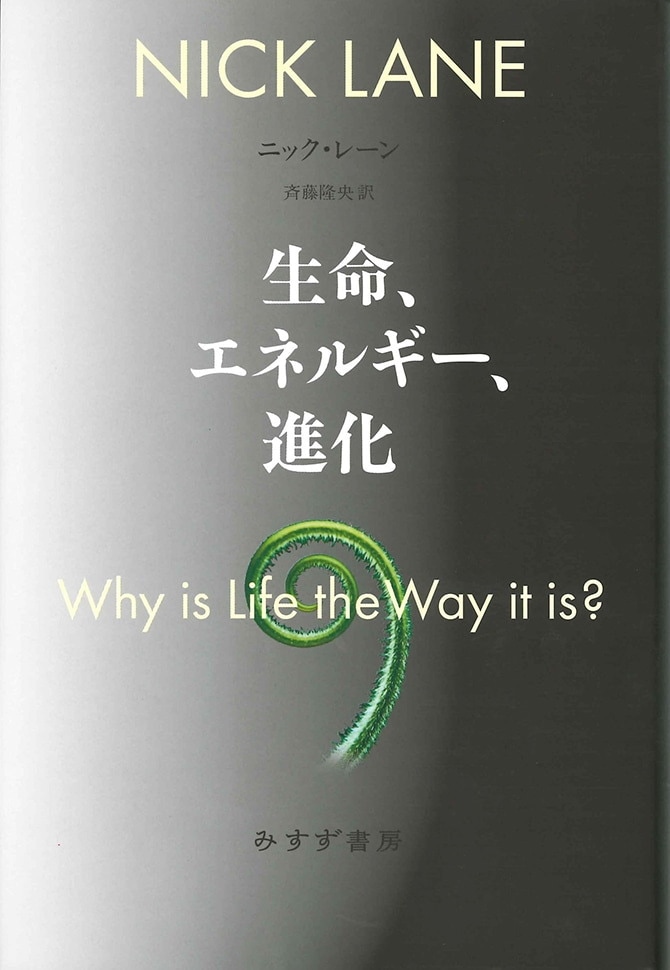『ミトコンドリアが進化を決めた』『生命の跳躍』『生命、エネルギー進化』といった著作で、わたしたちの生命観をアップデートしつづけてきた科学者、ニック・レーンによる約10年ぶりの邦訳最新刊『生命は変換の環である』。本書冒頭部分「はじめに」から抜粋してお届けします。
「はじめに 生そのもの」より
(抄)
ここ何十年も、生物学を支配してきたのは情報だった──遺伝子のもつ力である。遺伝子が重要なのは疑いないのだが、生きている原生動物と死んだばかりのそれとで、もっている情報量に違いはない。生と死の違いは、エネルギーの流れにあり、細胞が単純な構成要素から絶えず自身を再生する能力にあるのだ。*1
現代の生物学の見方では、遺伝情報がエネルギーと物質の流れを組織している。おおざっぱに見れば、生物は情報ネットワークと制御システムによって理解できる。分子のふるまいとその相互作用や反応を決定する熱力学の法則も、情報によって書きなおすことができる。シャノン・エントロピー、つまり情報のビットの法則だ。しかしこの見方は、生命の起源についてはパラドックスを生み出す。そもそもその情報はどこからもたらされるのか? 生物学の領域には、すでに単純な説明が存在する。自然選択がランダムな差異をふるいにかけ、世代を重ねるごとに、うまくいくものを残し、そうでないものを排除するのだ。情報は、時間をかけて機能とともに蓄積される。細かい点についてはあれこれ論じることもできるが、難しい考えではない。ところが生命の起源に対しては、この見方は役に立たない。情報を生命の中心に据えると、機能の出現、つまり生物の情報の起源にかんする問題が生じるのだ。そればかりか、進化の厄介な道筋を理解するうえでも問題がある。とくに、カンブリア爆発における動物の出現のように、急激な変化が長い間隙をおいて起きることは、さまざまな生命で遺伝子配列──情報──を継続的に探っても理解しがたい。問題はほかにもあり、われわれがなぜ老化して死ぬのか、何十年も研究していながら、なぜいまだにがんなどの病気に苦しめられているのか、またなにより根本的な疑問になるが、主観的な経験がいかにして意識を生み出すのかを理解することもできない。
生命を情報のみによって考えるのは、ゆがんだ見方だ。情報の起源を説明しようとして新たな物理法則を探し求めるのは、間違った問いかけのしかたであり、なにしろ意味がないのだから答えられない。はるかに良いのは、生物の形成期にまでさかのぼる問いかけで、「どんなプロセスが細胞に命を吹き込み、無生物と分け隔てるのか?」というものだ。生気というものがあり、生命は無生物とは根本的に違うとする考えは、ずいぶん前に覆され、今ではいわば燃やすべきわら人形として持ち出されるばかりになっている──レーウェンフックと同じようにせわしなく動く微小動物に魅せられた人にとっては、無理もない錯覚だが。しかし、生化学──細胞をめぐるエネルギーや物質の流れを扱う私の専門分野──はこれまで、この絶えざるフラックスがいかにして生じたのかや、今日そのフラックスによる基本的な刻印が、いかにして細胞やそれが構成するあなたや私のような生物の生死を決定しているのかについては、いくつか例外として目を引く研究例を除けばまるで無頓着だった。
本書では、エネルギーと物質の流れがいかにして生命の進化や、さらには遺伝情報をも構成し、われわれ自身の生に消えないしるしを残しているのかを探ることになる。私は標準的な見方を覆したい。遺伝子や情報は、われわれの生の核心的な部分を決定してはいない。むしろ、ずっと非平衡の状態にある世界で、エネルギーと物質の絶えざる流れが遺伝子そのものを魔法のように生み出しており、情報に浸りきった現在のわれわれの生においてさえ、遺伝子の働きはそうしたフラックスが決定しているのだ。動きはフォルム(形)を生み出す。私は、外見上今は隠れているとてつもない温故知新をとらえてみたい。生化学の教科書に載っているような周知の機構が、(とくにふたつ挙げるとすれば)生命の起源とがんの両方についての、新たなパラダイム(理論的枠組み)を生起させつつあることを。数十億年も隔たり、とりまく惑星環境も大きく異なるそんな異質なふたつの問題が、どうして結びつくのか? この新たな見方の中核には、エネルギーを使って無機分子──ガス──を生命の構成要素に変えながら、その逆もおこなうような、驚くべき両面的な反応回路がある。このエネルギーと物質のサイクルを理解すれば、生命の起源を破壊的ながんと結びつける、あるいは最初の光合成細菌をわれわれ自身のミトコンドリアと、進化における動物への急激な飛躍を硫黄のぬかるみと、われわれの惑星のビッグヒストリーをわれわれ同士のわずかな違いと──さらにはひょっとしたら意識の流れとも──結びつける、深遠な化学的関連性を明らかにできる。本書では、生命に命を吹き込み、死ぬと消え失せるような本質的な化学反応を理解すると、生物学およびわれわれ自身の存在にかんするしぶとい謎のいくつかを解明できることを見ていこう。
*1 私がエネルギーの流れについて語る場合,実際には物理学で「自由エネルギー」と呼ばれるものを指している。つまり,(熱として散逸されるのではなく)仕事の動力に利用できるエネルギーのことだ。これは本書全体を通して言える。また構成要素について語る場合,アミノ酸やヌクレオチドなどの低分子を指している。組み合わさってタンパク質やDNAのような巨大なマクロ分子(高分子)を作り出せる要素だ。やはりこれも本書全体を通して言える。
(中略)
クレブス回路
生化学や医学を学ぶたくさんの学生は、クレブス回路の各段階を丸暗記させられる。そうした学問で象徴的な地位を占めながら、それはほとんど学生に好かれることがなく、きちんと理解されることもない。その一因は、生化学的メカニズムが視覚化しにくい点にある。目に見えない難解な反応群からなり、どの段階も、一見ささいにしか思えない炭素原子と水素原子と酸素原子の組み換えなのだ。そのうえ、真の機能さえもよくわかっていない。教科書によれば、クレブス回路は、食物の炭素骨格から水素原子を剝ぎ取り、それを酸素という飢えた野獣に与えることによって、エネルギーを生み出す(もちろん、教科書にはこのとおりの言葉で書かれてはいないだろうが)。これが細胞呼吸のプロセスである。各段階で解放されるエネルギーは、細胞のなかで巧みにとらえられ、利用される一方、水と二酸化炭素という不活性の骸が外界に排出される。だが、そもそもなぜ回路なのか? なぜ単純な数段階ではないのだろうか? クレブス自身がもっともらしい答えをひとつ提示している。非常に短い炭素骨格をただ燃焼させるだけでは効率的なプロセスにならないので、回路が必要になったというものだ。しかしのちに微小な炭素骨格を燃焼させる細菌が発見されると、その考えは完全に間違いであることが証明された。
クレブス回路がそのような形で存在する理由は、この回路が細胞を形作る基本的な素材の多くを提供するという事実のために、いっそうわかりにくくなっている。ほとんどのアミノ酸は、クレブス回路にある分子から直接あるいは間接的に作られている。細胞膜を作るのに必要な長鎖の脂質分子もそうだ。糖も、やはりクレブス回路によって作り出されている。DNAに含まれる「文字」(ヌクレオチドという)までも、糖とアミノ酸でできているので、元をたどればクレブス回路に行き着く。ほかにもまだまだ挙げられるが、クレブス回路は細胞の成長と再生をうながす生合成のエンジンだと言えばもう十分だろう。だが、作るのにも壊すのにも、燃焼にも再生にも、同じ経路を用いるのはなぜなのだろうか? 不死鳥でさえ、燃焼と再生の両方を同時にすることはできない。たいていの代謝経路では、フラックスが一度にふたつの方向には進めないという単純な理由により、生合成と分解は分かれている。ところがクレブス回路では、同じ分子が、アミノ酸に変換されてタンパク質の合成に使われることもあれば、呼吸の炉のなかでちぎれて燃え、細胞のエネルギーを生み出すこともある。エネルギーの生成と物質の合成がせめぎ合うこのメリーゴーラウンドの存在に、何か理由があるのだろうか?
10年前なら、この疑問に答えるのは難しすぎて、ほとんどの研究者は考えあぐねていただろう。「なぜ」と問うことは、これまで生化学者には空理空論と片づけられていた。ところがその後、クレブス回路に蓄積される分子が、細胞の状態を遺伝子に知らせ、何百、何千もの遺伝子のスイッチのオン・オフをしていることが明らかになった。教科書に載っている味気ない生化学的メカニズムどころか、いまや、クレブス回路を経る代謝フラックスがさまざまなパターンをもち、両面的ではあるが強力なシグナルを生み出すことがわかっているのだ。ウミガメなどの水に潜る動物が酸素なしで何時間も水中で生きられるようにするシグナルが、がんの増殖や炎症をもうながす。クレブス回路と関係のある一部の遺伝子の変異が、侵攻性〔増殖が速いこと〕の腫瘍において何度も生じるのだ。さらに、クレブス回路を通るフラックスは、(たとえば糖尿病に罹っている場合に)心臓発作を起こしても生き延びる可能性と関係している。それも意外ではないかもしれない。酸素を利用しにくくする要因は、呼吸だけでなく、クレブス回路を通るフラックスにも影響を及ぼす。呼吸は生死に直結する問題だが、身体を構成する分子の入れ替わり、すなわち代謝回転〔全体としての量は変わらないが代謝によって更新されている状態のこと〕も生死に直結しているのである。このようにさまざまなケースが混じり合うなかで、クレブス回路における陰と陽のバランスをどうやってとっているのか──エネルギー生成の需要を新たな有機分子の合成でどう埋め合わせているのか──が問題となる。この問題によってクレブス回路はいまやとくに注目を集めているが、そもそもなぜ回路に陰と陽が併存しているのかは説明できていない。
私が思うに、クレブス回路が細胞内のエネルギーと物質の両方の流れにおいてこれほど核心的な役割を果たしている理由がわからなければ、がんやアルツハイマー病でどこに問題が起きているのかを理解することは望めないだろう。この回路のフラックスを支配するルールは何なのか? 遺伝子は全体像の一部でしかない。車の流れのたとえを脇に置き、川の水の流れを考えてみよう。川の堤防が水を導くように、遺伝子が代謝フラックスを導いているのだとしても、山から海へ水が落ちるのを堤防が決定してはいないのと同じように、遺伝子は流れそのものを決定しているわけではない。川の流れを決定しているのは、水の性質と、太陽のパワーと、地形──海からの蒸発、山々の高い場所での降雨、地表の岩石の軟らかさ、水分子をまとまって流れる液体にする分子間のゆるい電気的結合、そうした水に絶えず働く重力──だ。街なかで川の流れを高い堤防のあいだに導くことはできるが、どんなに巧みな工事をしても、ひどい洪水に対してはほとんど役に立たない。代謝フラックスでも同じことが言える。遺伝子が触媒となるタンパク質をコードしていても、触媒は魔法ではない。自然に起こる反応をただ加速するだけだ。生じるのは化学反応の生成物なので、どのみち触媒がなくてもできる。ただ、触媒がなければ反応の速度はずっと遅くなるが。代謝の原動力となるのは熱力学である。熱力学というのは大仰な言葉だが、ここでは、水が低いほうへ流れたがるのと同じような、反応する(その結果エネルギーを散逸する)という化学的な要請を意味しているにすぎない。
クレブス回路が熱力学によって定められているとしたら、遺伝子がなくても、何かうまいこと適した環境があればそれは自然に生じるはずだ。その考えは、かつては「ブタが空を飛べたら」と言うような化学的にありえない想像だと否定されていた。だが、新たな画期的研究から、少なくともこの回路の一部は、遺伝子のコードでできるタンパク質が触媒となるのではなく、岩石や金属が触媒となって実際に生じうることが明らかになっている。こうした新発見によって、クレブスが数十年前に初めて明らかにした実際の化学反応への関心がよみがえったが、その反応は彼がほとんど思いつきもしなかった原始の条件によるものであり、しかも彼が明らかにしたのとは逆向きの反応だったのである。いまや、代謝の根本的な理屈が明確になりはじめている。代謝をなす反応の多くは熱力学的に起こるべくして起こっており、一部は触媒によって促進されている。また、遺伝子によって洗練されているものもある。さらに、生命そのものの変遷にもとづく部分もあり、そうした変遷が進化をおよそありそうもない道へたどらせながら、地質学的にせわしなく変動する地球を、命なき無酸素の惑星から今日の命ある活気に満ちた世界に変容させた。
これが、われわれの細胞の内側からわれわれの惑星の歴史をたどる物語だ。この物語では、どうしてわれわれは今のような姿になったのか、また結局のところなぜわれわれは、ひとりひとりまったく違う形で老いて死ぬのかが語られる。私にも、生化学が多くの人にとって難解で縁遠く思われる科目で、聖職者が真意を隠そうとして使うような神秘的な記号だらけに見えることはよくわかっている。だが、それはまったくもって事実からほど遠い。生命を生かしている化学的メカニズムほど重要なものがあるだろうか? あるいは、われわれに死をもたらす化学的メカニズムや、われわれの意識ある自我を生み出す化学的メカニズムはどうだろう? しかも、なんとこのすべてが同じ化学的メカニズムなのだ! 私はこれからこの生の化学的メカニズムを平易な言葉で活写してみることにするが、重要な細部をごまかしはしない──われわれは、人間の知識のフロンティアへ旅しようとしているのだ。旅の航海が必ずしも楽でないことは認めるが、あなたがその苦労に値する褒美を見つけられるように願っている。この航海は、私自身が生化学者として、クレブス回路の根本的な意味──なぜ今日なお生と死の核心で活動しているのか──を見出そうとするものだ。どうぞお付き合いいただきたい。
――続きは書籍をごらんください――
(著作権者のご同意を得て抜粋・転載しています。
なお読みやすいよう行のあきなどを加えています)