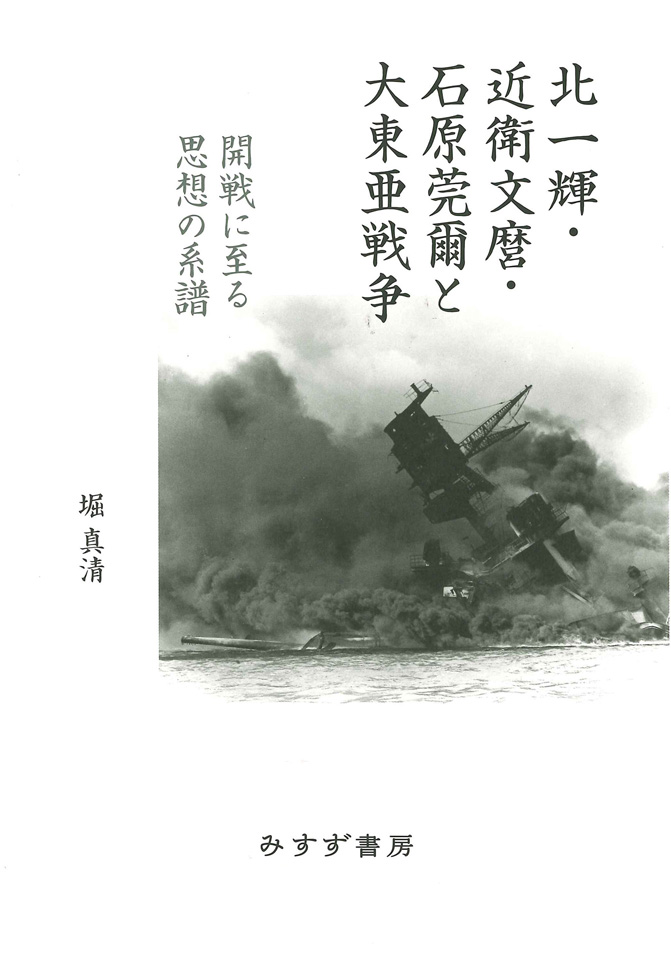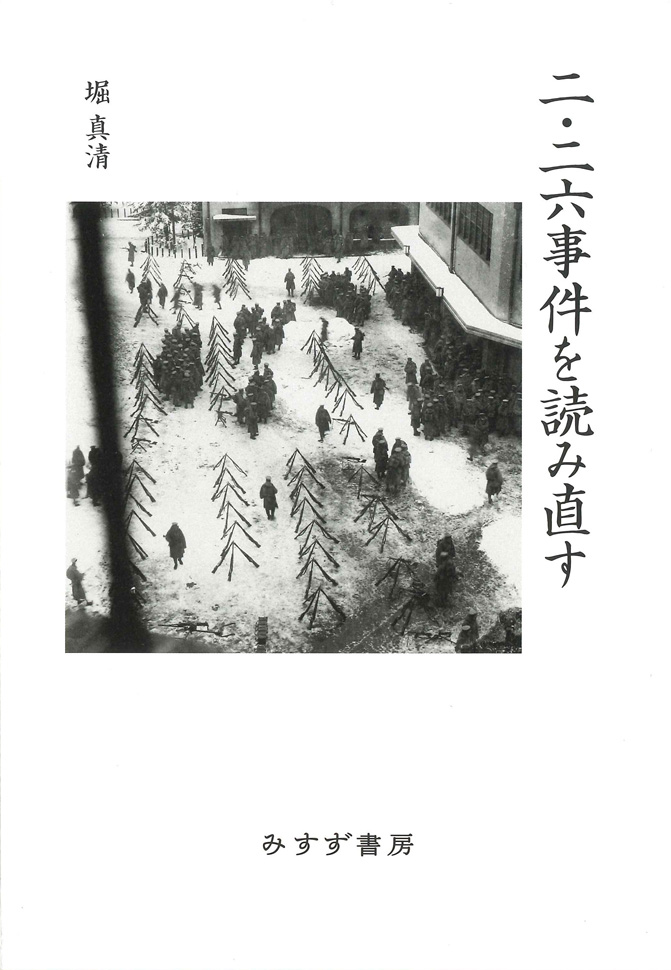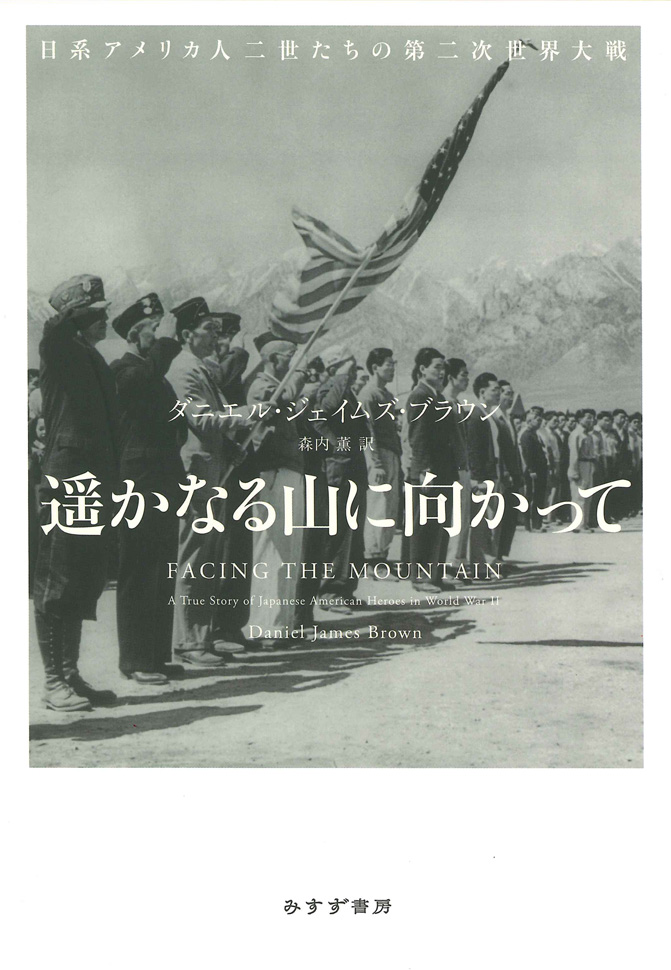北一輝、近衛文麿、石原莞爾の3名を、本書は国家生存権の思想を体現する重要人物として位置づけている。国家生存権の思想とは、文字どおり国家が生存する権利で、そのために必要であれば戦争も正当だとする。
しかし著者の結論は明快で、この自国本位の思想が日本を誤った戦争に導いたと断じている。
では具体的に、かれらはなにをどう主張したのだろう。それを伝えるために、本書は当人の著作などにくわえ、公文書その他の史資料から多くを引用しているが、著者による要約を適宜はさむことで、広範な記録をできるだけ読みやすく提示している。
一例として下記を挙げたい。石原莞爾が1938年5月10日に満州国留日学生会館でおこなった講演概要の筆記で、ときに石原は49歳、関東軍参謀副長、陸軍少将。「 」内は筆記そのものの引用、それ以外は著者による要約、[ ]内は著者による補足。これを含む節に、著者は「石原莞爾の甘え」という小見出しを与えた。
「[…]今から三十五六年前、日露戦争の前であるが、私はその頃仙台幼年学校に居た。私は当時から支那問題の研究者であつた」。──日本は明治維新によって立派になったが、「支那はだめだ。何卒支那が革命を成就し、日本と同様に発達し、手を携へて行き度いと希つた。近衛公の先代霞山公[篤麿]や頭山満なども皆志を同じくする、いはば同志であつた」。
多田[駿]さんも板垣[征四郎]さんもみな同志であり、孫文以下も日本では兄弟のごとく待遇された。日清戦争で敗れた中国も日本に悪意は抱かず、留学生がぞくぞくと来日する。日露戦争では辛うじて勝った。これは東亜諸民族を覚醒させた点で世界史的大事件である。
ふたつの戦争をへて日本資本主義経済は飛躍的に発達したが、そのための市場が必要となった。そのためいやでも応でも「支那を市場として獲得搾取しなければならぬ事になつた」。日本の政策は西洋と伍して発展しなければならず、西洋人のいうほど悪いものではないが、たしかによいものではなかった。
「欧州大戦当時の例の二十一ヶ条の如き、悪いには悪いとは云へ、西洋諸国の間に立つて唯一の独立国として立つて行かうとする日本としては、支那に利権を求めざるを得なかつた。支那としても英米をやつつけることが出来ず成り上り者の日本を苛めた。日本としてはどうしようもなかつたのである。このゆき方は私は日本人の見地を離れても已むを得なかつたと思ふ。この点支那の人も同情的に見て呉れてよいのである」。しかし、暴力は暴力であり、[第一次世界]大戦がおわり、[ヴェルサイユ]平和条約締結のときになると中国は得意の外交手段をもって欧米とむすび、日本をこっぴどくやっつけた。これも無理はない。こうして「兄弟喧嘩」となり、ついに日本を満州から「閉出さうとして、昭和六年の満州事変を惹起すに至つた。此事変と云ふものは、実に已むを得ざる必然的結果である」。
満州はもともと蒙、満、鮮人の土地であって最近まで「支那の土地ではなかつた。支那の植民地であつたが、現実的には支那と異つている」。満州事変を契機として満州が独立したことは「来るべきものが来る処まで来たものであると私は思ふ[そうあるべきものがそうなったという意味か]。私は自ら先覚者を以て任ずるのも気恥しい事であるが、[あなたがた満州国から陸軍士官学校に来ている留学生]同志も満州をそう云ふ処として認識して欲しい。だから満州事変後の我々としては土下座をして支那にあやまれと云つた。三十年この方日本が支那に侵略した事をあやまれ、[…]今や幸にして我々は西洋を恐れる必要がなくなつた。我々は支那本土に於ける政治的権益は全部返却する。白人種が云ふことをきかなかつたら武力でとり上げても真の中国の独立を完成しよう。日本の三十年来の暴力行使をあやまるがいい。と私は主張した」。
だが、日本人全部がこの考えに転換することは不可能である。侵略主義的な気もちは清算されていない。「そして悲しむべき[支那事変という]今日の大事件となつた。そう云ふ気持が今回の事変の発生にも手伝つているが、[…]しかし満州事変の時とは日本人の気持は非常に変化している。御詔勅にもある通り、今次事変は中国人の反省を促し、東亜の平和を求めるためのものであり、又、吾等尊敬する本庄大将も亦日本の中国に望むものは権益擁護に非ず領土的野心に非ず、両国の提携であると言はれてゐる。しかし戦をやつて見ると仲々さうは行かない。だが西洋人の考へている様な利権獲得の問題ではない」。