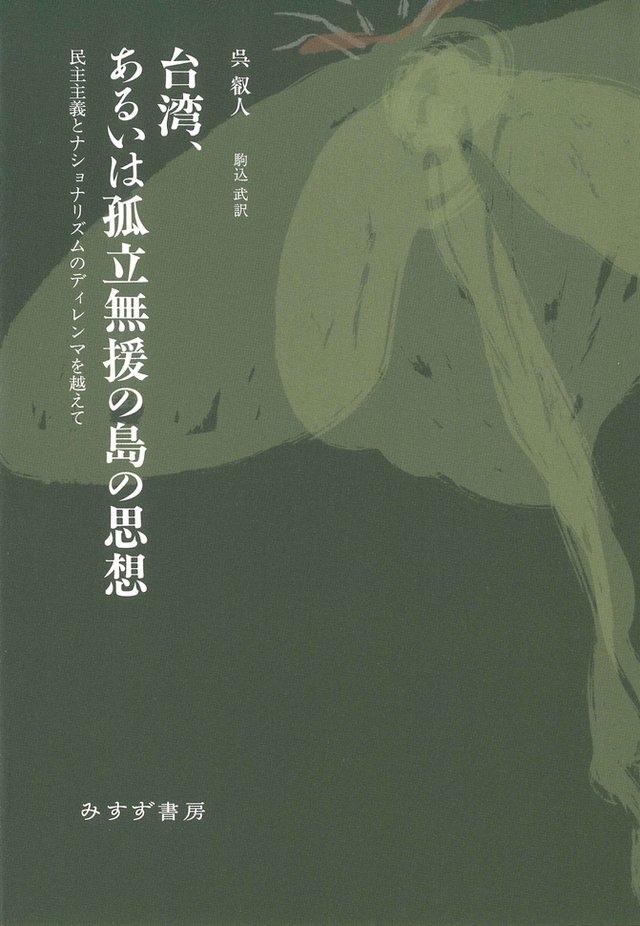
台湾から日本へ、投げかけられた課題(「訳者あとがき」抄録)
呉叡人『台湾、あるいは孤立無援の島の思想――民主主義とナショナリズムのディレンマを越えて』駒込武訳
2021年1月26日
本書を編むまで
駒込武
2021年12月、安倍晋三元首相は「台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事でもある」と語りました(『朝日新聞』2021年12月1日付)。この言葉が象徴するように、日本社会では一部の与党政治家が「台湾有事」の可能性をことさらに煽りながら、沖縄など南西諸島の人びとを犠牲に供する施策を強引に推し進めてきました。実際、与那国、石垣、宮古、沖縄、奄美などの島々では、「台湾有事」が生じた場合に日米で連携して武力行使する想定のもと、自然や生活環境を強引に切り裂きながら島々を軍事要塞化してきました。石垣島の自衛隊基地に配備されたミサイルは当初射程200キロ程度の専守防衛のためのものと説明されていましたが、2024年になって中国本土を直接攻撃できる射程1000キロ超のミサイル配備準備が住民合意のないままに進められています。
リベラル・左翼勢力のあいだでは、このような社会的合意なき戦争準備への批判が高まるとともに、その大前提である「台湾有事」、すなわち中国による台湾侵攻の可能性への懐疑論が唱えられてきました。さらに、中国の軍事的脅威自体が虚構だとする論もあります。ですが実際、2022年8月、23年4月、24年5月に中国人民解放軍は台湾を八方から海上封鎖する軍事演習を挙行し、台湾が「籠のなかの鳥」であることを示しました。軍事的緊張関係のなかで、たとえ中国政府首脳にその意図がないとしても、偶発的な衝突をきっかけとして戦火が一挙に拡大する可能性も否定しきれません。それは日本という国家がかつて日中全面戦争において実際にたどった道でもあります。
「台湾有事」に備えて抑止力を高めるべきだと語る日本政府首脳の議論と、これを虚構として批判するリベラル・左翼勢力の論は対照的です。ただし、両者に共通している側面もあります。台湾の人びと自身がこの現状をどのように認識し、どのように打開しようとしているかという問題がすっぽりと抜け落ちてしまっていることです。台湾近現代史研究者としてふだんから台湾社会と接している自分には、その欠落がとても大きなものに感じられました。台湾は中国の一部であり、中国の内政問題なのだから台湾人の意向など考える必要などない、と語る人もいます。それでは、沖縄は日本の一部だからという理由で、沖縄人の意向にかかわりなく島々の軍事要塞化を進めてもよいのでしょうか? 立場を変えて考えてみる必要があります。「台湾有事」と呼ばれる状況をめぐって、台湾の人びと/沖縄の人びとが対外的・対内的にどのような問題に直面し、どのような経験をしているのかと考えたとき、日本の「本土」に暮らす者は、わたし自身を含めて実は知らないこと、分からないことばかりです。
「台湾有事」は絶対に起こしてはならない。同時に、それにとどまらず、「台湾有事」論の地平を越えて、台湾や沖縄の歴史と現在から発する問いかけに耳を傾けなければならない。そうした課題意識を共有する人びとと一緒に、2023年7月8日に京都大学でシンポジウム「台湾と沖縄 黒潮により連結される島々の自己決定権」を開催しました。
本書は、このときの記録を中心としながら、各登壇者がシンポジウムのために準備した資料を改稿した文章と、その後に重ねた対話の記録から構成されています。
このシンポジウムのテーマ設定が冒険的なものであることは、主催者として自覚していました。中国に対抗するために日本やアメリカの援助を期待せざるを得ない台湾と、中国から台湾を防衛するという名目のもと、日本やアメリカによって軍事化される沖縄諸島の人びとは一見、対立しているように見受けられるからです。しかし本当にそうだろうか、ということが、このシンポジウムで考えてみたいことでもありました。重要な手がかりとなったのは、2022年1月に石井信久さん、植松青児さん、加藤直樹さんが連名で発した声明文「日本の戦争に「帝国の狭間」の民衆を巻き込むな」です。そこには、日本・アメリカvs中国という「強者の秩序」を批判する立場から、次のように記されています。
3つの大国〔日本・アメリカ・中国〕が実際に戦火を交える可能性は低いかもしれない。だが重く垂れこめる軍事緊張それ自体が、その地に生きる人びとの平和に生きる権利と自己決定権を奪い、地域社会の軍事化を助長することになる。東京、ワシントン、北京のための戦争が、「帝国」の中心から遠く離れた小さな島々の人びとを脅かしている(1)。
台湾や沖縄の島々に生きる人びとは、くりかえし植民地主義的な支配を経験してきた点でも、今日にいたるまで集団的な自己決定権を否定されてきた点でも、共通した命運をたどってきました。このように考えれば、本当の対立は、「帝国」の中心(ワシントン、東京、北京)にある人びとと、中心から遠く離れた島々の人びとのあいだにこそあるのではないでしょうか。
台湾の政治学者である呉叡人さん(台湾・中央研究院台湾史研究所副研究員)は「黒潮論」という文章のなかで、台湾島、沖縄諸島、日本列島東岸を環流する黒潮の流れこそが生命を育み、歴史を切り拓き、島々を外部世界へとつないできたと論じました。そのうえで、台湾と沖縄の歴史的共通性(これを呉さんは「帝国の狭間」にある「賤民」の境遇とも表現しています)に着目しながら、台湾の独立・自立を目指す者は琉球人民の自己決定と米軍基地撤廃を支持し、「永世中立」を究極の目標とすべきだと論じてきました(2)。自らの目的を果たすために、同じく弱い立場にある沖縄の人びとを見捨てるのではなく、連帯しようとするその姿勢は、『新沖縄文学』編集責任者であった川満信一さんがかつて、フィリピンから台湾を経て韓国済州島にいたる「黒潮ロード」を非武装地帯とする構想を提唱したこととも通底するように思われます(3)。
日本「本土」中心の「一国平和主義」を越えた、本当の意味での東アジアの「平和」はそうした構想のうちに潜在しているのではないか。衰退しつつある「帝国」アメリカ、およびその「属国」ともいうべき日本と、新興の「帝国」中国との覇権争いがあたかも海を切り裂くかのように深まっているいまだからこそ、黒潮の流れが島々を連結してきた歴史を思い起こす必要があるのではないか。ロシアによるウクライナ侵攻は、こうした議論のできる空間を狭めてしまったように思えます。しかし、まずは「平和」を準備する開放的なビジョンを共有したい、そのうえで少しでもそこに近づける道を考えたいと思い、このシンポジウムを企画するにいたりました。
シンポジウムの企画にあたって留意したのは、当事者性を複数の次元に腑分けして考えることです。
台湾の人びとが当事者であるのはもちろん、沖縄や八重山、奄美など、中国との戦争に備えて生活の場が軍事化されている南西諸島の人びとも当事者です。まず当事者の方々がどのように感じているのかに耳を傾ける必要がある。そうした思いから、シンポジウムのパネリストとして上述の呉叡人さんを台湾からお招きし、さらには石垣島の自衛隊基地建設の是非を問う住民投票訴訟に取り組んでいる宮良麻奈美さん、京都大学に学ぶ台湾人留学生の張彩薇さんにご参加いただきました。
他方で、台湾や沖縄の人びとの当事者性とは意味合いが異なるけれども、京都や東京を含む日本「本土」の人間もまた当事者であるといえます。日本「本土」の人間こそが、このようなジレンマに充ちた現実をつくりだしていると考えられるからです。そのことを自覚したうえで、われわれはどのように目下の状況について言葉を紡ぐことができるのか。このような問題意識から、シンポジウムでは、声明「日本の戦争に「帝国の狭間」の民衆を巻き込むな」の起草に参加された加藤直樹さんにもご登壇いただき、わたし自身も進行役として議論に参加しました。
本書の第I部「帝国の狭間から考える」には、対話の大前提として台湾と沖縄の歴史についてわたしたが執筆した文章のほか、シンポジウムの資料として4名のパネリストにお寄せいただいた文章を改稿のうえ収録しています。呉叡人さんの「帝国の狭間の中の台湾民主」は総統選前の2023年3月に台湾でおこなわれた講演をもとにしたものであり、これに対するコメントとして張彩薇さんに書いていただいたのが「悲劇の循環を乗り越えるために」の一文です。宮良麻奈美さんには、住民投票訴訟を提起するにいたった背景から現在までの経緯を、石垣島で生活する宮良さんの視点に即して記していただき、加藤直樹さんには、前述の声明を出すにいたるまでの思考の軌跡を、1980年代末の加藤さんご自身と台湾との出会いにまで遡って書いていただきました。さらには「沖縄対話プロジェクト(4)」の呼びかけ人のお一人でもある上里賢一さん(琉球大名誉教授)に近世東アジア世界の国際秩序についてのご寄稿をお願いし、第Ⅰ部の結びとして収録しています。
本文をお読みいただければ分かるように、第Ⅰ部に収めた6編の文章は、論文調のものからエッセイ的な文章まで文体に差があるばかりでなく、内容のうえでも微妙な力点の相違があります。そのことは、この台湾と沖縄をめぐる対話について、出来合いの「落とし所」がどこにも存在しないことを示唆しています。しかし同時に、これらの文章がそれぞれの立場から「帝国の狭間からの問い」を表現しようとしている点において強く通底していることも、読者のみなさんにしっかりと感じ取っていただけるのではないかと思います。その問いかけの宛先は、本書を手にされたすべての方々です。
続く第II部は「対話の試み」と題して、シンポジウムの記録を収録し、さらにその後の対話を往復書簡と鼎談の形式で収録しています。シンポジウムでは4名のパネリストの方々に加え、「沖縄対話プロジェクト」共同代表の前泊博盛さん、ナチズムの歴史を研究されている藤原辰史さん、編集者で加藤直樹さんとともに声明を出された植松青児さん、京都大学台湾留学生会の王薫鋌さんにもご発言いただいたほか、ハンナ・アーレントの政治思想を研究している森川輝一さん、パレスチナ問題に取り組まれている岡真理さんに実行委員としてご挨拶をいただきました。
往復書簡は、宮良麻奈美さん、張彩薇さんに引き続きご参加いただいたほか、シンポジウムに聴衆として参加して長文の感想を寄せてくれた京都大学大学院生の齊藤ゆずかさんに加わっていただきました。巻末の鼎談は、わたしと呉叡人さんに加えて、辺野古基地建設問題などで住民投票制度の可能性を追求してきた元山仁士郎さんにご参加いただき、東京都内でおこなわれました。
第II部のシンポジウム、往復書簡、鼎談においても、語り手のあいだには微妙な見解の相違が存在しており、そうした不一致はかならずしも解消されるにはいたっていません。ですが、それはこの冒険的対話においては当然起こりうる事態であり、違和を覚える主張に接した際に対話の場から下りてしまうのではなく、不協和音に戸惑いながらも対話を続ける姿勢こそ、わたしが本書を編むにあたって大切にしたいと考えたことでした。編者としては、対話に臨むための知的・精神的土台を準備するという意味において、その目標は十分に達成することができたと感じています。
当事者である人びとの声を聞き、自らの当事者性を自覚したうえで、「台湾有事」論の地平を越えて、帝国の狭間にある人びとの自己決定権・生存権からこの状況を捉えなおすこと。その先にこそ対話があると考えて始まったこの試みは、しかし実験的なものです。台湾・沖縄の人びとにとっての危機は非常に切迫したものであり、その地政学的な立場の違いを超えることは容易ではありません。また、日本「本土」の人間が、台湾や沖縄の人びととの対話のテーブルにつくことも、言葉で説明するほどには簡単ではありません。なぜならわたしたちの社会的/個人的意識の裏側には、「帝国の狭間」の人びとの犠牲を当然視するような思考が拭いがたく張り付いており、それを自覚することすら今日の日本社会においては困難になっているからです。
このように困難な試みであることを知ってもなお、この対話は必要であると考えます。政治的に、あるいは軍事的に隔てられている人びとが実際に出会い、語り合う経験のなかに、すでに新しい世界の胚珠が宿っています。本書を通じてそうした確信が日本から、世界へと伝わることを願っています。
copyright © KOMAGOME Takeshi
(著作権者のご同意を得て転載しています。なお
読みやすいよう行のあきなどを加えています)
(1) 「《寄稿》声明 日本の戦争に「帝国の狭間」の民衆を巻き込むな」、「島々スタンディング」ウェブサイト、2022年1月1日のブログを参照(https://simazima.jimdofree.com/2022/01/01/寄稿-声明-日本の戦争に-帝国の狭間-の民衆を巻き込むな/)。この声明文は日本語、韓国語、中国語の各言語で発表された。亀甲括弧内の補足は引用者による。
(2) 呉叡人『台湾、あるいは孤立無援の島の思想――民主主義とナショナリズムのディレンマを越えて』駒込武訳、みすず書房、2021年、273頁、413頁。
(3) 森宣雄・冨山一郎・戸邉秀明編『あま世へ――沖縄戦後史の自立にむけて』法政大学出版局、2017年、35頁。川満信一『沖縄発――復帰運動から40年』世界書院、2010年、214頁。
(4) 「沖縄対話プロジェクト」とは、「台湾有事」「南西諸島有事」を決して起こさせてはならないと考える沖縄の市民が、政治的な立場や意見・思想の違いを超えて対話していこうとする企画である(ウェブサイトの説明を参照 https://okinawataiwa.net/)。