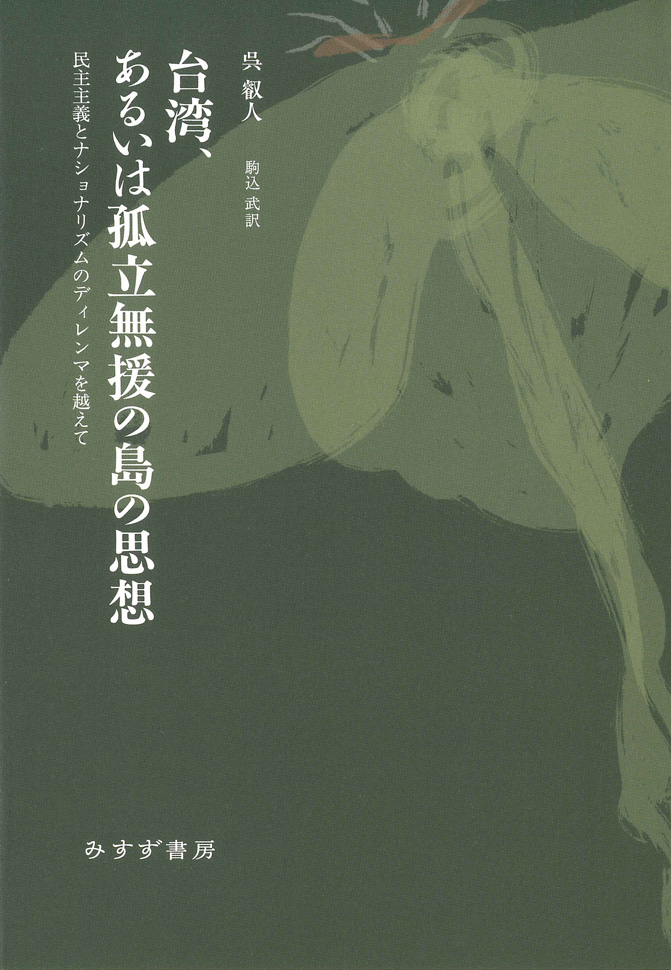梅森直之
(早稲田大学政治経済学院教授)
目次
- 歴史という戦場
- 比較帝国研究における〈東洋的植民地主義〉
- 台湾という教養小説
- 東アジアの未来に向けて
歴史という戦場
本書は、台湾ナショナリズムの生成と展開に関する比較思想史的研究である。「ネーションは分析のカテゴリーではなく、実践のカテゴリーである」。著者は、本書150頁において、ナショナリズム研究に向かうみずからの姿勢を、このように表明している。これは、本書が、台湾ナショナリズムの歴史的分析であることを越えて、台湾というネーションを生成し展開する著者自身の実践でもあることの表明である。このメッセージに応答するために、読者もまた二つの視角を持って、本書に向き合うことが要請される。一つは、本書で示された台湾ナショナリズムの歴史的起源に関する著者の分析の妥当性を吟味する経験主義的歴史学の視座である。いま一つは、台湾というネーションに仮託して提示された著者の政治理念の可能性を問う規範的政治思想研究の視座である。本書の顕著な特色は、この二つの視座が、きわめて自覚的かつ緊密に結びあわせられるかたちで叙述が織りなされていく点に求めることができる。
著者の呉叡人氏は、2023年8月現在、台湾を代表する学術研究機関である中央研究院の台湾史研究所に所属する政治学者である。1962年に台北近郊の桃園で生まれ、国立台湾大学在学中の1980年代に学生運動に深くコミットしたのち、アメリカ・シカゴ大学政治学部に留学し、主として政治思想と比較政治を専門として研究を進めた。2003年に同大学から、博士論文The Formosan Ideology: Oriental Colonialism and the Rise of Taiwanese Nationalism, 1895‒1945により、博士号を授与された。本書は、この英文で記された博士論文の全訳に、その後当該の主題について発表された二つの英文のペーパーを補論として収録したものである。著者は、政治思想と比較政治の研究者として知られる一方、台湾における種々の社会運動ならびに香港における民主化運動にも深くコミットし、行動する知識人としても世界的な注目を集めている。また、『想像の共同体』の著者である故ベネディクト・アンダーソンとも親交が深く、同書の台湾版(のちに一部削除のうえ、中国でも出版)の翻訳をおこなっている。
著者は、近年日本においても、『台湾、あるいは孤立無援の島の思想――民主主義とナショナリズムのディレンマを越えて』(駒込武訳、みすず書房、2021年、原著2016年)の出版を契機として、大きな注目を集めるにいたっている。台湾という「故郷」の苛酷な運命を見定め、そこに新たな解放の可能性を開こうとする著者の視線は、「美しき島」の領域をはるかに超えて、日本、沖縄、香港をも射程におさめ、帝国主義から冷戦、ポストコロニアリズムへといたる世界的な構造変動のなかで変容するナショナリズムの運命を見定めようとしている。領域を横断し、哲学や文学も自らのフィールドとしながら、現実政治へと切り込んでいく著者の姿勢は、まさに現代の有機的知識人と呼ばれるにふさわしい。博士論文として執筆された本書には、多分野で有機的に活動を展開する著者の現在の思考の原点が、いわばむき出しのかたちで表現されている。本書は、この意味において、思想家・呉叡人の誕生を画する作品でもある。ネーションが「実践のカテゴリー」である以上、著者の学術的活動をたどることは、そのまま台湾というネーションの可能性と苦境を理解することへとつながっている。そしてそれは、読者であるわれわれ自身が、みずからのネーションと向き合い、その可能性と苦境をともに引き受ける道へとつながっているはずである。執筆からすでに20年が経過した本研究を現在日本語で世に問う意味も、この点に求められる。
著者が所属する中央研究院には、台湾史研究所のほかに、近代史研究所という歴史を対象とするもう一つの研究センターが存在する。歴史をめぐるこうした研究機構の二重構造が、台湾というネーションの可能性と苦境のあらわれとなっている。中央研究院は、1928年に中華民国の最高学術研究機関として設立された。それが国共内戦を経て、台湾へ拠点を移した国民党政権により台北において復興されたのは、1954年のことであった。中央研究院における「近代史」の研究は、その復興直後の1955年から開始されている。一方の「台湾史」研究所の正式な設立は、2004年のことである。歴史をめぐるこのような制度的二重構造とその時間的なズレは、戦後台湾において「歴史」とは「中華民国の歴史」を意味していたということ、そして台湾史というジャンルは、比較的最近になって公式の承認を受けるようになったものであることをあらわしている。日本に暮らす一般の日本人は、日本の歴史をきわめて自然なもの、自明なものとして受けとっている。しかし台湾に暮らす多くの人々にとって、台湾の歴史はけっして自然なものでも自明なものでもありえなかった。それは、中華民国の歴史を「公式の歴史」として教え込んでいた国民党政権に対する民主化運動を通じて闘い取られたものであり、そして現在においては、民族的な共通性を論拠として統一への圧力を強めつつある中華人民共和国に対して、防衛されなければならない戦場となっている。こうした文脈において、台湾史の研究は、台湾というネーションを立ち上げ、防衛し、それを発展させるための実践をも意味する。本書は、その最前線に立ち続けてきた著者の、闘いの始まりを画する作品である。
比較帝国研究における〈東洋的植民地主義〉
本書は、英文で書かれた博士論文としての性格上、第一義的には、英語圏の研究者に向けて台湾ナショナリズムという研究主題の意義と可能性を示すことに重点が置かれている。その際著者が採用した戦略が、帝国主義/植民地主義研究の理論的枠組みの再検討である。著者は、台湾ナショナリズムがそのもとで勃興した日本の植民地支配を、歴史上登場したさまざまな帝国主義/植民地主義と比較し、それが〈東洋的植民地主義〉という一つの独立した類型としてみなされるべきことを主張する。著者は、これまで英語圏でなされてきた帝国主義研究の問題点を、日本帝国主義に関する分析の欠落もしくは軽視という点に求めている。歴史的に登場した帝国主義を相互に比較し、その特質を明らかにすることで近代世界の動態を探ろうとする研究は、これまでもなされてきた。しかしその際考察の中心とされてきたのは、もっぱら西洋列強による植民地支配であり、日本による周辺アジア諸地域の植民地化は、独立の事例としては無視されるか、または西洋植民地主義からの逸脱として軽視されるかのどちらかであった。
著者は、こうした比較植民地研究における日本の欠落という問題に、以下の二つの手続きをもって挑戦する。まず著者は、従来の植民地研究が、本国から地理的にも文化的にも民族的にも大きく離れた海外の植民地支配、すなわち海外帝国をその典型例とみなしてきたことを指摘する。著者は、そうした海外帝国に加え、地理的にも文化的にも民族的にも近接した周辺諸地域の包摂を推進した隣接帝国の存在を指摘し、それもまた等しく比較植民地研究の類型として位置づけられるべきことを主張する。こうした隣接帝国は、歴史的には、東ヨーロッパや中央ヨーロッパにおいて多くその事例を見いだすことができるが、日本帝国主義もまたこうした隣接帝国の一例とみなされるべきであるというのが著者の主張である。こうして帝国日本は、東欧や中欧の隣接大陸帝国に対し、東アジアの隣接海外帝国として、独立した考察に値する事例としての資格を獲得する。そこでは帝国日本の隣接帝国としての特殊性を分節化することが、〈東洋的植民地主義〉の内実を明らかにする重要な手続きとなる。
日本の〈東洋的植民地主義〉は、他の隣接帝国の場合と同様に、植民地化した地域/人々を本国に統合/同化することを目的とする統治であった。そして植民地化された地域/人々は、他の隣接帝国の場合と同様に、統合/同化の圧力のもと、けっして終わることのない国民化のプロセスのうちに置かれることになった。これが著者のいう〈閾〉の状態である。しかし東アジアの隣接海外帝国としての日本の植民地支配には、ヨーロッパの隣接大陸帝国にはみられない特質が存在した。それは日本におけるナショナリズムの〈派生的〉性格に由来するものである。西洋列強による植民地化への危機意識に端を発した日本のナショナリズムは、多くの非西洋圏における反植民地ナショナリズムとも共通する〈派生的〉性格がみられると著者は主張する。ここでいう〈派生的〉性格とは、みずからのナショナル・アイデンティティを確立するにあたり西洋との差異化を第一義的に想定する態度を意味している。すなわち、〈派生的〉言説において、日本的であることは、西洋的であることの否定もしくはそれとの差別化のうちに求められることになる。こうした日本ナショナリズムの〈派生的〉性格は、本国への統合/同化を進める日本帝国主義の植民地支配にも転写された。〈東洋的植民地主義〉は、いわば西洋の海外植民地支配の〈派生的〉言説である。それは西洋的植民地主義の否定もしくはそれからの差別化を意識する植民地主義である。それは具体的には、差別/差異を強調/前提化する西洋の植民地支配に対し、同化/同質性を強調/前提化する植民地支配であり、それを実践する本国が、みずからのナショナル・アイデンティティを、西洋的であることの否定もしくはそれとの差別化に求めているような植民地主義である。このような性質は、日本の植民地主義が西洋を中心とする世界の周縁で発生したという〈東洋的〉性格に由来するものである。
周縁で発生した〈東洋的植民地主義〉は、新たに獲得した領土・台湾に対し、同化/同質性を強調/前提化する非西洋的な植民地支配を実践した。しかしそのことは、けっして台湾が、日本本国に対等/平等な存在として受け入れられたことを意味しない。なぜならその際日本は、封建主義に基礎を置く新伝統主義的な家族国家という階層秩序を、国民統合の基本原理として持ち出したからである。台湾は、北海道や沖縄といった日本本国の周辺地域や朝鮮や樺太などの他の植民地と同様に、周縁の帝国である日本のさらに周縁に位置づけられることになった。これが、台湾が、他の周辺地域や植民地と同様に引き受けなければならなかった〈二重の周縁性〉という歴史的運命である。周縁帝国としての日本は、〈二重の周縁性〉に置かれた周辺地域/植民地の人々に対し、〈差別的包摂〉という方法によってその統合/同化を進めた。それは、新たに獲得された領土を、文明化の度合い、すなわち「民度」の低い存在として国民統合の底辺に位置づけ、完全なる統合の条件として、「よき日本人」となることをその住人たちに義務づけるものであった。著者は、そうした階層的支配構造を、日本政府が近代以前の社会から受け継いだ封建思想に由来する「新伝統主義」であるとみなしている。そこで期待された「よき日本人」になることとは、単に近代化/文明化された人間になることにとどまらず、階層的秩序をその構成要素とする日本の「伝統」文化、すなわち「家族国家論」を受け入れ、西洋的であることの否定もしくはそれとの差別化を根幹とする日本の創られた伝統へとみずからを同化させていくことを意味した。
本書の第1章と第2章は、比較帝国研究の理論的枠組みのなかに、〈東洋的植民地主義〉によって特徴づけられる日本の帝国主義を、独立した一類型として位置づける正当性と必要性の弁証に向けられている。第3章と第4章で本格的に展開される台湾ナショナリズムの考察の正当性と必要性も、この〈東洋的植民地主義〉との連関から引きだされるものである。日本の帝国主義が、これまで植民地主義の典型とみなされてきた西洋列強による植民地支配とはその内実を異にする〈東洋的〉特質を有するものであったとすれば、それへの抵抗として発生した台湾ナショナリズムもまた、これまで反植民地ナショナリズムの典型とみなされてきた西洋列強による植民地支配への抵抗とは異なる、独立した反植民地ナショナリズムの類型として分析される必要が生ずる。比較帝国研究の一類型としての日本帝国主義から、比較ナショナリズム研究の一類型としての台湾ナショナリズムへ。著者はこうした手続きをもって、帝国主義やナショナリズムに関心を有するすべての研究者を、台湾ナショナリズムという未知の研究領域へ誘ってゆく。
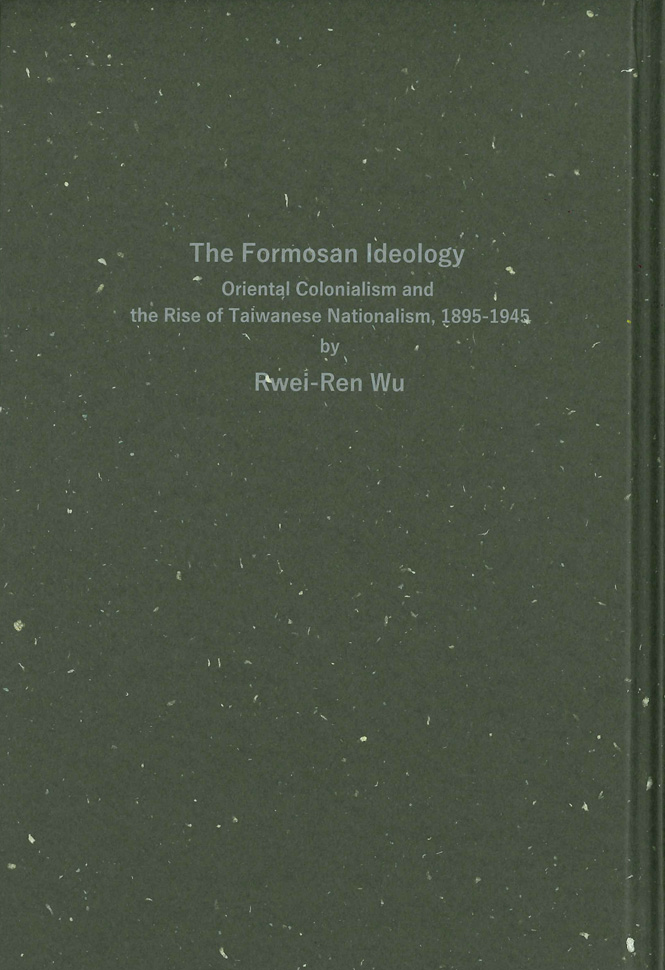
(本書表紙)
台湾という教養小説
本書冒頭の「謝辞」は、トーマス・マンの『魔の山』の引用からはじめられている。この小説の主人公ハンス・カストルプは、23歳という若さで、アルプスの山中のサナトリウムで結核の療養生活を余儀なくされていた。現世から隔離された環境において不治の病という宿命を背負った青年の精神の彷徨を描いたこの小説は、代表的な教養小説として世界的に知られている。主人公の、隔離されてはいるが、教養と個性に満ちあふれた友人たちとの対話やさまざまな民族の人々との交流によって彩られ、豊かでもあった精神生活は、第一次世界大戦の勃発によって破られた。7年間の「眠り」から呼び覚まされた主人公は、「魔の山」を出て母国ドイツのために従軍する決意をし、泥土の戦場へと消えてゆく。ここで著者が、シカゴ大学におけるみずからの学究生活を、ハンスのサナトリウムでの精神的彷徨になぞらえていることは明らかであろう。この一文は、著者が、豊かでありかつ心地よくもあったアカデミックな教養生活に別れを告げ、有機的知識人としてナショナリズムという戦場へ「従軍」することを決意した時点での心象風景を、浮き彫りにするものとなっている。
本書は、〈二重の周縁性〉という宿命を自覚した著者が、いかにして普遍性という開かれた場所への出口を見いだしていったかというその精神的彷徨の記録ともなっている。それはまた、著者自身が、シカゴ大学での学究生活を通じて、台湾知識人たちの自由と解放を求める植民地統治下での闘争の痕跡を濃密にたどることによって見いだした出口でもある。パルタ・チャタジーは、反植民地主義ナショナリズムが負わなければならなかった宿命を、〈派生的〉言説と呼び、みずからと西洋を差異化しなければならなかった非西洋圏のナショナリズムにおいてしばしば登場する反近代的・反普遍的な身振りにその問題点を見いだしている。しかし〈二重の周縁性〉に閉じ込められていた台湾の知識人たちにとって、こうした〈派生的〉言説をみずからのナショナリズム戦略として取り込むことは、そもそも不可能であった。なぜなら、それ自体が〈派生的〉言説であった〈東洋的植民地主義〉に抵抗し、みずからのナショナル・アイデンティティを想像するためには、〈東洋的植民地主義〉が否定し、消去しようと試みた西洋・近代・普遍といった諸価値を、みずからのナショナリズムの基盤に置くほかはなかったからである。〈二重の周縁性〉はまた、台湾人が近代/西洋を、普遍的な価値として指向することを促した点で、西洋列強の植民地支配のもとで展開された反植民地ナショナリズムとは異なった解放への道行きを条件づけた。著者が台湾ナショナリズムに読み込んだ可能性は、まさにこの点に胚胎している。
本書第3章と第4章では、台湾の知識人たちがどのように〈弱小民族〉というみずからのナショナル・アイデンティティを想像するにいたったのか、その苦難に満ちた道行きが描かれている。台湾人の〈弱小民族〉という自己理解は、けっして〈東洋的植民地主義〉下の〈二重の周縁性〉という条件から自動的に生み出されたものではない。著者はそれを、台湾人の反植民地活動家同士の論争や台湾人活動家と日本人支配者・知識人との論争・共闘を通じて徐々に形成され、成熟し、そして急進化していくプロセスとして描き出していく。それは〈差別的包摂〉により生み出され、「日本ならざる日本」という永遠の〈閾〉に閉止された台湾という一個の精神が、自分とは誰なのか、そして誰であるべきなのかを問い続け、その「出口」をみつけるまでの彷徨の物語でもある。
著者は第3章において、台湾ナショナリズムが、その誕生の時点から一貫して近代的・普遍的価値を志向するものであったことに注意を促す。それは、台湾における自治主義の出現を画した台湾議会設置請願運動の理念において、またその運動のリーダーであり治警事件の被告となった蔣渭水が法廷で展開した弁論のうちに、確認できるものである。著者は前者を、民族自決というウィルソン的な自由主義と、日本の大正デモクラシーの民主主義的発想を取り込むことによって生み出されたものと特徴づける。また著者は後者を、マルチナショナル/マルチエスニックな国家とシビック・ナショナリズムの理論構築の実践であったと解釈する。この双方に共通しているのは、帝国日本の特殊性への同化を拒絶し、近代的・普遍的価値へ訴えかける精神的態度である。1920年代の後半になると、民族自治をめざして展開されていた台湾知識人の統一戦線は、社会主義者とリベラリストの左右両陣営へと分裂し、階級運動と民族運動の優位性をめぐって激しい論争を繰り広げることになる。たしかに左右両派のあいだには、「労働者と農民が主導する台湾の国民革命」か「台湾人全体の政治的・経済的・社会的解放の実現」かという、めざすべき目的と路線に関する差異が存在していた。しかし著者は、それらの言説が、そのイデオロギー的な、あるいは戦略的な差異にもかかわらず、「台湾人」や「台湾民族」を民族自決の権利を有する「被抑圧民族」ないし「弱小民族」として想像することでは一致していた事実を強調する。
台湾の知識人たちにとって、「台湾民族」はけっして自明のカテゴリーではなく、日本への同化に抵抗することによって闘い取られなければならない想像の共同体であった。「台湾民族」の民族自決の主体たる資格を、日本に、そして世界に対して弁証するために、台湾の知識人たちには、創造性に満ちた固有の台湾文化を創造するという責務が課せられた。「台湾民族」を単一の主体にまとめうる共通の文化とはいったい何なのか。この問いに対する回答は、1930年代には、文芸批評、言語学、民俗学、現象学といったさまざまなジャンルにおいて探求される文化的主題へと発展した。
台湾の知識人たちが、「台湾文化」を創造するにあたり、その固有性を弁証する主たる対象が、同化主義の圧力を昂進させてゆく帝国日本であったことは疑いない。しかし同時にそれが、初期の中国的「漢族」意識からの離脱でもあったことは、注目されなければならない。このことは、けっして台湾のナショナリズムが、その発生の当初から、反中国的もしくは非中国的であったということを意味しない。むしろ台湾における文化ナショナリズムの発展において、「中国」という要素は、漢民族の文化的伝統(おもに儒学)と台湾の社会的習慣の関係をめぐって闘わされた新旧文化論争においても、中国を救う正しい道を日本の社会主義者とともに議論した中国改造論争においても、つねに問題の焦点であった。とりわけ大陸の五・四運動や白話文運動によって示された急進的な反伝統主義は、日本の植民地支配の新伝統主義イデオロギーに対する台湾知識人たちの対抗運動を導き、鼓舞するものでありえた。しかし、そうした論争において、「中国的なるもの」は、「台湾的なるもの」を吸収するかたちでは機能しなかった。むしろそれへのオルタナティブを、「台湾的なるもの」として想像させるべく、そのテコとなる一種の「他者」として機能したのである。それは、〈二重の周縁性〉に閉じ込められた植民地台湾の政治的条件から、そして中国白話文が台湾においては書き言葉に限定された「外国語」にほかならないという言語的条件から、もたらされた帰結であった。こうした条件により、「台湾民族」は、その想像の黎明期において、中国的「漢族」意識とは明確に区別された独立した内容を付与されていたのである。
東アジアの未来に向けて
「台湾民族」をめぐる知識人たちの精神的彷徨は、1937年、台湾総督府によって台湾語の公的使用がほとんど全面的に禁止され、また「皇民化政策」が攻勢を強めたことにより、最終的に断ち切られることになった。このように見てくるならば、台湾のアカデミズムに身を投じた後の著者の学術活動は、まずは帝国日本により、その後中華民国の国民党政府により中断を余儀なくされた台湾知識人たちのネーションをめぐる実証的・規範的考察を再開し、東アジアにおいて、そして世界において、台湾というネーションの出口を模索する実践であったといえよう。この点に関して、本書のメッセージの主たる受け手となるのは、英語圏の読者ではなく、むしろ東アジアの現在を生きるわれわれである。英語圏の研究者に向けて、台湾ナショナリズムという主題の存在とその意義を弁証するために準備され発表された本研究は、いわば20年の時を隔てて、東アジアで開封されることで、新しい思想的意味を獲得することになる。
台湾というネーションの原型は、日本の植民地支配のもとで誕生した。しかしそれは、「親日台湾」というイメージにつきまとう、日本のおかげで台湾が発展したというようなものではなく、日本に抗したがゆえに発生したのだということの意味を、日本の読者は深く認識すべきであろう。本書は、台湾における植民地支配の思想史であるにとどまらず、日本本国における国民形成の思想史でもある。これは日本の植民地支配を〈国民化する植民地主義〉と規定した本書の視座より導き出される帰結である。この点において、植民地化の圧力にさらされた台湾の人々の経験と運命は、国民化の圧力にさらされた日本本国の人々の経験や運命と重なっている。〈東洋的植民地主義〉は、日本本国における支配や抵抗とカテゴリカルに区別されるものではなく、むしろ後者の特徴と意義を、より際立たせたかたちで表現するものにほかならない。この意味で植民地台湾における〈差別的包摂〉は、日本本国における統治のカリカチュアでもあった。日本イデオロギーの新伝統主義的な理念と実践を、日本本国の人々はどのように受けとめ、またそれにどのように抗ったのか。かつての周縁の帝国として〈東洋的植民地主義〉により周辺地域を支配した日本は、現在みずからをどのようなネーションと認め、またどのようなネーションであるべきだと考えているのか。著者が本書を通じて示した台湾政治思想史が日本政治思想史に対して突き付ける問いとは、このようなものである。
本書はまた、緊張を高める現在の中台関係に関しても、重要なインスピレーションの源泉となりうる。習近平中国国家主席は、2019年の「台湾同胞に告げる書」発表40周年記念式典で、台湾統一への圧力を強める姿勢を明確にした。その統一の思想的根拠は、「台湾同胞に告げる書」における「民族の復興」という語が示しているように、台湾人の中華民族としての同質性と一体性にその基盤を置くものである。しかしながら、こうした民族主義的ナショナリズムをもって台湾の「統一」を実現しようとする中国の戦略は、台湾において大きな抵抗を引き起こさずにはいないであろう。なぜなら、台湾ナショナリズムの原点には、日本の新伝統主義的な統治に対して普遍的な民主主義の理念をもって対抗した、台湾知識人たちの理想が刻まれているからである。中国の台湾統一が、「軍事力」と「経済力」、そして共通の「民族性」に基礎を置くものであるかぎり、普遍的な理念を志向する台湾ナショナリズムとの距離は、拡大する一方であろう。
本書は、自民族の優越性を誇示するエスノ・ナショナリズムが競合する現在の東アジアにおいて、民主主義を根幹とするマルチナショナル/マルチエスニックなナショナリズムが台湾に生まれ、それを台湾の人々がこんにちにいたるまで育んできたことの意義を、東アジアと世界の人々に向けて問いかけている。日本語版への序文にあるように、著者はいまだ「旅の途中」にある。そして著者が20年前にその輪郭を示した「フォルモサ・イデオロギー」もまた、今日に至るまで発展と変容を重ねている。たとえば、本書における著者の分析の対象は、あくまでも「漢族」の知識人に限定されたものであった。その意味において、本書で提示されたマルチナショナル/マルチエスニックな台湾というイメージも、多分に観念的な性格を残したものであったといえる。しかし、こんにちの台湾において、「漢族」以外の先住民の歴史・思想は、著者自身の「台湾ポストコロニアル・テーゼ」(前掲『台湾、あるいは孤立無援の島の思想』所収)や、台湾の新しい通史を目指した周婉容『増補版 図説 台湾の歴史』(濱島敦俊ほか訳、平凡社、2013年、原著1997年)、著者の実弟である呉豪人による先住民の思想に立脚した近代法体系の批判的再検討である『「野蛮」的復権――台湾原住民族的転型正義與現代法秩序的自我救贖』(台北:春山出版、2019年)などの作品において示されているように、台湾というネーションの根幹をなす要素として位置づけられている。本研究が発表されて以後、こんにちに至る著者自身の、そして台湾社会のネーションをめぐる思考の旅路は、ある意味で、このマルチナショナル/マルチエスニックな台湾というイメージを、実質化する営みであったのではないか。2019年のアジア初となる同性婚の合法化という台湾社会の選択も含めて、現在の台湾社会を特徴づけているのは、東アジアのナショナリズムにおいては例外的な、民主主義の理念に裏打ちされた多文化主義への強い志向性である。この20年のあいだ、台湾の人々は、こうした多文化主義的な政治文化を養い、それをひとつひとつ開花させてきた。そしてそのことの政治的意味は、世界的に見ても、けっして小さなものではない。本書は、台湾社会のそうした実践が、特定の民族的伝統を根拠とするのではなく、近代/普遍の追求を志向する「フォルモサ・イデオロギー」の基盤のうえに発生し、さらにそれを乗り越えるかたちで展開されていることの意味を、あらためて考えさせてくれるものである。
〈東洋的植民地主義〉の〈二重の周縁性〉に閉じ込められることにより誕生した台湾という「弱小民族」が見いだした、近代的/普遍的なマルチナショナル/マルチエスニックなネーションという「出口」は、こんにち台湾という境界を越えて、香港、沖縄など、帝国のはざまで苦悩する多くの人々の解放のインスピレーションとなりつつある。本書によって示される著者の、そして台湾というネーションの精神的彷徨には、たとえどれほど微かなものであるにせよ、未来を変える可能性が含まれている。なぜならそこに見いだされるべきは、ナショナリズムの衝突を、民主主義の競争へと変奏する可能性であるからである。台湾ナショナリズムの運命は、東アジアの未来の選択と密接に関連している。それは、われわれ日本人にとっても、けっして無縁なものではありえないのである。
Copyright © UMEMORI Naoyuki 2023
(筆者のご同意を得て転載しています。なお、
読みやすいよう行のあきなどを加えています)