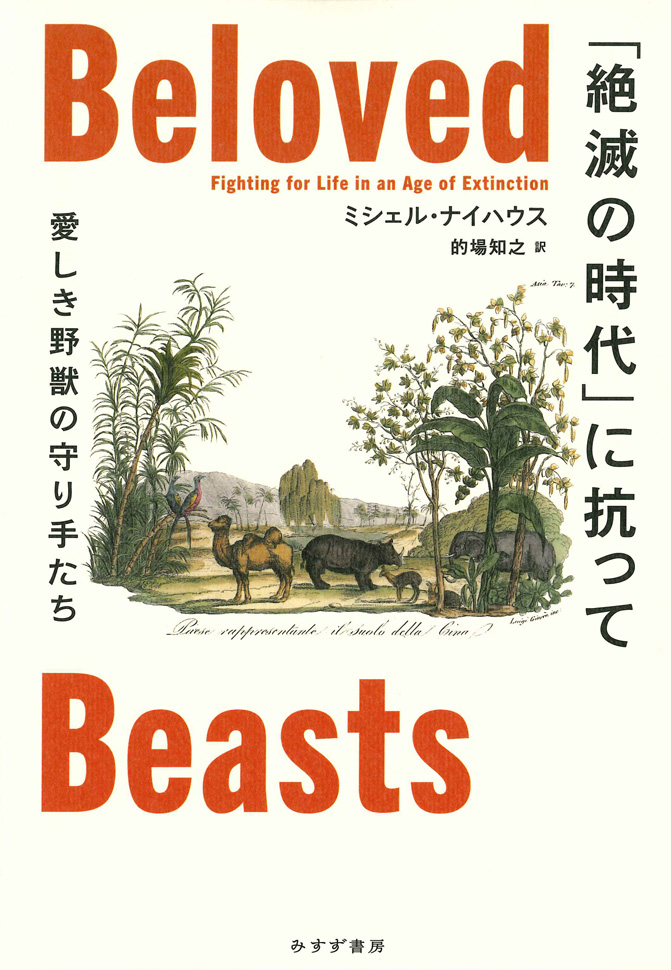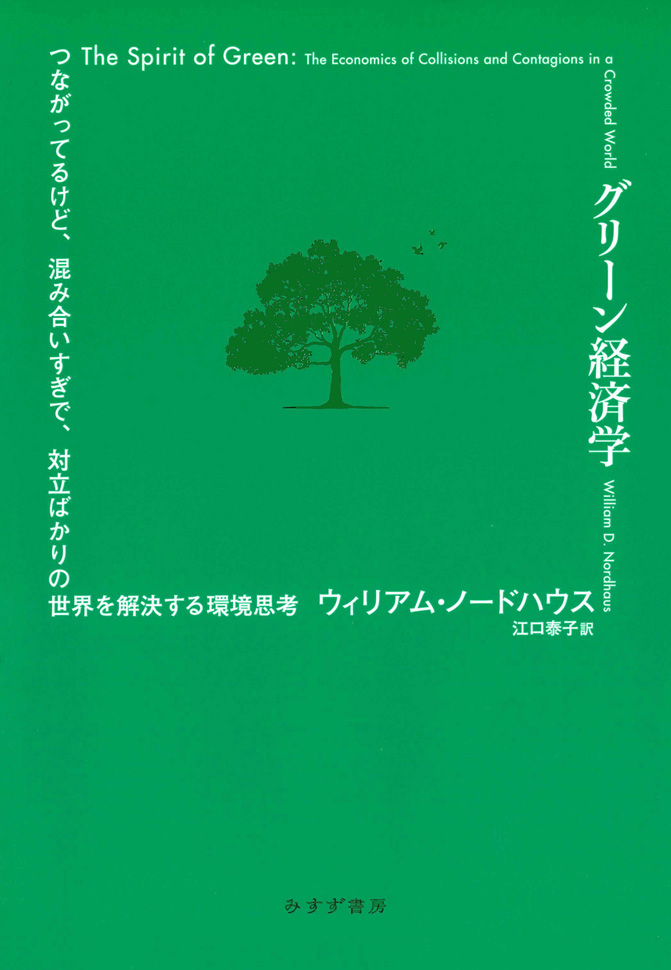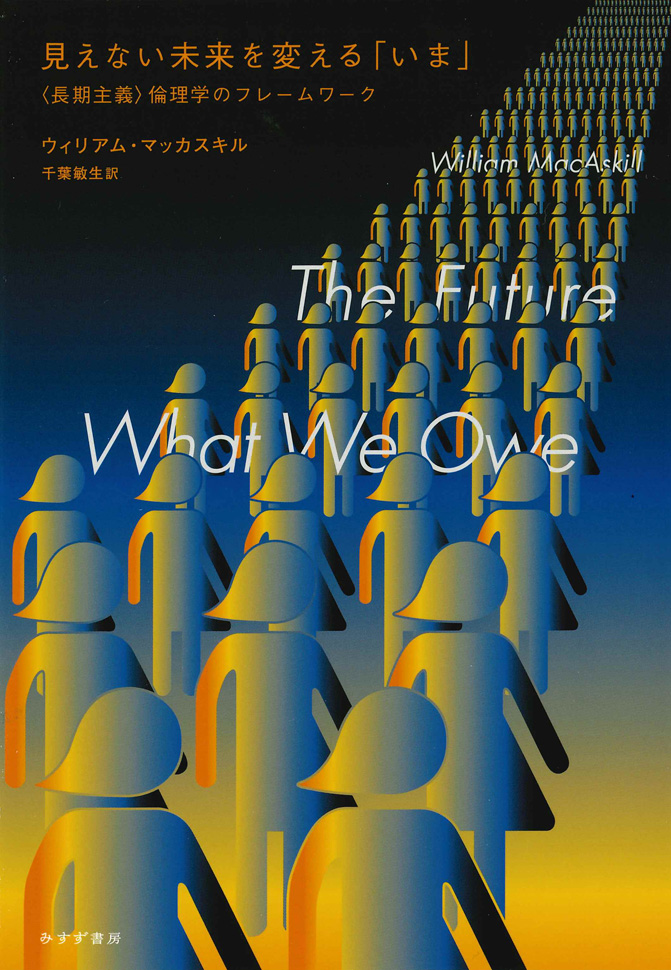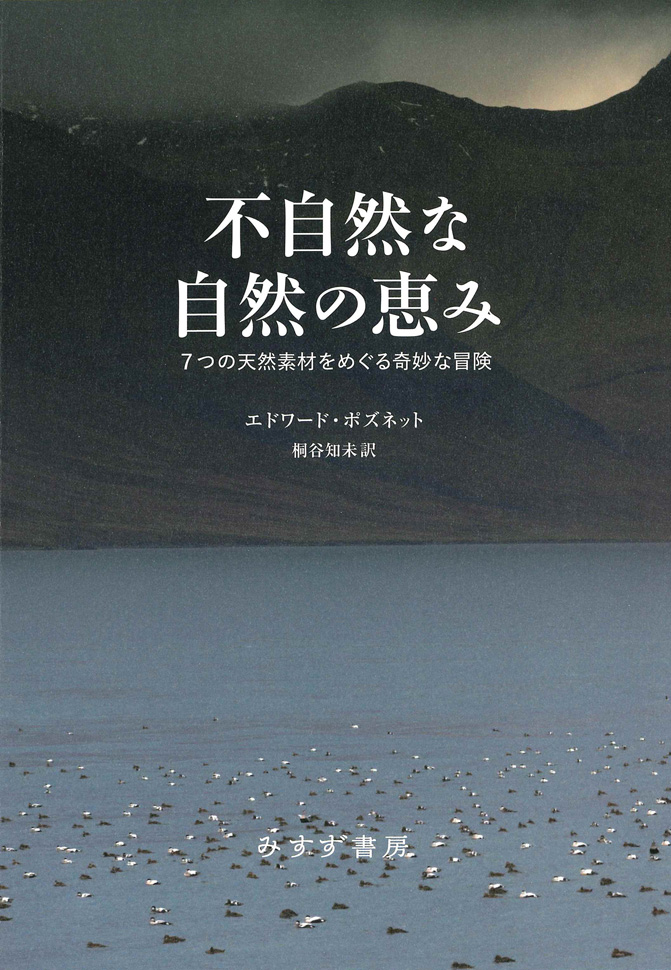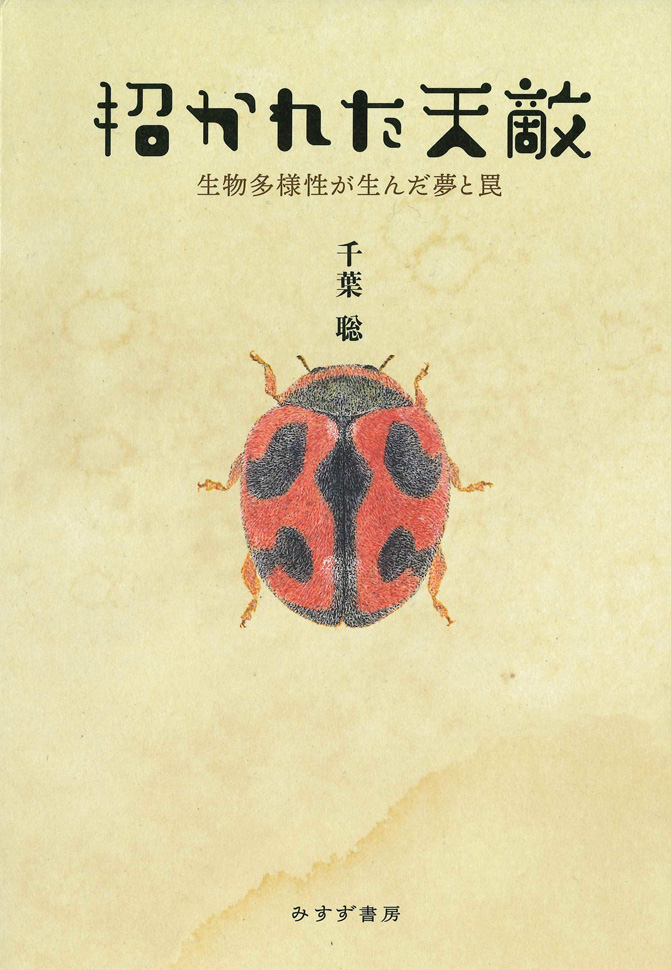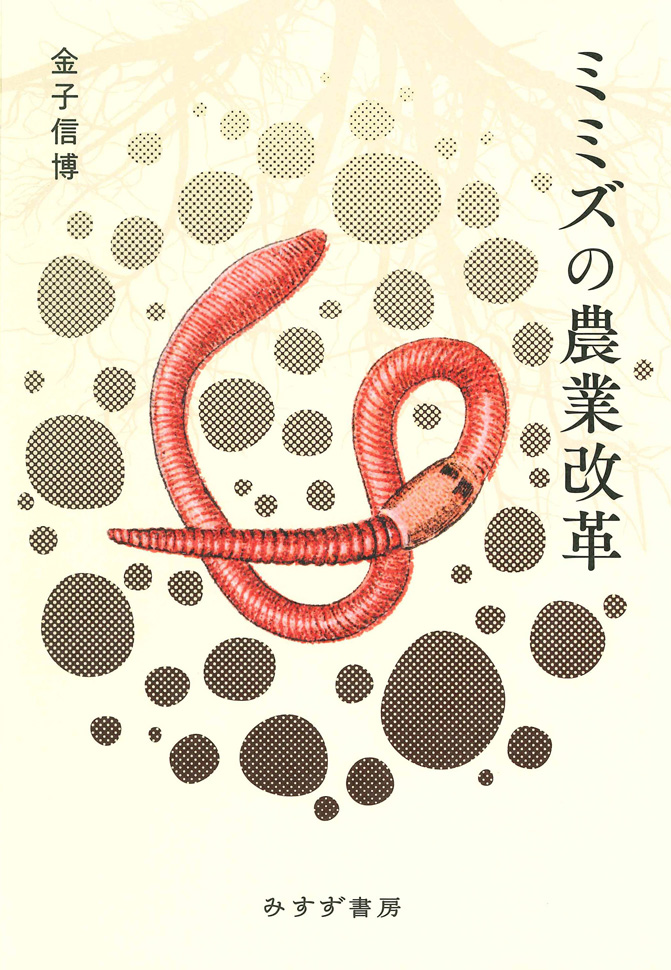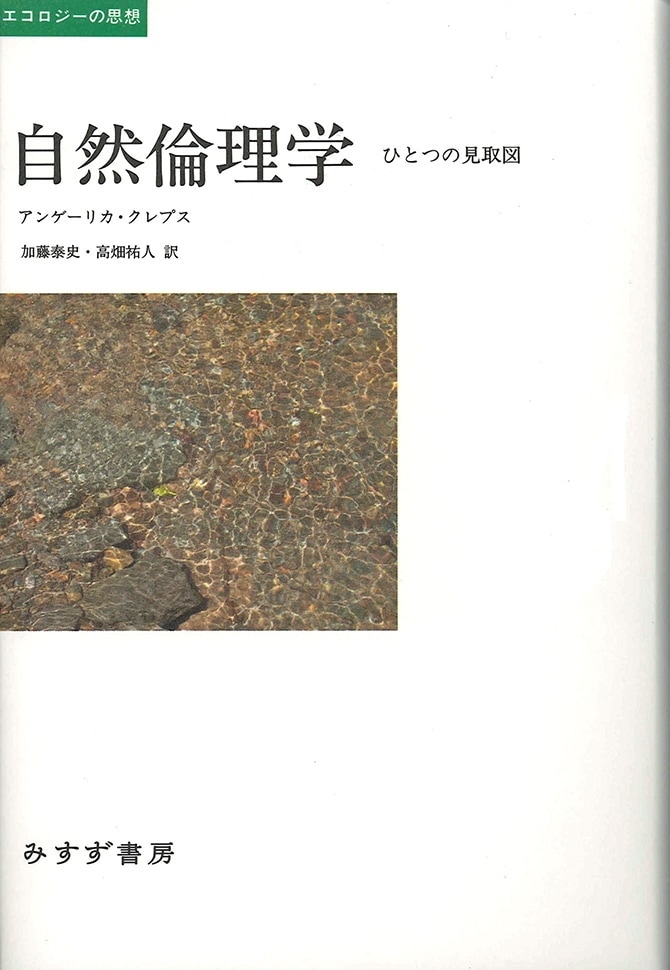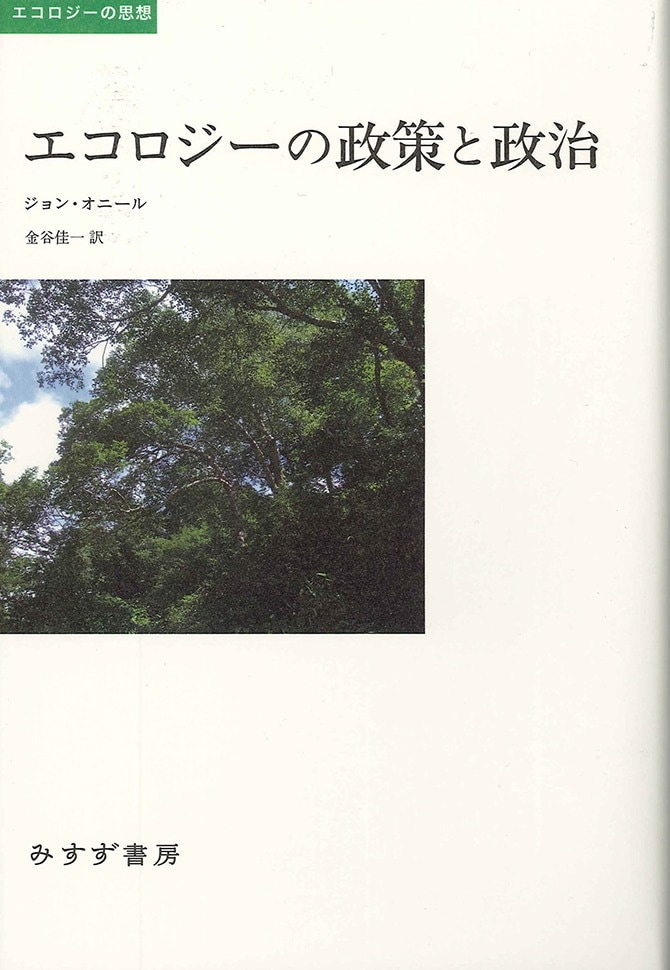絶滅という概念すらなかったほんの300年前の世界はいまや大きく様変わりし、生物多様性という用語を知り、その価値を知る人が多くいる世界になりました。地球環境に配慮することが一つの倫理的ステータスとみなされるようにもなっており、程度の差こそあれ、環境保全の重要性を標榜しない政府のほうがめずらしいほどです。
本書『「絶滅の時代」に抗って』は、こうした世界的な変化のなかで重要な役割を果たした人物にスポットを当てて書かれた、生物多様性保全活動の歴史の本です。
野生生物がおかれた状況を改善するには、生物学や生態学の知識さえあればよいわけではありません。科学的知識を実際の対策へ応用するには多くの資金や人員が必要だし、法や制度の整備も必要です。つまり政治・経済の力が欠かせません。そうなると、権限を持つ政治家や資本家を説得しなければなりませんが、それも簡単なことではありません。政治家や資本家もほうぼうに責任があって独断できることは多くなく、通常は票を投じる有権者や、企業の製品を購入する消費者の意向を重要視します。それに、現実に野生動物とやっていくのは、分布域の近くの地域に住む人びとです。
すなわち、野生生物の状況改善には市民一人ひとりの理解と協力がきわめて重要なのです(そもそも、生物学の研究を行うにも資金が必要で、税金が占める割合は大きく、つまり市民の理解が欠かせません)。
どんな歴史でも個々人の価値観の変化が重要視されますが、生物多様性保全活動の歴史も例外ではありませんでした。「生物多様性には価値がある」というのは現代の多くの人が認めるところでしょうが、その価値観は時代とともに現れたものだし、その詳細はいまも人によってまちまちです。金額に換算して価値を測ったり、豊かな生物多様性それ自体に価値があると考えたりと、たくさんのバリエーションやグラデーションがあり、一つの絶対的な価値観に統一することはむずかしいです。「野生動物を保護する理由」が時と場合で変化してきたことは、本書にも記されています。
でもひとつだけたしかに言えるのは、本書が語るように、生物多様性保全活動は質実に成功を積み重ねて市民の価値観に影響を与え、社会的なプレゼンスを広げることでここまできたということです。
このプレゼンスの広がりの過程は本書に詳しく記していますが、この新刊紹介記事でとくに取り上げたいのは、第7章に登場する生物学者マイケル・スーレです。彼は保全生物学(Conservation biology、保全生態学とも)という学問分野の立ち上げに大きく貢献しました。保全生物学は、生物多様性保全のために必要なあらゆる知識を探求する応用的な学問領域で、基礎生物学的な課題と、社会学・経済学的課題とをあわせて考察対象とします。その探求の目的のひとつは「自然保護をめぐる政治を動かすこと」。これは1970年代後半の発足当時、きわめて斬新でした。科学者の大多数が「神、形而上学、道徳、政治、文法、修辞、論理に首を突っ込む」ことを避ける傾向にあるなかで、そうしたものごとに首を突っ込むことをいとわないぞ、という決意がにじむものです。
スーレは、保全生物学の設立を提案する1978年の集会でこう演説しました。「学問分野は論理的構成物ではない」「一定数の人々の集団が、集合し対話することに意義を見出したときに立ち現れる、社会的作用の結晶である」(p. 231)。つまり、保全生物学は、生物多様性保全の問題に着手すべきだという社会の意識の反映だ、というわけです。
では、なぜその当時、社会が生物多様性保全を問題として意識するようになっていたのでしょうか。本書に書かれたすべての要素が、この問いの答えになっています。
リンネが確立した生物の命名体系のもとで受け継がれてきた膨大な生物名カタログは、後世の人々が生物を理解する足がかりになりました。ウィリアム・ホーナデイが、狩猟で絶滅しかかったアメリカバイソンの剥製をつくって博物館に展示したことが、当時のアメリカの人々の胸を打ち、その保全活動を後押ししました。アルド・レオポルドの『野生のうたが聞こえる』に記された「土地倫理」の考え方は、自然保護従事者を中心に多くの人の自然理解に強く影響しました。ダーウィンの進化理論は、生物種と自然環境との密接な関係を強調するとともに、ヒトとその他の生物種との関係をあばくことで、社会に多大な影響を与えました。レイチェル・カーソンが『沈黙の春』の冒頭に記した暗い未来――鳥は鳴かず、昆虫はおらず、小動物の死に絶えた静かな春――は、世界中の人々の危機感を呼び起こし、多くの人が生態学的概念を知るきっかけとなりました。
生物学の知識を発展させた人がいたこと。そして無思慮な人間活動がもたらす帰結が広く知れ渡るよう、訴えかけた人がいたこと。これが、社会が変わってきた原因であり、社会が今後もさらに変化していく理由になります。
では、みなに訴えかける人はなぜ、そんなことをしようと思ったのでしょうか。そのモチベーションの源泉はなによりも「生命愛」でした。平原を駆けるバイソンを、優雅に宙を舞うタカやツルを、美しい声で歌う小鳥たちを、うんざりするくらいありふれたカエルたちを愛し、かれらが永遠にいなくなってしまうことを受け入れたくない、理屈を越えた気持ちでした。
人間活動の拡大は、いまのところとどまるところを知りません。その影響が気候変動という形で表出しはじめていますし、開発によって野生生物のすみかは減少を続け、人と野生動物の軋轢も激しくなっています。絶滅危惧種のリストはいまも増大し続けており、著者が「悲劇と緊急事態のごった煮」と書いているように、種の保全の状況はこれから先も決して楽観視できません。
ですが、成功を積み重ねてきたこともまた事実なのです。著者は次のように記しています。
妄想と絶望に流されないためには、歴史から学ぶことが役に立つ。自然保護活動のこれまでの成果はけっして必然ではなかったし、いま失敗に終わるだろうと言われていることも、そうなる運命などありはしない。苦難を乗り越えて脈々と続いてきたこれまでの活動の来歴を知れば、わたしたちは前に進めるし、まだ見ぬこの先の展開を思い描くことができる。(p.10 序章「イソップのツバメ」)
いまは「第六の大量絶滅期」とも言われています。この抗いようもないようにもみえる大きな流れに抗うために、先人が積み重ねたこれまでの努力に本書で触れ、私たちのこれからに思いを致してみてください。