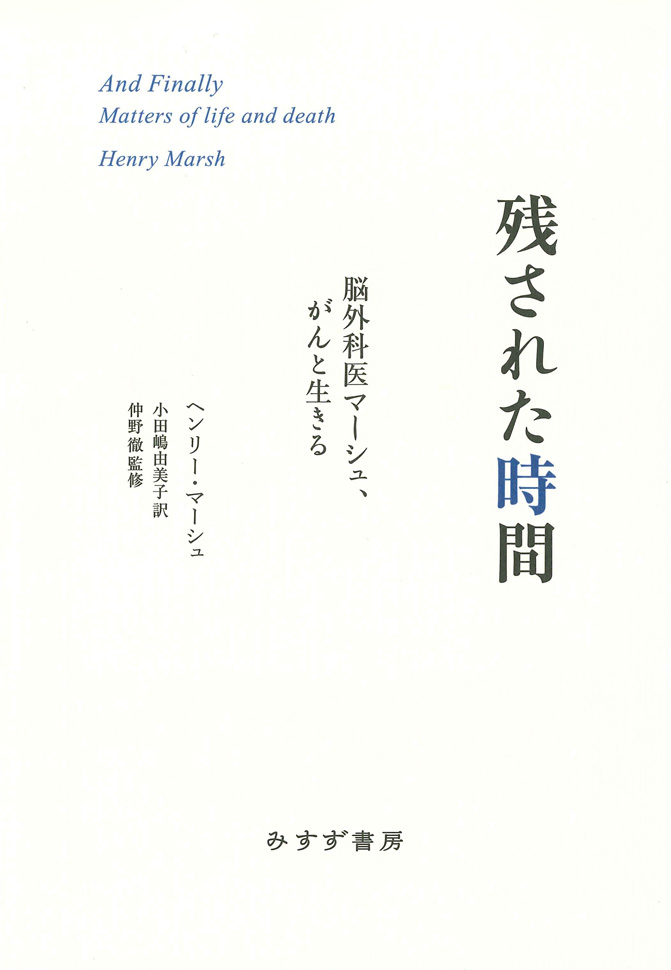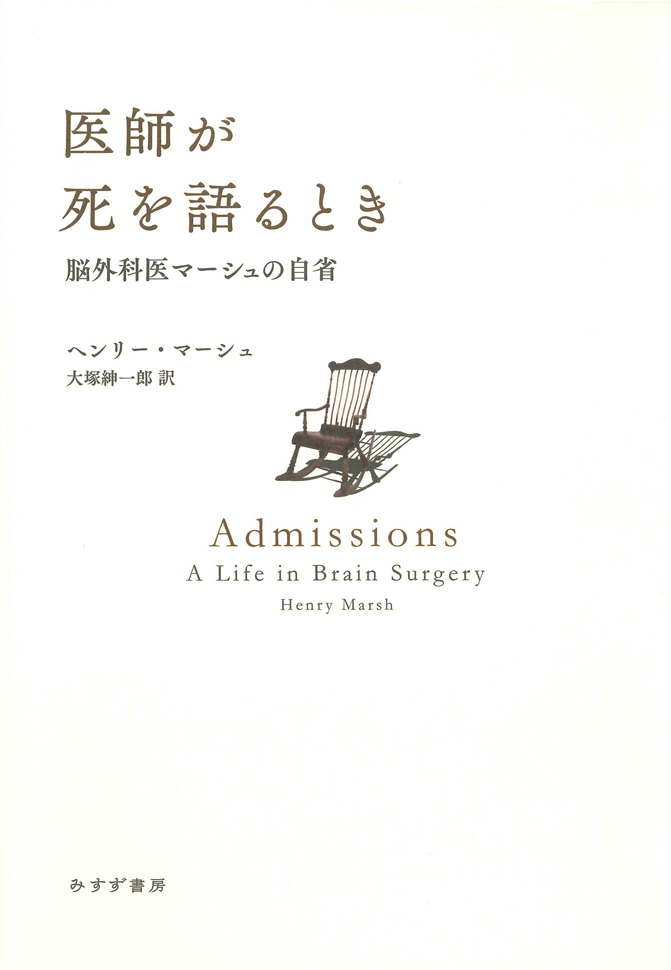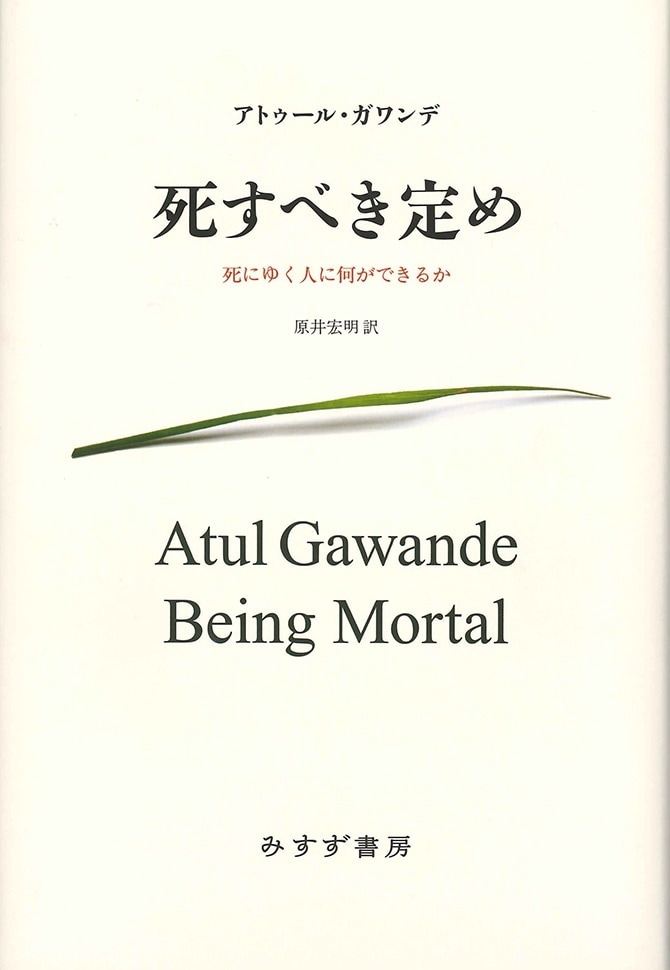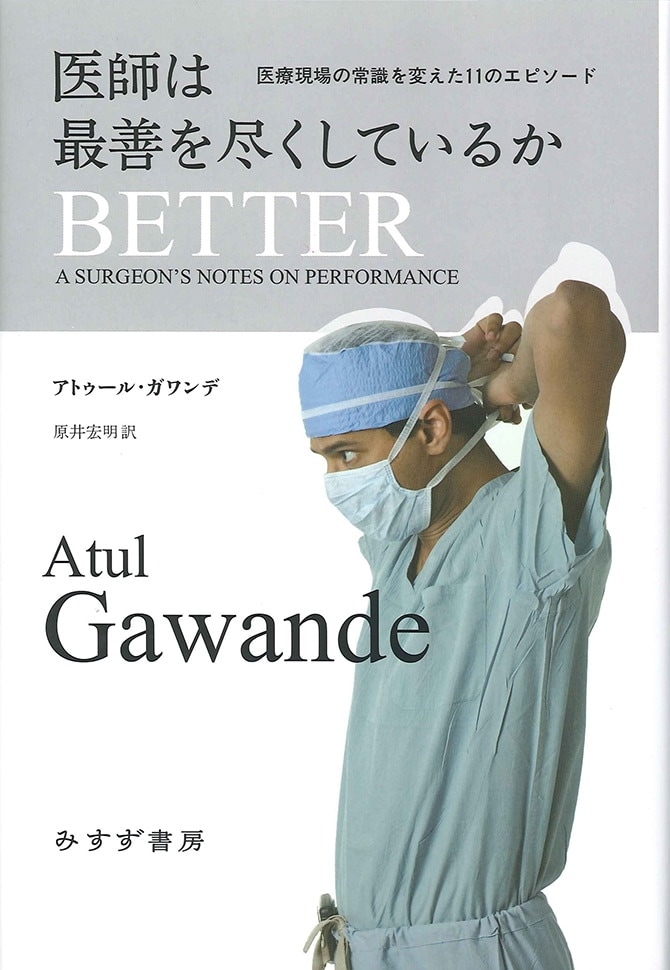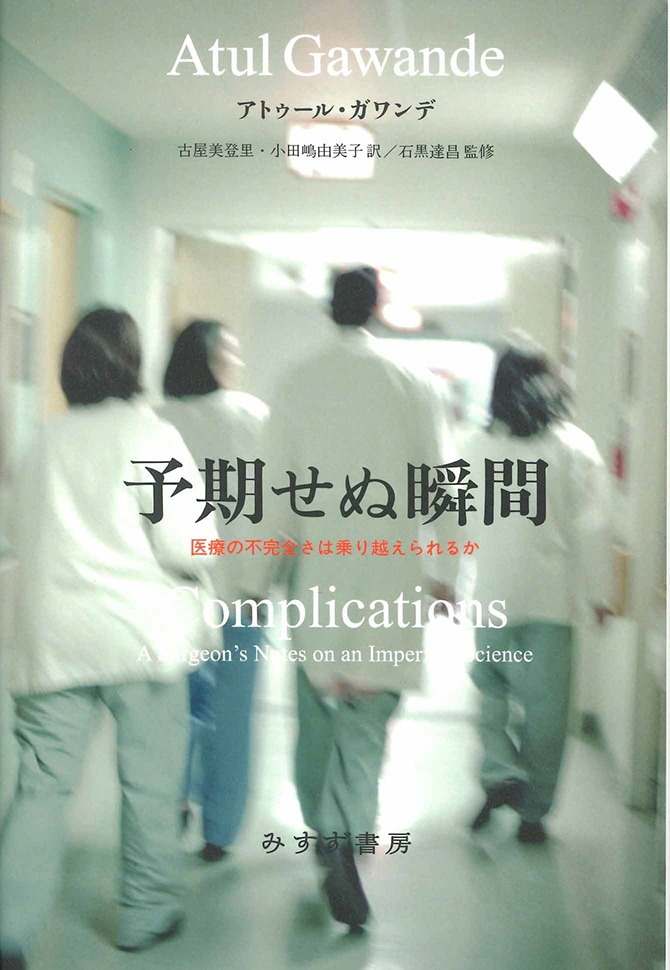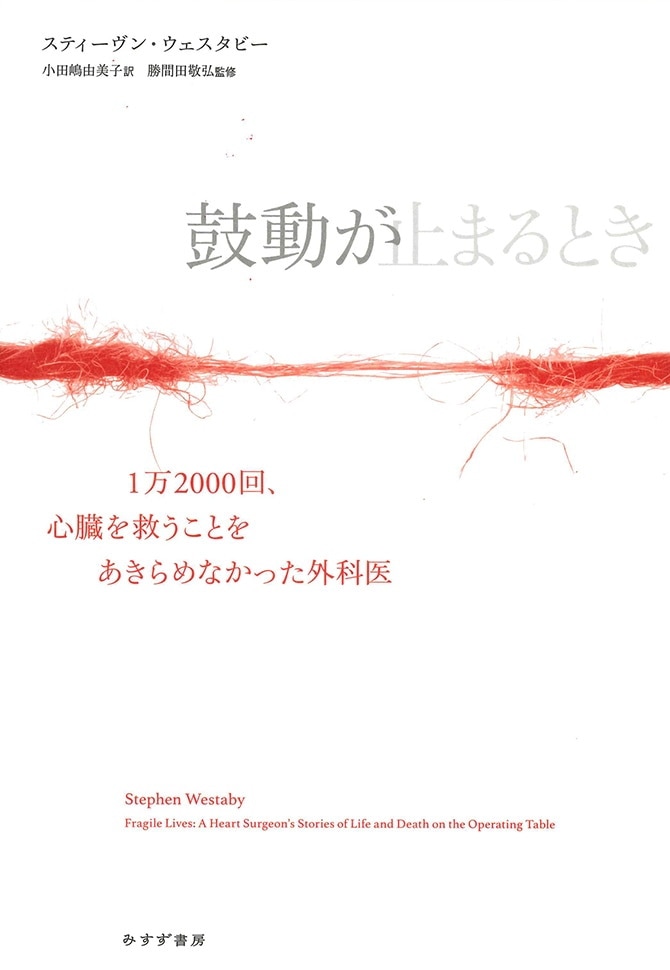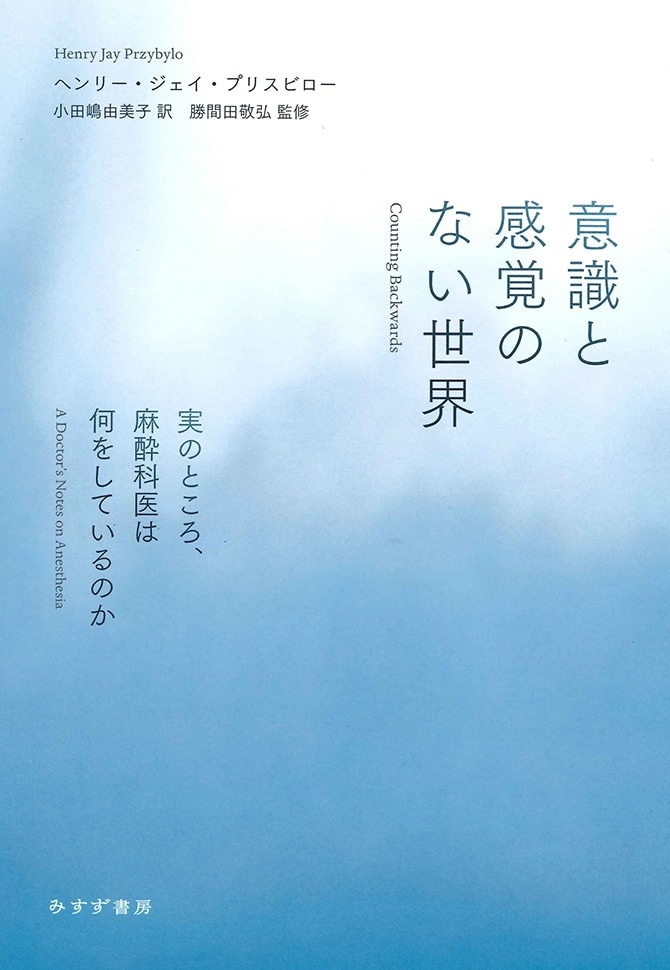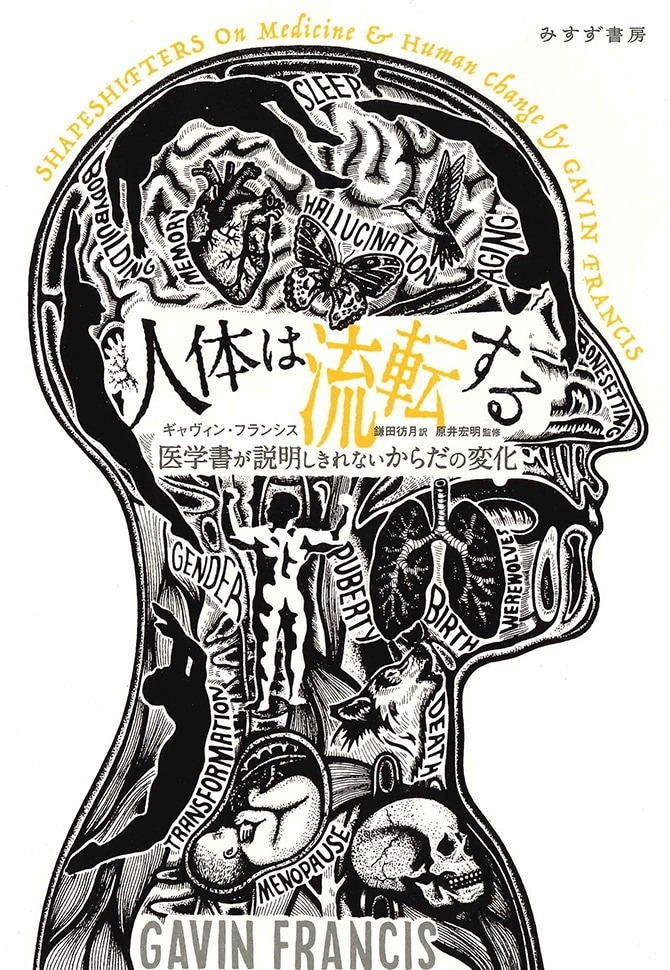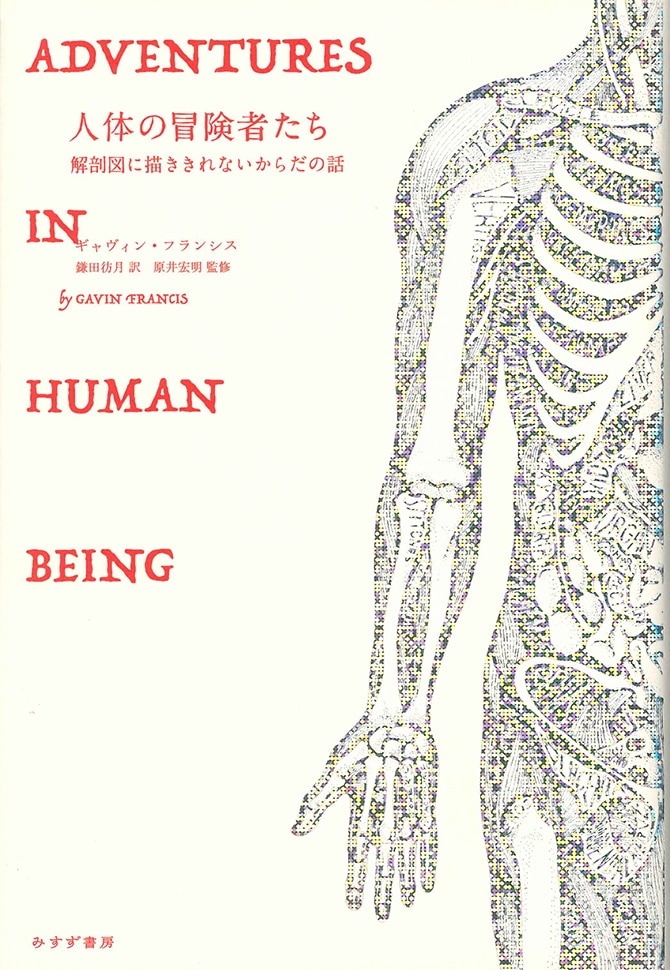仲野徹
ヘンリー・マーシュ先生。会ったことのない著者は呼び捨てにするのが習わしだろう。しかし、マーシュ先生の処女作を読んだときから、先生とつけて呼びたくなってしまっている。
医学部を卒業したが、医業を営まずに生命科学の基礎研究に従事していた。とはいえ、もちろん医師の友人も多い。医師同士は互いを「○○先生」と呼び合う。いささかおかしな習慣だと思うのだが、たとえ同級生同士という親しい間柄であってもそう呼ぶことがあるくらいだ。しかし、そんな理由で「マーシュ先生」と呼びたくなったわけではない。なんだか、どこかで会って話をしたことがあるような親近感を覚えたからだ。
マーシュ先生は脳外科が専門で、基礎研究の経験はお持ちではなさそうだ。私といえば、内科医として3年間勤めたことがあるとはいえ、その後は研究ばかりしていた。だが、医学部の教授として学生たちに長い間教育をしていたので、医学や医療についてはそれなりの考えがある。永年の臨床経験に裏付けられたマーシュ先生のお考えとはレベルが違うけれど、僭越ながら、考え方がとても似ていると感じたのだ。
「ヒポクラテスの誓い」という宣誓文がある。医療の倫理や実践について、古代ギリシア時代に作られたものだ。マーシュ先生が二人目の妻である社会人類学者ケイト・フォックスの勧めによって出版された一作目の原題Do No Harmは、そこからとられたものである。この誓い、実際にはヒポクラテスが作ったものではないようだが、「害をなすなかれ」という意味だけでなく、医聖につながる有名な言葉をタイトルに用いたところにマーシュ先生の心意気が感じられる。
その本、邦題である『脳外科医マーシュの告白』(NHK出版)からわかるように、マーシュ先生が赤裸々に語られる脳外科医としてのさまざまな経験が主な内容である。父はオックスフォード大学で教鞭をとったこともある高名な人権派弁護士、母は反ナチス的な発言を密告されドイツから逃れてきた書店主だ。有名パブリックスクールからオックスフォード大学に進み、政治学・哲学・経済学を学んだのも自然なことだったろう。
大学入学前には、アフリカの僻地で英語を教えるボランティアをするなど二年間の空白があったが、生え抜きのエリートコースだ。ここまでは順調だったが、失恋の絶望感から大学を離れ、北アイルランドにある炭鉱町の病院でポーターとして働きはじめる。そこでのさまざまな経験から医師になることを決意し、学業にもどることになった。
卒業して1年半のとき、脳手術を初めて見学した瞬間、脳外科医になることを決意する。この天恵のような決断とその後の脳外科医としての活躍から考えると、天職と言って間違いない。しかし、「わたしはよい外科医でありたいと思っているが、どう考えても偉大なる外科医ではない。わたしが覚えているのは成功――成功したと自分では思っている――例ではなく、失敗例だからだ」と綴られているように、マーシュ先生は自分の働きに自信を持っておられるけれど、あくまでも謙虚だ。
一方で、手術がうまくいった場合には、患者さんが自分に対して必要以上に感謝しているのではないかと照れてしまう。謙虚すぎるではないか。優れた技量だけでなく、その経歴や医療に対する姿勢が素晴らしい。なりたくはないけど、もし脳腫瘍になったらこんな先生に診てもらいたい。
『脳外科医マーシュの告白』にはさまざまな医療経験が描かれているが、特筆すべきは、ソビエト連邦崩壊後すぐの1992年から始めたウクライナでの活動だ。意欲的だが医学界から異端視されていた脳外科医イーゴル・グリレッツと友情を結びながら、20年以上にわたりキーウでの脳外科支援に全力を尽くす。その姿は、日本では公開されなかったが、The English Surgeon(イギリスの外科医)というドキュメンタリー映画になっている。
イメージ通りだった。映画で見るマーシュ先生は、黒縁の丸眼鏡のよく似合う、優しそうな、しかし芯が強そうな人だ。すでに経歴を知っていたからかもしれないが、少なからぬ陰影が感じられる。ユーモアにあふれ穏やかだけれど、仕事に対しては厳しく、時には激しく怒ったりする。
「医師は、医学の「アートとサイエンス」について語るのが好きだ。しかし、医学を「術(アート)」と「科学(サイエンス)」に分けて考えるのはずいぶん傲慢ではなかろうか。わたし自身は、医学とはむしろもっと実践的な職人技であり、長い歳月をかけて習得するものだと思っている」
マーシュ先生は根っからの職人、究極の脳外科職人だ。
『脳外科医マーシュの告白』が現役時代の華やかな記録――と言うとマーシュ先生に叱られそうだが――とすれば、二作目『医師が死を語るとき――脳外科医マーシュの自省』(みすず書房)は、引退した後の、以前よりは穏やかだが悩みのつきない日々を描いた本だ。友人のデヴが経営するネパールの脳外科病院での日々、ライフワークともいえるウクライナでの活動、そして、終の棲家として購入した「水門管理人のコテージ」の改修作業などが語られていく。
「水門の管理人のコテージを見つける4カ月前、2014年6月のことだ。私はかっとなってロンドンにある病院を退職することに決めてしまっていた」
マーシュ先生の本は、イングランドのNHS(国民健康サービス)をはじめとする医療制度に対する不満も隠れたテーマかもしれない。辞表を出した理由は、勤務していた病院の医長から、ドレスコードを守らなかったがために懲戒処分を宣告されたことによる。スーツとネクタイを着たまま診療したというのがその理由だ。他にも「せっかちで無愛想」なマーシュ先生にとってはくだらないと思える仕事が増えてきたし、医師になってから40年、あまりに多くのことが悪い方向に変わってしまったという意識があったのも大きかった。英国ほどではないにしても、日本も似たようなところがあるかもしれない。
退職の二週間前にトラブルを引き起こしてしまう。腫瘍を摘出した手術の翌朝、経鼻胃チューブを抜くように看護師に指示した。しかし、言語療法士のチェックなしにそれはできないという。そもそも入れる必要のない経鼻胃チューブだったと考えるマーシュ先生は腹を立て、看護師の鼻を引っ張ってしまう。
「着実に権威を失い、信頼が低下し、そして医療業界の悲しい衰退に直面してきたことへの長年の不満と落胆が、突然爆発したのだった」
やってはいけないことだが、マーシュ先生らしいではないか。深く反省し、謝罪されたのは言うまでもない。「患者からの感謝の気持ちが込もった手紙や写真。プレゼントや表彰盾」や、「告訴された症例に関する書類や苦情の手紙」などを片付けてオフィスを後にした。65歳のときだが、「後悔はまったくなかった」という。
そしてネパールに旅立った。30年前、共に脳外科の研修をうけたデヴの病院を手伝うために。ネパールの医療事情はきわめて悪い。そのような国では、非常に高価な機器を必要とし、失敗や達成がないことも多い神経外科はある意味「贅沢品」である。デヴは一人、そんな国で30年間がんばってきた脳外科医だ。病状がきわめて悪くなってから、脳腫瘍なら先進国では見られないほど大きくなってから、運ばれてくる患者も多い。治療をしても意味がないとわかっていても、懇願されてやむなくおこなうこともある。もちろん良くならない、あるいは、かえって状態を悪くするようなこともある。このような国では、死が身近だ。
マーシュ先生の考えは、無駄な希望は抱くべきではないというものである。ハーバード大学教授アトゥール・ガワンデが、進行を止めることができない疾患である末期がんと認知症になったときにどうすべきかを説いた『死すべき定め――死にゆく人に何ができるか』(みすず書房)を思い出していた。
全米で100万部を売り上げたというこの本の最大のメッセージは、いまを大事にすることである。死についてのマーシュ先生の考察はガワンデに似ているだけでなく、同じくらい深い。
若いころのさまざまな思い出など、紹介したいことは山ほどあるが、そこは読んでいただくしかあるまい。ただ、「記憶にあるかぎり、私は神を信じたことはない。一瞬たりともだ」という完全に無神論的な考えと、悲しいことにイーゴルと決別してしまったこと、それから、幸いなことにコテージの改修は順調に進んでいったことは記しておきたい。
古代インドからヒンドゥー教に由来する四住期(しじゅうき)という考えは、人生を学生期(がくしょうき)、家住期(かじゅうき)、林住期(りんじゅうき)、遊行期(ゆぎょうき)という4つのステージに分ける。それぞれ、学び成長していく期間、家庭を設け仕事に励む期間、世俗を離れ自由に生きる期間、人生の終焉を迎えつつある期間、に相当する。マーシュ先生の「三部作」はいずれもエッセイ集なので、その内容は時代を行ったり来たりする。それでも、おおよそ、『脳外科医マーシュの告白』が学生期と家住記、『医師が死を語るとき』が林住期、そして本書『残された時間』が遊行期に相当する。「人生の終焉を迎えつつある期間」というのは失礼ではないかと思われるかもしれないが、この本を読みはじめればすぐに納得できるはずだ。
まず紹介されるのは、「老化の兆しがほとんど見られない稀有な人間である」ことが証明されると思い込みながら受けた脳のMRI画像についてである。そこには紛れもなく進行中の「老い」があった。「患者や友人たちに、よほどの問題でもなければ脳のスキャンをしない方がいいとアドバイスしてきた」のは正しかったのだ。自分が、自分の脳が「腐りはじめて」いて、「命の期限が切られた」不安にさいなまれる。さらにその20カ月後、進行性前立腺がんの診断を受けた。
「本気で感情移入したら、つまり、患者の気持ちをそのまま感じるとすれば、医師という仕事はできないだろう」
患者としては受け入れたくないかもしれないが、これはおおよそ真実だ。そのような医師として患者を診る側だったのが、患者として医師に診られる側に移り、あらたな思索が展開されていく。エリザベス・キューブラー・ロスは、古典的名著『死ぬ瞬間――死とその過程について』(中公文庫)で、死を受け入れるには、否認、怒り、取引、抑うつ、受容の段階を経ると説いた。必ずしも当てはまるものではないとされているが、マーシュ先生は時系列的ではなく、同時並行的に受け入れていかれたようにみえる。豊富な経験と死についての熟考がすでにあったからこそだろう。
それでも第一部のタイトルは「否認」となっている。老いや死を意識したとき、マーシュ先生に思い出されたのは、完全に忘れていた昔の患者のこと、ネパールでのトレッキング、自らの手で20年も改修をつづけた家、ウクライナでの医療やそこで診察したスナイパー、左右を間違えて手術してしまった医療ミス、専門だけど十分な技量がなかったのではないかと考えてしまう聴神経腫瘍の手術、孫娘のために作るドールハウス、何かを作ろうと買い貯めた多くの木材など、さまざまだ。もしかすると、そういった思い出や行動に逃避したということなのかもしれない。新型コロナ禍とも重なり、引退した医師への復職の呼びかけに応じることにしたタイミングでもあった。人生とはなんと複雑なものなのか。
第二部「治療的破局化」には、屋根の修繕詐欺にひっかかったような話もあるが、多くは前立腺がんの治療――化学的去勢と放射線治療――と、その過程において考えたことである。タイトルの治療的破局化とは、考えられる最悪のシナリオ――当然、死に終わる――を想像し、「いったんそれを脇に置いて」、「人生に残されたことをやり遂げる助け」にすることを指す。一方で、それとは真逆に、「都合のいい作り話を信じこもうとする」こともあった。
「私は死にたくない。そもそも死にたい人などそうはいない。だが、言うまでもなく、老いてよぼよぼになるのもいやだ」
人生と同じく人間も複雑だ。マーシュ先生の揺れ動く気持ちがさまざまな角度から詳しく述べられているのがとてもいい。
「いつまでも幸せに」が第三部である。「私が求めるべきは、あと数年よい人生を過ごすことだけだ」と考え、安楽死や自死幇助、そして認知症に考えをはせる。「私たちは誰でも死を恐れるが、信仰を持つ人にはさらなる恐れがある」というのはかなり逆説的な感じがするが、無神論者マーシュ先生の真骨頂というところだ。
全編を通じて、マーシュ先生の興味の広さには驚かされる。量子力学、顕微鏡の威力、神経伝達物質、新型コロナ、高山病、睡眠、夢、進化人類学、「おばあさん仮説」、宇宙論、光に反応するタンパク質であるオプシン、意識と無意識などなど。何かをきっかけに、じつにさまざまなことがわかりやすく説かれていく。こういったことのできる人こそが真の教養人だ。
以前の二作を読んだ人にはもちろん、読んでいない人にも十分楽しめる内容になっている。重要な出来事や考えは、簡潔にではあるが、この本でも繰り返して紹介されているからだ。良かったことばかりではなくて、悪かったことについても。もちろん、前作を読んだ人は、マーシュ先生との再会を心から楽しめる。
一作目の延長だろうと予想して二作目を読んだとき、トーンの違いにかなり意外な感じがした。この三作目も、前二作とはかなり異なった印象を受けた。もちろん通底する考え方は同じなのだが、語られる対象の違いが大きいためだろう。年齢を重ねられたし、ご自身の病気のことなどもあってトピックスは暗くなっていると言わざるをえない。しかし、マーシュ先生の姿勢は決してそうではない。何があっても光明を見出していく。ウクライナについても同様だ。
『残された時間』は、あとがきだけがロシアのウクライナ侵攻後に書かれている。そこでは、戦争によって「私の母の人生がそうであったように、友人たちの人生も根底から変わってしまった」、「ウクライナをまたこの目で見ることができるのか、あるいは友人たちに再会できるかどうか、私にはわからない」としながらも、
「私たちは楽観的でありつづける義務がある。それをせず諦めてしまったら、悪が確実に勝利を収めるから。私は必ず戻る」
と締めくくられている。さすがはマーシュ先生!
「年を取って死に近づいて初めて、自分自身と自分の過去について理解できるようになったのはなぜだろう?」
それはあなたが真摯に生きてこられた証しでしょう。この本の原題はAnd Finally、「そして最後に」とでも訳せばいいのだろうか。マーシュ先生の四作目を読んでみたいが、このタイトルを見たら、残念ながら次はなさそうな気がしてしまう。
マーシュ先生、ありがとうございました。そして、さようなら。
Copyrigt © NAKANO Toru 2024
(筆者のご許諾を得て転載しています。なお
読みやすいよう行のあきなどを加えています)