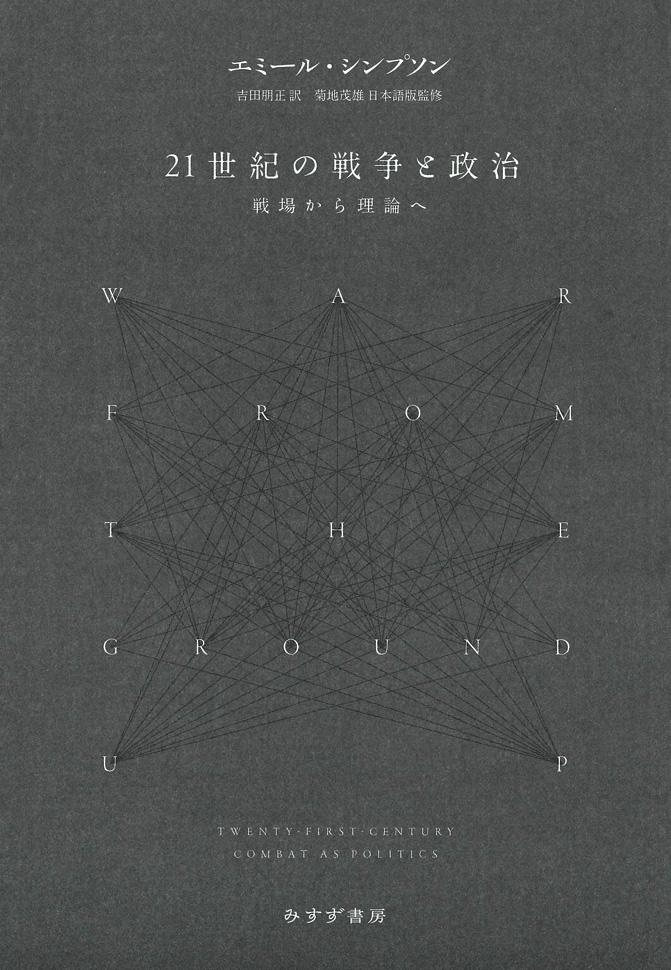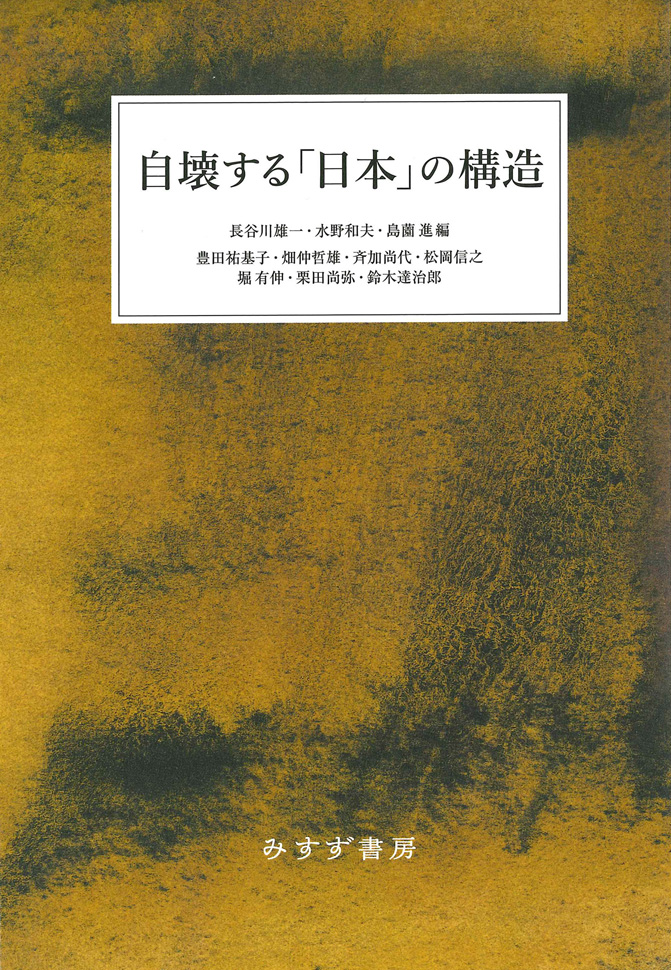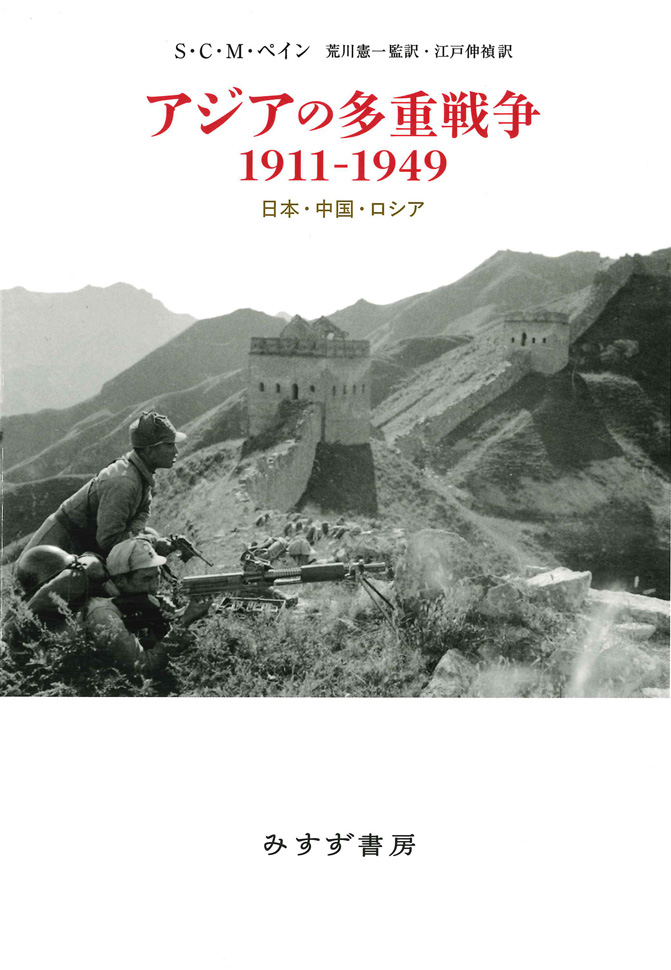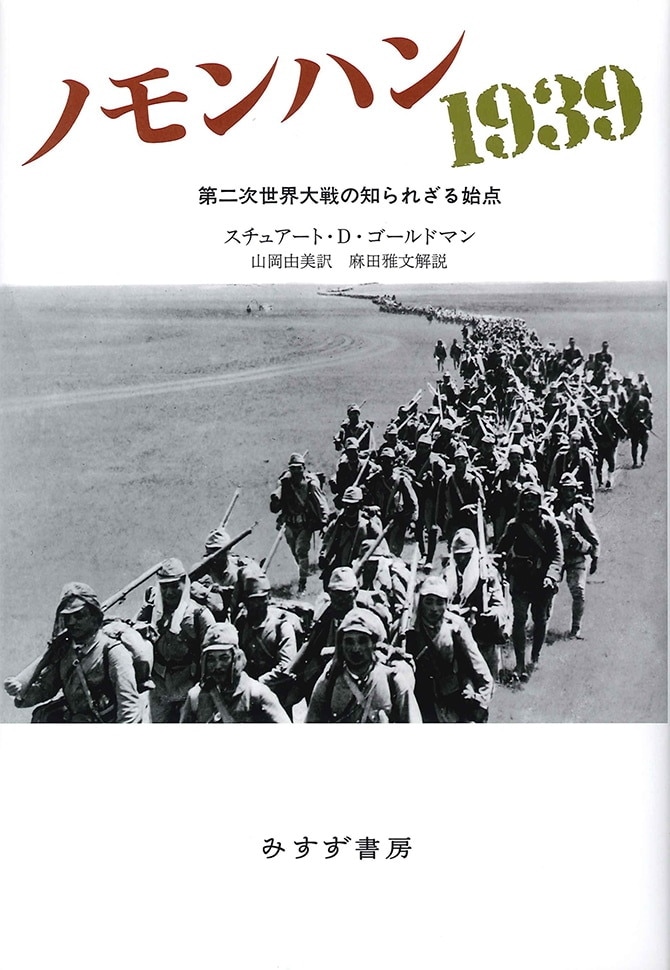戦争というのは通常、敵味方の二極に分かれた争いと理解されている。この二極性こそは、戦争を異なる陣営間で争われるものとする考え方の根底にあるものだ。こうした捉え方では、通常まず敵と味方の二陣営が存在し、仮にそれ以外のグループが存在しても、彼らはこの典型的な二陣営に応じて分別され、いずれかに同盟者として連なることになる。こうした二極性は、伝統的に理解されてきた戦争が、政治の道具としての基本機能──つまり軍事上の成果によって条件を整え、政治的解決をもたらすという役割──を果たすには欠かせない。こちらが味方で、あちらは敵という区別を立てることで、戦争はシーソーのような相互排他的な帰結、つまり一方には勝利を、他方には敗北をもたらすことができるからだ。仮に戦争の成果が絶対的ではなかったとしても、敵との相対的関係によって、一方が戦いにおいて総じて成功を収めた、あるいは失敗したということが決まるわけである。しかし多くの現代的紛争では、戦いの成果は、単に敵に対する成果として定義されるわけではない(本書4頁)
著者はアフガニスタン紛争を2006年から6年間英国陸軍士官として戦い、2012年に本書を刊行した。周知のように、これは2001年9月11日アメリカ同時多発テロ事件への対応として始まった「対テロ戦争」と呼ばれるもので、2003年のイラク戦争につながっている。イラク戦争についてはアメリカ主導によるその開戦理由の正当性は今ではほぼ否定されており、戦後の復興計画の杜撰さもすでに広く知られた。本書はそうした意味での事後的検証には触れていないが、オックスフォード大学の歴史学徒であった青年が戦場でまざまざと目撃した、戦争というものへの誤った認識を批判したものである。誤った認識で立てられた戦略の帰結が端的にあらわれるのは戦場なのだ。
暴力を政策の直接的延長として用いることは、作戦としては効果が高いかもしれない。だが、明確な戦略が構築されていなければ、これは相当に危険なゲームであり、しかもそのリスクは、それが戦争であるという思い込みのおかげで覆い隠されている(本書345頁)
ところで今現在もっとも深刻なのはウクライナ戦争であり、イスラエルとハマスの戦いであって、それは本書が扱っている「21世紀の戦争」とは違う旧い型の戦争である。そうした戦争を考えるとき、本書は参考になるのだろうか。
現代の紛争や、これに関わる一般的議論では、政策が合理性を強調することで正当化を図るのは当たり前のことで、しばしば理にかなってもいる。だが、人間の生きる感情的な現実世界で共感を得られない合理的思考にばかり偏っていては、政策が過度に抽象的なアイデアを重用することを助長してしまう。戦争とは、政策が用いる血の通わぬ道具であると同時に、一つの人間的活動である。それでも現実を合理化する抽象化のプロセスは、戦争から感情的な内容を抜き取ってしまいかねない──人間が統計データに、兵士が地図上の軍事的配置図になるとき、戦争は本当にボードゲーム上の「リスク」と化してしまう(本書352頁)
本書の慧眼はここでは断片的にしかお伝えできないが、私たちがロシア式の侵略戦争に加担したり、国際法を無視し人権を踏みにじる暴力行使をよしとするのではないかぎり、武力を行使する必要のある局面で陥ってはならない過誤がなんであるかを、本書は説いている。
自分たちの直面している問題について、自由陣営諸国が自分自身をではなく、「戦争」それ自体を咎めるのはまやかしでしかない(本書350頁)