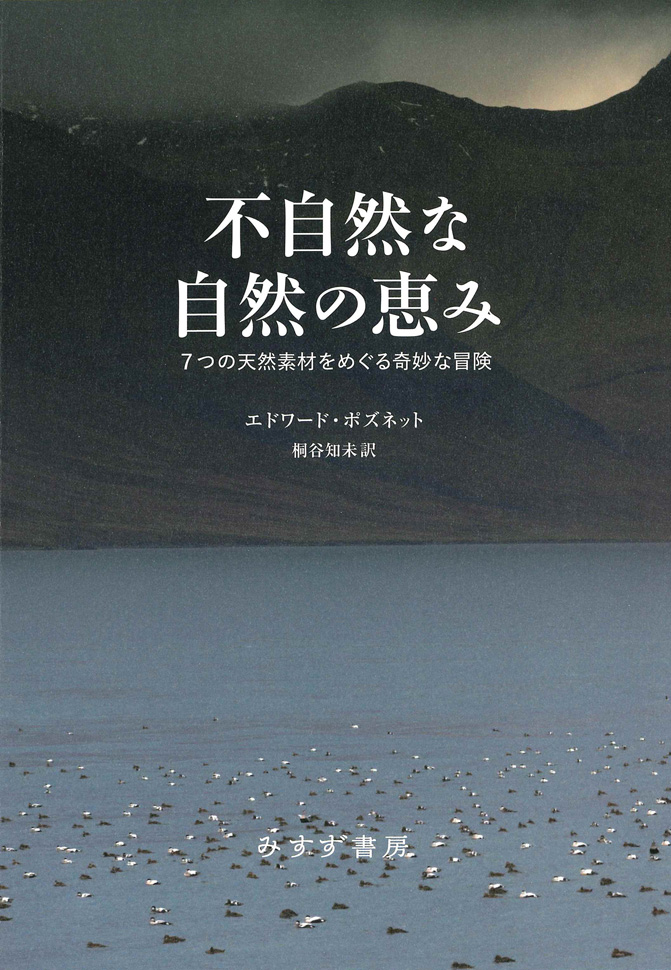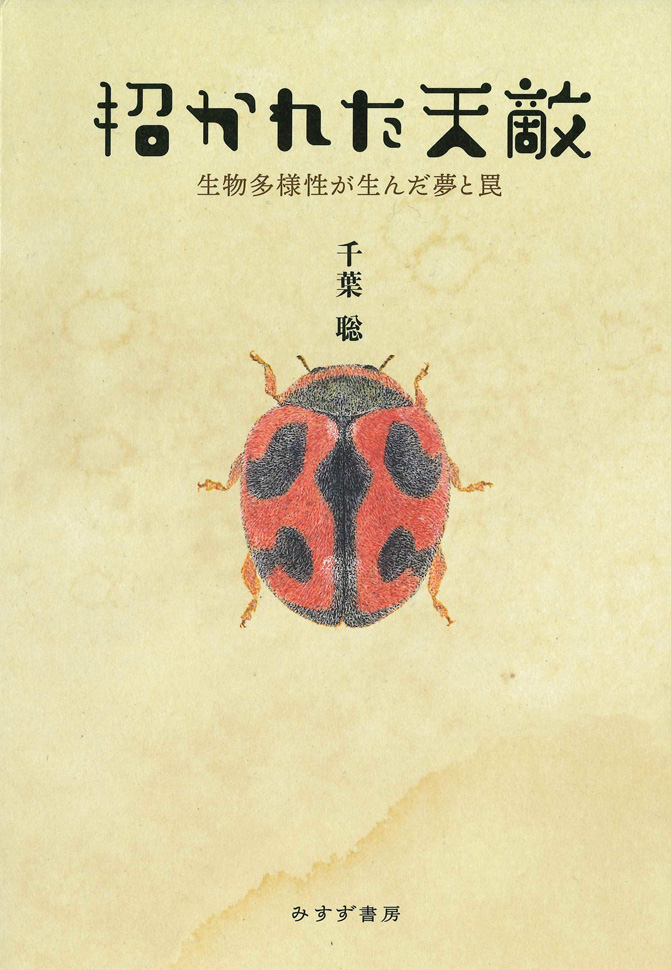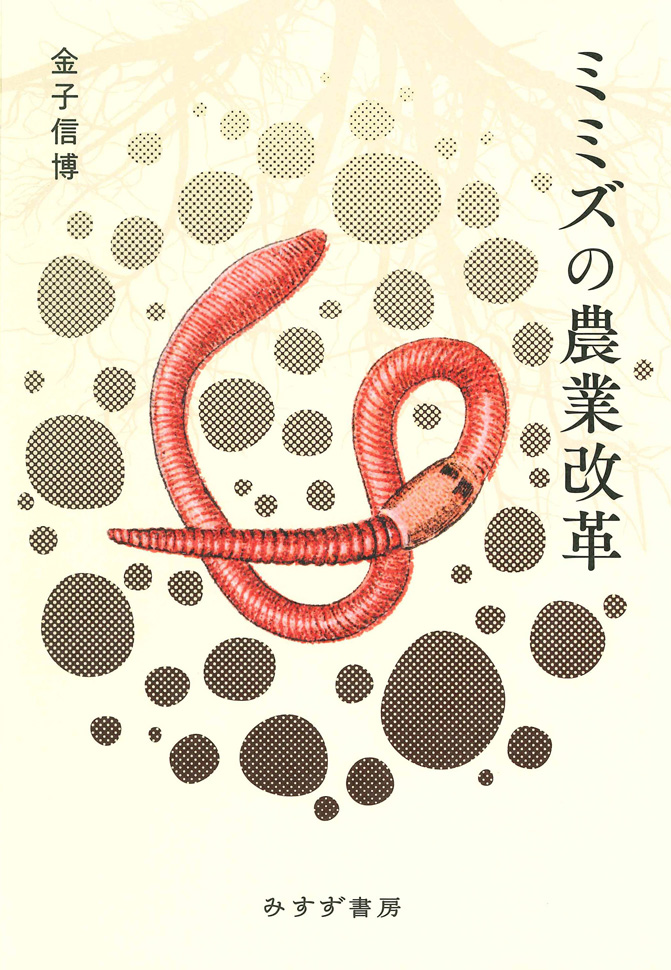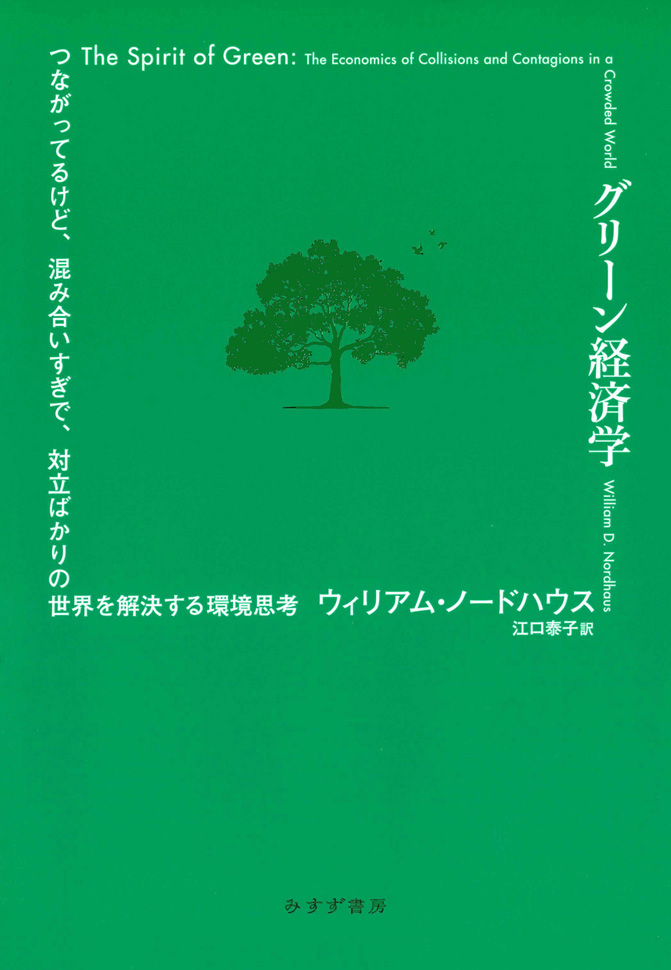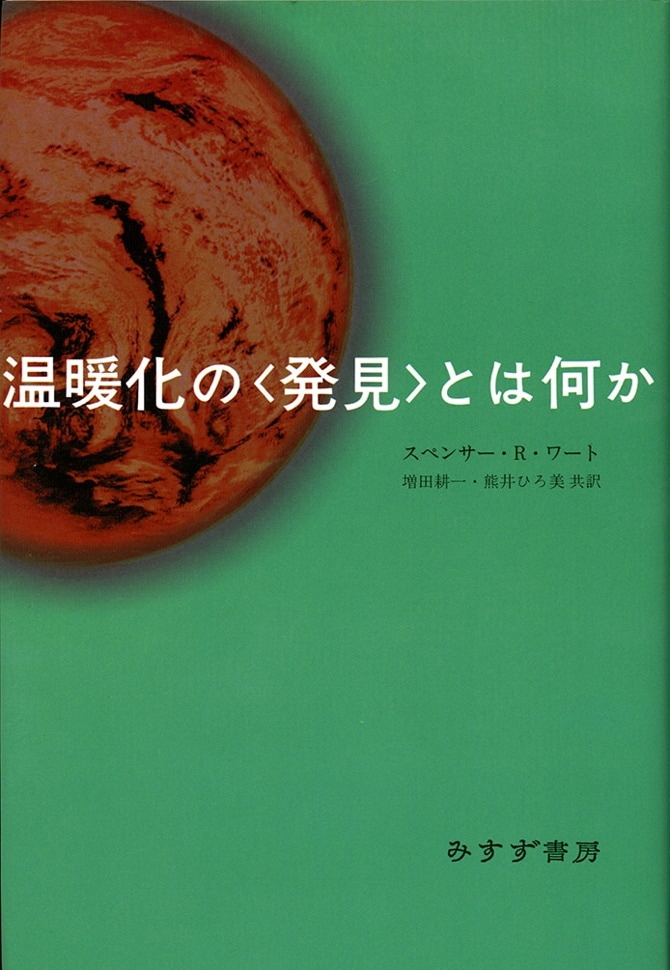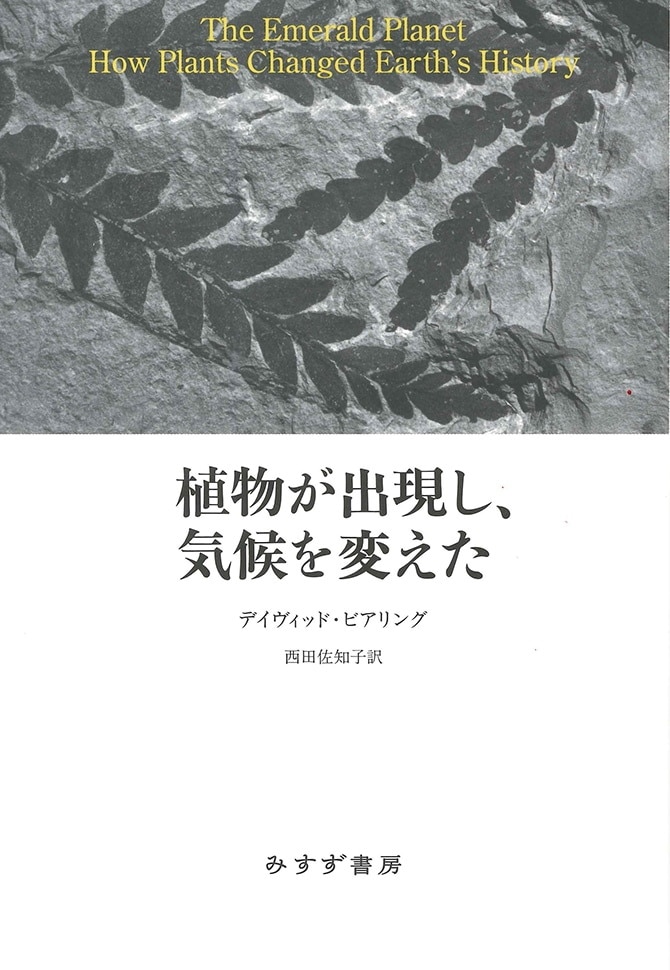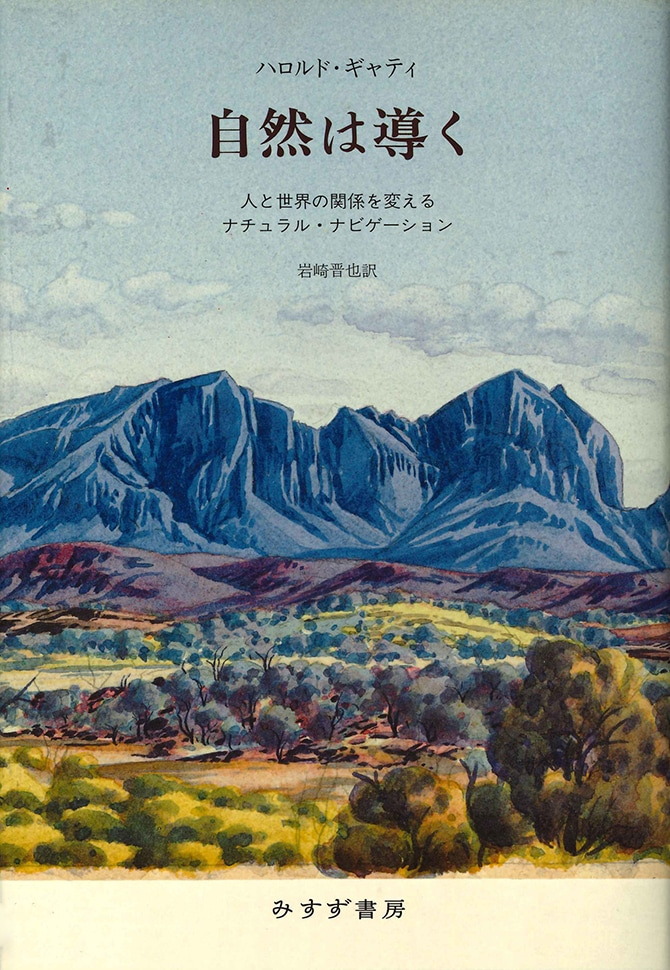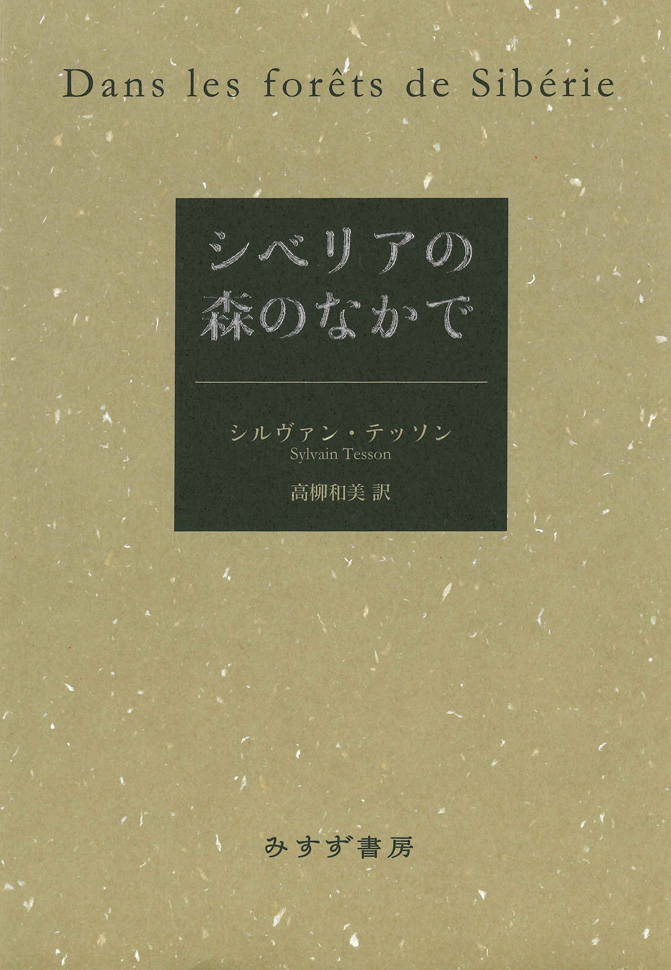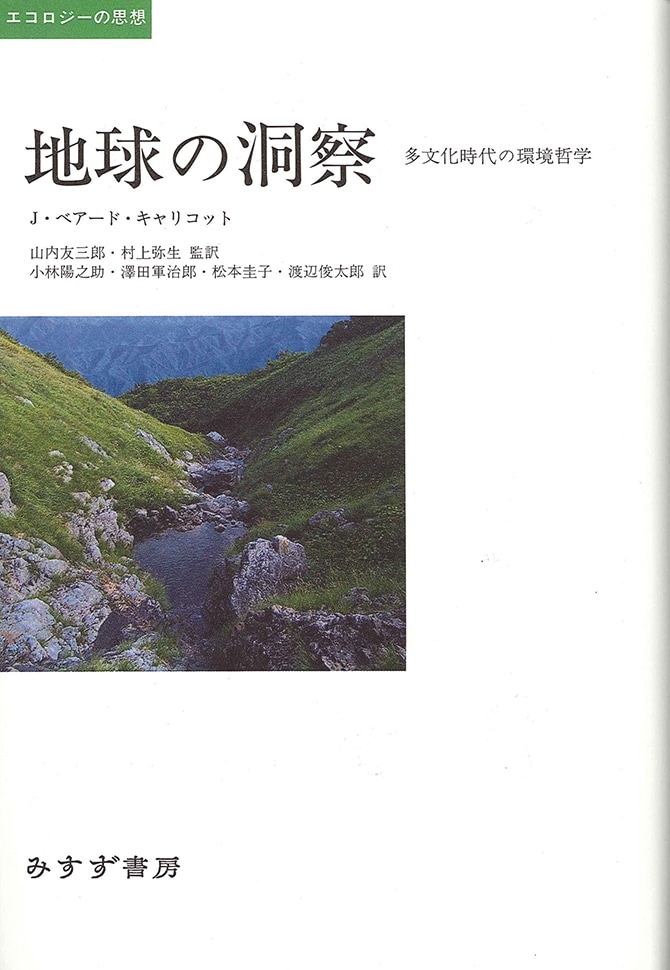驚異と秘密に満ちた7つの品々、それが本書の主役だ。アイダーダウン、アナツバメの巣、シベットコーヒー、シーシルク、ビクーニャの毛、タグア、グアノ。なじみのない、好奇心をそそる名前が並ぶ。7つの品すべてをよく知る人は稀だろう。ファッションにこだわりのある人なら、アイダーダウンのジャケットやビクーニャの毛のストールを持っているかもしれないが、シーシルクの織物をふだんから身に着けている人はさすがにいないだろう。アナツバメの巣やシベットコーヒーについては、聞いたことがある人、一度くらいは口にしたことがある人も多いかもしれない。けれど、食用の巣をつくるアナツバメが日本でよく見かけるツバメとはまったく別の鳥であることや、シベットコーヒーを生み出すジャコウネコが猫よりもハクビシンに近い動物であることを知る人は、案外少ないのではないだろうか(ちなみに訳者は、本書を読むまでどちらも知らなかった)。タグアとグアノに至っては、名前だけではどんなものかすら想像がつかないかもしれない。一般人の日常とは遠く離れた神秘的にも思える7つの希少な品が、どのように自然から生み出され、人間に求められ、加工されて取引されるようになったのかを、本書は膨大な文献の調査と、世界を飛び回る積極的な取材、誠実で的を射たインタビューで少しずつ明らかにしていく。まるで、それぞれの品の緻密な製造工程をなぞるかのように。
著者のエドワード・ポズネットは、ロンドンの金融地区カナリー・ウォーフでの仕事を辞めた直後、アイスランドの海に暮らすアイダー(ケワタガモ)の、驚くほど軽くて暖かい貴重な羽毛のことを知った。アイダーダウン農家の人たちは、アイダーを天敵から守るのと引き換えに、ひなが巣立ったあとに残る巣の羽毛を集めるのだという。異種間の共生に近い、支配ではなく協力に基づく自然界との関係に興味を覚えた著者は、アイスランドへと旅立ち、アイダーダウンの生産と取引をめぐる記録を文章にまとめた。完成したエッセイ「アイダーダウン」は、ボドリー・ヘッド社と『フィナンシャル・タイムズ』紙が主催するエッセイ賞を受賞。そのエッセイを土台に、世界じゅうに見られる希少な品々と人間の関係を追い求め、初めての著書を書き上げた。
それぞれの品を見極めようとする著者の姿勢には、いくつかの拠りどころがあるように思う。まずは、原料となる動植物と人間の関係をめぐるこれまでの伝統や歴史。そして現在、動植物と人間の共生関係は成り立っているか。採取や取引が、虐待や搾取、乱獲、個体数の減少、生息環境の破壊につながっていないか。原料の採取や生産に関わる人々の生活は豊かになっているか。
特に、著者が理想として思い描いていたのは、選んだ品々が、動植物にはなんの義務も負わせない、リスクのない関係を体現している物であることだった。しかし、採取が行われている現地に赴き、そこで起こっていることを実際に取材し、さらに詳しく文献を調査するうちに、それぞれの品に一筋縄ではいかない複雑な物語があることがわかってくる。
たとえば、理想的に思えるアイスランド人とアイダーの共生関係も、ホッキョクギツネやカラスなどの捕食動物を駆除することで成り立っていて、生態系の破壊が深刻な問題となっている。かつてはマレーシアの大洞窟を埋め尽くさんばかりだったアナツバメの巣は、中国などの輸入国で価格が高騰したせいで、乱獲され急激に数を減らした。どこにでも入り込んでくる市場の力に困惑した著者は、イタリアのサンタンティーオコ島を訪れ、千年以上前から世襲でシーシルク織りの伝統を受け継いでいるという人物に会う。彼女は市場を敵視しているが、そこには商品化の拒否によって隠されている別の種類の商品化があった。ペルーの高原に棲むラクダ科動物ビクーニャは、生きたまま毛を刈る方法で合法的に毛の採取が行われるようになって以来、絶滅が危ぶまれていた個体数も順調に増えた。しかし、成功に見える事例の裏には、政治的混乱と血みどろの紛争、共同体の苦悩の歴史が隠されていた。
また、品々の多くは一般人には手の届かない値段で売られているにもかかわらず、アイダーダウン農家で羽毛を集める人、ビクーニャの毛を刈る人、ゾウゲヤシの種子を削ってタグアのボタンをつくる人など、原料の採取者や生産者の生活は一様に貧しいままだ。それはなぜなのか?
7つの品のほとんどは、大量生産・大量消費の時代に逆行するもの、あるいはそこから取り残されたものだ。SDGsが叫ばれる現代、そのいくつかが注目を集めて広がりを見せるのも納得できる。しかしそれだけでは、森林破壊や地球温暖化、プラスチックごみなど、人類が抱える大きな問題の解決策にはならない。単純に時代をさかのぼってやり直すことがどれほどむずかしいかを、本書は教えてくれる。人間が自然を壊すことなくその恵みを享受し、先へ進むにはどうすればいいのか。大量生産された品に囲まれて生きざるをえないわたしたちも、考えなくてはならないのだと。
桐谷知未
Copyright © KIRIYA Tomomi 2023
(筆者のご同意を得て転載しています。なお、
読みやすいよう行のあきなどを加えています)