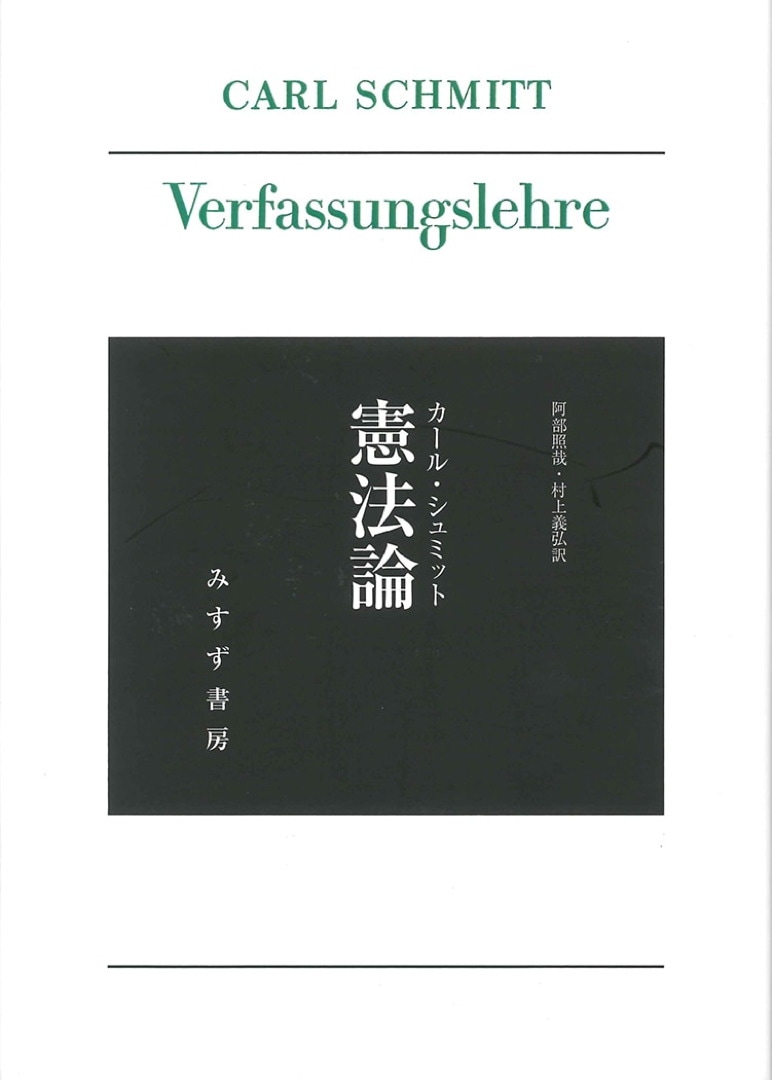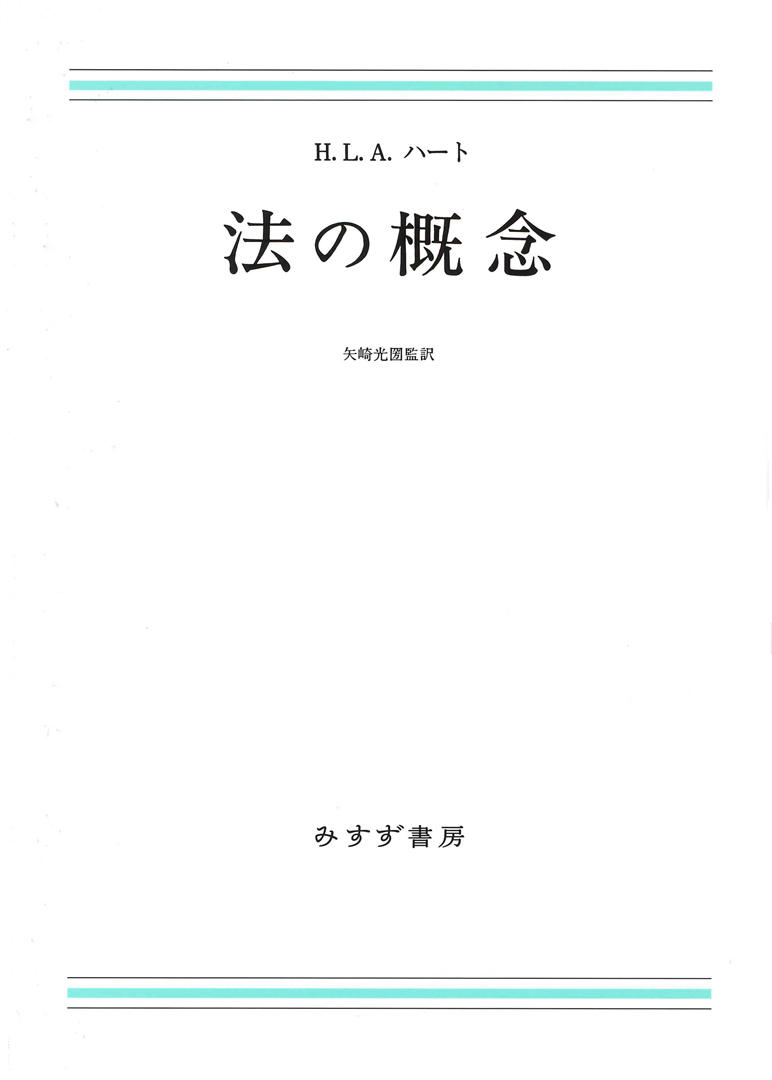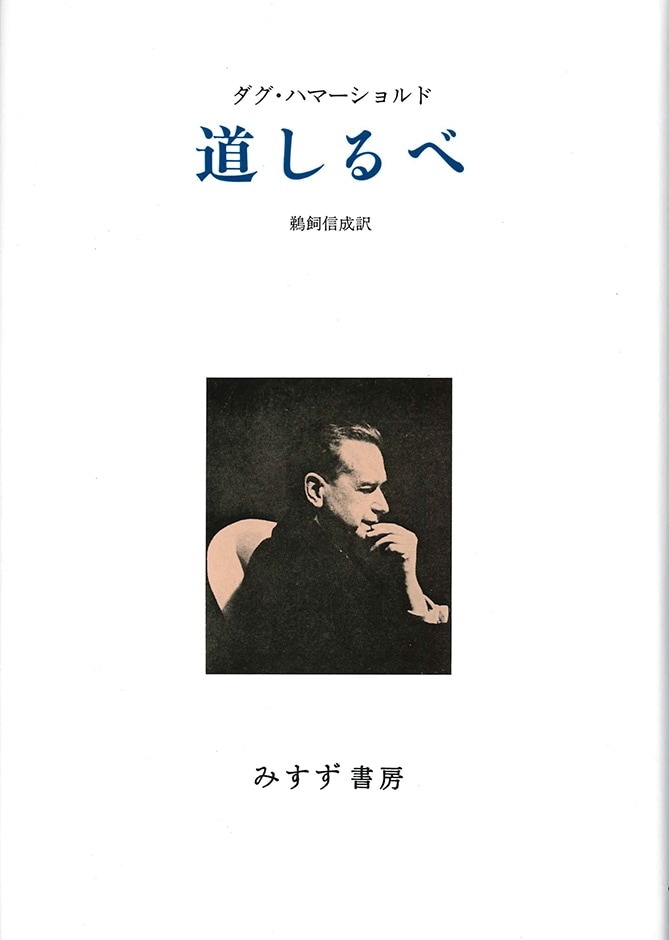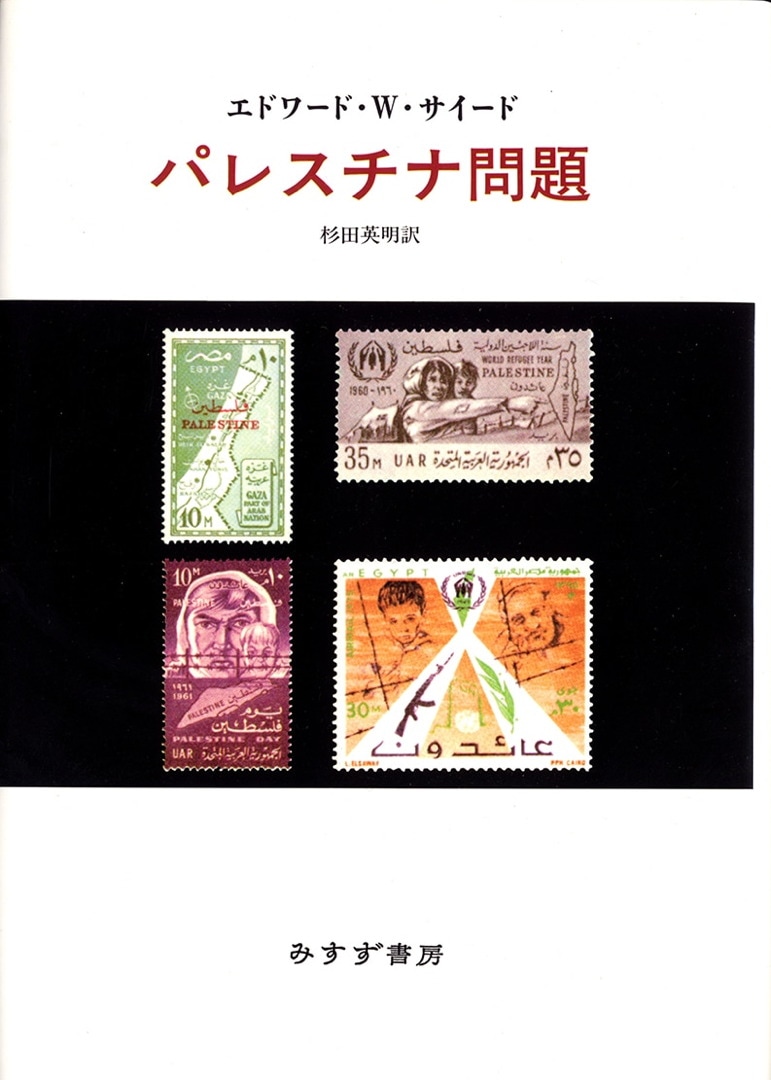本書はいわゆる国際法学者向けに書かれた本ではない。国際法の本であるならそのしきたり(「方法論」と呼ぶ国際法学者もいる)の枠の中で書かれることが必要だろう。各種条約を中心に、国際法学者によって「国際法」と呼ばれているものの紹介と解説あるいは解釈に始まり、種々の国際判例を網羅的に解説して、国際法がどのように存在し機能しているかを伝えるのである。折々、そのように確固として存在してはいるが問題点や欠点もある、と添えながら。いずれにせよ、存在の確かさを前提した上で、その一時的・局所的機能不全にも若干の言及をしつつ、「存在」するものの合理性に信を置いたまま、法解釈論としての「方法論」は守る。これはある知の体系の正統性を守るうえできわめて重要な儀礼だ。[中略]
一読して明らかなように、本書はそのしきたりに従っていない。部分的には従った個所もあるが、この狭い枠組みに自閉していてはならないというのが基本的問題意識だったから、しきたりにも安易に従うことはできなかった。それは国際法を否定する営みではない。国際法規範の存在意義(あるいは必要性)は認めつつ、現存する国際法規範は本当に実効的なのかという問いに発し、実効性に疑義があるならそれを問い直さない学問について自省する。そういう動機から本書は書かれた。
国際法は実効的かという疑問は、多くの国際法「専門家」にとって素人の素朴な疑問であるだろう。ある専門家にとって国際法はある部分で十分に実効的であり、他の専門家にとっては法学で問題にすべきではない事柄であり、さらに他の専門家にとっては、実効的か否かとは無関係に処理すべき実務的課題のほうが重要かもしれない。そのことを承知の上で本書は、その、素人の素朴な疑問から出発した。2019年の晩夏、日本の大学における最後の国際法講義の準備を、バーゼル大学ヨーロッパ国際問題研究所の自室でしていたときのことである。最後の講義だから、それまで40年近く蓄積してきた講義内容の総決算でなければならない。それは国際法が国際社会にとっていかに重要であり、それなりに機能しているかを、未来への希望も込めて語るはずの作業だった。しかし、講義録の洗い直しがどうにも進まない。いろいろ考え、それまでの講義において、常に一つの問題を封印して国際法を語ってきたことに思い至った。多くの面において国際法規範が実効的ではないという点である。実効性に疑義があるのに、「それを脇に置くならば」という変な条件をつけて、国際法はこう言っている、このように機能している、と語っていた。時には知らぬふりをして、このように機能すべきだ、とさりげなく言い添えながら。「機能している」と「機能すべきだ」とでは、全く別次元の議論である。
これで最後の講義を終えてはいけないと考えた。多くの面で実効的でない点がある、ということを真正面から扱う講義をしなければならない。とはいえ、国際法の教科書などで実効性そのものを正面から論じたり、独立の項目にしているものは、筆者の知る限りほとんど皆無である。それほどこのテーマは語ってはいけないものであり、あるいは多くの国際法学者が語ろうとさえしないものだったのか、とあらためて痛感した。[中略]
むろん原点は暴力に対抗するものとしての法規範への信頼であり、法の支配の確立を目ざす価値観である。その意味では「国際法」をぜひともよくしなければならない。問題は、「よくする」ということが何を意味するのかである。世界観の問題として、これまでも非常によく機能している・満足すべき程度には機能していると認識する立場もあるだろう。しかし、なぜ暴力や貧困や人権侵害など、これほどの国際的難題を前にして国際法は機能しないのだろうと(素人的に)疑問を抱き、それを突きつめようとするなら、まずは実効性の欠如を認めるほかない。そしてさらに、実効性を高めるにはどうするか、どうしても高める可能性がないのなら代案はないか、等々を考えることになるだろう。こうして本書の非専門家的作業が始まった。