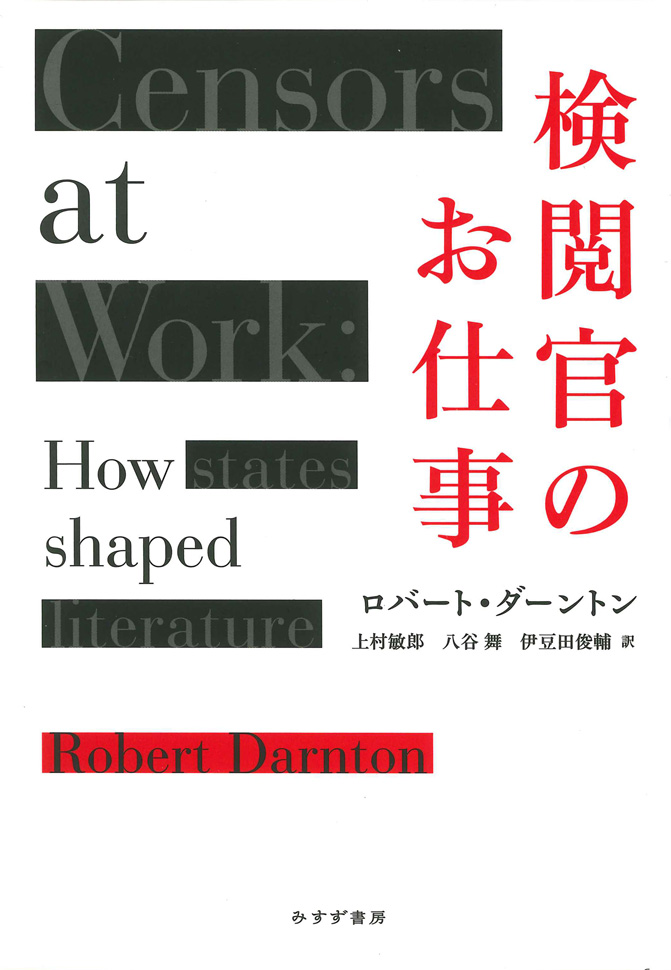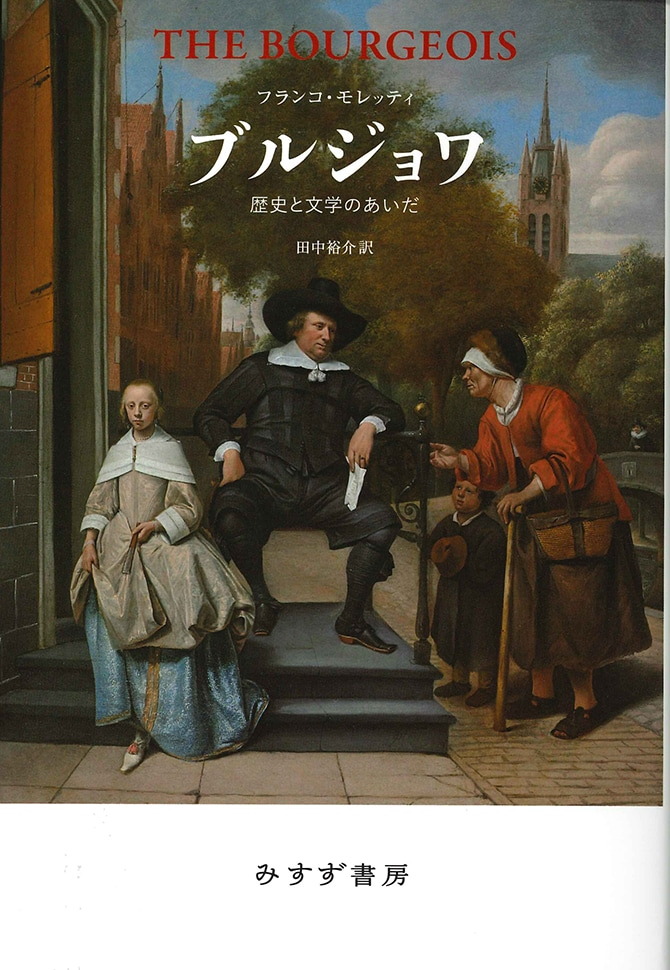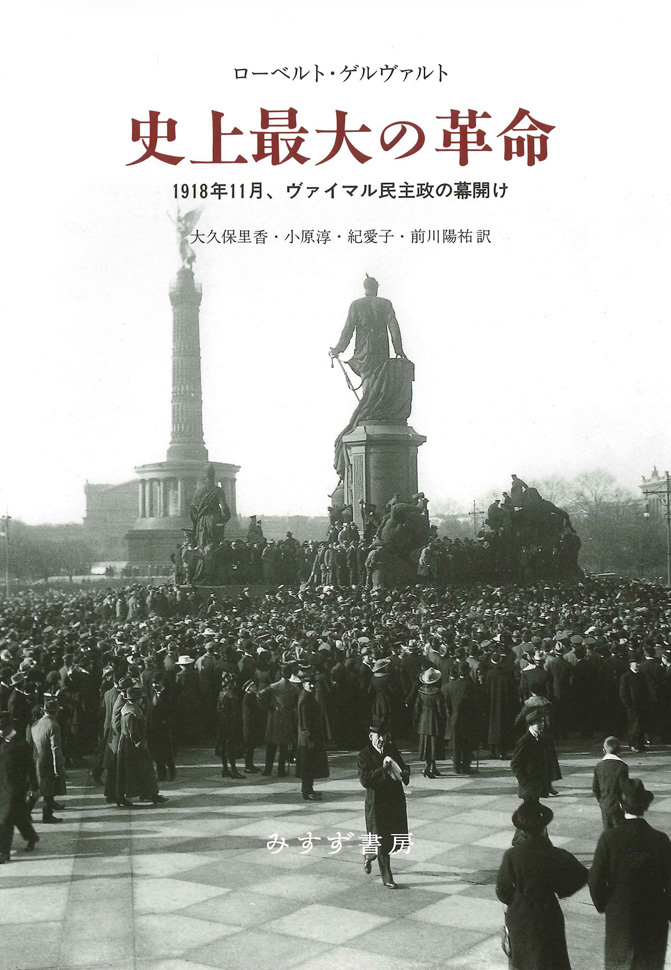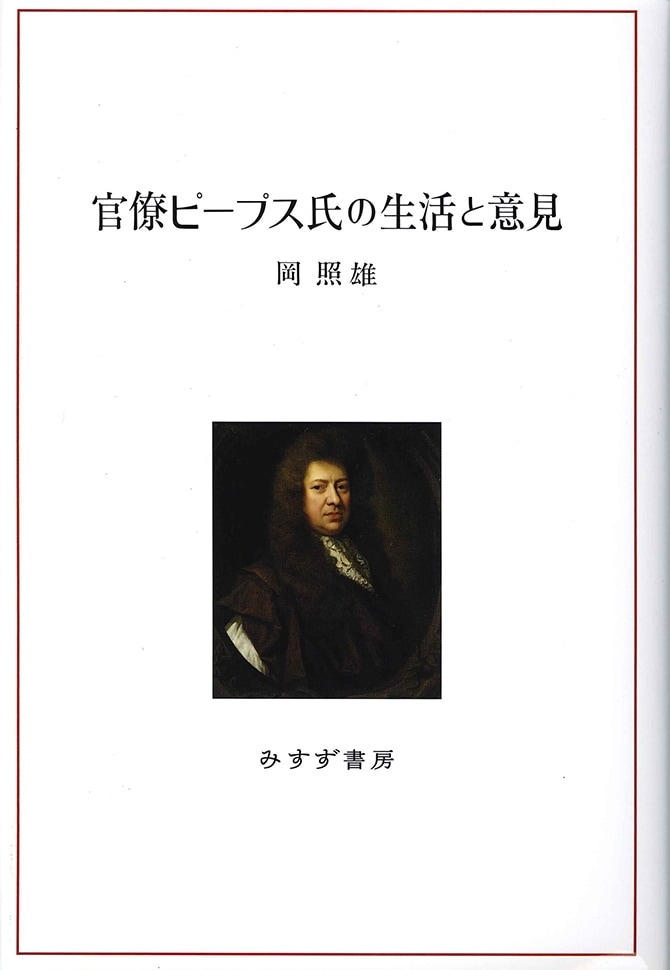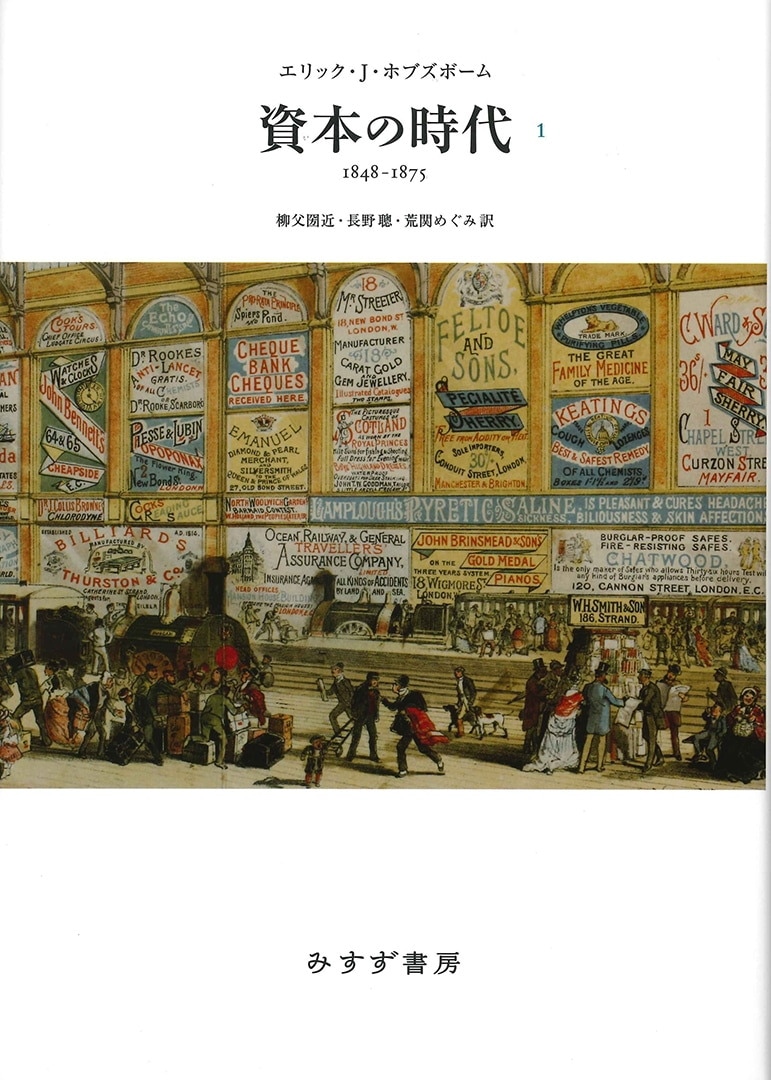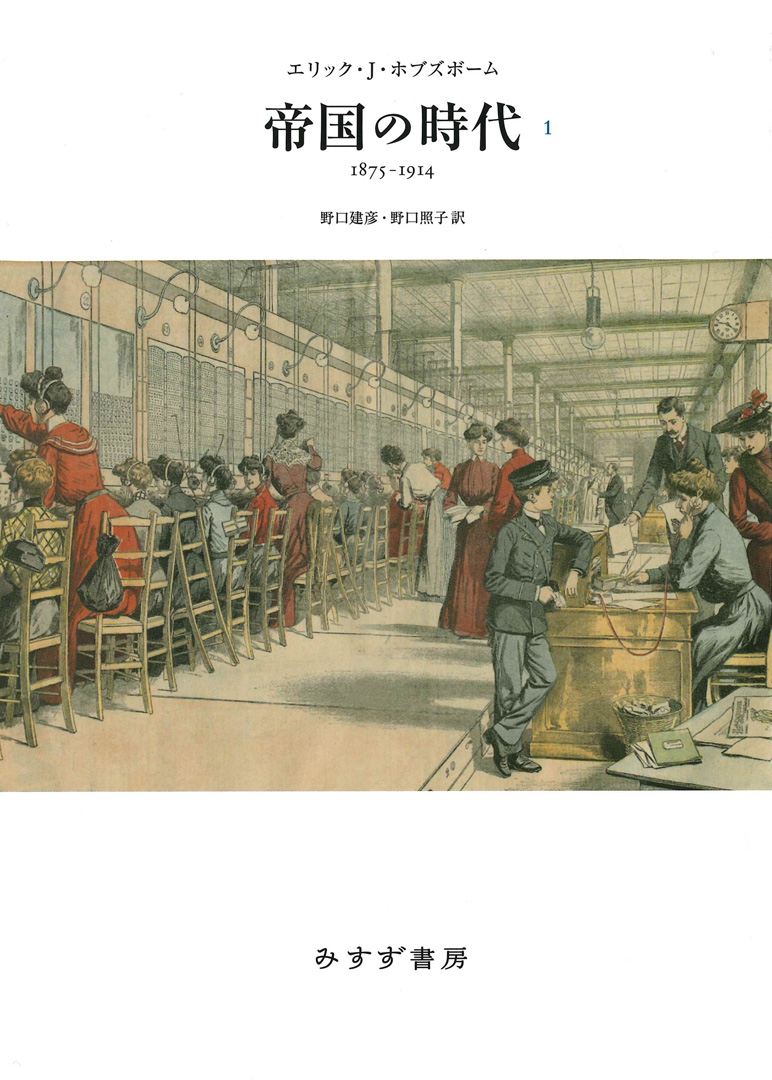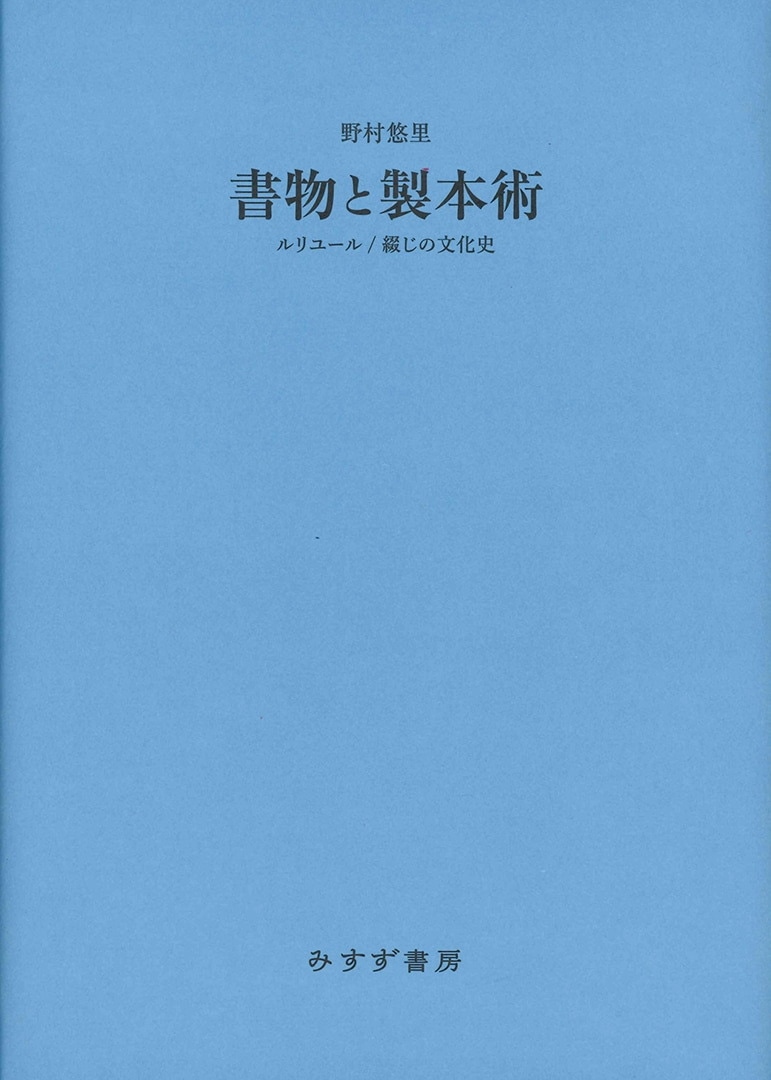本書の概要は書誌ページをごらんいただくとして、編集担当の私にとっての本書の魅力を紹介したい。その魅力とは短くまとめると、「原稿を精査するのって、いつの時代もこんな感じだったのか」という驚きと共感である。
検閲する編集者
本書の第三部・共産主義東ドイツには、共産主義国家にお定まりのイデオロギー統制があった。共産主義体制下では、すべての産業は共産党の「計画」のもとで運営されており、それは出版社も例外ではない。共産党のイデオロギー統制は、出版社――著作物という「思想又は感情を創作的に表現」するものを取り扱う組織――にも当然およぶ。したがって、出版実務を担う編集者らも検閲官としての役割を果たすことになる。どんなことをするかというと、「イデオロギー的にふさわしくない原稿」を修正するよう、著者に依頼するのだ。
こうした編集者と著者のやりとりは、本書内で「交渉」と表現されているのだが……、これがまさに私が日常的に行っている仕事とほとんど変わらないのだ! たとえば、こんな記述がある。
……編集者の職務をイデオロギーの門番に限定するのは誤解を招くだろう。彼らは原稿の芸術的質に多大な注意を払い、著者と密接に協力して言い回しを改善し、語りの強度をより高めていった。報告書を読む限り、東ドイツの編集者たちは知的で教養のある批評家であり、西ベルリンやニューヨークの編集者と共通するところが多い。編集者たちは才能を求め、原稿のために献身的に働き、最も適切な外部の査読者を選び、複雑な制作スケジュールの中でテキストを導いていった。(p. 207)
つまりはこういうことだ。東ドイツの編集者にとって、出版物が国家のイデオロギーに背くのはダメ。そのうえで、出版される作品は、質が高くないとダメだ。
では一方で、ここ日本をはじめとする現代資本主義社会の編集者ではどうか。読者がつくものでないとダメ。そのうえで、出版される作品は、質が高くないとダメだ。どうも似ている。
こんな記述もある。
ほとんどの著者は融通が利き、交渉は正真正銘のギブ・アンド・テイクであった。編集者からの提案を著者が拒否しても、編集者が譲歩することもあった。(中略)もっと多かったのは、編集者が変更を主張する際、傷つけないように、著者が気持ちよく受け入れられるように譲歩しているパターンである。(p. 209)
これは、同じ仕事に見える。この記述の近辺には、東ドイツの作家エーリヒ・レーストが後年記した手記の引用がある。レーストは編集者との「交渉」を振り返って「最後まで戦ったボクサーのように私たちは互いに尊敬の念を抱いた」(p. 222)と書いている。
編集者の仕事のやり方は実に人それぞれだが、ふつうは上記のように「交渉」をする。原稿は著者のものであるから、編集者が好き勝手に修正することは通常しない。編集者が思い描く最終形がある場合、それを実現するためにはきちんと著者にうかがって、同意を得なければならない。著者がNOと言えばそれまでだが、時には喧々諤々の議論の末に「最後まで戦ったボクサーのように」なる著者-編集者関係もあるだろう。
正式な「検閲官」も、こんなことを
ブルボン朝フランスの検閲官たち(第一部)のお仕事にも、現代社会で似た構図が見られる。驚くことに、こんな記述がある。
……ある検閲官は、『ラ・ロシェル地方の歴史』を承認したが、その退屈な文体には難色を示した。彼は原稿整理編集者のように鉛筆を持って原稿に目を通し、最も不快な箇所を削除し、著者の同意を得て書き直した。(p. 42)
検閲官といえど、原稿を修正するのにわざわざ同意を取り付けているのだ。
お仕事はときに、現代の学術雑誌の査読をする研究者の様相も呈する。もちろん検閲官たちは、王や政治体制への批判や宗教的に異端な主張を、訂正させたり、出版させない判断をしたりする。だが、「多少批判的だが論理が優れているからOK」とか「国王への賛辞の書き方が下手くそだからNG」といった判断を下すこともあった(「説得力を欠いた形で宗教を擁護することは、思わぬ形でその弱点を暴露することになるのです」p. 47)。ほかにも、検閲しなければならない原稿が多すぎて精神的に参ってしまう者や、似たような原稿が多すぎてつまらないからと、さっと表面的な注意を払って後は机に積んでおくだけだ、と述べる者も登場する(こんな論文査読者はいてほしくないが……、ありそうな話ではある)。
ここで疑問がひとつわく。同じような仕事をしているということは、現代資本主義社会の編集者や論文査読者が行っている仕事は、検閲にならないのだろうか? この点には、著者ダーントンが明確な答えを与えているから、ぜひ本を手に取って確認していただきたい。
まとめ
この記事では紹介しきれなかったが、第二部の英領インドでは法曹が検閲官の役割を果たし、そこでは「翻訳」が問題となった。ほかにも本書全体を通じて、印刷業者や書店主、図書館員なども大いに顔を出す。こんな調子で、執筆・翻訳・編集・印刷・流通まで、本にまつわるあらゆるプロセスがすみずみまで取り上げられていて、編集担当者としてはそれがいちいちおもしろかった。
ぱっと見ると本書はお堅い歴史の本に見えるし、その印象は正しい。歴史を通して「検閲とは何なのか」というむずかしい問いの答えを探すための本である。だが「検閲という現象」にかかわった一人ひとりに詳しく注目するという点では、ある種ノンフィクション小説を読むような感覚で楽しむこともできる。出版業に関わる方だけでなく、日常的に他人の文章に目を通す方など、大いに迷いながらじっくりと原稿を読むことがある方にはとくに楽しんでいただけるはずだ。
歴史学の大家ロバート・ダーントンの、検閲というひとつのテーマを対象とした歴史分析の一業績ながら、本書の記述は出版文化の全体像も見せてくれる。氏の業績をふくむさまざまな情報については、訳者の一人、上村敏郎教授(獨協大学)による本書巻末の解説をご参照いただきたい。
本記事の内容は、担当者の一感想にすぎません。読者の皆様には、本を実際に手に取って、私の気付いていない他の魅力をたくさん見出していただき、本に挟んである読者カードのはがきでお知らせくだされば、私どもにとってはこの上ない喜びです。『検閲官のお仕事』を、なにとぞよろしくお願いいたします。