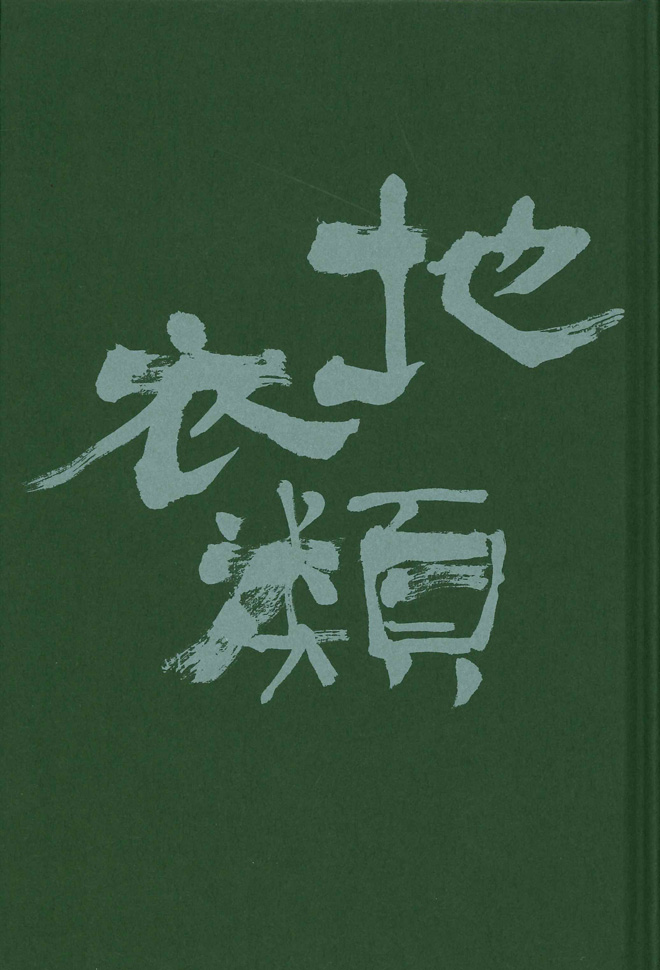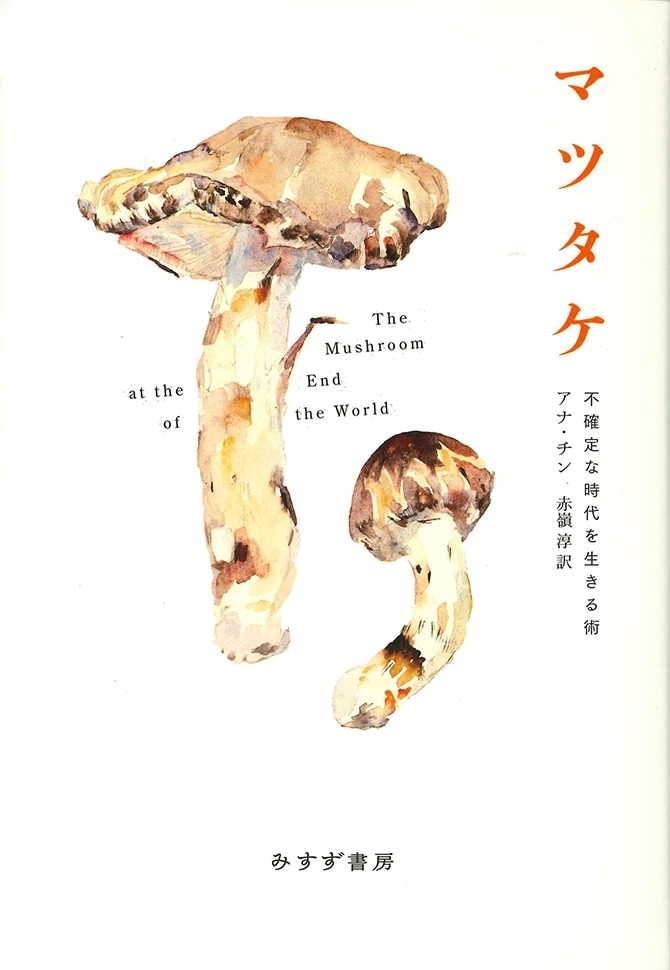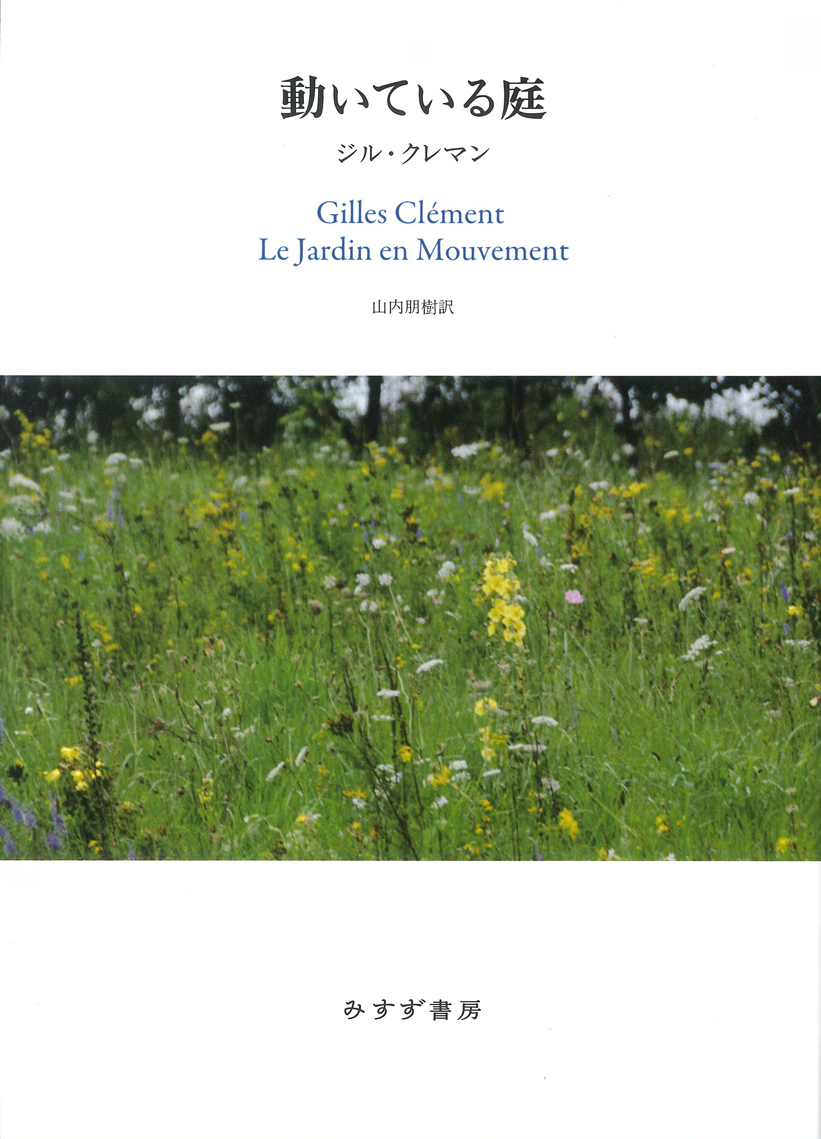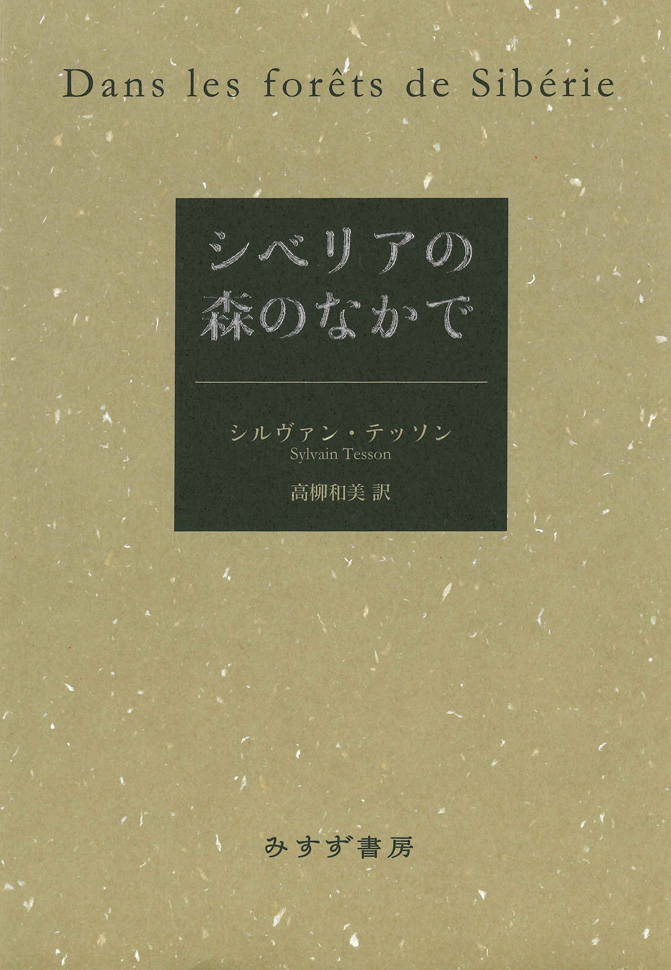大村嘉人(国立科学博物館)
科学に携わる私にとって、文学は別世界である。もちろん、研究結果をまとめて公表するために論文を書いたり、エッセイを書いたりするので、広い意味での文学に少しは関わっている。しかしながら、文学=文芸と言われるように、文学は言語による芸術作品だ。その表現方法は、詩、小説、散文、戯曲、哲学など多種多様であり、科学の世界で慣れ親しんでいる文章とは異なるために、それらの世界を理解することが時に困難であることもある。
『地衣類、ミニマルな抵抗』の著者であるヴァンサン・ゾンカ氏は、「地衣類」をキーワードとして、そのような別世界を繋ごうという挑戦的な試みをしている。ゾンカ氏は、フランスのリヨン高等師範学校で比較文学と哲学に関する分野での博士号を取得した後、スイス・ジュネーヴの高校で文学を教える教員であった。学校現場であれば、ふとしたことで地衣類を知る機会があったことは想像できる。知人の紹介で、ジュネーヴ研究植物園のフィリップ・クレール博士に出会い、地衣類の奥深い世界へと入り込んでいったようである。ジュネーヴ研究植物園を訪れた際に、そこで見聞きした地衣類に関する話や標本に対する驚きが、本書の中心的な部分を構成していることが読み取れる。高校教員の仕事を離れた後、ゾンカ氏はブラジルのフランス大使館へと転職された。
そこでの仕事は、ブラジルの文化とフランスの文化をつなぐことであった。ゾンカ氏のSNSのプロフィールには「カルチャー・マネージャー」と自己紹介がある。なるほど、と思った。本書では、「地衣類」を素材にした文学やアートの情報がかなり幅広く拾い集められている。それらの多くはインターネット上から約3年の歳月を経て収集したものだそうだ。そして得られた情報を元にゾンカ氏は行動した。科学や芸術分野で活躍する世界各地の人たちに連絡を取り、現地を訪れ、自分の目と耳、肌でそれらの文化を感じ取ろうとしたのだ。
フランス語で書かれたオリジナル版(2021年)は英語版(2022年)へと翻訳され、そして今回の日本語版へと翻訳が行われた。オリジナル版が出版される前の2020年3月にゾンカ氏から私にEメールが届き、「執筆中の本のうちのある章は、日本における地衣類の表現と考え方(科学、絵画、詩など)に特化したもので、これらの関係をよりよく理解するためには、現地への旅が不可欠だと思われる」と来日を切望していたが、あいにくのコロナ禍のために、ブラジルから日本への渡航が不可能となってしまった。
日本語版の出版準備が着々と進む2023年、記録的な猛暑の夏にようやくゾンカ氏と面会した。東京滞在中の彼に、地衣類と日本らしい風景を短い時間で同時に見せてあげたいと思った。そのような場所と言えば真っ先に頭に浮かぶのは皇居である。皇居には江戸城跡の見応えのある石垣やお濠、城門、庭園などがあり、そして何よりも都心で最も多様な地衣類が報告されているうってつけの場所でもあるからだ。
待ち合わせをした大手町駅で、スラリとした若者が近づいてきた。哲学や文学を専門としているのでどこか気難しい面をお持ちの方なのではないか、という先入観や偏見も少しばかりあったが杞憂に終わった。日本でも見かけるような控えめな印象の若者と気さくに会話を弾ませながら皇居に向かって歩き始めた。午後2時の最も暑い時間に外を歩かせることになり申し訳ないと思ったが、緑豊かな皇居の東御苑や北の丸公園には木陰が多いために、さほど暑さを感じることもなく、心地よく地衣類を見て回る時間となった。
「なぜ、あなたは地衣類の本を書こうと思ったのですか?」と私は尋ねた。
「都会という場所であっても、私たちは自然の中にいることを伝えたかったのです。多くの人々にとって〈自然〉は都市圏の外、すなわち田舎の里山や海、山岳地域にあるもので、それらの場所へ出かけて行くことで〈自然〉に出合えると考えがちです。しかし、そうではありません。ほら、今ここに地衣類があるではないですか! 地衣類の存在を知ることは、都市部であっても、私たちがいる場所が〈自然〉の中であると知ることに繋がるのです。」
都市部というと、自然から切り離された人間が活動をするための場所であると、多くの人々が思っているだろう。また、都市部における動物、昆虫、植物などの生物は、人によって管理され、家の中や飼育箱、庭やプランターの中で育てられるべきものと考えている人も少なくない。それらの人々にとっての〈自然〉の中でしか見たことがない生物が都市部で見つかると、しばしば騒動になることもあるようだ。一方で、都市部で観賞用に育てていた植物が、いつの間にか道端で雑草化し、やがては在来種を駆逐するような特定外来種になってしまうケースも見受けられる。
しかし自然は連続的であり、境界線できれいに区切れるものではない。適切な環境があればそこに定着できるのであって、人間の都合は関係ないのである。都市部と郊外、人間活動と自然、それらは地衣類を通して見てみれば、すべて〈自然〉の中でのエコロジーなのだろう。
私はゾンカ氏の話に頷きながら、こちらからは、皇居の地衣類が人間活動の変化とともにどのように変わったのかを説明した。高度経済成長期以降の日本の都市部や工業地域では、深刻な大気汚染により、それらの地域では地衣類の多様性が著しく衰退していた。大気汚染がかなり改善した1995-1996年に実施された皇居内の地衣類は57種があることが報告されたが、2009-2013年に行った調査では98種にまで大幅に増加した。この間、2003年に首都圏で始まったディーゼル車規制により、都市部の大気環境は著しく改善した。かつての東京ではスモッグのために見える機会が少なかった富士山も、ディーゼル車規制後には日常的にその姿を見ることができるようになった。この大気汚染改善によって、皇居における地衣類の多様性や量的な回復が起こったものと考えられ、都市環境の他の地域でも同様の現象が確認されている。
「都市部に地衣類が戻ってきた!」本来のあるべき自然の姿が回復して喜ばしいはずだった。しかし、20世紀の大気汚染時代に生まれ育った大人たちは、街路樹や公園の樹木のイメージはツルリとした「きれいな」樹皮であり、地衣類がないことが当たり前であった。21世紀の大気汚染改善に伴って、街路樹上に増えてきた地衣類を見て「カビみたいな苔のような変なものがついている」、「木を枯らしているのではないか? 除去して欲しい」という声も聞かれるようになった。それらの苦情には科学的根拠はない。地衣類は木の表面を着生するための場所として利用しているだけであり、呼吸ができなくなるような密閉性もない。また、共生体である地衣類は自前で栄養を作り出しており、木から養分を吸収して枯らすこともない。
「そういうことだ」と言わんばかりの少し微笑んだ表情で、ゾンカ氏は黙って私の話を聞いていた。地衣類は自然の中に存在しており、人間活動の影響を受けて消長が起こる。「知らない」ということは、ものの見方を一変させてしまうのだ。地衣類を見て、「ここは空気がきれいな場所なのですね」と思う人もいれば、「気持ち悪い、木を枯らすのではないか?」と思う人もいる。本来の清浄な環境であれば、地衣類はそこに存在する。地味ではあるが、いにしえより花鳥風月の日本画にも描かれている雅な存在なのである。断片的な印象で誤解してしまうのは残念なことである。異なる文化の世界を繋げれば、新たな理解や正しい見方が生み出される。ゾンカ氏は「カルチャー・マネージャー」として、地衣類によってその創造への扉を開けることに挑戦したかったのではないだろうか。
ゾンカ氏は、東京で私と会った後、日本のアーティストや庭園師、コケの研究者など、様々な分野の専門家たちと面会し、交流を重ねたらしい。京都、屋久島、宮崎など巡り、苔寺や古い街並みの路地裏の何気ない風景、野山などの写真をSNSにアップしていた。それらの写真は、日本の古き良き時代の「侘び寂び」や「静寂」が切り出されているように見て取れた。もしコロナ禍がなく、彼がオリジナルのフランス語版を執筆する前に日本を訪れることができていたら、地衣類を通じた視点から描き出される日本文化の美意識や感覚をさらに鮮やかに表現されたことだろう。その可能性を思うと、ある種の残念さを感じずにはいられない。(2023年8月記)
Copyright © OHMURA Yoshihito 2023