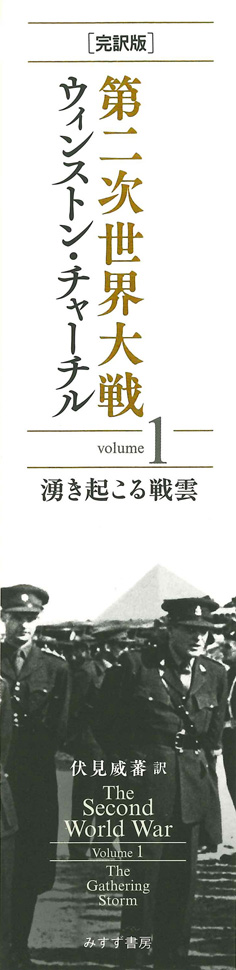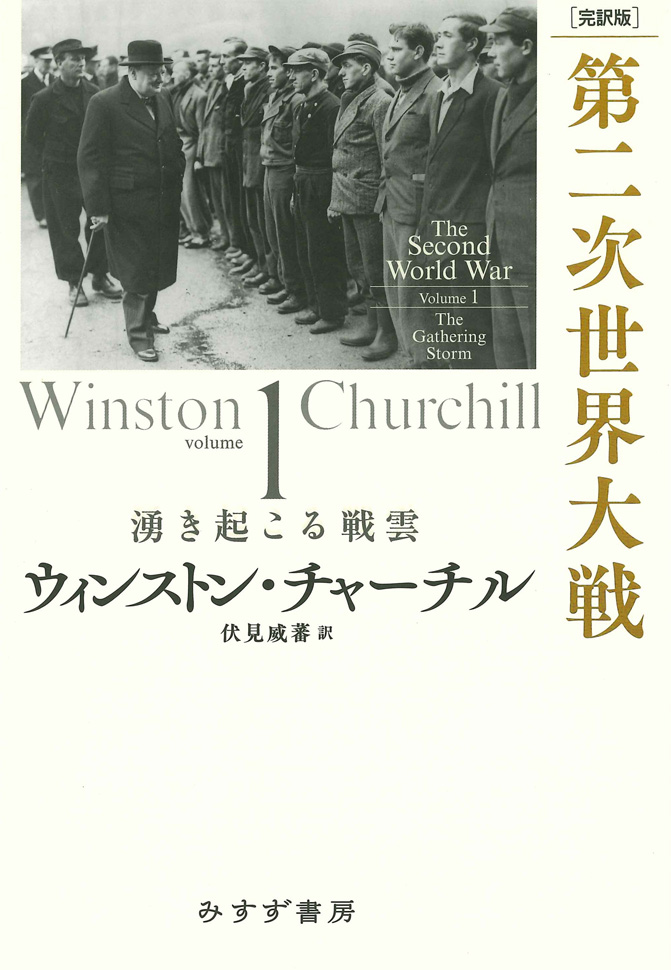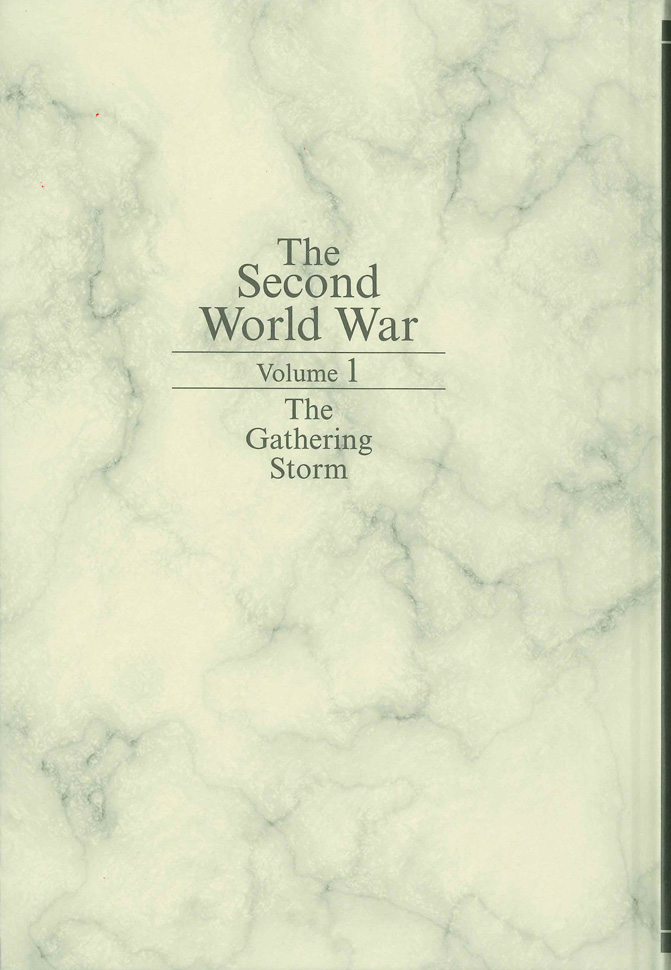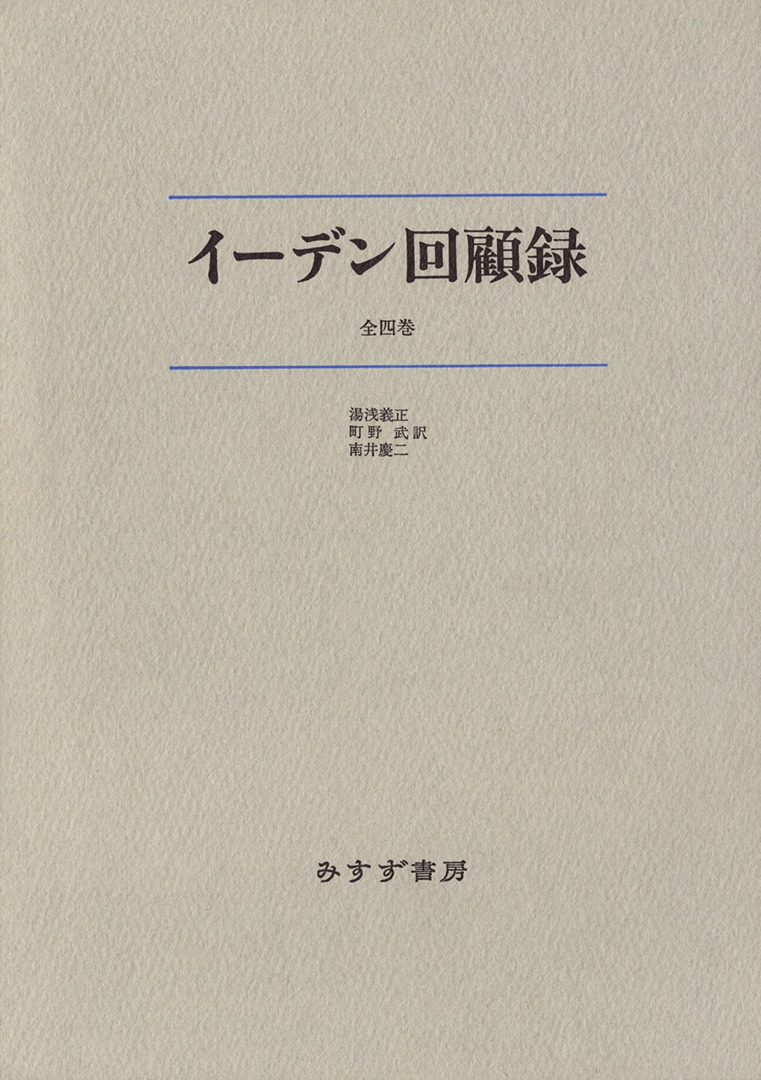大戦後間もない1948年から54年にかけて原著が刊行され、政治家チャーチルが1953年にノーベル文学賞を受賞するきっかけとなった全6巻の全面新訳となる『[完訳版]第二次世界大戦』。戦争前史から大戦勃発をへて首相となるまでを描く本書の第1巻『湧き起こる戦雲』から、一部を先行してお届けします。
序文
(全文)
『第二次世界大戦』全6巻を、私は『世界の危機』『東部戦線』『戦後』などで描いた第一次世界大戦の物語の続編と見なしたいと思う。現在の作業が完成したなら、それらと併せて第二の三十年戦争の記述となるはずである。
これまでの巻とおなじように、私はできるだけデフォーのMemoirs of a Cavalierの手法に従った。そこでは作者が、大規模な軍事・政治事件の年代記と論議を、一個人のみずからの体験という細い糸で吊るしている。行政府の一員として史上最大の激動を二度とも経験した人間は、私しかいないかもしれない。第一次世界大戦ではいくらか下位の役職で責任を担っていたのに対し、二度目にドイツを相手どった5年以上におよぶ長期戦では、英国政府の首班だった。それゆえに、前作とは異なる観点から、より明確な権威をもって述べている。
私の公務のほとんどすべてが、秘書官の口述筆記によって処理されていた。総理大臣の任期中に、私は合計100万語近い非公式文書、公式命令、電報による私信、覚書を発した。それらの文書は、そのときの出来事の重圧を受けながら、その時点の知識をもとに書かれたものなので、不備が多々あるに違いない。それでも、すべてをひとまとめにして考えれば、大英帝国および英連邦諸国(コモンウェルス)の戦争と政策に主な責任を負っていた人物がそれらの途方もない出来事をどう見なしていたかを、当時の視点から説明しているはずである。戦争と政権運営をこれとおなじように日々記録したものが、ほかに存在するとは思えない。これは前代未聞の記録なのである。私はこれを歴史として書き表わすことはしない。それはのちの世代がやることだからだ。しかし、これは未来に役立つ歴史への一助になると、確信をこめて申しあげたい。
30年間のこれらの行動と弁論は、私の一生を懸けた努力の賜物であり、私が心血を注いだ証左なので、評価は甘んじて受ける。私は、自分が事前に公に、もしくは正式に、意見や警告を述べていなかった場合には、戦争や政治のどんな方策も断じて事後に批判しないという方針を貫いてきた。また、当然のこととはいえ、当時を省みて、激しく論争した問題の多くについて論調を和らげるよう心がけた。自分が敬愛している多くの人々との意見の相違を書き記すのはつらいが、過去の教訓を未来に示さないのは正しくない。また、自分が公務をどれほど果たしているかを省察せずに、本書に行動を記録されている高潔な善意の人々を見下してはならない。それよりも過去の教訓を未来の自分の行動に応用すべきだ。
私の述べることにすべての人々が賛成すると期待してはならないし、いわんや受けがいいようなことだけを書くのは許されない。私はみずからの善悪の判断に基づいて証言を行なう。事実を検証するために、あらゆる注意を払う。しかし、押収された書類やそのほかの驚くべき発見が公開され、新事実がたえず明らかになっているから、私が導き出した結論はあらたな様相を呈するかもしれない。だからこそ、当時の真正な記録や、あらゆることが明確ではなかった時期に示された意見を拠り所にすることが重要なのである。
ある日、ローズヴェルト大統領が、この戦争をどう呼ぶべきか、公に提案を求められたと、私にいった。私は即座に〝不必要な戦争〞だと答えた。前回の長期戦によって甚大な損害を受けていた世界を破壊し尽くしたこの戦争は、どんな戦争よりも容易に阻止できたはずだった。数億人が苦難と犠牲を強いられ、正当な大義が勝利を収めたあとも、平和や安全保障を確保できず、せっかく乗り越えた危機よりもさらにひどい危機の罠にはまったとき、人類の悲劇は頂点に達した。過去について熟慮することが、今後の歳月の指針となり、新しい世代が何十年も前の過ちを修復して、人間がほんとうに必要とする物事と栄華に則り、未来におぞましい光景がくりひろげられるのを抑制することを、私は心の底から願っている。
ウィンストン・スペンサー・チャーチル
ケント州
ウェスタラム
チャートウェルにて
1943年3月
本文より
避けられた悲劇
この時代に生き、行動したひとりとして、第二次世界大戦の悲劇は容易に避けられたはずだということを示すのが、私の目的なのだ。善人の弱さによって佞悪なやからの敵意が強化された。民主的な国々の構造と体質は、より大きな機構によって結合されないと、粘り強さと信念という要素に欠けていた。それがあれば、一般大衆に安全保障を提供できていたはずだった。たとえ自己防衛のためでも、10年か15年つづけられた政策はひとつもなかった。慎重で節度のある助言が、生死に関わる危険の主因になりうることを、私たちは悟らなければならない。安穏な暮らしを望んで中道を歩むと、一直線に災難に跳び込むおそれがある。数多くの国が、国家政策の潮流とは無関係に共同で幅広い国際的な行動を起こすことが不可欠なのだと、私たちは悟らなければならない。(第1章、18頁)
日英同盟の終焉(1923年)
アメリカはイギリスに、日本が几帳面に守ってきた日英同盟の継続は米英関係を阻害すると明言した。それにより、日英同盟は終焉した。この同盟破棄は日本国内に深甚な影響を及ぼし、アジアの勢力が欧米世界に冷淡に捨てられたと解釈された。〔中略〕その反面、ドイツとロシアの凋落によって自国の海軍力が一時的に世界第3位になり、いずれ最大勢力になれるだろうという事実に、日本は元気づけられていたかもしれない。〔中略〕日本は、米英が自分たちの資源を節約し、二大国の責任を果たすのにじゅうぶんな軍備を整えていないことを、注意深く見守っていた。戦争に勝った連合国が平和という建前で急遽創りあげた状況は、こうしてヨーロッパとアジアの両方で戦争が再燃する道を拓いた。(第1章、14-15頁)
新兵器の開発
1925年に私は早くも、ある技術的な問題について考え、調査した。いまそれに触れないのは間違っているだろう。
以前の物とは比較にならないくらい強烈な爆発エネルギーを使用する手段が発見されないといい切れるだろうか? 一街区の建物すべてを破壊する秘密の力を備えたオレンジほどの大きさの爆弾──無煙爆薬1000トンの威力を凝縮し、一発で町ひとつを爆破できるような爆弾──が発見されないといい切れるだろうか? 既存の爆発物を空飛ぶ機械に積んで、人間の操縦士が乗らず、無線か光線で自動的に誘導し、敵国の都市、武器庫、陣営、造船所を絶え間なく精密に爆撃できないだろうか?
毒ガスとあらゆる形の化学戦については、まだ恐怖の物語の第一章しか書かれていない。この新しい破壊手段すべてが、人間の持てる限りの科学と忍耐を注ぎ込んでライン川の両側で研究されていたことはたしかだった。それらの資源の利用を無機化学のみに限定しなければならない理由がどこにあるだろう? 疾病の研究──伝染病を組織的に準備して、人間や動物に故意に感染させるというようなこと──は、複数の大国の研究室で行なわれているはずだ。穀物を枯らす病害、馬や牛を殺す炭疽病、軍隊だけではなく地域の住民すべてを害する伝染病──軍事科学のこういった路線は、容赦なく進歩している。これらはすべて、25年ほど前の技術にすぎない。(第3章、44-45頁)
戦勝国の務め
戦勝国には、打ち負かした敵国に非武装をつづけさせる責任がある。そのために、ふたつの要素から成る政策をとらなければならない。まず、自国の武装を存分に維持し、監視を怠らず、威光を放って、かつての敵国の軍事力復活を禁じる条約の条項を執行する。つぎに、敗戦国が和解してその地位に甘んじるように、あらゆる方策を講じる。温情溢れる行為によって、打ちのめされた国がおおいに繁栄するようにする。労力を厭わずに、ほんものの友好関係と共通の利害の基盤を創り、武装を欲しがる動機がしだいに消えるように仕向ける。その時期、私は格言をこしらえた。〝戦勝国の軍縮よりも、敗戦国の不満の種を除くことを優先すべきだ〞。(第3章、45頁)
ヒトラーとのニアミス(1932年夏)
ミュンヘンのレジーナ・ホテルで、私の連れの何人かに、ひとりの紳士が自己紹介をした。ハンフシュテングルという人物で、親しくしているらしい〝指導者(デル・フューラー)〞のことをずいぶん持ちあげた。快活で話好きな男のようで、英語に堪能だったので、私は彼を食事に招いた。ハンフシュテングルは、ヒトラーの活動や考え方について、かなり興味深い話をした。まるで魔術にかけられているような話しぶりだった。きっと私と接触するよう命じられていたに違いない。明らかに取り入ろうとしていた。食事のあと、ハンフシュテングルはピアノのところへ行って、びっくりするような技巧で何曲も演奏したり歌ったりしたので、私たちはみんなたいそう楽しい思いをした。私が好きなイギリスの曲を、彼はすべて知っているようだった。ハンフシュテングルは演芸に優れていて、当時、ヒトラーに気に入られていたことが知られていた。ヒトラーに会うべきだし、簡単に引き合わせることができると、ハンフシュテングルがいった。ヘル・ヒトラーは毎日午後5時にホテルに来るし、もちろんあなたにぜひ会いたいと思っています。
私にはこの時期のヒトラーに対して、イギリス人として含むところはなかった。彼の思想体系や経歴のことをほとんど知らず、人品についてはなにも知らなかった。私は戦勝国の側だったが、打ちのめされた国のために立ちあがる男たちを尊敬していた。ヒトラーが望むなら愛国的なドイツ人になる権利がじゅうぶんにある。私は常々、イギリス、ドイツ、フランスが友好的になればいいと思っていた。しかし、ハンフシュテングルと話をしているときに、私はたまたま口にした。『あなたの指導者はどうしてユダヤ人に暴力的なのですか? 悪行をなしたり、国に逆らったりするユダヤ人に対して怒るのは、よくわかります。彼らがなんらかの職業で独占的な力を握ろうとしたときに対抗するのも理解できますが、ユダヤ人に生まれたというだけで敵視するのは、理屈に合わない。だれだって生まれはどうにもできませんからね』。ハンフシュテングルが、それをヒトラーに伝えたに違いない。翌日の正午ごろに重苦しい態度でやってきて、きょう指導者(デル・フューラー)はホテルに来ないので、私との会見の約束を取り付けられなかったといった。私たちはそれからも数日、滞在していたが、〝小男(プッチ)〞──それがハンフシュテングルの綽名だった──の姿を見たのは、それが最後になった。こうしてヒトラーは私と会うたった一度の機会を逸した。その後、ヒトラーが強大な力を握ってから、何度か招待を受けた。だが、そのころにはさまざまな出来事が起きていたので、私は断った。(第5章、89-90頁)
ミュンヘン会談を受けて(1938年9月)
理解しづらい困難な問題に単純明快な解決策を求めようとする気質と性格が強く、外国が対抗してきたときにはつねに戦おうとする人間が、つねに正しかったとは限らない。いっぽう、頭を下げて、辛抱強く誠実に平和的な妥協を求める傾向がある人間が、つねに間違っているとは限らない。むしろその逆で、多くの場合、そういう人間は道徳的に正しいだけではなく、現実的な面でも正しいかもしれない。忍耐と揺るがぬ親善によって、幾多の戦争が回避されてきた! 信仰と徳目も、人と人のあいだばかりではなく国家間に、従順さと謙虚さという拘束力を発揮する。扇動者たちによって引き起こされた戦争は、枚挙にいとまがない! 戦争を引き起こすような誤解がじっくり時間をかければ解消されたかもしれないという実例も、枚挙にいとまがない! 悲惨な戦争で敵対していた国々が、平和な数年を経て友好的になり、同盟国になることは珍しくない!
山上の垂訓は、キリスト教徒の倫理の最上のものだとされている。だれもが平和主義のクエーカーを尊敬している。しかしながら、大臣たちはそういった条件に則って国を導く責任を果たしているわけではない。国家もしくは思想上のどんな目的にもとづくにせよ、紛争や戦争を避け、あらゆる形の不当な侵略を控えるために、諸外国に対処するのが、彼らの第一の責務なのだ。とはいえ、国民の負託を受けて重職に就いている彼らが国の安全や国民の生命と自由のために最後の手段に訴えるのは、正しいことであり、なすべき急務でもある。すなわち、最終的に一点の迷いもなく確信したときには、武力行使の可能性を排除してはならない。武力行使が正当とされるような状況では、武力を使うこともありうる。さらに、そのような事態になった場合には、もっとも有利な条件で使用すべきだ。戦争を一年延期したら勝利がおぼつかない最悪の戦争になるおそれがあるようなときに開戦を先送りしても、なんの利益もない。歴史上、人類はこういった苦しい板挟みの状況で身動きがとれなくなったことが何度となくあった。最終的な判定は、事変当時の当事者が知っていた事実や、その後立証された事柄との比較によって、歴史に刻まれるしかない。(第17章、361-62頁)
独ソ不可侵条約の締結(1939年8月)
会議テーブルの周囲で歓声があがり、乾杯がさかんに行なわれた。スターリンはその場の勢いでヒトラー総統に乾杯を捧げ、つぎのように述べた。『ドイツ国民が総統を深く敬愛していることは知っているので、彼の健康を祈って乾杯すべきだろう』。このありふれた素朴な行為から、ひとつの教訓が得られるかもしれない。〝正直は最善の策である〞という諺がある。その実例が、本書でこれからいくつも示される。この先、書き記すように、ずる賢い人間や国家指導者が、手の込んだ目論見のせいで間違った方向へ導かれてしまうことがある。これもそれを示す兆候だった。わずか22カ月後にスターリンとソ連国民数百万人が、恐ろしい罰金を払うことになる。道徳的な逡巡のない政府は、自由に行動でき、きわめて優位に見えることが多い。しかし、〝一日が終わったときの採算は差引ゼロになるし、すべての採算が出るのは、すべての日が終わったとき〞なのだ。(第21章、445-46頁)
初の空襲警報(1939年9月3日)
〔チェンバレン〕首相がラジオで、われわれがすでに戦時にあることを知らせて、間もおかずにしゃべりつづけていたとき、延々とつづく泣き叫ぶような禍々しい騒音が耳朶を打った。その後、私たちはその音をさんざん聞かされることになる。危機によってすっかり備えができていた妻が部屋にはいってきて、ドイツ人はやることが早いし、几帳面だわねというような誉め言葉を口にした。なにが起きているのか見届けるために、私たちは館の平らな屋根に出た。清涼な九月の陽光のなかで、ロンドンの屋根や尖塔が四方に聳えていた。そのはるか上のほうで、3、40機の弾丸形の阻塞気球が上昇していた。戦時態勢が整っている明らかな印だったので、私たちは政府に高得点を献上した。空襲警報が出てから15分後には外に駆け出して、ブランディなど気休めの適切な医薬品〔ブランディは気付け薬に使う〕を持って、指定された待避所へ行くことになっていた。
私たちの待避所は、通りの100ヤード先にある掩蔽物のない地下室で、土囊すら積まれていなかった。フラット5、6軒の店子がすでに集まっていた。だれもが元気よくひょうきんだった。未知のことに出遭ったとき、イギリス人はそういうふうになる。ひと気のない通りに面した戸口から込み合った地下室を覗いたとき、想像力が働いて、破壊と大虐殺の光景が頭に浮かび、すさまじい爆発で地面が揺れたような気がした。土煙と瓦礫が巻きあがって建物が崩れ落ち、敵機の爆音の下で、煙のなかを消防車と救急車が走りまわる。空襲がどれほど悲惨なものであるか、われわれはみんな身をもって学んだのではなかったのか?〔中略〕政府が開戦から数日のあいだに、空襲の負傷者二五万人分を超える病床を用意したことを、私は知っていた。すくなくとも、状況は軽視されていなかった。いまからは事実を直視しなければならない。
約10分後に、また泣き叫ぶような音が響いた。ふたたび警報が発せられたのではないという確信はなかったが、ひとりの男が通りを走りながら叫んだ。「敵機なし(オール・クリアー)」。私たちは解散してそれぞれの住まいに帰り、仕事に戻った。(第22章、460-61頁)
海軍卿(=海軍大臣)への復帰(1939年9月5日)
私は海軍卿に就任することを即座に海軍本部に伝え、その日の午後六時に出向いた。海軍本部委員会が、親切にも艦隊へ電報を送ってくれた。〝ウィンストン帰還〞。かくして私は、ほぼ四半世紀前に心痛と悲しみを味わいながら立ち退いた部屋に戻った。〔中略〕以前座っていた椅子に腰かけると、1911年に私が修理した木の地図箱が数フィートうしろにあり、いまだに北海の海図がしまってあった。究極の目的に注意を集中するために、私は毎日、海軍情報局にドイツの外洋艦隊の動きと位置を記録させていた。1911年から四半世紀以上が過ぎていたが、以前とおなじ致命的危機が、以前とおなじ国の手によってわれわれを脅かしている。そしてまたもや、弱国の権利が、挑発なき不当侵略行為によって、凌辱され、犯され、われわれは剣を抜くことを余儀なくされた。われわれはまたもや、勇敢で規律正しく非情なドイツ民族のすべての力と憤怒に対して、命と名誉を賭して戦わなければならない。またしても! まあ、それもよかろう。(第22章、462-63頁)
開戦時の日本の動向(1939年9月)
この時点では、日本は敵対的な行動や意図を示していなかった。日本は当然ながら、もっぱらアメリカに多大な関心を抱いていた。極東におけるヨーロッパ諸国の権益基盤に対して日本が多岐にわたる攻撃を行なった場合、アメリカがその権益にまったく関与していなかったとしても、消極的に座視することはありえないと私は見ていた。その場合、できればアメリカが介入するほうが、私たちにとってははるかに好都合だった。口惜しいかもしれないが、日本の敵対行為でイギリスが被害を負うとしても、そのほうがずっといい。極東でどういうことが脅かされているにせよ、絶対にヨーロッパにおける主要目標から注意をそらすことはできない。イギリスが黄海にある権益や所有物を日本の攻撃から護ることは不可能なのだ。日本が参戦した場合、イギリスが護れる最遠の地域は、シンガポールだった。地中海が安全になり、イタリアが始末されるまで、シンガポールは持ちこたえなければならない。(第22章、470頁)
午睡の効用
サイモン卿と〔チェンバレン〕首相を除けば、前世紀の遺物の年寄りは私ひとりだった。若者の力と斬新な発想を求めるのが自然で受けがいい危機の時代には、それが非難の材料になりかねない。そこで私は、いま権力を握っている世代や、いつなんどき現われるかもしれない非凡な才能を備えた元気な若者に遅れをとらないように、精いっぱい努力するべきだと考えた。そのために、知識に頼るだけではなく、熱意をふり絞り、精神力の限りをつくした。
この目的のために、1914年から1915年にかけて海軍本部で強いられていた日々の手順を採用した。それによって、毎日の仕事の許容量が飛躍的に拡大することがわかっていた。私はつねに、できれば午後の早いうちに一時間以上、ベッドにはいり、あっという間に熟睡できるありがたい才能を満喫する。これによって、一日半の仕事を一日に圧縮できる。人間はそもそも、元気を回復する余裕なしに午前8時から夜中の12時まで働くようには創られていない。〔中略〕それによって午前2時かもっと晩くまで--場合によっては明け方近くまで--働いて、朝の8時か9時にまた働きはじめることができた。(第22章、474頁)
チェンバレン首相夫妻との会食(1939年11月)
息子としての責務だけではなく確信と敏活な性格から、チェンバレンは指示に従い、それから5年間、ときどきハリケーンに襲われるこの淋しい島〔バハマ諸島のアンドロス島〕で、ほとんど裸で暮らし、労働力を得るのにも苦労し、あらゆる障害にぶつかりながら、サイザル麻を栽培しようとした。文明社会がかすかに見られるのは、ナッソーの町だけだった。年に3カ月、イギリスに帰る休暇を要求したと、チェンバレンは私に語った。チェンバレンは、小さな港、浮き桟橋、短い鉄道もしくはケーブルカーを建設した。土壌に適していると判断された施肥の手順をすべて使い、大体において完全に原始的な野外での生活を送った。だが、サイザル麻は育たなかった! とにかく、市場に出せるようなものはできなかった。5年目の終わりに、この計画は成功しないと、チェンバレンは確信した。帰国して、結果に満足するはずがない手強い両親と正面から話し合った。家族は彼をとても愛していたが、5万ポンドを失ったのは残念だったと思ったようだった。
チェンバレンが話をしているうちに興奮するのを見て、私は心を奪われた。果敢な大事業の話にも魅了され、ひそかに思った。〝ヒトラーのやつ、気の毒なことに、雨傘を持った〔慎重居士だという意味〕このイギリスの政治家とベルヒテスガーデン、ゴーテスベルク、ミュンヘンで会ったときに、大英帝国の外征に加わっていた百戦錬磨の開拓者だとは知らなかったにちがいない!〞20年以上もともに政界にいたにもかかわらず、こういうふうに親しく話をしたのは、この一度だけしかなかったと記憶している。(第27章、558-59頁)
泊地スカパ・フローに向かう艦上にて(1940年3月)
私は司令長官と話し合うことが数多くあったので、艦橋へ行ったときには午前零時をまわっていた。あたりは漆黒の闇だった。大気は爽やかだったが、星は見えず、月も出ていなかった。巨大な軍艦は約16ノットで突き進んでいた。追躡している戦艦が、後方に黒い塊となって見えるだけだった。30隻近くがともに航行し、秩序正しく進んでいた。船尾の小さな灯火がいくつか点いているだけで、ほかに明かりはなく、所定の対Uボート機動にしたがって絶えず転舵していた。陸地も空も観測できなくなってから5時間が過ぎていた。やがてフォーブズ提督がやってきたので、私はいった。『私はこういうことを実行する責任を負うのは、まっぴらごめんだな。夜明けにミンチ海峡の狭い出口に到達すると、どうしてわかるのかね?』提督が答えた。『あなたならどうしますか? この瞬間、命令を下せるのが自分ひとりだとしたら?』私は即座に答えた。『錨をおろして朝を待つだろうね。ネルソン提督がいったように、〝錨だ、ハーディ〞〔ネルソンが息を引き取る間際の言葉〕と』。しかし、提督はそれに対してこういった。『いまこの下は100尋近い深さです』。もちろん私は、海軍に対して長年のあいだに培った全幅の信頼を置いている。この話をするのは、陸(おか)の人間には不可能に思えるこういう離れ業が、必要とあればあたりまえのことのように、すばらしい技倆で正確に執り行なわれることを、一般読者に知ってもらうためだ。八時過ぎに私が目を醒ましたときには、艦隊はミンチ海峡の北の広々とした海に出ていて、スコットランド西端をまわり、スカパ・フローを目指していた。(第32章、646-47頁)
戦争は避けるべき
じっさいの戦いは、ひとりの悪党がべつの悪党の鼻面を棍棒か、金槌か、もっとましなものでぶん殴るようなものなのだ。すべて嘆かわしい所業で、それは戦争を避けなければならないもっともな理由のひとつだった。少数派の権利をきちんと考慮し、反対派の意見を忠実に記録して、友好的なやり方で合意によって万事を解決するほうが望ましい。(第33章、666頁)
組閣の大命を受けて(1940年5月10日)
政局危機末期のこの繁忙な日々、私の脈は片時も速くならなかった。来たれるものをそのまま受け入れていた。だが、午前3時に寝床にはいったときに、心の底から安堵がこみあげたことを、このありのままの記述を読んでいる人々から隠しおおせることはできないだろう。ようやく私は、すべての局面で指示を下す権限を得た。避けがたい宿命とともに歩んでいるような心地だった。私のこれまでの半生すべてが、この秋(とき)、この試練のための備えであったかのように思えた。(第38章、755頁)
* 〔 〕内は訳注、および編集部注
* 本文にない小見出しを付しました
――つづきは本書でぜひご覧ください――