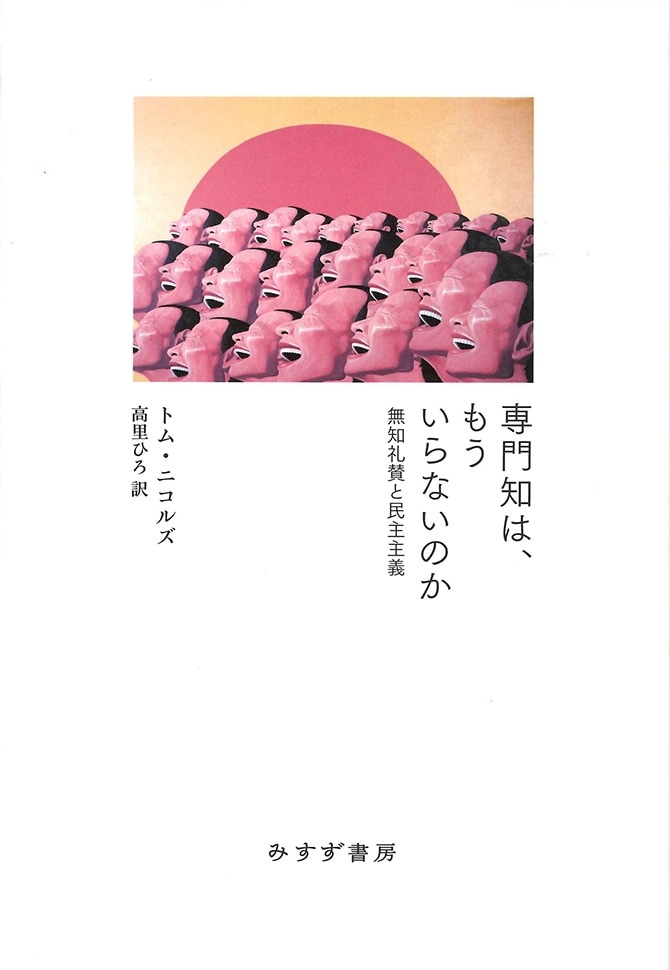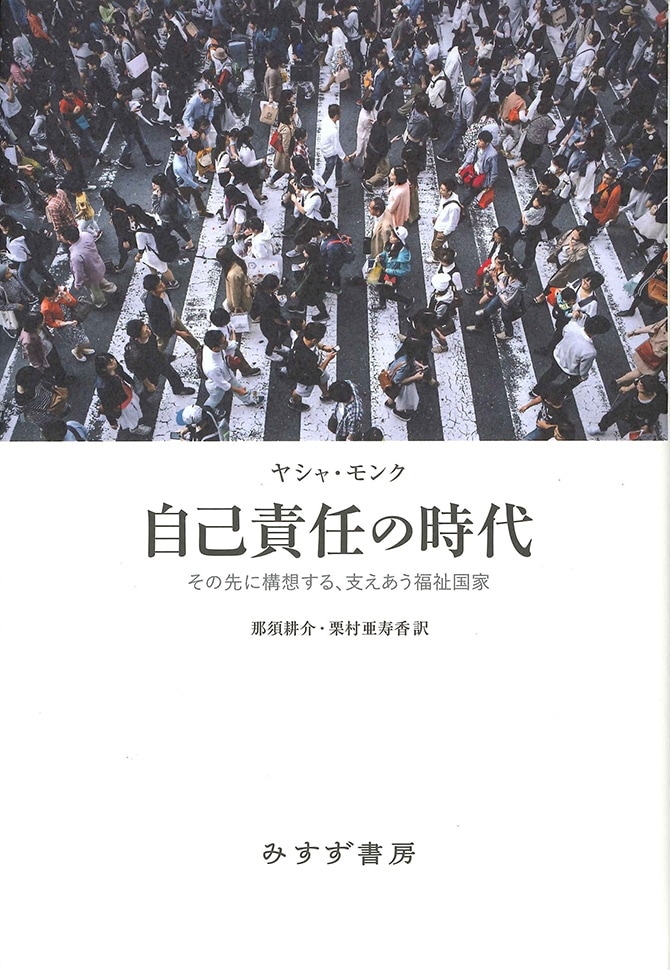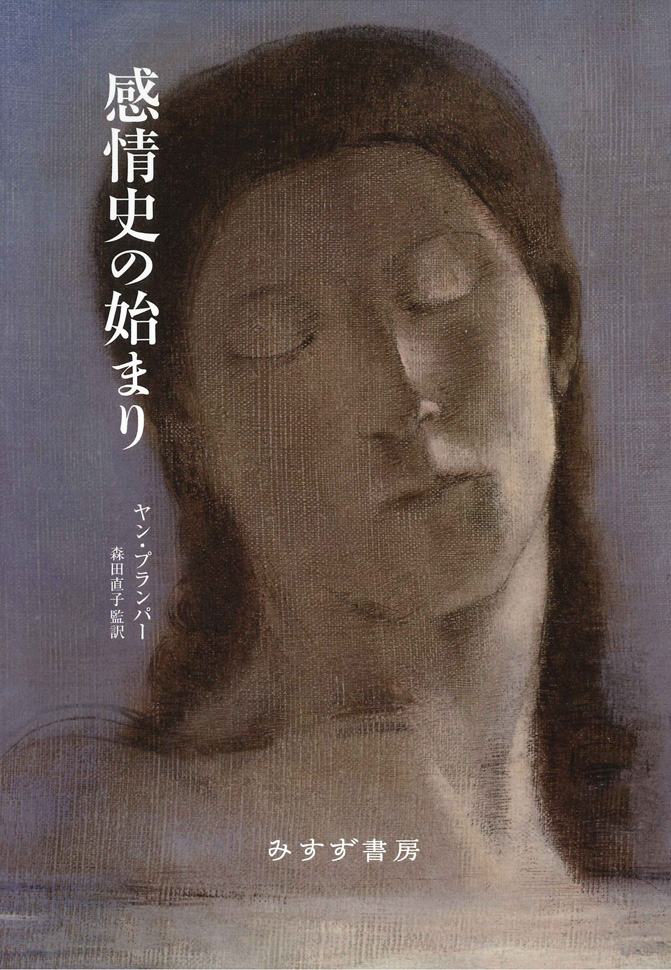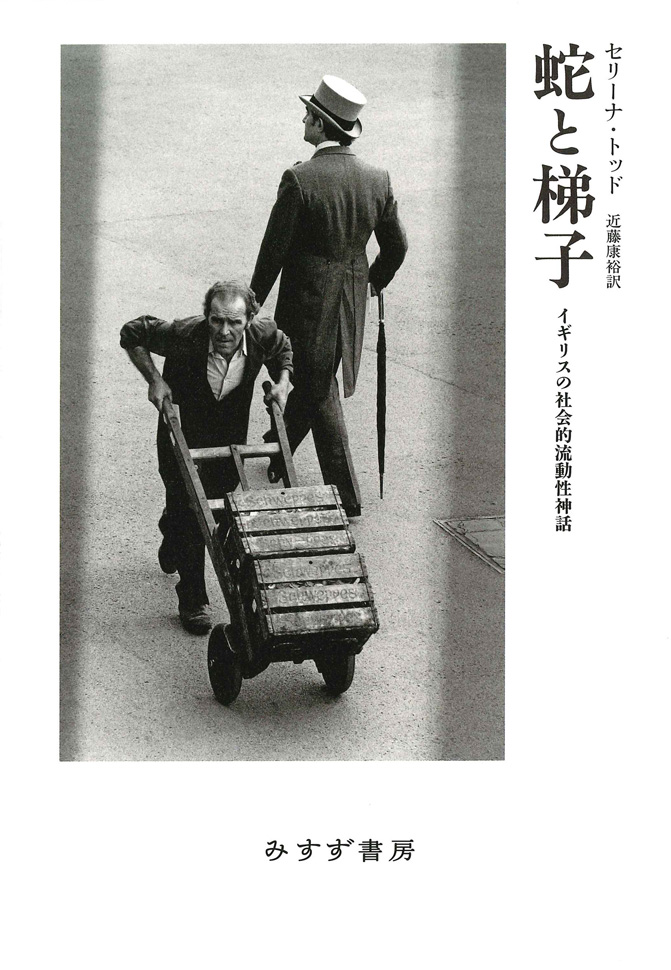本書は、「幸せ」への過度のこだわりが特定の科学と産業によって助長されてきた側面と、その悪影響を研究対象としている。著者らの主張を裏づける例や現象はじつに興味深いのだが、それはぜひ本文をお読みいただくとして、ここでは原注から周縁的な指摘を取り上げてみたい。冒頭の「この現象」というのは、自分自身の内に閉じこもりたいという衝動の広がりを指している。
この現象の、徴候的ではあるが極端な例に、2008年以来、サバイバリズムの存在とそれに対する関心が世界的に増しているということがある。サバイバリズムは、社会が崩壊しつつあり最悪のときが迫っているのだから、サバイバルする(生き残る)ためには誰でも独力で危険に備える必要があるという世界観のもと、常時準備、完全自給、みずからの安全への過度の関心といった大いに個人主義的な考え方を駆り立てる。サバイバリズムは新しいものではないが、この社会的なトレンドは、ここ10年ほどのあいだとくにアメリカ合衆国で、一部の人の趣味的なものから、急速に成長しつつあるサバイバリスト産業によってまったく新しいライフスタイルへと変貌をとげた。サバイバリストのテレビ番組、ハリウッド制作の映画や自己啓発書の消費も、2008年以来、世界的かつ指数関数的に伸びている。たとえば世界中で12億人が視聴したといわれる『サバイバルゲーム(Man vs. Wild)』〔ディスカバリーチャンネル〕のようなサバイバルを題材にしたテレビ番組は、世界でもっとも視聴率の高いジャンルとなり、2010年代に公開されたゾンビ/サバイバル映画の数は1990年代に公開された数とくらべて4倍に増えている。
「2008年」は金融危機の年で、それ以降、不安定な雇用や低賃金に苦しむ人が増加した。そうした世相を背景にサバイバリズムが関心を集め、それを商機にさらにサバイバリズムが流行り、「個人主義的な考え方を駆り立てる」。問題の原因も、政治ではなく個人に求められるようになる。「幸せ」の概念は、そこで重要な役割を果たしている。
「流行っているから」と何気なく消費しているサバイバルものの映画や、自己啓発本や、「幸せ」アプリの背後にあるものを私たちはふつう意識しない。本書はそこに、心理学と社会学の学知からいくつもの窓を開こうとしているが、「幸せ」を求めることが愚かだと言っているわけではない。本書が分析している「幸せの科学」や「幸せの経済学」の主張を、印象深くも「生きがい搾取」と評した人がいる。搾取されることが幸せなわけがない。搾取されることも、踊らされることもなく、満たされた毎日を送ること。それを可能にする社会をみんなでつくること。本書はその一助になるだろうと思う。