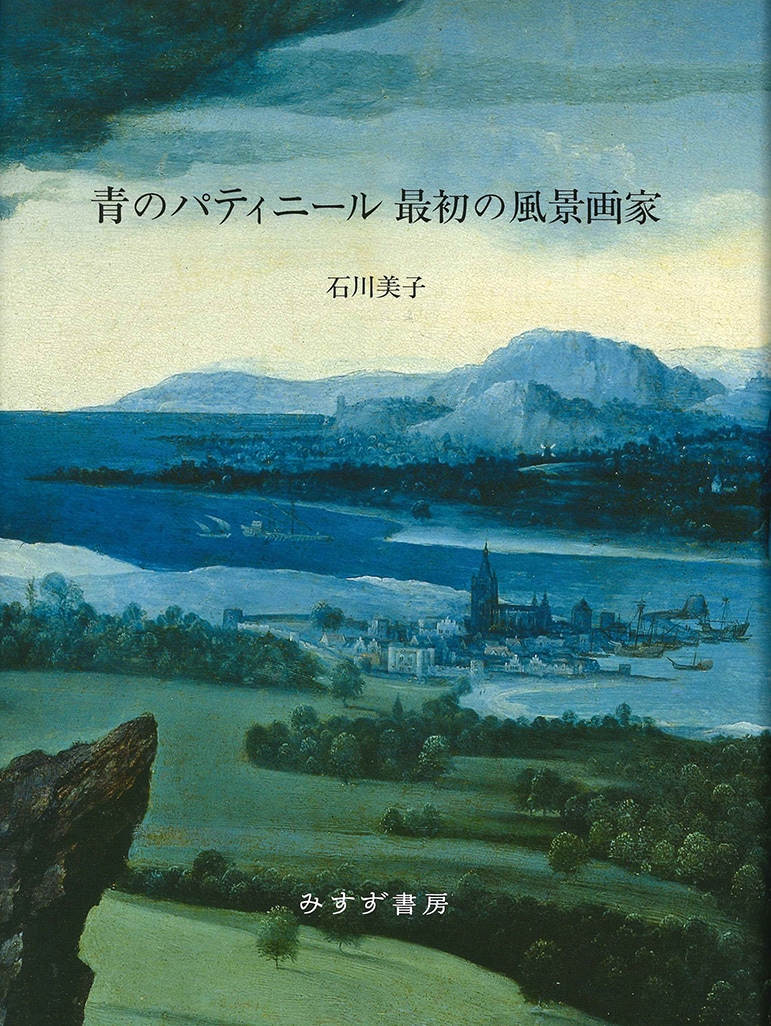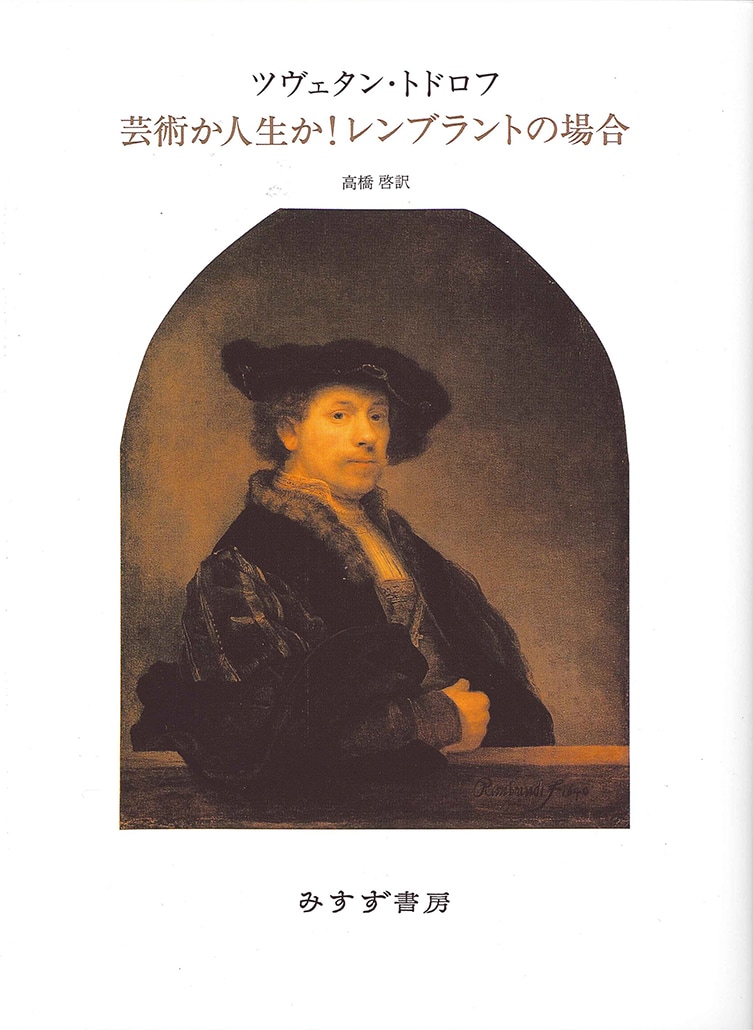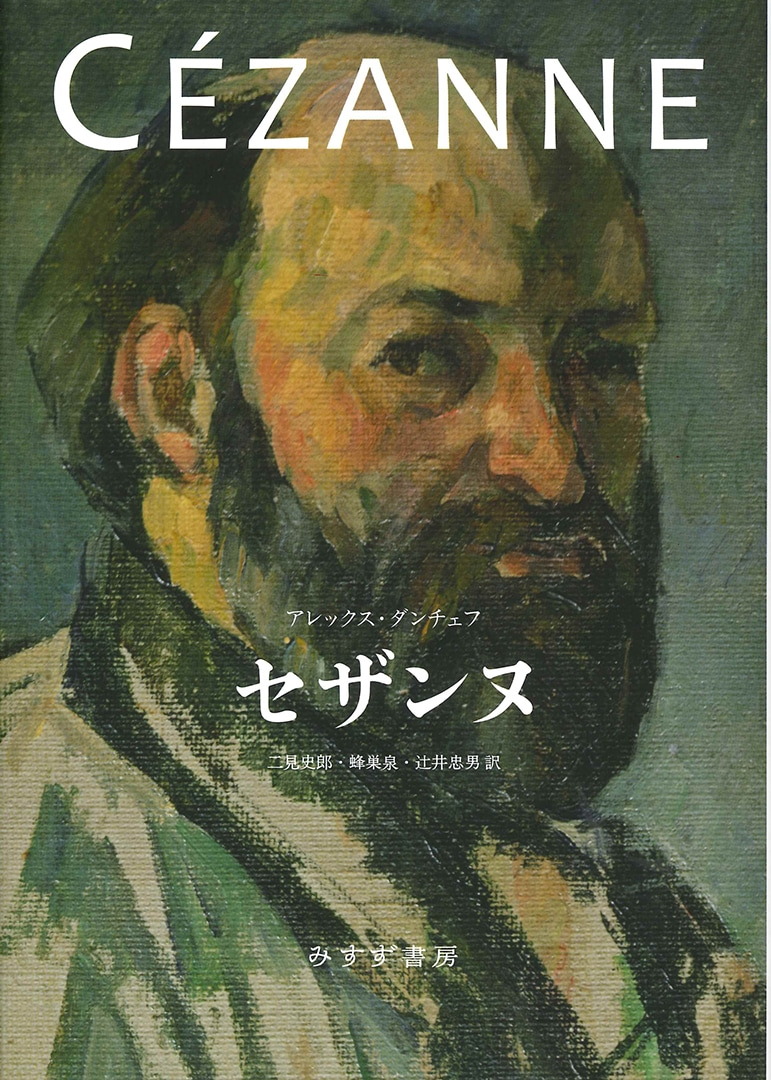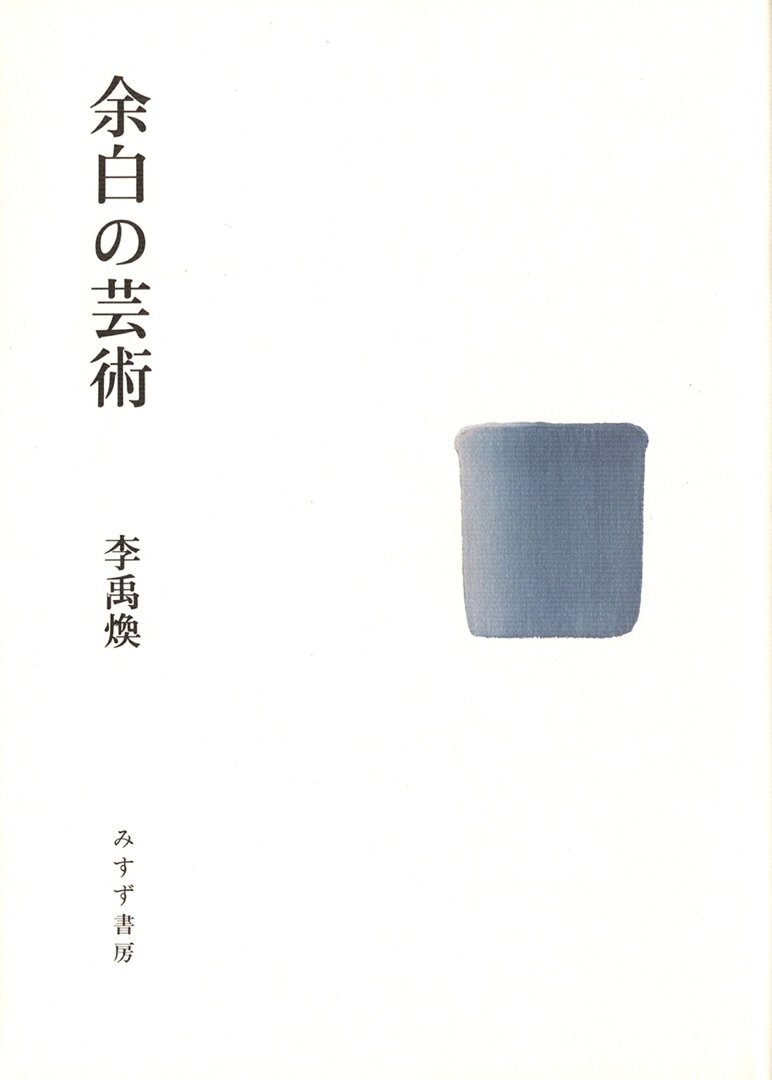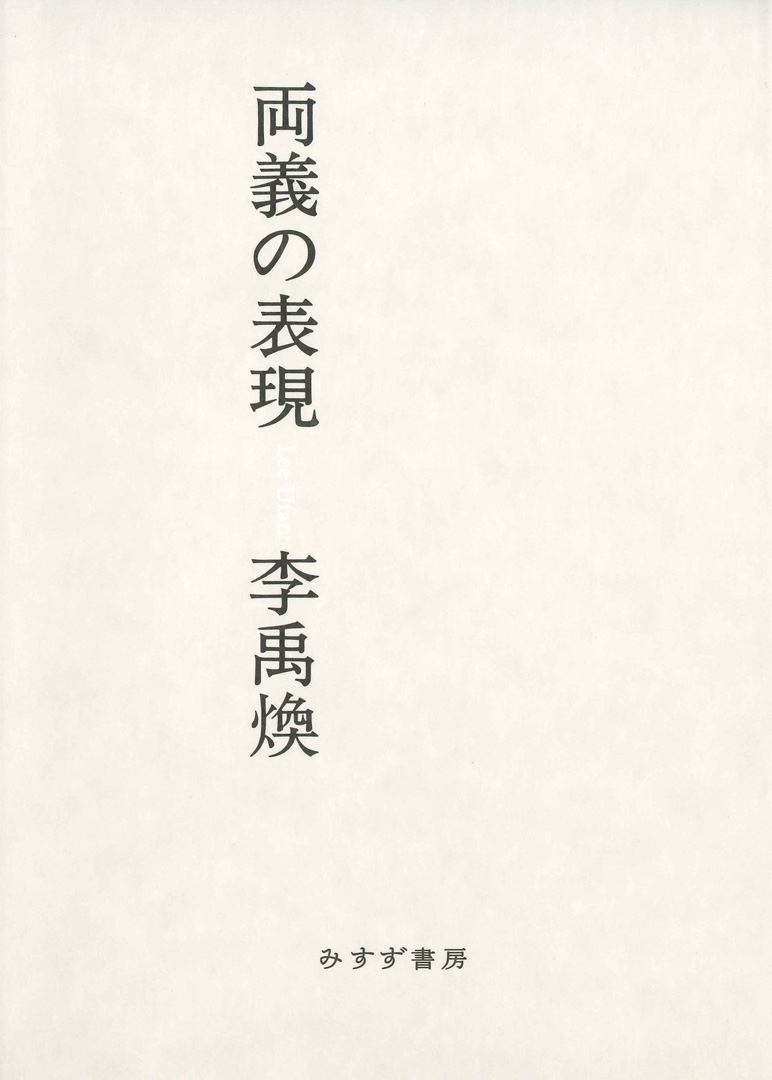《夜警》として知られるレンブラントの絵のタイトルは〈フランス・バニング・コック隊長の市警団〉だし、クールベの〈画家のアトリエ〉には「7年に及ぶわが芸術生活決定づける現実的寓意」という長い副題がついている。パイプの下の余白にCeci n’est pas une pipe. と手書きの文字が書かれたマグリットの《これはパイプではない》の正式なタイトルは、〈イメージの裏切り〉――
誰もが知っていて、今後もそう呼ばれつづけるだろうあのタイトルは、いつ、どのように、そう呼ばれるようになったのだろう。それは画家が描こうとしたものを本当に正しく伝えているのだろうか?
美術館に来た人に、絵の下のパネルではなく絵そのものを見てもらうことは、学芸員にとっての永遠の課題。その小さなパネルに書かれていること――画家名、制作年、画材と支持体、所蔵、そして何よりもまず絵のタイトル――を、人は一生懸命読む。それから、おもむろに絵に目を移し、キャプションに記されたタイトルどおりのものが絵の中にみつかると、安心して隣の絵(のキャプション)へと移動していく。どんなタイトルであれ、それは絵の解釈の枠組みを決めることになり、見る人はその枠の中で絵の意味を考えてしまう。
かつて絵は、教会の壁や天井を、王侯貴族の居館を飾るものだった。パトロンの依頼によって描かれたフレスコ画は、そこから動かすことができない。見ることができたのは、その地に住み、同じ文化を共有する限られた人だけで、画家、パトロン、「見る人」は、絵の主題を共有していた。
絵画の売買の記録は14世紀から存在するが、遠く離れた土地、共通する文化の土壌がないところでは、「何が描かれているのか」を言葉で説明しなければならない。仲介人を通じて売り買いが盛んになったのは16-17世紀のネーデルラント。アントワープに絵の展示・販売のための建物ができ、1616年にオークションカタログが作られた。やがてフランスの王立アカデミーによる作品展、いわゆる「サロン」を皮切りに絵が一般公開されるようになると、人びとは説明が書かれた小さなカタログをしっかり握りしめて、絵の間を歩きまわるようになる。
画家たち、版画家に画商、学芸員、美術史家、評論家、カタログ編集者、詩人や出版者、印刷業者……絵と、絵にまつわる言葉に、こうした人びとがどう向き合ってきたか。その歴史をひもときながら、ルース・B・イーゼルが伝えようとするのは、タイトルの肯定でもなければ、否定でもない。タイトルの持つ「力」だ。
タイトルの力についてはマーク・トウェインも書いている。
「ローマでは誰もが〈処刑前日のベアトリーチェ・チェンチ〉の絵の前で涙を流す。タイトルがなければ、ただの若い女の絵にすぎないのに」
と。さらに、涙する人たちは絵についた説明は熱心に読むのに、絵のほうはちらっと見るだけだ、と手厳しい。(『ミシシッピの生活』1883)
タイトルの力にもかかわらず、画家たちが作品に自分で名前をつけるようになるまでには長い時間がかかった。そもそも、美術館という場所で誰もが絵を見ることができるようになってから200年と少ししか経っていない。革命と王政廃止によって、王室や教会の所有する美術品が「公共財」となり、市民に公開された共和国美術館――初の近代的ミュージアム、ルーヴル美術館の登場は1793年のこと。その美術館の歴史よりも、画家みずからタイトルをつけるようになってからのほうが、もっと短いのだから。
言葉が絵に対して持つ力を自覚し、その力をおおいに利用した6人の画家たちが、自分の絵と言葉とのあいだに切り結んできたスリリングな関係。
寄り添い、あるいはせめぎあいながらセットで世界中に広がっていった、絵画とタイトルの近くて遠い関係。
詩人、批評家、小説家のベン・ラーナーはこの本に魅せられて、こう書いている。
「作家として、視覚芸術に対していつも嫉妬をいだいてきた。しかし、この本でいかにタイトルが見る人に影響を及ぼすかを知った。つまり、言葉が絵に対して持つ力を確信した」
(『ニューヨーカー』誌、“The Books We Loved in 2015”)