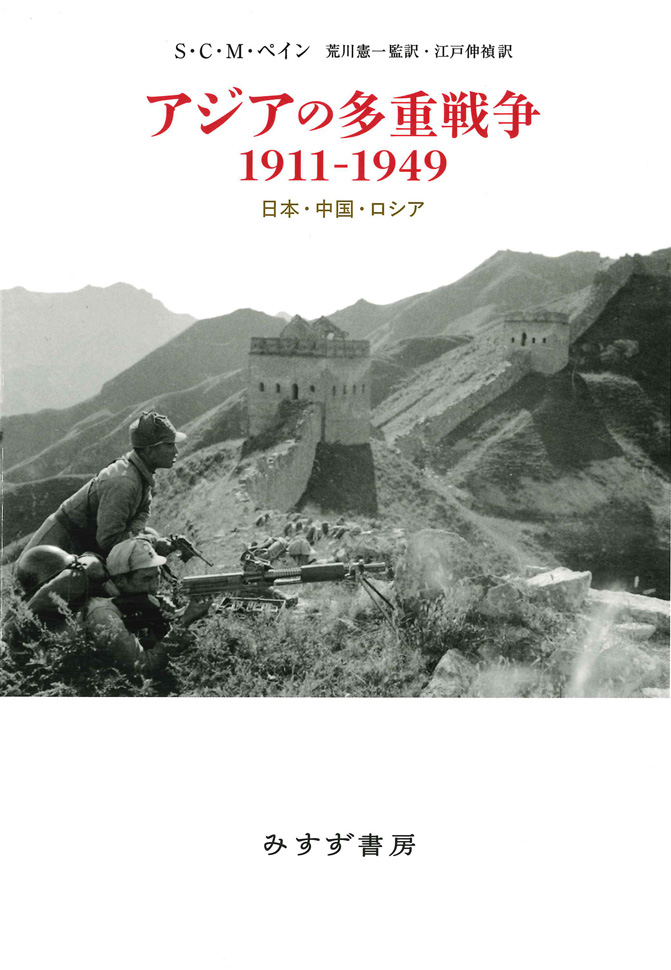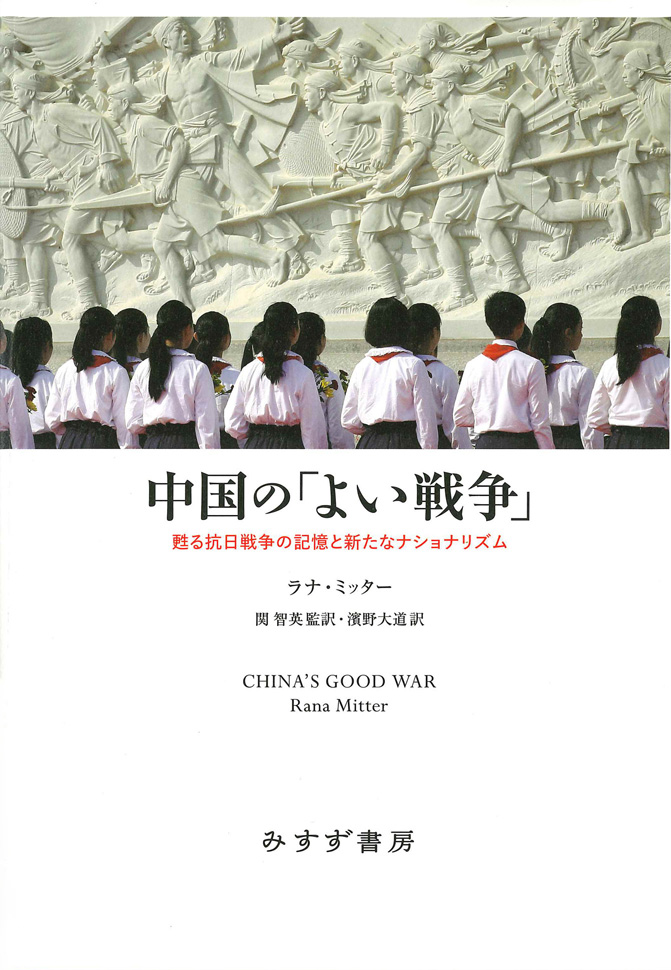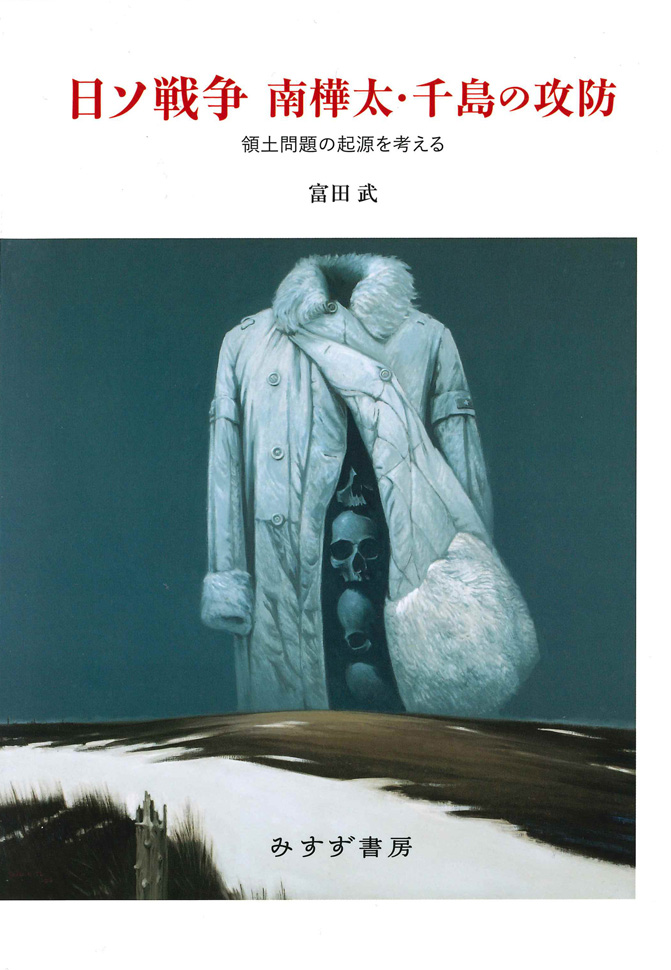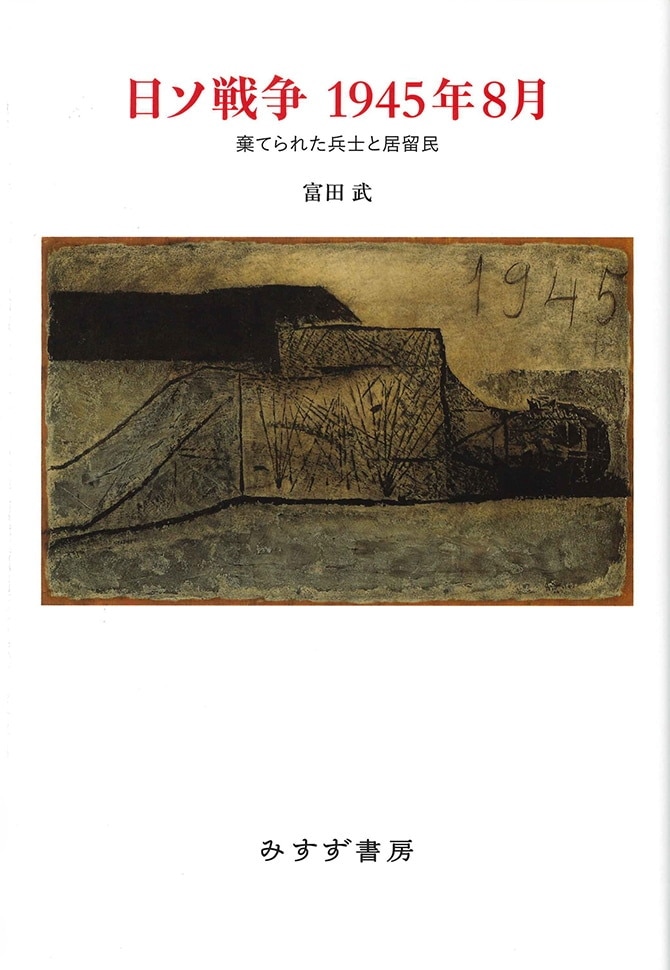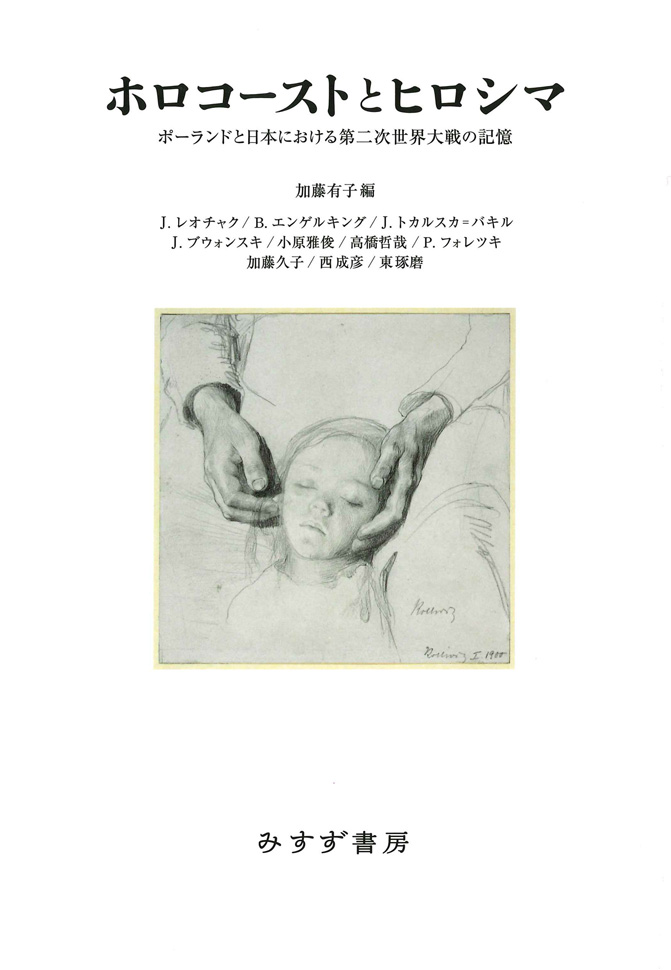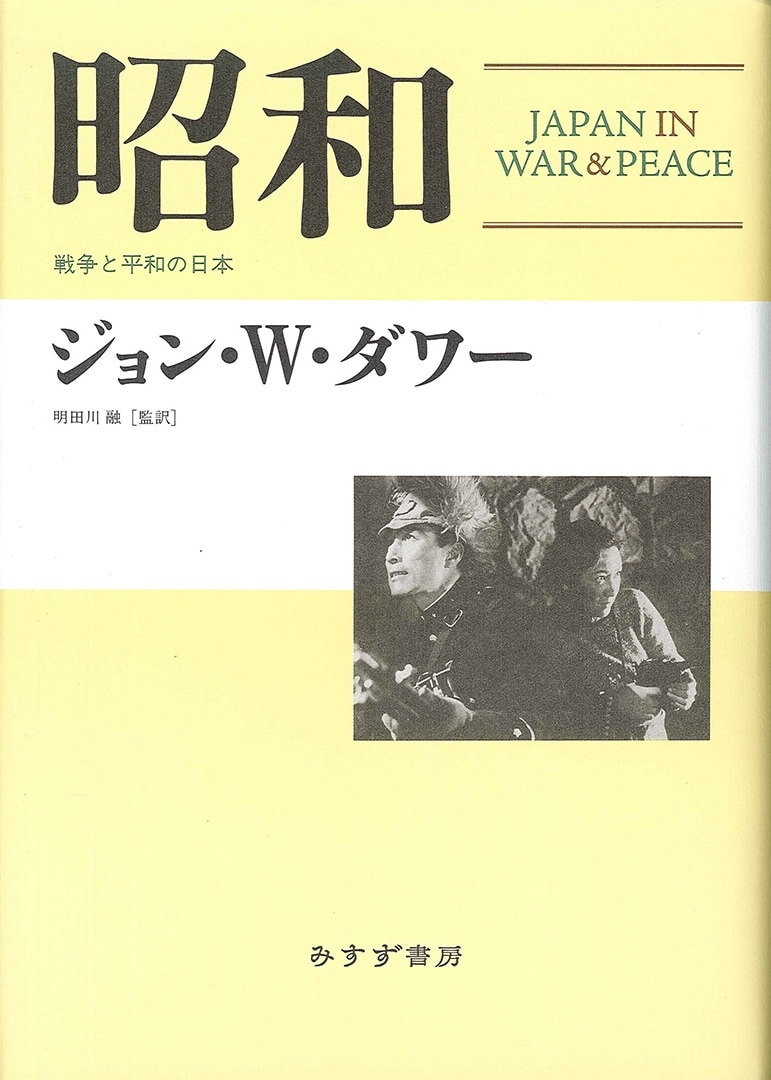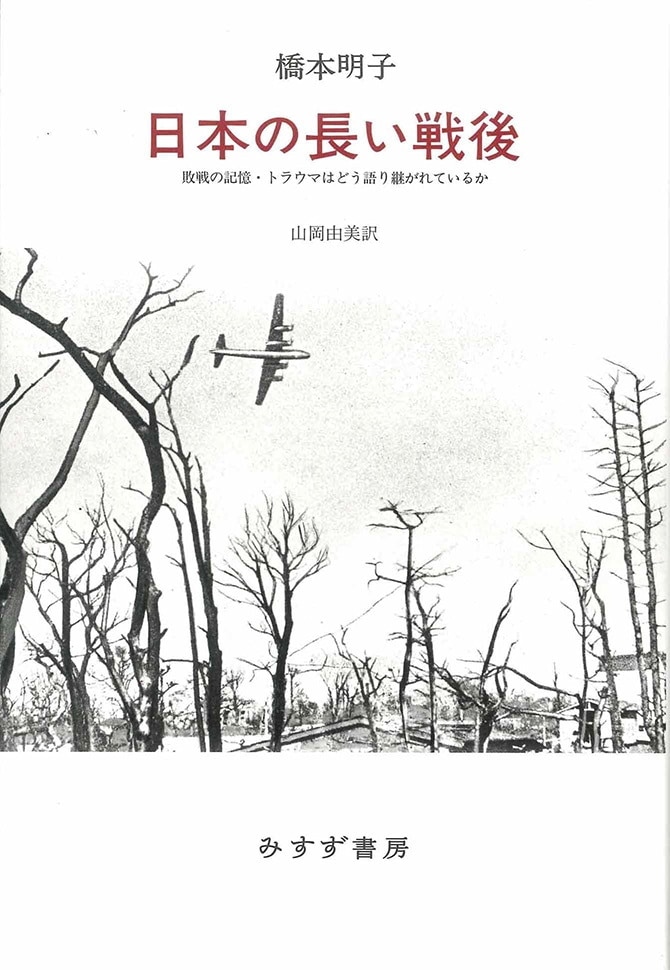終戦から70年、真珠湾攻撃から75年を経て本書を書き終えた筆者たちは、ここに語られた人々の経験がどれほど重要でタイムリーなものだったかを実感している。また戦後の混乱の状態を振り返り、現在の日本がこのレガシーをどのように認識してきたかに思いを馳せることができる。
大分の人々は、本土内の前線にいた一般市民も各地の戦線にいた兵士たちも20世紀の前半は天皇や軍の指導者たちに明白な忠誠を尽くしてきた。多くが戦死し、生きのびた人々も親戚や友人を遠く離れた戦地で、あるいは国内でアメリカ軍の空爆を受けて失っている。子どもたちも学校へ行かずに軍需品製造や航空機の修理工場で働いた。10代の若者が「神風」特攻隊として嘆き悲しむ両親を残して飛び立った。看護婦や助産婦になった若い女性たちは焼け落ちた病院で患者の手当てをしたり、地下の防空壕で赤ちゃんをとりあげたりした。
人々はメディアを信じ、どんなに混乱した命令を出されても指導者たちに従った。そして確固たる盲目的な忠誠心で天皇をあがめた。しかし今日、自分たちが戦時中にどうしてこんなにも誤った方向に導かれたのかと愕然とする人々が多い。彼らは最後まで日本の勝利を信じていたし、アジアの同胞を解放するという政府のプロパガンダを鵜吞みにしていた。政府が国民全体をだますことができたのはなぜだろう? このことを理解するために中国で起こった同様の事例を見よう。筆者の妻ランインが学生時代に経験した文化大革命とよく似ているからだ。個人の権利や表現の自由を当然のものとしている社会から来た人がこの絶対的な「集団思考」を批判するのは簡単だ。しかし批判的なコメントを口にできないばかりか考えることすら許されない全体主義的な社会にいる者には、みずからの人生を描くことなどとうていできないのだ。ランインが政府の認可した新聞や革命的な小説ばかりを読んでいたのと同じように、当時の日本人も政府のお墨つきの新聞が「戦勝」のニュースや敵を倒して犠牲になった英雄を美化する記事ばかりを読んでいた。事実がいくらかでも明らかになったのは戦後になってからだった。
そしていまはどうだろう?
政府のあらゆるレベルで、あの当時を鋭く分析したり侵略の事実を認めたりする作業はほとんどおこなわれていない。むしろ政治家も教育者もその当時のことを討論するのを避けたがっている。ドイツはヨーロッパを戦争に巻きこんだ責任を認めたが、日本がアジア太平洋地域でおこなった残虐行為を認めるにはまだとまどいや困難があるようである。
歴史を抹殺する事例が最近大分市の出版した県の歴史年表にみられる。これは石器時代から21世紀までを網羅したものだが、奇妙なことに1934年から1945年までの出来事がいっさい省かれているのだ。何も知らない読者は歴史的に重要な出来事が何も起こらなかった時期だと思うだろう。しかし、もちろんこの沈黙は、妥協することのできないつらい過去を覆い隠そうとする自己欺瞞を声にならない声で叫んでいるのだ。汚職や大失態が明らかになった大企業のCEOや政治家が深々とお辞儀をして謝罪する姿をテレビで見かける。しかし、日本の総理大臣がかつて植民地としてひどい扱いをした国々を訪問するとき、同じように礼を尽くして現地の人々に謝罪する姿は見たことがない。これこそがとるべき方向だということを日本はドイツから学んでいないようだ。
戦時中のリーダーたちの役割を明確に判断することができていないまま、時間的にも意識的にも真空状態が生まれてしまった。しかし、真空状態はそのままでは収まらない。国家主義的な人々がこの空白を埋めることを画策しはじめた。こうして戦争の恐怖をうまく言いつくろい、日本の平和主義的憲法を改定して、より大きな軍事力をもとうとしている。その結果、日本はアジアの隣人たちから孤立し、正直な評価を叫ぶ声を抹殺しようとしている。
個人的なレベルで見ると、戦時中を生きた人々はいまもなお複雑な思いで戦争を振り返るようだ。この国がおこなったことを嫌悪する一方、あの時代に対してある種のノスタルジックな思いを抱きつづけているのだ。たとえば聞き書きを始めたころだったが、私たちがハワイ出身だと知ると、インタビューを受ける人が「貴国に「不当な」攻撃をして申し訳なかった」と謝罪した。続いてランインが中国で育ったことを知って「中国を侵略して、お国の人々に恐怖を与えてすまなかった」とも言った。しかし、自分の故郷の佐伯は真珠湾攻撃の準備に関して多大な貢献をしたと胸を張るのもこの同じ人物なのだ。また、学生ながら動員されて軍需工場で働いていたとき、アメリカ軍の爆弾で友人たちが焼死するのを見た人は、戦争は大きな間違いだったと言いながら、かつて少年時代にその修理に携わった零戦の模型を誇らしげにオフィスに飾っていたりした。
戦争にロマンをかきたてるような試みが現在も地方の玩具屋などにみられる。筆者たちは模型屋の店先に一連の零戦や「武蔵」「大和」といった戦艦のモデルキットが並んでいるのを見た。あの当時の憧れの的に抱いた思いは、もちろん完全に拭い去ることはできないだろう。だが、政府が平和主義のスタンスから攻撃的な軍事色を前面に出そうとしているいま、それが強まってきているように思えるのだ。
私たちになじみ深い別府でも、国家主義的な動きが高まるのを見た。右翼の組織が黒い旗を飾ったバスやバンで中国人や韓国人に対するヘイトスピーチを大音量で流しながら街路を行進していた。多くの日本人は、あれはやくざのような犯罪組織で社会のごく一部にすぎないと反論するだろう。しかし、ああいう集団がいずれは反対派を黙らせ、映画館を閉鎖させ、日本史の暗黒部分をはっきり批判するジャーナリストを襲ったりするのだ。
八十六歳の被爆者、谷口稜暉さんが2015年8月9日の長崎原爆犠牲者慰霊平和式典で語った言葉を、日本の人々が今後もじっくり聴くことを願うばかりである。彼や被爆者たちが経験した恐怖や苦しみを語った後、谷口さんはこう述べている。「戦後日本は再び戦争はしない、武器は持たないと、世界に公約した「憲法」が制定されました。しかし、今集団的自衛権の行使容認を押しつけ、憲法改正を推し進め、戦時中の時代に逆戻りしようとしています。今政府が進めようとしている戦争につながる安保法案は、被爆者をはじめ平和を願う多くの人々が積み上げてきた核兵器廃絶の運動、思いを根底から覆そうとするもので、許すことはできません」。それは被爆者の思いに反してふたたび戦争へ導こうとしている安倍晋三首相〔当時〕への警告だった。
最後に、別府のアメリカ軍占領本部跡を訪れて本書を閉じたいと思う。キャンプ・チッカマウガの跡地はいまでは別府公園として剣を鋤に変えた美しいあかしとなっている。春には桜が公園を覆い、秋には紅葉が散って地面を赤や黄色に染める。子どもたちはボールを追いかけて走りまわり、家族連れがピクニックをしたり、小川のそばの木陰で静かに読書を楽しんだりしている。キャンプ・チッカマウガはひと握りの人々の淡い記憶のなかにそっと残っていて、たったひとつの簡素な石碑が過去の軍事的な役割を伝えている。
こここそが文字どおり、また象徴的にもこの本の物語が始まり、そして終わった場所である。最初私たちは戦時中のことや日本の敗北について進んで思い出話をしてくれた大分県のこれらの老人たちに導かれてアメリカの占領について書こうと思った。皮肉なことに、彼らのなかにはいまもなお毎年別府公園の桜の木の下で家族や友人たちと酒を酌み交わして楽しんでいる人々がいる。最初にインタビューに応じてくれた湯谷さんとともにこの本を閉じよう。彼は子どものころにこの公園でルーズベルトやチャーチルの顔を描いた藁人形に「突撃」したのだという。彼は言った。「私たちが負けてほっとしました。そうでなければ日本もいまの北朝鮮のようになっていたでしょうから」