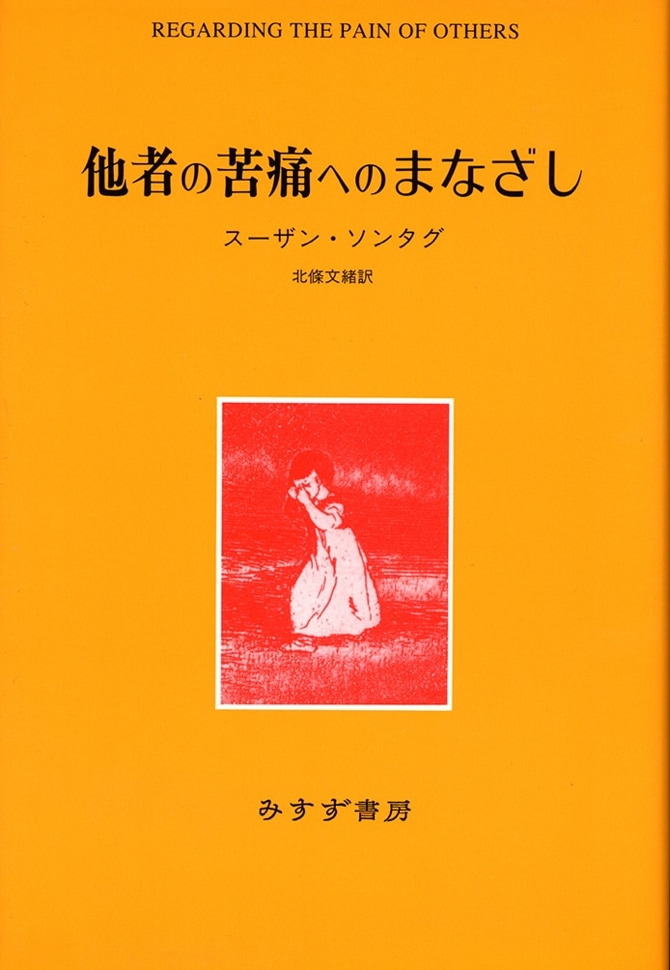このたび【改訳新版】としてサイードの主著のひとつ『文化と帝国主義』を復刊いたしました。本書とあわせて「帝国と文化」への理解を深める、思想・文学ジャンルの本をご紹介します。
1. エドワード・W・サイード『文化と帝国主義』【2025年2月改訳新版】
大橋洋一訳
「本書は30年以上も前の本ではない。むしろ今この時期に緊急出版された「新刊」といっていい。」
「本書『文化と帝国主義』は、帝国主義と文化のかかわり、または帝国主義への抵抗を現代アメリカ文化にまでたどる歴史書なのだが、現在のパレスチナ問題をつねに念頭に置いて読まれると、理解が早く、また深まることを最初に述べておきたい。」(「改訳新版への訳者あとがき」)
重なりあう領土、からまりあう歴史……今日もなお形を変えてつづく世界史の諸相を描いた、ポストコロニアル批評の金字塔。
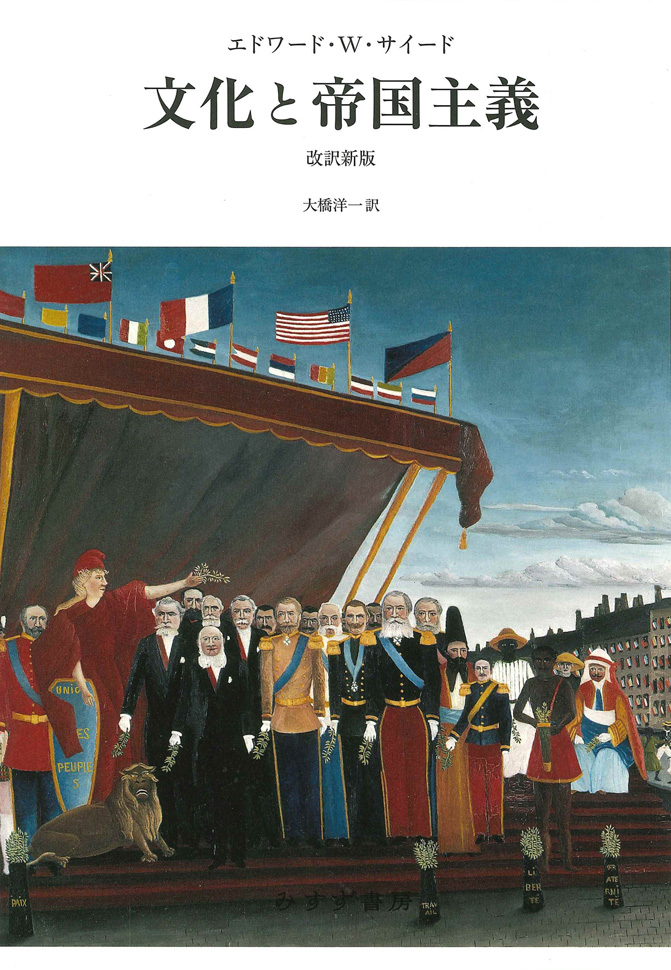
2. エドワード・W・サイード『イスラム報道【増補版】――ニュースはいかにつくられるか』
浅井信雄・佐藤成文・岡真理訳
『オリエンタリズム』の著者が、西洋(=アメリカ)のメディアに現れるフィクションとしての「イスラム」を描き、アクチュアルな問題を本書を通して世に問うたのは、1981年のことだった。……原著刊行16年後に出た新版に著者が寄せた50頁を超える序文を加えた増補版。SNS上のフェイクニュースなど、フィクションの拡がりが加速する現代においても示唆に富み、リップマン『世論』、オーウェル『1984年』に並ぶ、新たなるメディア論の古典。
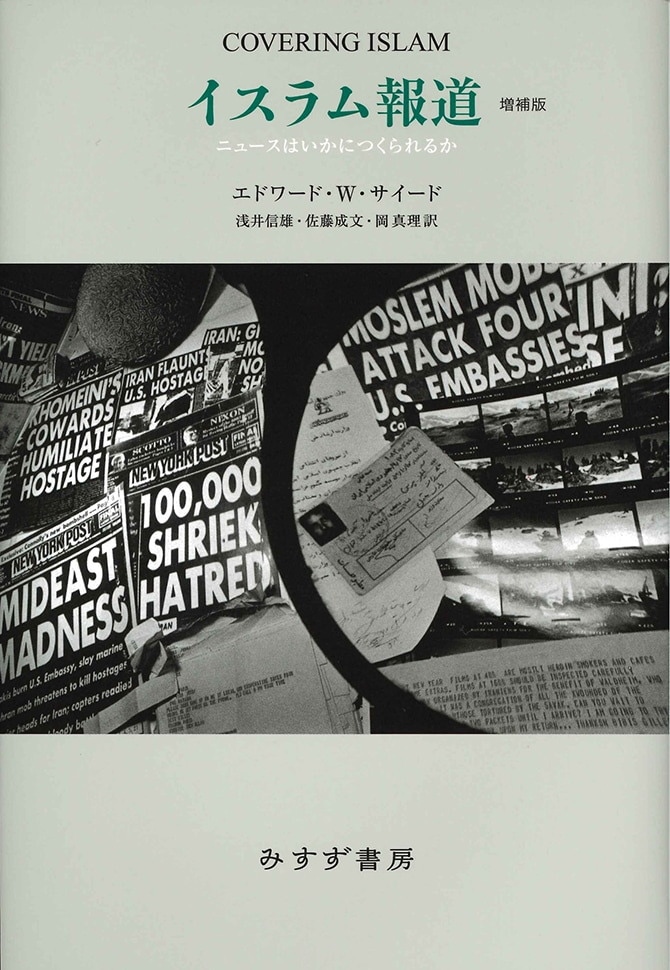
3. エドワード・W・サイード『パレスチナ問題』
杉田英明訳
西洋のオリエンタリズム的・植民地主義的な視点が、いかにイスラエルの視点にすりかえられ、そこから「アラブ」に対する歪んだ表象が生み出されてきたか。問題の起源からシオニズム、バルフォア宣言、イスラエル建国、四次にわたる中東戦争、キャンプ・デーヴィッド会談をへて1990年代へ。現代世界の矛盾の象徴であるパレスチナ問題への最も信頼に足る基本文献。
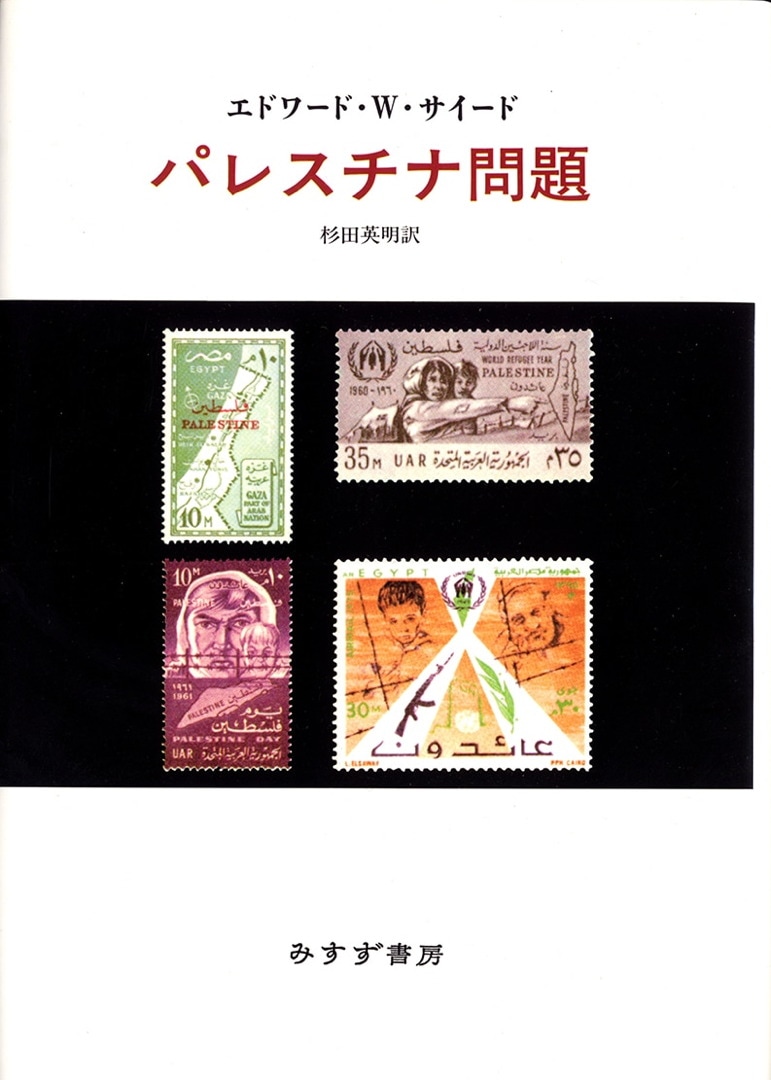
4. D・バレンボイム/E・W・サイード『バレンボイム/サイード 音楽と社会』
A・グゼリミアン編 中野真紀子訳
エルサレム生まれカイロ育ち、ニューヨークに住むパレスチナ人エドワード・サイード。ユダヤ人としてブエノスアイレスに生まれ、イスラエル国籍、ロンドン、パリ、シカゴ、そしてベルリンを中心に活躍する指揮者・ピアニスト、ダニエル・バレンボイム。つねに境界をまたいで移動しつづけている二人が、音楽と文学と社会を語り尽くした6章。パレスチナとイスラエルの若き音楽家をともに招き、学んだワークショップの話から、グローバリズムと土地、アイデンティティの問題、オスロ合意、フルトヴェングラー、ベートーヴェン、ワーグナーなど、白熱のセッション。
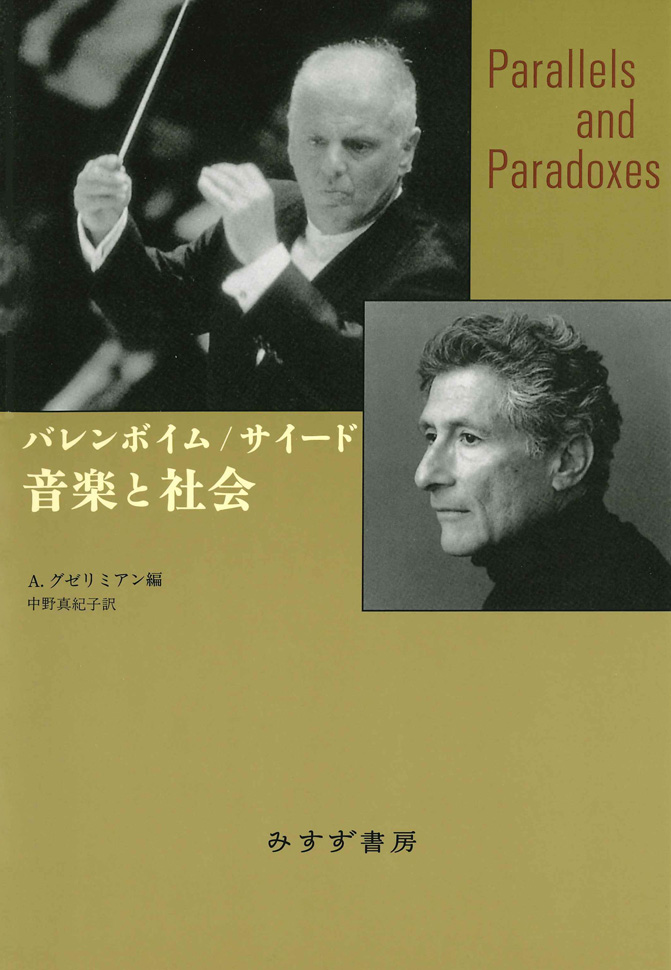
5. 岡真理 『アラブ、祈りとしての文学』
小説を書き、読むという営みは理不尽な現実を直接変えることはない。小説は無能なのか。悲惨な世界を前に文学は何ができるのか。古くて新しい問いが浮上する。
ガザ、ハイファ、ベイルート、コンスタンティーヌ、フェズ……、様々な土地の苛烈な生を私たちに伝える現代のアラブ文学は多様な貌をもつ。しかし各作品に通奏低音のように響く、ひとつの祈念がある。「世界と私の関係性が変わる」傑作文学論。
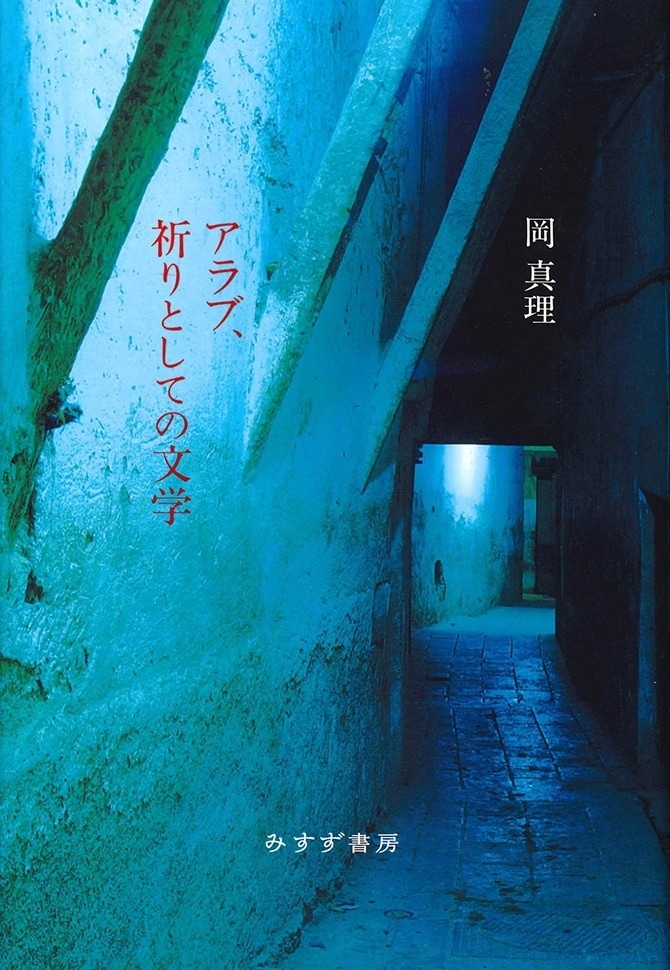
6. 岡真理『ガザに地下鉄が走る日』
イスラエル建国とパレスチナ人の難民化から70年。高い分離壁に囲まれたパレスチナ・ガザ地区は「現代の強制収容所」と言われる。そこで生きるとは、いかなることだろうか。著者がパレスチナと関わりつづけて40年、絶望的な状況でなお人間的に生きる人びととの出会いを伝える。
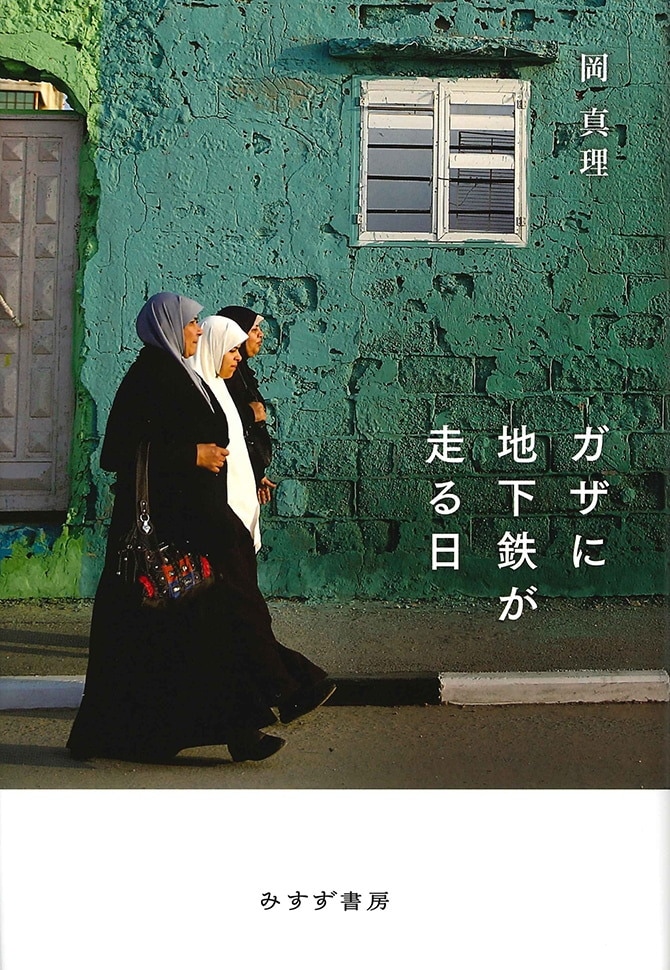
7. G・C・スピヴァク『サバルタンは語ることができるか』
上村忠男編訳
スピヴァクはデリダとマルクスの方法を武器にして、フェミニズムとポストコロニアルの問題圏の交差する地点から、現代世界における権力と知識の地政学的布置関係に果敢な介入をくわだててきた。本書は著者の代表作であり、ポストコロニアル批評の到達地平をしめす書である。
従属的地位にあるサバルタンの女性について、知識人は語ることができるのか。フーコーやドゥルーズを批判しながら、一方でインドの寡婦殉死の慣習を詳細に検討した、現代思想の傑作。
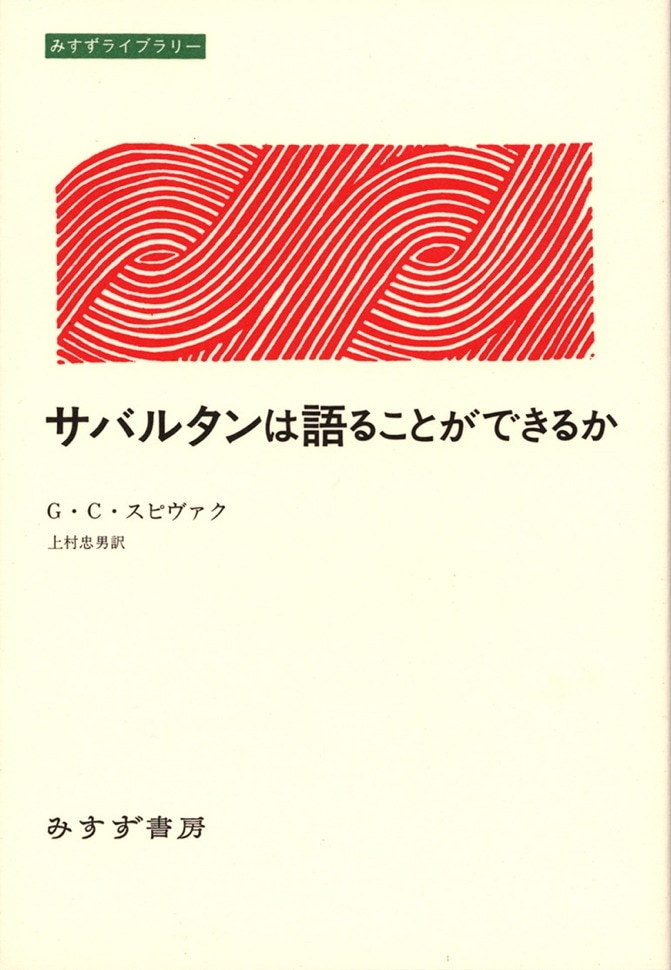
8. フランツ・ファノン『黒い皮膚・白い仮面』
海老坂武・加藤晴久訳
「ニグロは存在しない。白人も同様に存在しない。」
精神科医であり、フランス領マルチニック島に生まれたひとりの黒人でもある思想家、ファノン最初の著作。本書は、植民地出身の黒人が白人社会で出会う現実と心理を、さまざまな側面からえぐり出してみせた。内面においても自己を疎外する黒人に向け、解放を訴えたファノンの主著。
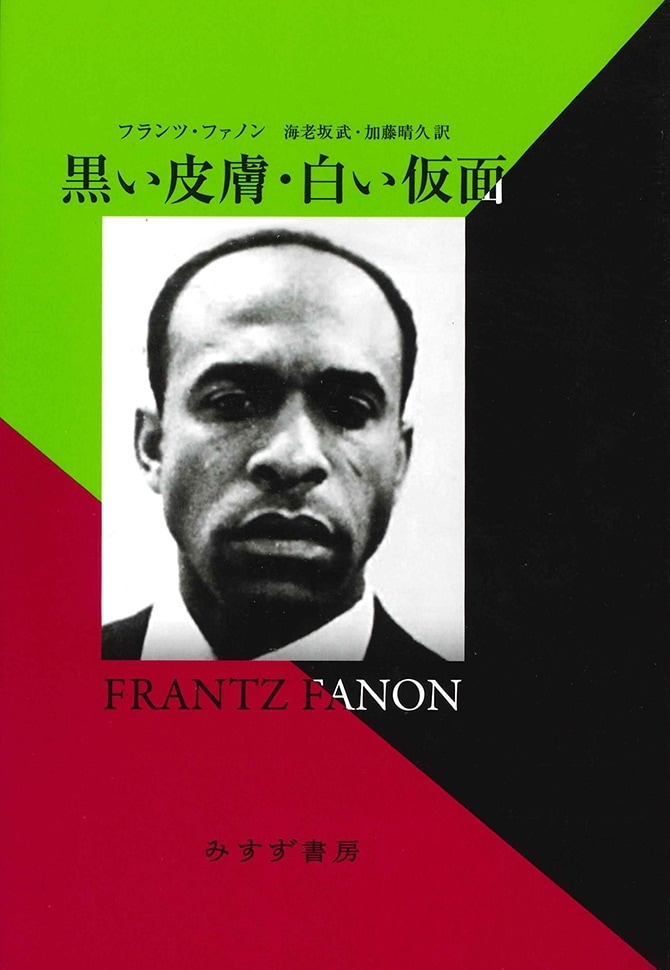
9. アラン・マバンク『アフリカ文学講義――植民地文学から世界‐文学へ』
中村隆之・福島亮訳
フランス語圏ブラック・アフリカの作家は、カリブ海やアメリカの黒人文学作家とパリでどのように出会い、みずからの文学を築き上げていったか。2016年、フランスのコレージュ・ド・フランス芸術創造講座で行われた「アフリカにかんする8つの講義」を収録。文学を超え、現代史や思想、社会問題にも広がる視野をもつ類のない文学史。
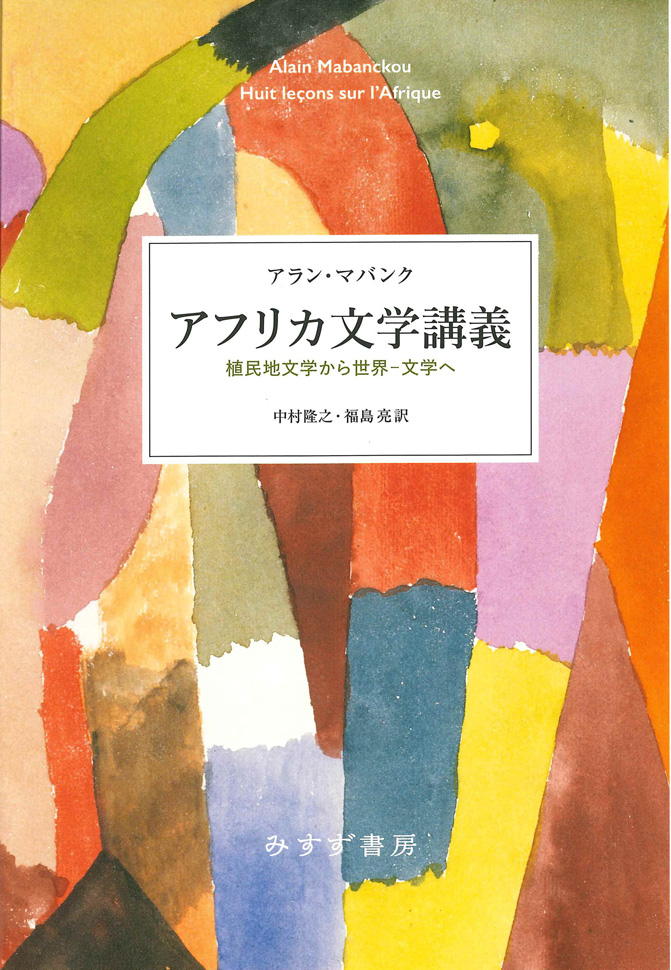
10. スーザン・ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』
北條文緒訳
本書は、戦争の現実を歪曲するメディアや紛争を表面的にしか判断しない専門家への鋭い批判であると同時に、現代における写真=映像の有効性を真摯に追究した〈写真論〉でもある。自らの戦場体験を踏まえながら、ソンタグは、ゴヤの「戦争の惨禍」からヴァージニア・ウルフ、クリミア戦争からナチの強制収容所やイスラエルとパレスチナ、そして2001年9月11日のテロまでを呼び出し、写真のもつ価値と限界を検証してゆく。戦争やテロと人間の本質、同情の意味と限界、さらに良心の責務に関しても熟考をわれわれに迫る、きわめて現代的な一冊。