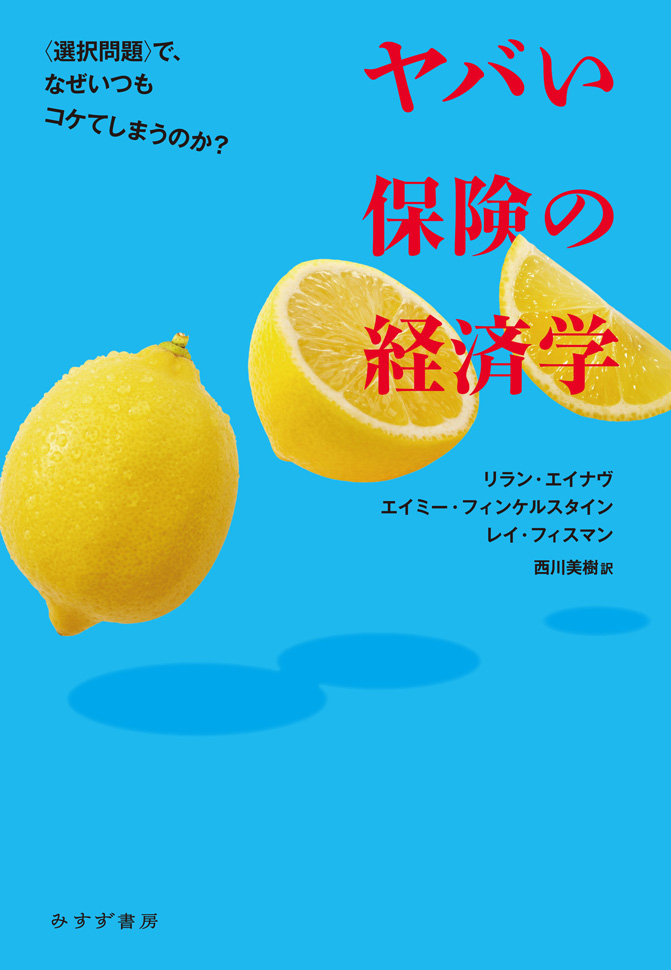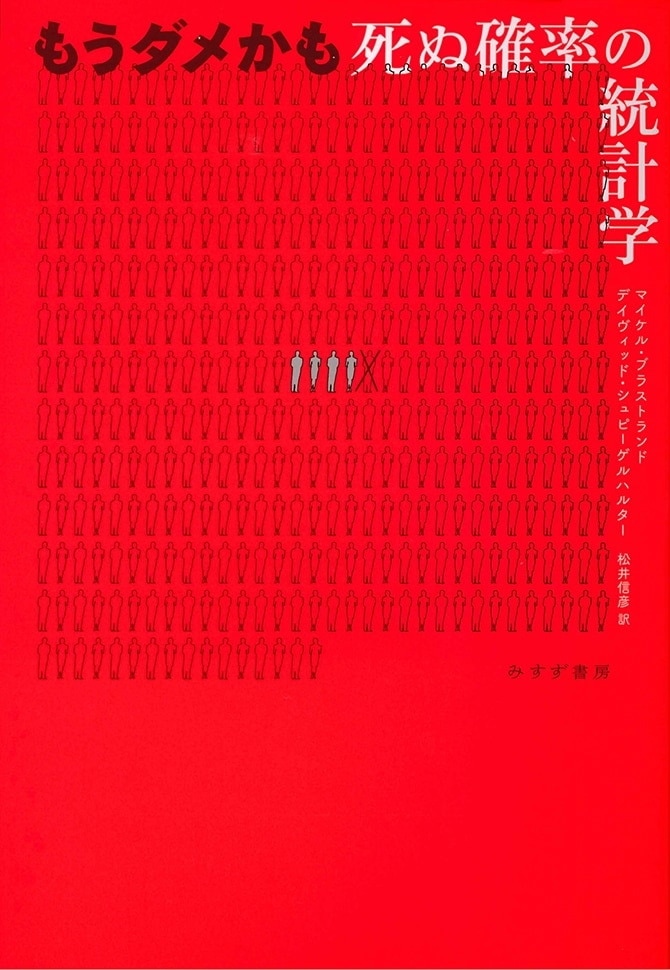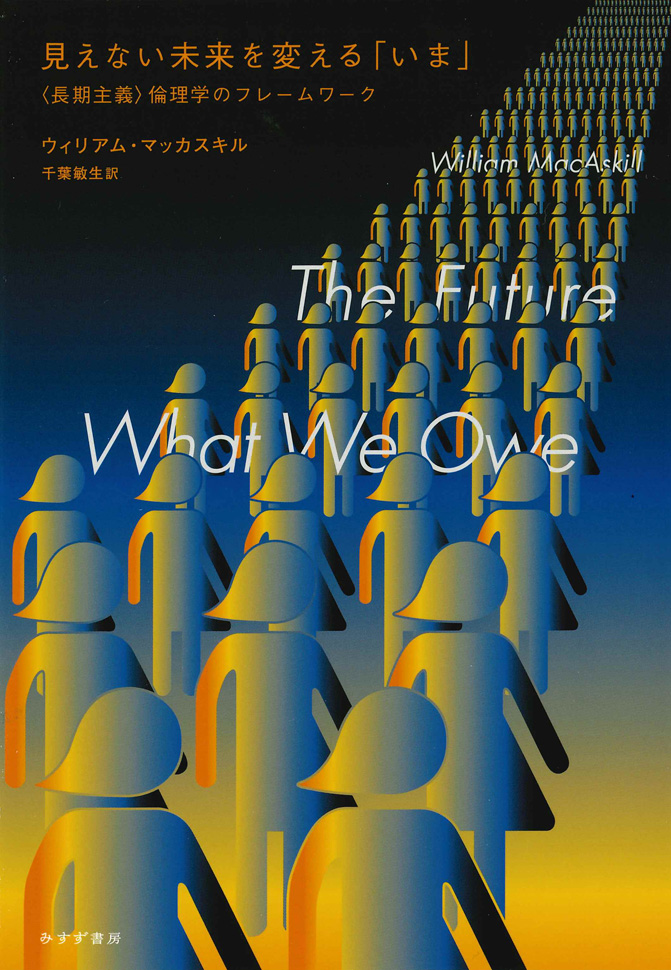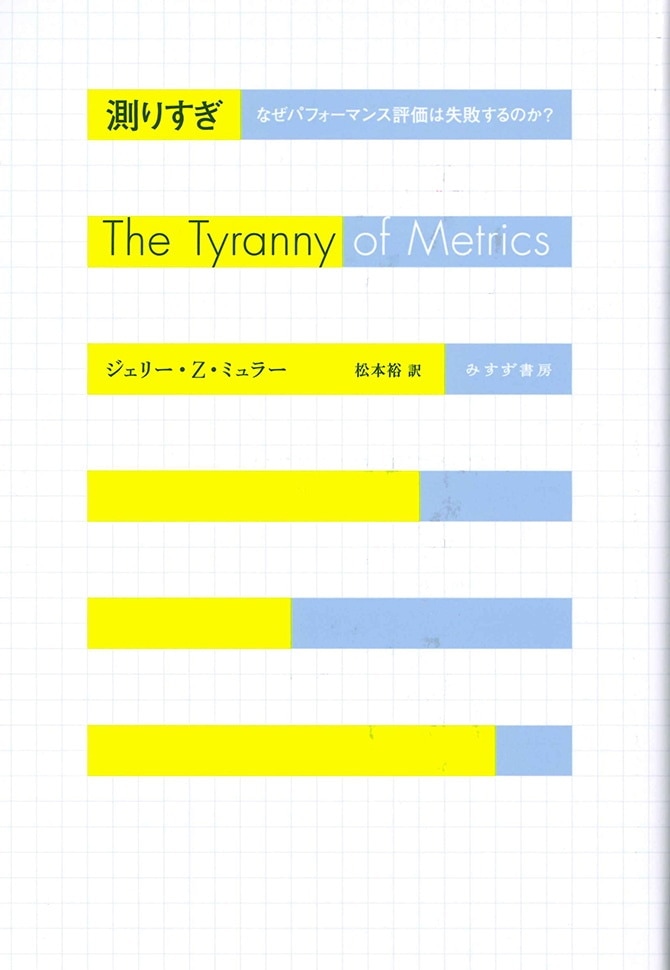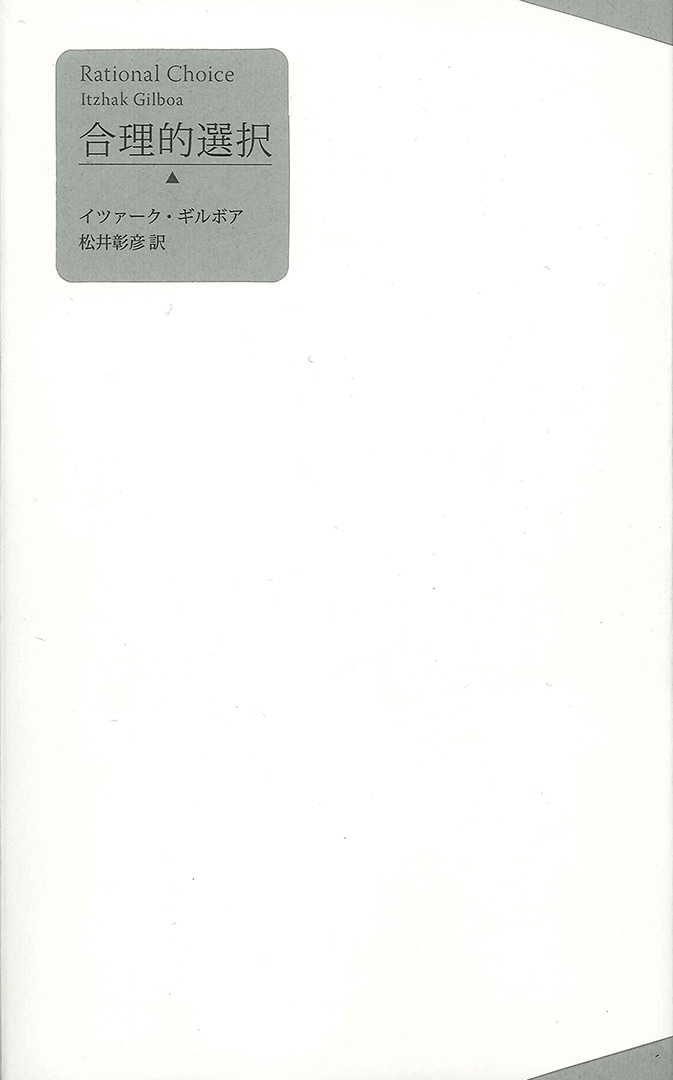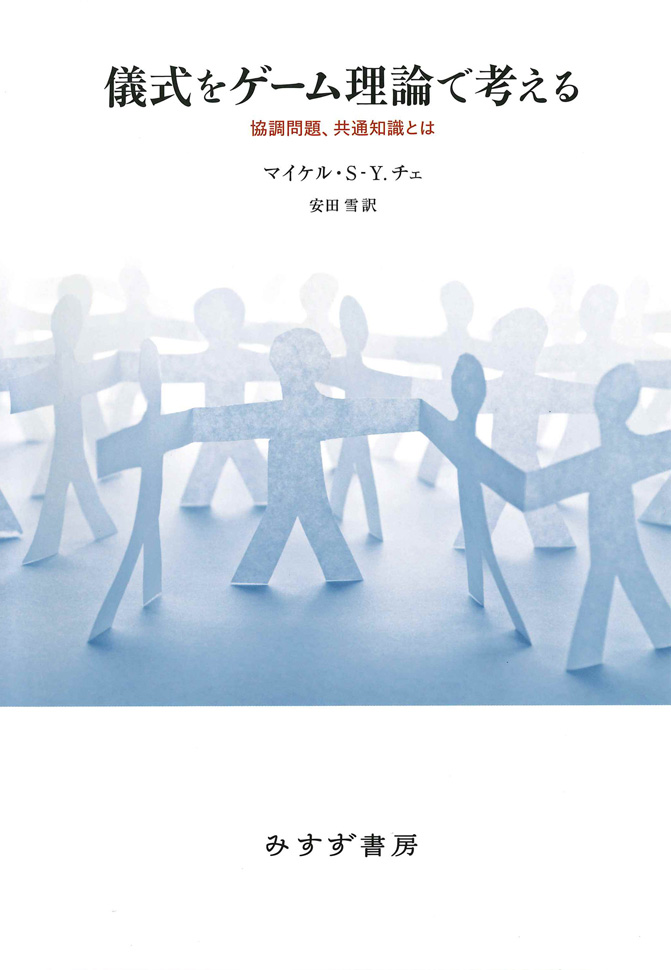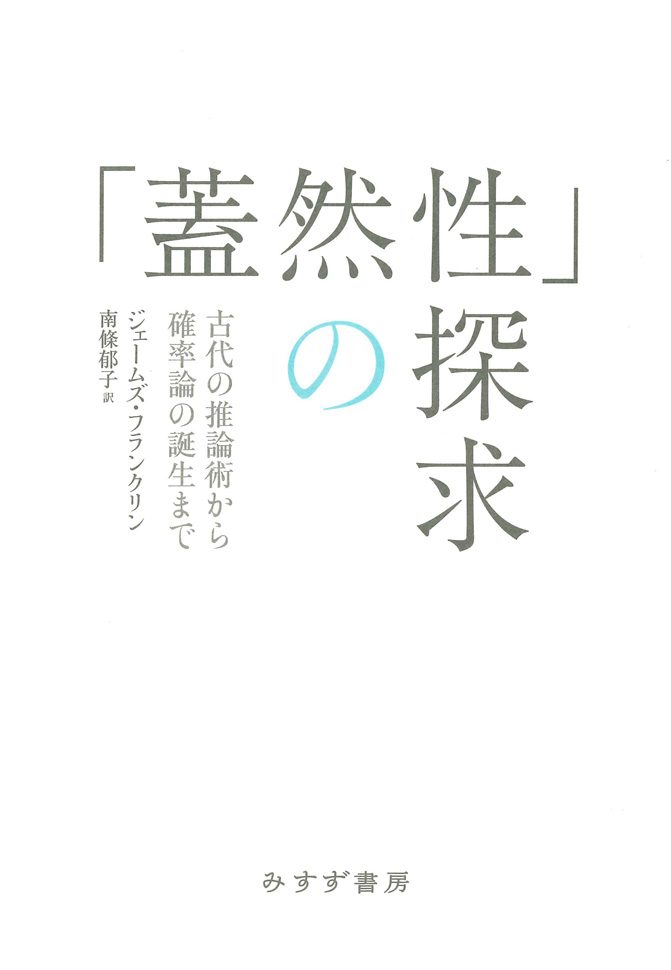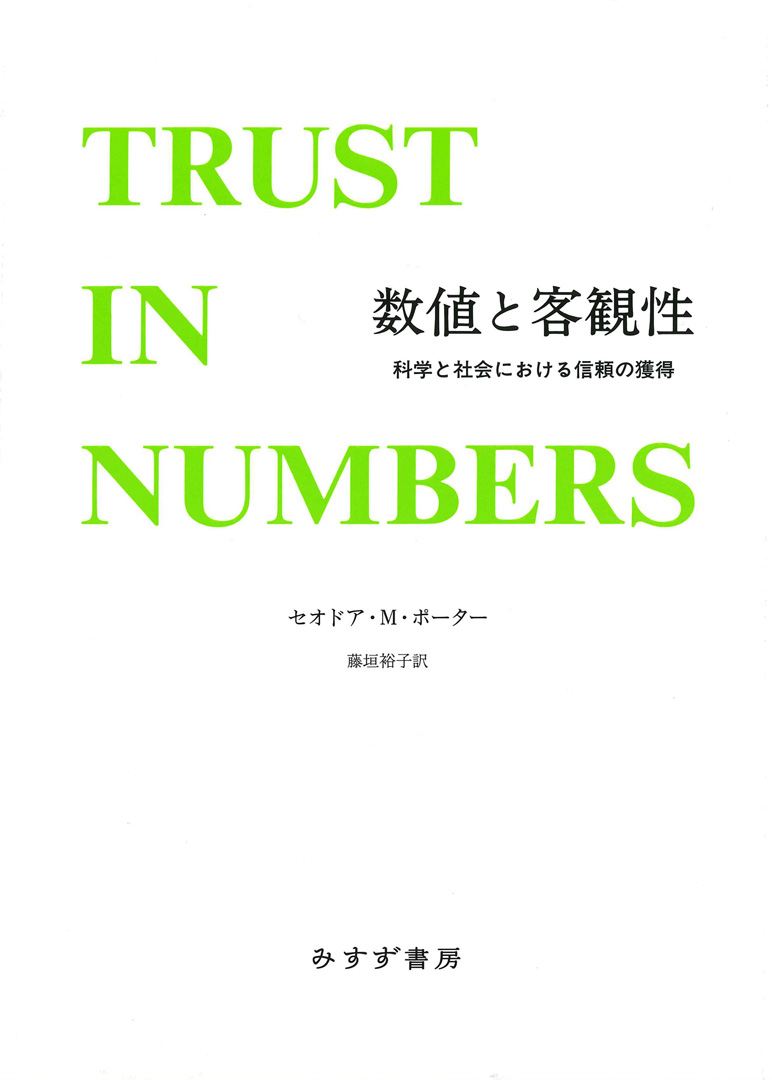9月の新刊『ヤバい保険の経済学』はタイトルの通り、保険や年金がテーマ。顧客としては保険に加入すべきかするまいか悩ましいし、保険会社としてはこの顧客に加入してもらってよいかどうかが悩ましい……。保険加入以外にも、人は生きていればリスクの評価と判断が必要な場面がどうしてもやってきます。今回のブックリストでは、選択や意思決定に役立ちそうな、みすず書房の本をご紹介します。
1. L・エイナヴ/A・フィンケルスタイン/R・フィスマン『ヤバい保険の経済学――〈選択問題〉で、なぜいつもコケてしまうのか?』
西川美樹訳【2025年9月最新刊】
保険会社は生命保険をなるべく健康な人に売りたい。しかし、生命保険を強く求めるのは健康に不安がある人たちだ。さらに政府は、国民の健康を守ろうと必死に制度設計するが、そのデザインは常に情報市場に裏切られる……。このような、複雑至極な保険市場のヤバくてリスキーな実態をユーモアたっぷりに明らかにするのが本書。これまでありそうでなかった、保険市場の経済学入門。
売り手と買い手の情報格差によって、安くて粗悪な商品ばかりが出回り、高くて品質の良い商品が出回りにくくなる市場のことを、中古車の英語でのスラングであるレモンにたとえてレモン市場という(保険市場はレモンだらけだ)。これがカバーのレモンの理由。
2. M・ブラストランド/D・シュピーゲルハルター『もうダメかも――死ぬ確率の統計学』
松井信彦訳(2020年刊)
「死ぬ確率の統計学」とサブタイトルのついた本書を、無味乾燥な数字を分析したものと思うなかれ! 本書は、一見冷徹な確率計算とかけがえない人生の物語とを組み合わせ、日常に潜むリスクとその意味を、冷静かつドラマチックに読み取れるように書かれている。統計の中の「1」の死と、この世で唯一無二のあなたやあの人の死を合わせて考えると、リスクはどんな顔をみせるだろうか。遊び心をふんだんに散りばめた書きぶりも魅力。
3. W・マッカスキル『見えない未来を変える「いま」』
千葉敏生訳(2024年刊)
リスク評価という話題では本書も。『もうダメかも』が個人の生死の話なら、本書は地球の存亡という壮大な話を大真面目に取り扱う。遠い未来に生まれる人びとの合計は、これまでこの世に生まれた人の合計とは比べ物にならないほど多い。そうであれば、未来の人びとにこの地球をきちんと引き継げるような行動をとるべきである。これが本書の基礎となる発想。気候変動や核戦争をはじめとする地球の存亡にかかわるリスクを今使えるあらゆるデータをもとに算出し、いま生きている人びとがとれる効果的な行動を考察する。決して悲壮的ではない、ポジティブな提言の書。
4. J・Z・ミュラー『測りすぎ――なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?』
松本裕訳(2019年刊)
「世の中には、測定できるものがある。測定するに値するものもある。だが測定できるものが必ずしも測定に値するものだとは限らない」(p.4)。データをもとに判断することは重要だ、というのは現代人の多くが認めるところだが、その判断に本当に重要なのはどのデータなのか? 無駄としか思えないデータやエビデンスが蓄積していく社会で、本当に重要なことを考えるための一冊。
5. I・ギルボア『合理的選択』
松井彰彦訳(2013年刊)
「私は全ての人が本書に含まれているようなことを知るべきであると考えており、個人的にはここで議論される問題を全ての有権者が理解しているような社会に住みたいと思っています」(p.10)。著者がこうまで書くだけに、本書の射程は基本的かつ実践的。合理的選択とはいかなるものか、という話に始まり、複雑でとらえにくい現実をなるべく適切にとらえて選択を行うために精選された重要概念が記されている。自由市場を扱うChapter 8では、保険市場の「選択問題」をはじめ、市場で生じる一筋縄ではいかない問題の例を知ることができる。
6. M・S-Y・チェ『儀式をゲーム理論で考える――協調問題、共通知識とは』
安田雪訳(2022年刊)
本書が扱うのは、「みんなが見ている映画なら見たい」「みんなが買っている商品なら自分も欲しい」「みんなが参加する飲み会なら行きたい」といった問題(協調問題)。協調行動や集団行動の発生には「「人々がその事実を知っている」ことを、みんなが知っている」こと(共通知識)が重要だ、というのが本書のメッセージ。そうしてみれば、権威への服従という集団行動も、この考え方で考察できる。本書が重要視するのは、多くの人が参加する儀式を通じて、「ほかのみんなが知っていることを、みなが知る」、という事実。いくつかの儀式の実例をもとに、人々の意思決定と社会現象のメカニズムに迫る。
7. J・フランクリン『「蓋然性」の探求――古代の推論術から確率論の誕生まで』
南條郁子訳(新装版2023年、初版2018年刊)
不確実性が「確率」という数学で扱われるようになったのは、1653年のこととされている。ではそれ以前、人々は不確実性を前に手をこまぬくばかりだったのかといえば、そんなはずはなかった。本書は、確率の登場以前に「蓋然性(=確からしさ、プロバビリティー)」がどのように取り扱われていたのか、その歴史を繙いたものである。史料からは、法・科学・商業・哲学・論理学を含む圧倒的に広範な領域で、驚くほど精緻な考え方がなされていたことが見いだされる。そのなかには、保険料や年金額算定に必要な「リスクの蓋然性」の検討も含まれる(10章)。本書以前の確率前史を刷新する著作。
8. T・M・ポーター『数値と客観性――科学と社会における信頼の獲得』
藤垣裕子訳(新装版2024年刊、初版2013年刊)
なぜ「数字は正しい」のか。現代社会や政治では、費用便益分析やリスク定量化が強い信頼を得て、事業の推進にはなくてはならないものとさえ考えられている。本書は、現代社会における定量的方法の威信と力の根源を理解することを目的に書かれた。本書の切り口はさまざまだが、経済学と財政分野に着目した5~7章が、本ブックリストのテーマに沿う。数値化やそれにともなう没個人化は信頼を獲得するために欠かせなかった、という指摘が、数字による判断と客観性の本質を浮き彫りにする。