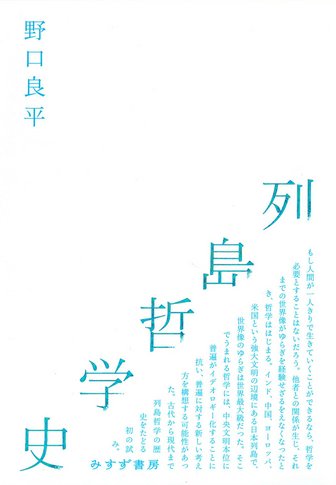いま、列島哲学は僕らに必要とされている
【書評】野口良平『列島哲学史』
2025年12月1日
哲学がはじまって、深まっていくときの、その様態を摑むこと。日本という国がくぐり抜けてきた、長く果てしない時間に対する思念。哲学とは、日本とは何か、を同時に問うことは、たとえるなら右手と左手で別々のフライパンを操るような、たぐいまれな器用さが求められる思索でもあるのだが、この本は果敢にもそうした困難に真正面から立ち向かっている。
しかし野口は、中江の言い方は正しいが、間違ってもいるという。日本には列島で生まれた哲学がなかったからこそ、育まれた思惟があったのではないか。不在があったという指摘は単純な言葉遊びではなく、そこに「せめぎ合い」が生じていた事実を教えるものであり、揺れて動く、列島の精神史をつぶさに見ると、紛れもなく「哲学のモト」が存在していたことを看取できるのではないだろうか。
そう考えながら、この島国がまだ日本と呼ばれていなかった太古から戦後にかけての思想の歩みを言葉のうちに象っていく本書は、興奮を隠さずに読めないほどに独創的だ。地理的条件がゆえに「外」と「内」を意識せずにはいられなかった日本はたえず優者(「外」)に対する劣者の立場に置かれ続けてきた。劣位の側から優位にいる存在へ対峙することを漫才の原点でもある「太夫と才蔵」をモデルにしてとらえる野口は、沈黙からロゴスが生成される過程を精妙に論じていく。
孤立していた列島が、対他的な意識のもとで辺境にいる自覚を抱き、やがて鎖国へと向かう。「日本人」という自意識はそのなかで芽生えたもので、本書ではその最初期のあらわれを『日本書紀』のなかに見ているが、それはつまり、少し前に流行った国民国家批判とは別様の、あのポストモダン的な視座からの考察よりも射程の長い、〈わたしたち〉の摑み直しなのである。
〈他〉あるいは〈異〉なるものと出会った列島の人々は、大陸から流れ込む思想に刺激を受けながらも警戒心を高めていった。そのさきで展開されるのが鎖国だったが、それによって生じることになった変化の遅滞を、野口はG・H・ミードの言葉を借りて「遅れ反応」と呼ぶ。それは「自己の反応を遅らせることで、問題解決に必要な過去の記憶と未来への洞察を育てるプロセス」のことなのだけれど、そうした概念によって結晶化されるものをふた文字で言い換えれば「文学」となるだろう。この列島で示された「遅れ反応」とは、まさしく「文学」的な成熟のことであり、本書は哲学とは何か、日本とは何か、に加えて、文学とは何かという問いの答えまで、僕の前に開陳しているように読めるのだ。
だからこそ、本書の中核には「『日本語』の生成」という問題が置かれる。外向けの文書だった『日本書紀』とは違い、内に向かって書かれた『古事記』は話し言葉の影響が見え隠れする書き言葉(和文)で紡がれていた。そこにあったのは無文字社会が「せめぎ合い」のなかで言葉を摑もうとした痕跡であり、ここに「日本語」の誕生を見ることは不可能ではない。そしてそのさらなる形成の様子を「漢字(男文字)とひらがな(女文字)のあいだでゆらぐ『私』の像」を綴った『土左日記』や「漢字とひらがなとに見事な均衡を与えた」随筆文学の嚆矢である『徒然草』のなかに見る。
つまり「日本語」とは、「外」(漢語)への抵抗によって生まれた、しなやかな弱さを持つ言葉だったのであり、その生成にこの列島の精神性が宿っている言語なのだと本書は教えてくれるのである。
たえず揺動する思考と言葉。日本の哲学的な信念はそうした不安定な地盤の上でかたち作られていた。中世になり、『源氏物語』的な「あはれ」の世界から武士社会の荒々しさによって生まれる「無常」の世へと移ると、「実存的なよるべなさ」から末法思想が生まれたが、そこで「無力な個を自覚せざるをえなかった人びと」は「強力な文明が主導する『上からの普遍性』に拮抗し、無力のなかで信じるに足る事柄を探り合う、『下からの普遍性』の領域を発見」したのだと野口はいう。「下」とは「公」(上)に対する「私」であり、個としてのひとのこと。列島的な精神のダイナミズムをそのような思惟様式として見定めたところに、この本のじつに鋭利な洞察眼がひかっているのだ。
さて、本書と近い時期に刊行された歴史書に、やはり日本の思想史をユニークな視点で編み直した原武史『日本政治思想史』(新潮社)がある。丸山眞男の見事な批判的継承である同書と本書を並べると、列島で人々を動かしていた思想の様態を「上」からと「下」から、両方の視点で見つめることができると僕は感じている。
この本で原は戦後も変わらず天皇が権力の主体となっているわけを問うのだが、その解を導くのにイデオロギーのような共同性の側から考えることはしない。むしろ同書では、日本には体制イデオロギーは「国体」を標榜していた戦前・戦中の頃も、朱子学や儒教が盛んに説かれていた近世の時代も、決して根づいたことがないという歴史的な事実が検証されるのである。
では原は、この国で支配的な政治規範は人々の意識をどのように縛りつけてきたと考えているのか。ここが同書で最も批評性が発揮されるところなのだが、日本の支配者が空間をとおして(また鉄道が開通してからは時間によって)人々に規範を内面化させてきたことが暴かれるのである。
「支配者の資質とは関係のないフェティシズム(物神崇拝)に基づく支配を、『視覚的支配』(Visual Domination)と呼ぶ」原は、「支配者の顔が見えづらく、いったん確立した制度のフェティシズム化が進行しやすい」日本では、「イデオロギーではなくシステムの支配が確立されやすい」ことを見抜く。大名行列、皇居前広場、列車……。こうした公共的な空間をとおしていかに権力者の精神的な支配が確立されていったのかが論じられるのが、原の『日本政治思想史』なのだ。
この議論を『列島哲学史』に接続させるとどうなるだろう。野口は荻生徂徠の思想を読み解きながら、近世という時代には「『公』こそが普遍であり、『私』は取るに足りない下位範疇として定位された」と論じる。そして、「『近世的』とは、この『上からの普遍性』に基づく公私観の特質を意味する語でもある」ともいうが、近世の日本では「公」(「政治と学問の世界」)が「私」(「道徳と文学の世界」)を凌駕し、締め付けていたのだった。
そうした「上からの普遍性」は列島に生きる人々によって内発的に摑まれたものではない。だから、イデオロギーとして根づかない。その代わり、日本の人たちは視覚的に支配されることになったと考えられよう。もちろん原が言うように、近世に「公共性」という概念が成立していたとは言いがたいが、少なくともその下地はあったわけであり、空間をとおした「視覚的支配」は、もう一つの「上からの普遍性」として日本人の「私」性を抑圧したのだと言えるのではないか。
ここからは、「公」と「私」の「せめぎ合い」こそが近世以降の日本列島に固有の問題だったことがわかるだろう。野口は本書で、前者が後者を支配しがちなこの時代にあって、「私」の側から考えることで「公」へと至る理路を作り出そうとした只野真葛という、多くの歴史書に無視されてきた孤独な女性の思想家にひかりをあてる。聖賢の道を歩くことのない小さな人たちが私利私欲をとおして道を見いだす、その方途を考えようとした彼女の言葉をたどることで、「私」のいる場所からはじめて普遍性を摑むという、ヨーロッパ哲学に極めて近い思考の原理を取り出すのである。
野口のこの着眼は、これからの日本思想史に大きな課題を与えるはずだ。野口はほかにも漂流経験を持った近世の日本人に近代的な思想の萌芽を見るが、マージナルな場所にいた人々が「上からの普遍性」を突き崩せる可能性を手にしているのはなぜか。その検討は進まねばならないだろう。
野口が只野真葛に発見した〈「私」から公共性へ〉という思考様式は、加藤典洋が戦後思想の礎に置いたものだった。私利私欲を基礎に考えなければ、公共的な政治性は作りえないというのが加藤の主張だった(『戦後的思考』)。その思想を正統的に継承する野口は、只野が示したような、「内在」的な思考の花ひらく様子を幕末の日本社会に観察する。
じぶんのいる場所から考えを推し進める「内在」と、外部からの刺激をとおして他者との関わりのほうへ思考をシフトする「関係」。加藤は「内在」から「関係」に思考法が移るときのゆらぎに思想的な深まりを見たのだったけれど、本書では、そうした豊かな対話をとおして列島の思想が深化するうごめきが、幕末の思想家たちのうちに探られる。そこが本書の白眉であり、日本の思想がヨーロッパ哲学にはない――「日本語」がほんらい持っているあの柔軟さを基にした――しなやかな身体性を獲得する可能性があったことを僕らは知ることになるのだ。
しかし、その希みは近代文明の到来、たび重なる対外的な戦争のなかで失われてしまう。「上からの普遍性」は、原の言う「視覚的支配」によって完遂され、「公」と「私」の「せめぎ合い」のダイナミズムを、本書で触れられる中里介山や永井荷風など一部のひとを除いて、多くの「日本人」は棄捨してしまった。そしてそのまま戦後社会がやってくるのだが、だからこそ、いま、列島哲学は僕らに必要とされている。
本書では敗戦後も「私」の場所から考える権利を手放さなかった鶴見俊輔、福田定良、竹田青嗣、加藤典洋の思索が断章的に、最後、紹介される。そういえば、原の『日本政治思想史』でも「下からの民主主義」という項が立てられ、「上」から押し付けられる民主主義(普遍性)をただ受け取るのとは別の回路を見いだした思想家として、丸山眞男と小林一三が挙げられていた。
野口は本書の最初で「哲学とは何か」と問い、みずから答えている。「人間が世界像のゆらぎを経験した際に、自分ともう一人の自分、自分と他人(たち)との対話を通して、自分の視野を育て、態度を整えていく努力。またその努力を支えうる方法。それを私は哲学と定義する」。列島的な精神とはこの対話のなかで育まれるものだった。ネット空間で押し付けられる普遍性に素早く反応することが求められる現在の時代にあって、「外」との対話、そして、反応の遅滞によって育まれた思想を取り戻すことは単なる復古ではなく、未来を作る営為なのだと本書は示している。
(評者:長瀬海 ライター・書評家)