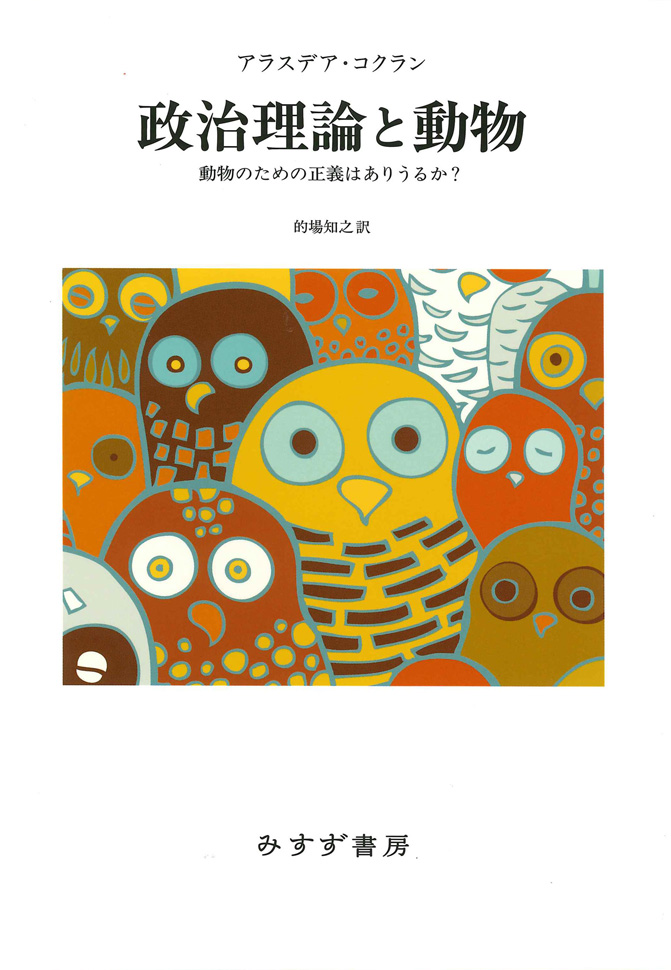動物倫理の政治的転回
【書評】アラスデア・コクラン『政治理論と動物』
2025年9月1日
哲学は世界を変える。少なくともここ数十年のうち、世界を最も大きく変えた哲学書はピーター・シンガー『動物の解放』(原著1975年)だろう。この書は、現代社会が食肉生産の効率化のために推し進めた集約的畜産が動物にもたらしている悲惨な状況を背景に、功利主義の立場から動物の道徳的扱いを論じた。シンガーの議論は世界に衝撃を与え、「動物倫理」と呼ばれる応用倫理学の一領域を切り開いた。現在では、動物への向き合い方が少なくとも真剣な倫理的考慮に値することを多くの人々が認識するようになった。これはシンガーの著作以前には考えられなかった世界の変化だ。
本書『政治理論と動物――動物のための正義はありうるか?』(原著2010年)は、そうした流れの延長にある重要な一冊だ。著者はイギリスのシェフィールド大学で政治理論の教授を務めているアラスデア・コクランであり、その最初の著書である。本書はパルグレイヴ・マクミラン社の「動物倫理」シリーズの最初の1冊として公刊された。このシリーズは2025年時点で60冊以上にのぼっており、動物倫理をめぐる学問的アプローチが驚くほど多様になっていることがわかる。コクランにはその後、『解放抜きの動物の権利』(1)(2012年、未邦訳)と『有感主義の政治』(2)(2018年、未邦訳)、『動物は政治的権利を持つべきか?』(3)(2020年、未邦訳)の3冊の著書がある。コクランはこうした著書によって、動物倫理の「政治的転回」の主導者とみなされている。
動物倫理の政治的転回
動物倫理の「政治的転回」とは何か。それは動物を「正義」の対象として扱うべきだという発想の転換である。人間の社会は例外なく、人間以外の動物たちと相互作用しながら存続している。その関係を「政治的」なものとして見るということは、動物を政治共同体の「正義」の対象に含めるということだ。ここには2つの重要な意味がある。人間と動物との関係は、個人の生き方や心構えとして説かれる「倫理」を超え、ときに法律のように強制力をともなうルールによって規律される。そして、そこでの動物たちは正義に「値する」存在として、人間ではなく動物自身の権利や利益のために扱われる。
さて、政治理論はそのような存在として人間以外の動物を扱ってきただろうか。本書の第2章「政治思想史における動物」は、古代ギリシャ以来のさまざまな政治思想がいかにして動物たちを排除してきたかを描き出す。そこでキーワードになるのが「理性」だ。動物は理性を持たないがゆえに、正義の対象にならない――そのようにして人間と動物の間に本質的な線を「政治理論として」引いたのがアリストテレスであり、それを受け継いだストア派であった。キリスト教ではアウグスティヌスとトマス・アクィナスによって、理性をもった人間による自然の支配という自然観が確立された。その後のマキャヴェッリ、デカルト、ホッブズ、カント……など、近代の西洋思想の枠組みを作った思想家たちもそれぞれに、「理性」を基準として人間と動物の間に線を引いた。本書はそれぞれの思想家の議論のポイントを〈どのようにして政治共同体から人間以外の動物を排除してきたか〉という観点から読み解いてみせる。
人間と動物の関係から捉え直される本書の西洋政治思想史は、政治共同体からの動物の排除という一貫した問題意識によって理解しやすくなっている。その記述は全体に明晰であり、政治理論の教科書としても有用である。とはいっても決して一本調子ではなく、読者に注意を喚起する箇所も多い。たとえば動物の理性を信じたプルタルコスやポルピュリオスといった思想家の記述は、古代ギリシャ世界での動物正義論が現代に通じるような豊かな論点を有していたことを明らかにする。また、アウグスティヌスやトマス・アクィナスの動物観が、人間に動物を「治めさせる」という聖書の一節をただ反映しただけのものではなく、その国家観(神の国/地の国)に根ざしたものであることを確認しているのも手堅い。本書は全体を通じて功利主義に高い評価を与えているが、動物倫理の出発点とみなされるベンサムの有名な記述が実のところ1つの脚注であって包括的な理論ではないと確認していることもフェアな姿勢である。
現代政治理論と動物
本書の中心となるのは第3~7章、現代政治理論の有力な立場(順に功利主義、リベラリズム、共同体主義、マルクス主義、フェミニズム)での動物の扱いの検討である。思想史パートの堅実さに比べると、現代のそれぞれの立場に対する著者コクランの検討はメリハリが利いている。コクランは功利主義とリベラリズムを高く評価し、その折衷というべき「利害関心ベースの権利アプローチ」を主張している。その他の共同体主義、マルクス主義、フェミニズムについては、それぞれの動物正義論への貢献をある程度認めつつも、だいぶ消極的な評価がなされている。これはコクランの議論の保守的な性格を表しており、それは本書の個性でありつつ、深刻な問題を含んでいるともいえる。この点については後に検討する。
第3章「功利主義と動物」は、快楽と苦痛のみが道徳的に重要であるとする功利主義が、「福祉主義」と「平等主義」という特徴をもっていることを指摘する。ここで「福祉」というのは幸福、厚生、効用、ウェルビーイング、関心充足など、さまざまな言い方がなされるが、とにかく功利主義にとっての唯一の価値のことだ。それらは多かれ少なかれ、人間以外の動物も感じることができる。したがって「最大多数の最大幸福」という計算において、人間以外の動物も平等にカウントされなければならない。これが功利主義の「平等主義」面であり、それ以外の基準(「理性」など)で動物を排除するのは、シンガーが告発した「種差別」にほかならない。
功利主義からのアプローチは、動物倫理を考えるうえできわめて強力だ。人間もそれ以外の動物も、その福祉は平等に計算されなければならない。集約的畜産が膨大な数の動物たちに与えている苦痛をまともに計算するならば、それはすぐさま廃止されるべきか、少なくとも現在のあり方を大きく変える必要があるだろう。
一方で動物実験がどうあるべきかはもっと微妙な問題である。たとえば化粧品や洗剤、食品添加物などの安全性テストのために行われる動物実験は、かなり厳しく見られることになる。それに対し、医薬品開発目的の動物実験は将来の人間に与える利益がきわめて大きくなるため、功利主義的には――実験者がその利益を証明すべきという条件は必要だとして――必ずしも禁止されない。この結論が動物の利害関心に十分に配慮できていないと思われるならば、それは功利主義の関心があくまで福祉であって、それを感じる主体である動物自身ではないからだ。「動物権利論」はここに功利主義の限界を見出す。トム・レーガンを代表とする論者は、動物自身の存在に内在的な価値を認め、敬意をもって扱い、その基本的権利を守ることを主張する。
第4章「リベラリズムと動物」で著者は、リベラリズムの核心を「個としての人格の価値」の尊重に見出す。そして、現代リベラリズムの代表であるジョン・ロールズの議論が検討の対象とされる。ロールズは『正義論』(原著1971年)で、自分が何者かわからない「無知のヴェール」をかぶった「原初状態」での合理的な意思決定によって正義の原理が導出される思考実験を行った。これは「偶発的状況」に起因する人々の差異を正義の議論から排除するためのものだ。だとすると〈自分はもしかしたら人間以外の動物かもしれない〉とも想定すべきではないか。そうすれば動物の利害関心も組み入れた正義の原理が採用されるだろう。しかしロールズはそれを否定し、動物を正義の対象から排除した。ロールズの議論では、正義の対象となるべき参加者は互恵性と道徳的人格を備えていなければならない。同じ社会を協力して作り上げることが互恵性であり、善の概念と正義感覚の能力をもつことが道徳的人格の条件である。ロールズによれば、人間以外の動物はそれを満たしていない。
ロールズが想定する政治共同体の範囲が狭いことは、しばしば批判の対象となってきた。しかし「原初状態」の条件は固定したものではない。人々の「熟慮された判断」と絶えず照らし合わせながらその条件が問い直されるという「反照的均衡」の方法によるならば、ここで登場する「人格」の概念自体がアップデートされるべきかもしれない。動物権利論の代表的論者であるレーガンは、ロールズの枠組みをすべて受け入れることはせず、「人格」概念に集中した議論を行った。ロールズにおける人格はカント的な自律した主体が想定されているが、それは要求水準が高すぎる。代わって、ある程度の持続した意識と利害関心をもった「生命の主体」を敬意をもって接するべき人格の基準とした。その線引きが具体的にどのようになされるのかには曖昧な点があるが、リベラリズムが排除してきた動物のうちの相当の範囲が「人格」として尊重されるべきものとされた。
コクランはこのようにして、功利主義とリベラリズムの両者の長所を調停する鍵として、動物権利論の洞察を生かしている。動物の福祉を平等に計算に入れる点では功利主義が有望だが、それは動物自身には関心を持たないので多数の人間の利益のために動物を犠牲にする危険がつねにある。他方、リベラリズムは個としての人格を多数派から守るという長所があるが、その人格概念はしばしば狭すぎた。ここで動物権利論による人格の修正を受け入れるならば、人格性と福祉を両方とも尊重することが可能になる。つまり、福祉の最大化という功利主義の関心を維持しつつ、決定的に重要な利害関心については個々の人格がもつ権利として、多数派の利益に優越する形で保障される。これが著者のいう「利害関心ベースの権利論」である。
もちろん、では権利として保障されるべき利害関心とは何か? という問題が生じるのだが、これは今後に向けた開かれた問いとされる。ここで著者の強調する「政治的転回」は線引きの難しさを和らげる方向に働くだろう。私たちはすでにある程度、動物の中核的な利害関心といえそうなものを認識しているし、その一部は法的に強制力のある形で保護されるようになっている。この〈ゼロから考える必要はない〉ということも(その意義は十分に明言されてはいないものの)著者の議論を頑健にしているように思われる。
本書の保守性?
本書の後半は、共同体主義(第5章)、マルクス主義(第6章)、フェミニズム(第7章)における動物の扱いが論じられる。コクランはこの3つの立場について、自身の提示した「利害関心ベースの権利論」が現実の社会で有効なものとなるための重要な条件を示していると見ている。共同体主義の洞察は、動物もまた現実の社会に生きる存在である以上、「動物個体が充実した生を送れるかどうかはある種の共同体の支援次第(192頁)」ということである。またマルクス主義は、動物の権利を保障する法律を制定するだけでは正義にとって足りず、社会構造の抜本的転換が必要であることを強調した。現代の動物の利用が資本主義的生産様式によって効率化が追い求められた結果のグロテスクな姿であるならば、マルクス主義からの資本主義批判はいまなおオルタナティブを考えるための資源たりうるだろう。最後に、フェミニズムのうち「ケアの倫理」を重視する議論は、動物との関係における不正を人々に意識させ、変化に向けて動機付けるためには「理性」を超えた情緒的な想像力もまた一定の役割を果たしうるという洞察を示した。
コクランはこうしてこの3つの立場が動物正義論の〈現実的条件〉にとって重要な洞察を示していることを認める。しかし、それぞれに対する批判はしばしば一刀両断するようなものとなっており、自身のアプローチとの連帯の可能性を必要以上に狭くしているようにも思われる(本書に対する反応のうち、批判的なものの多くはその点に集中した)。たとえばマルクス主義については「動物を利益目的で飼育しつつ、動物に苦痛を与えないような資本主義社会を想像することは、少なくとも不可能ではない(148頁)」と述べ、自身の立場が動物の全面的な解放とは異なる、より保守的・漸進的なものであることが示される(誤解のないように付言すると、コクランの実践的な主張には相当にラディカルなものも多いのだが)。また、フェミニズムからの動物倫理については、女性と動物に対する抑圧が本質的に関連しているという想定には確たる証拠がない、と批判される。さまざまな社会的抑圧がしばしば交差的・複合的に作用するというのは現代フェミニズムの重要な洞察だが、それはまさに個々の現象に還元することの難しさを述べているのであって、コクランが求める実証性はそれとすれ違っている。そのため、傲慢な「理性」を超える想像力の可能性を制限してしまっている。
こうした論法は、コクラン自身の主張の輪郭を明確にするために必要なものとされたのかもしれない。しかし、そうした理論的洗練は同時に、他の立場との連帯の可能性を狭めていることも確かである。それだけでなく、とりわけマルクス主義とフェミニズムという代表的な「批判理論」とのこうした距離は、コクランの議論に否応なく保守的な性格を付与することになる。もちろん、新しい道具立てを使わずとも議論できるという意味での保守性はむしろ、動物正義論の理論的長所ともいえる。しかし、それが政治的な意味での保守性にも結びつくとき、はたしてそれがコクランの「政治的転回」のポテンシャルを生かす方向のものであるかどうか、という難題を引き寄せているようにも思える。
対話に向けて
ここまで本書についてやや踏み込んだ紹介を行った。ネガティブな点も指摘したが、それはコクランの記述が明快であるためだ。コクランによって批判されている共同体主義、マルクス主義、フェミニズムの論者はそれぞれ、コクランに反論することでその動物正義論を深化させることができる。比較的高く評価されている功利主義やリベラリズムも同じことだ。本書は将来の対話に向け、恐れることなく自身の立場を打ち出している。
この書評では動物倫理の「政治的転回」に注目した。多くの政治理論が参照され、動物との関係という問題意識からの一貫した位置付けを行ったことは本書の大きな功績だ。しかし、従来の動物倫理でおなじみの論者も多く出てくるため、その新しさがわかりにくいと感じた方もいるかもしれない。スー・ドナルドソン゠ウィル・キムリッカ『人と動物の政治共同体――「動物の権利」の政治理論』(青木人志・成廣孝 監訳、尚学社、2016年[原著2011年])のように、動物の政治参加の権利まで明確に論じている本もすでにある。この点についてコクランは、2020年の著書『動物は政治的権利を持つべきか?』で踏み込んで論じている。紹介は別の機会に譲るが、ここではコクランのいう「政治」は理論面にとどまらず、制度設計まで含めた実践も見据えていることを強調しておきたい。
最後に指摘した本書の「保守性」も、必ずしも悪い意味ではない。あらゆる「批判理論」が連帯しなければならないということはない。それぞれ評価できるところは評価し(本書でも実際になされている)、そうでないところは違いをはっきりさせるほうが、さらなる対話につながるだろう。また、コクランの議論に内在的にいえば、コクラン自身が社会の全面的な「革命」を目指すような議論を望んでいないということでもある。2冊目の著書『解放抜きの動物の権利』はシンガー『動物の解放』を意識したものだが、動物の全面的な解放なしでも動物の権利を尊重できるという主張が展開されている。たとえば、動物が人間に所有されつつ、それでも倫理的な扱いを受けることはできるといったことだ。そうした姿勢は本書でも随所に見られる。これまで動物倫理に関心はあるもののあまりに根本的な主張にはついていけないと感じてきた読者は、コクランの「現実的」な議論に触れてみると印象が変わる部分もきっと多いはずだ。
注
- Cochrane, A. (2012) Animal Rights Without Liberation: Applied Ethics and Human Obligations. Columbia University Press.
- Cochrane, A. (2018) Sentientist Politics: A Theory of Global Inter-Species Justice. Oxford University Press.
- Cochrane, A. (2020) Should Animals Have Political Rights?. Polity.
(評者:吉良貴之 法哲学)