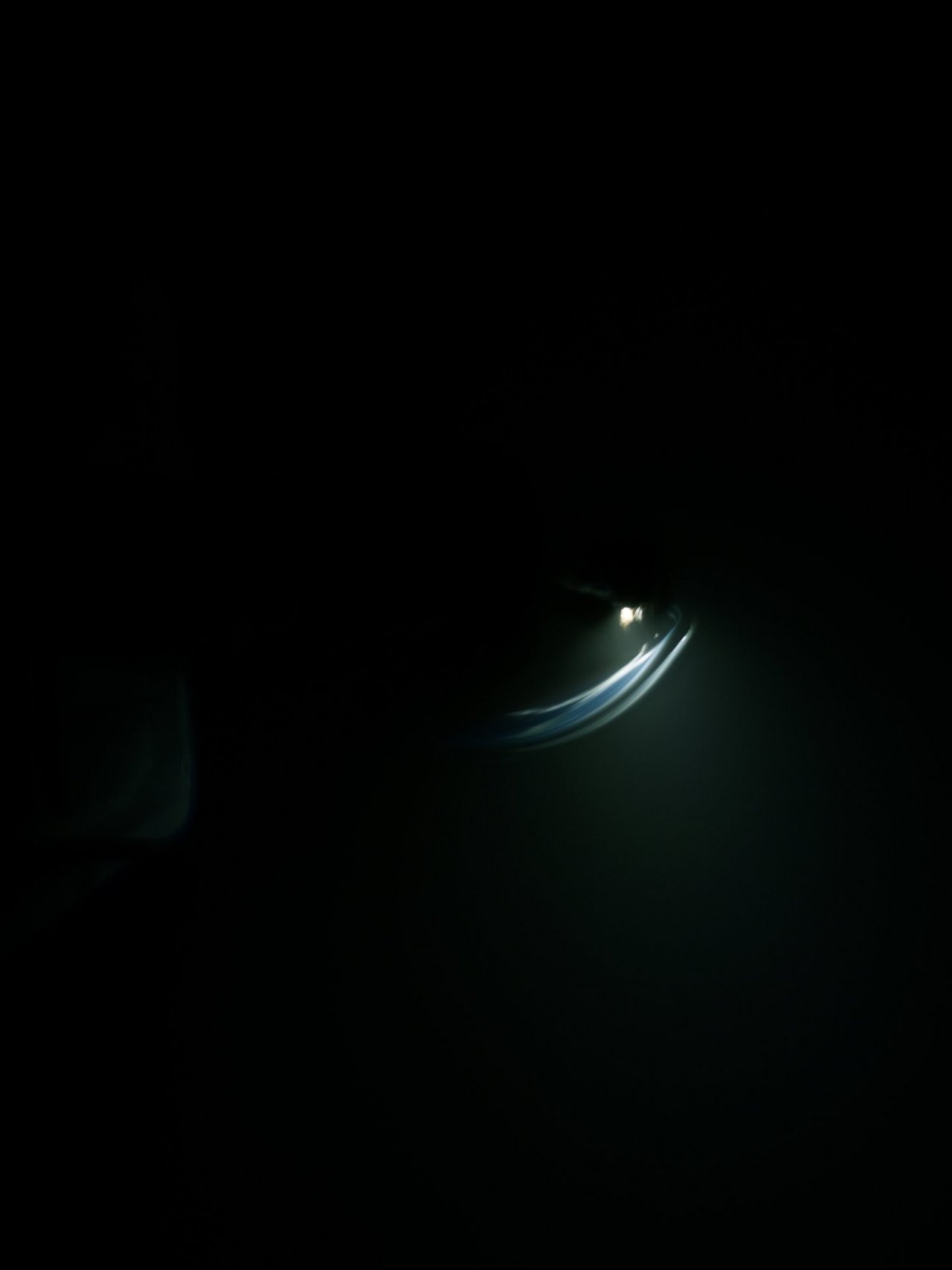この地の春を初めて経験したのは、冬の2シーズン目の後だっただろうか、3シーズン目の後だっただろうか。時日の情報は曖昧なのに、五感で捉えたその春のことは、何年も経った今も、昨日のことのように心身に刻まれて残っている。
私を家に招じ入れてくれたおじいさん、おばあさん、その後も、訪ねた家に上がるよう誘われ、もてなしを受ける経験を幾度も持った。いずれも初対面であった。私は紹介状もなく不意に訪れ、「写真を撮っています。ポートレートのモデルをお願いできませんか?そのまま、そこに立って(と私は指で屋外のその場所を示す)、お時間は取らせませんので」と尋ねるのだが、我がことながらいかにも不審で、東京ならば警察に通報されかねないのに、「あたっていかねか(上がって火で暖まってゆきなさい)」という挨拶の言葉を、見ず知らずの私にまで使ってくれるばかりか、やはり「何にもねぇでも、あがらっしゃい」とご馳走が振る舞われることも少なくなく、ここは稀有な場所と思った。その土地柄に助けられ、つながりも徐々に形成され、地元新聞の取材を受けて紙面で撮影協力をお願いしてからは、通りすがりの人に声をかけられたり、メールで撮影の連絡をもらえたりするようになり、やがて、雪山に行く猟友会やマタギの人に同行を許されるまでになった。
私は、会う人会う人に、「雪はどうですか?」と判で押したように問うていた。私が「雪を撮っています」と言うと皆、驚いたような、それとも、理解できないというような表情を浮かべるからだった。答えの方もまた、判で押したようで、「雪は降るときゃ大変大変。だども、春がさ、いいやんそぉ」だった。私は12月からの冬の100日を越えて春まで居残ってみようと決めた。既に、人の定めた「津南町」という境は越えて撮影を始めていた。今度は、「冬」という季節の境だった。12月の半ばに滞在を始めるから、「100日」は3月の半ばに来る。この「100日」の数字は、単に切りが良いというだけで、滞在の終了即ち冬の終わりは、私が勝手に決めた境にすぎなかった。
3月となる頃には、降雪はめっきり減って、関東の緯度とさして変わらぬこの地だから、陽の軌跡の高さも、ファインダーに見る光の強さも、その影の濃さと短さも、春のものにはなっていた。しかし、実感としては「100日」の終了は、冬の終わりがようやく見え始めた頃であった。
4月に入って、それからどのくらい経ったろう、ある日、水の滴下の音が耳に入った。一つに心づくと、そこかしこにその音があった。最初はその正体が見あたらず、もちろん幻聴のはずもなく、不思議だった。
積雪の中から、と気づいた。
冬の間に、積もりつづける湿雪は、昼間は緩み、夜間は締まりを繰り返すうちに、丸みを帯びた造形となる。あるものは大波のように、またあるものは多段の鏡餅のように、そしてまたあるものは一抱えの鞠のように…。滴下の音の在り処は、雪の、その球体の奥だった。
ピツンッ。 ピツンッ。 ピツンッ……
丸い形状の雪塊の内部の雪が融けて空洞が生じ、それが広がってドームに変じてゆく際の滴の音だった。一滴一滴のその音ほど、冬のあいだ停留していた「時」が動き始めたことを告げるものはなかった。
ピツンッ。 ピツンッ。 ピツンッ……
雪が水に相を変えて流動を得たように、それまで自らの内に停止させていた「時」もまた流れだし、滴下はその「時」の刻みそのものだった。冬のあいだに殻のように硬化して形をなお保つ雪塊の奥に、滴りの音はやや籠もって、しかし、聴いているこちらの心音まで同調して高まるようなその音。
ピツンッ。 ピツンッ。 ピツンッ……
萩の祖父母の家には、居間の柱の高いところに、ゼンマイ式の振り子時計が掛かっていて、時が来ると、図体に似合わぬ大きな音で鉦を響かせていた。振り子は常に刻みの音を立てていた。硬いドアのノックのような、それとも、無人のトンネルの中の足音のような…
コッ。 コッ。 コッ……
私が、振り子の規則正しい動きに見とれ、その反転の際に刻まれる等間隔の音に耳を傾け、もう少しで鉦が響くと待つ間、周りでは物事が生起し連続していった…祖父が庭の潅水を終えて縁側から上がってきた…祖母が、おやつにと、茹でたトウモロコシを運んできた…
コッ。 コッ。 コッ……
逆流のない事象の流れに、振り子の音は、明瞭な刻印を打ち付けていく。それを数えれば時の長さが知れ、『時の物差し』と私は思った。振り子は「時」を指揮しているかのように左右に振れつづけた。
内縁に置かれたロッキングチェアに足も上げて収まって前後に揺らすと、それは逆さでも、『あの時計と同じ』と気づいた。自分が振り子になって、そう、「時」を指揮しているみたいだった。世界が身を揺すって各々刻む「時」を私に合わせていた。遠い、揺れない空の域は別にして。

夜、明かりが落とされると、様々な音が、昼の間はいったい何に隠されていたのだろう、にわかにその存在を明らかにする。子供の私は、その出現の理由が解らなかった。庭の木々のざやめく音は潮騒のようだったし、家のどこかで弾けるピシッという音は私の頭が割れたかのようだったし、トイレで流された水の音は私を体ごと拉し去るかのようだった。わけても、居間の振り子時計の音の高まりは私にはとても怖かった。昼間とは打って変わって、夜の家の内のしじまに最も大きな音でありつづける振り子の刻み、その等間隔は無慈悲なまでに厳格で、指揮の範疇をはるかに逸して、全てに君臨して全てを支配し、鉦の響きは絶対的命令の大声、私は布団の中でそれを恐れた。
…雪の壁の迷路に迷う私が招じ入れられた室内で聞いた丸時計の秒針の音は、物事の生起が絶たれたなか、進行の方向を失い、前進も後進も確証なく、ループをしているようでもあった。しかし、雪のドームの滴下の音は、祖父母の家の柱時計のように、自らの「時」を刻み、また、変転するあらゆる事象の「時」の流れに刻印を打っていた。そして、この地の万物は自らが刻む「時」を雪のそれに合わせて速め出した。何かの支配による強制でそうなっているのではなく、万物が自らそうしていた。
日に日に、滴の音は増え、かつ、そのテンポを上げていった。
ピツ、ピツ、ピツ、ピツ、ピツ……
ある日、積雪のドームに穴が開き、滴下が止む。
それが、冬の終焉、春の開始、と私には感じられた。その日までに経験していたのは冬の衰退だった。街中の山のような積雪が新雪の供給を絶たれて、その体躯を貧弱にしながら灰色に汚れてゆき、その足元に少しずつ溜めた水で浮島に見えたことも。冬枯れの森の大木の根方の幹の周囲の雪がまず融けて、土や落ち葉が現れたことも。
無数の積雪のドームに開いた穴から、「時」が色彩と匂いを連れて躍り出て、この地を駆け巡るように感じられた。「時」は身をよじるようにして、どんな妨げも振り切る勢いで疾駆する。この地の万物が、それに合わせ、自らの刻む「時」を速め、高め、一つに和合して酔うたようになる。
つい昨日まで残雪に覆われていた地は、雪が緑色に染まったかのように満目の草原となっていた。低い場所から高い場所へと、緑は、布にみるみる染み上がってゆく染料のようで、集中して見つめるなら、その移行が判別できるのではないかと思える迅速だった。雪の下敷きとなって地に伏せていた灌木は、頭をもたげ腕を空へ差し伸べるみたいに幹と枝を起こし、その枝の無数の芽は包皮の裂け目に緑を覗かせていた。丈高い広葉樹はなお裸木でも、木々の枝の密な重なりは、膨らみだした芽のせいで全体が仄かに赤く色づき、その林には既に、種類も数も豊かな鳥の声に満ちていた。田畑には耕運機が入り、方々に起こるエンジン音が空気を響した。人も動植物も種や類を越えて一つの生であるように躍動していた。
山のあちらこちらで、雪解け水が、斜面の見渡す限りを薄皮のように覆って流れ落ちていた。地の面には、前年の朽ち葉や堅果…橅林であれば卵型の葉と三角錐の実が、杉林であれば保存食のゼンマイのような形状と色の針葉が折り重なっていて、そこに下生えの緑草が芽吹いて早本葉をひろげだし、雪解け水は、飲めそうなほど澄んで、朽ち葉を半ば沈めて艶やかに濡らし、あるいは、草の根元を浸して沼沢植物のように見せていた。その水面は、落ち葉のわずかな凹凸に縮緬となり、日の当たる場所では陽とその破片を宿して明滅している。しゃがむと、水が確かに斜面を下っているのが見て取れ、その流れの囁きも聞き取れた。澄んだ水は、しかし無機的な印象はなくて、むしろ傷口から脈動しつつ溢れ広がる血液のような生命感を見せ、そう感じると、私は怖ささえ覚えた。水は目の及ぶ範囲を覆い尽くしていた。
雪解け水は斜面を下り、谷状の浅い窪みに集まり、場所によって土を巻き込んで濁り、その泥水も清水もさらに下って渓流で合すると、対話も聞き取れない轟音を上げて里を目指し、多くの用水路に流入し、あちこちで氾濫しては生活道路を水浸しにして、そうして畑や田植え前の田んぼを潤した。
広葉樹は見る間に葉を展べ、その若葉がまだ薄く、日差しを透過させ、森の中は緑色の柔らかな光が遍満していた。わずかな風に、枝はたおやかに揺れ、一枚一枚の葉は閃いてやまず、眺めやる山々は海原のように騒いでいた。誰も彼も、山菜を求めて草いきれの渦巻く山へと踏み入った。冬に知り合ったおばあさんは足腰もおぼつかなく、室内では歩くのも心もとなかったのに、春の山の斜面では一転、密生する緑を掻き分け掻き分け、まるで泳ぐように事も無げに、私を置いてきぼりにして先へ進んでいった。
…雪は、水へと相を変え、一滴一滴の滴下であったものが、徐々に合し、ある段階を超えると規模もテンポも爆発的な展開となった。渓谷で白波を上げ、捩れ砕けて、轟然と響きを上げていたのは「時」の奔流だった。人・動植物・物、万物もまた、徐々に動き出し、やがて、自らの内に停留をさせていた「時」を、目一杯たわめられたバネの反発力の解放のように一気に溢れさせて、その各々の「時」の流れを、「時」の奔流に合一させた。未だ他所者の私だけが、その流れに乗れずに、唖然として一切を眺めていた。
春に撮影した写真をチェックしていて気づいたことがあった。「雪」をモチーフにしていないその写真は、シリーズに組み込むことを意図していたのではなかった。ところが、プリントをした写真と対峙してみると、春の写真のその気配は、不思議に冬の写真のそれと同じなのだった。もちろん、季節が異なるのだから、外光には仰角や強さに差があり、室内においても、雪の反射がないので、光線には相違がある。それに応じて、影の生まれる方向、その濃さもまた。にもかかわらず、気配、空気感が一緒と感じられる。
不思議とも思えるそのことが、私にさらに夏の撮影を促した。
猟師に同道して入った夏山の森は、陽が広葉樹の葉叢に遮られ、気温が平地よりも下がっていた。頭上の高みの暗い茂みは所々が破れて、そこに透かされる蒼空はたいそう高く見え、純白の積雲がゆっくりと流れていた。森のどこも空気は湿りを帯びていて、風が起これば、滝や急流の傍にいるかのような涼感だった。風は、木の枝を揺らしながら、どこからか来て、どこかへと消えていった。
「ここらの森は年じゅう梅雨なんそ」
この地の地形は河岸段丘で、その各層に湧水があるという。日本海の対馬海流は九州の方からくる暖流で、冬、蒸気を供給して上空に厚い雲を作る。雲は、冷え切った偏西風に流されて、この地の東から南を半ば囲むようにして聳える高山にぶつかり、多量の雪となって地に降る。高山に積もった雪は地中に染み込み、深い地下へと下り、十年、経路によっては四十年の間、水脈を流れ、段丘の各層の処々に湧水として出現する。雨の乏しい年も涸れないそれら湧水が夏の森の湿りであり、植物、動物の全ての命を保証し、さらには、里の稲の根も浸しつづける。
『雪…』と私は思った。今、この夏の森で私を包んでいるのは「雪」。この地には一年中、「雪」が存在する。水に大気に、相を変え、しかし、それらはこの地ではまぎれもなく「雪」だった。

そう実感したとき、私の撮影の領域は季節の境を完全に越えて、一挙に広がった。通年で「雪」が存在する以上、「雪」をモチーフにしたこのシリーズは、春も夏も秋も撮られなければならない。ようやく、私が撮るべきものが見えてきた。撮影を開始した当初から、自分が撮影するのは、雪の風景写真でも、雪の中での人々の生活の記録写真(風土記的写真)でもないと、そのことだけは解っていたけれど、では何を撮るのかは皆目掴めていなかった。すでに、人の定めた地の境を越えていた。今度は、季節の境を越え、そう、少なくとも撮影の時空は目の前にはるかに広がっていた。
水音が岩間に反響する湧水を訪ねた。飲料水にも用いられ、神域のように囲いで守られた木深い源泉も訪ねた。マタギが山に入って泊まり込むさいに使っていた洞穴も訪ねた。夏草に埋もれた廃村の跡形も訪ねた。太古の地層が地殻変動で露出し聳える崖も訪ねた。湧水の沼沢地も訪ねた。縄文遺跡の発掘現場も訪ねた。
夏に撮った写真もまた、春の写真同様に、風景・光景であれ、人であれ、冬の写真と同じ雰囲気を放っていると見えた。
この地の秋は早い。まだまだ夏の盛りと思えていた8月の半ば過ぎに不意にやってくる。ある朝、起床して窓を開けた瞬間、『秋…』と感じられるのだ。しんとしたその気配は、通年でこの地に存在する「雪」の存在感の一つ、本来の「雪」の相に戻る直前の存在感と思われた。
その日を境に、山上から吹き降りてくるようになる冷涼な風の中、人も自然も夏仕舞いを、と言うよりも、冬支度を始める。私の周りにも「じっき(じきに)まーた白いもんが降ってくるがな」が挨拶のように聞かれた。人も動植物も、物さえも、冬が瞬く間に到来し、雪が水や大気の姿から本然の姿に還ることを感取する。
それに合わせて、春にそうであったように、万物はそれぞれに刻む「時」を一斉に速めだす。ただ、春は、生命が沸き立つような「時」の速まりであったけれど、秋は、何か避けようのない終焉に向かってでもいるようなそんな「時」の迅速だった。稲刈りはもちろん活況を呈する。しかし、春の田植えの活況が、自ずと動き出す始まりのそれであったのに対し、秋の稲刈りの活況は、何かから急かされているような終わりを前にしてのそれで、あたりに稲刈り機の爆音が轟いていても、ひとたび機械が停止するや、広々とした空間は深閑とし、透徹した気配に占められた。
春には、枯れた林が低い場所から高い場所へと、緑の染料が布にみるみる染み上がってゆくように芽吹くのが見られたが、秋は、その緑の森が、春とは逆に高い場所から低い場所へと、これは春同様の速さで黄や紅に染め直されていった。そして再び高所から低所へと、落葉が世界の凋落かと思うほど異様に速やかに進み、気づけば、全ての森は裸木の重畳の灰色と地面の朽葉の茶色の入り組んだ斑模様に一変していた。この「時」の速さに、翻って夏の「時」が、束の間ではあっても、野太く安定した歩みであったと気づかされる。
「山のてっちょ(苗場山の頂上)に三度雪が降ると里に降りてくる」と古くから言い習わされてきたとおりに、この地の南東、一番秀でた苗場山の頂が幾度か薄く雪をまとうと、或る日、白灰色の空に綿雪が見え、見え始めれば、無数の雪片がふわふわと舞い降りてくる。この始まりだけは、子供の私が暮らしていた滋賀の真冬に稀に見ることのできた雪のさまに似ていた。この地でさえ最初は、綿雪は地に触れるやふっと消え失せた。海の波が陸を目指してなんどもなんども打ち寄せるように、雪はいくど消失してもけして諦めずに地に降り続ける。海の波は、天変地異でもない限り、どれほど打ち寄せてもついに陸を侵すことはない、しかし雪はほどなく、常緑樹の木の葉に、地面の枯れ草に、落ち葉に、その姿をとどめだし、みるみる全てを覆い始める。滋賀の私が生まれ育った辺りでは、たとえ積もっても足首までであったのに、この地では一夜で腰まで降り積もる。
そして、あの「時」の停留する真冬がこの地に巡り来る。
『繡』の撮影には6×7の中判フィルムのカメラを用い、この新シリーズには35ミリサイズのCCDのカメラを用いていた。画面の縦横比が異なり、カメラを通常に構えるなら、後者は前者よりも左右が伸びて、ポートレートでは、中央の人物を囲む背景がより画面に写り込むようになった。『繡』の撮影に慣れていた私は当初そのことに撮りにくさを感じた。しかし、そうして背景が入り込むようになって、その場の気配もより写るようになり、それで季節の相違を越えた共通性が知れたのだった。
その共通の気配は、写っている人物もまた纏い、その場の気配を醸成している要因の一つとなっていた。今回のポートレートは、『繡』と同じフォーマットで撮影していたから、写し出された人物それぞれの「個の存在」とその人の創る自己イメージは、写真ごとに厳然と異なっている。けれども、背景と人物が同じ気配で響き合っていて、第一印象としてはむしろその共通の気配が目に入ってくると私には感じられた。
気配は、表層の自己イメージの下、最深の「個の存在」の手前に被るベールで、それは、ある土地、ある時代の相を帯びている。意識的に形成される自己イメージはまだ取り払いやすい。けれども、ある土地、ある時代に生まれ育つことで自然と形成される、いわば通底イメージ(ベール)は、当人が無自覚だけに拭いがたい。
『繡』と同一フォーマットであっても、撮影を重ねるほどに、表現の中心は自ずと異なっていった。
撮影の最後の一年は、この地に家を借りて、通年の滞在をおこなった。そうして改めて確認したのは、この地では「雪」が水に大気に相を変えて一年中存在し、絶対的な存在として、万物それぞれの刻む「時」を律している、ということだった。言い換えれば、人を含め、万物が、一年中存在する絶対的な「雪」に、それぞれの「時」の刻みを合わせて、その速さを伸縮させている、となる。
『雪』が万物を律する」「万物が『雪』に合わせる」…〈律する〉も〈合わせる〉も、人の行いを表すことを基本にした語で(言葉というものは、とてつもなく人間中心主義のツールだと思う)、雪や万物が、人のように意思・意志を持っているかのような印象に図らずもなってしまう。〈律する〉の表現のほか、〈司る〉〈支配する〉〈統べる〉〈治める〉なども思い浮かんだけれど、いずれも意思・意志を持つ存在が力・権力の行使で他を従わせているというニュアンスが濃かった。例えば、「絶対的な存在の『雪』が万物の『時』を統べている」と表現するなら、「雪」はすっかり擬人化され、「絶対的権力者」になってしまう。その点、〈律する〉は〈自らを律する〉という用法が普通に使え、他にばかり作用を及ぼすという意味合いがそのぶん薄いので選択した。〈合わせる〉の表現を採ったのも、〈従う〉〈服する〉では、自らの意思・意志からそうしているの意味合いが強く不適切と思ったからだった。
ただ、万物の中の生物、かつ、意思・意志を持つもの、なかんずく人の場合は、自らの意思・意志によって「雪」に自らの「時」を合わせていたから、人は「雪」に「時」を統べられ、それに従っていると言えるかと思う。しかし、この場合でも、人は「雪」の力によって屈従しているのではなく、「雪」がもたらす春・夏・秋の豊穣さを知っていて、それゆえに、「雪」の統治を認め、進んで「雪」に従い、この地に生き続けているのだった、…いつでもこの地を離れる自由の権利を有しつつ。
「雪」は、この地の万物の姿形に、直接的な刻印も施す。
例えば樹木。軽いパウダースノーとは真逆に極端に重い湿雪は、冬の間小木を地に押し付けて、春に木が挽回するといっても、やはり俯きかげんの樹形へと固めてしまうし、高木の枝を、盆栽の針金掛けのように捩れさせ、あるいは、付け根から圧し折って、そのとき幹を縦に深く裂いてしまうこともする。私には、森に入ると、捩れた枝ばかりの光景に、木々が常に振動している錯覚が起きた。また例えば、廃村の跡形。住人の絶えた家屋を積雪の過重で圧し潰して、ほんの数年で、すべてを草間に沈めてしまう。
また例えば人。「雪」は、雪掘り(雪かき)・雪下ろしを長年重ねた者の目を反射光で焼き、あの薄墨色に暗く澄んだ瞳に変え、また手を年齢よりも早く皺め、あるいは関節を変形させてしまう。
こうした自然、人に見られる「雪」の刻印に着眼してクローズアップに撮影することを、すなわち、細部を強調してつまびらかに記録することを、私は作品としては終始避けてきていた。もちろん、写真にはそういう細部が図らずも映り込んでしまうのだが、私は、それを撮影の目的(中心)に据えることをしなかった。雪がもたらす万物の姿形の変容の細部を合計してみても、「この地」の表現にはならないと思ったからだった。
長い期間、撮影してはプリントを見、それによって更新された目で撮影に戻り、再びプリントを見て…そのフィードバックの作業を積み重ねて、その果てに、私が心惹かれるようになっていたのは、ポートレートであれ、風景・光景の写真であれ、また撮影時期が冬であれ、それ以外の季節であれ、私が『写せた』と思えるカットの全部に共通して見て取れる気配であった。私は、それが「雪」の律する「時」に関わっていると感じられるようになってきていた。