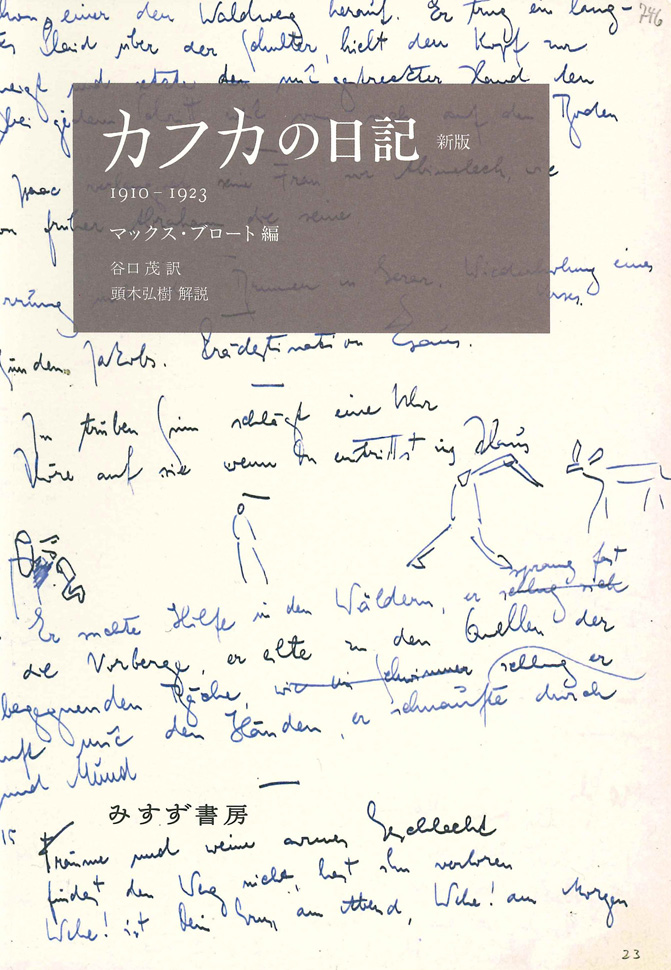この連載では、フランツ・カフカの小説『変身』を新訳しながら、超スローリーディングしていく(ものすごくゆっくり読む)。
さらに、読みながら私が思い出したこと考えたことも、脱線を気にせずに、どんどん書いていく。というのも、読書の半分は、本に書いてあることではなく、本を読みながら自分の内にわきあがってきたことにあると思うからだ。
私の脱線につられて、みなさんもそれぞれに、いろんなことを思い出したり考えたりしていただけたら幸いだ。自分の城の中にある、自分でもまだ知らない広間。
それを開く鍵のような働きが、多くの本にはある。(オスカー・ポラックへの手紙 1903年11月9日)
●前回まで
グレーテのヴァイオリンの演奏に魅せられて、居間に這い出してしまったグレーゴルは、間借人たちに見つけられ、騒動を引き起こしてしまう。
みんながショックを受けている中で、グレーテがついに決定的な言葉を口にする。
「もうこれ以上は無理よ。この怪物を兄さんの名前で呼びたくない。これを厄介払いしないと」
居間の床でじっとしていたグレーゴルがまた動きだして、他の家族はぎょっとするが、それは自分の部屋に戻るためだった。
グレーゴルが部屋の中に入ると、グレーテはすかさず外から鍵をかけた。
真っ暗な部屋の中で、もうすっかり動けなくなっていることに、グレーゴルは気づく。身体の痛みも、だんだん感じなくなっていく。自分は消えなければならないと彼は思う。やがて塔の時計が朝の3時を打ったとき、グレーゴルは死んだ。
朝になって、掃除婦がその死骸を見つけ、ザムザ夫妻の寝室のドアをいきなり開けて、暗い部屋の中に向けて、「すっかりくたばってますよ!」と怒鳴った。
●三者三様
ベッドに身を起こしたザムザ夫妻は、びっくりしたせいで、掃除婦が何を言っているのか、しばらくわからなかった。ようやく理解すると、それぞれ自分の寝ていた側から大急ぎでベッドを下りた。ザムザ氏は毛布を肩にかけ、ザムザ夫人は寝間着のままで、寝室を出て、グレーゴルの部屋に入った。居間のドアが開いて、グレーテも出てきた。間借人たちが引っ越してきてからずっと、彼女は居間で寝起きしていたのだ。まだ横になっていなかったらしく、きちんと服を着たままだった。青白い顔色からも、一睡もしていないことがうかがわれた。「死んでいるの?」とザムザ夫人は確認するように掃除婦を見上げたが、自分でも確かめられることだったし、確かめるまでもないことだった。「そうだと思いますよ」と掃除婦は言い、ほらこのとおりというように、箒でぐっと突いて、グレーゴルの死骸をずり動かした。ザムザ夫人は箒を押さえるようなそぶりを見せたが、実際には止めなかった。「さて」とザムザ氏は言った。「これで私たちも神様に感謝できるというものだ」彼が十字を切ると、3人の女たちもそれにならった。死骸からずっと目を離さずにいたグレーテが言った。「ほら、見て。彼はなんて痩せているんでしょう。長いあいだ、何も食べなかったのよ。食べ物を入れてあげても手つかずで、そのまま片づけるしかなくて」実際、グレーゴルの身体はすっかり平べったくなって、ひからびていた。今になって、ようやくそのことに気づいたのだ。じっと見ていられるようになったからだ。もはやその身体が小さな脚たちで持ち上げられることはなく、そうした動きなどに注意を奪われることもなかった。
「父親」「母親」「妹」というこれまでの呼び方から、「ザムザ氏」「ザムザ夫人」「グレーテ」へと変わる。「父親」「母親」「妹」と呼んでいたのは、グレーゴルの目線だったからだ。グレーゴルが死んだので、もうそうは呼ばれない。
前回の最後のほうでも書いたように、同じ三人称でも、グレーゴルが生きていたときと、死んだあとでは、視点が大きく変化するので、書き方も変化している(私の文章では、引き続き「父親」「母親」「妹」を使っていく)。
グレーゴルが死んだと聞いて、父親と母親は急いでグレーゴルの部屋に向かう。生きているうちは入ろうとしなかったグレーゴルの部屋に、死んだときにはすぐに入っていく。父親のほうはおそらく、グレーゴルが虫になってから初めて部屋に入ったはずだ。
妹が居間で寝起きしていたことが、ここで初めてわかる。グレーゴルの部屋の隣りだ。妹はずっと起きていたようだ。眠れなかったということだろう。寝間着に着替えてもいないから、眠ろうとさえしなかったようだ。グレーゴルの部屋に外から鍵をかけて、「やっとよ!」と叫んでいたのに、それで安心して眠れたわけではなかったのだ。グレーゴルに対して、死刑宣告にも等しい決断をしたことで、やはり気がとがめていたのだろうか。
それに対して両親は、寝間着に着替えてベッドに入っていた。掃除婦に起こされたとき、暗い部屋の中で、眠っていたのか、目をさましていたのかはわからない。しかし、おそらくは眠っていたのだろう。起きていたとしても、掃除婦が「勢いよくドアをバタンバタンと開け閉めするので、家の者はおちおち寝ていられなくなる」からだろう。
いちばん世話をして、いちばん残酷な決断をした妹が、いちばん罪悪感を抱く。なんの世話もせず、なんの決断もしなかった者たちのほうが、より罪悪感を抱くべきかもしれないのだが、そうはならない。
グレーゴルの死に対する、母親、父親、妹の反応は、三者三様だ。
息子の遺体に泣きすがる母親というのはドラマなどでよく見るシーンだが、グレーゴルの母親は、グレーゴルが本当に死んでいるかどうか、他人である掃除婦に問いかける。そして、箒で突いてずり動かしてみるという乱暴な確認方法に対して、そんなかわいそうなことはしないでほしいと止めるようなそぶりを見せるが、本当には止めない。息子に対する愛情はあるだろうし、かわいそうとも思っているだろう。そこに嘘はないと思う。しかし、あくまで自分が直接に関わることはしない。ある程度の意思や感情の表出だけで、行動や判断にはなるべく関わらないようにする。そういうところは首尾一貫している。従属的に生きてきた人の習い性なのか、自然と身についた処世術なのか。
父親は「これで私たちも神様に感謝できるというものだ」と、神に感謝している。息子が生きていたのでは、かえって神に感謝しづらかったわけだ。しかも、自分だけでなく、家族みんながこれで神に感謝できると思っている。実際、妻も妹も、彼に続いて十字を切っている。掃除婦までも。彼女たちの場合は、哀悼の意も含んでいたかもしれないが。
妹はグレーゴルを「これ」(es 英語だと it)と呼ぶようになっていたわけだが、ここではまた「彼」(er 英語だと he)と呼んでいる。死んだことで、また人間あつかいするようになったのだ。姿は虫のままでも。問題は、生きていることにあったわけだ。
妹は、グレーゴルが痩せていることに目を向ける。世話をし、食事の用意をしていたからこそだ。ヴァイオリン騒ぎのあと、グレーゴルが居間から自分の部屋に戻るとき、その動作はとても鈍く、家族はそれをずっと固まったようになって見つめていた。にもかかわらず、死んでしまうまで、その身体がすっかり平べったくなっていることに誰も気づかなかったのだ。
生きていることを嫌悪され、身体の変化にも気づいてもらえなかったグレーゴル。
母親、父親、妹の反応で共通しているのは、誰も泣いていないということだ。
死んで喜ばれるというのは、いったいどんな気持ちがするだろうか? 死ぬときに、みんなが悲しんで泣いてくれたら、やはり少しは死にやすいのではないだろうか。少なくとも、死んでいくときに、それにつれて喜びが高まっていく人がいたら、死ににくいと思う。
死んで悲しまれるために、誰にでも親切にしている人もいた。ある大きな企業で高い地位にある人なのだが、バイトにまですごく親切で、バイトの友達、そのさらに友達という、まるで無関係な相手にまで親切なのだ。私はまさにそういう遠い相手だったのだが、別荘にまで誘われた。しかし、どう見ても、権力を求め、競争的で、人を蹴落とすことがむしろ好きというキャラクターで、根っから親切な人という感じではないのだ。私は不思議でたまらず、ついに聞いてしまった。「どうしてそんなに誰にでも親切にするんですか?」こんなことを聞いても、どうせ「人には親切にするものだろ」というようなすかした返事が返ってくるだけかと思っていたら、実際には意外な返事だった。その人はきっぱりと言った。「自分の葬式に大勢来てほしいからだよ」
自分の葬式のときに、たくさんの人が来て、みんなで「いい人だった」と悲しんでほしいのだそうだ。「それが人生の目標だ」とまで言っていた。そのためには、お金もかなり惜しみなく使っていた。プレゼントとか食事をおごるとか旅行の費用を持つとか。「死んだあとで、惜しんでもらってもしかたないでしょう」と言ったのだが、「そんなことはない」と。自分の葬式にさぞたくさんの人がやってきてくれるだろうと思うと、幸せなのだそうだ。こんな現世利益だけのために動きそうな人が、一方でこんなことを思っているのだ。私など、むしろ葬式はやってほしくないくらいだから、びっくりした。
この人は、コロナの時期、「今は絶対、死にたくない」と言っていた。葬式に誰も来てもらえないのだから、これまでしてきた努力がすべて水の泡だ。
●窓が開けられ、3月が告げられる
「グレーテ、ちょっと私たちの部屋においで」とザムザ夫人がもの悲しげな微笑を浮かべて言った。グレーテは、死骸のほうを振り返りながらも、両親のあとに続いて寝室に入った。掃除婦はドアを閉め、窓をすっかり開け放った。まだ朝早いのに、流れ込んでくるすがすがしい外の空気には、いくらかあたたかさが混じっていた。もう3月の終わりだった。
母親は「もの悲しげな微笑」を浮かべる。グレーゴルの死に対してなら、微笑することはないだろう。家族に大変なことがあり、その傷はまだ深いけれども、それでもついに終わったという、そういう表情ではないだろうか。
母親と父親と妹は、家族だけになろうとする。死骸も掃除婦もそこに残して、家族だけで寝室に入る。
ザムザ家は間取りがはっきりしないところがあるが、寝室とグレーゴルの部屋が隣り合っているとしたら、死骸を振り返りつつ寝室に入ったグレーテは、自分でドアを閉めなかったのだろう。それで掃除婦が閉めてやったのか。掃除婦は、いろいろ気を利かせようとしている。自分が発見した事態なので、自分が仕切ろうとしているところがあるのかもしれない。一種の高揚が感じられる。他人の災難にたまたま自分が関わると、妙に高揚することがあるものだ。
掃除婦は、グレーゴルの部屋の窓を開ける。グレーゴルがそこから外をながめることで、なんとか解放感を味わおうとしていた、あの窓だ。窓の重要性については、この連載の第16回で書いた。
閉ざされていた状況に、外の風が流れ込んでくる。ひとつの時期が終わったのだ。
その風のすがすがしさと、あたたかさを感じさせて、不意に「もう3月の終わりだった」と時期が明確にされる。
この連載の第14回でも書いたように、この作品での時間の進み方は一定ではない。最初はリアルタイム中継のようだったのが、グレーゴルがひきこもると、時間の感じ方が変化して、それに合わせて作品内の時間経過も何日たったのかよくわからなくなっていく。ときおり「もう変身してから1カ月はたち」(第16回)とか「この2カ月の間に」(第17回)とか、大きく経過日数が告げられるのみだった。
ひきこもっているので、季節感がない。最初に、虫になったグレーゴルが部屋から出てきて大騒ぎになったとき、「むこうでは母親が、寒いのに窓を開け放し」(第12回)という描写があった。寒い季節から始まったのだ。そして、最近になって、「もう春が近いのか、激しい雨が窓ガラスを叩いていた」(第22回)と、季節の名前が初めて出てきた。そして、「もう3月の終わりだった」と、何月であるかが、ここで初めて明確にされる。
グレーゴル視点では、何月であるかまではわからないだろうから、これはグレーゴル視点ではなくなったからこその明確さだ。
その唐突な感じが効果的だ。夢からさめて、現実に引き戻されたような感じがする。
●矛盾と純粋性
3人の間借人たちが部屋から出てきて、自分たちの朝食が用意されていないので、びっくりしてあたりを見回した。彼らは忘れられていたのだ。「朝食はどこだ?」と真ん中の男が不機嫌そうに掃除婦に尋ねた。しかし掃除婦はひとさし指を口に押し当て、黙ったまま、あわただしく身ぶりで伝えた。いいからすぐにグレーゴルの部屋に行ってみろと。3人はそのとおりにしてみた。そして、少しくたびれた上着のポケットに両手を突っ込んだまま、今はもうすっかり明るくなった部屋の中で、グレーゴルの死骸を取り囲んで立っていた。
あれほど重視され、かいがいしく世話をされ、料理を気に入ってもらえるかどうか母と妹が「はらはらしながら見守っていた」(第23回)間借人たちだったのに、朝食の用意がされていない。それどころか、存在すら忘れられていたのだ。
間借人たちは当然、これまでどおりの横柄な態度で、「朝食はどこだ?」と言うが、掃除婦から「しーっ、静かに」と黙るように指図されてしまう。掃除婦の伝え方があわただしいのは、事件が起きたという意識と高揚からだろう。
そのいつもとちがう様子に、間借人たちはとりあえず素直に指示にしたがってみる。すると、そこに昨晩の大きな虫が死骸となってころがっていたのだ。
間借人たちは、その死骸を取り囲んで立つ。グレーゴルは横、間借人たちは縦。虫はそもそも横の存在だ。ベッドで寝ている病人と同じように。横と縦では、世界の見え方も感じ方もちがう。
「間借人たちが食べて生きつづけ、ぼくが食べずに死んでいくとは!」とグレーゴルは嘆いていたが(第23回)、まさにそのとおりになってしまった。食べずに死んだグレーゴルを取り囲んで、「朝食はどこだ?」という間借人たちが生きて立っている。
このシーンについて、三原弟平がこういう指摘をしている。
「最後の文章は以前に書いてあったことに矛盾すると思う。グレゴールの死骸を取りまくようにして三人の間借人が立ちつくす余地が、不要な家具やゴミなどに満ち満ちているグレゴールの部屋にはたしてあるのだろうか」(『カフカ『変身』注釈』平凡社)
たしかに、言われてみると、そのとおりだ。
これをカフカの書き方の雑さととらえることもできるだろう。前に書いたことを忘れて、矛盾したことを書いてしまったのだと。
しかし私は、そもそもカフカはそういうことに頓着していないと思う。カフカのイメージには、不要な家具やゴミなどに満ち満ちている部屋を虫のグレーゴルが這うイメージがあった。また、ここではグレーゴルの死骸を間借人たちが取り囲んで立っているイメージがあった。だから、自分のイメージに忠実にそれらを書いた。
普通なら、それらのイメージを忠実に描きたいとしても、それなら途中に、不要な家具やゴミなどが何らかの理由で片づけられるシーンを入れるだろう。そうすれば、なんの問題もない。矛盾が起きないように辻褄合わせをするわけだ。しかし、そうすると、その辻褄合わせのシーンは、そのためだけに存在することになる。そのシーン自体は、自分がもともとイメージしたものでないし、書きたいものでもない。
カフカはそういうシーンは決して書かない。カフカの作品には、辻褄合わせのためだけに書かれたようなシーンは、どこにも存在しない。すべて自分がイメージし、書きたいと思ったシーンばかりだ。だから、矛盾が起きることもあるし、つながらないこともあるし、まとまらないこともある。カフカの作品のほとんどが断片だったり未完だったりすることも、このことと無関係ではないだろう。というより、この純粋性こそ、断片化と未完成の理由だと私は思っている。不純物がなく、つなぎがないから、ひとつにまとまらないのだ。
●家族の死による家族の再生
そのとき、寝室のドアが開き、ザムザ氏が制服姿で現れ、一方の腕には妻を、もう一方の腕には娘を抱きかかえていた。みんな、少し泣きはらした顔をしていた。グレーテはときどき顔を父親の腕に押しつけた。
ザムザ氏は寝間着から制服に着替えている。
そして、父親を中心に、父と母と娘の3人がひとつになっている。まるで間借人たちのように一体化したのだ。
3人をひとつにしたのは、大きな苦難をいっしょに乗り越えたという経験だ。同じ苦難を経験するだけでは心はつながらないが、それをいっしょに乗り越えることができると、とても強く心がつながる。映画などで、いっしょにピンチに陥った男女が、すべてが解決したあと、ひかれあうことに、観客の誰もが納得するのはそのためだ。
では、3人がいっしょに乗り越えた苦難とは何かというと、それはグレーゴルのことで、乗り越えたとは、グレーゴルが死んだということだ。「家族がひとつになる」なんて言うと、なにかいいことのようだが、こういう場合もある。
グレーゴルの死を確認したときには誰も泣いていなかったが、寝室ではみんな少し泣いたようだ。それはグレーゴルの死を悲しんでのことではないだろう。自分たちのこれまでの苦労に対する、そして苦労から解放されて安堵したための涙だろう。私たち大変だったね、でももう苦しまなくていいんだよ、という涙だろう。
3人の結束は、これまでになく強い。
ここはこの短い文章だけで一段落になっている。
●家族だけになる
「私の家からすぐに出ていってもらおう!」とザムザ氏は言い、妻と娘から身体を離さずに、ドアを指さした。「それはどういう意味ですか?」と真ん中の男は、少しうろたえて、こびるように微笑んだ。他のふたりは、両手を背中に回して、しきりにこすり合わせていた。これからひと騒動あるが、けっきょくは自分たちに有利に終わるにちがいないと、うれしそうに待ち構えているようだった。「まさに言葉どおりの意味です」とザムザ氏は答え、妻と娘と横一列に並んで、真ん中の男に迫った。真ん中の男は、無言で立ちつくし、床を見つめていた。頭の中で物事を整理し直しているようだった。「いいでしょう、それなら、出ていきます」と真ん中の男は言い、ザムザ氏を見上げた。まるで、急にへりくだった気持ちになって、出ていくことさえ、あらためて許可を得ようとするかのようだった。ザムザ氏は大きく目を見開き、何度か軽くうなずいて見せるだけだった。すると真ん中の男は、本当にすぐさま玄関のほうに大股で歩きだした。仲間のふたりは、しばらく前から手の動きをとめて、じっとやりとりを聞いていたが、跳びはねるようにして真ん中の男のあとを追った。まるで、ザムザ氏が先回りして、真ん中の男と自分たちのあいだに割り込むのではないかとおそれているかのようだった。玄関で3人は同じようにコート掛けから帽子をとり、ステッキ立てからステッキを抜き、無言のままお辞儀をして、家から出ていった。ザムザ氏は、妻と娘とともに玄関の外まで出てみた。間借人たちの様子におかしなところがあったわけではないが、まだ信用できない気がしたのだ。階段の手すりから身をのり出して、3人の男たちがゆっくりと、でも立ち止まることなく、長い階段を下りていくのをずっと見ていた。1階ごとに階段の曲がっているところでいったん姿が見えなくなり、少ししてまた現れた。3人が階を下りていくほど、彼らに対するザムザ一家の関心も薄れていった。頭の上に商品の入った木の箱を載せた肉屋の若い職人が下から階段を上がってきて、3人とすれちがい、誇らしげな態度で上までのぼってきたとき、ザムザ一家は手すりを離れ、ほっとしたように、自分たちの家に戻った。
昨晩は、間借人たちから「ただちに部屋を解約します」(第25回)と言われて、よろめいて椅子に倒れこんでいた父親が、今は自分から「すぐに出ていってもらおう!」と告げている。
妻と娘とひとつになったまま言い、そのままの状態で間借人たちに迫る。
三位一体どうしの戦いだ。
間借人たちの真ん中の男は、リーダー格だけあって、情勢が変化したことを敏感に察知している。うろたえているし、こびた微笑みさえ浮かべている。
しかし、他のふたりは、考えることは真ん中の男に任せているのだろう、グレーゴルの死骸を見たあとでも、父親と母親と妹が一体になっているのを目の前にしても、まだ昨晩のように自分たちに有利に事が進むと思って、争いをむしろ楽しんでいる。
今では、間借人たち3人組のほうが一体感が弱いのだ。真ん中の男は、形勢が逆転したことを感じ、すぐさま出ていこうとする。あとのふたりはあわててそのあとを追う。父親が自分たちを分断したことだけは感じている。
間借人たち3人は、玄関でまた三位一体となり、まったく同じ動作をくり返して、出ていく。
父親は引き続き妻や娘と一体となったまま、間借人たちが去っていくのをちゃんと見届けようとする。グレーゴルが死んだ今、わが家の異物は、この間借人たちだけなのだ。このとき、掃除婦はやはり視野に入っていない。社会的に、見えない存在なのだ。
階段の手すりから身をのり出して、3人の男たちが階段を下りていくのを見る。ゆっくりと、しかし確実に小さくなっていく姿を見るのは、父親たちの心をなぐさめただろう。わが家から出ていってくれさえすれば、もうまったく関係ない他人だ。父親たちの心からも間借人たちが出ていってくれる。
●肉屋の生命力
下から肉屋が階段を上がってくる。これについては、カフカがフェリーツェに出した手紙に、こういう一節がある。
今日はひどい不眠の夜でした。輾転反側し、やっと最後の二時間になって、むりやりの、思いあぐねた眠りにはいりましたが、夢はとても夢といえず、眠りはなおさら眠りとはいえない有様でした。それに家の戸口で、肉屋の小僧の担いだ荷にぶっつかり、木の部分をいまでも左の眼の上に感じます。
(『決定版カフカ全集10 フェリーツェへの手紙(Ⅰ)』新潮社)
日付は1912年10月24日で、『変身』を書き始める1カ月くらい前だ。ブロートはこの一節に注を付けて、「翌月書かれた小説『変身』参照。「……やがて三人を下にして肉屋の小僧がひとり、いばったようすで頭に荷をのせて……」」と親切に書いてくれている。この実際の体験が、『変身』のこのシーンの元になっているということだ。
しかし、たまたまこういう体験をしていたから、それでここに取り入れただけだろうか。ちょっとした飾りとして。もちろん、そんなことはカフカにはありえない。
肉屋のかついでいる荷は当然、肉だ。誰かが注文したのだろう。つまり、誰かが食べるのだ。それを肉屋の若い職人、つまり普段から肉を切ったりしているたくましい男が、誇らしげに運び上げていくのだ。一方、部屋の中には、食べることができなくて、身体がすっかり平べったくなって死んでしまったグレーゴルがいる。肉を食べる生命力に満ちた存在と、肉どころか何も食べられなくて生命を維持できない存在。こういう対比をカフカはよくする。『変身』のラストでも、『断食芸人』のラストでも。このことについては、次回さらにくわしく書く。
なお、カフカは基本的に肉を食べない、菜食主義者だ。医者の勧めで肉食をしなければならないときもあったが、それをやめたとき、水族館に出かけて、「さあ、これでまた君たちの目を安心して見られるよ」とうれしそうに魚たちに話しかけたほどだ。
前にも書いたように、カフカの祖父は家畜屠殺業者だった。ユダヤ人であったため、差別されていて、職業も住む場所も制限されていた。カフカの父は幼いころから仕事の手伝いをさせられ、冬の雨の日でも、肉を載せた荷車を引いて村々を回らなければならず、そのころの霜焼けや傷の跡が足にずっと残っていた。差別が緩和されると、カフカの父は14歳で故郷の村を飛び出し、裸一貫から、一代で財を成す。プラハという都市の一等地に、高級雑貨の店を開けるほどに。おかげで、息子のカフカは金銭的に何不自由なく育つことができ、父とはちがって、高度な教育を受けることができた。
しかし、父親が自分の足の傷を見せながら苦労話をし、おまえは恵まれているんだと言うことに、カフカは強い反発を抱いていた。「父はたしかにそういう苦労をしたし、ぼくはたしかにそういう苦労をしなかったが、だからといって、ぼくのほうが父よりも幸福だったということにはならないのだ」(『絶望名人カフカ×希望名人ゲーテ』拙訳 草思社文庫)
カフカの祖父は、怪力の大男で、手で持つのも難しい穀物袋を、口でくわえて持ち上げることができたそうだ。カフカの父も、大柄でたくましい、大いに肉を食べビールを飲む、ヒゲの似合う男だった。カフカは菜食主義者で、子どものような顔をして、背は高いものの、棒のように痩せていた。健康で若い24歳のときでも、身長182センチで体重61キロ。BMI(肥満度)の計算をすると、「低体重」の判定になる。危険なほどの痩せすぎで、標準体重になるにはあと12キロ近く太らないといけない。
そういうカフカが肉屋の荷に頭をぶつけるというのは、痛かったというだけでなく、皮肉な出来事であったわけだ。
ちなみに、「商品の入った木の箱」と訳したのは、Trage で、辞書を引くと「背負い籠、てんびん棒、担架」という訳語が出てくる。頭の上に載せているので、どれも該当しない。「籠」と訳すのがよさそうと思ったが、先のカフカの手紙には「木」とあったので、「商品の入った木の箱」としておいた。正直、どういうものなのかよくわからない。ご存知の方がいらしたら、教えていただきたい。
「若い職人」と訳したのは、Geselle で「職人」という意味。既訳では「小僧」と訳されていることも多い。ただ、「職人」だと年配な感じもするし、「小僧」だと子どもという感じがする。Geselle は、徒弟の期間を終えて職人試験に合格した者で、見習いと親方(マイスター)の中間にあたるとのことなので、「若い職人」とした。たくましい男性なんだということをはっきりさせたかったからだ。
いよいよ、次回は最終回だ。
永遠に終わらないのではないかと思ったこの連載も、ついに終わる。
よろしかったら、最後までおつきあいいただきたい。
過去の連載記事
(咬んだり刺したりするカフカの『変身』)なぜこのラストが気に入らないのか?
2025年10月1日
「家族がひとつになる」ことの怖ろしさ
2025年8月1日
家族獣
グレーゴル、死す
2025年6月2日
燃えつきるケア
2025年4月1日
グレーゴル、見つかる!
2025年2月3日
わからないものを待っている
2024年12月2日
グレーゴルとベートーヴェン
2024年10月1日
自分の部屋が物置になる
2024年8月1日
家族につけられた傷が、家族を思って痛む
2024年6月3日
家族熱
2024年4月1日
林檎が背中にめりこむ
2024年2月1日
いちばんの味方がいちばんの敵に
2023年12月1日
ケアの熱狂
もっと世話するために、もっと不幸になってほしい
2023年10月1日