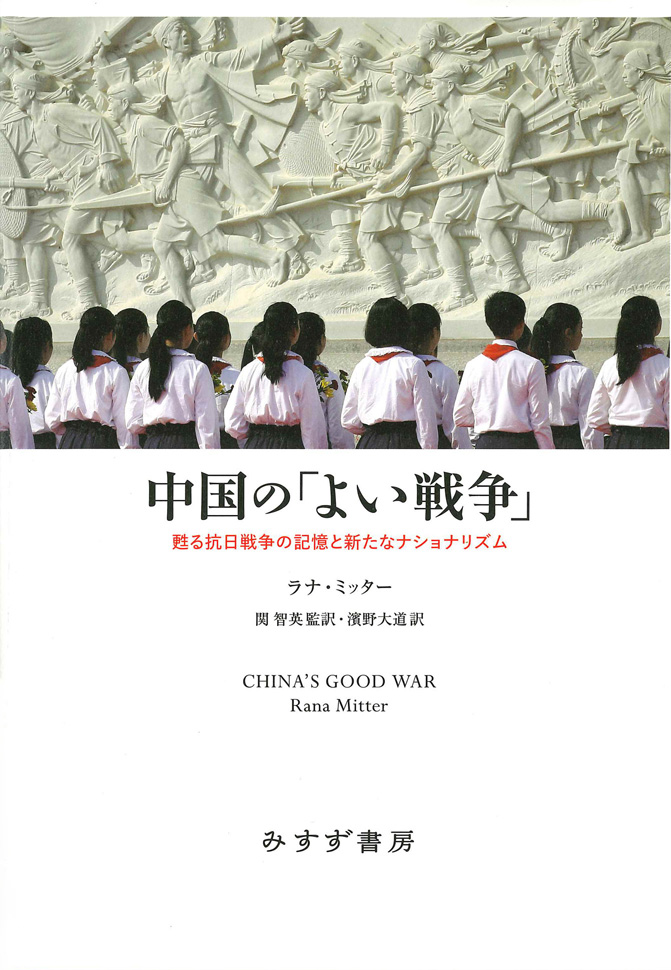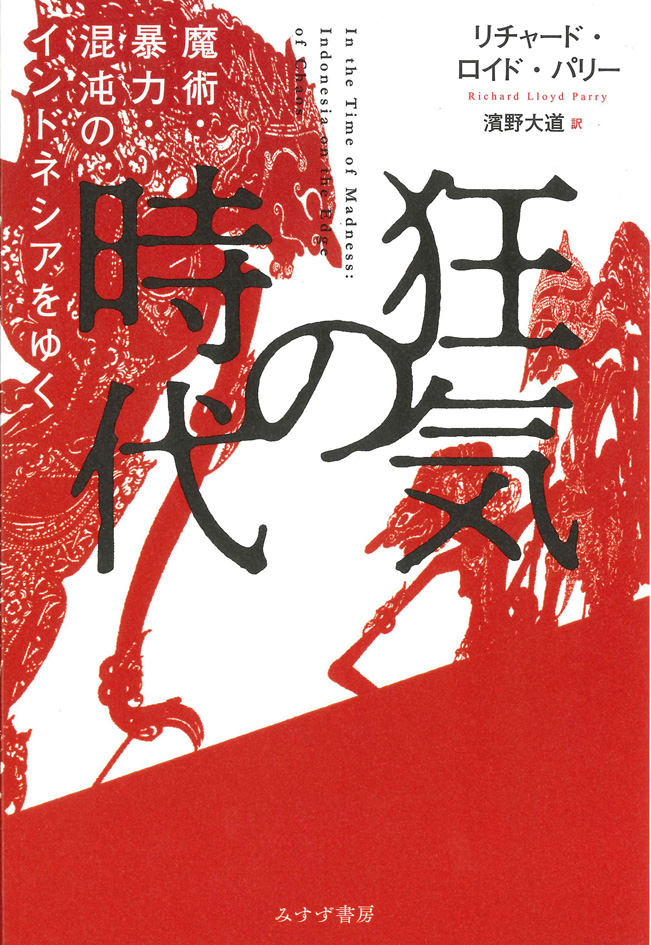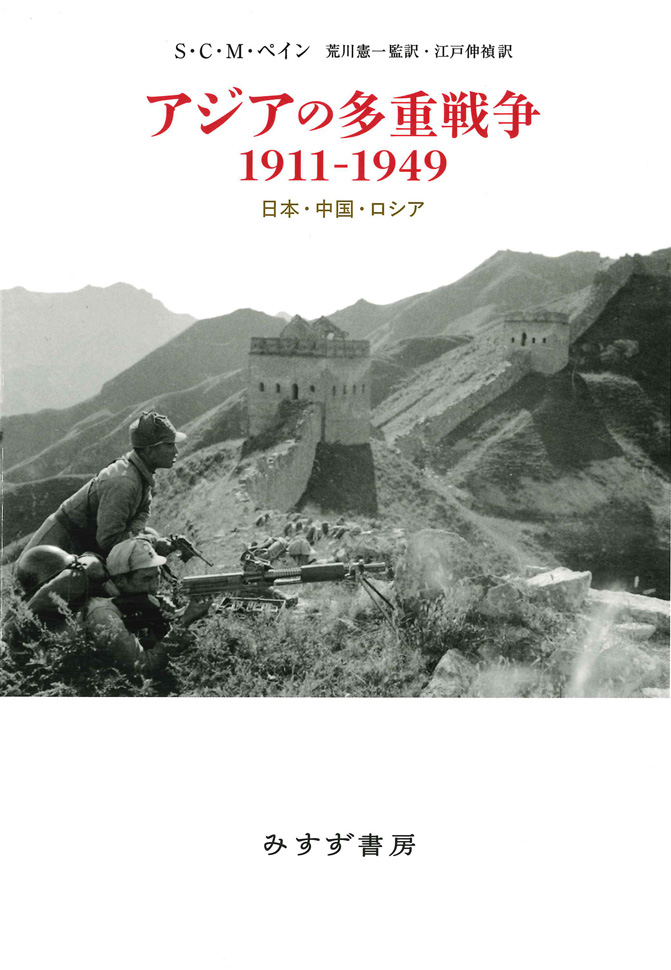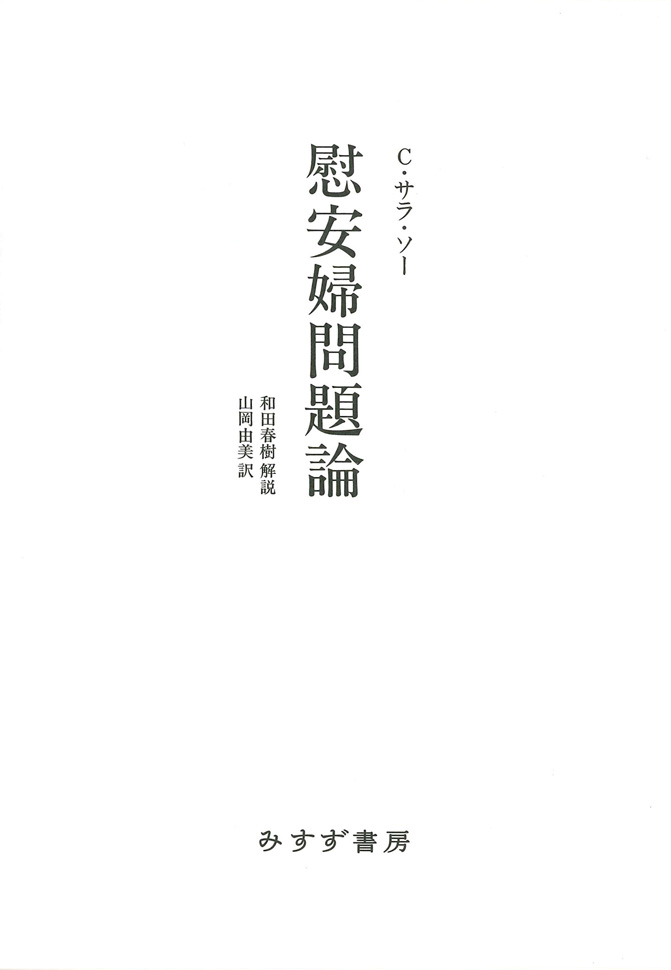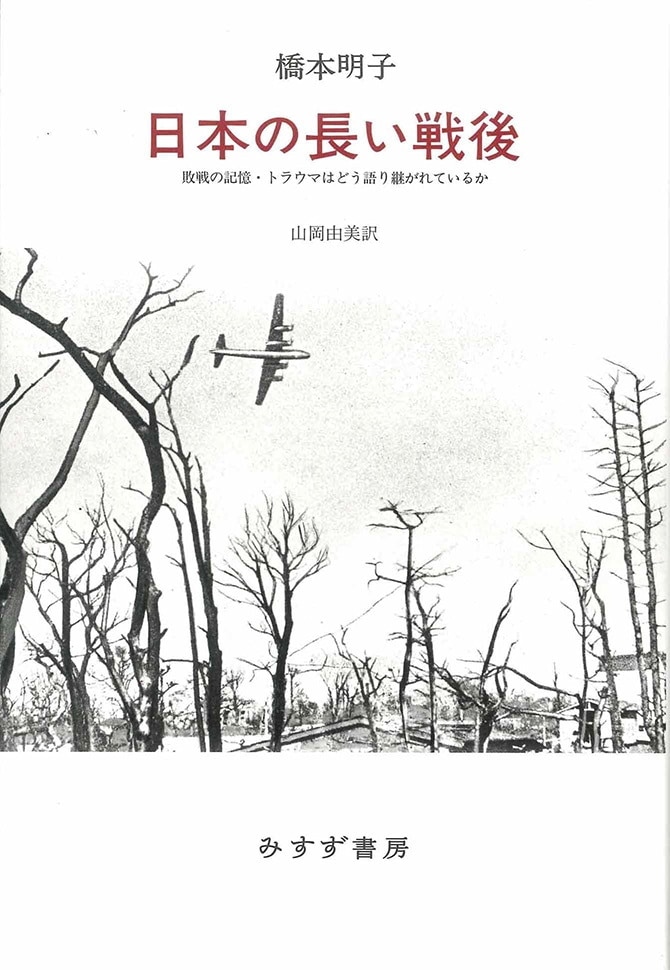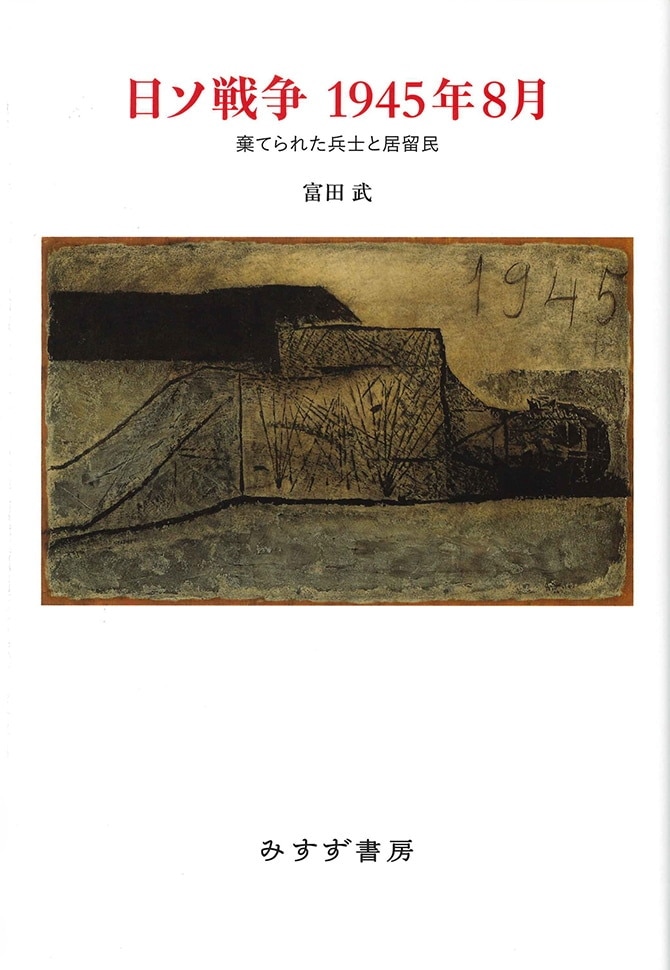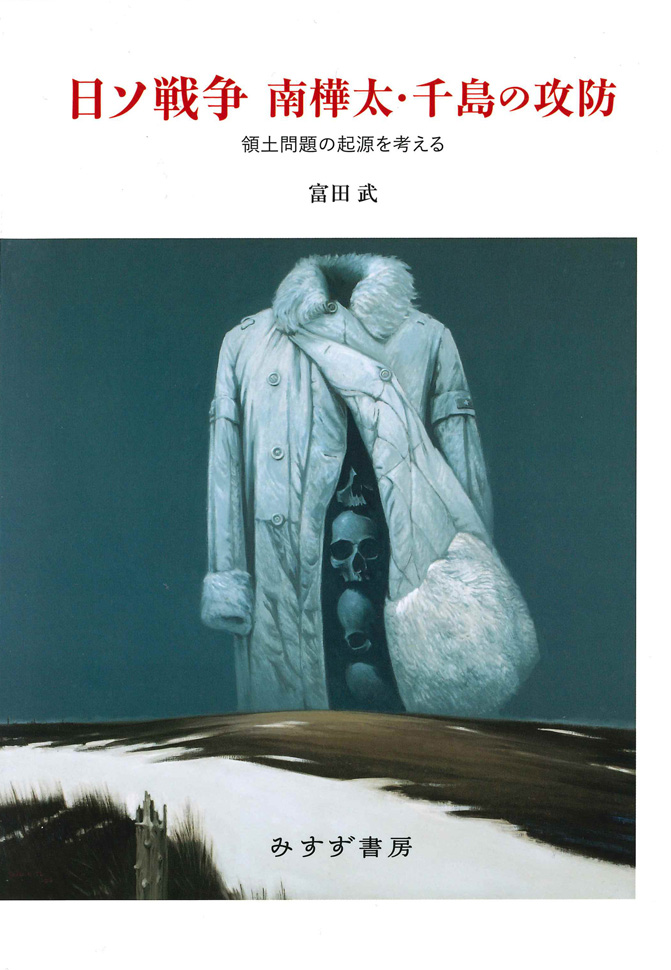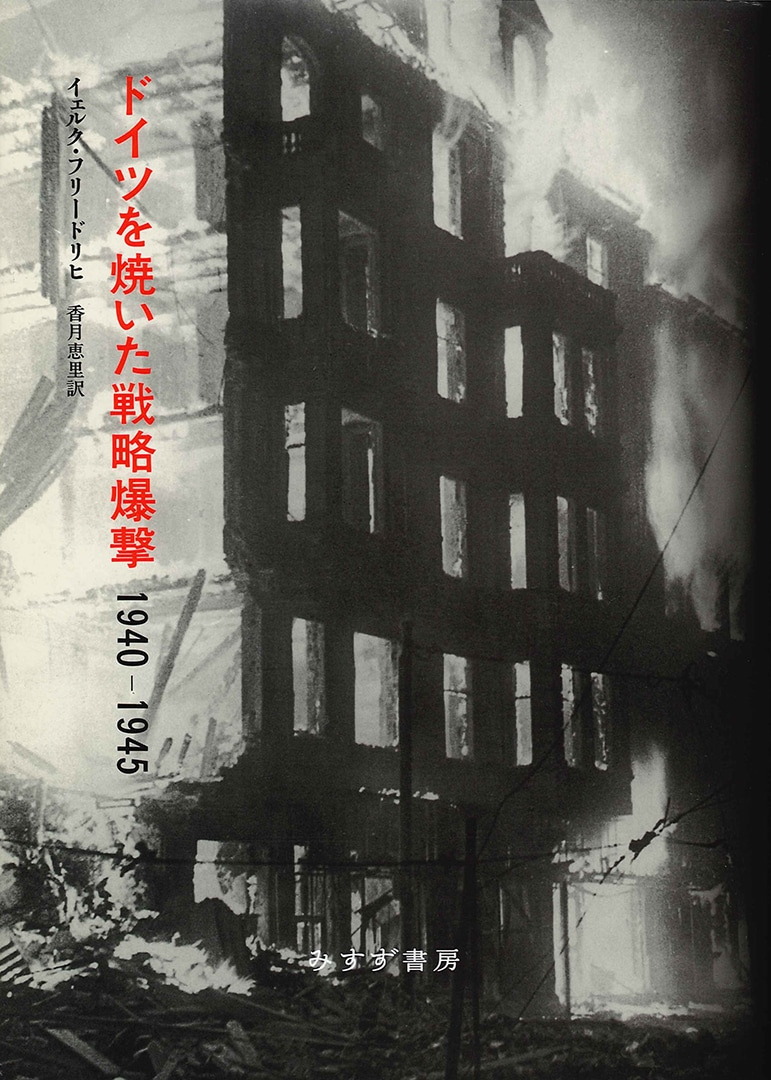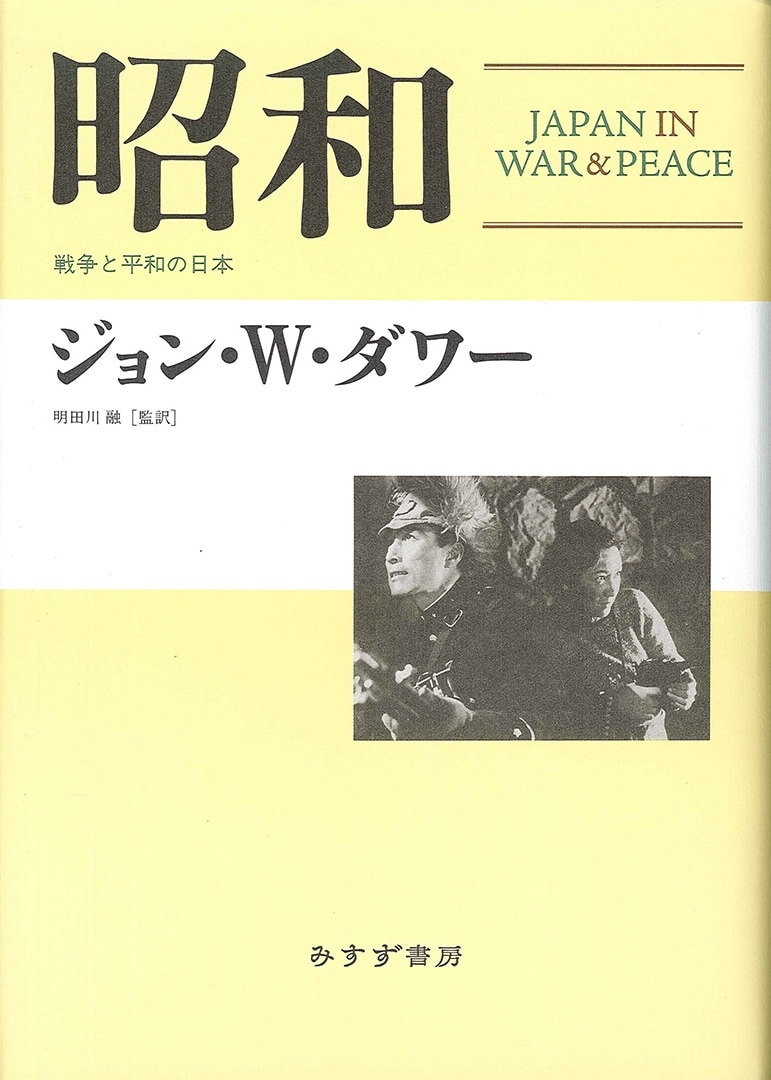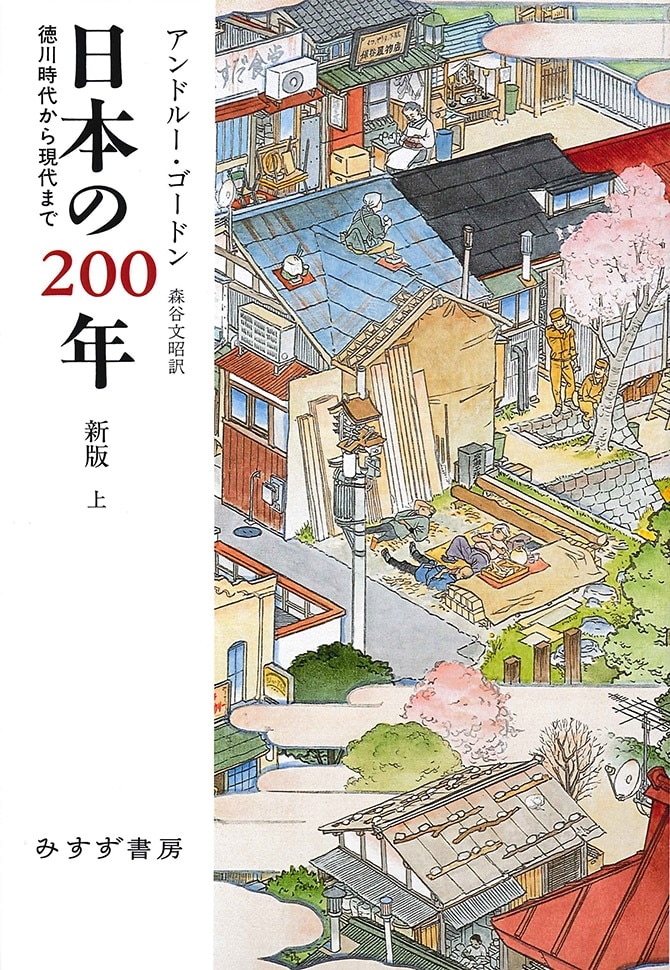新刊『帝国の虜囚――日本軍捕虜収容所の現実』(原題はPrisoners of the Empire: Inside Japanese POW Camps, Harvard University Press, 2020年刊)の著者サラ・コブナー氏がアメリカから3年ぶりに来日し、邦訳刊行を記念して編集部でインタビューを行ないました(2022年12月9日、みすず書房にて)。

著者写真
(みすず書房の書庫にて。Photo: Yuki Fukaya)
Q(みすず書房編集部。以下同):最初に日本に関心を持ち、近現代史研究の道に進まれたきっかけを教えてください。
A(サラ・コブナー。以下同):わたしがニューヨーク市で育った1980年代は、まさに「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代で、日本の自動車メーカーの攻勢や、日本企業によるロックフェラー・センターの買収などが大きく報じられていました。そうした報道だけではなく、もっと実際の姿を知りたいと思い、プリンストン大学で東アジアの地域研究を専攻し、言語の勉強を通して次第に日本への関心を深めていきました。学生時代には函館にホームステイし、京都大学にも留学しました。ジェンダー研究に関心があったため、その後、東京大学の上野千鶴子教授のもとでも1年間研究しました。上野先生のご専門は社会学なので、私の専攻する歴史学とは異なりますが、アメリカでのジェンダー研究は多くの分野にまたがる横断的な領域ですので、日本のジェンダー研究の知見も含めて、得るところがたくさんありました。
歴史を専攻したのは、「現在を理解するためには過去を知る必要がある」と考えたからです。言語やジェンダーなどに対するわたしの関心は、「いま」を理解したいという思いに発していますが、言語もジェンダーもみな過去に根差すものであり、歴史を学ぶことは、この世界を理解するための最良の方法だと考えています。
Q:本書のテーマである、第二次大戦中に日本軍に捕らわれた捕虜について研究しようと思われたのはなぜでしょうか?
A:わたしの祖父の世代にあたる年配のアメリカの方と日本について話すと、しばしば第二次世界大戦の、とくに日本軍による捕虜の過酷な扱いの話になります。これらは、大学の日本史の講義では教わらなかったテーマです。南京事件や慰安婦問題、太平洋戦争における重要な戦闘については教わりましたが、捕虜問題にはそれまで触れてきませんでした。大学で論じられている歴史と、一般の人の語る歴史との間にこうした乖離があるのを不思議に思い、詳しく調べて発表することでその溝を埋められるのではないかと思ったのです。
Q:アメリカではそうした捕虜体験がしばしば語られるのに対して、日本では連合軍捕虜の歴史に対する関心はそれほど高くありません。本書が、国同士で異なるナラティブ(語り)に、橋をかける一助となることを願っています。お考えをお聞かせください。
A:日本にも、わたしが本書で参照している内海愛子先生の一連のお仕事(『日本軍の捕虜政策』ほか)があることは、申し上げておきたいと思います。
また、甥が米陸軍のレインジャー部隊に所属しているのでよくわかるのですが、得てして軍人は、戦闘において勇敢に闘い、勝利の栄光を勝ちとることをもっとも重視し、捕虜になったり収容所の監視兵を務めたりという経験には、そもそも重きが置かれません。ニューメキシコ州のアルバカーキで開かれた元捕虜たちの集いに参加した折、当事者である親たちよりも、その子供世代の方々のほうが、捕虜体験を語り伝えることに熱心だと感じました。ただし、両親から聞いた過酷な体験談に固執するあまり、(その他の語りには耳を傾けない)やや非妥協的な姿勢も感じました。とはいえ、捕虜体験者たちの貴重なオーラル・ヒストリー(口述歴史)は着実に積み上げられていますので、それらにもっと耳を傾けることは重要です。
Q:本書では、兵士だけでなく、女性や民間人の捕虜についても取り上げている点がユニークですね。
A:もともとジェンダー問題に関心があったこともあり、女性や民間人捕虜にも自然と目が向きました。男性兵士にくらべて記録が少なく、より語るのが難しいテーマです。ただし、捕虜生活で困難に直面したのは女性だけでなく、男性兵士も同様でした。1940年代の兵士にとっては、戦場で武勲を立ててヒーローになることが至上価値であり、日本でも米国でもそこに差はありませんでした。捕虜になれば戦闘には参加できませんから、兵士たちにとって時間が止まってしまうような経験であり、そこには男性性の危機という、もうひとつの興味深いジェンダー問題が存在していたのです。
Q:本書の第1章でも詳しく紹介されているように、日露戦争や第一次世界大戦時に日本が敵国の捕虜に示した歓待ぶりは、鳴門市におけるドイツ兵捕虜との交流のように、いまでも「よい歴史」として言及されますが、第二次世界大戦時の連合軍捕虜に対する虐待については、日本国内で表立って語られることは多くありません。そうした過去の「不都合な歴史」に、私たち一般人が関心を向けるためには、どんなことが大切でしょうか?
A:わたしは研究者として多様なものの見方に関心があるため、適任な回答者ではないかもしれません。もちろん、過去を直視するのは簡単なことではありませんが、捕虜経験者がみな亡くなってしまうまえに、当時の実態についてもっと論議を深めておくことは大切です。韓国で、日本軍捕虜収容所の監視兵だった男性を訪ねた際に、かれが大切に保管していた新聞記事を見せてもらいました。そこには、かれがオランダ人の元捕虜と再会したときに、収容所での過酷な労働から守ってくれたことに対して感謝を伝えられた旨が記されていました。この挿話からは、被害者と加害者とを単純に切り分けられない歴史の複雑性が垣間見えます。韓国の元監視兵のなかには、自らを(大日本帝国統治下で監視兵の役割をやむなく担わされ、かつ連合国側からは捕虜虐待の戦犯として扱われた)二重の被害者だと認識している人も多くいます。
また、現在のロシアによるウクライナ侵攻でも、第二次世界大戦時と似た捕虜問題が起きているようです。もちろん、今般の侵略とそれに伴う一連の問題を引き起こしたのはロシアのプーチン大統領ですが、一方でウクライナ側も捕虜虐待などの戦争犯罪と無縁ではありません。第二次大戦後に、日本軍の過酷な捕虜の取扱いを受けて改訂されたジュネーブ条約にも改めて注目が集まっています。日本軍の捕虜収容所と同様の状況は、キューバのグアンタナモ収容所で起きた米軍によるテロ容疑者への拷問でも見られました。現在のウクライナの状況は目まぐるしく変化しており、現時点で断定的な評価を下すことには慎重でありたいと思いますが、こうした「いま」起きている問題をきちんと理解するためにも、過去に目を向けることはやはり有意義だと考えています。
Q:本書を書くための調査の過程で、どんな興味深い発見がありましたか?
A:大きく2点あります。ひとつ目は、それまでのわたしの不勉強もありますが、第二次大戦中にスイスをはじめとする中立国・組織が果たした役割について目を開かされたことです。スイスは、戦時中にアメリカの対日利益代表国を務め、日本治下の捕虜収容所への訪問や捕虜と本国との連絡役を担っていました。赤十字国際委員会(ICRC)は捕虜あての救恤品を届ける役割を果たし、スウェーデンは在日オランダ民間人の利益代表およびハワイの日本人の利益代表として機能していました。彼らは敵対国のあいだで、とても重要なコミュニケーションの担い手となっていたのです。ふたつ目は、朝鮮半島に置かれた捕虜収容所の実態です。京城や仁川の収容所は連合国側に見せるための「模範収容所」として設計され、他の収容所と比べても連合軍捕虜の扱いはかなりましでした。こうした実態は、虐待とセットで語られる従来の日本軍捕虜収容所のイメージとはかなり異なるものでした。2019年には、学校になっている京城俘虜収容所の跡地を訪問し、さらに理解を深めることができました。
Q:本書の刊行後、アメリカの読者の反響はどのようなものでしたか?
A:さきほど申し上げたように、捕虜になるのも監視兵になるのも、戦場の栄光からは遠く、ごくふつうの人間にとってはとても過酷な体験です。そのためか、「これは自分が読みたかった本ではない」という趣旨のメールがかなり届きました。一方で、この本の多様なものの見方やさまざまなニュアンスを込めた分析をほめて下さる方もいらっしゃいました。歴史研究者としては、読みたい歴史をつづるのではなく、史料に依拠して言えることを語るのみです。なかなか難しいことではありますが。
Q:現在取り組んでいる新たな研究プロジェクトについて聞かせてください。
A:第二次世界大戦中の日本人および日系人の強制収容について調査を進めています。アメリカ西海岸、ハワイ、英国、オーストラリア、ニュージーランドなど各地の事例を調べています。アメリカでは、太平洋戦争中の日系人の強制収容は政治的な文脈で語られますが、わたしはこの問題をもっと国際的な視野に立って理解したいと考えています。幸運にも、アメリカで強制収容された日系人の父が書き残したという手紙をその娘さんに見せて頂く機会がありました。それによると、かれは当時、日本が戦争に勝利することを願っていたそうです。強制収容された日系人で、同じように考えていた人はほかにもいたはずです。こうした事実は、アメリカでは政治的に不人気なテーマですが、いまは学校のカリキュラムも多様化しており、アジア系アメリカ人の歴史の掘り起こしも盛んになっていますので、新たな史料をもとに、過去の多面的な実態にさらに迫っていきたいと考えています。日本やオーストラリアでも調査が必要ですし、(中立国だった)スペインやスウェーデンでも調査を進めたいと考えています。

(Photo: Yuki Fukaya)