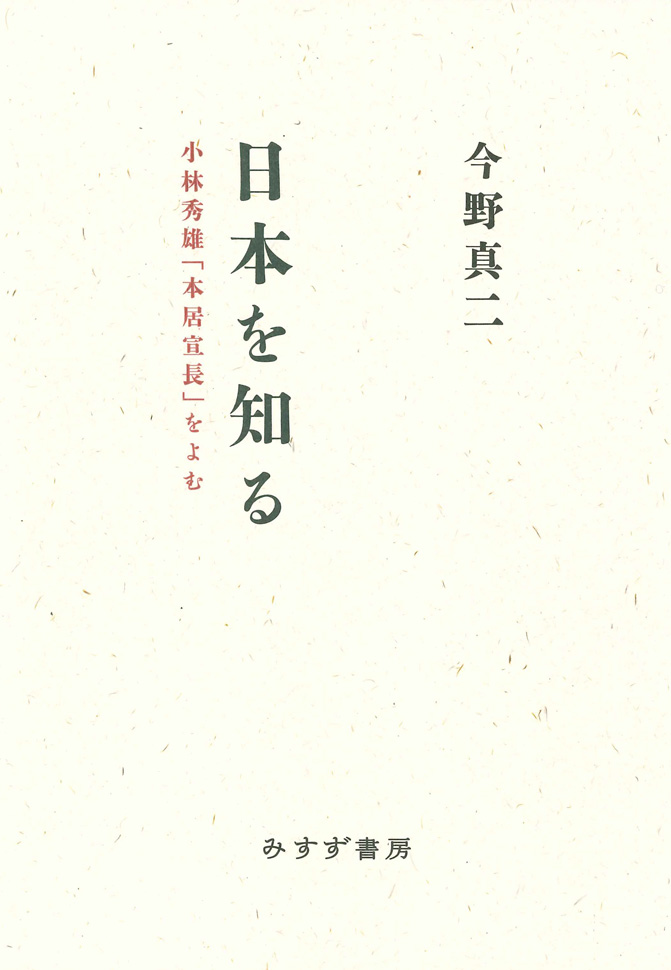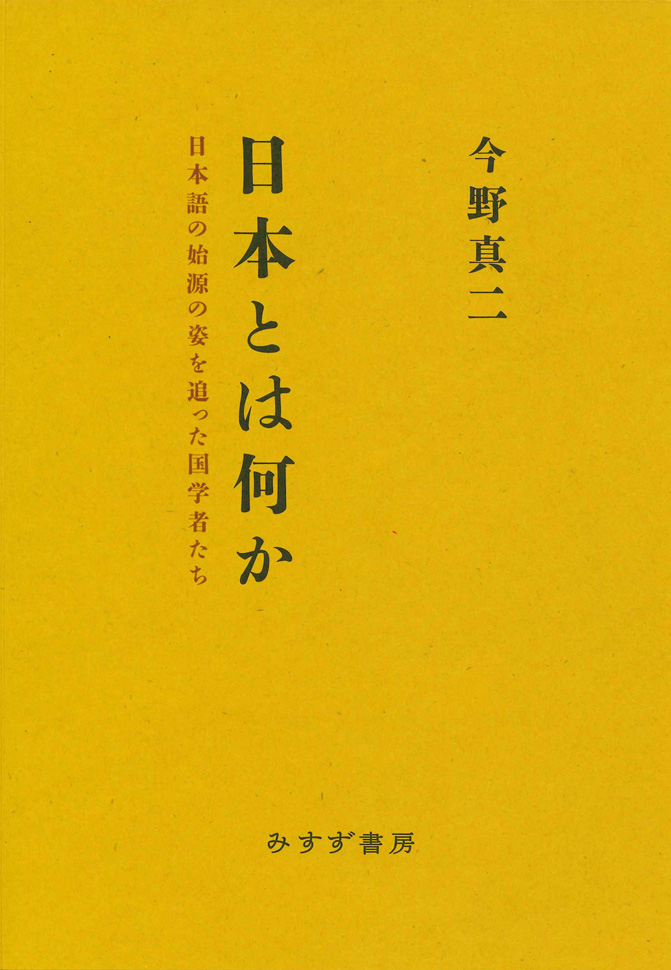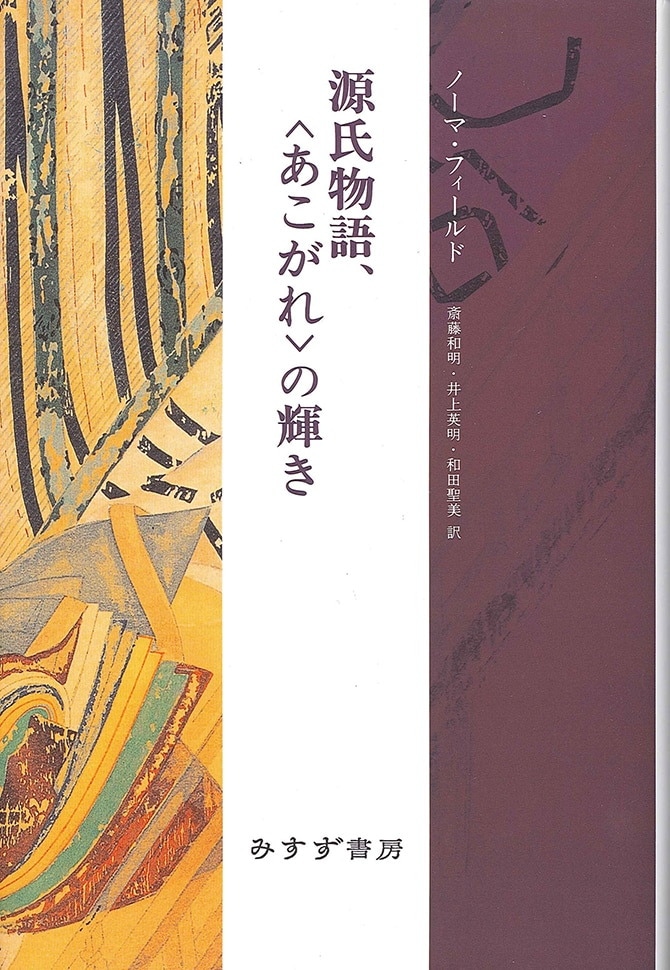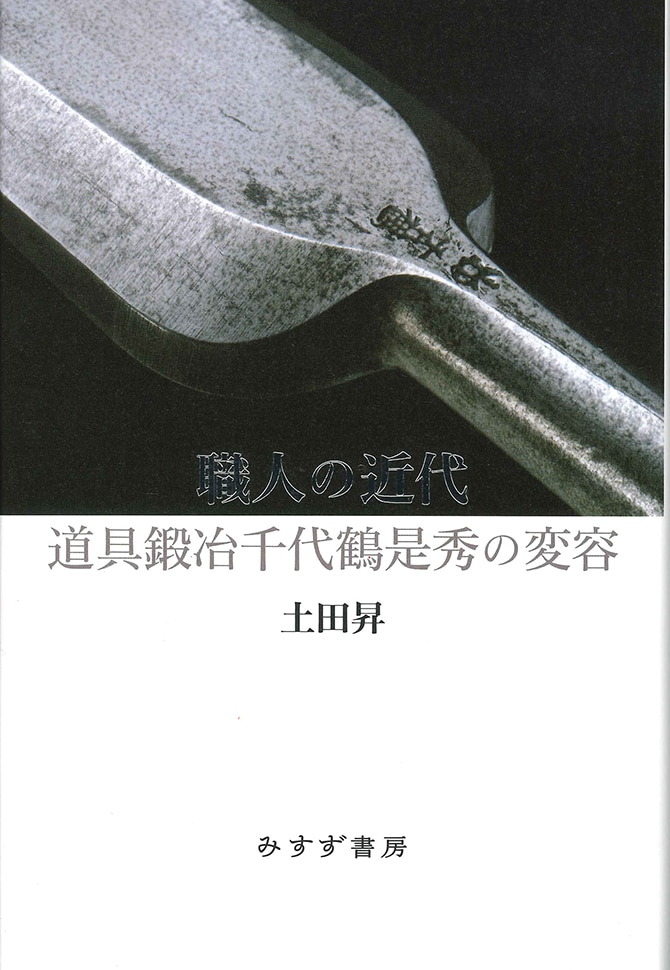小林秀雄は、自著『本居宣長』についてこんなことを言っている。
――私の本は、定価四千円で、なるほど、高いと言えば高いが、其の吟味に及ばないのは麁忽(そこつ)の至りなのである。私の文章は、ちょっと見ると、何か面白い事が書いてあるように見えるが、一度読んでもなかなか解らない。読者は、立止ったり、後を振り返ったりしなければならない。自然とそうなるように、私が工夫を凝らしているからです。これは、永年文章を書いていれば、おのずと出来る工夫に過ぎないのだが、読者は、うっかり、二度三度と読んでしまう。(……)
聴衆の諸君も解ってくれたのではないかと思う。売れました。誰よりも販売担当者が、まず驚いた。鎌倉でも、私のよく行く鰻屋のおかみさんまで買ってくれました。鰻の蒲焼と「古事記」とは関係がないから、おかみさんが読んでくれたとは思わないが、買った本は、読まなければならぬなどという義務は、誰にもありはしない。しかし、出版元は、客が買えば印税を支払う義務がある。私としては、それで充分である――(「本の広告」、新潮社『波』1979年4月)
1965年5月から1976年10月まで、雑誌『新潮』に断続的に連載されたものを一冊にまとめた『本居宣長』。新潮社のウェブサイト内にある「小林秀雄─その歳月」には、「昭和52年10月30日、「本居宣長」は菊判600余頁、定価4000円の単行本となって世に出た。葉書が20円、封書が50円だった年である。たちまちベストセラーとなって発売約2ヶ月で5万部を、約半年で10万部を刷った」とある。「定価4000円」というのは、はがきの値段を基準に考えると、今の金額にして17000円。その本を――「買った本は、読まなければならぬなどという義務は、誰にもありはしない」としても――半年で10万人もの人が買った。パチンコ屋の景品になったとか、財界人がお歳暮として贈ったとかという現象までおきた。
一方、昭和の受験生にとって小林秀雄は「よく出題されるので読んでおけ」と言われる必読書だった。それが平成になると入試に出されることもめっきり少なくなった。そして平成25年。この年のセンター試験の国語は平均点が前年を17点も下回る過去最低を記録したが、大幅に平均点が下がったのは、第一問の小林秀雄の随筆(「鐔(つば)」)のためだったという。
そういえば、「本居宣長」連載中盤の1970年に高校生だった先輩からこんな話を聞かされたことがある。近所の図書館に『新潮』の最新号が入るとすぐこの連載を読んでいたが、それでは飽き足らなくなり、ノートに筆写を始め、旧字旧仮名で書かれた小林秀雄の原文どおりに写す作業を何年も続けた、と。その先輩が、最近になってKindleで『本居宣長』を買いなおしたという。そして、漏らした言葉――「こんな面倒くさい文章を18歳で精読していた自分に驚いた。今の時代にこれを丁寧に読める若者がいるとは思えない」
今の時代にこれを丁寧に読める日本人がどのくらいいるだろう?
このことは、日本語の歴史について考えつづけてきた著者が『日本を知る』を書こうとした出発点にあった問いのひとつでもある。ただし著者がめざしたのは、「一度読んでもなかなか解らない」ように「工夫を凝らしている」と小林秀雄自身が言ってのける『本居宣長』を丁寧に読むことのさらに向こう、宣長から小林秀雄を逆照射しながら読むことで「日本を知る」ことだ。著者の考えを聞こう。
「日本を知る」が本書のタイトルであるが、一気に「日本を知る」ことができないことは言うまでもない。しかし、少しでも自分の感覚として日本を知ってみたいということになれば、日本を知ろうとしたテキストを「追跡(トレース)」することがいいのではないか。宣長は「日本の始原」を知ろうとした。そのアプローチが『古事記伝』『紫文要領』といったテキストとして残されている。「うひ山ぶみ」は宣長のテキストを「追跡(トレース)」するためのガイドブックといってよいかもしれない。宣長を「追跡(トレース)」することによって、あるいは「古典」を「追跡(トレース)」することによって、戦前から戦後の日本を知ろうとしたのが小林秀雄であったとすれば、小林秀雄「本居宣長」は「日本を知る」ために「追跡(トレース)」する対象としては恰好のものであることになる。
本書の原稿を書いたのは、日本が急速に変わっていっていることが実感されたからにほかならない。稿者の立場でいえば、「日本語が」というべきかもしれないが、「言」が「心」をあらわしているという宣長の「みかた」にしたがえば、日本語の急激な変化は、やはり日本の変化ということになる。
江戸時代以降の日本語が「近代語」だというのが日本語学の「みかた」である。稿者が大学生の頃には、「日本語の歴史」は明治時代の途中までで終わっていた。大正の日本語、昭和の日本語はまだ「日本語の歴史」の中に入っていなかった。場合によっては明治の日本語も、だっただろうが、大正の日本語も、昭和の日本語も、まだ「ネイティブスピーカー」がいた。知りたかったら直接聞くことができた。しかし、昭和が1989年に64年で終わり、平成が2019年に31年で終わり、大正の終わりからすでに100年近くが経過し、2025年が昭和100年にあたる年となった今、昭和は「歴史」になったといってもよいだろう。
江戸時代から現在までを「近代語」としてくくることはいずれできなくなるだろう。それができないと意識された時が近代の終わりということになるが、その時期はすでに到来しているのかもしれない。小林秀雄は昭和58(1983)年、昭和が終わる6年前に亡くなっている。無理に重ね合わせる必要はないが、昭和が終わる頃、「近代」が終わったという「みかた」はあるいは成り立つのかもしれない。だとすれば、現在できることはその「近代」をできるだけ過不足なく、未来に伝えることだろう。
本書第七章で、「小林秀雄は古い」という言説について採りあげた。そこでは小林秀雄が古くなったのではない、と述べた。しかし、小林秀雄が古いと感じるのであれば、それはそれでもいいかもしれないとも思う。小林秀雄が「近代」を体現しているのだとすれば、その古くなった小林秀雄を古典として読めばよい。ただし、やはり読み解くことは簡単ではないだろう。
(……)
「残そうという意志」がテキストを残し、未来へテキストを伝える。しかし、江戸時代をまがりなりにもとらえるための基本的な文献が揃わないうちに、江戸時代は遠ざかっていく。過去に目を向けなくなるということは「歴史」という概念を崩す。「おもしろい」かどうかという価値観もおそらく「歴史」という概念を崩す。「わかりやすい」ことはわるいことではない。しかし、「今・ここ」を起点として、「わかりやすい」ことを過剰に追究すると、今すぐにわからないことは価値がないという考え方を生み出す。(本書「おわりに」より)
2025年の今、あえて「今・ここ」を起点とした「わかりやすさ」を最優先にしようとせず、そこにある具体的なテキストだけを拠り所として、読む。江戸時代から明治、大正、昭和の時代への連続性と非連続性を探りながら、「近代」の日本を未来へと残し、伝える。