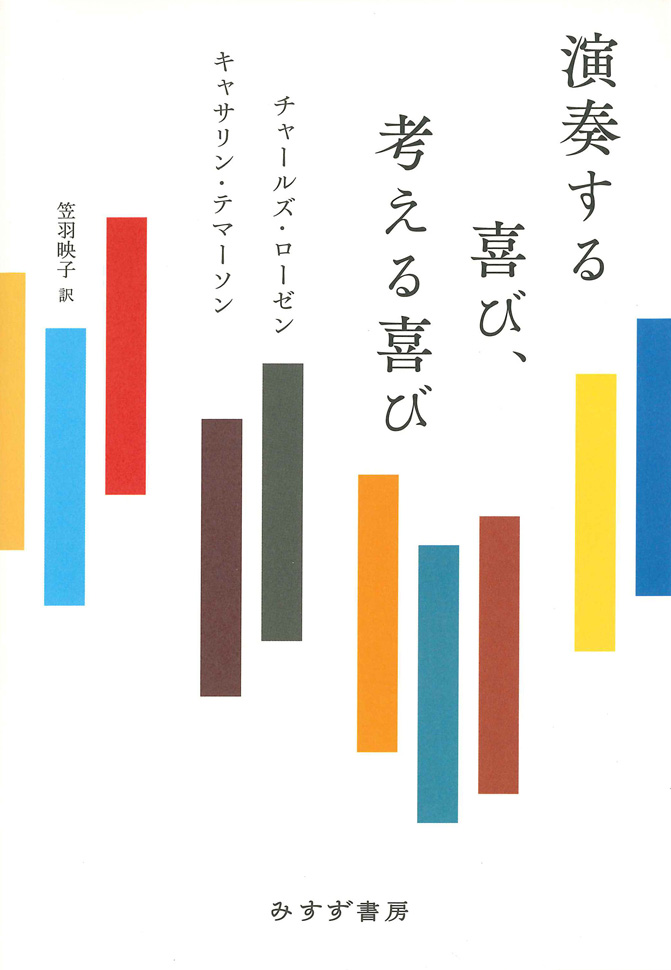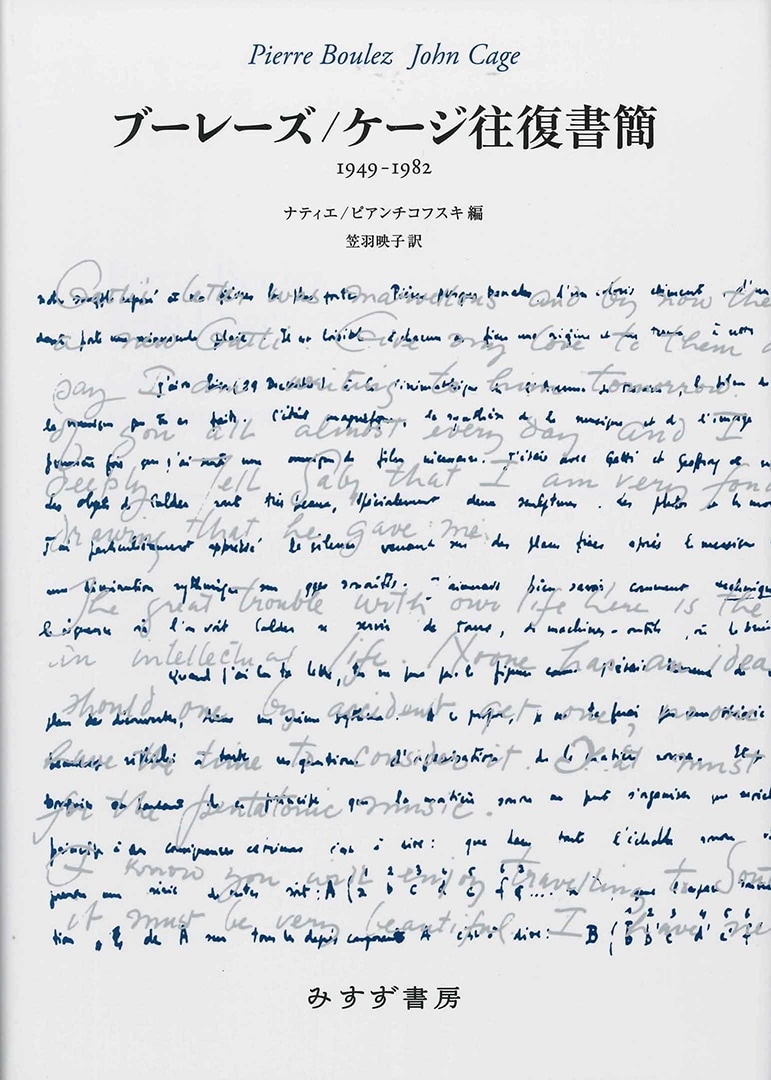〈スターバト・マーテル〉
ジョヴァンニ・バッティスタ・ペルゴレージ
(1710-1736)
これまでヴィヴァルディ(4月18日)、アリッサ・フィルソヴァ(7月24日)が魅力的な曲にしているのを聴いてきた〈スターバト・マーテル〉の第3弾、そして今年最後の〈スターバト・マーテル〉は、ジョヴァンニ・バッティスタ・ペルゴレージのもの。26歳で結核に倒れたペルゴレージは、その短い人生にあっといわせるようなことをやってのけた。オペラや協奏曲などその音楽はいくつもの形式にわたり、今日の私たちにはまったく古来のものと聞こえても、当時は、それを根底から覆す新しい、聴き手の心に直接響く様式の創始者とみなされていた。彼の次の世代のあるフランスで活動した作曲家は、「ペルゴレージが生まれ、真実が明かされたのだ!」と熱心に賞賛した。
〈スターバト・マーテル〉以外のそうした作品にもかかわらず、ペルゴレージの名前が音楽史に刻まれたのは、13世紀のカトリックの聖歌の、胸が張り裂けるような彼なりの解釈である。灼けつくような痛みの感情、ときに不協和なソプラノとアルトの二重唱は、磔台の下で夜を明かしたマリアを、ときに優しく心に触れ、ときに苦悶そのものの音楽のうちにまざまざと甦らせる。作品は当初より聴衆の心をとらえ、18世紀にもっとも頻繁に印刷された音楽作品となった。その評判はたちまちヨーロッパ中に広がり、イギリスではアレクサンダー・ポープの詩を、ドイツではフリードリヒ・ゴットリープ・クロップシュトックの詩をこの音楽にのせるなど、別のものに用いられた。他方バッハはこの曲に完全に圧倒されてしまい、詩篇51〔の言葉〕を乗せるのにペルゴレージの曲をそのまま下敷きにして編曲した(BWV1083)――それは彼の最大の賛辞のあらわれであったのだ。