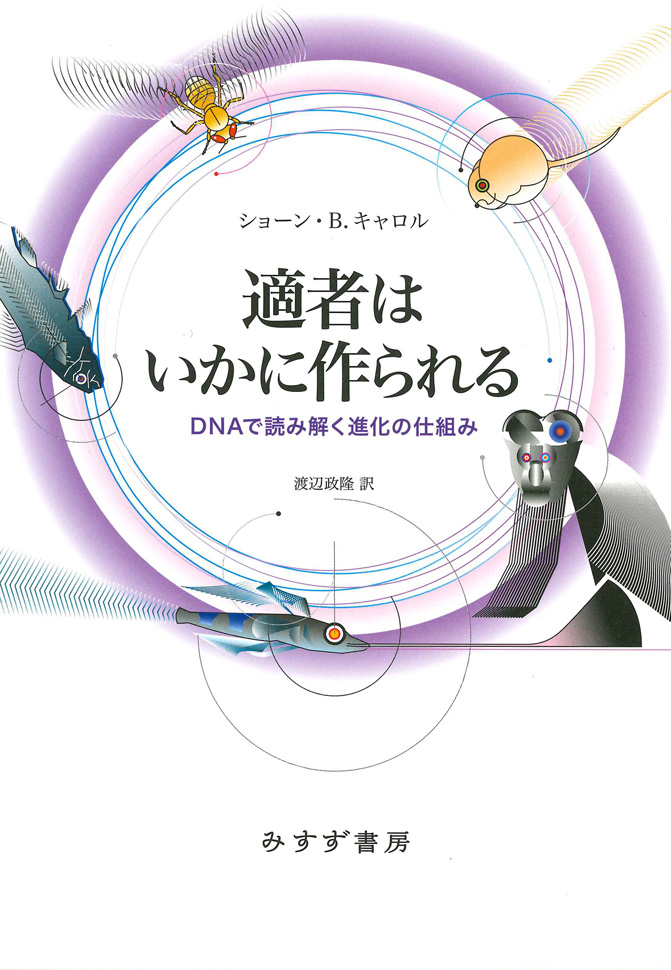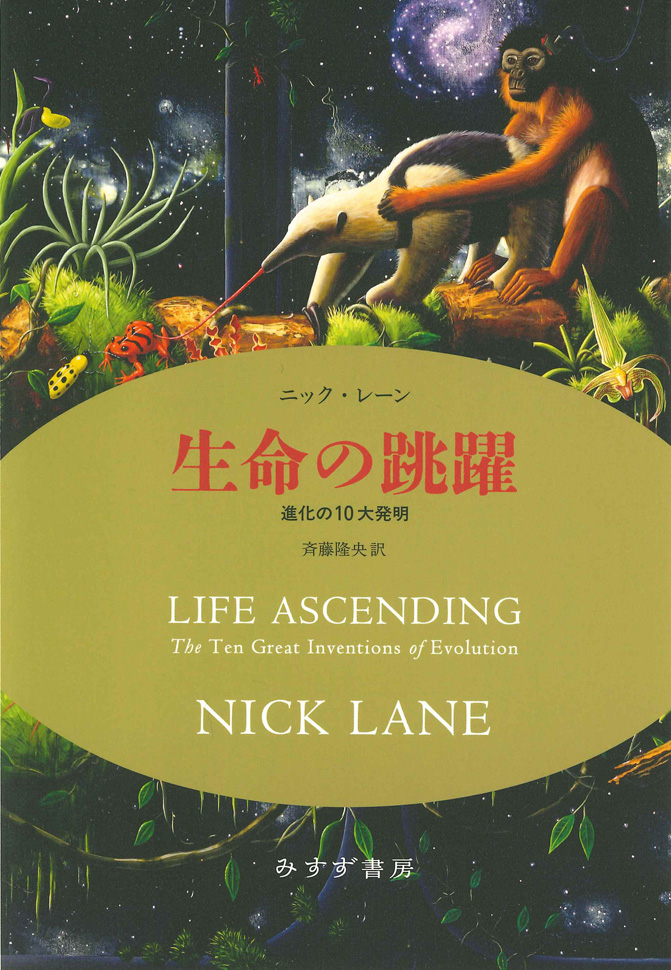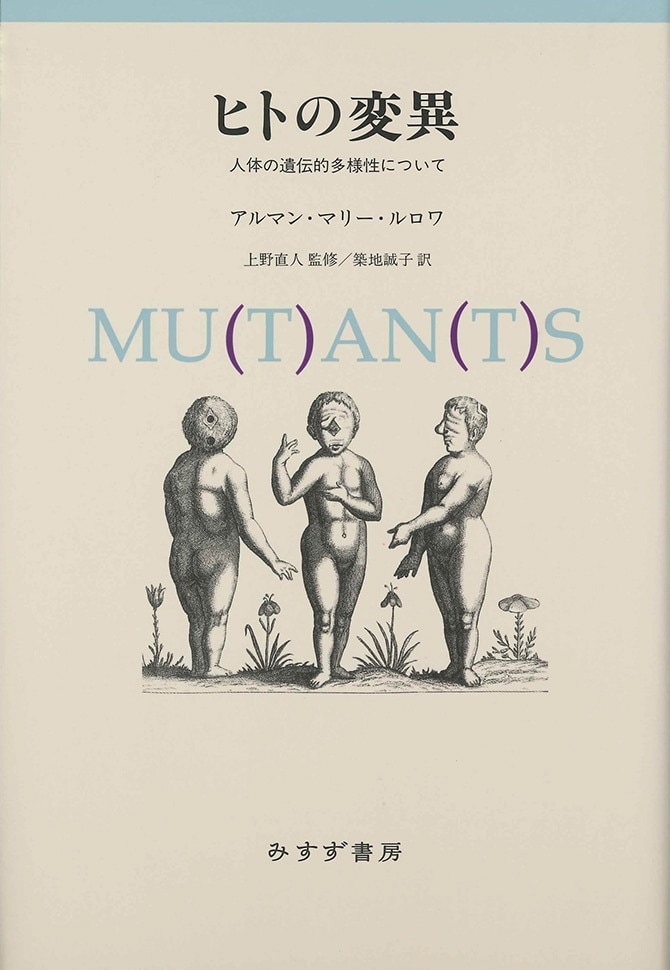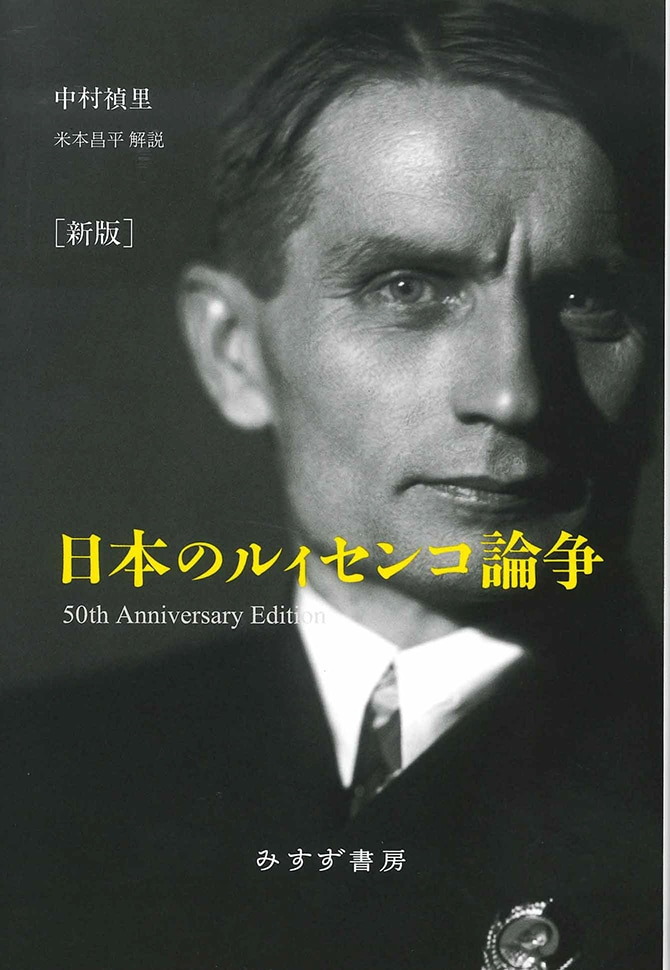渡辺政隆
実際の犯罪捜査のみならずドラマでもおなじみのDNA鑑定。それは一人ひとりのDNAの塩基配列がみな少しずつユニークでありながら、血縁者で共通する部分があることを利用した技術である。この技術は、生物種の同定や種間の類縁関係の推定でも活用されている。ダーウィンは、「生物は共通の祖先から分岐を繰り返すことで、かくも多様な種類に分かれてきた」と喝破した。その痕跡が、生物のDNAには刻まれているのだ。
本書の原著は、アメリカの進化発生生物学者ショーン・B・キャロルのThe Making of the Fittest: DNA and the Ultimate Forensic Record of Evolutionである。副題にあるUltimate Forensic Recordとは「法医学的証拠」つまりDNA鑑定のことで、DNAレベルで立証されている進化の驚きの例をあげながら、進化の原理を鮮やかに解き明かしている。原著の出版は2006年ではあるが、その内容は未だに大いに示唆に富んでいる。出版の翌年には、アメリカの一般向け科学書を顕彰する権威ある賞、ファイ・ベータ・カッパ賞に輝いている。
著者のキャロルは、1960年に五大湖の一つ、エリー湖の西端に位置する地方都市トレド(オハイオ州)で生まれた。セントルイス・ワシントン大学で生物学を学び、ボストンにあるタフツ大学大学院生物医学研究科に進学し、免疫学で博士号を取得した。その後、研究分野を発生生物学に変え、ショウジョウバエ、蝶その他の動物における体のパターン形成の研究で数々の業績を上げてきた。蝶の翅の目玉模様を形成する遺伝子が、じつは昆虫の脚の形成を支配している遺伝子と同じであることを突き止めた研究は特に有名である。キャロルは進化発生生物学(略称はエボデボ)と呼ばれているこの分野を牽引してきた。最近は、少年時代から愛してやまないヘビを材料に、毒遺伝子の進化に関する研究にも手を染めている。
キャロルは科学教育とサイエンスコミュニケーションにも力を入れている。『DNAから解き明かされる形づくりと進化の不思議』(羊土社、2003)はエボデボの教科書として定評がある。一般向けの科学書としては、『シマウマの縞 蝶の模様――エボデボ革命が解き明かす生物デザインの起源』(光文社、2007)、『セレンゲティ・ルール――生命はいかに調節されるか』(紀伊國屋書店、2017)のほか、高校生、大学生向けの副読本なども執筆している(いずれも未訳)。2010年には、進化学の普及に功績のあった人に国際進化学会が贈るスティーヴン・ジェイ・グールド賞に輝いている。かねてから同じ進化研究者で大の野球ファンでもあったグールドを敬愛していたキャロルにとっては何よりもほしい賞だったかもしれない。また、ハワード・ヒューズ医学研究所の科学教育担当副理事長(2010-20)、科学と教育メディアグループ担当副理事長(2022-23)を務め、科学ドキュメンタリー映画の制作にも幅を広げ、いくつかの作品は賞に輝いている。長らくウィスコンシン大学マディソン校に席を置いていたが、現在はメリーランド大学特別栄誉教授の称号の下、同大学に研究室を構えている。
キャロルが追究してきた大きな研究テーマは、生物の新規な形質はいかにして進化するかだった。生物進化の研究では、かつては化石を調べるか、現在の生物の形態や行動、生理生態を比較することで類縁関係や進化の経路を類推するしかなかった。しかし分子生物学が発展したことでDNAレベルでの進化の研究が可能となった。
進化を操っているのは、主に偶然、淘汰、時間という要素である。偶然に生じる突然変異に自然淘汰が作用することで、有用な変異は保存され、集団中に広がっていく。こうした過程がゆっくりと長期にわたって繰り返されることで新しい形質や種が進化し、生物は多様化してきた。これが、1980年代まで進化学説の主流だった進化の総合説の骨子である。しかし分子レベルの研究が進んだことで驚きの発見がもたらされた。
分子レベルでは自然淘汰の網の目にかからない中立な変異が多く保存されている(いずれ有用な変異に変わる可能性もある)。機能を失い不要となった変異は除去されずそのまま痕跡として残されることがあり、進化の経路を教えてくれる「遺伝子化石」となっていたりする。新しい形質の誕生にあたっては、まったく新しい遺伝子が出現するとは限らず、既存の遺伝子の流用や改変による場合が多い。多くの動物の体作りにおいては共通する遺伝子群が関与している。それなのに見かけや性質が異なるのは、それらの遺伝子のスイッチ切り替えを担う調節遺伝子が変更されているからだ。たとえばキャロルが発見した、翅の目玉模様の発生機構もその一例である。発生生物学のアプローチによる進化研究(エボデボ)が、新たな地平を開いたのだ。進化発生生物学の新知見を導入することで総合説を拡張できるというのがキャロルの立ち位置である。
本書ではイントロである第1章に続き、第2章から第6章まで、キャロルが考える進化の原理がさまざまな実例をあげながら存分に語られている。
第7章は、農耕文化と共に開始された人類とマラリアとの闘い――進化の軍拡競争――やがんとの闘いが語られている。進化の研究は、生物の歴史を探ることにとどまらず、医学にも新しい知見をもたらすのだ。
進化の研究が抱えてきた難問の一つが眼の進化だった。生物界には、単純な眼から複雑な眼まで、さまざまな眼が存在する。しかも、脊椎動物の眼が最も複雑な構造とされているが、イカやタコの眼も、それと同じ構造をしている。いったいこれはどうやって進化したのだろうか。かつてそれらは、それぞれ独立に進化したと考えられていた。それに対して、複雑な構造はどうやって一足飛びに進化したのか、そんなことはあり得るのかというのが、反進化論者の常套句だった。しかしこれもエボデボの成果により、多様な見かけの眼も、じつは分子レベルでは多くの共通点があることがわかってきた。眼に限らず内臓や神経系にしても、複雑な器官を組み立てるにあたっては共通の遺伝的な仕組みを流用していることがわかってきたのだ。第8章ではそれが語られている。
第9章で取り上げられているルイセンコ騒動、反進化論、反科学論の話題は、一見すると場違いな話、対岸の火事じゃないかと思えるかもしれない。しかし科学は政治と無関係ではないし、現在のアメリカの政治状況、新型コロナウイルスの反ワクチン騒動、陰謀論などを見れば、決して人ごとではないことがわかる。
第10章では、貴重な生物資源に対して人類が課している淘汰圧の例が語られている。自然は長い時間をかけて生息環境に適応した「適者」を作り出してきた。そのバランスを人類は崩壊させようとしている。進化学者からの警世のメッセージである。
進化の総合説の立役者の一人だった遺伝学者セオドシウス・ドブジャンスキーは、「進化を考慮しない生物学は意味をなさない」と語った。この言葉を筆者なりに拡張するなら、生命進化の歴史に向き合うと、人は自然に対して謙虚にならざるを得ないと言いたい。人類の進化は偶然と幸運の連鎖の結果であり、必然ではなかったかもしれないと自覚すれば、謙虚にならざるを得ないと思うからだ。その意味でも本書の内容は、今この時点でもタイムリーなものであると信じている。
copyright © WATANABE Masataka 2025
(筆者のご同意を得て転載しています。なお
読みやすいよう行のあきなど加えています)