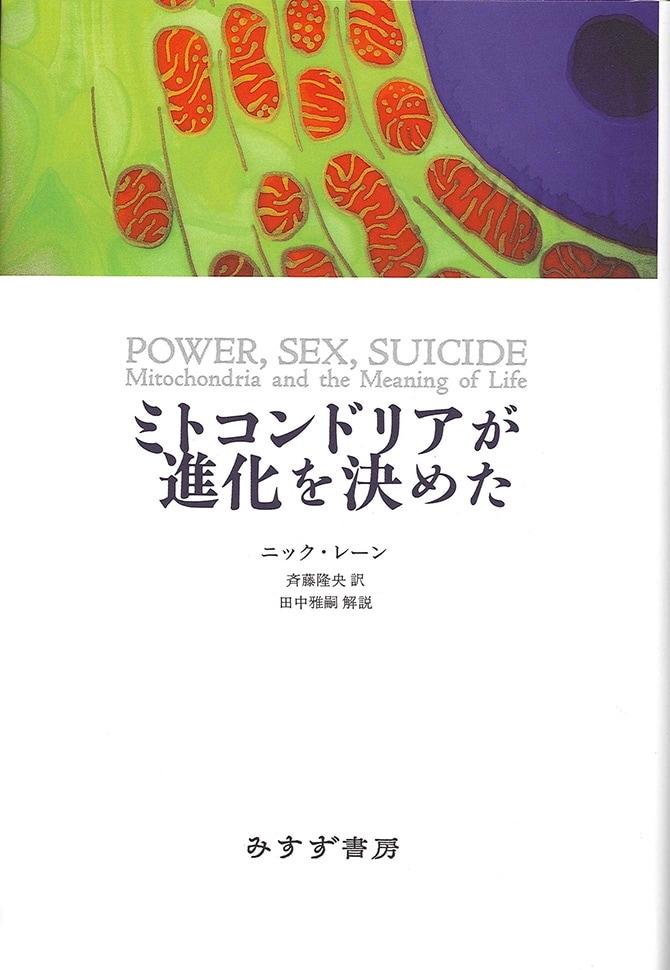ノーベル化学賞を受賞した生物学者V・ラマクリシュナンが、リボソームの構造解明までの競争と協力の日々を、繊細なユーモアあふれる文体でつづった科学史的自伝『ジーン・マシン』。このたびの邦訳刊行に先立ち、田口英樹氏(東京科学大学教授・タンパク質科学)による解説の一部を特別公開いたします。
リボソームという「巨象」を解明する人間ドラマ
田口英樹(東京科学大学 総合研究院 細胞制御工学研究センター)
本書はリボソームの構造と機能の解明への貢献で2009年にノーベル化学賞を受賞したヴェンキ・ラマクリシュナン博士の自伝的科学エッセイである。本編を読む前や本書の購入を検討している人の中にはこの解説欄から読み始める人も多いだろう(私はいつもそうである)。本来の解説に踏み込む前に、想定される読者に合わせて、本書の読み方や読みどころを挙げてみる。
A: 生命科学について興味はあるが詳細は知らないという一般の方々。ノーベル賞を受賞する研究者がどんな人なのか、ノーベル賞級の研究がどのように進められるのか、真実を究めるための競争がどういうものなのか、それらの一端が本書でよく理解できるだろう。なお、章によっては第三章などのように研究手法のかなりマニアックな詳細が記載されている。難しいところはスキップしても十分楽しめるはずである。
B: 大学で生化学を学んだ方。抗生物質に興味のある方。製薬業界の方。リボソームやタンパク質合成のよい復習になるとともに近年の動向まで把握できる。もし、いま生化学を学んでいる学生ならば、リボソームに関する知識が異常に深まり、期末試験で高得点が約束されるにちがいない。生命の根幹に関わるリボソームはストレプトマイシンをはじめとした何十種類という抗生物質のターゲットである。ラマクリシュナン氏は抗生物質がどのようにリボソームに結合するのかを結晶構造解析を駆使して明らかにしたパイオニアであり、その経緯が詳細にわかる。
C: リボソーム研究者。一気読みまちがいなしの必読の書である。本書で登場する人物やエピソードの背景まで知っているとより楽しめるだろう。私自身は筋金入りのリボソーム研究者ではないが、2000年頃にリボソームの結晶構造が《ネイチャー》《サイエンス》《セル》のような超一流誌に続々と出ていた頃をリアルタイムに体験しており、リボソームがここまでわかったのか! と感嘆していたものである。その裏にあった熾烈な競争、駆け引きなどの(ラマクリシュナン氏から見た)記録がおもしろくないわけがない。
いずれのカテゴリーの人でも、(いい意味での)普通の若者がノーベル賞という最高峰の栄誉に輝くまでの研究者人生、途中からはリボソーム構造解明の熾烈なレースを臨場感たっぷりに読み進められること請け合いである。熾烈と言っても、シリアスなだけではなく、著者の信念、逡巡、後悔、共同研究者との交流や友情などが著者独特のひねりの効いたユーモアとともに綴られている。
1952年にインドで生まれたラマクリシュナン氏は研究者として決してエリートコースを歩んできたわけではない。インドでの大学進学も希望通りのところではなかったようだし、理論物理学者を目指してアメリカに渡ろうとしたときも受け入れてくれる大学院に難儀している。苦労して入った大学院で「自分の研究を面白いと思えなかった」というのも驚きである。博士号取得後に生命科学に転向したあとに、たまたま雑誌で見つけたリボソームの記事に魅せられてリボソーム研究を開始したが、当初は比較的地味な生物物理学的な研究に携わっていた。リボソームの真理を知りたいという熱い思いと冷静に編み出した独自の戦略を携えて、リボソームのX線結晶構造解析という表舞台に乗り込み、キラキラと輝くスター研究者たちとレースを繰り広げ、他の誰よりも詳細な結晶構造を得て、最終的にノーベル賞を勝ち取る。このストーリー展開は判官びいきの日本人にぴったりである。また、その率直な物言い、ときに垣間見えるライバルたちへのチクリとした批判など、人間くさいドラマが繰り広げられるようすは、DNA二重らせん構造解明の立役者であるジェームズ・ワトソンが著した古典的エッセイ『二重らせん』を彷彿とさせる。
ここで、ラマクリシュナン氏が人生を賭けて取り組んだリボソームについて補足しておこう。
生命で最も大切な分子は何かと問われてDNAという回答が多いかもしれない。実際、遺伝子情報をもつDNAが生命の設計図として重要な分子であることに間違いはない。しかし、DNA自体は代謝などに代表される生命活動そのものを担っているわけではない。生命における機能分子は基本的にアミノ酸がペプチド結合でつながってできたタンパク質であり、ヒトでは2万種類を超えるタンパク質が存在する。DNAの情報からタンパク質が合成される際の主役がリボソームである。もう少し具体的には、DNAのコピー(転写)であるRNA(mRNA)の情報がリボソームで読み取られてタンパク質が産まれてくる。核酸が連なったDNAやRNAの配列情報(言語)が、核酸とは化学的な性質が大きく異なるアミノ酸がつながったタンパク質に変換されるので、RNAからタンパク質ができる過程は「翻訳」と呼ばれる。本書ではバクテリアのリボソームを扱っているので大腸菌を例にしたファクトを少し紹介しよう。
・細胞の乾燥重量の約30%はリボソームが占める。
・細胞一つあたり6万〜7万個程度のリボソームが含まれる。
・リボソームは50数種類のタンパク質パーツ(サブユニット)と三種類のRNA(リボソーマルRNA)からなるタンパク質─ RNA複合体である。総分子量は250万ダルトン程度で細胞内で最も巨大な分子である。
・機能的な側面から言うと、リボソームは一秒間に15~20個のアミノ酸を順次つないでペプチドとする。タンパク質の平均的なアミノ酸数は約300個なので、リボソーム一分子は一分間にタンパク質四個程度、細胞一つだと一分間で24〜28万個ほどのタンパク質を合成する。
・細胞全体のエネルギーの約半分がリボソームを中心としたタンパク質合成反応に使われている。
こう見ると、細胞というのはリボソームだらけ、生命とはリボソームがひたすらせっせとタンパク質を作っている物体とみなせるかもしれない。
このように生命にとってリボソームの存在感は圧倒的である。分子生物学の黎明期の1950年代に細胞生物学者が電子顕微鏡で観察したタンパク質を合成する「粒々」をリボソームと命名したあと、多くの研究者が長期にわたってその仕組みの解明に取り組んできた。しばらくは生化学的な解析が主であり、本書でのライバルの一人、ハリー・ノラーはリボソーム研究の大御所としてよく知られる人物である。ただ、生化学は「群盲象をなでる」ような学問であり、象がどのような姿をしているのかはっきりしない。ある生体分子の正確な姿(立体構造)がわかると「百聞は一見にしかず」ということでその分子の構造と機能を分子レベルで決定的に明らかにできる。*
そのような理由で、リボソームの詳細な立体構造解明は悲願でもあり、原題「リボソームの秘密を解読するためのレース(The Race to Decipher the Secrets of the Ribosome)」が始まったのだ。
* 実際、これまでにリボソームを含めて10件ほどの生体分子構造の解明にノーベル化学賞が授与されている。
――続きは書籍をごらんください――
(著作権者のご同意を得て抜粋・転載しています)