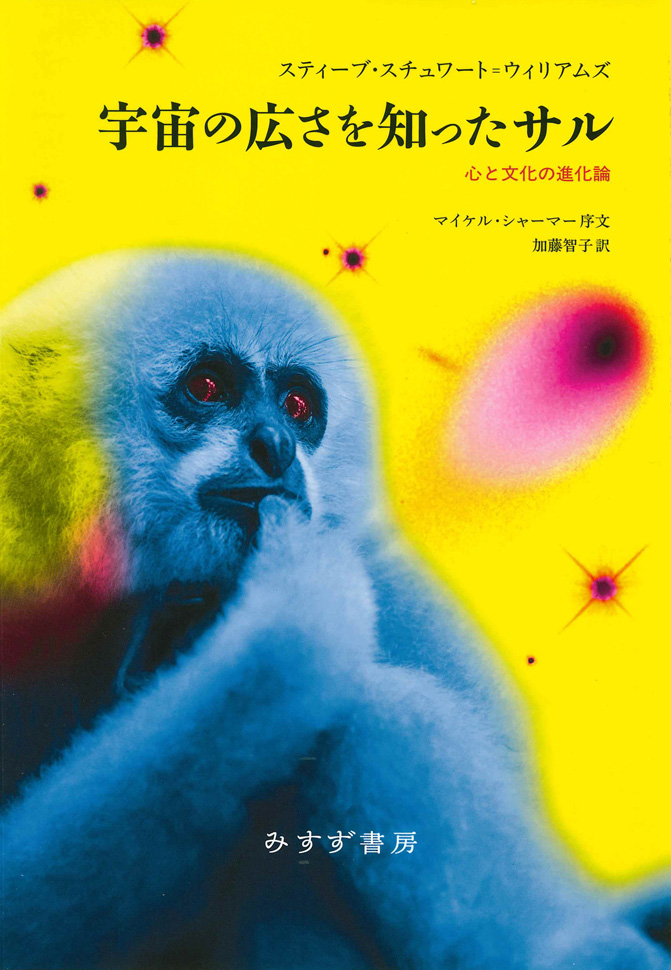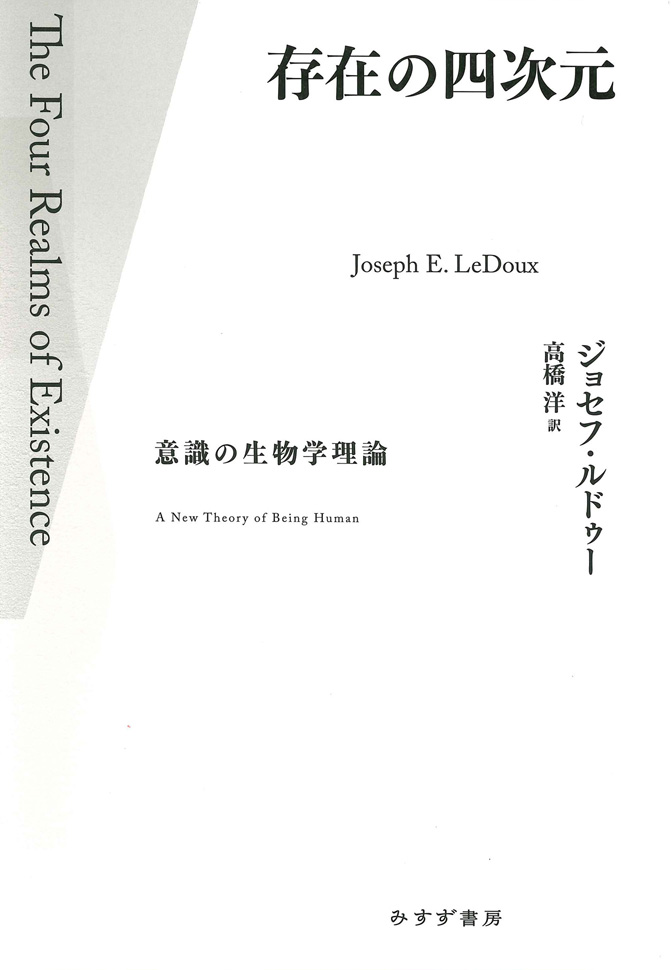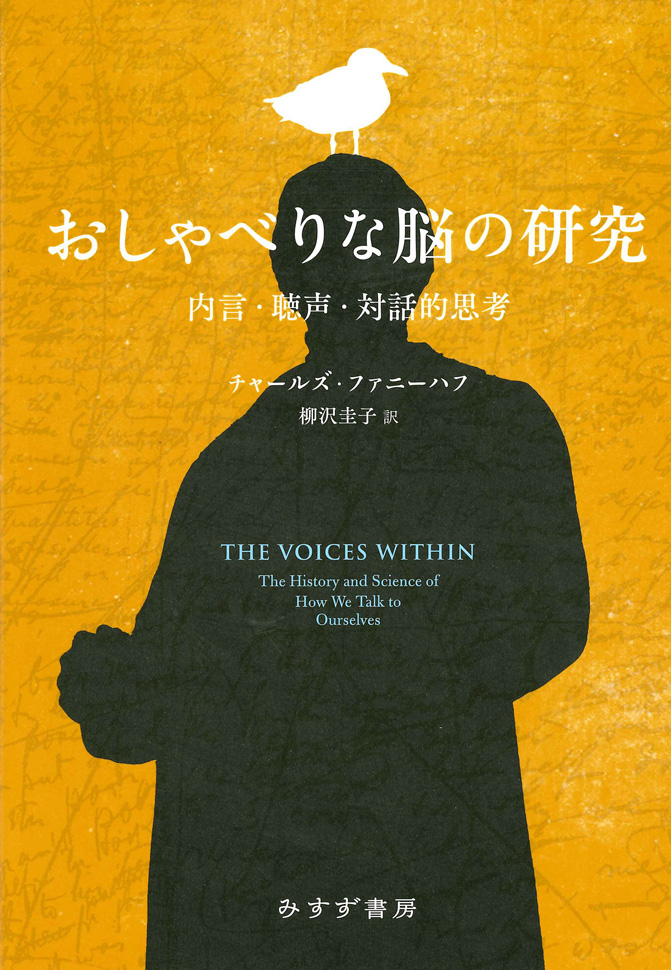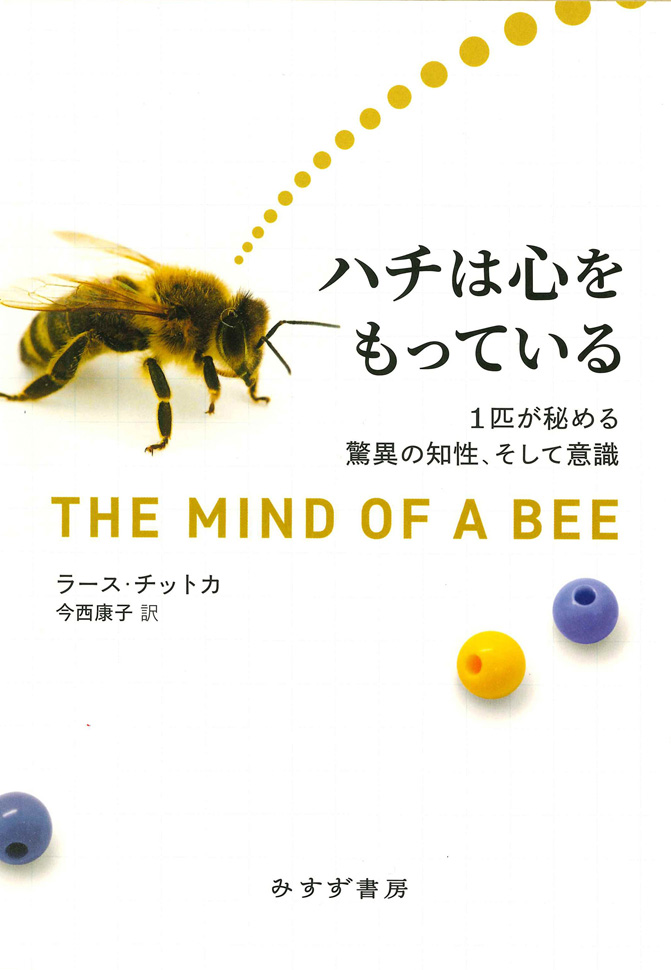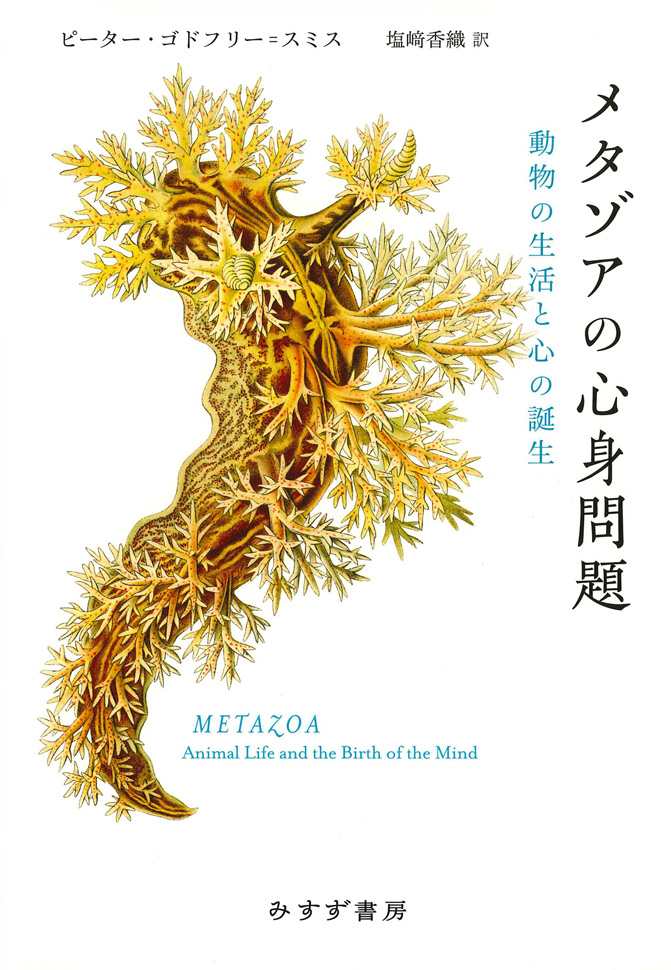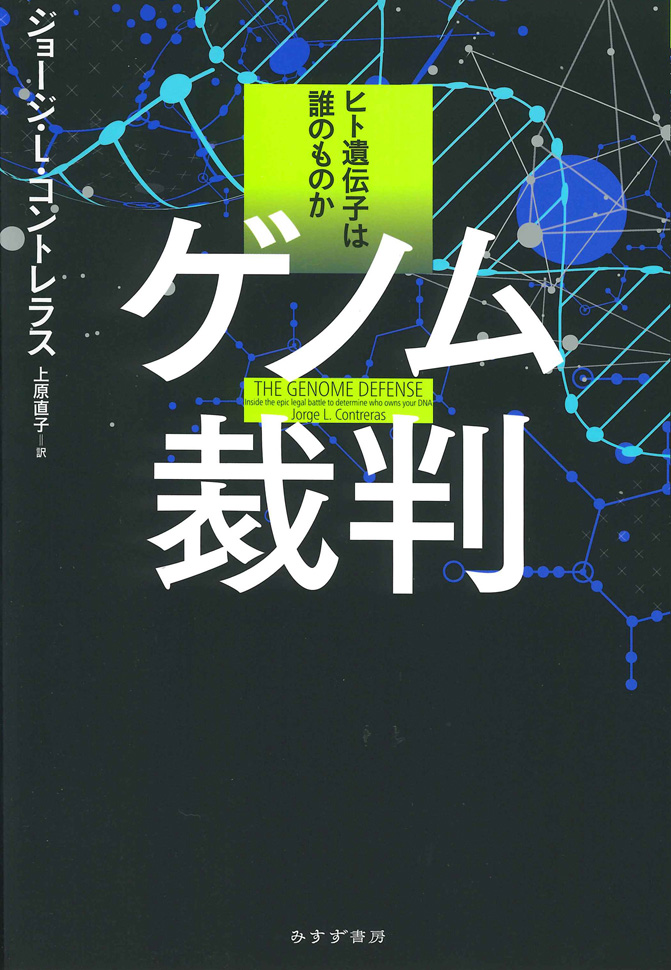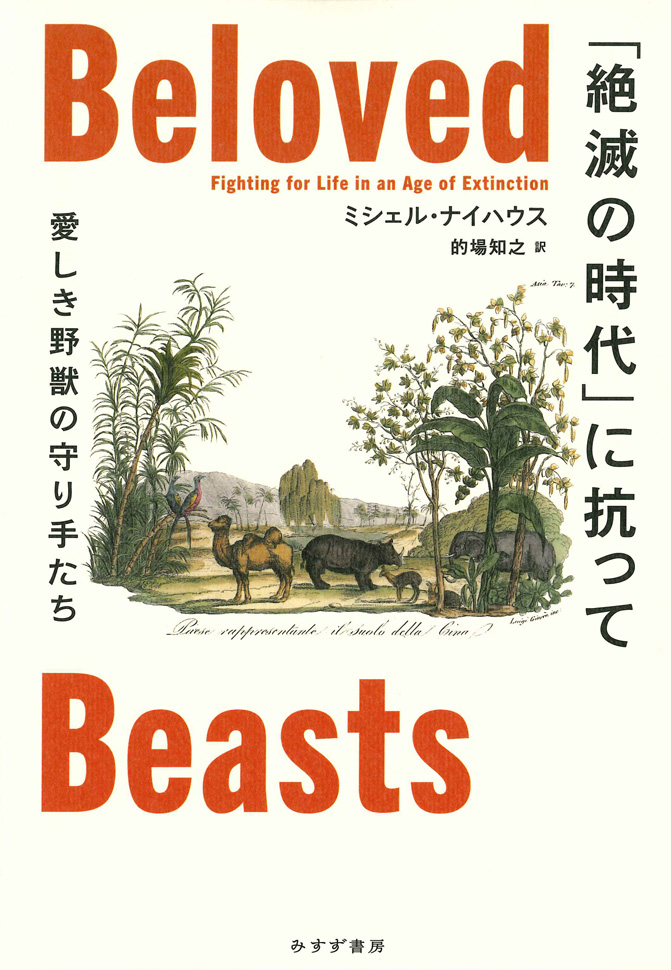地球は、我々の銀河系のはずれにある平均的な恒星の周りをまわる、先行き不透明な小さな惑星だ。大銀河評議会が地球に初めて注目したのは約25周期前のこと、一流の異世界学者であるラム・ティン卿が、この惑星とその周囲で起きている奇妙な出来事に目を留めたことがきっかけだった。45億年にわたるその歴史を通して、地球の変化はごくゆっくりとしたものであり、ときおり隕石の衝突や火山活動による大変動がみられる程度だった。ところが数千年前になって、変化のペースが突如として劇的に速まったのだ。森林は消えはじめ、かわりに「トウモロコシ」「米」「小麦」などの畑が登場した。地面からは奇妙な建造物が次々に生えてきて(これは「都市」とよばれる)、カビのように地表を覆っていった。都市周辺の土地は、長方形などの幾何学的図形に分割されていった。そしてこの100年で、この変化はさらに激しさを増した。地球は突然、大量の電波を発しはじめた。奇妙な金属製の物体が飛び出してきて地球の周りの軌道に乗ったり、完全に地球を離れてほかの天体に向かったりもした。この放浪する孤独な物体は、母星に向けて絶え間なく情報を送信し続けていた。そのためベテルギウス人のなかには、地球が自身の感覚系を発達させ、自分とその周囲についての認識を得るにいたったのではないかと考える者もいた。大銀河評議会は、この可能性に注目した。
3ナノ秒に及ぶ徹底的な議論の結果、評議会は、経験豊富な異世界学者を地球に送りこみ、より詳細な調査を行なうべきとの結論に達した。そして、すぐに仕事に取りかかれる優秀で著名な異世界学者として、私にこの名誉ある任務が託されたのだ。こうして私は地球への途についた。到着してすぐ、私は、地球の周りをまわる金属機械に肉塊生物が乗っていることを確認した。これにより、すでに指摘されていた疑いが事実であることがはっきりした。地球では、自然選択による進化が起きていたのだ。当初、その肉塊生物(「ヒト」とよばれる)が、我々が検知したさまざまな奇妙な出来事にどのように関係しているのかは不明だった。一説では、ヒトは都市あるいは例の金属機械の生殖器官であり、都市または機械は、ヒトを通して繁殖をしているのかもしれないともいわれた。また別の説では、ヒトはトウモロコシや米、小麦の奴隷であるという可能性も提示された。これらの植物がなにかしらの方法でヒトを騙し、自分たちの主要な競争相手である「樹木」を大量殺戮により一掃させ、自らの種を蒔いて広める方法を編み出すように仕向けた、という考えだ。
これらの仮説はどれも完全には却下できていないとはいえ、現在は、地球で起きている奇妙な出来事を主導しているのはヒトである、という説が、異世界学者のあいだで有力になっている。妥当性のもっとも高いコンピューター・シミュレーションによれば、この脆弱な惑星は近年になって、テクノロジーを駆使するヒトという疫病に取り憑かれた。偶然にせよ意図的にせよ、この狂った肉塊ロボットたちは、地球の生物圏に存在する物質を次から次へとヒトに変換し、その数を増やしていく方法を見つけ出したのだ。その過程で、ヒトは急速に地球を支配していった。彼らは植物を奴隷化し、都市を築き、金属製の感覚器官を地球の軌道へと送り出していった。このような所見に基づいて、我々はヒトを調査の焦点に据えることにした。私がこれまでに行なった観察の概要を、以下に記載する。
この先を読む者は注意されたし! ヒトはあまりに常軌を逸した奇妙な生き物であるため、当初ベテルギウス人のなかには、そのようなものが存在していること自体、認めたがらない者もいた。彼らは、すべては第四セクターのグリミーたちが仕組んだでっち上げなのではないか、と考えた。あるいは、D恒星領域のナルボ人たちが悪ふざけで選抜育種をした結果できたのがヒトなのではないか、という者もいた。ナルボ人は、品種改良技術の応用に熱心なあまり、ときに劣悪な生命体をつくり出してしまうことで知られているからだ。このような疑惑があがっていることをふまえて、ここではっきりと述べておきたい。私がここに記載する報告内容は、すべて事実であることが大銀河評議会により確認されている。ヒトは現実に存在するし、彼らが地球外の知的生命体による干渉を受けたという証拠は、いっさいないのだ。
あまりに奇妙な生物
そもそものことの起こりから話を始めよう。ヒトは、原子の集まりによって構成された自己複製システム、すなわち、「生命体」だ。地球上のほとんどの生命体は、単細胞生物、つまり、自由に動き回る単一の細胞たちだ。ヒトもまた、成体の目ではほとんど見えないほど小さな細胞として始まる。しかしこの最初の細胞は、すぐに分裂し、増殖しはじめる。そのうち細胞の集合体はどんどん大きくなり、ヒトの形をとるようになる。つまりヒトの個体とは、単細胞生物の巨大な群体なのだ。ヒトの細胞群体は、「動物」とよばれる細胞群体の一分類だ。この群体は、定期的に新たな細胞群体を産出する。つまり、繁殖するのだ。ほかの多くの動物もそうだが、ヒトの繁殖方法は奇妙で、効率が悪い。単に自分自身を複製すればいいものを、わざわざ二体のヒトが対になって、それぞれの遺伝物質を融合させて子をつくるのだ。つまりその子は、親となる個体それぞれの「半クローン」でしかないということになる。ただし、どんな組み合わせでもいいというわけではない。どういうわけか、ヒトには二種類の基本形態がある。それが、オスとメスだ。そして新たな細胞群体をつくるためには、そのどちらも一体ずつが必要とされる。ほとんどの生物は海中に棲んでいるが、ヒトは、大気圏の底でゆっくりと動く漂流物(「陸塊」とよばれる)の上で生活している。とはいえ、ヒトも、ほかのすべての陸生動物も、海洋生物の子孫にあたる。より正確には、ヒトは魚が変化したもの、つまり陸生魚類といってもいい。ヒトの腕は魚のヒレが変化したものだし、顎はエラが変化したものだ。ほかの多くの陸生魚類、さらには動物たちと同様に、ヒトは一日に1、2回、活動を休止する。最終的には、その短い生命のおよそ三分の一にあたる時間を植物状態で過ごすことになる。彼らが文明を築くのにこれほど長い時間がかかったのも、当然といえば当然のことだ。
この小さなモンスターたちを仔細に観察すればするほど、私は困惑することになった。そのころまでには、ヒトは自然選択の産物であり、妙な実験によって生まれた生物などではない、ということはわかっていた。まともな教育を受けた生命体であれば誰でも知っていることだが、自然選択は、生命を維持し、自分と同じ種を産出するように設計された生物をつくり出す。ヒトは、多くの側面においてこれに当てはまる。彼らは自分を取り巻く環境から燃料を取り込み、脅威から逃げ、新たなヒト細胞群体の面倒をみる。しかし一方でヒトは、生存と繁殖のための古くからの生物的原則に逆らうことも多い。たとえば、彼らは自分にとって有害な物質をむやみに欲しがる。不健康で、寿命を大幅に縮めるような食べ物に、逆らいがたいほど強い食欲をいだくのだ。これはまるで、毒を欲しがるようなものだ。いったいどのようにして、このような進化が起きたのか? もう一つの謎は、ヒトがいだく恐怖が、環境中に実際に潜む危険に見合っていないという点だ。多くのヒトはヘビやクモなどの生き物を怖がるが、実際には彼らの多くは都市に住んでおり、そこではこうした生き物はほとんど脅威にはならない。同様に、小型のヒト(「子ども」とよばれる)の多くは暗闇を恐れる。だが、ほとんどのヒトは箱のなかで暮らしているため、夜の暗闇に潜む危険からは守られているのだ。さらにヒトは、生存や繁殖において脅威ではないものを恐れるというだけでなく、真の脅威であるものには恐怖をいだかないことが多い。たとえば、「ジャンクフード」や「タバコ」「シートベルトをせずに高速で運転すること」など、さまざまな脅威が存在する。さらに、「コンドーム」や「避妊薬」もそうだ。ほとんどのヒトは、繁殖の害となるこのような避妊道具に対して恐怖を示さないどころか、妊娠を防ぐためにわざわざそのような道具を使うのだ。いったいなぜ、自然選択はヒトにそんなことをさせるにいたったのだろう?
先述の通り、ヒト生物はオスとメスという二つの種類に分かれる。なかにはこの分類にはっきりと該当しない個体もいるが、多くはどちらかに当てはまる。オスとメスは、見た目が少し異なっており、行動にもいくらか違いがある。大柄なほう(オス)は、より攻撃的で、性に奔放で、生命を脅かすようなリスクを積極的に取る傾向がある。小柄なほう(メス)は、性的パートナーの選択により慎重で、子育てに深く関わり、オスよりも多少寿命が長い傾向がある。このような差異が明らかになるにしたがって、私はその違いがどのようにして生まれたのかに興味をいだきはじめた。ヒトのネックトップ・コンピューター(「脳」とよばれる)に、彼らの家族やまわりのヒトがこれらの違いをプログラムしたのだろうか? あるいは、オスとメスの違いはもっと根深いもので、この直立の毛皮のないサルたちの根本的な性質の一つなのだろうか?
これらの疑問を胸に、アニマスコープ5000型を使って動物界全体を手早くスキャンしたところ、二つの重大な発見が得られた。一つ目は、ヒトにみられる性差は、ほとんどのホニュウ魚を含むほかの動物にもみられる、ということだ。このことから私は、ヒトの性差は純粋に文化的なプログラミングによる産物というわけではないようだ、と考えた。ところが、二つ目の発見によりわかったのは、ヒトの性差はほかの種の性差と比べて顕著なわけでも、極端なわけでもない、ということだった。たとえば、ホニュウ魚の多くは、オスが交配の相手をめぐって争い、メスは求愛してくるオスのなかから相手を選ぶ。一方でヒトの場合、オスとメスはどちらも交配相手をめぐって争い、どちらも相手を選り好みする(少なくとも長期的な相手を選ぶ際にはそうだ)。さらに、ほとんどのホニュウ魚は、メスだけが子どもの面倒をみて、オスは精子を提供するだけだ。一方でヒトは、どちらの性も共通して自分たちの醜い子どもの世話をする。これは、ホニュウ魚よりも鳥ザカナに広くみられるやり方だ。たしかにヒトの場合も、オスのほうがメスよりも競争に熱中しやすいし、メスのほうがオスよりも選り好みが激しく、より子育てに熱心な傾向がある。しかし、その差異は、ほかの種と比較するとかなり小さいものだ。クルトン破壊王の名にかけて、これは大きな謎といわざるをえない。
(ちなみに、読者諸氏が万が一ヒトと遭遇するという不運に見舞われた場合は、このような性差についてはいっさい触れないことをおすすめする。奇妙なことに、ヒトはこの話題で気分を害することが多い。気化の刑に処される危険を承知で言うが、私にはその理由を突き止めることはできなかった。)
ヒトの生殖のプロセスは、地球上のほかの生物の基準に照らしても、おそろしく奇妙なものだ。ヒトは交配相手の候補を吟味する際、相手の体の外皮部分、特に頭部前面を目視により精査する。我々ベテルギウス人には、ヒトの個体はどれも同じに見える。しかしヒト同士にとっては、外見の微細な違い(左右対称性のわずかなズレや、シワのごく微かな兆候など)によって、「美しい」か、それとも「美的要素に障害がある」かが決まるのだ。このような恣意的に思える好みがあるのは、なぜなのだろう?
適切な交配相手を特定すると、ヒトは次に、実に奇妙な配偶儀式を開始するが、この儀式にはさまざまな種類がある。たとえば、オスが植物の生殖器(「花」とよばれる)を束にしたものをメスに贈る、あるいは発酵させた植物の汁をオスとメスが飲みながら、交互に相手に向かって音を発する、などだ。このような儀式によって、ときにふたりは激しく狂った状態に陥ることがあるが、この状態は「愛」とよばれる。この愛狂いに囚われると、ヒトは互いに執着しはじめ、まったく理に適わないやり方で相手を理想化するようになる。さらに奇妙なことには、この愛が破綻した場合、彼らは何ヵ月も、ときには何年にもわたって悲嘆に暮れ、嘆くことがある。ヒトにとって、これが生物として有益な時間の過ごし方とはとても思えない。さらに愛は、より積極的な危険も及ぼしうる。ヒトは、愛のために殺戮を行なうことがあるのだ。その対象は、自分自身のこともあれば、過去の愛の相手や、愛を奪い合う競争相手の場合もある。当初私は、この愛狂いについて、適応のし損ないによって発生した不具合か、あるいは心を操るウイルスによる作用なのではないかと考えた。だが、正確性を誇る我がアニマスコープ5000を使ってヒトのサンプルを精密に検査した結果明らかになったのは、愛はヒトという動物の根本構造に組み込まれている、ということだった。なぜ自然選択は、これほど不合理で、弱体化すら招きかねない症状を淘汰せずに残したのだろうか?
ヒトの奇妙な配偶行動は、ときとして半クローンの産出に結びつき、ヒトはこれを「赤ん坊」とよぶ。我々ベテルギウス人にとって、ヒトの赤ん坊は身の毛がよだつような恐ろしいしろものだ。ところがヒトにとっては、赤ん坊はなによりもかわいらしく、彼らの目に見える限りの宇宙全体においてもっとも本質的に大切な物質のかたまりなのだ。実際のところ、その親と子の絆というものは、火星の泥レスラーよりも強靭󠄂であるといっても過言ではない。親は子を守るためならば、ヒレが進化した腕どころか、命さえ失うことを厭わない。そして子が死んでしまうと、親は寿命が尽きるまでのあいだ、繰り返し眼球から塩水を流すのだ。言い添えておくと、ヒトは出会うすべての幼体に対してこのようにふるまうわけではない。彼らはほかのヒトの子に対してよりも、自分の子にエサを与えたり、服を着せたり、愛情を注いだりする傾向がずっと強い。私のような中立的なベテルギウス人からすると、これは理に適わないことだ。全員が全員を大切にするほうが、種全体のためになるのではないか?
わかっている。おそらく、あなたはこう思っているだろう。「よく聞け、このタコ足野郎! ヒトは進化上、シンギュラリティを迎える前の段階にいるんだ。ありがたいことに、我々にとってその時期はとっくの昔に過ぎた。だがこの段階にいるあいだは、なにがあっても自分の利益だけを追求する個体だけが、生存して子孫を残すことができる。だから、ヒトが他人の子よりも自分の子を大事にするのは、言うまでもなく当然のことだろう!」。たしかにこれは、もっともな意見だ(とはいえ、「タコ足野郎」はいささか言いすぎだ)。しかし、そのような見方をした場合、この謎は単に逆転する。ヒトは明らかに、自分と自分の子を大いに大切にする。だが彼らが大切にする存在は、ほかにもいるのだ。まず、自分の兄弟姉妹やいとこ、姪、甥など、自分の血を直接継ぐわけではない血縁者のことも大切にする。これは、どういうわけなのだろう? その答えがなんであれ、これはヒトに限ったことではない。ほとんどの動物は、自分と血縁関係のない生命体よりも、血縁関係がある生命体に優しくする。実は、ほかの動物と比較してヒトに特有な特徴とは、自分と血のつながっていない個体に優しくすることができる、という点なのだ。ヒトは、地球上のほかのどの種とも比べ物にならないレベルで、血縁以外の個体とも協力し合うことができる。そして協力にとどまらず、相手を深く気にかけることもよくある。ときには、血縁でもない誰かが世界の反対側で苦しんだり、腹を空かせたりしている姿を思い描いて、目から水を流すこともある。あるいは、相手がお返しをしてくれないことがわかっていて、ほかに誰も見ている人がいない状況であっても、その相手を助けたりもする。そして、ヒレが進化した腕でも命でも失う覚悟で、血のつながりのない相手や、ときにはヒト以外の種の個体さえ、助けることもある。このような利他的な行動もふまえると、やはりヒトは、あらゆる既知の法則に当てはまらない不可解な存在であるといえる。なぜ彼らは、地球上の利己的なほかの生物と同じように、自分と直近の血縁者を守ることに徹しようとはしないのだろう?
ここで付け加えておきたいのだが、ヒトは優しくもなれる一方で、互いに対してひどく残虐にもなる。ヒトの若いオスはたびたび集団を形成し、他集団のメンバーに怪我を負わせたり、殺害したりする。焼き討ちし、体を切り刻み、激しく罵り合うこともある。おびただしい数の動物を閉じ込め、苦しめ、その死体を加熱して食べもする。それでもなお、次のようにいわざるをえない。ヒトは多くの、本当に多くの欠点を持ちながら、同時に、この銀河系でもっとも協力的で利他的な炭素性生物なのだ。
飛び交う概念
ヒトはまた、おそろしく不可解な生き物でもある。彼らが多大な時間と労力を注ぎ込む活動は、ベテルギウス人である私からみれば、生存にも繁殖にもまったく役に立たないもののように思えるのだ。いくつか例を挙げよう。まず一つ目に、ヒトは毎日何時間にもわたって、顔にあいた穴から互いに向かってなにやら音を発し合う。実際のところ、活動停止時を除けば、彼らはひとときも静まることがない! この妙な顔音がもつ機能をつきとめるために、私はかなりの時間を(正確には、1ナノ秒)を費やすはめになった。ほとんどの場合、ヒトがこの音を使うのは、その小さな脳から脳へと概念を伝達するためだ。だが、奇妙な点が一つある。このような概念のほとんどは、生存や繁殖とはいっさい関係がないのだ。多くの場合、それは単に、ヒトが定期的に発する「ハハハ」という妙な音を引き出すことだけを目的として作られている。それ以外では、天候や、他人の失敗に関連していることもよくある。なんとも奇妙だ。
二つ目に、多くのヒトは「幽霊」「精霊」「神」等とよばれる目に見えない存在を信じている。彼らの多くは、このような存在について考えを巡らせ、テレパシーによる通信を試みることに膨大な時間を費やす。また、定期的に大勢で集まって、高コストで手の込んだ儀式を行ない、見えない存在を説得して自分たちに優しくさせようともする。さらには、ほかの個体を説得し、自分と同じ不可視の存在を信じさせ、高コストな儀式に参加させるためにたいへんな努力を払いもする。しかもそれだけの活動を行なっておきながら、不可視の存在の実在を示す証拠も、儀式の効果を示す証拠もほとんどもたないのだ。
最後に三つ目の例をあげる。ヒトはいたるところで、みずからの脳に刺激を与えるために人生のかなりの時間を費やすのだが、その方法が不可解かつ多岐にわたっている。たとえば多くのヒトは、四角い布や洞窟の壁に色を染み込ませたものを作ったり、眺めたりして何時間も過ごす。そのシミは、裸のヒトや、ほかの動物細胞群体、あるいは植物の生殖器など、世界に存在するさまざまな物に似せてある。また、規則的なリズムをもつ音によって、自ら催眠状態に入るヒトも多い。単純で繰り返しの多い音によって、どういうわけかヒトの強い情動的反応が引き起こされ、足を踏み鳴らす、頭を揺らす、ときには全身を規則的に痙攣させるといった奇妙な副反応が生まれる。さらに、多くのヒトは、特有の変性意識状態になって平らなスクリーンの前に座り、そこに表れる明滅する画像を見つめて毎日何時間もの時間を過ごす。その画像とはたとえば、実際には起こっていないとわかりきっている出来事を模したものや、ほかのヒトの交尾、おぼつかない様子で動きまわるホニュウ魚の赤ん坊などだ。
これがどれほど奇妙なことか、考えてみてほしい。ヒトがおしゃべりや、信仰および儀式、色のシミやリズミカルな音などに生涯の20パーセントを費やすとするなら、それはすなわち、彼らが摂取する食料の五分の一が、一見して無意味なこれらの活動のために吸収されるということになる。なぜ同じだけの時間とエネルギーを使って、できるだけ多くの子や孫を産出しようとはしないのだろう? 地球上のほかの生物たちは、みなそうしているではないか。現段階で、私にいえることは一つだけ――「お手上げ」だ。まったくもって、ヒトは奇妙な魚である。
だが、一番奇妙な話をまだしていなかった! すでにおわかりだと思うが、ヒトは知的に優れているとはとてもいえない存在だ。彼らの脳は、相対性理論や量子電磁力学といった比較的単純な理論をはじめとする、単純なものごとを理解するのにさえ何年もかかる。記憶力も低く、その短く困難に満ちた生涯のほとんどの瞬間をすぐに忘れてしまう。さらに、ベテルギウス人ならほんのピコ秒で自力で解けるような数学的問題であっても、ヒトは計算機やコンピューターといった補助具を必要とする。ところがこの奇妙なバイオロボットは、これほど知的に劣っているにもかかわらず、どういうわけか自らの力を完全に超えることがらについての知識を得ることに成功したのだ。もちろんそれは、我々の輝かしい知識に比べればごく初歩的なものだ。それでも、そのお粗末な知性にはまったくもって不釣り合いな知識なのだ。一番賢い個体でさえ暗算で微分積分もできないような種が、どうやってそのような複雑な知識を手に入れたのだろう? いったいいかにして、肉塊ロボットたるヒトが、宇宙全体を生んだビッグバンや、今の自分たちを塵からつくり出した進化のプロセスや、あらゆる物質やエネルギーを支配する物理的法則の本質を、ぼんやりとではあれ垣間見ることができるようになったのだろう? 読者諸氏は、きっとこう考えているだろう。「わかりきったことだ! この下等生物のもとを、第三象限のローキーたちが訪れたんだろう。やつらはずっと昔から疑われてきたように、銀河法に違反して、神聖な知識を原始生物に与えているに違いない」。しかしローキーたちには、過去3000年にわたる確固としたアリバイがあるので、それはありえない。よって、疑問は未解決のままだ。あのあわれな生き物が、いったいどうやってこれほど見事な知識の体系を持つにいたったのだろう? ちっぽけではかない宇宙の塵でしかないサルが、なぜこの広大な宇宙全体を理解できるようになったのだろう?