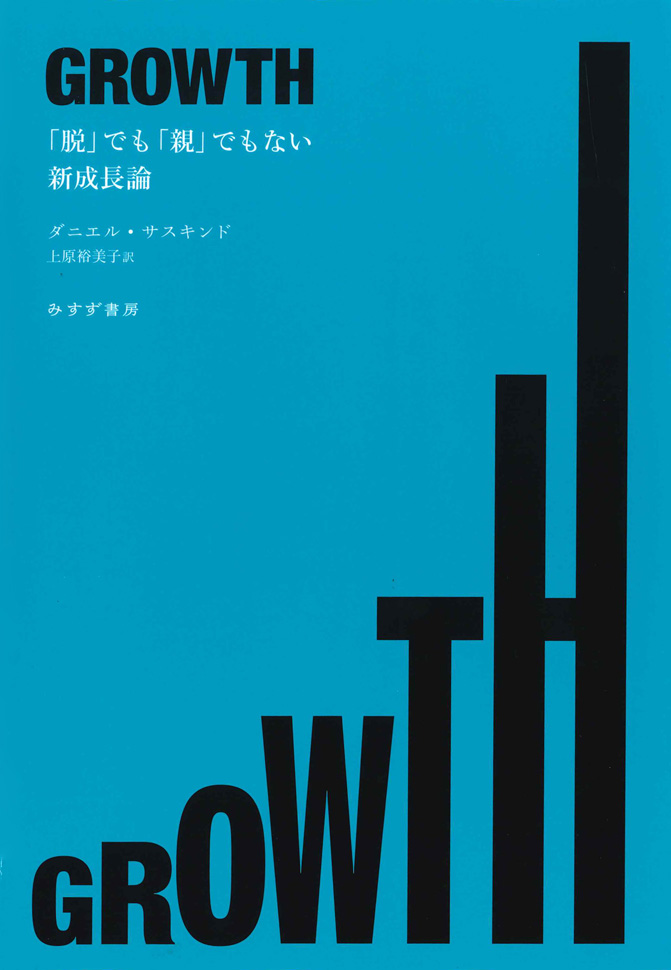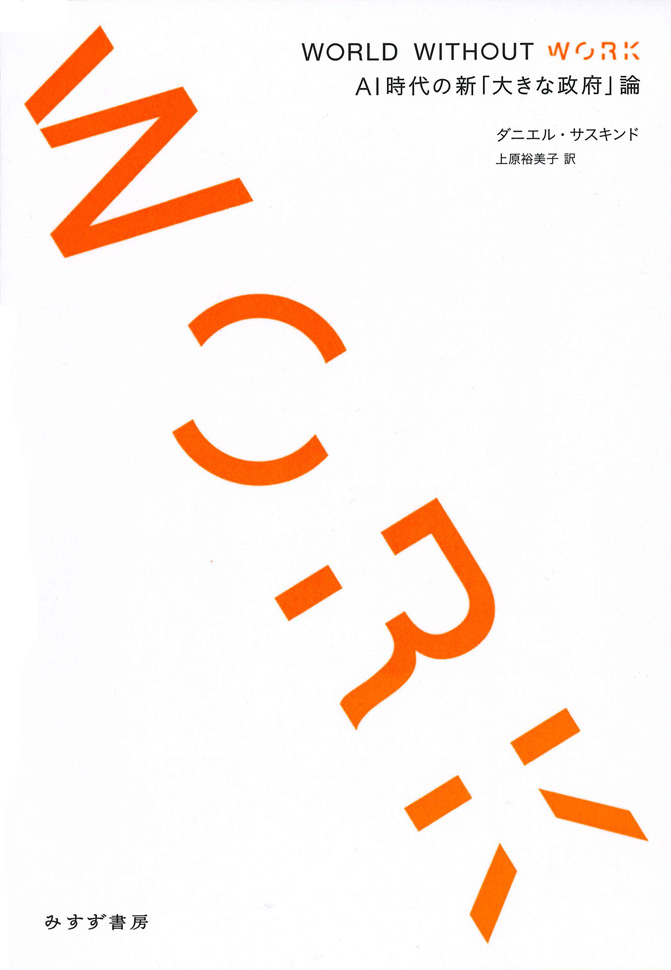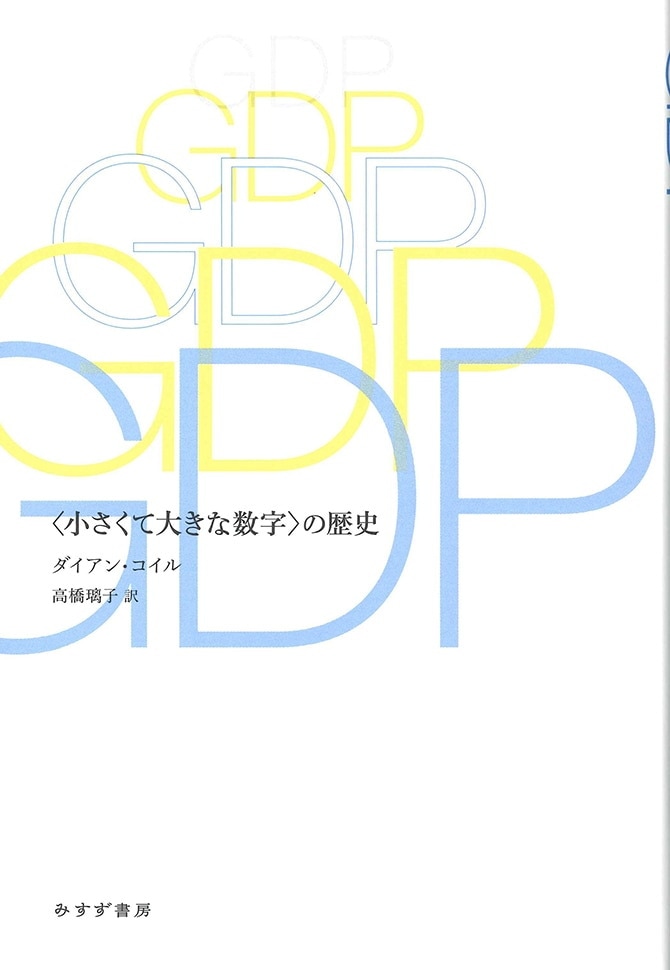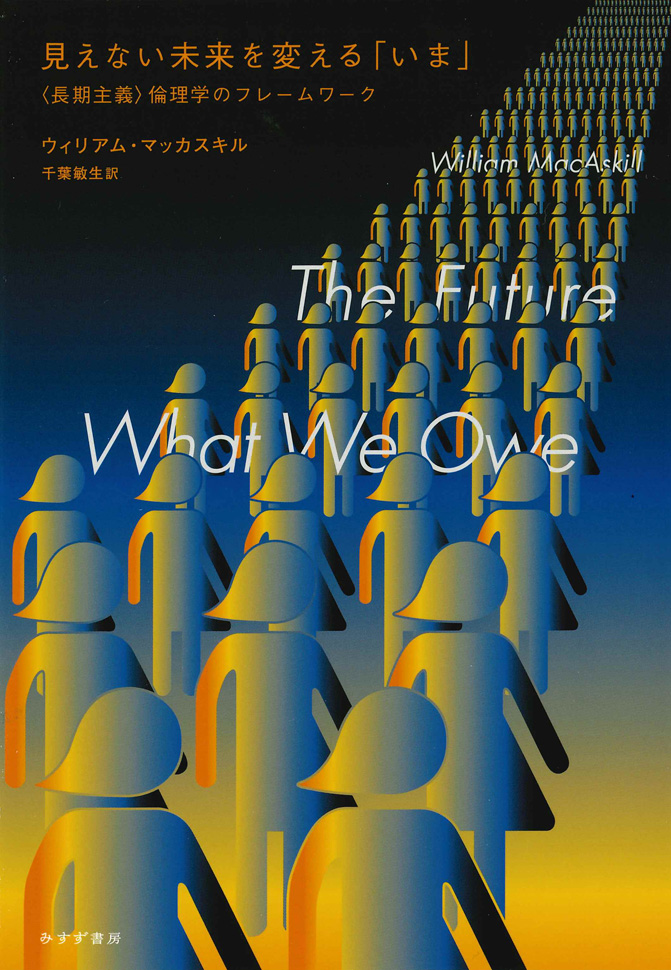イギリス政府の諸機関(首相戦略局、内閣府)を歴任し、現在はロンドン大学キングス・カレッジ研究教授としてAI倫理、テクノロジーの社会への影響を専門とする英国の研究者、ダニエル・サスキンド。最新作『GROWTH――「脱」でも「親」でもない新成長論』のテーマはずばり「これからの経済成長」。成長しない道を選ぶのは間違いだという前提から始めつつ、環境破壊、地域の荒廃、大きな格差などの「繁栄の代償」をどのように回避するか。この「成長のジレンマ」という問題に正面から向き合う本書から、冒頭部分をお届けします。
はじめに
(抄)
人類のこれまでの経済史には、単純だが注目すべき三つの事実がある。
第一の事実は、人類が存在してきた30万年という時間の大半において、経済はずっと停滞期にあったという点だ。人が狩猟と採集をしていた石器時代であれ、労働者として働いていた18世紀であれ、経済的な意味での運命は似たようなものだった。人々は貧しい暮らしをして、生存を維持するための過酷な苦労を強いられていた。
第二の事実は、この停滞が終わりを迎えたのはごく最近だという点だ。近代の経済成長はほんの200年前に始まり、世界の一部地域で生活水準がめざましく上昇した。人類史の合計を1時間と考えるなら、このような運命の逆転はほんの数秒前に起きた出来事だ。
第三の事実は、数秒前に起きたばかりの経済的上昇を、人類が維持し続けているという点だ。数世紀前までは、経済成長が起きたとしても限界があり、いずれ頓挫していくのが常だった。ところが今回の成長は甚大であると同時に持続している。まるで数千年にわたって隠され、抑圧されてきた生産力が、ここに来てついに解き放たれたかのように。この点が、近代の経済成長を過去の成長とはまったく異質なものにしている。
本書の前半では、こうした奇妙な歴史について論じていく。経済がまったく成長しない時期はなぜこれほど長く続き、なぜ急に成長が始まり、そしてどのように持続されているのか。20世紀において、経済成長の追求は、ふつうの生活における当たり前の活動になっていた。経済が成長する真の要因は謎に包まれたまま、それでも20世紀以降は比較的上首尾に――直近はその限りではないとしても――成長を遂げてきた。
拡大する物質的繁栄を利用して、人類は驚くべき成果を続々と実らせている。われらの祖先は生存維持のための苦役に縛られていたが、いまや数十億人がその苦役から解放された。寿命も延び、人は昔より健康になった。原子を分裂させ、遺伝情報の解明を進め、宇宙を探索するなど、世界に対する理解を一変させるような発見も進んでいる。
しかし、こうした繁栄の追求が莫大な代償を伴っていたことも、しだいに歴然と明らかになってきた。自然環境の破壊。地域の文化やコミュニティの荒廃。新たな富の大多数を受け取る者と、受け取らない者とのあいだに広がる、すさまじい格差の出現。一部の破壊的テクノロジーの誕生は、もはや制御できないと思わせるほど、人間の働き方や政治的生活に大きな影響をもたらしている。〔著者は「政治的生活」という言葉を、人間が文明社会で営む共同生活のあり方全体を指して使っている。前著『WORLD WITHOUT WORK』第11章参照〕
いまや経済成長は僕たちにとってのジレンマだ。一方において、成長とは、人類が成し遂げてきたあまたの偉大なる勝利と功績に結びついている。しかし他方において、成長とは、今日の僕たちが直面するあまたの甚大なる問題と結びついている。経済成長が差し出す明るい見通しの約束は、ときには強引かつ暴力的に、僕たちをさらなる成長追求へと引っ張る。同時に、成長に伴う代償が猛威を振るい、成長追求の道から僕たちを引きはがす。進めない道を進めと言われているかのようだ。
本書後半は、このジレンマを掘り下げていく。ジレンマはどのように生じてきたのか。ジレンマとの向き合い方にいかに失敗してきたのか。ジレンマへの具体的な対策が固まっていないのはなぜなのか。そして、今、何をすべきなのか。僕はここ数年で、成長のジレンマとの対峙こそ、人類に課せられた最大の任務の一つだと確信するようになった。この任務にしくじり続けてきたせいで、今の僕たちは危険な針路をたどっている。試練と真剣に向き合うことができるなら、それは少しでも良い方向へ舵を切るチャンスであるだけでなく、このあとの章で見ていくとおり、人の道徳的復興の入り口となるのではないか。ただただ経済の繁栄を求めるのではなく、本当に重要なこと――より公正な社会や、より健全な地球環境など、経済成長以外で人が大事にしたい目的――を求めるという、この新たな目標を人類全体の使命として、社会の中で芽生えさせていくチャンスとなるのではないか。
こうした考察とあわせて、本書は経済成長のストーリーを余すところなく語っていく――その不可思議な過去、その厄介な現在、その不確かな未来に至るまで。成長の未来をどう形成するか、それは今の僕たちの肩にかかっている。本書は一面においては思想に関する本だ。過去の偉人たちは、どのように、この重大な現象を理解しようと試みて(多くは失敗して)きたか。そして、ほんの100年ほど前、しかも偶然のなりゆきで、世界のリーダーたちがどのようにして経済成長をわれら人間の政治的生活の中軸に据えたのか。いまや経済成長は僕たちが後生大事に掲げる思想の一つであり、同時に、きわめて危険な思想の一つでもある。この急速な変化はどのように起きてきたのか。このあとのページでは、学問分野の垣根を飛び越えながら、刺激的かつ不穏な問いを投げかけていきたい。なぜ、人類はかなり長きにわたり、きわめて困窮した生き方をしてきたのか。人類の生活水準は今後はずっと上がり続けるのか。そして現代を生きる僕たちは、社会において具体的に何に価値を置くべきなのか。まだ生まれてもいない未来の数兆人のために、今の僕たちが尽くすことは、本当に必要なのか。
とはいえ、本書は実用的な本でもある。現実世界で成長のジレンマに対処していくためのハウツーガイドだ。はるかかなたの過去から、はるかかなたの未来まで、幅広くストーリーを展開しながら、今この瞬間の行動を考えるにあたっての教えを引き出していく。
(中略)
僕たちはいま、経済成長が優先される社会に生きている。一定期間でどれだけモノを生産できるか、それによって社会全体の成否が判断される社会だ。経済活動を支配するのは往々にして一種類の尺度、すなわち「この国の国内総生産(GDP)は増えているのか、減っているのか」という問いだ。この問いが最優先に掲げられているせいで、経済成長というコンセプトにはさぞ輝かしい歴史があるのだろうという印象を抱いてしまうのだが、実際にはそんなことはない。むしろ、経済の成長を追求するという発想は、古典派経済学者と呼ばれる人々には想像し得ないことだったに違いない。それどころか、経済の規模を測る実用的な尺度が生まれたのは1930年代になってからだったので、経済がどれくらい成長したか把握することが可能だとも思っていなかっただろう。実際のところ、成長が重大になったのはなりゆきだった。しかも幸運ななりゆきだ。20世紀のあいだ、GDPは明らかに、人間のゆたかさを測るほぼすべての指標と相関していたからだ。本書第Ⅱ部では、この思いがけない環境にフォーカスを向けて考察する。
とはいえ、経済成長はただ重大というわけではない。先にも述べたとおり、成長は危険だ。第Ⅲ部では成長の暗部に目を向け、経済成長が人間の生活を悪くしている多種多様な側面を明らかにする。そこでも指摘するが、成長のジレンマに対する反応は、主に二つのタイプが主流となりつつある。一つは、GDPという指標を少し手直ししつつも、引き続き経済成長を追求するという対応だ。実務的な効率性を重視する政策立案者や経済学者が、こうした取り組みを提案している。そして二つの反応のうちもう一つのほうは、よりドラマチックだ。経済成長の追求自体をまるごとあきらめ、「脱成長」を通じて、意図的に経済を減速させていくべきだと提案している。デイヴィッド・アッテンボローやグレタ・トゥーンベリのような影響力ある有名人が打ち出しているのはこちらの道だ。この二つの思想は、どちらも単独では成長のジレンマを解決できない――よく言えば不充分、悪く言えば何の意味もない自己破綻的着想である。しかし、だからといって無視すればいいということでもない。どちらも重要な真実を明らかにした主張であり、その真実は、今直面している試練に向き合うにあたって役に立つ。
本書は第Ⅰ部から第Ⅲ部を通じて、知的道具箱の中身を充実させるべく、経済成長という概念についての理解を深めていく。その上で第Ⅳ部と第Ⅴ部では、アイディアを実用へ転じることを目指して、現実世界で成長のジレンマに対して何をすべきか掘り下げていきたい。議論の出発点はこうだ――成長しない道を選ぶのは大間違いだ。その道は、社会として掲げるべき基本的目標――貧困の撲滅から、すべての人を対象とした優れた医療の提供まで――の放棄につながるだけでなく、未来はどのようにゆたかになっていくか想像する力を欠いている。本書は、人類がさらなる経済成長を実現する方法を提案しつつ、今日叫ばれている対策の多くが的外れと思われる理由も説明したい。
しかし同時に、繁栄のやみくもな追求に伴う莫大なコストを垂れ流し続け、無視し続けるわけにはいかない。成長の約束と代償というトレードオフの問題に、真正面から向き合っていく責任がある。何よりもまず、可能な限り、トレードオフ自体を回避しなくてはならない。社会に代償を強いずに成長していく方法を探すのだ。それでもトレードオフが避けられないなら――実際に完全な回避は不可能だ――トレードオフの弱体化に努める。使える道具を駆使して、経済成長の性質を変え、成長が少しでも破壊的ではないようにしていく。ただし、弱めることも現実として有効でないなら、僕たちは最終的にはそう認めなければならない。その際には、トレードオフを甘受し、避けることも弱めることもできないという事実を受け入れて、経済成長を追求するのか、それとも経済成長以外の重要なこと――環境保護や、富の不平等の改善など――のために成長を犠牲にする覚悟を決めるのか、どちらかを選びとる。この決断には二つの難しい道徳的問いがかかわり、見解は大きく割れるだろう。問いの一つは、「経済成長以外の何を重視すべきか」。もう一つは「未来のために現在の人間がどの程度尽くすべきか」。この二つは本書の終盤で探っていくつもりだ。
このようなテーマを扱う本が単純化を伴うことは避けられない。広大な思想をきわめて簡略にまとめ、積み重ねられてきた多種多様な研究を数百単語に短縮しなければならないからだ。目の前にある試練――気候変動、不平等、グローバリゼーション、人工知能など――のそれぞれについて詳細な研究を知りたくて本書を手に取った読者は、おそらく失望するだろう。本書では一つひとつを細かく掘り下げてはいない。各課題に対してとるべき具体的な政策介入の決定版リストを提示することもない。そうした任務は別の本に任せる。本書の目的は別にある。多くの課題を一つの舞台に集め、それらが交差する部分を新たな視点から見つめることだ。課題のそれぞれは細部では大きく異なるものの、全体を貫く共通の脅威がある。経済成長という概念、そして、その概念に人間が心を奪われてきた経緯だ。そこに本書のテーマがある。新たな視点を提示することで、すでに見慣れた課題の数々と別の角度から向き合えると僕は期待している。初めて見る角度で目を向ける機会になるだけでなく、僕たちが直面している問題に適切に対処してこられなかった理由について、理解を深める機会にもなるだろう。ぜひオープンな姿勢で向き合ってほしい――特に、昔からの手法を続けてしまっている人には、オープンな目が必要だ。今の活動のままでは、何であれ現実として効果はない。そしてタイムアップは近づきつつある。
――続きは書籍をごらんください――
(著作権者のご同意を得て抜粋・転載しています)