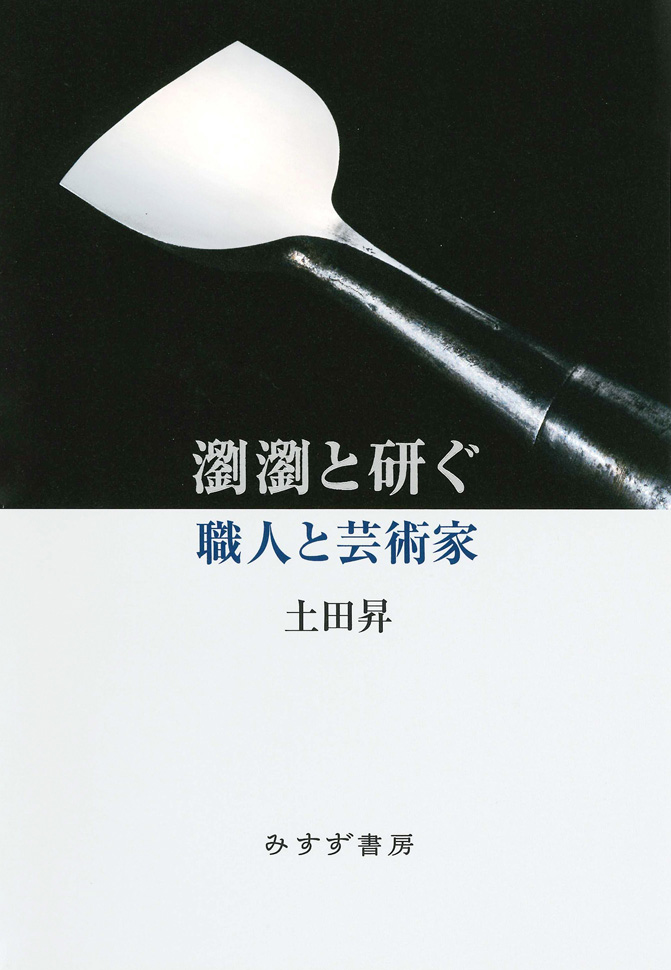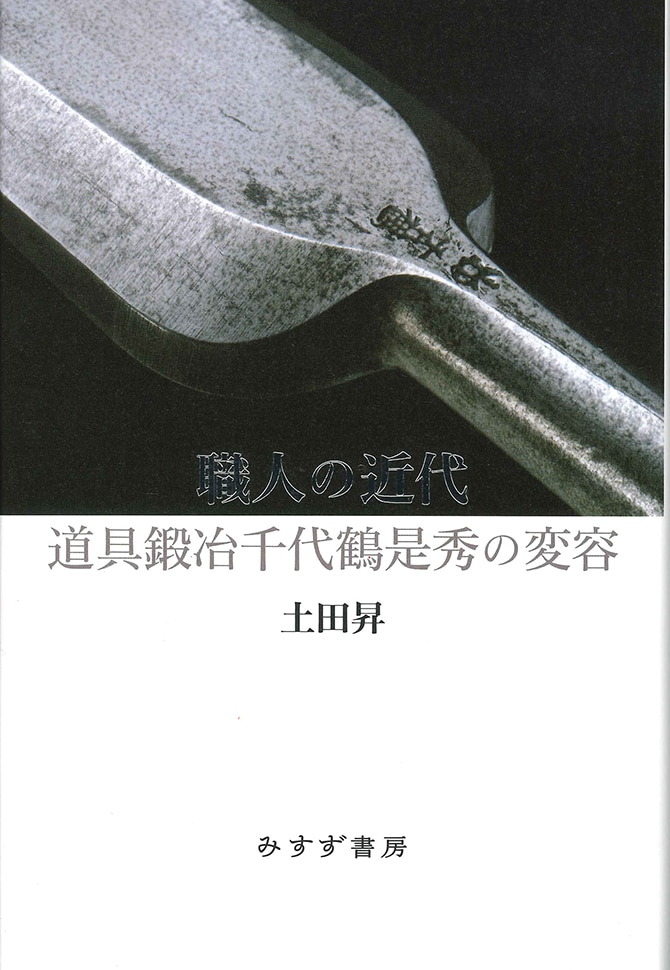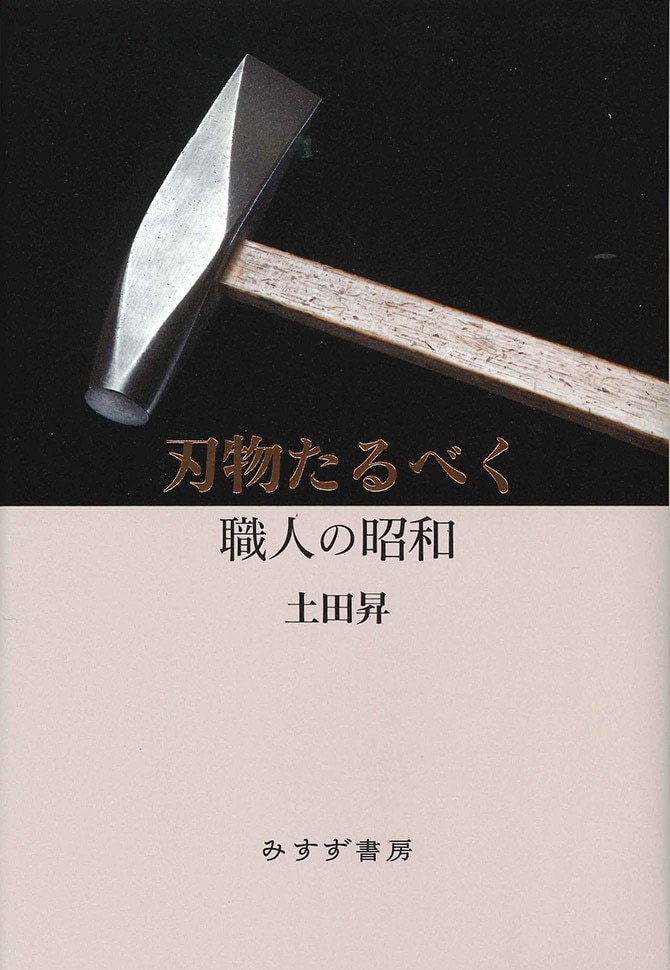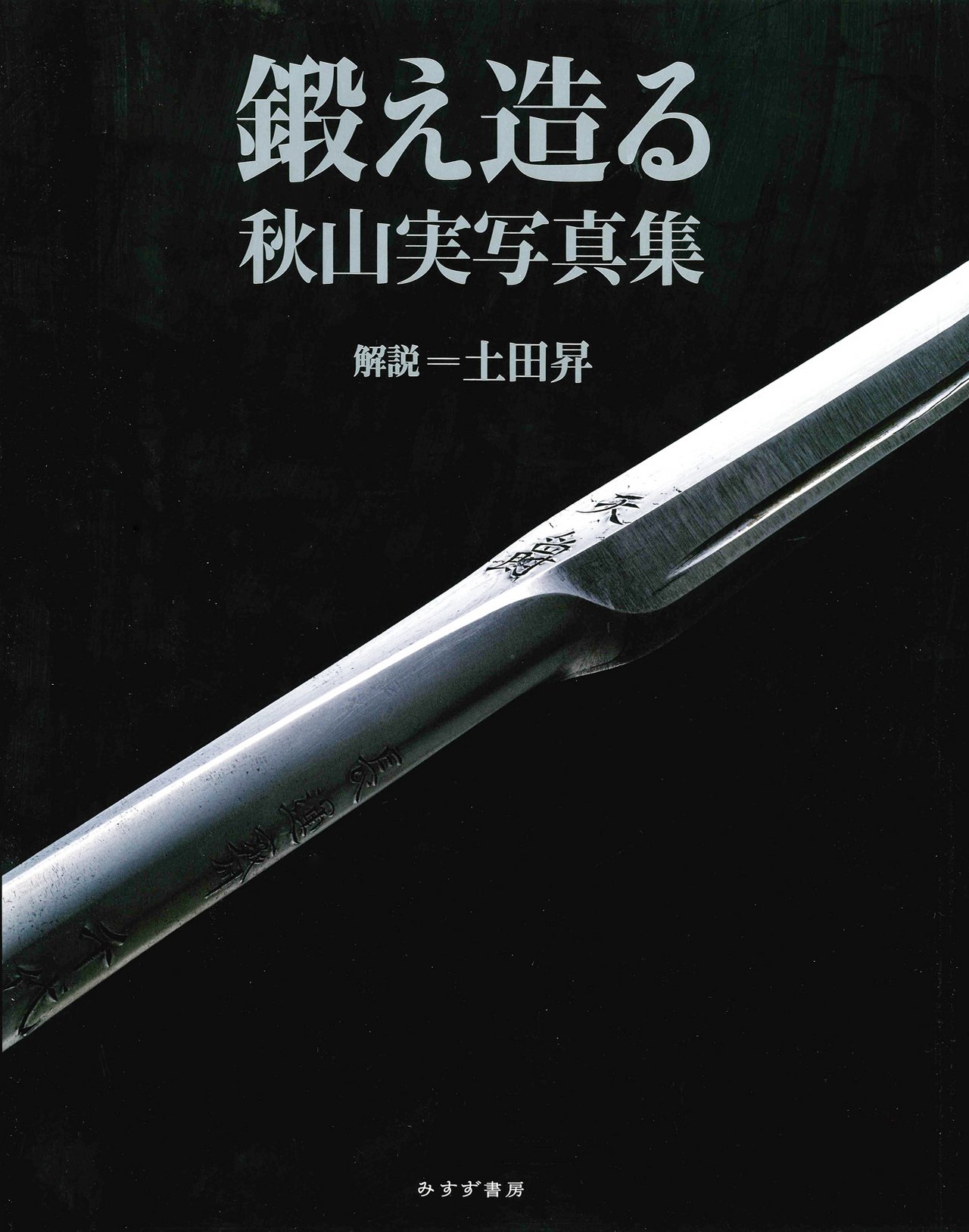東京三軒茶屋で三代にわたり大工道具を扱ってきた土田刃物店。二代目の時代までは休店日はなく、1年のうち元日のみ店を閉じたというが、現在は水曜定休である。
水曜日、まだ夜が明けきらない頃に、三代目店主である著者は大きなバッグをかついで家を出る。東京を離れ電車で3時間ほど――行き先は、上れば高原別荘地、下れば村につづく山のなかほどに位置する小屋。冬には零下十度以下ともなるこの地に、著者は水曜ごとに足をはこぶ。それは、積雪をスコップで掻き分けながらやっと小屋の入口にたどりつく冬もかわらない。
この小屋にいるときの土田昇は、ひたすら炎を操り、鉄を赤め、叩いて時を過ごす、自分だけの鍛冶場の主である。
自分はあくまで道具屋であって、大工道具にかかわる職人たちの領分は侵してはならない、との思いから、鍛冶仕事をやりたいという気持ちを封印してきた著者がはじめてその願いを口にしたとき、背中を押すように即座に山の鍛冶場の実現に向けて動き出したのは、当の鍛冶職人たちであったという。以来30年以上、たったひとりの鍛冶仕事を続けてきた。
初作の剣錐にはじまり、漆芸で使う沈金刀、底取鉋の刃、さらには木目鍛えの地金を胴中とした鋼付の玄能、自由矩という角度定規、表具師が使う紙断包丁――およそ聞き慣れないこんな道具のほか、木彫道具に刻印、レターオープナー、裁縫用の握り鋏まで、「火造って作れるものなら手あたり次第」に作ってしまう。火床で熱し赤めた鉄を槌で叩くその叩きごこちを楽しみ、ヤスリやセンによる成形時の感触を味わい、気に入ったようにできあがらなければ何度でも作りなおす。
江戸・明治・大正・昭和の名鍛冶の手になる大工道具を数多く撮ってきた写真家の秋山実は、この大工道具店店主が作る道具をはじめて見たとき、その完成度の高さに驚いたという。
「売るためでなく」作られるこれらの道具は、出来上がれば、現場で実際に使用して性能、使い心地を批評してくれる大工、家具や楽器製作者、彫刻家の手に次々にわたってゆく。過去の名品のレプリカ製作に挑戦すれば、見た目の姿を刻印まで含めてかぎりなく巧く写すにとどまらず、切味はもちろん、難易度の高い製作方法をも正確になぞる。
幼い頃から著者のまわりには大工道具と、道具を扱う祖父や父が身近にいる土田刃物店という日常があった。その日常の中にときにあらわれる芸術の世界、また職人の世界とは異なる芸術家の世界は少年時代の著者にとって、本人言うところの「反土田刃物店」的世界だった。大工道具店の店先から鍛冶空間への越境を果たすこの山の鍛冶場もまた、「反土田刃物店」的行為にほかならない。そして、道具を手にし、実際に自分の手でものを作る人間のみが読み取ることができたのが、彫刻家であり詩人、評論家であったかの芸術家の文章に隠された、職人の「作業感触」だった。
私は彫りかけの鯰を傍へ押しやり
研水を新しくして
更に鋭い明日の小刀を瀏瀏と研ぐ
(高村光太郎「鯰」大正十五年)
この詩から20年後、「わが詩をよみて人死に就けり」と戦争協力を悔いて、戦後は岩手の山奥の小屋に自耕自炊の生活を送った彫刻を作らぬ彫刻家――高村光太郎がその人である。
戦後すぐの時代、稀代の名工千代鶴是秀は光太郎から5、6種類の彫刻刀のセットを依頼するはがきを受け取っている。小屋の囲炉裏の灰の中からみつかった焼成の不完全な「野兎の首」1点をのぞいて、この小屋で暮らした戦後の7年間に光太郎が作品を彫った形跡はまったくないというのに。
戦時下に対照的ともいえる道を選んだ職人と芸術家――時代の要請である刀剣製作に手を染めることを拒んだ「刀は打たぬ」大工道具鍛冶、千代鶴是秀と、軍神など戦争彫刻は作らないものの戦争賛美詩を量産した高村光太郎。
当時、自分が作った彫刻刀を光太郎が研ぎ上げたのを見た是秀は、著者の父である土田一郎にひとこと、「光太郎は研ぎが上手い」ともらしたという。そして高村光太郎の死後、その彫刻刀のゆくえはしられぬままに時がすぎていった。
先代の技術を高度に受け継ぎつつ、時代の要請の中で自らの技術の落としどころを探り、変容していった道具鍛冶と光太郎の接点の証を、私は見てみたく思うのです。是秀が光太郎に作った彫刻刀を、錆にまみれていようが、鋼が尽きるくらい使い減らされていようが、あるいは、もはや光太郎の研ぎではなくなっていてさえ見てみたいのです。
そう願いつづける著者のもとに、コロナ禍の続く2021年春、高村家からみつかった光太郎旧蔵の錆びた彫刻刀の研ぎの依頼が舞い込む――
千代鶴是秀と高村光太郎をつなぐ幻の道具をめぐって、三軒茶屋の小さな道具店の砥石の上で、思いもかけない事実が姿をあらわすクライマックス。