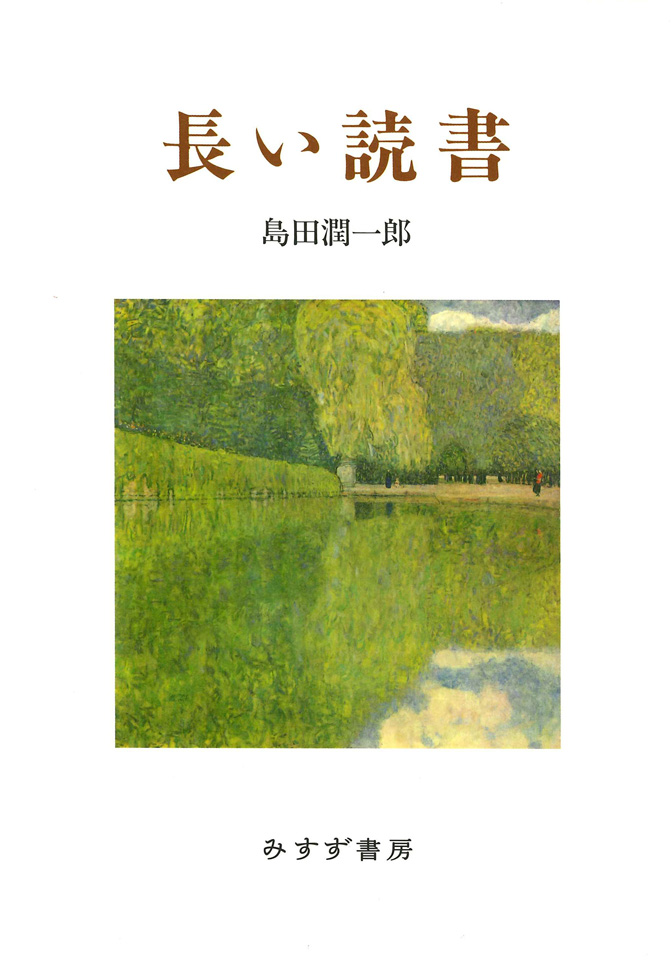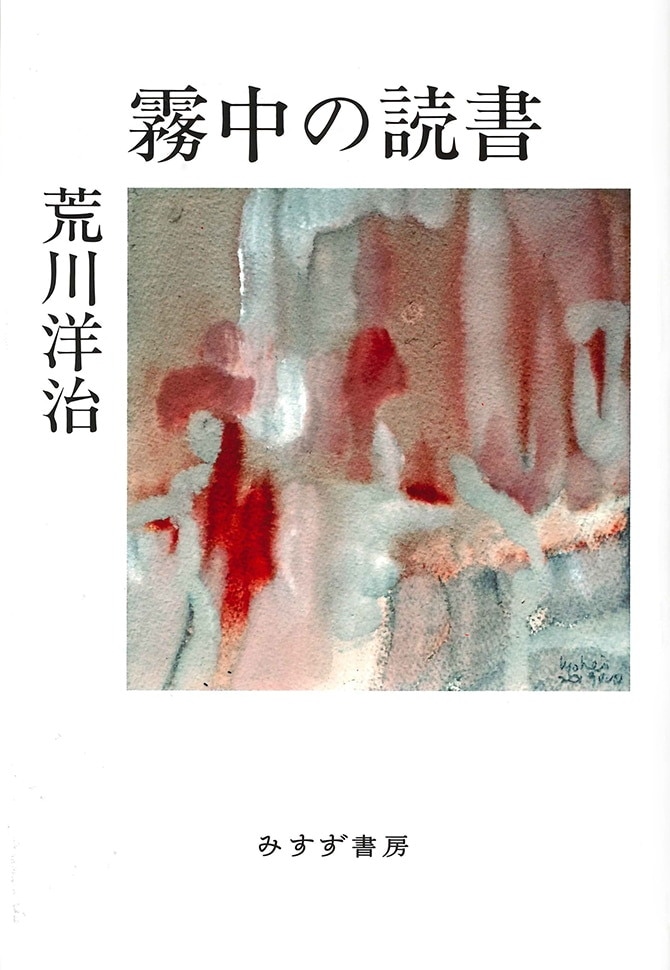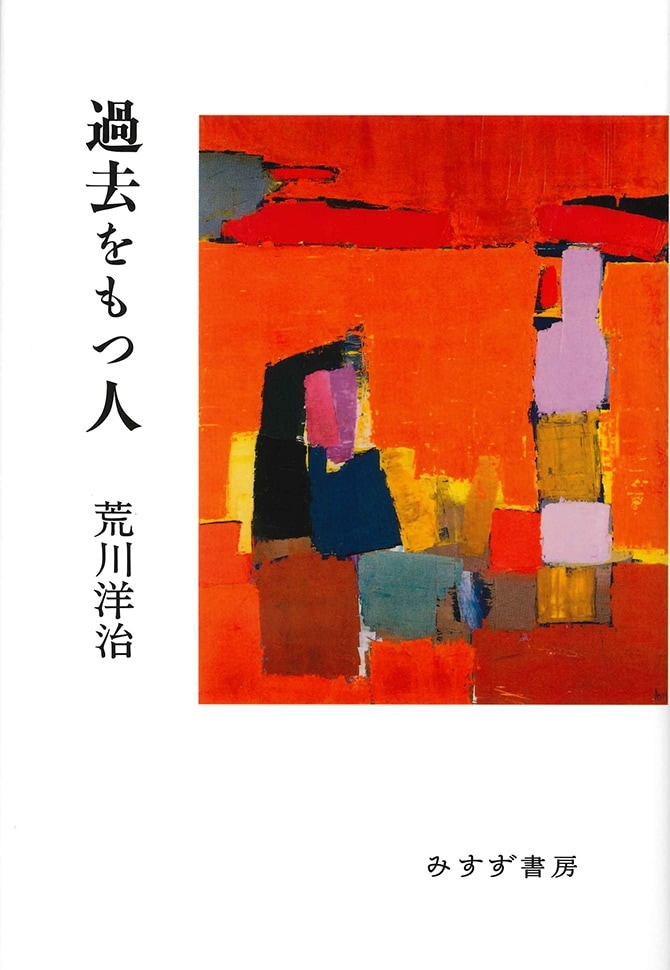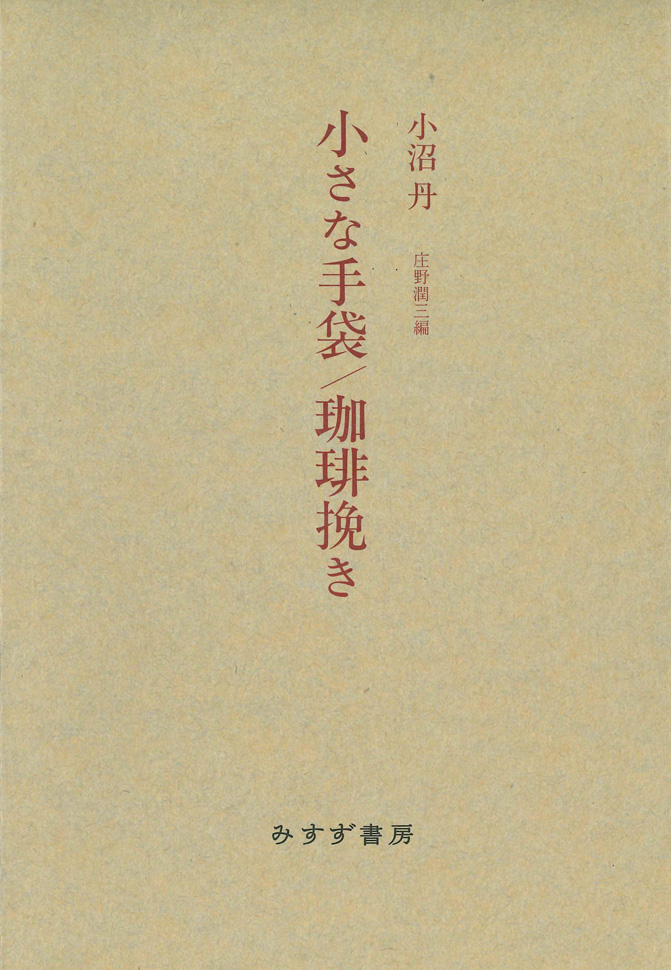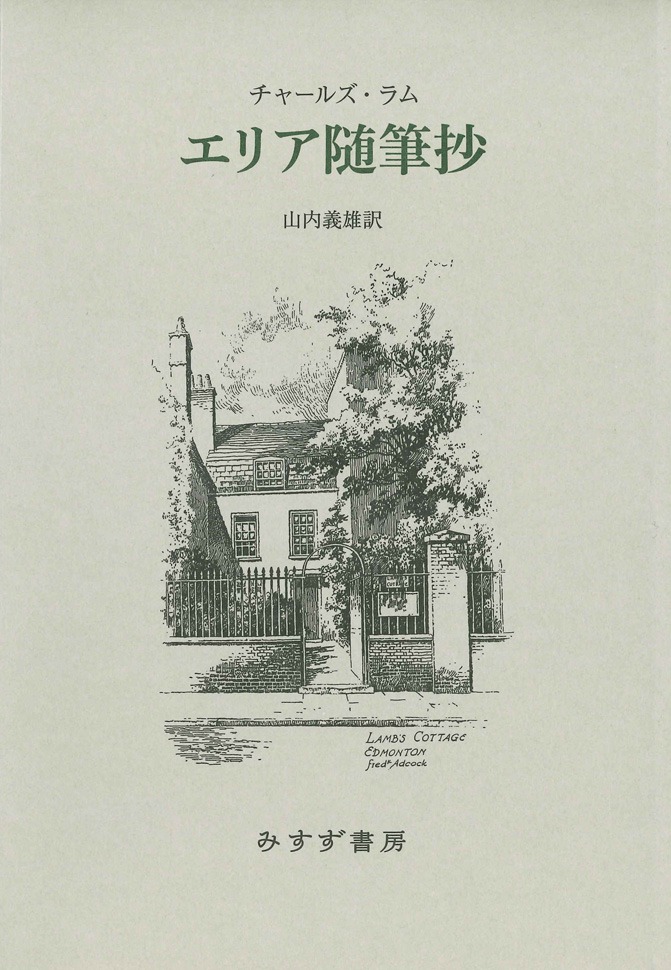あらかじめことわっておくと、本書『長い読書』に「はじめに」や「あとがき」はない。37篇のエッセイと目次、巻末の初出一覧だけの、簡潔なつくりになっている。そこでこの紹介記事では、もし、本書についての「序文」を、どこか別の時代の、別の土地に住む人が書いてみたらどんな風になりうるかと、少し妄想をふくらませてみた。以下はその内容である。
島田潤一郎『長い読書』のための序文(仮)
村上春樹が編訳者をつとめる中央公論新社の「翻訳ライブラリー」シリーズの一つに『バビロンに帰る』というフィッツジェラルドの短編・論集がある。その本に収載されている文芸評論家のM・カウリーが書いた文章に、フィッツジェラルドの「二重のヴィジョン」という概念が出てくる。作家の傑出した点がそこにある、とカウリーは書いている。
フィッツジェラルドは彼の偉大なる瞬間を生きた。そこにあったドラマを思い出すとき、彼はそのような瞬間をもう一度生き直した。しかし同時に彼は、そのような瞬間から一歩離れて立ち、冷ややかな目でその原因と結果を検証した。それは彼の二重性であり、あるいはまたアイロニーでもあった。そしてそれこそが彼の作家としての傑出した点のひとつだった。
(マルカム・カウリー「スコット・フィッツジェラルド作品集のための序文」村上春樹訳 より)
フィッツジェラルドは1920年代アメリカ東部の社交界をモチーフに小説を書いた。きらびやかな世界に生きる人々の中心で注目を集めながら、その時間を外側から見つめる視点を忘れなかった。自身の内側にある倫理のレンズを通じて、そこに生きる個人の悲哀と輝きを言葉にして残した。
描かれているモチーフに国と時代の違いがあるとはいえ、島田潤一郎が描くエッセイの世界にも、この「二重のヴィジョン」を通じて時代を描こうとする倫理観の表出がある。自分がこれまでに生きてきた時間、何かを感じたまま忘れられなかった瞬間について、振り返って考えたことが記される。自分が体験した時代とは何だったのか。その時に感じたことをもう一度生きるようにして、何度も見つめる。忘れてはいけないことは何だったのか。自分が生きた時間を感じるまま記すのではなく、描かれる思い出にはいつも、自分がいなくなった世界の視点からの判断と選択がある。
ぼくは校了するとき、いつも未来からの視線を感じる。それは「未来の世界の猫型ロボット」が登場するマンガからの着想であり、未来のぼくが現在のぼくに「ほんとうにそれでいいのか? きみはいま、決定的な間違いを犯そうとしているんだぞ」と脅すのである。(中略)ふつうに考えればそんなことはありえないのに、この本はもう世の中に出なくてもいいのでは? と思うくらいに校了という瞬間をおそれているのである。
(本書「アルバイトの秋くん」より)
この37篇のエッセイ集は3章構成で、それぞれ「本を読むまで」「本と仕事」「本と家族」という章題がついているが、通して読むことで一つの時代が浮かびあがる。1976年に生まれ、1990年代に青春を過ごし、2000年代に就職活動を行い、苦労のすえ出版社を創業し、2010年代に子育てをしながら本づくりを続けてきた著者の記録であり、また同時代を生きた人たちの観察日記でもある。その意味で本書はタイトルに反して、読書論や随筆というより、近代日本文学にありがちな露悪趣味のほとんどない私小説ともいうべき、文学性の濃い一冊となっている。著者の倫理的なモチーフは明確だ。それは読書を通じて、よい人間になりたいという願いを持ち続けること。最初の著書『あしたから出版社』から続く、具体的な生活の記録は本書においても続き、著者が語ってきた言葉に説得力を与えている。
本書の文学的魅力をもう一つ書くと、それは言葉の芸術がない世界から文学を書き始めようとする「スタート地点の海抜の低さ」にある。それはかつて、加藤典洋が高橋源一郎の小説『さようなら、ギャングたち』の魅力として記したものだ。
こういってみよう。
中学校の教室で、大昔、教師が富士山の高さはヒマラヤの高峰に比べればそれほどでもないが、海抜ゼロの海辺からそのまま裾野になって峨々とした山容をなしているところがほかと違う。他の山は最初からの土台分数千メートルを加算しているが富士は山だけで三千七百七十六メートル、そこが偉い、といった。高橋源一郎の言葉は才気があって切れがよくて、わたしは好きだが、そうである以上にわたしが高橋の小説にひかれるのは、そこで、言葉が、世界とつながる言葉の初期のたたずまいを、失っていないからである。(中略)彼は小説家としては富士山だ。いつも失語からそのまま山頂まで、一気にのびていく稜線を描いて、その小説を書く。
(高橋源一郎『さようなら、ギャングたち』(講談社文芸文庫)加藤典洋の解説より)
本書には、本を読む人たちを見つめる時の眼差しと同じ敬意でもって、本を読まない人たちの姿も描かれている。立派な本棚と文学全集を揃えながら、そこにある本を動かすことのなかった両親。読んだことのない村上春樹を否定しながら、叔父の書いた詩を暗誦する知人。近所のそば屋で働く人と、その子どもたち。猫とゴルフと郷里をこよなく愛する義理の父。読書の合間に描かれる人々の横顔は、どれも鮮やかで印象に残る。著者が書き残そうとする人々を描くときの視点は、本書に記されているジェイムズ・ジョイスの筆致とも重なる。
ぼくが驚き、こころ動かされたのは、複雑な構成、多様な文体によって表現される、主人公の凡庸さだった。(中略)ジェイムズ・ジョイスが二〇代のときに発表した短編集『ダブリン市民』を読むと、作家の凡庸さにたいするあたたかな目にあらためて気づく。
(本書「『ユリシーズ』がもたらすもの」より)
読書を特別視しない風通しの良さが、本書で描かれている思想の厳しさを和らげ、読みやすくしている。読者は自分の生活時間の続きが見えるような文体に導かれてこの本の中に入り、そこから出てくる時には「凡庸さ」へのあたたかな目を持って、自らの倫理性に向き合うことになる。決して長くはないこのエッセイ集を何度も読み返していくと、その下地に当たる部分には一貫して、自らの時代に目をつぶらずに生きる人々への励ましが描かれていることに気づくだろう。(編集担当・河波雄大)