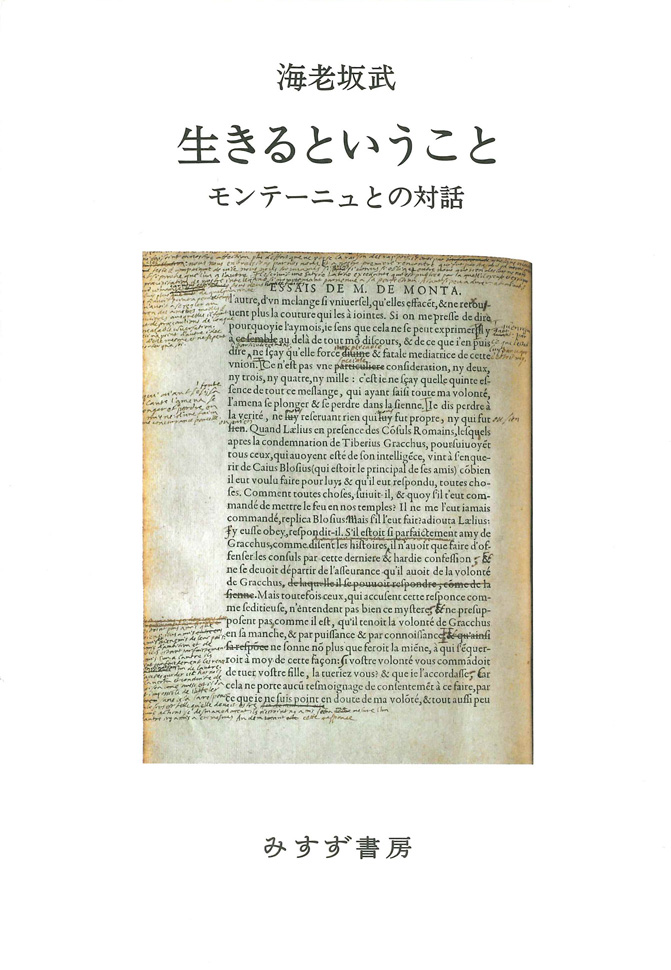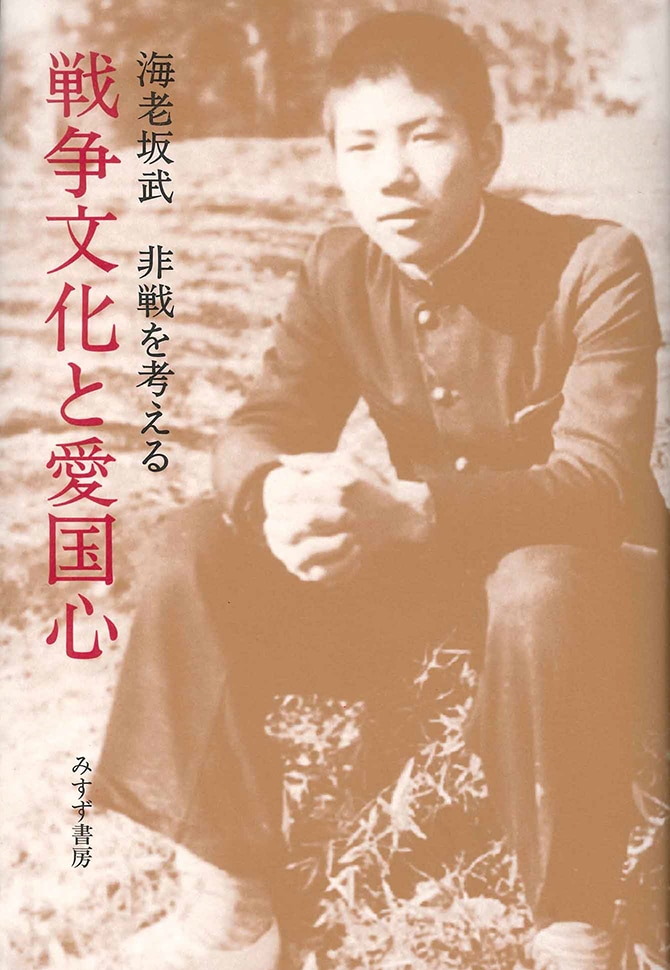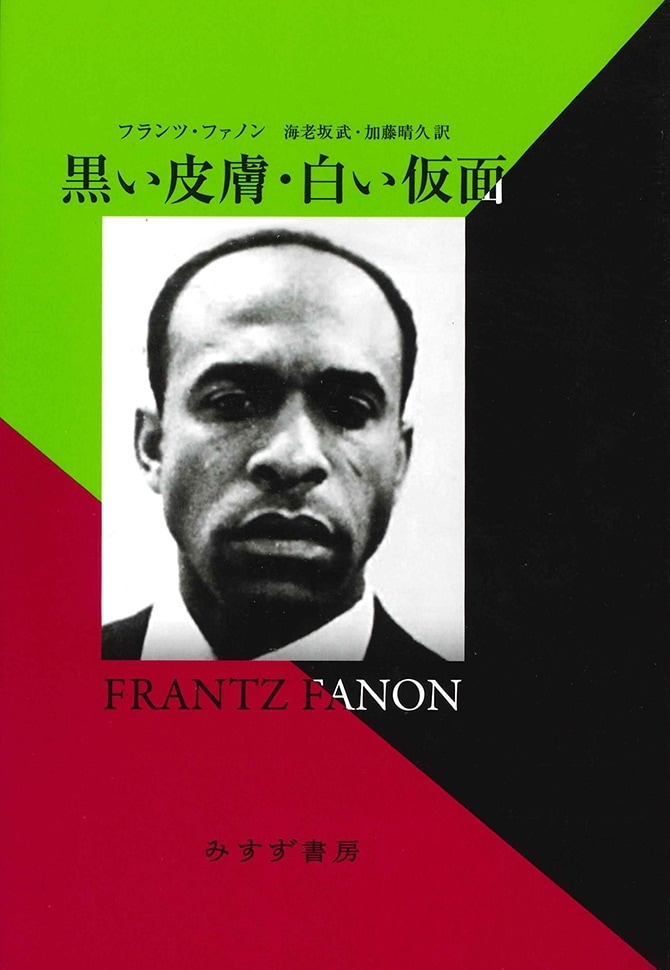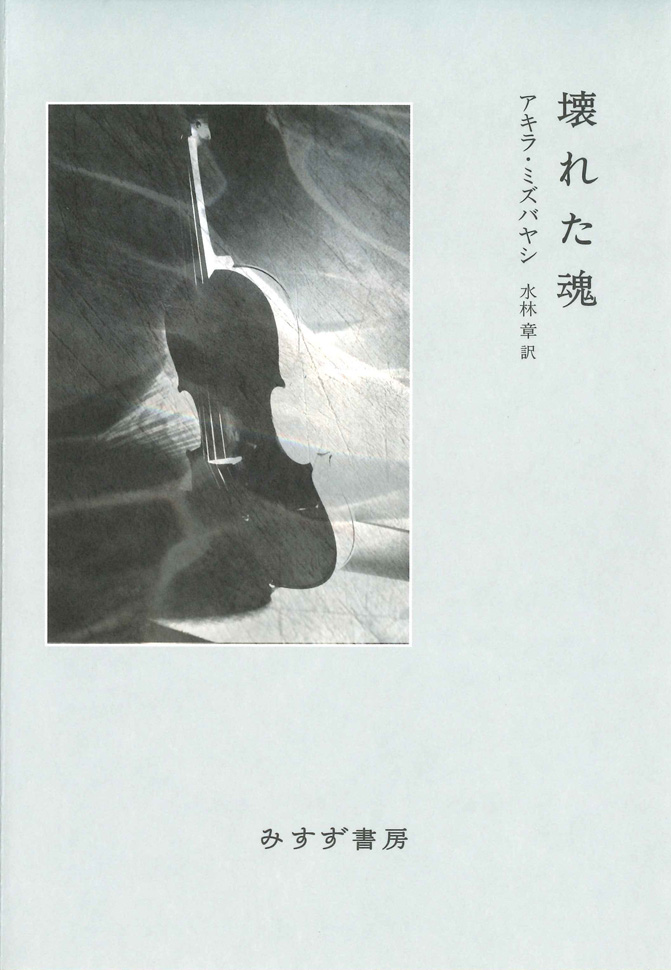著者がモンテーニュの『エセー』に出会ったのは、学生時代のこと。フランス文学史の必読書だからと「大急ぎで」読み、その後は「勉強のために」1日2、30ページ読んでいたこともあったが、「よくわからず、あまり面白いと思わなかった」という。
60歳近くになった頃に、その『エセー』を読み返すと、若い頃には気づかなかった「愛すべき人物」モンテーニュの姿が見えてくる。パスカルは『パンセ』第二章で、なかなかに手厳しい『エセー』評をくりひろげており、モンテーニュが「自己を描こうとした愚かな企て」に嫌悪感を示しているが、まさにその「自己を描こうと」する企てと、そこに描かれたモンテーニュの自画像こそが、著者を惹きつけてきたことは間違いない。モンテーニュの言葉を読む愉しさに身をゆだね、気に入った文章をノートに書き写し……
長年にわたり『エセー』を枕頭の書としてゆくうちに、やがて「モンテーニュにならって」エセーを書いてみる、という企てがはじまることになる。モンテーニュ論ではない。『エセー』の入門書でもない。この書を繙き、16世紀に生きたモンテーニュの言葉と対話するように、みずからが生きてきた戦後日本を振り返り、「わたし」を省みる。
モンテーニュは、40代なかばで、すでにこう書いている。
「われわれ老人は、自分のことをどうにかするだけで手一杯だ。自然が与えてくれた楽しみは、老いとともに、だんだんとなくなっていくのだから、人為的な楽しみで、自分を支えていこうではないか」
『エセー』「空しさについて」
時代かわって、21世紀。著者が80歳になろうとする頃、書くものに新たに加わったテーマがある。それが「老い」だ。
「令和5年度厚生労働白書」によると、2021年時点での日本人の平均寿命は、男性が81.47歳、女性が87.57歳。世界一長寿国の「死」に向けての助走期間は、どの時代の人類が経験したよりも、長い。
「終活」という言葉がメディアにはじめて登場したのは2009年のことだが、その「活動」内容は、生前整理、介護、葬儀と墓、のこされた家族が揉めない相続などなど……終活の重点は、「生きるということ」の先にあるゴール・インの決め方にあるようだ。
いっぽうで、「老い」に足を踏み入れてからの人生を、GO-GOES(元気に活動できる時期)、SLOW-GOES(体の衰えが活動のさまたげとなる時期)、NO-GOES(日常生活が難しくなる時期)と三段階に分け、やっとGO-GOESの入口に立とうかとする人びとに、それぞれの時期を「どんなふうに生きるか」をイメージさせ、最後までよりよく生きるために具体的に考えてみよう、という試みも始まっている。ヨーロッパでも長寿国といわれる国でのことだ。
「それにしてもわれわれは大変な愚か者なのである。だって、「彼は、人生を無為に過ごした」とか、「今日は、なにもしなかった」などというではないか。とんでもない言いぐさだ。あなたは生きてきたではないか。それこそが、あなたの仕事の基本であるばかりか、もっとも輝かしい仕事なのに」
『エセー』「経験について」
「もう一度生まれ変わるとしても、わたしは、これまで生きてきたように生きるのではないだろうか。過ぎ去ったことを悔やみもせず、未来をおそれることもない。
(……)
わたしは、わが身体という草がはえ、花が咲き、実がなるのを見てきたし、そして今、それが枯れるのに立ち会っている。しあわせなことだ。なぜならそれが自然のなりゆきであったのだから」
『エセー』「後悔について」
著者がモンテーニュに学ぶ「老い」の哲学、著者いうところの「老いを飼い慣らす」ための哲学は、「老いを生きる」哲学、老いをよりよく生きるためにモンテーニュがささやいてくれる哲学でもあるのかもしれない。