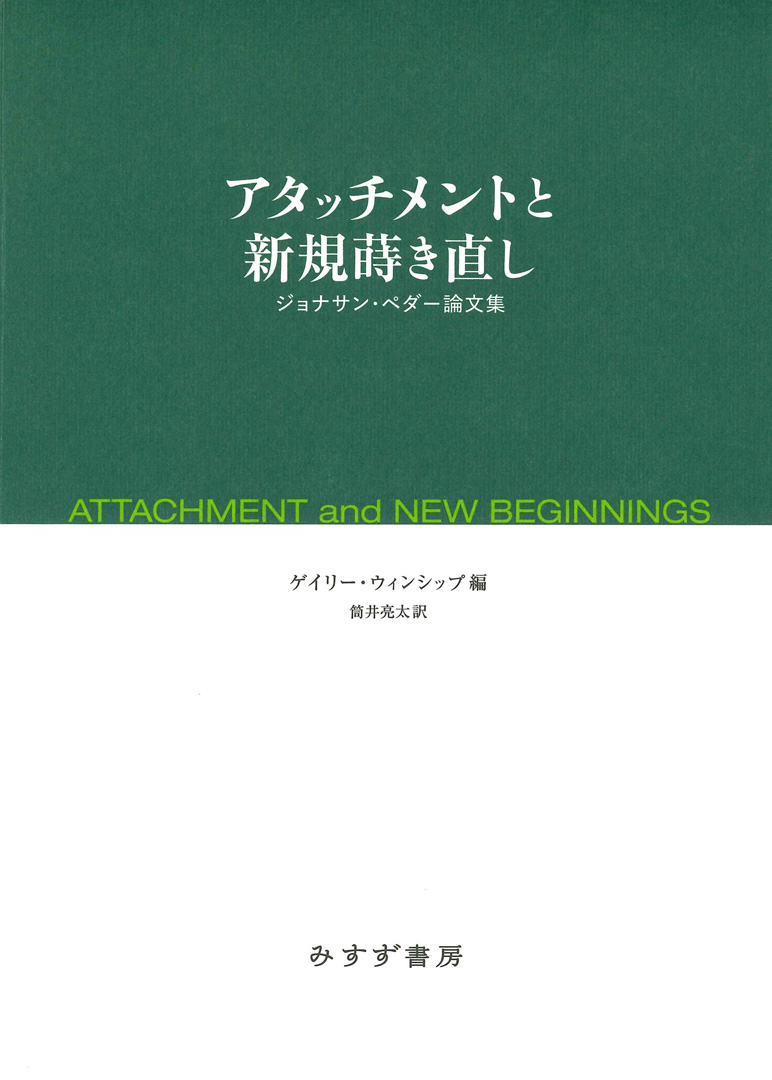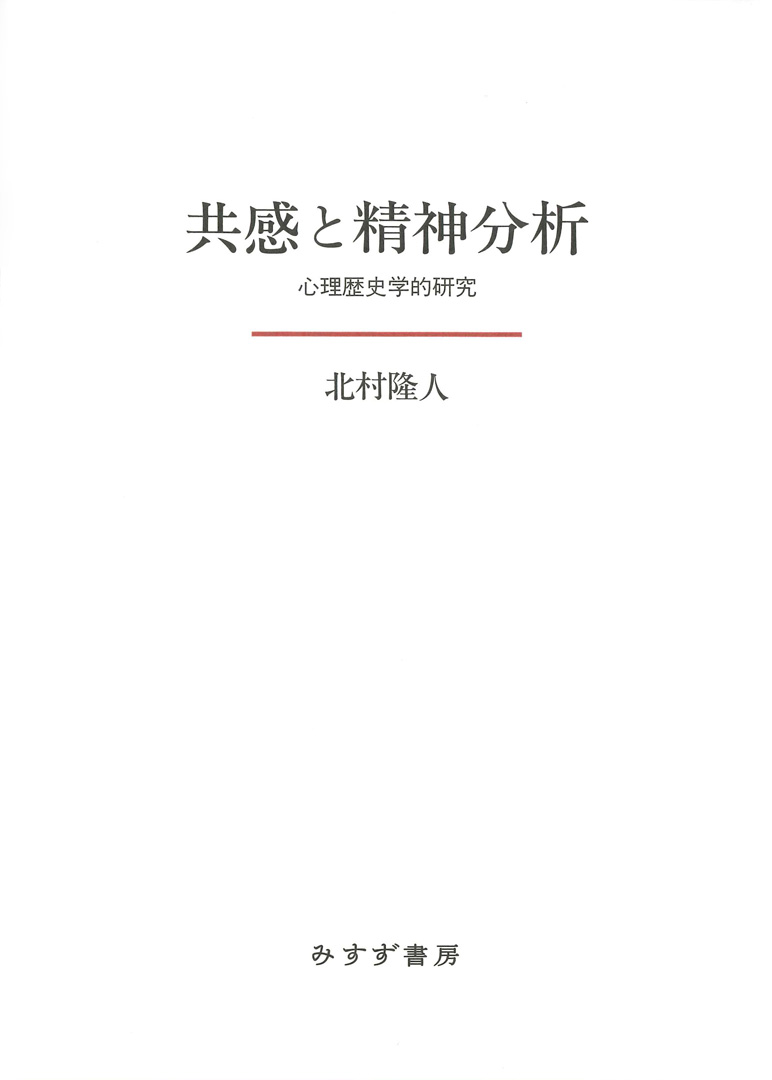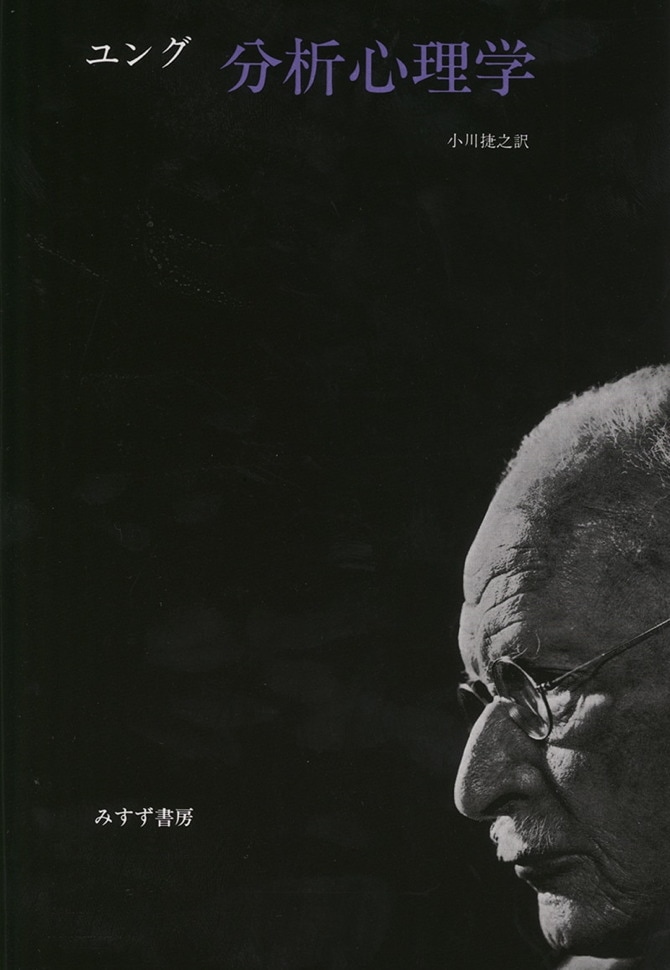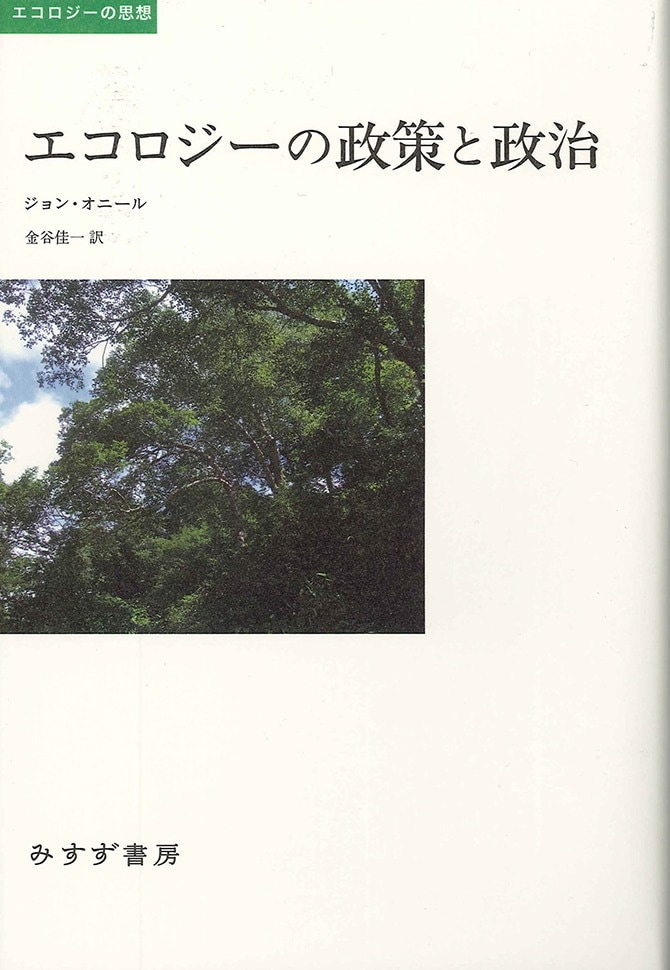本書は、世界6ヵ国(アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ジョージア、南アフリカ共和国)で実際に行われた選挙を材料に、有権者(棄権者も含む)が選挙からどのような影響を受けるのかを明らかにしようとするものである。それにあたり著者らは、選挙における行動(参加、投票先の選択)、選挙における経験(記憶、内面化した考え方)、選挙がもたらす解決感(和解、希望、敵意)という三つの変数に着目したモデルを立てた。これまでの選挙研究では、主に「行動」に目が向けられてきたが、著者らはそうした「常識」を覆そうという挑戦的な気概をもってモデルを設計し、調査を行った。
ここでは、このようなモデル設計に至った著者らの発想について、簡単に紹介する(モデルやデータ収集、そしてその分析の詳細は本書を繙いていただきたい)。
選挙研究の多くは、「あの政治家はなぜ当選したのか」「あの政党はなぜ勝利したのか」といった「代表者の選択」と、「今回の投票率の低さ(高さ)にはどんな理由があるのか」といった「選挙参加」の二つの点に注目してきた。しかし市民一人ひとりは、国や自治体を挙げた選挙という大きなイベントに関与するにあたって、「だれに投票するか」「投票に行くかどうか」という制度的な関心以外にも、さまざまな関心をもっている。本書の特別な点は、この「制度以外の関心」にも注目したことである。本書の第1章で、著者らは次のように述べる。
制度中心ではなく人間中心の見方をしたとき、選挙がいつ人々に幸福感を与えるのかを理解する方が、左派/右派の候補者にいつ票を入れるかを知るよりも、直感的に重要性を感じないだろうか? 議会制民主主義とその正統性を考えてみても、選挙が市民に満足感を与えることの方が、特定の候補者を選ぶよう導くことよりも大切ではないだろうか? そして解決感について言えば、何らかの状況によって選挙が和解をもたらすことができず、敵意が煽られ社会の平和と安定が乱されることの方が、左派/右派の勝者がいつ誕生するかということよりも重大なニュースではないだろうか?(p. 13)
たとえば選挙には、国民同士の意見の相違を調停する機能もある。ある人にとって選挙結果が納得のいくものではなかった場合でも、選挙という手続きを経たことで結果を受け入れる気になる、ということもある。著者らはこれを「選挙がもたらす解決感」と呼び、中心的な分析対象としている。
そもそも選挙は、投票して結果が出れば終わり、というものではない。投票日の少し前から選挙運動がはじまり、投票日になれば投票に行き(あるいは期日前に投票しておき)、投票日の夜(エレクション・ナイト)には開票速報がテレビ放送され、選挙後しばらくはその余韻が社会を包む。2016年イギリスのブレグジットをめぐる国民投票のように激しく賛否が分かれるケースでは、未だにブレグジットは正しかったのかどうか議論があるように、投票の余韻が長引く。中には、一つの選挙が終わった後に次の選挙を見据えた考えを持つ人もいる。このように選挙サイクルには個々人や状況次第で大きく幅があるなかで、市民の一体感や敵意、幸福感や解決感などがどのように醸成されていくのだろうか。著者らはこれを理解するために、「ほかの人はだれに投票したのだろうか」「あの政治家を支持する人がいるなんて信じられない」「初めての選挙だから緊張する」「選挙のことで家族や友人と言い争った」「こんな結果は受け入れられない」などといった投票者のいろいろな経験や感情に目を向け、選挙というイベントが市民一人ひとりにどのような経験をさせ、どのように解決感をもたらしているのかを明らかにしようとしたのである。
選挙が果たすべき機能やその意義を考え直すきっかけにもなりうる研究である。
蛇足になるが、本書で収集したデータのなかに、投票所から出てきた投票者へのインタビューや、選挙期間の前後で日記を書いてもらうなどして集めた自由記述があり、その一部が本書内で示されている。こうした定性的データからは、投票者一人ひとりの考え方の違いや具体的な感覚が読み取れる。こうした箇所を拾い読みするのもおもしろい。