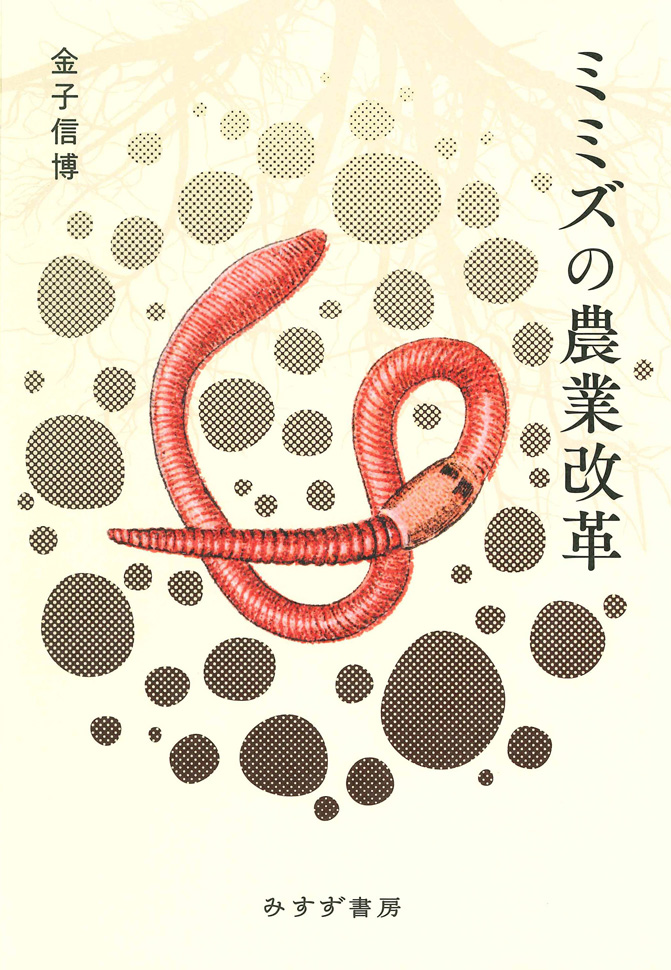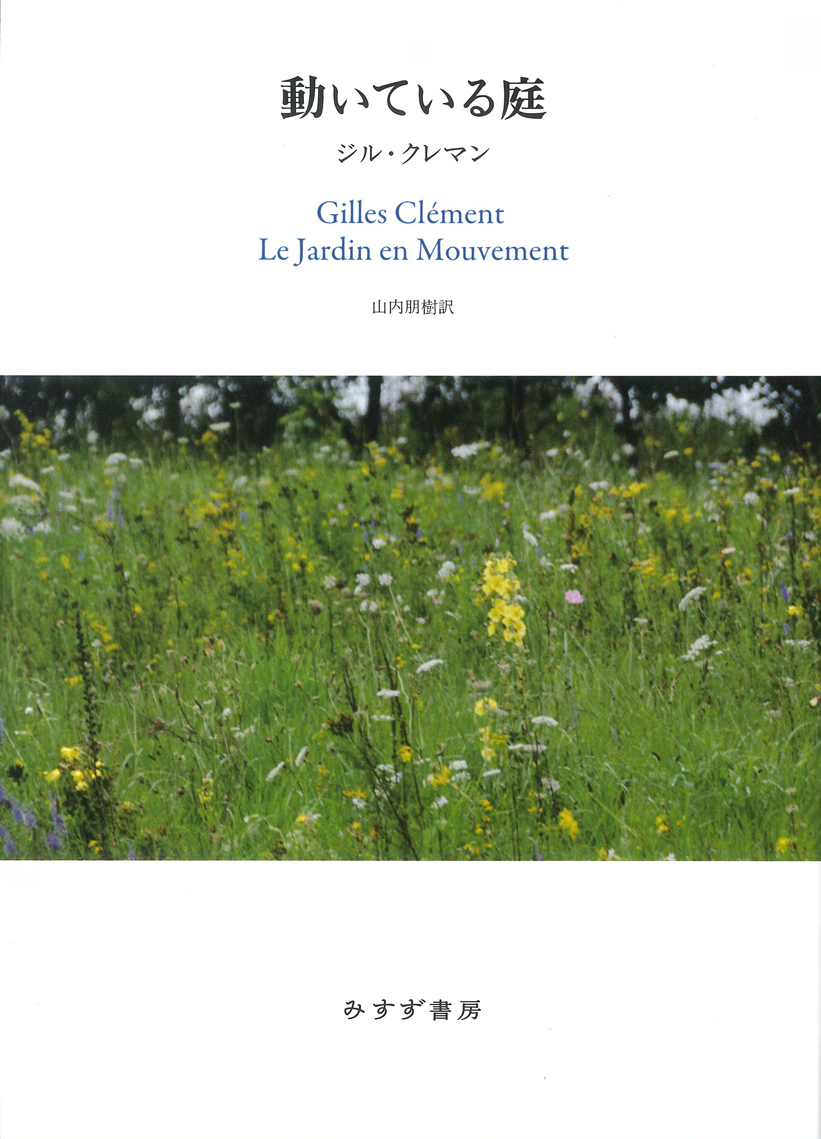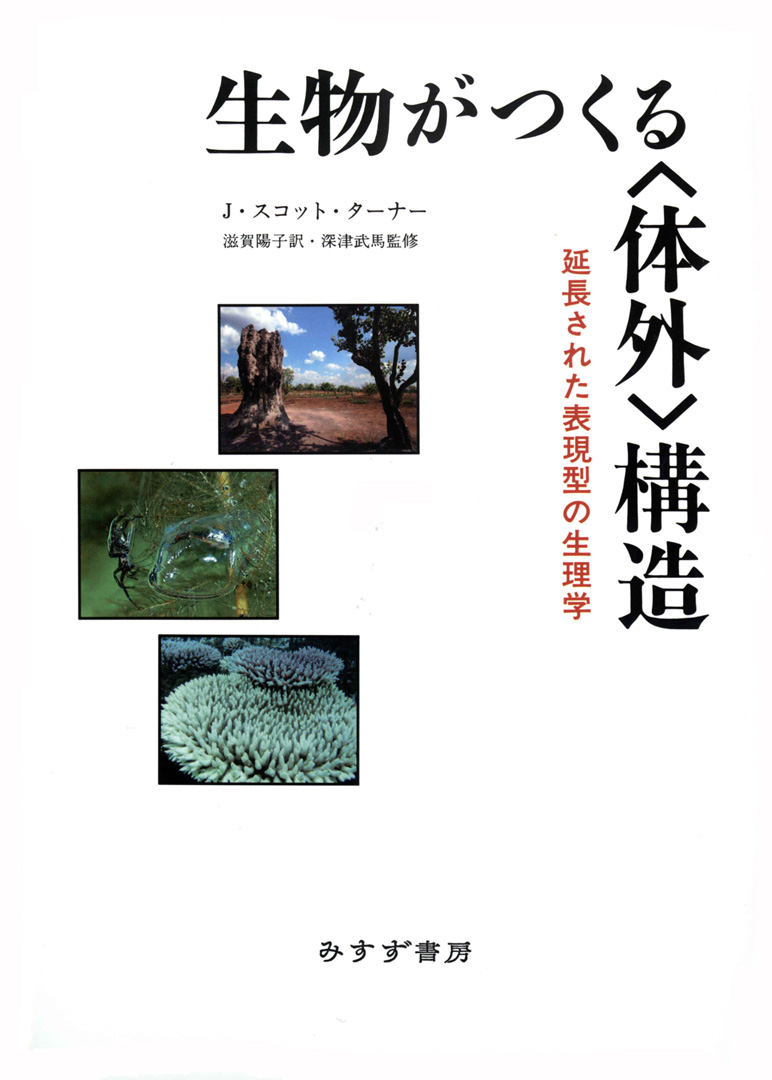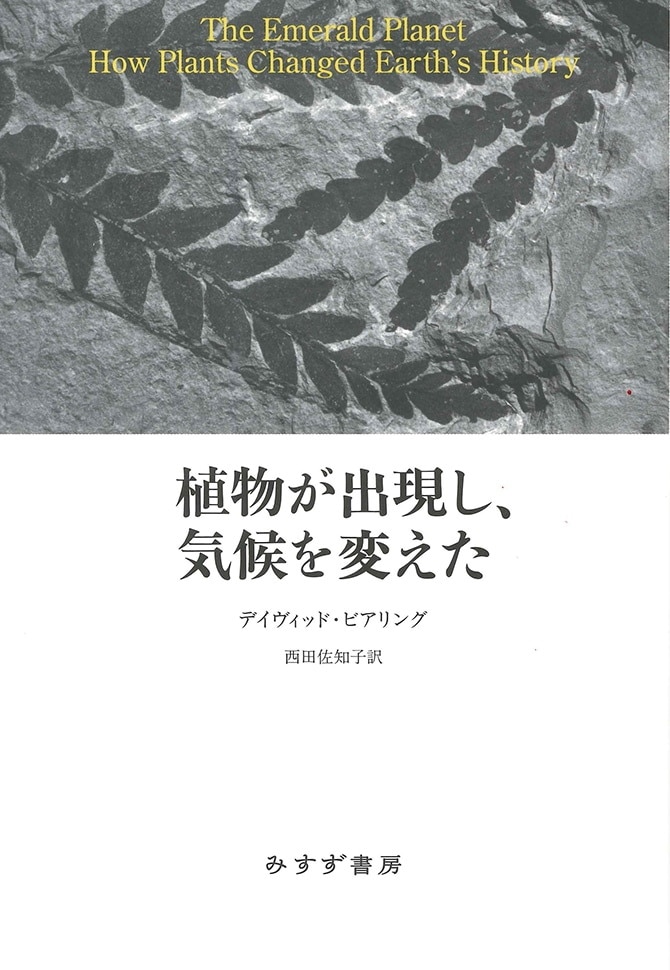土、という言葉を聞くとどのようなイメージが湧くだろうか? 普段目にするのは、たとえばグラウンドの土、畑や田んぼの土、工事のためにどこかから運ばれてきた土などだろうか。土は常に私たちの足元にあるので、変化のない、あって当たり前のものに思えるかもしれない。しかし土は、陸上に生物が進出してから、数億年かけて作られたものである。もしも陸上から生物が消えたら、土は消え、もとの岩と砂ばかりの陸地に戻ってしまうだろう。土は、常に変化し続けている複雑な構造物であり、生物が存在する地球上にしかないものなのだ。
土ほど、私たちの身近にありながら、その実態が知られていない環境は他にないのではないかと思う。地球環境問題が日常的に論じられるようになってきたので、たとえば「世界的に土壌劣化が進行」し、食料生産に支障が出てこれから大変なことになると聞いたことがある人も多いだろう。土は、空気や水のように環境の重要な部分を占めている。土はやっぱり大切なんだなと思ってはいても、では実際になぜ、どのように大事なのかと問われると説明に困るのではないだろうか。身近でありながら、よくわからない存在。あるいは、多くの人はその一面しか知らない存在が土であるように思う。月や火星、小惑星に探査機が飛ぶ時代になっても、私たちの足元には未知の世界がある。
では、土とはいったい何なのか。土を一言で説明するのは難しい。砂と落ち葉をただ混ぜただけでは土はできない。空気のように、窒素が78%、酸素が21%……と組成が一律に決まっているわけでもない。土には「構造」があり、それはさまざまな作用が働くことで維持されている。土は、岩石が風化したものに、生物が長い時間をかけて作用してできる。具体的には、微生物から植物、動物まで多様な生物が土に棲み、踏み固めたり、根を張ったり、分解したり、吸収したりして影響を与えあっている。私たち人も長い時間をかけて土を変えてきた。また、地層や気候も土地によって異なる。その結果、世界中で土地ごとに多様な土が形成され、それぞれ数億年にわたり変化し続けているのである。したがって、土を研究する学問分野は多岐にわたり、地質学、化学、物理学、そして生物学などがすべて含まれる。
このように土は複雑なものなので、どこに着目するかによって見え方が異なる。そこでまず、私が森林生態学の分野で土に出会った経緯と、農学における土とは何かを見た上で、土の生き物として誰でも知っているミミズを案内役にして、土の世界に飛び込んでみようと思う。
「土」との出会い
かくいう私も、はじめから土そのものに興味を持っていたわけではなかった。私は生物の研究や「生態学」という言葉にあこがれ、「森林生態学研究室」という名前にひかれて京都大学農学部に進学した。森林というと生物の中でも植物の研究が主であるように思えるが、私は動物のほうに興味があった。当時、演習林におられた渡辺弘之先生が1974年に書かれた『ツキノワグマの話』というクマの本を知り、渡辺先生のところに行けば動物の研究ができるのではと考えた。そこで、学部の3回生の時に同級生を誘って渡辺先生にご指導をお願いして、自主的な勉強会を開催することにした。その時は、北米のオジロジカの個体群管理の英語の文献を一緒に読んでいただいた。
学部の4回生になって卒論のテーマを考える時になっても、なんとか動物の研究をやりたかった。しかし、演習林の教員である渡辺先生には学生を受け入れていただけなかった。林学科の森林生態学研究室には土壌動物をテーマとされていた武田博清先生がおられたが、あいにく1年間タイに在外研究に出られていて、やはり卒論の受け入れはしてもらえなかった。結局、当時講師であった岩坪五郎先生のところで森林土壌の窒素無機化速度を野外で測定するというテーマに取り組んだ。窒素は植物の成長に欠かせない元素だが、空気中にある窒素(N2)も枯れた植物に含まれる窒素も、そのままでは植物は吸収できない。そのため、枯れた植物の分解過程で無機態の窒素(アンモニア態や硝酸態の窒素)になったものを、植物の根から吸収している。
実は、土のことは授業で習ったにもかかわらず、4回生になって研究室に所属するまでまったく意識していなかった。また、当初は土壌窒素の無機化に動物が関係しているようには思えなかった。しかし、結果的に窒素無機化は土壌の持つ重要な機能のひとつであると理解し、このテーマとはその後自分自身の研究でも長くつきあうことになった。土壌窒素の無機化には、動物も深く関係していたのだ。
さて、卒論を終え修士課程に進学した頃にちょうど武田先生も日本に戻ってこられたので、修士論文のテーマを相談に行った。すると、ササラダニという初めて聞く土壌動物の研究を勧められた。「僕はトビムシを研究しているから、君はダニでもやったら?」ときわめて軽い調子で言われたのだ。というわけで、急遽土壌動物の勉強をやることになり、かつて渡辺先生のところに一緒に行った同級生の天保好博君から青木淳一先生の『土壌動物学』という大部の本を譲り受けて、ササラダニのところから読み始めた。
窒素もトビムシもササラダニも、一般の生物好きには今もってあまりアピールしない素材であるが、たまたまこういった対象から土の勉強を始めたことで、私独自の土の理解ができたように思う。それは一言で言えば、「根や微生物、そして土壌動物が土というしくみを運営している」ということである。よく「土は生きている」というが、あくまで比喩である。土は生き物に維持され、生き物の振る舞いに敏感に反応しているので、土だけを見ても自律的に生きているように見えるのかもしれないが、生き物がいなくなれば、土は確実に「死ぬ」。なお、あとから気が付いたのだが、渡辺先生は守備範囲が広く、本書の主役であるミミズも先生の主要な研究テーマであった。
こんな風にして、私は人の手が入らない森林で土と土壌動物がどう関わっているかを研究するようになった。まず自然環境における土を見たことで、のちに農地における土を別の視点で見ることができるようになったと言えるかもしれない。
農学における「土」
土に関する学問として、土壌学という伝統分野がある。農学部には古くから農芸化学という分野があるが、土壌学はその始まりから農芸化学を代表する領域であった。農学の分野では、土は農業生産の基盤である。そして化学肥料の発明は、土を化学的に理解する研究を大きく進展させた。それは簡単にいうと、肥料分が土でどう保持され、植物への供給がどう進むかを元素や化合物別に調べる研究である。
植物は水と二酸化炭素、そして窒素やリンといった栄養塩類(生元素)と光エネルギーを使って光合成をし、有機物を作り出す独立栄養生物である。光合成は細菌から藻類、そして維管束植物まで多くの生物が行うが、私たちの身の回りの森林や農地では、維管束植物が光合成の主役である。維管束植物は土に根を張って自らを支えるとともに、根を通して土から水分と栄養塩類を吸収している。
ここで、栄養塩類という言葉を初めて聞く読者も多いかもしれない。化学で塩といえば、酸と塩基がイオン結合したものであり、水に溶けると陽イオン(酸)と陰イオン(塩基)を生じる。食塩、すなわち塩化ナトリウムはその一例にすぎない。そして、水素、酸素、炭素以外の生体を構成する元素は基本的にイオンの形で根から吸収される。つまり、植物が生活するために必要な元素(必須元素)は、塩の形で結晶として固定できる。これすなわち化学肥料である。また、生物に必要な元素という意味で「生元素」と呼ばれることもある。これで、肥料の役割がわかるだろう。農作物は水と光とCO2だけではできず、土壌から栄養塩類を奪っていく。それを肥料で補うというわけだ。土壌学は、このような植物の生長に関わるさまざまな元素の循環と化学反応を扱う。
さらに土壌学の分野では土壌物理学が発展した。化学肥料が発明された頃、人類は機械の動力を使って農地を耕すことができるようになった。耕すには土の物理的な性質をよく知る必要がある。土はさまざまな大きさの鉱物(粘土、シルト、砂、礫)と植物や微生物の遺体との混合物であり、これらの混合比が土の物理性を左右している。土の物理性は、耕しやすさの他に、水分の保持や排水の能力、土の隙間の空気の組成などにも影響していて、それらは植物の根にとっての生育環境を意味する。踏み固められたグラウンドのように土が固いと、雨水がなかなかしみこまず、植物の根も伸びにくい。耕すことで、土を柔らかくし、邪魔な雑草を根こそぎ排除できる。
以上をまとめると、農学ではそもそも土とは何かと考える時に、常に作物の生長への影響が意識されてきたと言える。栄養塩類や水分が適度に供給されており、なおかつ水分が多すぎて根が腐ることがない場合に作物の生長がよくなるので、「よい土とは、肥沃で、水もちと排水がよい土のことである」と考えられてきた。人は、土をこのように物理的・化学的に解釈し、その状態を管理するために介入し続けてきたわけである。
しかし、そもそも土は介入しなければ維持できないものなのだろうか。自然界では、多様な植物を育みながら、土が勝手に維持されているように見える。実はここまでの土の理解には、生物学的視点が欠けている。かつては、土の中に棲む微生物のほとんどが培養できなかったため、いったいどのような微生物がいるのか、その輪郭さえわからなかった。しかし昨今は、遺伝子解析の急速な発展もあって土の微生物のメンバーが一通りわかるようになり、微生物の役割と有用性が広く理解されるようになってきている。
ところが、農学の分野では、自然界の土は長らく病原菌の巣窟と考えられ、微生物の負の影響ばかりが注目されてきた。鳥や昆虫が農作物を食べる場合は被害や犯人が目に見えるので、被害の始まりがわかりやすいが、土壌病害の場合は、健康そうに育っていた作物がある日突然しおれてしまい、詳しく調べると病原菌のしわざであったとわかる、ということになりがちである。微生物はそもそも人の目には見えないので、事後的な対処が難しい。そこで、土にあらかじめ強力な薬剤を注入して、微生物をなるべく皆殺しにするという作戦がとられたりしてきた。土壌微生物と一口に言っても、その種類や数は膨大であり、作物に病気を起こす微生物はその中できわめてわずかだ。しかし、病原菌だけ殺す農薬はないものだから、まとめて殺すということが行われてきたわけだ。すると、もはや生物によって維持されなくなった土が残り、物理的・化学的介入が必要になってくるというわけである。
私自身は、このような農学の中の土壌学やその応用としての農学とはほとんど関係ないところで研究をしてきた。しかしどういうわけか、今は農地の土に関心があり、農場で試験研究も行うようになった。農学の外の立場から農地の管理や研究を見ていると、そもそも土が生物の生息場所であり、生物が土を作ってきたという視点を大いに欠いているように思える。この私の違和感を実感するには、一旦、人の視点を捨ててみるとよい。まずミミズを狂言回しとして、自然界の土がどんな場かを体感してもらおうと思う。
(…)
――続きは書籍・電子書籍をごらんください――
Copyright © KANEKO Nobuhiro 2023
(著者のご同意を得て抜粋・転載しています。
なお読みやすいよう行のあきを加えています)