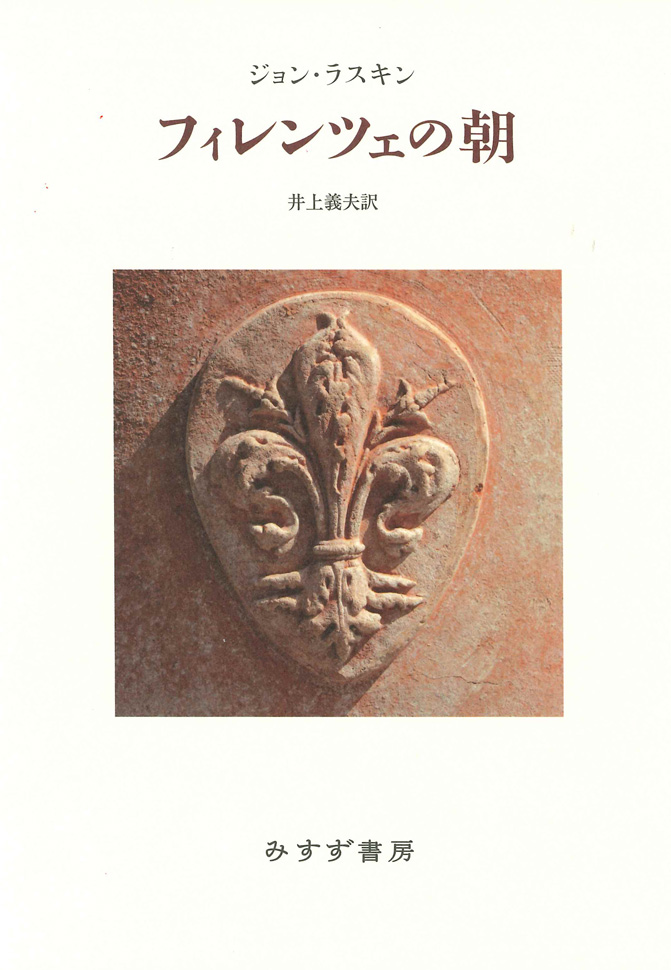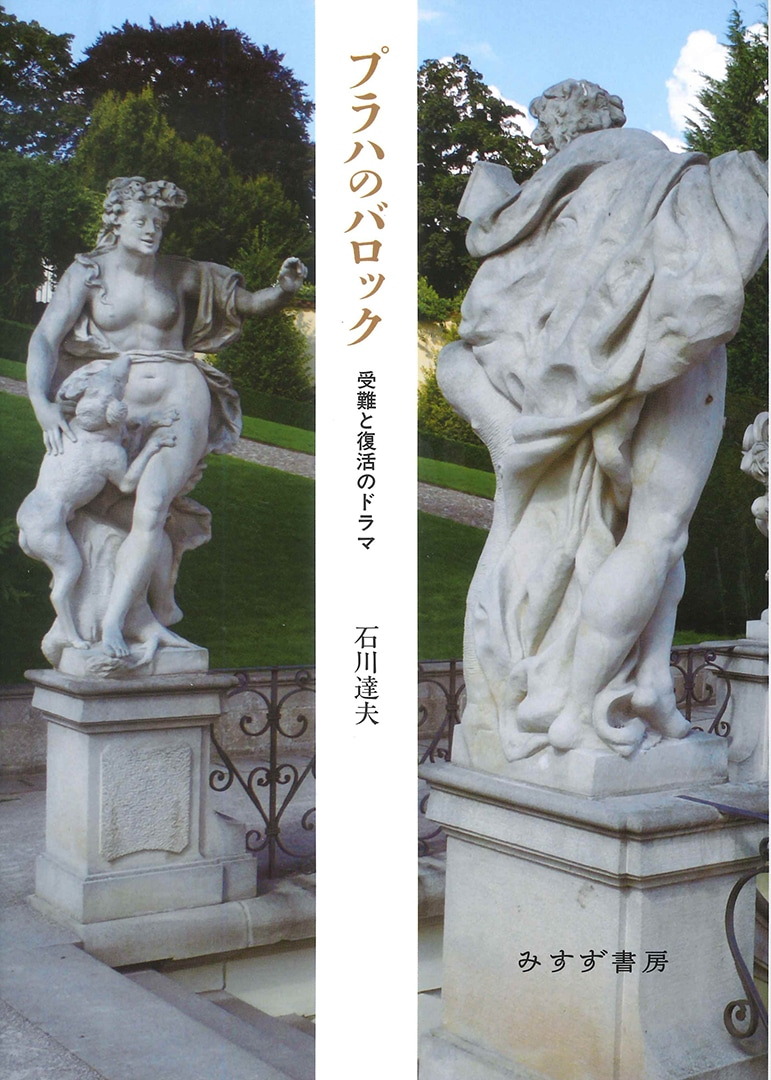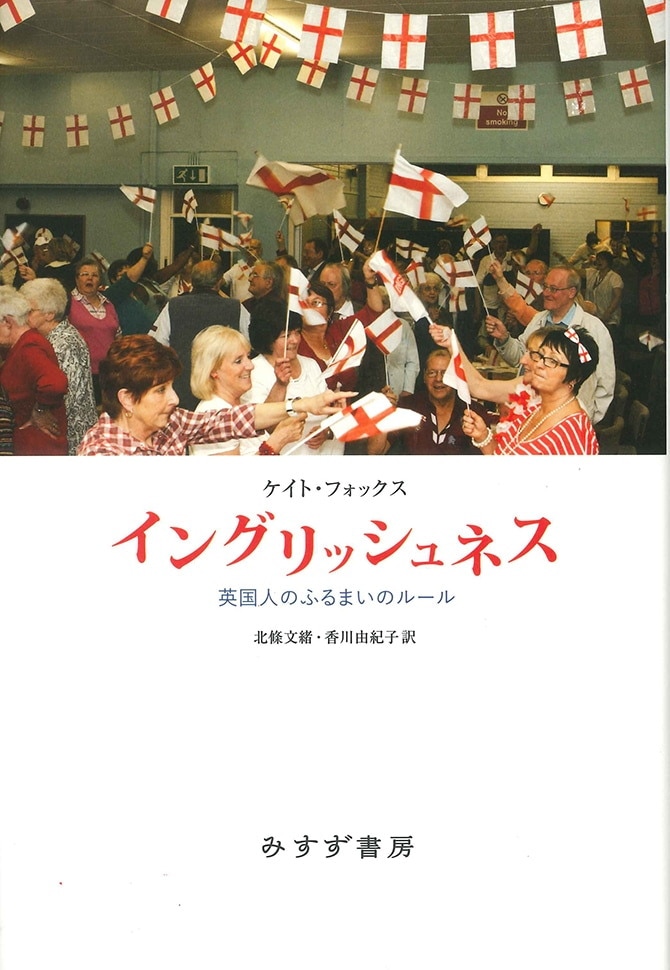フィレンツェの朝――Mornings in Florence: Being Simple Studies of Christian Art, for English Travellersの原書第一版は、1875年から77年にかけて分冊で刊行された。その頃、産業革命と植民地によって繁栄をきわめたヴィクトリア朝のイギリスでは、かつては貴族の子弟の特権だったグランド・ツアー(大陸旅行)が、より多くの人びとの手の届くところとなりつつあった。今でいうマス・ツーリズムのはじまりである。
前世紀のグランド・ツアーに倣って、イタリアへのアカデミックな「学びの旅」が人気だった。手に手に19世紀の『地球の歩き方』たるベデカーやマレーのガイドブックを携えて、フィレンツェではウフィツィ美術館に詰めかけ、祈禱書とともに名だたる教会をめぐる。
本書でラスキンが読者を案内するサンタ・クローチェ聖堂、サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂、そして、洗礼堂と鐘楼をもつフィレンツェの大聖堂(ドゥオーモ)といった教会堂と、聖堂の内部装飾は、21世紀のいま見る姿と19世紀とで大きく変わっていることもないだろう、と思うかもしれない。しかし、当時の人びとの目に映った聖堂のたたずまいやフレスコ画、彫像・彫刻のありようと、今日私たちが目にするそれとは、じつは、なんと違っていることだろう。
教会の外壁の大理石の浮彫彫刻や彫像は、修復と保存のために取り外されて別の場所に収蔵され、私たちがスマホにおさめるのはホワイトセメント製のレプリカだったりする。ラスキンの描写にあるフレスコ画、ヴォールトに描かれたメダリオン(円形装飾)の絵を見ようと「あるはず」の場所に目を凝らしても、影も形もないこともある。そして、「それを描いた画家は誰か」――作品の帰属、あるいは真贋という、見る者の「見かた」「受け取りかた」を大きく左右するであろう問いへの答え。
なぜなら、絵画に関しては二種類の知識があるからである。一つは芸術家の知識。二つめは骨董商と画商の知識であり、キャンヴァス、絵具、筆遣いの特徴に関する、非常に確かで広範囲な知識に立脚しているが、芸術そのものの質に関する知識を含んではいない。(……)
私は以前、ヴァーリーとカズンズの素描をターナーの初期の習作と考えていたが、それら素描の真贋については、画商の方が知識が上だと思い知らされる羽目に陥った。にもかかわらず、画商は私ほどにはターナーについても、ターナーの価値についても知らない。同様にあなた方は、初期ジョット諸派の作品群のあれこれの絵の真贋に関して、私が何度も誤りを犯すのを見いだされるかもしれないが、同時に私だけが(矜持の念よりも、ずっと多く悲しい気持ちを抱いて言うのだが)、それらのどの絵に関しても、現在のところその真の価値について語れる、ということに気づかれるであろう。(……)
私がカズンズをターナーと取り違えたとき、私は、画商がまったく意識することのなかった、本質的にターナー的であるとはいえ、他の画家もときには同じように描くかもしれない空のある部分の微妙な感じに目を留めていたのであり、画商の方は、カズンズは用いたがターナーは用いなかったワットマン紙の質だけを見ていたかもしれないのである。
(「六日目の朝 羊飼いの塔」章冒頭)
本書が世に出てから、まもなく150年。20世紀に、芸術作品の鑑定にかかわる分析技術は飛躍的に進んだ。数世紀のあいだ信じられてきた画家の名前が「本当の作者」の名前につぎつぎに書き換えられていく。そして、ラスキンが当時の定説に従って作者とした画家の名が、今では別の画家名に置き換えられているのを知るとき、驚かされるのは、「芸術そのものの質」「その真の価値」を見る批評家ラスキンの目は、「それを描いたのは誰か」に曇らされたことが本当にいっさいなかった、ということだ。
新たに「作者」とされた名前も、今後「誤り」とされ、また別の画家の作品になる日がくるかもしれない。それでも、サンタ・クローチェ聖堂で観光客の足の下で踏まれ、「深く彫られた線のあとだけを残し、大部分は摩滅して平べったい石になっている」作者のわからない浮彫の墓標に美をみいだすラスキンが本書に書きあらわしたものが、力を失うことはない。
ページをひらけば、ファサードが未完成でのっぺらぼうの大聖堂の前を、観光客を乗せた貸馬車と蒸気バスが行き交う19世紀後半のフィレンツェにタイムトリップしてしまう。そこから先は、ラスキンの道案内に導かれてさらに時代を遡り、ただ神の栄光のために画家が筆をとり、彫刻家が鑿を揮った中世のフィレンツェへ――